小粋なキューバン・スウィング ボビー・カルカセース [カリブ海]
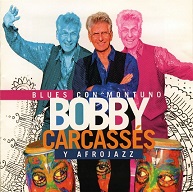
こりゃあ、面白い。この人、どういう人なの?
キューバのエンタテイナー歌手なんですか、へぇ、初めて知りました。
ブラジルのカウビ・ペイショートに続いて、
老練なヴェテラン歌謡歌手のアルバムを聞くというのも、なんだか奇遇ですねえ。
外交官の家に生まれたボビー・カルカセースは、38年キングストン生まれ。
一家はボビーが4歳の時にキューバに戻り、
56年にボビー・コジャーソのヴォーカル・カルテットでプロ・デビューしたシンガー。
アフロ・キューバンにジャズをミックスした、ジャイヴィーな味のあるジャズ・シンガーで、
マルチ奏者でもある多芸なお人なんですね。
チューチョ・バルデース、エミリアーノ・サルバドールと共に、
60年代以降のキューバン・ジャズのスタイルを決定づけた功労者なんだそうです。
御年78歳になるわけですけれど、ジャケットを見ると、そんなお歳には見えませんね。
キューバ新世代として活躍中の息子ロベルト・カルカセースがプロデュースした本作は、
オリベル・バルデース(ドラムス)、ホルヘ・レジェス(ベース)、
フリート・パドロン(トランペット)、マラカ(フルート)といった、
現代キューバを代表するトップ・プレイヤーたちが勢揃いしています。
ベニー・モレーをモチーフにした1曲目のボビーのオリジナル曲から、
エリントンの「キャラバン」にボビーが詞を付けた“Caravana”、
「テンダリー」「ナイト・イン・チュニジア」といったジャズ・チューンのほか、
ティト・プエンテとデイブ・バレンティン他がアレンジした、
ペドロ・フローレスの“Obsesión” まで取り上げています。
ソフトで軽快にスウィングする歌い口で、スキャットも鮮やかに決め、
いや~、粋じゃないですか。
フロアでレディと踊りたくなりますよ。
ラストはボーナス・トラック扱いの“Son De La Loma”。
かの古典ソンのスタンダード・ナンバーを、
全編ア・カペラのスキャットで歌うとは、降参です。
Bobby Carcassés Y Afrojazz "BLUES CON MONTUNO" Bis Music CD1141 (2017)
2017-09-30 00:00
コメント(0)
ブラジル大衆歌謡歌手の矜持 カウビ・ペイショート [ブラジル]
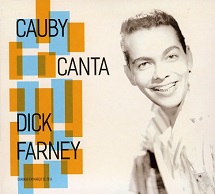
あの世に逝く前、最後にこんなふうに歌えたら、歌手人生も本望だろうなあ。
そんな思いを抱いた本作は、亡くなるわずかひと月前のレコーディングという、
カウビ・ペイショートの遺作です。
16年3月に本作のレコーディングを終え、
5月3日にリオでアンジェラ・マリアとステージで歌ったのを最後に、
そのわずか12日後の5月15日、肺炎で息を引き取ったというのだから、
急なことだったようですね。
カウビ・ペイショートというと、ちりちりヘアのルックスからして、
いかにも俗悪なブラジルの大衆歌謡歌手というイメージが強くて、
正直、これまでまともに聞いたことがありませんでした。
ロベルト・カルロス同様、本国では絶大な人気歌手でも、
ブラジル音楽好きの日本人が、無視するタイプの歌手といえます。
それなのに、このアルバムに手を伸ばす気になったのは、
大衆歌謡歌手らしからぬアーティスティックなレーベル、
ビスコイト・フィーノからのリリースだったこと。
そして、プレ・ボサ・ノーヴァの時代に、粋なクルーナー歌手として活躍した、
ぼくの大好きなディック・ファーニー(ジッキ・ファルネイ)のカヴァー集という企画に、
ソソられたからなのでした。
幼い頃ナット・キング・コールに憧れて歌手になったというカウビ・ペイショートは、
典型的なアメリカナイズされたポップス・シンガー。
今回あらためて経歴を調べてみたら、
50年代半ばにアメリカに進出して成功し、タイム誌やライフ誌に
「ブラジルのエルヴィス・プレスリー」と書かれるまでになり、
57年には、アメリカで初のポルトガル語で歌ったロックン・ロールのレコードを
出していることがわかりました。
なんと、シロ・モンテイロの従兄弟だったんですね。
ブラジルに帰国してからは、ナイトクラブを中心に、
ロマンティックな歌を歌うショー歌手として活躍した人で、
ぼくの視界にまったく入らなかった歌手です。
晩年もナット・キング・コールや
フランク・シナトラのカヴァー集を出していたようですけど、
ラスト・レコーディングがディック・ファーニーのカヴァーでなければ、
カウピのアルバムを買うことは、一生なかったでしょうね。
いかにもクラブ歌手といった雰囲気の歌い口ではあるんですが、
若い頃のキザったらしさや、大仰な歌いぶりは影をひそめ、
枯れた味わいがディック・ファーニーのジャジーな歌にぴったりで、
イヤミのないダンディさが、ほどよいムードを醸し出しています。
ピアノ・トリオにサックスとギターを加えた伴奏も申し分ありません。
老いらくの恋を歌うには、こういうオールド・スクールな歌い口がよく似合うというか、
ロマンティック歌手のひとつの理想像を見るかのようで、
80越えて、こんな歌を歌えたら、いいもんだと思いますよ。
Cauby Peixoto "CAUBY CANTA DICK FARNEY" Biscoito Fino BF466-2 (2017)
2017-09-28 00:00
コメント(2)
目が覚めるショーロ チアーゴ・ソウザ [ブラジル]

うひゃー、このリズムのキレ!
ボーっとしてた頭が、一瞬にしてシャキッと目が覚めました。
のっけからシャープなバンドリンに驚かされたのは、
エポカ・ジ・オウロのバンドリン奏者ロナルド・ド・バンドリンの息子
チアーゴ・ソウザのデビュー作です。
ジャケットに写る主役のルックスは優等生ぽく、ファッションもイケてないというか、
なんかいまひとつだなあと思いながら聴き始めたせいか、
出音イッパツで、椅子から転げそうになっちゃいました。
オープニング曲がチアーゴ自作のオリジナルなんですけど、
一瞬変拍子の曲かと思わせるような、複雑なリズムのシカケがある曲で、
おおっと前のめりになっちゃいました。
でも、いわゆるアミルトン・ジ・オランダのような
プログレッシヴなインスト・ナンバーではなく、まぎれもなくショーロなんですよね。
テクニカルな作曲能力と、ショーロ本来の味がちゃんと同居しているところが憎いなあ。
オリジナルは冒頭曲のみで、ほかはナザレーのような古典曲に、
マウリシオ・カリーリョ、ルシアーノ・ラベーロ、ペドロ・アモリン、
ゼー・パウロ・ベケールなどのショーロ・ナンバーを取り上げています。
どんなレパートリーでも、リズムが立っていて、
バンドリンの粒立ちの良い響きが鮮やか。
アルバム全編から、若々しさが溢れ出ていて、まばゆいほど。
曲ごとに編成も多彩で、ドラムスが入る曲もあれば、
トランペット、トロンボーン、バス・クラリネットなどの管楽器が加わる曲、
チェロ、アコーディオン、ヴァイオリンをフィーチャーした曲など、さまざま。
参加メンバーも豪華で、総勢40人近い名前がクレジットされています。
ヤマンドゥ・コスタ、ニコラス・クラシッキ、アレサンドロ・クラメルに、
お父さんのロナルドもいますよ。
ソンふうのトランペットを配した「ショーロ・クバーノ」なんておちゃめなナンバーや、
バイオーンとマラカトゥをミックスしたようなノルデスチ満開な曲もあり、
とにかく楽しめること間違いなし。
若手だからこそのフレッシュなショーロ・アルバムです。
Tiago Souza "DE SOSLAIO" Discmídia no number (2017)
2017-09-26 00:00
コメント(3)
ブラジルのコンテンポラリー・ジャズ最高峰のグループ ルデーリ [ブラジル]
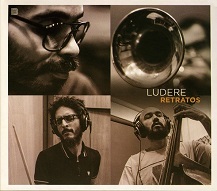
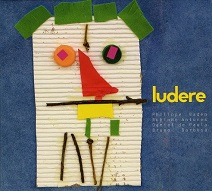
ルデーリの新作が出ました。
ルデーリは、バーデン・パウエルの息子フィリップ・バーデン・パウエルのピアノに、
ギリェルミ・リベイロのアルバムでもプレイしていたダニエル・ジ・パウラのドラムス、
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-12-06
ルビーニョ・アントゥネスのトランペット、ブルーノ・バルボーザのベースの4人組。
ブラジルのコンテンポラリー・ジャズ最高峰のグループと呼ぶのに、
なんのためらいもありません。
昨年リリースしたデビュー作が鮮烈で、
従来のブラジリアン・ジャズとはステージの違う、
世界標準の新世代ジャズのセンスを持っていることに驚かされました。
抜きんでたリズム表現、作曲能力の高さ、濃密なサウンド・アプローチ、
卓越したソロ・ワークと、どこを切っても、現代のジャズのエッセンスが充満しています。
パリ生まれ、ドイツ育ちのフィリップ・バーデン・パウエルをのぞき、
全員サンパウロのミュージシャンなのですが、
彼らの演奏には、ブラジル音楽の要素は見当たりません。
サンバやボサ・ノーヴァ、北東部など地方のリズムがまったく出てこないどころか、
参照すらされていないので、ルデーリの演奏を聞いて、
ブラジル人とわかる人は、まずいないんじゃないかな。
フィリップ・バーデン・パウエルのソロ作では、
ブラジリアン・ジャズらしい楽想も見受けられるんですけれど、
ルデーリではブラジルを封印しているかのようです。
今回の新作は、弦楽四重奏をゲストに迎えているところが聴きどころ。
アンサンブルが生み出すフック・ラインを、
弦楽四重奏が加わることで、より濃密なものにしています。
リズムの崩しも巧みなルビーニョのトランペット・ソロや、
現代ジャズ的な訛りのあるリズム・フィールを持ったダニエル・ジ・パウラの
サウンドに流れを生み出していくドラミングが、すごくイマっぽい。
う~ん、ライヴを観てみたいですねえ。
Ludere "RETRATOS" Blaxtream BXT0011 (2017)
Ludere "LUDERE" no label no number (2016)
2017-09-24 00:00
コメント(2)
リズムの偉才、爆発 ヴィジェイ・アイヤー [北アメリカ]
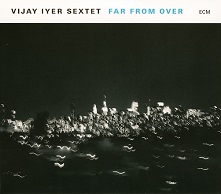
わ~お ♪
こういうフォーマットで聴きたかったんですよ。
3管入りのセクステットとなったヴィジェイ・アイヤーの新作。
ずっとピアノ・トリオの作品が続いていて、
リズムの鬼ヴィジェイの凄みは、そこでも十分発揮されていたとはいえ、
もっと大きな編成で聴いてみたいと思っていたもんだから、願ったりかなったり。
どういうメンバーを集めたのかとクレジットをみれば、
トランペットにグレアム・ヘインズ、アルト・サックスにスティーヴ・リーマン、
ドラムスにタイショーン・ソーリーを起用しているじゃないですか。
こりゃあ、すごい。俊英を揃えましたねえ。
M-BASE の影響大なヴィジェイにとって、グレアム・ヘインズはうってつけだし、
ぶっといトーンでぶりぶり吹きまくる期待の若手、
スティーヴ・リーマンを起用したのも嬉しいですねえ。
そして、マーカス・ギルモアから交替したドラマーが、
そのリーマンと一緒にプレイしているタイショーン・ソーリーなんだから、
こりゃあ期待が高まるってもんです。
半年前に“MISE EN ABÎME” を愛聴していたばかりなので、嬉しさ倍増。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-02-12
レーベルがECM なので、
ヴォリュームをいつもの13から20へと上げて、プレイ・ボタンを押したんだけど、
オープニングのピアノの音量がちっちゃすぎて、聞こえやしない。
まったく、どんだけ音圧低いんだよ、ECM。
ひとりごちながら、さらにヴォリュームを26まで上げると、
3管のユニゾンから一気に爆発。どひゃーあ、来た、来たぁ~!
数学的なリズム使いは、ヴィジェイのリズム探究の賜物ですけれど、
反復/垂直的なM-BASE を、加算的に変化させていくヴィジェイのリズム使いには、
やっぱりこの人、インド人だよなと思わずにはおれません。
時間軸に水平移動してリズムを動かしていくところなんて、
インド古典音楽のリズム・サイクルであるターラと同じ発想だもんねえ。
それが、ジャズのアフリカ起源的な垂直方向に動かすリズムとレイヤーして、
新しいポリリズムとグルーヴのあり方を提示しているかのようで、ドキドキしてきます。
ピアノ・トリオだと、
数理的なリズム・オリエンテッドな演奏が前面に押し出されますけれど、
今回は3管、ピアノ、ドラムスそれぞれのソロが大暴れして、
マッシヴなジャズの快楽を味わえる、ヴィジェイの最高傑作です。
Vijay Iyer Sextet "FAR FROM OVER" ECM ECM2581 (2017)
2017-09-22 00:00
コメント(2)
ビルマ大衆歌謡の黄金時代 コー・アンジー [東南アジア]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
先月、井口さんが出来立てほやほやのウー・ティンの新作CDを持って、
ヤンゴンのご自宅まで届けに行った際に見つけてきたというCD3枚。
井口さん、お土産、ありがとうございます。
コー・アンジーという、初めて聞く名の男性歌手のアルバムで、
ベスト・アルバムが3タイトルも出ているほどなのだから、
相当有名な歌手なんだろうなということは、容易に想像がつきます。
井口さんによれば、23年に北部シャン高地のメイミョー(現在のピーウールウィン)に
生まれ、今年6月23日に94歳で亡くなったとのこと。
さっそく聴いてみると、50~60年代とおぼしき録音で、
これまでほとんど耳にすることができなかった、
ビルマ時代の大衆歌謡がたっぷり入っていて、大カンゲキ。
サイン・ワイン楽団が伴奏に付く古典歌謡と、
ラウンジーな大衆歌謡がごたまぜになっています。
録音時期にもバラツキがあり、3枚のアルバムに、
レパートリーも新旧録音もお構いなしに放り込んだといった編集ですね。
3枚それぞれ編集の意図があるようには思えませんけれど、
第1・3集は古典曲が多く、第2集は大衆歌謡中心のレパートリーになっています。
古典曲は8分を超す長尺のものが多く、なかには、伝統スタイルの伴奏と西洋風の伴奏が
交互にスイッチする、のちのミャンマータンズィンのような曲も聞けます。
コー・アンジーは、メジャー曲では、晴れ晴れと伸びやかな歌声を聞かせる一方、
哀愁味のある曲では、情のある歌い回しで聴き手を引きつけます。
やわらかで甘いバリトンの声は耳に心地よく、
日本にも50~60年代は、こういう声の男性歌手が多かったような気がしますねえ。
アコーディオン、クラリネット、オーボエをフィーチャーし、
マラカスとクラベスがラテン・ムードを醸し出すナンバーや、
オルガンにブラシのドラムスのコンボ編成によるスウィンギーなナンバーなどは、
同時代のマレイシアのP・ラムリーやサローマを思わせます。
一方、アコーディオン、ギター、ヴァイオリン伴奏のポルカや、
オーケストラ伴奏による映画挿入歌ふうの曲などは、
「軽音楽の夕べ」といった雰囲気(若い人、わかります?)濃厚で、
昭和の香りが漂ってくるようじゃないですか。
CDのインレイを見ると、ギター、テナー・ギター、三味線(!)、
ピアノ、アコーディオン、オルガンを弾いていて、マルチ奏者でもあったようですね。
第2集のバック・インレイに、
ギターとバンジョーを弾く白人2人と一緒に写っている写真があり、
同じ時のものとおぼしき映像がYoutubeに上がっています。
それによると、二人の名は、スティーヴ・アジスとウィリアム・クロウ・フォードだそうで、
コー・アンジーと共にビルマ語で歌っています。
3人の後ろには、膝の上に置いたバマー・ギターをスライドしているギタリストもいますね。
このあと、3人は「おお、スザンナ」をギター、バンジョー、パッタラーの伴奏で歌い、
続いてサイン・ワイン楽団が演奏するという共演風景も記録されています。
CDには収録されていませんが、どういう人たちだったんでしょう。
まだまだ未知のビルマ時代の大衆歌謡、
さらにさかのぼって、SP時代の録音も、ぜひ聴きたくなるじゃありませんか。
そんな好奇心を強烈にかきたてられた3枚でありました。
【追記】 2017.12.20
ウィキペディアに記述のある7曲がこのシリーズに収録されていることが確認できました。
https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Gyi
第1集M1“Yin Ta Ko Me”、M2“Aung Pinle”、M7“Turiya Lulin”、
M8“Turiya Lon May”、M9“Yangon Thu”、
第2集M3“Lu Gyun Lu Kaung”、第3集M1“Shwe Mingan”。
【追記】2019.2.19
コー・アンジーと白人2人が歌うYouTube の映像は、
61年アメリカ大使公邸の庭で撮影されたものだそうです。
後ろでバマー・ギターを弾いているのは、ウー・ティンだということが、
2019年2月17日付ニュー・ヨーク・タイムズの
ウー・ティン死亡記事に書かれていました。
Ko Aunt Gyi "A KAUNG TA A KAUNG SONE TAY (1)" Rai no number
Ko Aunt Gyi "A KAUNG TA A KAUNG SONE TAY (2)" Rai no number
Ko Aunt Gyi "A KAUNG TA A KAUNG SONE TAY (3)" Rai no number
2017-09-20 00:00
コメント(0)
バマー・ギターの生き証人 ウー・ティン [東南アジア]

昨年のベスト・アルバムに、幻のビルマ・ギター(バマー・ギター)の名手、
ウー・ティンのアルバムを選ばなかったのは、泣く泣くだったんですよ。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-08-06
演奏内容こそ、ベスト・アルバムとしてなんら不足はないものの、
井口寛プロデューサー個人の自主制作盤のため、一般に出回っていないことに加え、
まったく世間に知られていないバマー・ギターのアルバムなのに、
なんの解説もないという不案内ぶりは、
ベスト・アルバムとして選ぶのに、ちょっとどうかと、ためらってしまったからです。
ミャンマーの謎めいたギターに、長い間ずっと関心を寄せてきたぼくのような物好きが、
ここでいくら大騒ぎしても、このままでは一般に知られず、忘れ去られてしまう。
このアルバムの内容がどれだけ貴重で、
リリースされたことの意義深さを痛感しているぼくには、それがどうにもじれったく、
焦燥感に駆られてどうしようもなかったんですよね。
そんな後ろ髪を引かれる思いがあったので、
井口さんから、ウー・ティンの2枚目のCDを出そうと思っているとの連絡を受け、
ついては、解説を書いてもらえないかという依頼には、
合点!と、すぐさまお引き受けしたのでありました。
今作は前回のアルバムと同時期の録音ですが、ソロ・ギター演奏ではなく、
竹製の木琴パッタラーと女性歌手をフィーチャーしています。
古い大衆歌謡のなかで演奏されてきた、
かつてのバマー・ギターのスタイルをうかがわせる趣向となっているんですね。
ぼくがウー・ティンを知るきっかけとなったオランダPAN盤でも、
ヴァイオリンやツィターなどとの合奏3曲が収録されていましたけれど、
今回歌手が加わったことで、歌のメロディとギター・フレーズの対比が、
よくわかるようになりました。
世にもまれなるユニークすぎるスライド・ギターの妙技を味わうにしても、
完全ソロ演奏よりも、今回のように歌の伴奏として聞く方が、
ミャンマー音楽に不案内の人には耳馴染みやすいのではないでしょうか。
今回、井口さんが新作のリリースを考えたのは、
実は今年の春、ウー・ティンが脳梗塞で倒れたことがきっかけでした。
ウー・ティンが元気なうちに、早くCDを届けたいということで、
急遽制作されたのですが、先日出来上がったばかりのCDを
ミャンマーに届けにいったところ、予後が良く、ギターも問題なく弾いているとのこと。
もうギターが弾けなくなってしまったのではと心配していただけに、ほっとしました。
解説はぼくばかりでなく、ウー・ティンに弟子入りした柳田泰さんも書かれています。
世界中を見渡したって、こんなスライド・ギター、ミャンマーにしかありません。
ぜひ聴いてみてください。
U Tin "MUSIC OF BURMA VIRTUOSO OF BURMESE GUITAR -MAN YA PYI U TIN AND HIS BAMA GUITAR-" Rollers ROL004 (2017)
2017-09-18 00:00
コメント(0)
ポップ・マロヤに見るレユニオン史 [インド洋]

インド洋レユニオン島で75年から86年に出されたシングル盤から、
マロヤのナンバーを選曲したコンピレーション。
サブ・タイトルに「エレクトリック・マロヤ」とあるように、
フランス人プロデューサーが海外向けに制作した伝統マロヤではなく、
現地のヒット・ソングとして聞かれていた、ポップ・ロック化したマロヤを集めているので、
ドス黒いパーカッション・ミュージックが苦手な人にも、
親しみやすいアルバムになっていると思います。
エレクトリック化したポップ・マロヤは、なんともローカルな味わいで、
垢抜けない電子楽器の使用もチープながら、ほほえましく聞けますね。
そして今回のストラット盤に驚かされたのは、32ページにおよぶライナーの解説。
いやあ、これはすごい勉強になりました。
セガを起源とするというマロヤ発祥の17世紀までさかのぼり、
マロヤの歴史を解説していて、これはマロヤ史の第一級の資料といえます。
これまでセガとマロヤは、別系統の歴史を持つとされていたのが、
マロヤがセガから生まれたという新説は、興味深いものがあります。
セガ=アフリカ+ヨーロッパ、マロヤ=アフリカ+スワヒリ+インドという理解が、
新たな視点によって新たな発見が生まれるかもしれません。
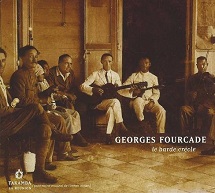
このほか、ジョルジュ・フルカド(1884-1962)について、
1928年に“Caïamb Et Sombrère” のなかで、
「ポルカを踊るのは好きじゃない。ぼくが踊るときはマロヤで踊るのさ」と
いう歌詞があるという指摘にも驚かされました。
あわててタカンバ盤の“LE BARDE CRÉOLE” をチェックしてみると、
確かにはっきりと maloya と歌っています。
これまでジョルジュ・フルカドを、ヨーロッパナイズされた歌手とみなしていたので、
認識を改めさせられました。
マロヤ初のLPをレユニオン共産党が制作したことや、
のちにマロヤがプロテスト・ソングに組み込まれていくこととなった
レユニオンの政治状況なども、今回初めて知りました。
おかげで、ダニエル・ワロが共産活動家だったという背景が、ようやく理解できました。
ほかにも、マロヤの宗教音楽としての側面から、
セガとマロヤとが歌謡化していくなかで互いに影響していく関係などが、
具体的なエピソードで書かれていて、なるほどとうなずくことしきりでした。
世界遺産に指定されたことで、マロヤの伝統文化の面については、
広く知られるようになりましたけれど、大衆歌謡史という面からは、
ほとんど言及されてこなかっただけに、この解説はとても貴重なものです。
解説はナタリー・ヴァレンティン・ルグロとアントワーヌ・ティションのお二人。
ストラット、いい仕事してます。
Caméléon, Michou, Jean Claude Viadère, Ti Fock, Gaby Et Les Soul Men, Vivi, Maxime Laope, Gilberte and others
"OTE MALOYA : THE BIRTH OF ELECTRIC MALOYA IN LA REUNION 1975-1986" Strut STRUT151CD
Georges Fourcade "LE BARDE CRÉOLE" Takamba TAKA0105
2017-09-16 00:00
コメント(0)
アフリカと欧米の相互作用 ムサフィリ・ザウォーセ [東アフリカ]
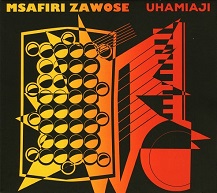
ウィキペディアによれば、故フクウェ・ザウォーセの5番目の子供という、
82年生まれのムサフィリ・ザウォーセ。
90年12月にバガモヨのフクウェ・ザウォーセのお宅にうかがった時、
家にいっぱい子供たちがいたけど、あの中にムサフィリもいたんだろうか。
12月31日生まれというから、ちょうど8歳になる手前だったはず。
あんまり子供が多いので、「この子たちみんな、あなたの子供なの?」と聞いたら、
「そうだ」と答えるので、絶倫男かよと思ったもんですけど、
5番目の子供というのは、これいかに。
あの時の人数から考えれば、十何人目の子供のはずなんだけどなあ。
それはさておき、ムサフィリ・ザウォーセは、
ザウォーセ・ファミリーの中でも若手のせいか、リアル・ワールド盤や
ザウォーセ・ファイヴのフィンランド盤には参加していません。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-06-04
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-04-27
ザウォーセ・ファミリーからチビテにグループ名を変えてから、
ムサフィリもメンバーの一員となり、08年に日本にも来ているんですね。
なんとその時、ぼくはムサフィリと会っているはずなんですけれど、
8人もメンバーがいたので、どの人が誰やら、記憶に残っていません。
というわけで、はじめて聴くムサフィリ・ザウォーセのソロ・アルバム。
デジタル・リリースでは、何作か出しているようですけれど、
フィジカルはこれが初のはず。サウンドウェイからのリリースで、
サム・ジョーンズというイギリス人(?)とコラボした作品になっています。
見開きジャケット内のライナーに、
かつてフクウェ・ザウォーセとマイケル・ブルックスがコラボした“ASSEMBLEY” に
触発されたようなことが書いてあって、おいおい大丈夫かよと心配しましたが、
あんな史上最低最悪の作品とは比べ物にならない、
アフリカ人と欧米人互いの理解が進んだ作品に仕上がっています。
サム・ジョーンズは、アレンジ、シンセ、ローズ、ドラム・プログラミングを
担当していますが、ゴゴのリズムをよく理解したプログラミングを施していて、
ゴゴのグルーヴを強化しています。
ホーンズの起用や鍵盤の扱いも、サウンドを装飾するのにとどまらず、
ムサフィリが弾くイリンバやゼゼとがっちり組み合ってサウンドをレイヤーし、
より肉感的に仕上げることに成功しています。
アフリカ人と欧米人の共演は、こうであってほしいですよねえ。
互いの音楽性を理解しあい、しっかりと組み合うことで、
化学反応を起こすコラボにしなきゃ、共演の意味がありません。
フクウェ・ザウォーセとブルックの共演なんて、
ザウォーセはブルックの音楽に何の関心もないし、
ブルックはザウォーセの音楽をサンプリングのネタ扱いして、
好き勝手にイジリ倒すだけという、およそ共演などとは呼べないシロモノでした。
欧米側の先鋭的な音づくりでハッタリかましたり、
コンテンポラリーな味付けでサウンドを装飾するだけじゃダメ。
アフリカ側も積極的にプログラミングに関与して、
ハイブリッドな相互作用が起こらなければ、コラボは成功しません。
それをきちんと実現しているのが、本作です。
Msafiri Zawose "UHAMIAJI" Soundway SNDWCD122 (2017)
2017-09-14 00:00
コメント(0)
トニー・アレンのビートに追い付いたジャズ [西アフリカ]

トニー・アレンがアート・ブレイキーのトリビュート盤EPを
ブルー・ノートから出すという話を聞いた時は、
これは面白い企画を考えついたもんだなあと期待したんですが、
出来上がりは、予想に反し平凡な仕上がりで、ちょっと肩すかしでした。
トニー・アレンのドラミングは、古いハード・バップ・スタイルまんまなところがあるので、
アート・ブレイキーをやるならバッチリと思ったわけなんですけど、
世間では、そんなふうにトニー・アレンを聴いている人はいないようで、
前にもピーター・バラカンさんのラジオ番組でそんな話をしたら、
ピーターさんもすごく意外そうな反応を示されたもんなあ。
でもねえ、言っときますけど、トニー・アレンって、フェラ・クティと活動する前は、
ジャズ・ドラマーだったんですからね。
だいたいトニー・アレンと出会った当時のフェラからして、
まだジャズに夢中になっていた時代で、
アフロビートを作り出すのは、もっとずっと後のことだったんですよ。
というわけで、せっかくブルー・ノートからリリースするのなら、
ジャズ・アルバムを作ればいいのにと思っていたので、
新作はまさに願ったりの作品に仕上がっていたのでした。
いやあ、これ、アレンのソロ作としては、
02年の“HOMECOOKING” 以来の大傑作じゃないですか。
あのアルバムとは、ぜんぜん性格が違いますけれども。
オープニングのチューバ、トランペット、サックスの合奏から、
いきなり引きこまれましたよ。
まるでギル・エヴァンスみたいなサウンド・オーケストレーションじゃないですか。
バックはどうやらフランス人ミュージシャンのようなんですが、
知っている名前が一人もいな~い。
トニー・アレンと並んで作編曲のクレジットに名を連ねている、
ソプラノ・サックス奏者のヤン・ヤンキルヴィツが、
どうやらキー・マンのようです。
オープニングの“Moody Boy” ばかりでなく、“Cruising” のホーン・アレンジにも、
ギル・エヴァンスの影響がはっきりと聴き取れますよ。
デューク・エリントンのオーケストレーションも、研究していそうだなあ。
5管編成のホーン・セクションの面々は、いずれも相当な実力者とみえ、
ダニエル・ジメルマンの呻くようなトロンボーン、
ジャック・イランゲのナマナマしいテナー・サックスには、耳をそばだてられます。
こういう管楽器の肉声を感じさせる鳴らしっぷりが、ぼくは大好物なんですよ。
達者なジャズ演奏などにするのではなくて、
ジャン=フィリップ・デイリーのピアノが転げまわったり、
ジャズ・マナーではないアフリカンなリズムを刻むギターを起用するところも、
トニー・アレンのドラミングとの相性をちゃんと考えていますよね。
ちなみに、このギタリスト、インディ・ディボングはカメルーン人とのことで、
フランス人じゃないのは、この人だけなのかな。
ムラトゥ・アスタトゥケを連想させる“Bad Roads”、
トランペット・リフがディジー・ガレスピー・オーケストラを思わせる“On Fire”、
ニュー・オーリンズのマーチング・バンドのサウンドを借りたような“Push and Pull”
マイルズ・デイヴィスがアフロビートをやってるみたいな“Ewajo” など、
曲ごとにおおっと思わせる仕掛けが凝らされたアレンジに、脱帽です。
それでいて、アルバムを通して、アレンのドラミングを浮き彫りにした統一感があり、
ヴァーサタイルなミュージックとなった現代ジャズとしても、一級品の作品。
トニー・アレンのキャリアとしても、最高のセッションになりましたね。
ようやくジャズが、トニー・アレンのビートに追いついたんですよ。
Tony Allen "THE SOURCE" Blue Note 5768329 (2017)
2017-09-12 00:00
コメント(2)
爆撃から守られたソマリ音楽のアーカイヴ [東アフリカ]
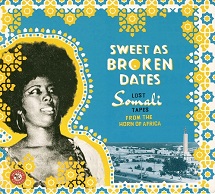
「ソマリ音楽のアーカイヴは、ちゃんと保存されている」
昨年来日したソマリランドのサハラ・ハルガンが、
ぼくにきっぱりと語ってくれたことが、忘れられません。
ソマリアの国営ラジオ局ラジオ・モガディシュに残された、
3万5千リールに及ぶ膨大な録音のデジタル化作業が
進行中ということは耳にしていましたが、
それとは別に、ソマリア北西部に位置するソマリランドにも、
オープン・リールとカセット・テープが大量に存在するという話を
サハラ・ハルガンから聞かされた時は、ちょっと興奮が抑えられませんでした。
ニュース映像などで、内戦でことごとく破壊された街を目にしてきた者には、
こんな状態で音源が残されたなんて、奇跡としか思えません。
ラジオ・ハルゲイサに勤務していたソマリランド初の女性ジャーナリストで、
現在ソマリランドの文化省副大臣の要職にあるシュクリ・アーメドが、
本作のライナーノーツで驚くべき秘話を明かしています。
ソマリア空軍の大規模な空爆が目前に迫っていた88年、
ラジオ・ハルゲイサの職員たちは、通信手段を破壊するために、
ラジオ局が標的となるのを見越して、空爆にも耐えられる地下深くに、
オープン・リールやカセット・テープを埋めたというのです!
空爆直前と思われる88年のハルゲイサ録音の曲も本作には収録されていますが、
ソマリの人々の決死の思いに、胸を打たれずにはおれません。
平和を取り戻してから掘り起こされた1万点を超すアーカイヴ音源は、
現在ラジオ・ハルゲイサとハルゲイサ文化センターに保管され、
デジタル化が進められています。
こうして内戦をサヴァイヴした音源や、ジブチで録音された音源、
さらに国外脱出したソマリ移民がトロントやミネアポリスで録音した音源が集められ、
ヴィック・ソーホニーを軸に、一大プロジェクトでモガディシュ、ハルゲイサ、
ジブチ、さらに在外ソマリ社会での取材・調査を経て制作されたのが本作です。
ソマリアが平和だった70年代は、60年代ロンドンをホウフツとする
若者文化が開花した「スウィンギング・モガディシュ」の時代だったと、
ヴィックはライナーノーツで語っています。
ソマリの伝統音楽にスーフィーのプレイズ・ソングやカラーミなどのソマリ歌謡、
アラブ音楽、スーダン歌謡、インドのフィルムソングなど、
さまざまな音楽がミックスされて独自のサウンドを生み出したソマリ・ポップは、
ロックやソウル、ファンクと出会って、
より若い世代にマッチした新しいサウンドを獲得していったんですね。
ライナーノーツには、社会主義の革命政権下のソマリアで、
州がスポンサーとなって音楽家や演劇人などのアーティストたちが組織化され、
管轄下におかれた様子や、国立劇場で政府主催のコンサートや文化イヴェントが行われ、
多くの公営バンドが活動した往時の様子が、詳細に語られています。
ドゥル・ドゥル・バンドのように、国の庇護を受けず自由な活動を求めて活動した
民営のバンドもいたとはいえ、それはごくごくわずかだったんですね。
2年前に復刻された民営レーベル、ライト&サウンドの音源は、
音楽産業が育たず、国営ラジオ局にしかレコーディング設備のないソマリアでは、
例外中の例外だったということがよくわかります。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-12-16
本作のライナーノーツには、
これまでまったく情報のなかったソマリ・ポップの貴重な証言が満載で、
むさぼるように読みながら、胸の動悸が高まるのを覚えましたよ。
ソマリ・ポップへの長年の渇望を癒してくれた、超弩級のリイシュー。
ヴィック・ソーホニー、本当にすごい仕事をやってくれました。
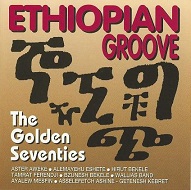
思い起こすのは、かのフランシス・ファルセトが、
94年に初めてエチオピアン・ポップの黄金時代の録音復刻を手がけた
“ETHIOPIAN GROOVE - THE GOLDEN SEVENTIES” です。
あのアルバムが、のちの「エチオピーク」シリーズを始める
原点となったことを知る人は、今どのくらいいるでしょうか。
ぼくには本作が、あのアルバムとダブってみえるんですよ。
どうか本作がこの一作に終わることなく、
ソマリ・ポップ発掘の第二弾、第三弾と続くことを、切に願います。
ヴィックも意欲満々のようなので、期待できそうですよ。
V.A. "SWEET AS BROKEN DATES: LOST SOMALI TAPES FROM THE HORN OF AFRICA " Ostinato OSTCD003
V.A. "ETHIOPIAN GROOVE - THE GOLDEN SEVENTIES" Blue Silver 002-2
2017-09-10 00:00
コメント(2)
アフロ・ポップ・リイシュー・レーベルのニュー・カマー [西アフリカ]

ニュー・ヨークで新たに誕生したオスティナート・レコーズは要注目です。
カーボ・ヴェルデの70~80年代音源をコンパイルした
“SYNTHESIZE THE SOUL: ASTRO-ATLANTIC HYPNOTICA
FROM THE CAPE VERDE ISLANDS 1973-1988” は、
確かな審美眼をうかがわせる選曲で、
ずっと無視していたのを、深く後悔させられました。
この内容だったら、『レコード・コレクターズ』誌にも紹介すべきだったなあ。
ずっとスルーしていたのは、タイトルを見て、去年アナログ・アフリカがリリースした、
カーボ・ヴェルデのコンピレーションと同趣旨の内容と思い込んでしまったから。
あれ、しょうもないモンド盤だったもんなあ。
最近アナログ・アフリカがコンパイルするCDは、
先日出たカメルーンのマコッサのコンピレーションもそうでしたけど、
B・C級とすらいえない駄曲ばかりセレクトしていて、ウンザリさせられます。
カーボ・ヴェルデものも、チープなシンセを使い始めた時期の録音を、
「コズミック・サウンド」などと称して面白がっているような内容でしたよね。
こういうイロモノを見る目で、
アフリカン・ポップスにアプローチする態度って、ヤだなあ。
カメルーンのフランシス・ベベイを、宅録エレクトロ趣味で再評価するのとかさぁ。
というわけで、「シンセサイズ」「アストロ」「ヒプノティカ」といったフレーズを
タイトルに散りばめたオスティナート盤も、
どうせ愚にもつかぬモンド盤だろうと、早とちりしてしまったわけなんですが、
レーベルを主宰するヴィック・ソーホニーの選曲は確かでした。
カーボ・ヴェルデ独立前後の熱気あふれる若者たちによる、
エレクトリック化されたコラデイラやフナナーが詰まっていて、
アナログ・アフリカの上っ面のサウンドを面白がるような視点と、次元が違います。
この人、ちゃんと音楽を聴いてるなという信頼感を持てますね。
すっかり感心して、フェイスブックでヴイックさんにコンタクトしてみたら、
この人、インド生まれで、タイ、シンガポール、フィリピンで育った人なんですね。
ニュー・ヨークの大学院を卒業した後、ドイツ、アフリカ、ハイチで仕事をし、
多文化の中で育ち、仕事をしてきた自身の体験とも重なって、
移民がポップスへ果たしてきた役割に、目が向くようになったといいます。
カーボ・ヴェルデ独立直後のエレクトリック・ポップに注目したのも、
リスボン、パリ、ロッテルダム、ボストンへ渡ったカーボ・ヴェルデ移民が、
本国の島にはなかった新しいポップスをクリエイトした過程に、興味を抱いたからとのこと。
独立後エミグレのカーボ・ヴェルデのミュージシャンたちは、
欧米で手に入れた電子楽器を島に持ち込む一方、
本国の伝統リズムを学ぶために、地方の農村や漁村を旅するようになったそうです。
そこで壊れたアコーディオンがシンセサイザーに置き換わり、
島と欧米の移民社会との間に、
文化的なサプライ・チェーンが築かれたと、ヴィックはいいます。
エレクトリック・フナナーも、そうした歴史の中から誕生したわけなんですね。
カーボ・ヴェルデ音楽の電子化のキー・マンとして、
アナログ・アフリカ盤と同じくパウリーノ・ヴィエイラに注目しながら、
選曲にこれだけ差が生まれるのは、単なるセンスの問題ではなく、
移民社会との文化交流に目を向けた、ヴィックの視点の確かさによるものでしょうね。
ヴィックは、オスティナート・レコードを立ち上げる以前、
アナログ・アフリカのサミー・ベン・レジェブとも一緒に仕事をして、
“ANGOLA SOUNDTRACK” や“BAMBARA MYSTIC SOUL” などを手がけています。
最近では、フローラン・マッツォレーニ監修のミスター・ボンゴ盤の
マリ音楽のコンピレーションも、ヴィックが選曲をしていたんですね。
そんな彼が、カーボ・ヴェルデに続いて、失われたソマリ音楽の復刻にアプローチ。
素晴らしい仕事をしてくれました。これについては、次回ご紹介しますね。
V.A. "SYNTHESIZE THE SOUL: ASTRO-ATLANTIC HYPNOTICA FROM THE CAPE VERDE ISLANDS 1973-1988" Ostinato OSTCD002
2017-09-08 00:00
コメント(0)
知られざるインスト・レゲエ名盤 アルベルト・タリン [南ヨーロッパ]

『ギター・マガジン』がおもしろい。
注目したきっかけは、「恋する歌謡曲」と題した今年の4月号。
ろくにクレジットされてこなかった歌謡曲のバックのギターにスポットをあてて、
山口百恵の「プレイバック part2」や中森明菜の「少女A」、
寺尾聰の「ルビーの指環」を分析する切り口も斬新なら、
チャーと野口五郎との対談や、歌謡曲のギター名フレーズなどなど、
これまで過小評価されていた歌謡曲のギター・プレイに注目した名企画でした。
その後も、モータウンのギタリストを特集したりと、企画が秀逸なうえ、
毎回100ページを超すという熱の入れようで、掘り下げ方がハンパない。
「最近の音楽雑誌は面白くない」とボヤく人には、『ギター・マガジン』を薦めています。
そんでもって、今回の9月号が、またスゴかった。
なんと、ジャマイカのギタリスト特集。
なんて地味なところに、焦点を当ててくれたんでしょうか。
スカ~ロック・ステデイ~レゲエに至るギター・インストの名盤を掘り下げ、
当時のジャマイカのギタリストたちが愛用した、安物のビザール・ギターを分析し、
アーネスト・ラングリン、リン・テイト、アール・チナ・スミス、
マイキー・チャン、ハックス・ブラウンのインタヴューをとるという、徹底ぶり。
これを画期的といわずに、なんというかってくらいのもんです。
メントやカリプソまで掘り下げていて、レゲエ・ファンのみならず、
ワールド・ファン必携の永久保存版でしょう。
ジャマイカのギター・インスト盤は、本号にすみずみまで取り上げられているので、
ちょっと違った角度からのインスト・レゲエ盤を
本号に敬意を表して、ご紹介しようと思います。
それがこのスペイン、バレンシア出身のギタリスト、アルベルト・タリンのアルバム。
え? スペイン人? と思うかもしれませんが、
ジャマイカ音楽を演奏する日本人ギタリストが、本号のインタヴューにも、
5人も登場しているくらいですからね。スペインにいたって不思議はありません。
アルベルト・タリンは、スペインにおけるレゲエ・バンドのパイオニア的存在で、
リタ・マーリーがスペインでコンサートをした際に共演もしています。
ギターはオーソドックスなジャズ・ギターのスタイルで、
ジョージ・ベンソン直系といったプレイを聞かせます。
02年の本作は、タイトルどおり、ジャズのスタンダード・ナンバーを中心に、
レゲエ・アレンジで演奏した内容で、“You'd Be So Nice To Come Home To”
“Days Of Wine And Roses” “Old Devil Moon” “Someone To Watch Over Me”
のほか、ボサ・ノーヴァの“Desafinado” にジョン・レノンの“Imagine”、
そしてアルバム・ラストは、マーリーの“Slave Driver” で締めくくっています。
選曲があまりにヒネりがなさすぎで、聴く前はどんなものかと思いましたが、
ジャズ・ギタリストがお遊びでやったなんていうレヴェルではない、
本格的なレゲエ・アルバムとなっていて、すっかり感心。
バックのメンバーも全員スペイン人のようですが、演奏水準はメチャ高くて、
即お気に入りアルバムとなったのでした。
本号にも紹介されている
リントン・クウェシ・ジョンソンのダブ・バンドのギタリスト、
ジョン・カパイのソロ・アルバムと似た仕上がりと思ってもらえればいいかな。
あのアルバムが好きな人ならゼッタイの、知られざる傑作です。
Alberto Tarin "JAZZIN’ REGGAE" Spanish Town no number (2002)
2017-09-06 00:00
コメント(2)
音楽の感動と想像力 ランディ・ニューマン [北アメリカ]

ランディ・ニューマンをわからないまま、聴き続けているファンとして、
もうひとつ触れておきたいことを思い出したので、今日はその話を。
16歳の時、“GOOD OLD BOYS” にすっかりヤられ、
そのあとデビュー作までさかのぼってニューマンのレコードを聴いて、
“GOOD OLD BOYS” と同じくらい惹かれたのが、
72年作の“SAIL AWAY” でした。
前回、音楽はわからなくていい、と啖呵を切りましたが、
耳の快楽として感動したのならば、
そこでどんなことが歌われているのか気になるのは、当然の人情です。
あの当時、ランディ・ニューマンの歌世界の理解に役立ったのが、
グリール・マーカスが書いた『ミステリー・トレイン』でした。
グリールのおかげで、ニューマンの物語の知識を得ることはできましたが、
それでニューマンの音楽の聞こえ方が変わったかといえば、
そんなことはありませんでした。
やはり知識は、音楽の理解に役立っても、感動の本質には関係がなく、
まずは感動ありきの後付け、参考としかならないことを、実感したものです。
それを強く印象づけられたのが、“SAIL AWAY” のタイトル曲でした。
ぼくはあの曲が、奴隷貿易をテーマとしているとは、
歌詞すら読んでなかったもので、グリールの文章を読むまで想像だにせず、
それを知った時は、ちょっとショックでもありました。
歌の意味をなんにもわからないまま、感動していたことにです。
自分たちの祖先が犯した、奴隷貿易という忌まわしい歴史を、
あれほど美しく、気品のあるメロディで歌ったのは、
恥ずべき歴史を正当化したい修正主義者の人々の喉元を、
皮肉でえぐるという、強烈なアイロニーだったんですねえ。
アメリカ社会が抱える、人種差別の歴史の罪深さを凝縮したこの歌の意味合いは、
グリールの文章を読まなければ、とても理解できなかったでしょう。
それでは、歌詞の意味も知らず聞いている外国人は、
ニューマンの音楽が「わかっていない」のでしょうか。
歌詞の意味を知らずに感動しているのは、「勘違い」なのでしょうか。
“SAIL AWAY” の発売から30年経った02年、ライノがCD化した際、
タイトル曲“Sail Away” の未発表ヴァージョンが、
ボーナス・トラックとして収録されました。
「アーリー・ヴァージョン」とクレジットされたそのヴァージョンには驚かされました。
LPヴァージョンとは、まったく違うアレンジだったからです。
鎖に繋がれた奴隷たちが行進するのを連想させるような、
軍楽隊ふうの勇ましいシンバルの響きや、スネアのロール。
そしてエンディングには、トーキング・ドラムや鉦といった、
アフリカのパーカッション・アンサンブルを
フィーチャーしたアレンジが施されていたのです。
それはまさしく、奴隷船に積み込もうとする様子を、
演奏で具体的に描写したものでした。
しかし、果たして、これが正規のヴァージョンだったら、
感動しただろうか、と思ってしまったんですね。
その説明的なサウンドは、聴き手の想像力を奪うものです。
奴隷制度を硬直的に非難する角度の付けかたは、プロパガンダにすぎません。
そこに聴き手の解釈が入る余地はなく、
それでは奴隷制を肯定しようとする立場の側の
人間の弱さや哀しみにまで、思いを至らせることはできなかったでしょう。
このテイクをボツにして、
美しい弦楽オーケストラのヴァージョンでレコーディングし直したのは、
表現者が角度を付けるのではなく、リスナーに解釈の余地を残すことの重要性を示した、
意義深い実例のように、ぼくには思えます。
わずか20秒あまりのアフリカン・パーカッションのアンサンブルが、
あまりに本格的なのにも驚かされたんですけれどね。
クレジットはありませんが、アフリカ人奏者を呼んで演奏したものに違いなく、
スタジオ・ミュージシャンにアフリカ風の演奏をさせてゴマカしたのではないところが、
ニューマン、偉い! というか、さらにそこまでしても、ボツにしたところも、
さらに偉いというか、信頼に足る人だと感じ入ったのでありました。
Randy Newman "SAIL AWAY" Reprise/Rhino R2-78244 (1972)
2017-09-04 00:00
コメント(0)
音楽はわからなくていい ランディ・ニューマン [北アメリカ]
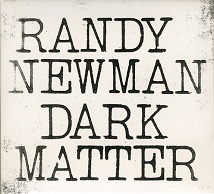
ランディ・ニューマンの新作が出ましたね。
新作が出れば必ず買うという人は、
とうとう、ランディ・ニューマン一人だけになっちゃったなあ。
ダン・ヒックスは亡くなってしまったし、
ライ・クーダーはとっくに聴くのをやめてしまったし。
ランディ・ニューマンを初めて聴いたのは、
高校1年の時の74年作“GOOD OLD BOYS” でした。
アクのある声で、独特の歌い回しをするその語り口に、すぐさまトリコとなり、
“GOOD OLD BOYS” は、ボビー・チャールズやダン・ペン、
ダン・ヒックス、ザ・バンドの『南十字星』同様、
ぼくにとってかけがえのない、生涯の愛聴盤となりました。
相変わらず、ニューマンが何を歌っているのかなどは無頓着に、
「あの」声で歌われる、クセのある語り口、
いわばニューマン節といったものに魅せられて、聴き続けているわけなんですが、
今回は「セリア・クルース」だとか「サニー・ボーイ」など、
聞き捨てならない言葉が、歌詞にやたらと出てきます。
まあ、気にはなるところではあるんですけど、
それでも、歌詞カードを読もうとは思いません。
読んだところで、ニューマンの難解な世界がわかるわけでなし、
仮に少しわかった気になったとて、感動が変わるわけじゃありませんからね。
ニューマンの音楽に限らず、世界中の音楽を聴く自分にとって、
歌詞に頓着しないのは、音楽を聴くうえで大前提となっています。
歌詞なんかどうだっていい、というとやや言い過ぎになりますけれど、
音楽を聴いて感動するのは、ぼくの場合、「サウンドの快楽」であって、
歌詞の意味や、文学的な意味性などにはありません。
歌だけでなく、バラッドや義太夫といった語りものですら、そうです。
エディット・ピアフを評してだったか、
「電話帳を歌っても感動する」という表現が、ぼくにはピタッときます。
ところが、ぼくが音楽を聴き始めの70年代初めの頃というのは、
「ブルースがわかる」だとか「コルトレーンがわかる」とかいったように、
やたらと精神論で音楽を語ったり、哲学的な語り口で過剰に意味付けする、
教養主義的な風潮がとても強かったんです。
メンドくさい時代だったんですよ、70年代って、ホントに。
「わかる」というワードは、おそろしいというか、都合のいいもので、
深い理解や洞察を語っているつもりが、いつのまにか自家中毒を起こして、
独りよがりの歪んだ愛情を文章にしているのにすぎないものが多くて、
ウンザリしたものです。
だから、ぼくにすれば、「音楽なんてわかる必要はない」。
どれだけ感じ取れるか、どこに感動したのか、どう自分が受け止めたのかが大事。
受け止め方は、人によって千差万別で、ひとつじゃない。
受け止め方を人に強制する必要もなければ、強制されるいわれもない。
自由に受け止めていい。そこにこそ、芸術の意味がある。ずっとそう思ってきました。
これって、音楽じゃなくて、絵画、写真、文学に置き換えてみれば、わかりやすいはず。
「絵がわからない」とかいう人、よくいるじゃないですか。
それは、絵を教養のように思い込んでいるからですよね。
絵なんて、「わかる/わからない」じゃなくて、「感じるか/感じないか」でしょう。
音楽だって、文学だって同じです。教養なんかじゃありません。
もっと気楽に接すればいいだけの話、娯楽だと思えばいいんです。
今でこそ、こんなこと当たり前で、何はばかることなく口にできますけれど、
70年代には、そんなことを言える時代の空気はなかったんですよ。
そんなことを言えば、ケーハクなヤツと見下されること必至でしたからねえ。
80年代のバブルが、それを蹴散らしたのかもしれませんね。
Randy Newman "DARK MATTER" Nonesuch 558563-2 (2017)
2017-09-02 00:00
コメント(5)




