ベロ・オリゾンチのサンビスタ デ・ルーカス [ブラジル]

めっちゃ好みのサンビスタ、みっけ!
ここ数年ずっとサンバ日照り、なんてボヤいていたら、
5年前に出ていたインディ作に、こんな良作があったとは。
オーセンティックなサンバは、こういうインディ作をマメにチェックしないと、
お目にかかれなくなっちゃいましたね。
大手のレコード会社からはまったく出ないし、
ビスコイト・フィーノぐらいしか、サンバ・アルバムを作ってないもんな。
デ・ルーカスことヴァンデルソン・ヴィエイラ・ルーカスは、73年生まれ。
リオでもサン・パウロでもない、ベロ・オリゾンチのサンビスタという変わり種です。
十代の頃からベロ・オリゾンチのサンバ・シーンで活躍して、
グループを率いて数多くのサンバを作曲してきたほか、モアシール・ルス、
ルイス・カルロス・ダ・ヴィラ、ファビアーナ・コッツァ、ウィルソン・モレイラ、
タンチーニョ・ダ・マンゲイラなど、多くのサンビスタの伴奏をしてきたそう。
作曲者としてリオのコンテストで2度優勝したことで注目が集まり、
サンバのヴェテラン・プロデューサー、パウローンに認められ、
本デビュー作の制作へ繋がったのだそうです。
タイトル曲の‘Clarear’ に‘Quinto Elemento’ の優勝曲を収録するほか、
パウローンにデ・ルーカスを推薦したというファビアーナ・コッツァも、
ゲストで加わっています。
デ・ルーカスの歌がもう、たまらなくいいんですよ。
かすれ声に味があって、ソフトな歌いぶりと、たまに音程が怪しくなるところが、
実にサンビスタ・マナー。サンバ好きにはたまらないタイプの歌い手です。
そして、デ・ルーカスが書くサンバが、これまた佳曲揃いなんだな。
サンバ作家としても抜きん出た才能の持ち主ですね。
そして伴奏はパウローンが音楽監督が務めているのだから、内容保証付。
アレンジは7弦ギターのパウローンと6弦ギターのマルコス・サントスがやっていて、
レコーディングはベロ・オリゾンチで行われています。
パウローンがいつも起用するミュージシャンの名が見当たらないのは、
パウローンがベロ・オリゾンチに出向いて、
地元ミュージシャンを起用したからなのかもしれません。
トロンボーンやフルート、ピアノを使っている曲もあって、
アレンジがいつものパウローンと違うのは、
マルコス・サントスという人がやっているのかな。
知らない名前ですけれど、ベロ・オリゾンチのミュージシャンだろうか。
曲ごとに工夫されたアレンジなど、しっかりとした制作ぶりで、
インディ作というのが、もったいなさすぎ。
このままビスコイト・フィーノから出せるようねえ。
ファビーニョ・ド・テレイロ、チノ・フェルナンデス、エデルソン・メローン、
メストリ・ジョナスなど、ベロ・オリゾンチの知られざるサンビスタたちに、
また一人、忘れられない名前が加わりました。
Dé Lucas "CLAREAR" no label no number (2016)
2021-05-30 00:00
コメント(0)
ファンクの肝はアタマの1拍目 ブーツィー・コリンズ [北アメリカ]

ダンプスタファンク新作のヘヴィ・ロテが止まらない。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-05-02
これ一枚じゃ物足んなくて、なんかほかに良さげなファンクはないかと、
少し前に出ていたブーツィーの新作に手を伸ばしてみましたよ。
ブーツィーはねぇ、昔大好きだったんだけど、世紀が変わったあたりから、
だんだん興味が薄れてきちゃったんだよなあ。
なんか健全になっちゃったというか、変態ぽいハチャメチャな感じとか、
ヒネくれたところが消えてしまって、ストリート感は失われたよねえ。
11年の“THE FUNK CAPITAL OF THE WORLD” だって、
ゴージャスでよく出来ているなあ、なんて感心しつつも、
どうもそのゴージャス感が受け入れがたくって、
妙に冷めて聴いちゃったんだよなあ。
やっぱゴキゲンなファンクはさあ、
パっと聴いただけで、身体に電気が走るような感触がなきゃ、ダメだよねえ。
17年の“WORLD WIDE FUNK” も、豪華絢爛なゲストばかりに耳がいって、
どうにも盛り上がれなかったんでした。
というわけで、正直おそるおそるという感じで、耳にした20年作。
うわぁ、いいじゃん!
ボトムをぐっと強調したミックスが快感で、オート・ワウをかけて、
ぐちゅぐちゅ、ぶりぶりとスラップするベースがサイコー!
ダンプスタファンクがスライの“FRESH” の1曲目をカヴァーしたけれど、
こちらは2曲目の‘If You Want Me To Stay’ を
‘Want Me 2 Stay’ と改題カヴァーしていて、
しかもラリー・グラハムをゲストに、ブーツィーとベースを競演してるよ。うぇ~い!
本作のタイトル『ザ・ワン(1拍目)のパワー』とは、ジェイムズ・ブラウン直伝の、
ファンクは頭の1拍目が命だという教えとのこと。
小節はじめの1拍目に、全身全霊、入魂で弾かんかい!
という教えにのっとったものなんだそうです。
ドアタマでアクセントを付けるパワーこそがファンクの真髄と、
JBから学んだブーツィーは、ジョージ・クリントンとバーニー・ウォレルにも
その教えを伝授して、Pファンクに継承したんだそうであります。
そんなタイトルを付けた心意気が伝わる快作です。
Bootsy Collins "THE POWER OF THE ONE" Sweetwater Studios SWS1020 (2020)
2021-05-28 00:00
コメント(0)
4トロンボーン・ジャズ ジェニファー・ウォートン [北アメリカ]


4トロンボーンというレアな編成で、主役はバス・トロンボーン。
しかも、このジャケ写ですよ。
これで買わないわけにはいかないでしょうという、
ニュー・ヨークの女性バス・トロンボニスト、ジェニファー・ウォートンのデビュー作。
アンサンブル重視のオーソドックスなジャズで、すがすがしい作品だったんですが、
新作ジャケが、これまたジャズとは思えぬポップなデザインで、
試聴もせずに飛びついちゃいました。
イマドキのジャズがいかに絶好調かを示す、洒脱なデザインですね。
ジャズ・シーンでチューバが脚光を浴びるようになったことと、
連動するのかどうかはわかりませんが、
アンサンブルのなかでサポート役に回ることが宿命的な低音楽器を、
メインに押し出そうという試みは、興味をそそられますよね。
もっとも4トロンボーンという編成じたいは、特に目新しいものではなく、
日本でも、鍵和田道男や中川英二郎たちが試みています。
ただ、トロンボーンの特性を発揮した面白いアンサンブルができるかどうかは、
なかなか難しいところなんですが、ジェニファー・ウォートンのアンサンブルは、
ラージ・アンサンブルの技術ばかりでなく、クラシックのテクニックも駆使して、
ユニークなアレンジをしています。4台のトロンボーンがハーモニーを生み出したり、
別々の旋律で動いたりして、さまざまに色彩を変えていくんですね。
もともとジェニファーはクラシックの演奏家で、
ニュー・ヨークのブロードウェイで、オーケストラ・ピットの仕事もするかたわら、
ジャズもプレイしているという人なので、より自由度の高い演奏を求めて、
4トロンボーンの可能性を試しているようです。
デビュー作の1曲目からそれは発揮されていて、
4拍子と7拍子がスイッチする構成の曲で、
メンバー全員が活躍するアレンジでのびのびと演奏しているのが、印象的です。
ファンキーなチューンあり、美しいバラードありと、楽曲のタイプもヴァラエティ豊かで、
‘Softly As In A Morning Sunrise’ やオスカー・ピーターソンの‘Tricotism’ では、
非凡なアレンジが楽しめます。
そして、アルバム・ラストでは、なんとダイナ・ワシントンの‘Big Long Slidin' Thing’ を
ジェニファーが歌うというサービス精神に富んだ趣向で楽しめます。
ブルースというより、キャバレー・ソングぽくて、
遊びゴコロを発揮したトロンボーン・ソリが痛快です。
新作はスタンダード曲はなく、ジェニファーとゆかりのあるミュージシャンたちに
作曲を依頼し、提供された曲を演奏しています。
オープニングは、ニュー・ヨークのジャズ・ピアニスト、
マイケル・エクロスに作曲を委嘱したラテン・ナンバー。
マイケル・エクロスは、話題となったキューバン・ビッグ・バンド、
オルケスタ・アコカンのアレンジャーとして名を上げましたよね。
今作も、4トロンボーンが生み出すサウンドスケープは、鮮やか。
4人が順にソロを取る‘Ice Fall’ のようなオーソドックスなアレンジのトラックから、
リズムがさまざまにスイッチする複雑なアレンジの‘Blue Salt’ まで、
トラックごとに趣向を変えつつ、
いずれでも遊びゴコロあるところが、このグループの良さですね。
カート・エリングをゲストに迎えたラスト・トラックでは、
トロンボーン・ソロを真似たスキャットを披露していて、いやぁ、もう、たまんない。
このアルバムには、豊かな物語があります。
Jennifer Wharton’s Bonegasm "BONEGASM" Sunnyside SSC1530 (2019)
Jennifer Wharton’s Bonegasm "NOT A NOVELTY" Sunnyside SSC1612 (2021)
2021-05-26 00:00
コメント(0)
コペンハーゲンの実験的ジャズ ネゼルホーンズ [北ヨーロッパ]

テナー・サックス奏者のナナ・パイが率いるコペンハーゲンのクインテット、
ネゼルホーンズのセカンド・アルバム。
リーダーのナナ・パイはデンマーク出身ですが、
トロンボーンのペッター・ヘンゼルと
ドラムスのクリストファー・ロステットはスウェーデン出身、
トランペットのエリック・キメスタッドはノルウェー出身、
ベースのヨハネス・ヴァートはエストニア出身と、
北欧各国からコペンハーゲンに集まった才能によるグループです。
グループの核となっているのが、
作曲を担当しているナナ・パイとペッター・ヘンゼルで、
二人とも調性と無調が行き来するコンポジションを書き、
協和と不協和が並列するサウンドスケープを、伝統的なジャズな語法で演奏しています。
即興性は強いけれど、フリー・ジャズとは言い難い構造のあるコンポジションを演奏する、
実験性の高いグループで、このビミョーな案配が、めちゃ好みだなあ。
タイトル曲の冒頭でナナが、テナー・サックスの無伴奏ソロを吹くんですが、
不協和音やノイズを駆使しながら、けっして破調になることなく、
抑制の利いた即興演奏となっているところが聴きものです。
ナナの独特なトーンは、やっぱ強烈な個性があるなあ。
坂田明が18年12月に渡欧ツアーした時、彼女と共演したんですよね。
北欧ジャズらしいダークなトーンのコンポジションは、
余計な抒情を挟み込んでこない、無糖コーヒーの味わいにも似て、
とても魅力的です。
Nezelhorns "SENTIMENT" Barefoot BFREC066CD (2021)
2021-05-24 00:00
コメント(0)
トンブクトゥの女王を悼んで ハイラ・アルビー [西アフリカ]

アフリカのアーティストで、ライヴを観たかった筆頭格が、ハイラ・アルビー。
ハイラをトンブクトゥのソウル・ディーバと礼賛した記事を、かつて書きましたけれど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-09-21
18年4月に届いた訃報には、全身から力が抜ける思いがしたものです。
59という年齢で逝くなんて、あまりに早すぎますよ。
ハイラ・アルビーを世界に紹介したクレモント・ミュージックが、
生前のライヴ録音を出すという知らせを聞いていたので、
首を長くして待っていたんですが、ようやくこの春、
10年8月にニュー・ヨークのバード大学で行われたライヴ・アルバムがリリースされました。
10年というと、ちょうど世界デビュー盤の“TIMBUKTU TARAB” を出し、
ヨーロッパ、北米、モロッコ、アラブ首長国連邦を回っていた
世界ツアーのときの録音ですね。
“TIMBUKTU TARAB” 収録の6曲を含む10曲が、収録されています。
天に駆け上っていくようなハイラの素晴らしいヴォーカルに、圧倒されます。
生命力が漲るその歌声には、ホレボレとさせられますよね。
地元トンブクトゥの大スターから、マリを代表するシンガーとしての栄誉を勝ち得て、
世界に羽ばたいたキャリア絶頂の瞬間を捉えた、輝きに満ちたライヴ盤です。
ハイラをバックアップするバンド・サウンドも完璧な仕上がりで、まさに当意即妙。
「トンブクトゥのアリーサ・フランクリン」とも形容されたハイラですけれど、
このアルバムは、アリーサのフィルモア・ウェストのライヴ盤をホウフツとさせますね。
10年の録音といえば、奇しくも同じ年の1月、
バマコで録音されたザ・スウェイ・マシナリーのアルバムに、
ハイラ・アルビーが大々的にフィーチャーされていたんですけれど、
このアルバム、日本ではまったく知られていないようなので、
せっかくだからここで紹介しておきましょう。
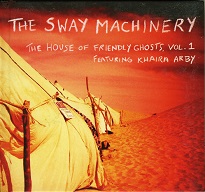

ザ・スウェイ・マシナリーは、
5人のジューイッシュをメンバーとするブルックリンのバンド。
ジョーダン・マクリーン(トランペット)とスチュアート・ボギー(テナー・サックス)
の二人は、アンティバラスのメンバーとしても知られています。
リーダーのジェレマイア・ロックウッド(ヴォーカル、ギター)は、
ユダヤ教会の典礼音楽を受け継ぐ一族の出身で、
ナイトクラブで演奏できるファンキーなユダヤ音楽をクリエイトしようと、
ザ・スウェイ・マシナリーを立ち上げたといいます。
そのザ・スウェイ・マシナリーが「砂漠のフェスティヴァル」に招聘され、
ハイラ・アルビーと出会って意気投合、バマコでセッションすることになったんですね。
ハイラとともに砂漠のフェスティヴァルに出演したシュペール・オンズや、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-02-26
ジェリマディ・トゥンカラ、ヴィユー・ファルカ・トゥーレ、ズマナ・テレタとの面々も、
セッションに参加しています。
砂漠への旅の途中で出会ったトゥアレグの男の子の歌や、女性たちのコーラス、
ラクダのいななき、街に流れるアザーンをフィールド録音したトラックなども織り交ぜ、
ザ・スウェイ・マシナリーがマリを旅した、
ロード・ムーヴィといったアルバムになっているんですね。
CDブック形式の80ページのフォト・ブックには、
マリで撮られた様々なスナップ・ショットとともに、
アメリカのジューイッシュがマリで出会った異文化体験を率直に書き記していて、
すがすがしさを覚えます。
その制作アプローチは、
デーモン・アルバーンの『マリ・ミュージック』とよく似ていながら、
デーモンの仕事を快く思わないぼくが感動できたのは、
異文化への敬意の熱量と、アティチュードの違いだろうな。
ライヴ盤でも歌われている‘Sourgou’‘Youba’ の2曲がこちらでも聴けるんですが、
ロウファイな魅力は、またひと味違う仕上がり。
シュペール・オンズも加わってタカンバの祝祭感溢れるヴァージョンに仕上げた‘Sourgou’、
バリトン・サックスのブルージーなリフとテナー・サックスのブロウに、
黄金時代のエチオピア歌謡を思わすド迫力の‘Youba’ と、
ライヴと甲乙つけがたいヴァージョンになっています。
ハイラ・アルビーのライヴ盤を契機に、
ザ・スウェイ・マシナリーのアルバムにも注目してもらいですねえ。
Khaira Arby "NEW YORK LIVE" Clermont Music CLE033
The Sway Machinery "THE HOUSE OF FRIENDLY GHOSTS, VOL.1 FEATURING KHAIRA ARBY" JDub JDUB124 (2010)
2021-05-22 00:00
コメント(0)
ヒップ・ホップ・ビートをヒューマナイズした遺作 トニー・アレン [西アフリカ]
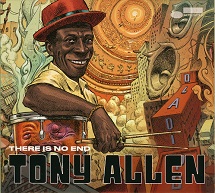
トニー・アレンを観たのは、19年1月のブルーノート東京のステージが最後。
サックスのヤン・ヤンキルヴィツを核とするセクステットでやってきて、
“THE SOURCE” のレパートリーを聞かせてくれたんですけれど、
まさかこの1年3か月後に亡くなってしまうなんて、想像すらしませんでしたよ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-09-12
ブルーノートのステージで繰り広げた、見事に力の抜けたドラミングは、
まさしく老練そのもので、半世紀以上昔の古臭いスタイルにもかかわらず、
それが現代ジャズとして響く不思議さに感じ入ったもんです。
スティックのグリップにしたって、今日びあんな持ち方するドラマーなんていないもんなあ。
それは取りも直さず、トニーが「ドラムスを叩く」のではなく、
「ドラムスを歌わせる」タイプのドラマーであることの証明だったと、ぼくは捉えています。
そんなトニーらしい遺作が登場しました。
未完成だったヒュー・マセケラとのコラボレーションが、
完パケになって世に出たときも驚きましたけれど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-04-01
ほかにもアルバム制作途中のものがあったとは、びっくりです。
最期まで意欲満々だったトニーのミュージシャンシップに感じ入るばかりなんですが、
ヒップ・ホップのアルバムだったところが、これまたトニーらしいところ。
アフロビート・レジェンドというポジションに安住する興味などさらさらなく、
常に新しいクリエイターを求め続けてきたトニーは、
これまでも、デーモン・アルバーン、モーリッツ・フォン・オズワルド、ジェフ・ミルズなど
気鋭の若手音楽家たちと次々とコラボして、ロック、ダブ、ジャズ、テクノを横断する
クロスオーヴァーな活動をずっとしてきたんですからね。
しかし本作は、ドラムスとベースのベーシック・トラックを作ったところで、
トニーが亡くなってしまい、生前に仕上がっていたトラックは、
ナイジェリアの詩人ベン・オクリのポエトリーとスケプタのラップをフィーチャーして、
デーモン・アルバーンがオルガンを弾いた‘Cosmosis’ 1曲のみだったとのこと。
他のトラックは、プロデューサーのフランス人ドラマーのヴァンサン・テーガーと、
フランス人ピアニスト、ヴァンサン・トーレルの二人が、
若い世代の素晴らしい才能を世に送り出したいというトニーの遺志を継いで、制作を続行。
サンパ・ザ・グレイト、ツナミ、ナー・イート、コリアタウン・オディティ、
ラヴァ・ラ・ルー、ダニー・ブラウンなど、新進のアーティストたちをフィーチャーして、
トニーの願いを遂げたのでした。
ヴァンサン・テーガーとヴァンサン・トーレルの二人って、
ウム・サンガレの“MOGOYA” で、作曲者にクレジットされていましたね。
アルバムの最初と最後にトニーのナレーションをフィーチャーして、
ドラムスを歌わせるドラマーの本領を発揮したジャジー・ヒップホップ作品。
ベスト・トラックは、西ロンドンの女性ラッパー、ラヴァ・ラ・ルーをフィーチャーした
‘One Inna Million’ だな。クールでセクシーなフロウと、
フランス人ベーシスト、マチアス・アラマンのグルーヴがサイコー。
ドラムスが歌うばかりかフロウする繊細なトニーの妙技は、
ダビーな空間にも、グライムやトラップ世代のビート感にも、
するりと滑り込む自由度を有し、
ヒップ・ホップ・ビートのヒューマナイズを鮮やかに表現しています。
Tony Allen "THERE IS NO END" Blue Note 0734546 (2021)
2021-05-20 00:00
コメント(0)
唯一無比のアヴァンギャルド・ジャズ・ドラマー ロナルド・シャノン・ジャクソン [北アメリカ]
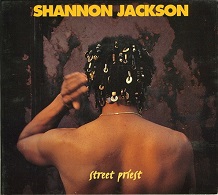

ひさしぶりに“BLACK ROCK” を聴いたおかげで、
すっかりウルマー祭りとなっております。
“NO WAVE” “ARE YOU GLAD TO BE IN AMERICA?” と続けたら、
ロナルド・シャノン・ジャクソンのドラムスがもっと聴きたくなって、
“STREET PRIEST” に手が伸びました。
ロナルド・シャノン・ジャクソンのアルバムで一番聴き倒したのは、やっぱりこれかなあ。
8年前にシャノン・ジャクソンのお悔やみ記事を書いた折、
“STREET PRIEST” がCD化されていることに気付いて、
おぃおぃ、いつの間にCD化してたんだよと、
ひとりごちしながら、あわてて入手したんだっけ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-10-23
CDジャケットの写真は、LPと別のカットに差し替えられていて、
メールス盤CDでは珍しく、デジパック仕様となっていたんですね。
お悔やみ記事に82年の”MAN DANCE” を掲げたのは、
吉田カツのドローイングが、シャノン・ジャクソンの音楽の本質を見事に描き切っていて、
弔意を示すのにふさわしいジャケットだと思ったから。
でも音楽的内容では、なんといっても“STREET PRIEST” が最高ですよ。
その理由はといえば、作編曲の良さ。
ツイン・サックスにツイン・ベースという特異な編成と、
シャノン・ジャクソンの手数の多いドラミングをフルに活かした
コンポジションとアレンジに、まったくスキがないのが、本作の傑作たるところ。
逆に言えば、他のデコーディング・ソサエティのアルバムでは、
なにかしらちょっとした不満が、それぞれあるんですよね。
“MAN DANCE” にせよ、“NASTY” にせよ、“BARBEQUE DOG” にせよ。
もたったり揺らいだりするリズムにのせて、アブストラクトな音列を、
リー・ロージーのソプラノ・サックスとゼイン・マッセイのアルト・サックスが、
ユニゾンで吹く変態的なテーマに、病みつきになったんだよなあ。
ロック・ドラムとも、フリー・ジャズのパルスとも違う、
マーチング・ドラムがフリー・ジャズに異化したかのような
シャノン・ジャクソンのタテノリのドラミングは、いまだに謎なんであります。
インプロヴィゼーションになると、
フリーキーなサックスと、引っかかりのあるベースが有機的に絡みあい、
その合間を、ヴァーノン・リードの轟音ギターがなめらかに縫っていく場面など、
いまだ実体のよくわからない、ハーモロディクスの片鱗を味わうことができます。
メルヴィン・ギブスとブルース・ジョンソンの2台のベースのヘテロフォニックな動きが、
すごくカッコイイんだよなあ。
ゆいいつスローな‘Sandflower’ だけが、ブルース・ジョンソンにベースの役割を任せ、
ゆったりとしたサックスのソリをバックに、
メルヴィン・ギブスがリード・ギターのように細かなパッセージのソロを取っています。
アルバム中、ゆいいつ抒情を漂わせたオーセンティックなスタイルのトラックで、
テキサスのフォーク・ルーツを感じさせるメロディに、グッときますよ。
続く‘Hemlock For Cordials’ では、リー・ロージーとゼイン・マッセイの二人が
テナー・サックスに持ち替えて、冒頭から吠えまくり。
ハイ・トーン中心にキーキー鳴らすロージーと、
低音中心にパワフルなブロウを聞かせるマッセイが対照的なプレイを聞かせます。
そしてラストの‘Chudo Be’ では、サックス、ベース、ギターが同時に
インプロヴィゼーションを繰り広げる集団即興のパートから、
一転リズム・チェンジしてソロ・リレーに移るという趣向が、スリリングですよねえ。
あぁ、やっぱ、このアルバム、サイコーだわ。
あまりに唯一無比すぎて、シャノン・ジャクソンを継ぐ人が現れないのも
無理ないと思わせる、アヴァンギャルド・ジャズの驚異的なドラマーだったのでした。
Ronald Shannon Jackson and The Decoding Society "STREET PRIEST" Moers Music 03002CD (1981)
[LP] Ronald Shannon Jackson and The Decoding Society "STREET PRIEST" Moers Music MOMU01096 (1981)
2021-05-18 00:00
コメント(0)
ブラック・パワー・ジャズ ジェイムズ・ブラッド・ウルマー [北アメリカ]
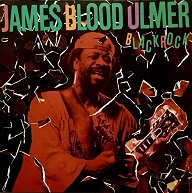
ひん曲がったリズムで、アブストラクトな音列を並べるテーマに、はや昇天しかけていると、
痙攣するようなリックをがしがしと弾き倒すギターが畳みかけてきて、
その圧倒的なブラック・パワーには、ただただひれ伏すほかありませんでした。
81年にジェイムズ・ブラッド・ウルマーと出会ったのは、
自分の音楽人生の中でも、一二を争う強烈な体験だったことは間違いありません。
ラフ・トレードというポスト・パンクのレーベルからアルバムが出たのも必然で、
むしろその後、メジャーのコロンビア・レコードに移籍したことの方が、ビックリもの。
コロンビアがウィントン・マルサリスに先んじて、ウルマーやアーサー・ブライスを
手がけていたというのは、今思えば先見の明があったと思うけど、
セールスが思わしくなければバッサリ切り捨てるメジャーの非情で、
ウルマーはたった3枚でクビになっちゃいました。
でも、そのコロンビアの2作目、82年の”BLACK ROCK” が、
ウルマーの一大傑作でしたからねえ。
今回、オランダのリイシュー専門レーベルがCD化して、LPと変わらぬ音質に大カンゲキ。
20年以上前に日本でCD化したことがあるんだけど、その日本盤は、
霞がかかったような音質だったんだよなあ。
それだけに今回のCD化は、嬉しさひとしおです。
ただ、何度も聴いて気付いちゃったんですが、このCD、盤起こしなんですね。
‘Family Affair’ のイントロのギターで、軽いプチ音が聞こえます。
ヘッドフォンでなければわからない程度なので、
気付かない人がほとんどだと思いますけれど。
フェイド・アウト処理なども丁寧にしているので、これなら盤起こしでも不満はありません。
本作は、ミュージック・リヴェレイション・アンサンブル名義の“NO WAVE” や、
“ARE YOU GLAD TO BE IN AMERICA?” のフリー・ジャズ/ファンク路線はそのままに、
ロナルド・シャノン・ジャクソンから、
カルヴィン・ウェストンとコーネル・ロチェスターのツイン・ドラムに
交替しています。これにより、ロック的なビートが強調され、
ジャズにカテゴライズされることを抵抗した、タイトルどおりの内容となりました。
ウルマーが弾きまくる曲ばかりでなく、ウルマーがバックに回り、
ロナルド・ドレイトンのソリッドなリズム・ギターを前面に出して、
フルートがミステリアスなムードを醸し出す‘Moon Beam’ など、アレンジも多彩。
コロンビアの1作目の“FREE LANCING” ではバッキング・ヴォーカルだった
アイリーン・ダッチャーが、2曲でリード・ヴォーカルを務め、
ウルマーと夫唱婦随を聞かせるのがハイライトです。
“FREE LANCING” とリズムのウネリがケタ違いになったのは、
ロックを志向したからという、単純なストーリーではありませんね。
ジャズを解体した前衛的手法で、ブルースやゴスペルにさかのぼる、
ブラック・ミュージックの原初的なエネルギーを呼び覚ましたからでしょう。
ブラック・ジャズのフィジカルの強さを仰ぎ見る、歴史的傑作です。
James Blood Ulmer "BLACK ROCK" Music On CD MOCCD14019 (1982)
2021-05-16 00:00
コメント(0)
アコーディオン・ジャズの決定盤 ドム(ドミニク)・フロンティア [北アメリカ]
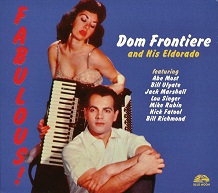
うわぁ、なっつかしい~!
秘蔵盤がとうとうCD化されちゃいましたぁ。
アコーディオン・ジャズの知られざる名盤、
ドム(ドミニク)・フロンティアのリバティ盤2枚。
ハタチの頃、池袋のメモリーレコードのおじさんに教えてもらった逸品ですー。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-11-05
ジャズでアコーディオンといえば、完全にその他楽器扱いで、
アート・ヴァン・ダム、ジョー・ムーニー、
レオン・サッシュといった人たちに代表されるとおり、
スウィング・マナーのラウンジーなジャズばかり。
バップ・イディオムのモダン・ジャズなんて、てんでお呼びじゃない、
イージー・リスニングの世界ではあるんですが、
ドム・フロンティアのこの2枚はひと味違って、スウィング・ジャズのスリルもたっぷりの、
ヒップなアルバムに仕上がっているのですよ。
でも、リバティというレコード会社からおわかりのとおり、
ポピュラー寄りの作品ではあるんですけれどね。
ドムことドミニク・フロンティアは、『アメリカ連邦警察 FBI』『逃亡者』
『ラット・パトロール』『インベーダー』など、
60年代の人気テレビ・ドラマのテーマ・ソングほか、
『奴らを高く吊るせ!』『大列車強盗』『薔薇の素顔』などの映画音楽を手掛け、
アコーディオン演奏でも、『ナイアガラ』『慕情』『帰らざる河』『愛のセレナーデ』ほか、
多くの映画に起用されてきた人。
70年代には、パラマウント・ピクチャーズの音楽部門の責任者にもなり、
映画スタジオの音楽部門をフルタイムで担当した、最後の現役ミュージシャンの一人でした。
そのドミニクが50年代にリバティに残したアルバムは、
今回スペインのブルー・ムーンから2イン1でCD化された
55年の“Dom Frontiere Sextet”、56年の“FABULOUS!” のほかに、
ショパン、バッハ、ラヴェルなどのクラシック曲を演奏した
58年の“MR. ACCORDEON” があります。
“Dom Frontiere Sextet” は、ドムのアコーディオンに、
バス・クラリネット、クラリネット、ギター、ベース、ドラムスのセクステット編成。
クラ2台というのがユニークです。
ドムのオリジナル曲のほか、キューバの名作曲家エルネスト・レオクーナの「そよ風と私」、
ラグタイム時代のピアニスト、フェリックス・アルントが残した
ノヴェルティなラグタイム「ノーラ」、「テンダリー」などを演奏しています。
かなり精緻なアレンジをしていて、
ルースに即興するほどの小節数は各楽器に与えられていません。
アコーディオンとクラ2台の絡みなんて、よく練られているんですよね。
3台の合奏のハーモニーが崩れて分散和音に移るところなんて、何度聴いてもゾクゾク。
“FABULOUS!” の方はヴィブラフォンとハープ(!)が加わったオクテット編成。
こちらもさらに、きっちり譜面に落としてある演奏ぶりで、
リズムが変わってがらっと場面展開する編曲などは、
映画音楽の技法が駆使されています。
もう30年以上、ジャズ雑誌を読んでいないので、不確かですけれど、
ジャズ雑誌のその他楽器の特集などにも、
この2枚が取り上げられたのを見たことがないので、
ほとんど知る人もいないんじゃないかなあ。
ジャズ・ファンより、モンド方面の趣味人にオススメしたい逸品であります。
Dom Frontiere and His Eldorado "FABULOUS!" Blue Moon BMCD902 (1955/1956)
2021-05-14 00:00
コメント(0)
70年代ソウルの帰還 PJ・モートン [北アメリカ]
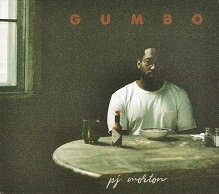

ジョン・バティステの“WE ARE” を絶賛愛聴中なんでありますが、
あのアルバムにはPJ・モートンも客演しているんですよね。
何年か前、PJ・モートンの“GUMBO” が話題になったとき、
CDを探すも見つからず、そのまますっかり忘れていたことを思い出しました。
あ、日本盤は出ているんですけれどね。
できるかぎりオリジナル盤で買うという、メンドくさい性分がいまだ抜けないもんで。
その後、ライヴ会場でしか売っていないらしいとかの情報を耳にして、
んじゃ、しかたがないかと諦めてたんですが、
思い出しついでにネット検索してみたら、ご本人のサイトで販売していることが判明。
翌年に出したスタジオ・ライヴ盤“GUMBO UNPLUGGED” もあったので、
一緒にオーダーしたのでした。
ニュー・オーリンズ出身のシンガー・ソングライター、というより、
キーボーディストやプロデューサーとしての活躍のほうが有名なPJ・モートン。
マルーンなんちゃらという人気ロック・バンドへの参加が、
この人の名刺がわりのように必ず言われますけれど、
かつてのビートルズとビリー・プレストンみたいなもんでしょうかね。
もともと楽曲提供や客演仕事などの裏方仕事が長かった人で、
ゴスペルを出自とする音楽性に加え、職人肌のR&B、ヒップ・ホップ、ジャズ使いに、
プロデューサーらしい才能ぶりがうかがわれます。
“GUMBO” というタイトルに、ルーツのニュー・オーリンズ色濃い内容なのかと思ったら、
さにあらず。人肌のぬくもりが伝わる70年代ソウル・マナーの生演奏サウンドに、
思わず感涙してしまいました。
そして、この徹底したスティーヴィー・ワンダー節も、いいじゃないですか。
こういうスティーヴィー・ワンダーそっくりさんシンガーって、
ときどき登場するけど(ミュージック・ソウルチャイルドとか)、
なぜかこの人の歌いっぷりには、その種のフォロワーにおぼえる抵抗感を感じず、
素直に聞くことができました。
おそらく彼が単なるシンガーではなく、演奏能力も高いプロデューサーとしてのセンスを、
サウンドのすみずみまでに発揮しているからじゃないかな。
ニュー・オーリンズ色はないと言ったものの、
前のめりに突進していく‘Stickin To My Guns’ あたりは、
ニュー・オーリンズ・ファンクらしいところ。
ストリングスのアレンジが、マット・ジョーンズという人がやっていて、
演奏はマット・ジョーンズ・オーケストラとクレジットされていますね。
シカゴの若手アレンジャーだそうで、独特のサウンドを生み出していて、
アレンジばかりでなくミックスも独自の個性を感じさせます。
そして、“GUMBO” 全曲をスタジオ・ライヴで一発録りした“GUMBO UNPLUGGED” の
一体感は見事としかいいようがありません。YouTube でも視聴できますけれど、
ストリングス・オーケストラ含め、
ミュージシャン全員がひとつの部屋に入り(コーラスだけ別部屋)、
せーのでやっている臨場感の素晴らしさといったら、もう。
こういう現場を取り仕切れる能力も、プロデュース経験のなせる業でしょう。
また、BJザ・シカゴ・キッドとハミルトンズをフィーチャーした
‘Everything's Gonna Be Alright’ の高揚感がたまりません。
ゴスペルばかりでなく、ニュー・オーリンズ・ファンクのテイストも加わっていて、
曲順を変えたライヴ盤では、アルバム・ラストに置いて、
大団円の盛り上がりになっているのも、サイコーです。
PJ Morton "GUMBO" Morton no number (2017)
PJ Morton "GUMBO UNPLUGGED" Morton no number (2018)
2021-05-12 00:00
コメント(0)
ポップになることの意味 カサイ・オールスターズ [中部アフリカ]
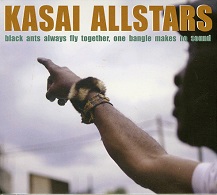
あれま。ずいぶんとポップになったこと!
コンゴの5つの民族(ルバ、ソンギエ、ルルア、テテラ、ルントゥー)の
メンバーが集合し、それぞれの民族のフォルクロール(伝統音楽)を融合して、
新たなるアンプリファイド・フォルクロールをクリエイトしたカサイ・オールスターズ。
17年に出た、映画『わたしは、幸福(フェリシテ)』のサウンドトラック
“AROUND FÉLICITÉ” 以来のアルバムですね。
コノノNo.1(ヌメロ・アン)ですっかり有名になった電化リケンベ(親指ピアノ)と、
電化リケンベ以上に強烈なバズ音を生み出すビビリ太鼓のディトゥンバ、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-12-12
サワリ音の利いた木琴、大型スリット・ドラムが生み出すグルーヴはそのままに、
リズムを整理したプログラミングとシンセの導入によってキャッチーなメロディを強調し、
より幅広い層にアピールするサウンドに仕上げています。
本作はメンバーのギタリスト、モペロ・ムペンバがプロデュースをしていて、
リズム・プログラミングもモペロとエンジニアのパピ・アトゥケの二人が担当したんですね。
パピ・アトゥケはシンセも演奏していて、メロディの補完役を務めています。
どうやらポップ化の立役者は、モペロ・ムペンバとパピ・アトゥケの二人のようだな。
従来のトランシーなビリビリ感電フォルクロールを期待すると、
はぐらかされた気分になると思いますけど、ぼくはこの方向性、強く支持しますね。
同じカサイ地域に暮らす民族でも、言語も文化も違い、
それぞれの音楽的伝統は相容れないとされていたのを、
カサイ・オールスターズは乗り越え、見事に共有してみせました。
‘Unity Is Strength’ と題した曲があるように、本作を貫くテーマは「結束」です。
先行シングルで出された‘Olooh, A War Dance For Peace’ でも、
村人の争いが起こった時、武器を手にして戦いの踊りを踊ることによって
紛争解決を図るという、平和的解決のための昔からの智慧が歌われています。
自国/自民族優先主義が引き起こした社会の分断を立て直すためにも、
今必要とされているのは、いかに人々の連帯や結束を取り戻すかです。
そのためにも、一部の尖ったファン向けのアンダーグラウンドな音楽に向かうのではなく、
幅広いファン層を求めていくポップな方向性を、ぼくは支持したいのです。
Kasai Allstars "BLACK ANTS ALWAYS FLY TOGETHER, ONE BANGLE MAKES NO SOUND" Crammed Discs CRAM295 (2021)
2021-05-10 00:00
コメント(0)
マダガスカル伝統ポップ・ア・ラ・カルト ハンタ [インド洋]

マダガスカルの聞き逃し物件、発見。
02年にフランスのマリオンから出ていた女性歌手の2作目で、
本名のヴニハンタマララ・ランパラニを略して、ハンタと称しています。
マラガシ(マダガスカル語)では、「イヤント」と発音するそうですが、
いやぁ、マラガシの発音って、本当に難しくって、よくわかんない。
カボシ、マルヴァニ、ヴァリハ、ソディナといった民俗楽器主体の編成で、
ベースを除き、オール・アクースティックの伝統サウンドを聞かせます。
ゲストに、マダガスカルを代表するミュージシャンで世界的にも知られる、
ヴァリハのジュスティン・ヴァリとアコーディオンのレジス・ジザヴが参加しています。
軽やかな声で歌うハンタのスピード感溢れる歌いっぷりは、実に爽やか。
コーラスで早口ヴォーカルを聞かせる曲でのリズムのキレが、バツグンです。
女性コーラスに男性メンバーも加わって歌うポリフォニーも、味がありますね。
ハンタは、母方の祖父がピアニストで、母親は有名な合唱団の歌手という
中央高原の音楽一家に生まれ、幼い頃から音楽とダンスに没頭していたのだとか。
幼少期のほとんどを南部で暮らしたため、伝統儀式を通じて南部の伝統音楽を身につけ、
ツァピキ、バナイケ、ジヘ、ベコといった南部の伝統音楽も得意としています。
ハンタのグループは、マダガスカル南部代表として
フェスティヴァルに参加することもあるそうです。
本作では、西部のサレギや南部のツァピキといったシンコペイトの利いたリズム曲のほか、
南部の葬送歌のベコや、中央高地の伝統芸能ヒラガシの影響を思わせる曲も歌っていて、
マダガスカル音楽の多彩な伝統音楽の魅力をアピールしています。
アリオンらしい企画のアルバムですけれど、そんな企画と見事にハマったのは、
マダガスカルの多様な民族の音楽を習得した、ハンタの幅広い音楽性ゆえですね。
Hanta "RANO" Arion ARN64570 (2002)
2021-05-08 00:00
コメント(0)
そよ風香るフォーキー・マコッサ マリオ・コンボ [中部アフリカ]

爽やかなアフリカン・フォーキー・サウンドに、
どこの人?と思ったら、カメルーンでした。
マリオ・コンボ。初めて聴く名前ですが、
20年のキャリアがある人だそうで、これが4作目だそうです。
こんな感じの人、なんかいたよねえと、しばし思案して、
ブリック・バッシーが浮かんだところ、
なんとそのブリック・バッシーが音楽監督・アレンジをしていて、ビックリ。
しかもこのアルバム、15年作じゃないの。
ブリック・バッシーに世界の注目が集まった“AKÖ” が出たのと、同じ年ですよ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-09-27
う~ん、なんだか引き寄せるものがあるなあ。
ギターやカヴァキーニョを中心とした生音中心のアンサンブルに、
やわらかな男性コーラスと、爽やかなフルートが彩を添える
シンプルなプロダクション。余計な音を積み重ねず、
スルドなどのブラジルの楽器を使いながら、
マコッサやサンバの軽やかなリズムにのせて、マリオ・コンボは歌います。
まるでブラジルかカーボ・ヴェルデのようなサウンドですね。
クセがなく、親しみやすいメロディは、
カメルーンらしいアフロ・ポップといえますけれど、
考えてみると、カメルーンでは60年代のエボア・ロタン以降、
こうしたギター弾き語りの系譜が続いているともいえそうですね。
そよ風のようなリズム、なめらかな声と気さくな歌い口に、
カメルーン・マナーの洗練を味わえる良作です。
Mario Combo "DIMBAMBE IDENTITÉ" Bright Moon Production MC201597/1 (2015)
2021-05-06 00:00
コメント(0)
アマピアノ・シリーズ第2弾 DJ・ブラック・ロウ [南部アフリカ]

オウサム・テープス・フロム・アフリカが、
テノ・アフリカに次いでリリースしたアマピアノ第2弾。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-03-31
テノ・アフリカはインストでしたけれど、
こちらは多彩なMCやシンガーをフィーチャーしています。
DJ・ブラック・ロウことサム・オースティン・ラデベは、
プレトリア出身の20歳のDJ/プロデューサーで、本作がデビュー作。
テノ・アフリカがジャズやハウス色の強いプロダクションだったのに比べると、
ブラック・ロウは、より実験性のあるアフロ・テックなサウンドを狙っているようで、
刺激的なダンス・ミュージックを作り上げています。
ループするビートはポリリズミックで、単調な四つ打ちのハウスやテクノとは別物だし、
電子音のパーカッションと深みのあるベース・ラインが生み出すグルーヴは、
生の打楽器使いと変わらないウネリを、しっかりと生み出しているじゃないですか。
クリアでヘヴィな重低音を響かせるオーディオ・エフェクトは、生楽器にはない快感で、
これこそエレクトロ・ミュージックならではの魅力でしょう。
ディープ・ハウスのジャジーでスムースなサウンドに、
不穏なシンセ音やドープなムードが漂うシンセ音がレイヤーして、
未来的なサウンドとなっているところが、アマピアノの真骨頂でしょうか。
また、歌詞については、ズールー語ばかりでなく、
ツワナ語やペディ語でも歌われているそうで、
ローカルをグローバルに連結させるハイブリッドな試みを、
若い才能が結実させています。
DJ Black Low "UWAMI" Awesome Tapes From Africa ATFA042 (2021)
2021-05-04 00:00
コメント(0)
ニュー・オーリンズ・ファンク・パワーハウス ダンプスタファンク [北アメリカ]

いぇ~い! 来た来たぁ、ダンプスタファンクの新作!!
ゴールデン・ウィークに間に合って、ステイ・ホーム期間をゴギゲンに過ごせますよ~。
なんつったって、ニュー・オーリンズ・ファンク最高のバンドですからね。
12年に来日して、渋谷のクラブクアトロの密なステージで踊りまくったことが、
昨日のことのように思い出されますよ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-08-03
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-06-24
それにしても、前作が13年ですからねえ。
ずいぶん長いインターヴァルだったよなあ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-08-14
ドラマーがニッキー・グラスピーからデヴン・トラスクレアに交替して、
トランペットとトロンボーンの2管が加わって7人編成になったダンプスタファンク、
ますます強力になりました。
オープニングが、なんとバディ・マイルスの‘United Nations Stomp’。
豪快なロック・テイストのファンクになっていて、
ゲストのマーカス・キングのギターが大暴れ。
ノッケから血流が上がって、コーフンしまくっちゃいました(嬉)。
これですよ、これ。打ち込みなんぞ用はないぜって。
肉弾飛び散る人力ファンクは、まさしくパワーハウス。
2管がレギュラーになったことで、バンド・サウンドはパワー・アップ。
さらに曲によりサックス、トランペット、トロンボーンのゲストも迎え、
厚みのあるサウンドを生み出しています。
ほかにもゲストが大勢いて、アルヴィン・フォード・ジュニアが
半数の曲でドラムスを叩いている(準レギュラー?)ほか、
ヴェテランのワディ・ワクテル(!)がアディショナル・ギターとして参加しています。
平野琢也もパーカッションで参加していますよ。
スライ・ストーンの‘In Time’ のカヴァーも、聴きどころのひとつ。
リズム・ボックスとぺなぺなギターにトボけたサックスという、
スライ流のクールなファンクが、
剛腕で筋骨隆々の肉体美を誇るファンクに様変わりしています。
この正攻法なファンクぶりに、
トランプ政権末期のアメリカにカウンターとして迎え撃とうとする、
彼らの姿勢を感じ取りました。
それがより明確となっているのは、
ラッパーのチャーリー・ツナとトロンボーン・ショーティをゲストに迎えた、
ラスト・トラックの‘Justice’。
彼らは、いまは斜に構えている時代ではないと、
正義を真正面に見据える勇気を、人々に奮え立たせています。
Dumpstaphunk "WHERE WE GO FROM HERE" The Funk Garage TFG76302 (2021)
2021-05-02 00:00
コメント(0)




