シンセサイズ・フナナーの傑作 アントニオ・サンチェス [西アフリカ]
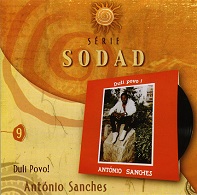
カーボ・ヴェルデのアントニオ・サンチェスが生涯にたった1枚だけ残した
83年のLPは、知られざるポップ・フナナーの快作でした。
アナログ・アフリカが、18年にLP限定でリイシューして、
ぼくもこのレコードの存在を知ったんですけれど、玉石混交というより、
ほとんど「石」だらけのポップ・フナナーのなかで、
このレコードは間違いなく「玉」といえる名作でした。
ところがこのレコード、ポルトガルのソダッド・シリーズの一枚で
すでにCD化されていたんですね。うわぁ、知らなかったなぁ。
あわてて入手して、じっくりと聴いてみれば、シンセサイズされたフナナーばかりでなく、
‘Bencã̧o De Gente Grande’ と‘Pinta Manta’ の2曲はバトゥクじゃないですか。
アナログ・アフリカのサイトにはそうした指摘がなく、
ひょっとしてサミー・ベン・レジェブは、バトゥクをわかってないのかも。
アコーディオンをシンセサイザーに置き換え、
ギターやドラムスを取り入れてエレクトリック化したポップ・フナナーは、
カーボ・ヴェルデ独立後の70年代末、新世代の若者たちが集まったバンド、
ブリムナンドが始めたものでした。
独立前に演奏を禁止されていたフナナーを、ブリムナンドはまったく新しい姿で蘇らせ、
ポップ・フナナーは瞬く間にブームとなり、
新生カーボ・ヴェルデを象徴する音楽となったんですね。
しかし、ぼくがこうしたポップ・フナナーを評価しないのは、
ドラムスがフナナーのリズムに合った叩き方をクリエイトせず、
安直なロックのエイト・ビートを持ち込んだからです。
これがブリムナンドからフィナソーンまで、
主要なポップ・フナナーのバンドに共通するダメなところで、
レパートリーもフナナーに焦点を絞らず、
つまらないポップ・ナンバーやスロー・バラードをやる不徹底ぶりに、
なおさら興味をそがれたものです。
さて、そんな安直なロック化とは次元の異なるポップ・フナナーを生み出した
アントニオ・サンチェスは、49年のクリスマス・イヴに、
サンティアゴ島の都市シダーデ・ヴェーリャで生まれました。
父親はフェロー(金属製ギロ)奏者で、母親はバトゥクのグループに所属する音楽一家で、
アントニオも幼い頃から歌とフェローを習い、プライアの食肉市場で働いていました。
カーボ・ヴェルデ独立3年前の72年に、
友人の歌手フランク・ミミタとともにリスボンに移り住み、
音楽以外のさまざまな仕事で生計を立てていましたが、
ミミタの勧めで、カーボ・ヴェルデ人歌手のバナが経営していたレストラン、
モンテ・カラで歌を歌ったことから、運命が変わります。
当時モンテ・カラでハウス・バンドを務めていたのが、
カーボ・ヴェルデ伝説のグループ、ヴォス・デ・カーボ・ヴェルデでした。
70年代初頭に一度解散したものの、バナと音楽監督のルイス・モライスによって再結成し、
モンテ・カラを拠点に演奏活動を再開していたんですね。
その後バナは、グループに新しいサウンドを取り入れようと、
キーボードを加えることを考え、パウリーノ・ヴィエイラを島からリスボンに呼び寄せ、
ルイス・モライスに代わって、パウリーノがリーダー兼チーフ・アレンジャーとなります。
当時のヴォス・デ・カーボ・ヴェルデには、
ドラムスのティト・パリス、ベースのベベトがいて、
パウリーノの弟のトイ・ヴィエイラが82年にリスボンに招かれて参加していました。
モンテ・カラで歌ったアントニオ・サンチェスの生々しいヴォーカルに
惹きつけられたパウリーノは、すぐさまアントニオをレコーディングに誘い、
リスボンのスタジオでたった一日のセッションによって、本作を完成させます。
アントニオはレコーディング当日、スタジオへ歌詞を持たずにやってきて、
ヴォス・デ・カーボ・ヴェルデのメンバーを驚かせます。
ところが、フナナーを即興で歌うアントニオの本領が発揮されて、
メンバー全員がノリまくり、レコーディングを特別の場に変えてしまったという、
メンバーの証言が残されています。
モルナやコラデイラの伝統のなかで育ったトイ・ヴィエイラは、
当時ブームになっていたブリムナンドのポップ・フナナーをなぞろうとしましたが、
アントニオは違うサウンドを作りたいと、トイのシンセサイザーの音色に注文を付けます。
そうしたアントニオの注文が功を奏し、
ポップ・フナナーの特徴といえるシンセの軽いサウンドではなく、
アコーディオンの音色に近づけた低音の利いたサウンドで、
粘りのあるリズムを生み出しているんですね。
ポップ・フナナーらしからぬ重量感が、本作のキモですね。
アントニオが演奏していると思われるフェローのビートも前面に打ち出され、
バトゥクの2曲では、チャベータを叩くビートがしっかりとグルーヴを生み出しています。
アントニオの怒鳴るように歌う奔放なヴォーカルも、パワフルそのもの。
奴隷文化の伝統を継いだフナナーのどす黒さが発揮された名作です。
ちなみに、アナログ・アフリカの2000枚限定LPは、
バンドキャンプのページを見ると、まだ150枚以上売れ残っているようです。
どういうわけだか曲順を変えていて、なんでこういう無意味なことをするのかなあ。
António Sanches "BULI POVO!" Sons D’África CD332 (1983)
2021-08-30 00:00
コメント(2)
代表作はどれ? ラルフ・タマール [カリブ海]

マラヴォワの新作“MAIBOL”で、
マルチニークの名クルーナー健在を示してくれたラルフ・タマール。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-01-12
ラルフ・タマールがマラヴォワを87年に退団したのは、
パリで本格的な歌手活動をめざすためだったことは、ご存じのとおり。
同じ87年にカッサヴのジャン=クロード・ネムロと
ジョルジュ・デシムスのプロデュースで、ジョルジュ・デブスのGDプロダクションから
ソロ・デビュー・アルバム“EXIL” を出したんでした。
以来、タマールのソロ・アルバムをずっと聴いてきましたけれど、
タマールの代表作というと、どれになるのかなあ。
どれも決定打に欠けるというか、これ!というアルバムが思い浮かばないんですよね。
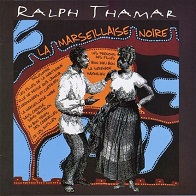
ぼくが一番愛着があるのは、98年の奴隷解放150年を記念したアルバムで、
グアドループの作曲家ジェラール・ラ・ヴィニの曲を取り上げた
“LA MARSEILLAISE NOIRE”。
あのアルバムにはビギンやマズルカばかりでなく、ボンバ、カリプソ、メレンゲもあり、
ジェラール・ラ・ヴィニを題材として汎カリブ音楽を取り上げた、
スケールの大きな作品でした。
大力作ではあったものの、トリビュートものという企画作ゆえ、
タマールの代表作と呼ぶには、ちょっとためらいもおぼえてしまうんです。
そう考えると、カッサヴ所属のGDプロダクションからデビューして、
ズーク色の強いデジタル・サウンドのなかでは、
タマールのクルーナーとしての魅力を発揮できなかったように思えるんですよね。

“LA MARSEILLAISE NOIRE” 以外では、
ピアニストのマリオ・カノンジュとの共同名義作で、
近年再評価著しいピアニストのマリウス・クルティエをトリビュートした
“HOMMAGE À MARIUS CULTIER” が、タマールの魅力をよく映し出していました。
若き日のタマールは、ピアニストのマリウス・クルティエのもとで修行していたんですね。
でも、これもトリビュートものだしなあ。やっぱり、ビギン主体の生演奏のサウンドが、
タマールにはやっぱりよく似合うということなんだと思います。
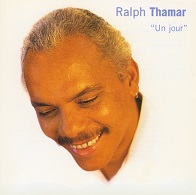
やはり00年代以降のアクースティック回帰の音づくりになってからの方が、
タマールのヴェルヴェット・ヴォイスは魅力を放ちましたね。
ビギン・ジャズ・ピアニストのロナルド・チュールがキー・パーソンとなった
02年作の“UN JOUR” も良かったしねえ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-10-07
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-02-20

でも、デジタル・ズーク時代にも、聴き逃せないレコーディングはありました。
ジャン=クロード・ネムロのプロジェクトのターボ・II では、
ビギン、シューヴァル・ブワ、カドリーユなどのマルチニークの伝統リズムを使って、
デジタル・サウンドとの融合をトライしていました。
デジタル・ビートに絡むタンブー(太鼓)の生音が絶妙なブレンド具合で、
リード・ヴォーカルで参加したタマールも、セクシーな歌いぶりを聞かせていました。
ターボ・II は2枚のアルバムしか残しませんでしたが、
2作目には、ベースのティエリー・ファンファン、
パーカッションのデデ・サン=プリも参加して、実力者が脇を固めていました。
カーニヴァル色を打ち出したアゲアゲのアルバムで、ラスト・トラックでは、
「グアンタナメラ」のクレオール・ヴァージョン‘Sa Ou Ka Lavé’ で
大団円を迎えるという10曲以上のメドレーが、最高潮に盛り上げてくれます。
ジャケットには、なんと、金髪のウイッグをつけて女装したタマール(!)が、
バイクの一番後ろにまたがっていますよ。
90年頃というと、ロナルド・ルビネルが主導したエスニカラーというプロジェクトでも、
マルチニークの伝統リズムとデジタル・サウンドを融合し、ヒップ・ホップも取り入れた
サウンドに挑戦していて、伝統回帰がひとつのトレンドになっていた時期でしたね。
そうそう、エスニカラーにもタマールは参加していたし、エディット・ルフェール、
ジョセリーヌ・ベロアール、ジャン=フィリップ・マルテリーといった歌手陣に、
ジャコブ・デヴァリュー、ティエリー・ファンファン、デデ・サン=プリなど、
オールスター勢揃いでした。
このターボ・II もそうした流れのアルバムだったと思いますが、
当時ほとんど知られていなかったから、タマール・ファンでも知らない人は多いかも。
ソロ・アルバムで決定作がなくても、往年のマラヴォワ、そして復帰後のマラヴォワに
名作は目白押しなんだから、なにも困ることはないってか。
Ralph Thamar "EXIL" GD Productions GDC45004 (1987)
Ralph Thamar "LA MARSEILLAISE NOIRE" Wagram 3045252/WAG334 (1998)
Ralph Thamar & Mario Canonge "HOMMAGE À MARIUS CULTIER" Déclic Communication 09702-2 (1994)
Ralph Thamar "UN JOUR" Créon Music 5806172 (2002)
Turbo Ⅱ "VOLUME 2" Sonodisc CDS7234 (1991)
2021-08-28 00:00
コメント(0)
ジャズ・サンバのニュー・ディメンション ジャニ・ドゥボッキ [ブラジル]
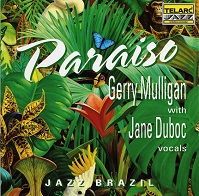
夏の疲れがたまってくると、手が伸びるチルな一枚。
今年もまた棚から取り出してきた、
ジェリー・マリガンとジャニ・ドゥボッキの93年コラボ作です。
ジャニ・ドゥボッキは、85年の“PONTO DE PARTIDA”(乞CD化!)でファンになった人。
フュージョン調の伴奏にのせて、スキャットを駆使した高い歌唱力を聞かせるところは、
MPBシンガーというより、
ジャズ・ヴォーカリストの資質をくっきりと映し出していました。
こういうと、キレッキレのタイプと誤解されちゃうかもしれないけれど、
じっさいは柔らかな歌い口で、大仰な表現をせず、静かに歌うタイプのシンガー。
そのジャニがジェリー・マリガンに乞われてニュー・ヨークで録音した本作は、
極上のリラクシン・アルバムに仕上がりました。
ジェリー・マリガンは、バリトン・サックスの第一人者というより、
作編曲家として優れた作品を残した音楽家という印象があります。
バリトン・サックスの深い音色をあれほど美しく吹奏できたのは、
マリガンをおいてほかにはおらず、
ブラジル音楽と親和性の高いジャズ・ミュージシャンという意味では、
ポール・デズモンドに共通するタイプと、ぼくには見えました。
じっさい二人は、若い頃共演もしていたしね。
ところが、ジェリー・マリガンがブラジル音楽に接近するのは、
ようやく晩年になってからのことで、なぜこれほど遅れたのか不思議ですが、
長年想像していたとおり、抜群の相性の良さを示してくれました。
レパートリーは、ジョビンの‘Amor En Paz’ ‘Wave’、
トッキーニョの‘Tarde En Itapoan’ をのぞいてすべてマリガン作の曲で、
ジャニが歌詞を書いています。
ジャニの温かな声質と、マリガンのふくよかなサックスがベスト・マッチングで、
ジャニのリリシズムに富んだ、繊細で丁寧な歌い回しのなかに、
ジャズ・ヴォーカリストらしい表現が鮮やかに示されています。
グレッチェン・パーラトのようなヴォーカル表現が高く評価されるいま、
現代的なジャズ・ヴォーカルの文脈から、本作は見直されてもいいんじゃないかな。

レパートリーはジャズ・サンバあり、バイオーンあり、ボサ・ノーヴァありで、
ぼくの大好きなマリガンのアルバム、76年作の“IDOL GOSSIP” から、
‘North Atlantic Run’ をやっているのも、嬉しいんです。
この曲って、サンバだったんだよね。
テーマのメロディをハミングするジャニは、まるでショーロ・ヴォーカルみたいで、
グレッチェンの先取りともいえるんじゃない?
これほどの傑作なんですが、最大の難点はジャケットのアートワーク。
チャールズ・リン・ブラックなんて絵描きを起用する悪趣味が、いただけない。
ラッセンとかとおんなじ手合いで、カンベンしてよ、もう。
Gerry Mulligan with Jane Duboc "PARAISO - JAZZ BRAZIL" Telarc CD83361 (1993)
Gerry Mulligan "IDOL GOSSIP" Chiaroscuro CR(D)155 (1976)
2021-08-26 00:00
コメント(0)
越僑シーンで渇きを癒すヴェトナム歌謡 クイン・ヴィ [東南アジア]
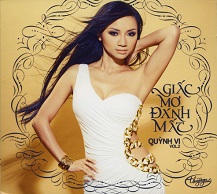

コロナ禍でヴェトナム音楽の新作CDがまったく手に入らなくなってしまいました。
2020年作なんて、1枚も手元にないんだから、惨憺たるありさまです。
喉の渇きを癒したくて、久しぶりに越僑ものに手を伸ばしてみました。
知っている歌手で、誰か新作を出していないかなとチェックしてみたところ、
クィン・ヴィの近作2枚を見つけました。
ずいぶん前にこの人のアルバムを買って、ぼく好みの人と記憶していたんですよね。
その2枚が届いて、気付かされたのは、
ぼくの持っていた09年作がデビュー・アルバムだったということ。
17年作に VOL.2 の表記があって、2作目が出るまで8年もかかったんですね。

クィン・ヴィは、83年ハノイ生まれの歌手。高校卒業後に渡米して、
07年のパリ・バイ・ナイト・タレント・ショー・コンテストで優勝し、
09年にトゥイ・ガからデビュー作を出しました。ぼくが持っていたCDがそれでしたね。
たしかな歌唱力で、クセのない素直な歌いぶりが好ましく、
泣きのバラードを情感を込めて歌っても、歌いすぎることがなく、しっとりとしていて、
胸に心地良い余韻が残ります。
ただ、このアルバムには、男性歌手とデュエットするロック歌謡のような曲があり、
う~ん、こういうのはいらないかな、なんて思っていました。
果たせるかな、今回手に入れた17年・18年作とも、バラード・アルバム。
デビュー作にあったロック歌謡調は姿を消し、17年作にEDMぽい曲があるものの、
メロディが哀調なので、バラード・アルバムのなかのチェンジ・オヴ・ペ-スで、
違和感を感じさせません。
歌もデビュー作から表現力が増しましたよねえ。
ハイ・トーンがよく伸びるようになって、声に磨きがかかりました。
そして18年作は、全曲スロー・バラード。
ホルダー仕様の特殊パッケージに、
ファッション・モデルばりの写真を載せたポスターを封入して、
近年のヴェトナム本国のCDを意識しているのは、間違いないでしょう。
アメリカ盤でこのタイプの美麗ジャケットは、初めて見たなあ。
中身の方も、本国のボレーロ・ブームを意識したプロダクションで、ゴージャス。
ただし楽曲は、オールド・ヴェトナム歌謡のボレーロのような深い叙情ではなく、
香港ポップスに近いドライなバラードといった趣を感じさせます。
そこが本国と越僑の差なのかな。
全曲、悲恋ソングでしょうか。哀切たっぷりの楽曲が並びます。
ちなみに、ヴェトナム民俗色はありません。念のため。
両作とも、男性歌手がゲストで加わってデュエットしている曲がありますが、
男性歌手は、旦那さんのフィ・ヴーのようです。
クイン・ヴィは11年にフィ・ヴーと結婚し、二人の息子がいるとのこと。
久しぶりにヴェトナム歌謡を堪能できて、大満足です。
Quỳnh Vi "GIẤC MƠ ĐÁNH MẤT" Thúy Nga QV01 (2017)
Quỳnh Vi "VẬY LÀ DỦ" Thúy Nga no number (2018)
Quỳnh Vi "VÙI SÂU TRÁI TIM BUỒN" Thúy Nga TNCD453 (2009)
2021-08-24 00:00
コメント(0)
ファミリーが伝えるガリフーナ サリー・エンリケス・レイズ [中央アメリカ]

15年も前に出ていた、知られざるガリフーナの名作を発見しました。
ガリフーナの歌を歌い継いできた家系に生まれたサリー・エンリケス・レイズが、
亡くなった母親セミオナを偲んで制作したアルバム。おそらく自主制作盤でしょう。
アルバム冒頭で、サリーがアルバム制作の意図を述べています。
ジャケットには、サリーの名前が明記されておらず、
ライナーのクレジットに小さく記名があるのみ。
『セミオナからの贈り物』というタイトルと、
母親セミオナのポートレイトが、ジャケットを飾っています。
サリーが歌うストーリーテリングのよう曲もあれば、
姉のヴァージン・エンリケスと甥のガリフが囃子役を務め、
コール・アンド・レスポンスで歌うダンス・トラックもあります。
語りが途中に差し挟まれる曲など、
さまざまなタイプのガリフーナの歌を聴くことができます。
サリーやヴァージンの自作曲とともに、母が作った曲も4曲歌っていて、
そのうちの2曲はレコーディングされ、シングルになったとのこと。
伴奏は、ガリフーナ・ドラムの叩き手であるグレン・Q・ガルシアと
クラベスやマラカスなどのパーカッションを担当するスパイス・キラの二人が
多重録音をして、アンサンブルを作っています。
パカン、パカンと乾いた高音を響かせるドラミングがシャープで、
前へ前へと疾走するリズムに血が湧きたちますねえ。
多くのレパートリーは、打楽器のみのオーセンティックなガリフーナですが、
シンセサイザーを取り入れて、ポップに仕上げたトラックもあって、
これがとてもいいアクセントになっています。
サリーのサビの利いた歌声からは、潮焼けした肌の匂いが香ります。
ガリフーナ文化を伝えてきた、ベリーズの家族の物語が詰まったアルバムです。
Sally Enriquez Reyes "TIDEWESE SEMIONA" no label no number (2006)
2021-08-22 00:00
コメント(0)
晩夏の幻影 南佳孝 [日本]

立秋を過ぎ、残暑の気配を感じられる頃になると、
毎年聴き始める、南佳孝の『SOUTH OF THE BORDER』。
40年以上も変わることのない、生涯の晩夏の定盤であります。
今年も、仕事帰りのウォーキングで汗を流しながら、聴いているのでありました。
このレコードが出たのは、大学2年の後期が始まった、たしか9月のこと。
先行シングルの「日付変更線/プールサイド」を聴いて、
アルバムを心待ちにしてたんでした。
7月21日に発売されたそのシングルは、
レコーディングを終えた後に買いに行ったから、
いまだにその日付をちゃんと記憶してますよ。
レコーディングってなんのこと?と思われるでしょうが、
まあ、そこは軽く受け流してくださいな。
前作の『忘れられた夏』では、まだ未完成だった南佳孝の世界観を、
当時気鋭の若手アレンジャーだった坂本龍一という才能を得て、
一気に拡張することに成功したアルバムでした。
『摩天楼のヒロイン』のノスタルジック路線とはまた意匠を変え、
南独自の虚構の歌世界を完成させた最高傑作です。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-11-19
ぼくは、いまでも本作が、日本のポップスの金字塔であると確信しています。
生涯再生回数だって、ダントツのアルバムであることは間違いないし。
来生えつこ、三浦徳子、松任谷由実たちがペンをふるった
短編小説のような歌詞は、日本ではない、どこか仮想の国を舞台としていて、
まるで外国映画を観ているような映像が立ち上ってきます。
そのスクリーンに繰り広げられるロマンティシズムとダンディズムは、
日本のポップスとは思えぬ洋楽的洒脱さに溢れていたのでした。
のちに、「モンロー・ウォーク」(79)や
「スローなブギにしてくれ」(81)というヒット曲によって、
南の音楽は大衆化し、シティ・ポップの旗手扱いされますけれど、
そうしたヒット曲にありがちな俗受けする野暮ったさは、
『SOUTH OF THE BORDER』にはみじんもありませんでした。
池田満寿夫のリトグラフをジャケットに選んだのも、この名盤にふさわしく、
どこまでも上質で、気品とも呼べる風格が、このアルバムには備わっています。
細野晴臣のスティール・ドラム、佐藤博のラテン・ピアノ、南自身が弾くカリンバが、
幻想の熱帯を演出し、サンバやボサ・ノーヴァ、ボレーロを援用して、
仮想のトロピカル・ミュージックを組み立てた坂本龍一のアレンジは、
細野晴臣の『泰安洋行』のサウンド・プロダクションをホウフツさせます。
どれだけスコアを書いたのか、若き日の坂本の凄まじい熱気が伝わってくるかのようです。
40年以上聴き続けていても、いまだに感服してしまうのが、
アルバム・ラストの「終末(おわり)のサンバ」のコーダ部で、
坂本が施した弦楽オーケストラの編曲。
このオーケストレーションは、坂本龍一のベスト・ワークの一つじゃないですかね。
メロディ・メイカーとして、南が群を抜く才能であることは言うまでもないですけれど、
クルーナー・ヴォイスも、ちょっとフラットする音程にめちゃくちゃ色気があって、
誰にもマネのできない個性ですよね。
生涯聴き続けても、けっして色褪せることなく、
聴くたびにその世界に没入して官能を呼び覚ます、永遠の名作です。
南佳孝 「SOUTH OF THE BORDER」 GT MHC7 30006 (1978)
2021-08-20 00:00
コメント(0)
ライ・クーダーのアクースティック・セット [北アメリカ]
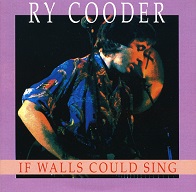
ジョゼフ・スペンスを知るきっかけとなったのが、
ライ・クーダーの『紫の渓谷』だったことは、前回書きましたけれど、
あのレコードのオリジナル曲を聴いてみると、
ライのヴァージョンとはぜんぜん違ったりして、ずいぶん驚かされたもんです。
ウディ・ガスリーの「自警団員」なんて、とても同じ曲とは思えなかったもんねえ。
ライがさまざまなアイディアを施して、曲をアレンジするばかりでなく、
ギター・プレイ向けにかなり曲も改変していて、その独創性にただただビックリでした。
ライ・クーダーの『紫の渓谷』と、ポール・サイモンの『ひとりごと』の2枚は、
15歳のぼくに、音楽の奥深さを教えてくれたばかりでなく、
アメリカ音楽探索の旅へと向かわせたアルバムでもありました。
ライは、アルバムでは大勢のミュージシャンとともに、
かなり作り込んだサウンドを聞かせていましたが、
ステージでは、アクースティック・ギター一本のソロ・ワークで、
抜群の腕前を披露していて、これがまた絶品だったんですよ。
当時日本でも放映されていたアメリカのテレビ番組、
「ミッドナイト・スペシャル」にライ・クーダーが出演したことがあって、
その時にテレビから録音したテープは宝物でした。
そういえば、あの番組って、今考えると贅沢なラインナップでしたよねえ。
マリア・マルダー、リトル・フィート、ランディ・ニューマンなんかが観れたんだもんなあ。
アルバムでは聞くことのできない、ライのアンプラグド・ヴァージョンをたっぷり味わえる
この時のテープが好きすぎて、のちに初めて手を出したブートレグも、
カリフォルニアのレコード・プラントとニュー・ヨークのバッファローで
74年に録音されたライヴ音源だったっけ。
“PARADISE AND LUNCH” のプロモーションとおぼしきライヴで、
リズム・セクションにコーラスも加わって、ライがエレクトリックでスライドを弾く曲も
あるんですけれど、メインはアクースティック・ギターとマンドリンの弾き語り。
ジョゼフ・スペンスを聴いていたら、
ライ・クーダーのアクースティック・ギターも聞きたくなって、
思わず棚からCDを引っ張り出してきました。
CDにはLPには収録されていなかった曲も追加されて、
バンド演奏のエレクトリック・セットの曲が増えたんだっけ。
70年のデビュー作から74年の“PARADISE AND LUNCH” まで4作の
レパートリーをまんべんなくセレクトしていて、
この時代のライをこよなく愛するぼくにとっては、最高なのでした。
Ry Cooder "IF WALLS COULD SING" Triangle PYCD082
2021-08-18 00:00
コメント(0)
バハマが生んだギター・マスター ジョゼフ・スペンス [カリブ海]
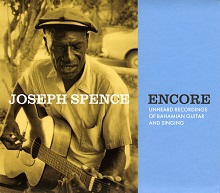
ジョゼフ・スペンスの65年未発表録音集?
へぇ~、半世紀以上も眠っていた音源かぁ。
もう何十年もジョゼフ・スペンスを聴いていないので、
懐かしくなって手が伸びました。
ぼくがこのバハマのギター・マスターの存在を知ったのは、
ご多分に漏れず、ライ・クーダーの『紫の渓谷』がきっかけ。
ジョゼフ・スペンスの‘Great Dreams From Heaven’ をライがカヴァーしていたんですね。
タブ譜があったおかげで、三拍子の短いギター・インストは、
高一のギター初心者でも、なんとかサマになりました。
6弦をDに落とすドロップDという変則チューニングを覚えたのも、
この曲がきっかけでしたね。
探究心旺盛な年頃だったので、本家本元のジョゼフ・スペンスも聴かなきゃと、
すぐさまフォークウェイズ盤を買ったんですが、そのギターのスゴ腕にノケぞりました。
フィンガー・ピッキングのリズムが、とにもかくにも強力。
メロディをアタックの強い音で弾き、流れるようなラインを生み出す一方で、
親指が弾く精度の高いベース音の対比が鮮やかで、
これホントに一人で弾いてんのかというグルーヴを生み出すんです。
キレまくったギター・ワークとスピード感は、とても高一の手に負えるものではなく、
早々に白旗を上げて、コピーしようという気さえ起こらなかったもんなあ。
今回の未発表録音集は、レコーディング・エンジニアのピーター・シーゲルが、
ナッソーのスペンスの自宅に妹のエディス・ピンダーの家や、
ニュー・ヨークのシーゲルの自宅、コンサート会場などで録音したものだそうです。
65年というと、ジム・クウェスキン・ジャグ・バンドのフリッツ・リッチモンドが
ナッソーに出向いて録音した、エレクトラ盤の“HAPPY ALL THE TIME” を出した
翌年にあたり、スペンスの絶頂期ですね。
そのエレクトラ盤でもやっていた‘Out On The Rolling Sea’‘Bimini Gal’ など
おなじみの名曲をはじめ、初出の賛美歌‘Death And The Woman’(原曲は‘O Death’)や、
スペンスが亡くなった時の葬儀で演奏されたという
賛美歌の‘Won't That Be A Happy Time?’ を聴くことができます。
卓抜したギター・テクニックはここでも十二分に発揮されていて、
スキャットやハミングを交えたヴォーカルは、自由奔放そのもの。
よくスペンスの歌のことを、「のんびりした」とか「脱力」とかいう人がいますけれど、
ぼくから言わせれば的外れで、スペンスのスゴさがわかってない形容ですね。
スペンスがギター・プレイとハミングをフィードバックしながら、
物凄いインプロヴィゼーションを繰り広げているのが、聴き取れていないからでしょう。
耳のある人なら、‘Brown Skin Gal’ のハミングとギターのコール・アンド・レスポンスに、
スペンスの並外れた即興能力を悟るはずです。
フォーク・リヴァイヴァルの黎明期に評価を高めたミシシッピ・ジョン・ハートや
レヴェレンド・ゲイリー・デイヴィスと同列に扱われがちなギタリストでしたけれど、
ぼくにはそうしたブルース・ギタリストとは、性格が違うように思えてならないんですよね。
教会音楽由来の和声感覚をフィンガーピッキング・ギターに取り入れ、
独自の即興スタイルを生み出した才人であったことを、
この未発表録音集は示しているんじゃないでしょうか。
Joseph Spence "ENCORE" Smithonian Folkways SFW40242
2021-08-16 00:00
コメント(0)
ジュジュが沸点を迎えた81年 エベネザー・オベイ [西アフリカ]
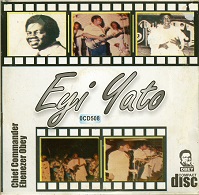
いぇ~い! ついにオベイの81年作“EYI YATO” のCD見っけ!
キング・サニー・アデとともにジュジュの一時代を築いたエベネザー・オベイのレコードで、
ゆいいつCDが手に入らなかったんですよ。
オベイのレコードは、ナイジェリア現地ですべてCD化されていることがわかっているのに、
なぜかこの1枚だけ、長いこと見つからなかったんですよねえ。
これでぼくの持っていたオベイのレコードは、すべてCDで完揃い達成!
81年のオベイでは、“AMBITION” とともに愛聴したアルバムです。
(遠藤斗志也さんのディスコグラフィに「1980」とありますが、正しくは81年です)
ワウをかけたファンキーなリズム・カッティングに、
エイト・ビートの割り切ったドラムスのビートが
アフロ・ソウルのニュアンスを打ち出しつつ、
そこにトーキング・ドラムが有機的に絡んで、ジュジュ特有のグルーヴを生み出します。
オベイのジュジュに、ロックのセンスが持ち込まれたレコードでもありましたね。
ジュジュ三羽烏と呼ばれたエベネザー・オベイ、サニー・アデ、デレ・アビオドゥンの
81年を振り返ってみると、アデは名盤3部作として名高い“THE MESSAGE”
“CHECK E” “ARIYA SPECIAL” を、デレはロック色濃い一大傑作
“THE BEGINNING OF THE NEW ERA” を出した年なんですよね。
いやぁ、あらためて、1981年はジュジュ黄金時代のスゴい年だったんですねえ。
三人三様の個性で、シャープでカッコいいアデに、ドスコイ相撲するロックなデレに対し、
オベイののどかでユルさのあるジュジュは、
どこかのほほんとしていて、庶民的な親しみやすさは一番でしょう。
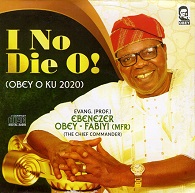
今回はオマケで、久しぶりとなる新作も同時に入手しました。
『70歳記念』アルバム以来のスタジオ録音かな?
オベイがゴスペルに転向して以降のアルバムは、正直あまり熱心に聴いていませんが、
出来は思ったほど悪くなかったです。
ただ、曲に起伏がなく、アレンジも平板。一本調子なのが、ちょっと退屈かな。
ジュジュが沸点を迎えた81年の“EYI YATO” とは、比べるまでもありませんでした。
Chief Commander Ebenezer Obey & His Inter-Reformers Band "EYI YATO" Obey OCD508 (1981)
Evang. (Prof.) Ebenezer Obey-Fabiyi "I NO DIE O! (OBEY O KU 2020)" Obey no number (2020)
2021-08-14 00:00
コメント(0)
タラヴァの現場から トラボイン・メハイ [東ヨーロッパ]

前回に続き、コソヴォのタラヴァです。
こちらはメダよりだいぶ若い歌手で、トラボイン・メハイと読むのでしょうか。
ネット検索しても、あまり情報がなく、本作がデビュー作なのかもしれません。
全9曲、どれもメロディがオリエンタル色濃厚で、タラヴァらしさ満点。
う~ん、いいねぇ。リスナーをグイグイとダンスに誘いますよ。
9曲ともすべてメドレーで繋いで、ノン・ストップ形式でラストまで突っ走るのは、
エドナ・ラロシの『ライヴ』と同じスタイルですね。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-04-18
本作は、ライヴとタイトルに謳ってはいませんが、
タラヴァお約束のダンス・オリエンテッドなアルバムであります。
曲間をつなぐシンセの即興パートに、すごく惹きつけられるんです。
ズルナやドゥドゥクのような管楽器を模していたり、
チフテリのような弦楽器を模していたりして、
バルカンらしいサウンドを発揮しているんですけれど、シンセの合成音であることは明らか。
それなのに、生楽器のようなナマナマしい響きがあるから、
シンセ代用とはいえ、すごく魅力的に聞こえるんですよ。
この人のライヴを撮ったYouTubeのアマチュア映像で、面白いのを見つけました。
体育館のような会場で、ステージ上はトラボインただ一人。
鍵盤二台を前に、シーケンサーの自動演奏によって、マイク片手に歌っていて、
曲間のつなぎをトラボイン自身が手弾きで演奏しています。
うわー、こういう超簡素なスタイルが、タラヴァの現場なのね。
面白いのは、観客がほとんど女性で、手を繋いでチェーン・ダンスをしているんですよ。
しかも、全員ステージに背を向けて踊っていて、
誰もステージ上のトラボインに、目をくれもしないという(笑)。
要するにタラヴァの現場は、徹底してダンス目的で、
歌手目当てのコンサートなんかじゃないんですね。
シーケンサー主体の人件費抑制のライヴというと、
エチオピアのレストランでもよく見られる光景といえますけれど、
そのサウンドがけっしてチープに感じず楽しめるのが、タラヴァの強みですね。
Traboin Mehaj "KËNGË DASMASH" Eurolindi no number (2019)
2021-08-12 00:00
コメント(0)
キング・オヴ・タラヴァ メダ [東ヨーロッパ]



エドナ・ラロシにテウタ・セリミの二人の女性歌手をきっかけに、
コソヴォにタラヴァというポップスがあることを知りました。
歌手の層が厚く、ミュージック・ヴィデオもかなり作られていて、
つまみ食いしただけでも、面白い人にゴロゴロ当たるんですよ。
タラヴァのCDを売っているアルバニアのお店を見つけたので、
気になった歌手のCDをオーダーしてみたんですが、
わずか1週間足らずで届きました。
アルバニアからの荷は、これが初めてですね。
う~ん、また世界がひとつ開けたみたいで、嬉しいな。
サブスクでちゃちゃっと聴いてしまえば、そりゃ簡単だけど、
こういう手間ヒマかけるのが、楽しいんですよ。
オーダーして届くまでの、心待ちしている時間が、いいんだなあ。
待っている間に、またいろいろ調べられるしね。
こういうプロセスを経てこそ、道楽は深まるんだから、
効率なんて考えちゃダメだよね。
それに、簡単に聴いたものは、簡単に忘れちゃうだけだし。
で、ヴィデオを観ていて、歌の上手さに引き込まれたのが、メダという男性歌手。
79年プリシュティナの音楽一家に生まれ、
00年からプロ歌手として活動を始め、04年にデビュー作を出したメダは、
「タラヴァの王様」とも称されている歌手だそう。
タラヴァを代表するシンガーというわけで、
こちらのアンテナにもすぐ引っかかるわけですね。
在庫のあった10年、18年、20年の3作を買ってみたんですが、
どのアルバムも歌に安定感があり、安心して身を任せられます。
ハリのある声と、ノドを詰めた歌いっぷりに魅力のある人ですね。
10年作は、シンプルな打ち込みのトラックに、ズルナ、クラリネット、
ダルブッカ、ダフなどの生音がよく映え、サウンドがとてもすがすがしいんです。
90年代のアラベスクにも通じるこういうプロダクションは、もろ好みだなあ。
これが18年作になると、鍵盤系のサウンドがぐんとグレード・アップして、
ボトムに厚みが増すかわり、ズルナなどの生音がシンセに置き代わってしまい、
ダルブッカなどのパーカッションも不在になってしまうのは、残念です。
ラッパーをフィーチャーして、ヒップ・ホップ・ビートを強調した曲や、
レゲトンを取り入れた曲もあり、かなりワールド・ミュージックぽいというか、
グローバルなポップ・サウンドにシフトしているのを感じます。
おやと思わせるのは、生音のサズが聞こえるラスト・トラックかな。
これが20年作になると、生音のサズやストリングスなどが使われていて、
生音回帰の傾向がみられます。すべて打ち込みに頼るのではなく、
生演奏とのバランスを考えて制作されているのは、好感が持てますね。
管楽器や弦楽器によるオリエンタルなメロディがタラヴァの魅力なので、
やっぱりこうした楽器のソロやオブリガードは、必須だよなあ。
ウィキペディアのディスコグラフィによると、
今回買った10年作は7作目、18年作は20作目、20年作は39作目。
04年のデビュー作以降、年1作のペースだったのが、
18年から多作となり、18年は9作、19年は7作、20年は13作も出しています。
なかにはベスト盤のようなアルバムも混じっているのかもしれませんけれど、
それにしてもこのハイ・ペースはスゴイですね。
Meda "MOS GABO!" EmraCom/Lyra no number (2010)
Meda "NJO PO NJO" Emra Music/Lyra no number (2018)
Meda "NA NA" Emra Music/Lyra no number (2020)
2021-08-10 00:00
コメント(0)
門外漢向けブレイクビーツ名作 ジョン・ハッセル [北アメリカ]
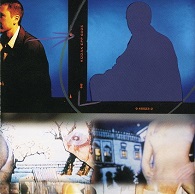
ジョン・ハッセルの音楽は、凋落する西洋文明の断末魔と捉えていた(いる)ので、
テリー・ライリー同様、自分とは縁がない音楽家と思っていただけに、
ブルースクリーンと組んだ94年の“DRESSING FOR PLEASURE” を聴いたときは、
ひっくり返らんばかりにオドロいたものでした。
えぇ~? このゴキゲンなブレイクビーツが、ジョン・ハッセルなのぉ??
そのジョン・ハッセルが亡くなったと聞き、急に思い出して、
CD棚から何十年ぶりかで引っ張り出してきたんですけれど、
う~ん、クールだよねえ、カッコよすぎ!
ジョン・ハッセルがこんなクラブ・ミュージックを作るなんて、予想もしなかったけれど、
ジョン・ハッセルのファンにしたら、これきっと駄作扱いなんだろうなあ。
スクラッチとサンプリング音に、ひしゃげたケニー・ギャレットのサックスが絡む、
アブストラクトな1曲目の‘G-Spot’ から、トリコになりました。
一転、2曲目の‘Villa Narco’ では、
ヒップ・ホップ・ビートでアッパーに迫るダンス・トラックで、もう最高やん!
サンプリングと生演奏のバランスが絶妙で、すごく緻密に作っているんですね。
ドラムスの音色だって、生音を生かしたトラックもあれば、
スネアにゲーテッド・リヴァーヴ(「ゲート・リヴァーブ」じゃない)をかけたのもあり、
ハッセルのトランペットやピアノも、生だったり、加工していたり、
要所要所に合わせてかなり作り込んでいます。
ワン・コードで反復を繰り返す曲が多いなか、
さまざまな楽器音にヴォイスやサンプリング音が変化をつけ、
サウンドスケープを動かしていくところが、もう絶妙。
不安定なビートやブレイクの多用など、リズムを切断したり、ノリを崩すような処理は、
トリップ・ホップに通じるだけでなく、今聴き直すと、
現代のジャズに繋がるものも感じさせますよね。
というわけで、思いがけずヘヴィ・ロテになっていたりするんですけれど、
もう1枚持っていた(なんで持ってんだ?)99年の“FASCINOMA” も聴き返してみたら、
こちらはハッセルの本領発揮盤で、一度聴いてまた棚に戻してしまいました。
タンブーラやバーンスリーが絡む‘Caravan’ とか、やっぱ鼻持ちならないなー。
ブルースクリーンとのコラボでも、エリントンのエキゾ・ナンバー‘Bakiff’ を
サンプリングしていますけどね。まあ、こちらはさりげなく引用したという感じで、
そんなにハナにはつかなかったので。
アンチ・ジョン・ハッセルの人間でもイケる異色作にして、ブレイクビーツの名作です。
Jon Hassell & Bluescreen "DRESSING FOR PLEASURE" Warner Bros. 945523-2 (1994)
2021-08-08 00:00
コメント(0)
祝! ブッダ盤CD化 ウィルバート・ハリソン [北アメリカ]

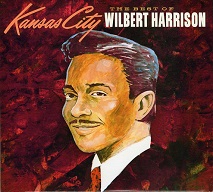
ウィルバート・ハリソンの71年ブッダ盤がCD化されていたのか!
いやぁ、これには気がつかなかったなあ。
ウィルバート・ハリソンのベスト盤3枚組の中に、さりげなく全曲収録されていたとは。
う~ん、これは、嬉しい。
リー・ドーシーの“YES WE CAN” にカンゲキして、
アラン・トゥーサンがアレンジしたレコードを
片っ端から探していた、高校生の時に出会ったアルバムです。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-09-01
“YES WE CAN” のような名盤とは比べようもない、B級盤ですけれど、
ニュー・オーリンズR&Bのいなたさが味わえる、忘れがたいアルバムです。
ブッダ盤を買った当時、ウィルバート・ハリソンが誰なのかも知らず、
のちになって「カンサス・シティ」の大ヒット曲を出したR&Bシンガーということを
知りましたけれど、今回のベスト盤3枚組を買うまで、
オリジナルの‘Kansas City’ を聴いたことがなかったというお粗末。
「カンサス・シティ」の大ヒットにまつわる契約問題が仇となって、
のちのちもヒットに恵まれず、不遇の歌手だったということは、
ハリソンの全キャリアを追ったこのベスト盤を聴いて、ようやくわかりました。
なんせこの3枚組、70曲中30曲が初CD化だというのだから、タイヘンです。
その意味で71年のブッダ盤は、ニュー・オーリンズ・ブームを巻き起こした
立役者のマーシャル・セホーンをプロデューサーに迎えて、
起死回生を狙ったアルバムだったんですね。
残念ながら、それは果たせはしませんでしたが。
リトル・ウォルターの‘My Babe’、ジミー・リードの‘Honest I Do’ といった
ブルース定番曲に、ファッツ・ドミノの‘Ain't That A Shame’ ‘Going To The River’、
そしてニュー・オーリンズを代表する
‘When The Saints Go Marching In’ というレパートリーは、
71年当時としても、ちょっと古臭かったんじゃないかと思います。
それでもねえ、ニュー・オーリンズならではの人懐っこいサウンドが、たまんないんだなあ。
リズムの塊と化した‘Girls On Parade’ のセカンド・ラインに、腰が揺れます。
クレジットはないけれど、“YES WE CAN” 同様、
ミーターズがバックを務めたと思われる演奏は、
この時代ならではのグルーヴに溢れていて、もうサイコーです。
ディスク3には、ブッダ盤をオリジナル盤の曲順どおり並べた後、
76年作の“SOUL FOOD MAN” がこれまた丸ごと収録されているんですね。
トゥーサンとセホーンの共同プロデュースで、こちらは初めて聴きましたが、
ちょっとこっちはユルいかなあ。ジミー・リードふうのハープはいいんだけど、
ホーン・セクションは不在だし、バックもミーターズではなさそう。
というわけで、個人的には、ブッダ盤CD化バンザイな3枚組ベストでした。
[LP] Wilbert Harrison "WILBERT HARRISON" Buddah BDS5092 (1971)
Wilbert Harrison "KANSAS CITY: THE BEST OF WILBERT HARRISON" Sunset Blvd CDSBR7991
2021-08-06 00:00
コメント(0)
ディスク1枚分の未発表音源リイシュー ドゥドゥ・プクワナ [南部アフリカ]
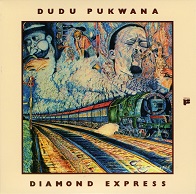
南ア・ジャズのサックス奏者ドゥドゥ・プクワナの77年作が、2度目のCD化。
これまでに、オリジナルのままCD化したのは日本だけですけれど、
今回はディスク1枚分の未発表音源を付けてリイシューしたんだから、
これは大事件です。
ボーナス・トラックならぬボーナス・ディスク付きという今回の2枚組CD化、
40年以上このレコードを聴き倒してきた人間には感涙ものなんですが、
いったいどこに眠っていた音源なんでしょうね。
片岡文明さんの解説を読むと、配信のみで流通していた音源とのこと。
え~、ぜんぜん知らなかった~と、慌ててチェックしたところ、
12年にブラック・ライオン・ヴォルト・リマスタード・シリーズの1枚として、
デジタル・リリースされていたようです。
それを今回、日本で初ディスク化したというわけか。これは快挙です!
77年に出た“DIAMOND EXPRESS” は、二つのセッションからなっていて、
B面2曲目の‘Tete And Barbs In My Mind’ だけが、
ドゥドゥのアルトとモンゲジ・フェザのトランペットに、
サクセロとトロンボーンを加えて4管とした、8人編成のセッションだったんですが、
どうやらこちらのセッションのアウトテイクが、残されていたようです。
デジタル・リリースされたアウトテイク集に収録された‘Blue Nick’ は、
‘Tete And Barbs In My Mind’ からタイトルを変えた、フル・ヴァージョン。
‘Tete And Barbs In My Mind’ はエンディングをフェイド・アウトしていましたが、
‘Blue Nick’ はノー・カット・ヴァージョンになっています。
ロック色が強く出た“DIAMOND EXPRESS” のなかで、このトラックだけが、
ブラザーフッド・オヴ・ブレスを想わす異色なフリー・ジャズ演奏だっただけに、
エンディングの強烈なドゥドゥの吹奏をカットして、フリー色を薄めたかったのかも。
ちなみに、アウトテイク集含め、全曲ドゥドゥ・プクワナの作曲なのですが、
この‘Tete And Barbs In My Mind’ = ‘Blue Nick’ だけは、
ピアニストのテテ・ンバンビサとの共作となっていて、
テテとドゥドゥ夫人のバーバラ・プクワナに捧げられています。
60年代初めに、テテがリーダーを務めていたヴォーカル・グループ、
フォー・ヤンクスに参加したのが、ドゥドゥのプロ入り初の仕事だったのでした。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-05-19
アウトテイク集では、ドゥドゥがソプラノ・サックスも吹いているのが、聴きどころ。
このレコーディングのあとに急死してしまうモンケジ・フェザのトランペットも、
随所で目の覚めるようなプレイを聞かせています。
ブリティッシュ・ジャズの名手キース・ティペットの転がりまくるピアノは、
痛快そのものですね。
ビバップをフリー解釈した‘Blessing Light’ なんて、すごく面白い。
ソウル・ジャズの‘Black Horse’ では、ペニーホイッスルをドゥドゥが吹きまくっています。
あー、こんな素晴らしい録音が残されていたなんて、もう涙が止まりませ~ん。
最後に、一つだけ不満も。
紙ジャケットはオリジナル盤を表裏とも忠実に再現しながら、
なぜ地の色だけ、ホワイトからペール・オレンジに変えたの?
こういう意味不なデザイン変更が残念でなりません。
ドゥドゥ・プクワナ 「ダイアモンド・エクスプレス+6⃣~コンプリート・フリーダム・レコーディングス」 ミューザック MZCB1441 (1977)
2021-08-04 00:00
コメント(0)
モーリタニアン・サイケデリック・ギターの饗宴 [西アフリカ]
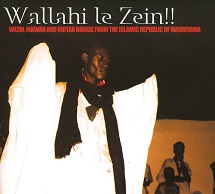
17年の夏に来日したヌーラ・ミント・セイマリを取材したとき、
ドラマーでプロデューサーのマシュー・ティナリから連絡先を渡され、
少しばかりメールをやり取りしたことがありました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2017-10-20
そのなかで、ヌーラの夫のギタリスト、ジェイシュ・ウルド・シガリのギターが聞ける
現地録音のCDがあることを、ティナリから教えてもらったんですね。
それがこのシカゴの無名レーベルから出た、“WALLAHI LE ZEIN!!” なのでした。
この2枚組CDは、
アメリカ人ジャーナリストのマシュー・ラヴォワがモーリタニアで集めた、
約700本のプライヴェート・カセットをもとに編集した、たいへんな労作。
モーリタニアン・ギター・ミュージックの獰猛なサウンドに、驚かない人はいないでしょう。
32ページのブックレットには、ムーア音楽の基礎知識から、
ヌアクショットの音楽の現状を詳述したラヴォワの解説が載せられていて、
一級品の資料といえるその内容の濃さにも、強烈な刺激を受けました。
サブライム・フリークエンシーズの作品に足りないものが、すべてここにはありますね。
これほどの名編集盤が、なぜ世に知られていないのか謎すぎるんですけど、
ティナリも「誰もこのCDを知らないんだ」と言っていたとおり、
ネットにもまるで情報がない(ひとつだけピッチフォークの記事を発見しました)、
激レア盤だったのでした。
ところが、つい最近、ミシシッピ・レコーズがこのCDを再発したんですね。
デジタル・リリースの28曲フル・ヴァージョンと、
11曲に短縮したLPヴァージョンが発売され、
今月号のミュージック・マガジンの輸入盤紹介にも載ったので、
あらためてこのCDの内容について、書いておこうという気になりました。
なお、ミシシッピから出たジャケットは変更されていますので、念のため。
ムーアのグリオが弾くギターは、ムーアの伝統楽器ティディニートを
ギターに置き換えて演奏していることは、すでによく知られていますね。
フレットを増やしたり抜いたりして、ティディニートのような微分音を出すための改造をし、
ディストーションやフェイザーをかけ、轟音ロック顔負けの強烈な磁場を生み出します。
これほど激烈なサウンドスケープは、
トゥアレグのアンプリファイド・テハルダントといい勝負で、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-06-02
コノノNo.1に熱狂した人なら、夢中になること必至でしょう。
モーリタニアには、音楽産業がないんですね。
大衆音楽が娯楽として提供されるナイトクラブのような場もなければ、
カセットやCDを制作販売する業者も存在せず、音楽は、結婚式や誕生日祝い、
政治集会など、招待された者だけに振舞われるものとして存在しています。
そうした冠婚葬祭の場で録音された個人所有のプライヴェート・カセットを、
ラヴォワは何度も現地に赴いては、買い集めてきたのでした。
当然ながらその録音はローファイの極みで、
西洋人によってレコーディングされた伝統音楽のアルバムとは、
天と地ほどの違いがあるのも仕方がありません。
思い立ったラヴォワは録音機材を運び込み、02年の年末から03年にかけ、
30以上のレコーディング・セッションを敢行したものの、
クリーンな音質のデジタル録音は、生気を欠いた退屈なものにしかならず、
プライヴェート・カセットの生々しい躍動感に、遠く及ばなかったといいます。
自身によるフィールド・レコーディングを諦めたラヴォワは、
プライヴェート・カセットのコレクションから、
このコンピレーションを制作することにしたのですね。
ディスク1の1~5曲目には、俗にホワイト・ムーアと呼ばれる
ハラティン(アラブとベルベルのミックス)のギター・ミュージックが収録されています。
これまでディスク化されてきたムーア音楽は、
ほとんどがベイダン(アラブと黒人のミックス、俗にブラック・ムーア)の音楽のため、
ハラティンの音楽が聞けるのは貴重です。
ハラティンの社会には、ベイダンのようなイガウィン(グリオ)の階層がなく、
誰でも自由に音楽を演奏することができます。
ハラティンのギター・ミュージックは、ジャクワールと呼ばれてきましたが、
76年にベイダンのティディニートの名手ジェイシュ・ウルド・アッバが作曲した、
テンポの速いダンス・メロディがジャクワールと名付けられて流行したことから、
両者が紛らわしくなったために、ハラティンのギタリストのケブルは、
バンジーと呼び変えています。
そして、ディスク1の残りとディスク2は、ベイダンのギター・ミュージックで、
本作のタイトルとなった‘Wallahi Le Zein!’(「神に誓って、これはすばらしい!)という
熱狂する叫び声が、アテグ・ウルド・セイドの‘L'Ensijab’の2分30秒に収められています。
ババ・ウルド・ヘンバラのギターなんて、
エレクトリック・ティディニート以上にティディニートらしくて、
本来ティディニートは、こういうふうに鳴らす楽器なんじゃないかと思えるほど。
改造ギターのイノヴェイターであり、フェイザーを初めて使うなど、
革命的なギター・サウンドをクリエイトして多くのギタリストたちに影響を与えてきた
ルレイデ・ウルド・デンデンニのプレイもしっかり収録されています。
ここに収録されたギターが、どんなにサイケデリックな音響に聞こえようと、
ギターの奏法も、演奏される旋法も、ムーア音楽の伝統に忠実に沿っているんですね。
エレクトリック・ギターによって、ムーア音楽が逞しく更新されている姿を
鮮やかにドキュメントしてみせた、名コンピレです。
v.a. "WALLAHI LE ZEIN!! - Wezin, Jakwar And Guitar Boogie From The Islamic Republic Of Mauritania"
Latitude 07 (2010)
2021-08-02 00:00
コメント(0)




