セリア・クルースのアフリカン・ポップ・カヴァー アンジェリク・キジョ [西アフリカ]

アンジェリク・キジョの『リメイン・イン・ライト』には、本当に驚かされました。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-10-13
アンチ『リメイン・イン・ライト』のぼくにとっては、「瓢箪から駒」以上の、
「ウソから出たマコト」クラスの衝撃でしたよ。
あの偽アフロ音楽を、ホンモノのアフリカ音楽が奪還してみせた痛快さといったら。
まさしく、アフリカがロックを取り返した象徴的作品でした。
キジョの作品を、まさか自分の年間ベストに選ぶことになるとは
想像だにしませんでしたけど、なんのためらいもありませんでしたからね。
その『リメイン・イン・ライト』に続き、今度のテーマはセリア・クルースとは、
なーるほど、これまたいいところに目を付けたもんだ。
セリア・クルースが歌ったサンテリーアの曲なら、
ベニン生まれの彼女に格好の選曲となるし、
セリア・クルースのような強い声をカヴァーできるシンガーといったら、
たしかにアンジェリク・キジョぐらいしか、見当たりませんよねえ。
かつてのディアスポラ3部作にせよ、『リメイン・イン・ライト』にせよ、
キジョはよくよく鼻が利くというか、企画先行の作家タイプですねえ。
音楽家としてよりも、そういう政治性を感じさせる立ち回りが、
あいかわらず油断ならんという気分にさせられるんですが、
題材がセリア・クルースとあっては、ますます警戒心が高まります。
なんたってセリア・クルースは、ぼくにとって音楽の女神さまですからね。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-07-15
でも、こうして記事を書いていることからもおわかりのとおり、面白い作品となっています。
批判するくらいなら、ガン無視するのが、このブログの基本ですので、はい。
キジョなら、セリア・クルースに歌の強度で迫ることができるだろうことは認めつつも、
しなやかさがまるでないキジョのヴォーカルが、
あのバツグンの跳躍力を持つセリアの歌声に、どれほどまで迫れるのかが、
聴く前の関心事でした。
これが案外、面白い聴きものとなっているんですね。
キジョのヴォーカルはやっぱり硬いし、
セリアのダイナミクスとは比べようもありません。
それでも、十分健闘していると好感を持てるのは、
バックの演奏との有機的な絡み合いにありました。
前回の『リメイン・イン・ライト』では2曲のみの起用だったトニー・アレンが、
今回は全面参加。近年のスウィング感たっぷりのジャズ・マナーなドラミングが、
セリアのヴォーカルが持つ柔軟性をサウンド面から作り上げているんですね。
ゆるやかなアフロビートとコンゴリーズ・ルンバをミックスした、
ふくよかなグルーヴに揺れるオープニングの‘Cucala’ から、存分に発揮されています。
トニー・アレンのドラミングって、
先日の来日公演でもあらためて思いましたけれど、すごく古臭い。
フィル・インの使い方やシンバル・レガート、スティックの持ち方だって、
ファンキー・ジャズ時代のアート・ブレイキーみたいな古いスタイルなのに、
テクノと共演しても親和性のある柔軟さがスゴいというか、アレン・マジックといえます。
トニー・アレンと並んで光るのが、トーゴ人ギタリストのアメン・ヴィアナ。
キング・メンサーの来日公演でそのユニークなスタイルに感心しましたが、
ここでも冴えたギター・ワークを聞かせています。
キジョとバック・コーラスをしたりと、今作でのアメンの貢献度は大ですね。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-05-27
そして、ベニンのガンベ・ブラス・バンドも活躍していますけれど、
UKジャズ話題のシャバカ・ハッチングスとサンズ・オヴ・ケメットが参加していて、
シャバカの切れたサックス・ソロが聴きものとなっています。
ほかに、ミシェル・ンデゲオチェロがベースを弾いているのにも、
話題が集まりそうですけれど、目立ったプレイは特になし。
手数の多いアレンとのドラミングと彼女とでは、ちょっと持ち味が違ったかも。
いずれにせよ、キューバン・サウンドを範とせず、
ユニークなアフリカン・サウンドでセリア・クルースの名曲をカヴァーしつつ、
歌そのものはメロディもいっさいいじらずに歌った本作、ぼくは面白く聴きました。
こうして聴いてみると、案外キジョの歌の強度はそれほどでもないというか、
かえってセリア・クルースの歌の、とてつもない強度を再認識させられましたね。
屈伸から大きくジャンプするバレーボール選手の身体の動きを見るかのようで、
そのダイナミクスの大きさとともに、その圧倒的なバネの強さにも、
あらためてセリア・クルースのスゴ味を思い知らされる、キジョの新作でした。
Angelique Kidjo "CELIA" Verve 7744498 (2019)
2019-04-29 00:00
コメント(0)
知られざるチャドに赴いて プロ・NDJ [中部アフリカ]
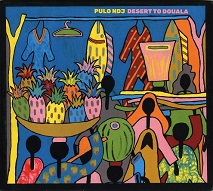
ワンダーウィールを主宰するニコデマスの新プロジェクトが面白い。
チャドの首都ンジャメナに赴いたニコデマスが、チャドの音楽家ばかりか、
カメルーン、トーゴ、コンゴ民主共和国の才能ある音楽家たちと出会い、
ンジャメナが想像以上の文化のるつぼであることに驚いたんだそう。
なんでそもそもチャドなんだ?と思うわけですが、
アフリカで音楽シーンの様子がもっとも伝わってこない国ということで、
プロデューサー一流の勘みたいなものが働いたんでしょうかね。
ンジャメナが多様な文化の交差点となっていることに触発されて、
ニコデマスはプロ・NDJなるプロジェクトを組んで、
現地でレコーディングしたのが本作です。
タイトルの『砂漠からドゥアラへ』からは、
チャド北部のサハラ砂漠から、カメルーンの港湾都市ドゥアラへと至る、
砂漠~サヴァンナ~森林地帯をまたいだ文化の多様性を表す意図が感じられます。
プロジェクト名の「プロ」とはフルフルデ語の「プール」、すなわちフルベ人を表わす語、
NDJ はンジャメナの略でしょう。
フルベの素朴な2弦の弦楽器ガラヤの弾き語りのミニマルな歌に、
エレクトロニクスを控えめに絡ませた‘Cera Cera’ から、アルバムはスタート。
羊飼いであるフルベのワーク・ソング、チャド南部の儀礼音楽、
カメルーンの結婚式の歌などのフォークロアを題材に、
ガラヤ、バラフォン、女声のウルレーションといった
アフリカの響きを全面に押し出しながら、
伝統リズムのグルーヴをエレクトロで強化したサウンドを作り上げています。
カン高い声で歌う女性コーラスの伝統唱法の歌に、
ベース・ミュージックのサウンドを絡ませる試みも、とてもしっくりしていて、
長年ワールド・ビートを扱ってきたニコデマスのDJスキルの賜物といえそうです。
フランス語ラップのスキルも高く、
現地ミュージシャンたちの伝統とモダンのバランスの良さが、
ニコデマスが持ち込んだテクノロジーと親和性高く、
両者のコラボレーションを成功させています。
Pulo NDJ "DESERT TO DOUALA" Wonderwheel Recordings WONDERCD37 (2018)
2019-04-27 00:00
コメント(0)
日本のロック史上最高のソウル・バンド 上田正樹とサウス・トゥ・サウス [日本]

キー坊ーーーーーーーーっ!!!
40年以上も昔の、女ともだちの黄色い声が耳元でものすごくリアルに蘇り、
全身の毛が逆立つような感覚に襲われました。
「懐かしい」なんて、ナマっちょろいもんじゃない。幻聴ってやつですね。
あれは確か、A・H嬢の絶叫。ずっと忘れていた彼女の名前まで突然思い出しちゃって、
人間の記憶の回路って、不思議だなあ。
聴いていたのは、74年8月、福島県郡山のワンステップ・フェスティバルでの
上田正樹とサウス・トゥ・サウスのライヴ録音。
2年前にワンステップ・フェスティバルのライヴ音源が、
CD21枚組という超弩級のボックスで世に出ましたけれど、
まさかそのボックスを買うこともできず、
「あー、上田正樹とサウス・トゥ・サウスだけは聴きたいなあ」と願っていただけに、
バラ売りされたと知り、狂喜乱舞して買ってきたのでした。
高校2年のことです。ぼくの高校は男子校でしたけれど、
同じ学校の女子部があり、よくツルんで遊んでたグループがありました。
その中に、上田正樹とサウス・トゥ・サウスの熱狂的なファン(A・H嬢)がいましてね。
その子に引きずられるように、ぼくらの仲間もライヴへ通うようになり、
全員サウス・トゥ・サウスのファンになったんでした。
当時サウス・トゥ・サウスはまだレコード・デビュー前で、
その年の6月に、上田と有山淳司とのコンビの『ぼちぼちいこか』が出たんだったな。
サウス・トゥ・サウスのライヴは2部構成になっていて、
第1部が有山のラグタイム・ギターとのアクースティック・セット、
第2部がサウス・トゥ・サウスのソウル・ショーで、その2部のライヴが、
その半年後の暮れに『この熱い魂を伝えたいんや』として出たのでした。
ジャケット・デザインが、「ロンパールーム」(当時の幼児番組)みたいで、
ぼくらの間では超不評でしたけれど、LPリリース後のNHKテレビの公開録画の時、
メンバー全員にサインを入れてもらったことを覚えています。


あの公開録画もケッサクだったな。
いつものグループで押しかけたんだけど、
ぼくらが踊ろうと立ち上がると、NHKの職員に制止されるんですよ。
サウス・トゥ・サウスのライヴを、大人しく座って観てろって、アホか。
さらにアタマにきたのが、NHKはわざわざ雇ったお姉さま二人だけを踊らせて、
カメラに映すというフザけた演出をしていたことで、A・H嬢が怒りまくったっけ。
想い出は尽きないわけですけれど、当時の日本のロック・シーンで、
上田正樹のパフォーマンスは、本当にずば抜けていたんですよ。
「おおきにっ!」という関西弁が、どれだけ観客の心を熱くしたことか。
関東のバンドは、トークが不器用というか、ヘタくそで、
エエカッコしいの誤解を招いたものですけれど、
関西弁の生活感溢れるトークは、ストレートに観客のハートをつかんだんですね。
オーティス・レディング、ルーファス・トーマス、
レイ・チャールズのナンバーを借り物でなく、
あれほど咀嚼して歌えた日本人は、上田正樹ただ一人でした。
歳月を経て、いまや本格的なR&Bシンガーが大勢輩出するようになったとはいえ、
あの時のサウス・トゥ・サウスが持っていた熱量を凌ぐライヴ・バンドは、
いまだ現れてないように感じるのは、
過去の想い出を美化した、自分の思い込みのせいですかね。
そんなことも確かめてみたくて、今回ワンステップ・フェスティバルのライヴを
やや緊張して聴き始めたんですが、有山とのアクースティック・セットで始まる、
冒頭のキー坊のしゃがれ声に、いきなり胸アツになっちゃいました。
そこにあるのは、自分が惚れ込んだソウル・ミュージックに身を投じ、
全身全霊で立ち向かっている若者たちの姿でした。
そんな真摯で、純粋な思いが、ビンビンと伝わってくる生々しいパフォーマンスは、
技術や演出が格段にグレード・アップした現代のR&Bでは生み出せない、
原初のエネルギーを感じさせます。
うん、やっぱり、これはホンモノだわ。記憶の美化でも、思い込みでもなかったね。
第1部は、NGワードもピー音なしでそのまんま収録した「タバコが苦い」から、
ブラインド・ブレイクの‘Police Dog Blues’のイントロを拝借した
「負けると知りつつバクチをしたよ」まで、
有山淳司のラグタイム・ギターがスウィングしまくります。
ゆうちゃん(藤井裕)のグルーヴィなベースでスタートする第2部は、
ホーン・セクションも従えファンキーに迫り、
「Soul to soul! そうちゃうか!」「後ろ! 元気ないやんけ」
「よっしゃあ、死ぬまで言うたろ」と観客を煽るキー坊も、最高潮。
このむせかえるような熱さに、グッとこないヤツはいないでしょう。
この当時のサウス・トゥ・サウスは、
ドラムスの正木五郎とキーボードの中西康晴がまだ参加する前で、
ジャズも叩ける上場正俊と、スタジオで活躍していた
実力あるキーボーディストの宮内良和、
関西ロック・シーンで名をはせたギタリストの萩原義郎を擁していました。
この郡山のわずか1週間前には8.8.ロック・デイに出演し、
そのライヴ盤に6曲を残しているので、既聴感はあったとはいえ、
ここでは倍の13曲、これこそサウス・トゥ・サウスのライヴですよ。
‘Licking Stick’‘Funky Broadway’ でギタリストのくんちょう(堤和美)が歌う
シブいヴォーカルもまた、サウス・トゥ・サウスの魅力。
サポートで加わった石田長生のジャジーなギター・ソロに導かれて
キー坊が歌い出す‘Try A Little Tenderness’ も、
オーティスに少しでも近づこうとする、その気合の入りぶりに、
胸を打たれずにはいられません。
上田正樹とサウス・トゥ・サウス 「1974ワンステップ・フェスティバル」 スーパーフジ/ディスクユニオン FJSP371
[LP] 上田正樹と有山淳司 「ぼちぼちいこか」 バーボン BMC3003 (1975)
[LP] 上田正樹とSouth to South 「この熱い魂を伝えたいんや」 バーボン BMC7001 (1975)
2019-04-25 00:00
コメント(3)
アダルト・オリエンテッド・シャバービー アンガーム [中東・マグレブ]

ああ、ようやっと手に入りました。
エジプト最高のフィメール・シンガー、アンガームの新作。
15年の復帰作から3年ぶりとなった昨年の前作“RAH TETHKERNI” は、
リシャール・ボナ、ヴィクター・ウッテン、ルイス・コンテなどが参加した
アメリカ録音を含むアルバムで、新たにハリージにも挑戦した意欲作となっていました。
ところが、これが入手できなくってねえ。
なんとか手に入れようと、四方八方手を尽くしたんだけど、とうとう実らず。
ロターナがフィジカル生産に後ろ向きなのは承知しているものの、
アラブ世界のトップ・スターの新作すら、まともに流通しないんだから、ヒドいもんです。
きっと関係者に見本盤を配るわずかな数くらいしか、いまやCDは作ってないんだろうなあ。
結果、ロターナのCDは、アラブのお金持ちのマニアにしか行き渡らず、
一般庶民はダウンロードかストリーミングで聞けってか。しくしく。
19年の新作もまたダメかなあと思っていたので、
レバノンのお店から、「あるよ。」のメールをもらった時は、小躍りしてしまいました。
アルバムのっけから、アンガーム節が炸裂。
アンガームの十八番、ほろほろと泣き崩れるようなメリスマが冴えわたります。
エジプト・トップ・クラスの歌唱力をこれでもかと見せつけるかのように、
ヴォーカルを伴奏からくっきりと浮かび上がらせたミックス・バランスが絶妙です。
若い頃は、その高すぎる歌唱力が
かえって情感を損なうマイナス面もあったアンガームですけれど、
いまやその熟したメリスマが、
切ないオンナ心を十二分に伝える最強の武器となっていますね。
新作はハリージなどの新趣向はなく、
カーヌーン、ヴァイオリン、ダルブッカが舞う王道のアラブ歌謡から、
ルンバ・フラメンカ調など、ヴァラエティに富んだポップなシャバービー路線。
ダンス・トラックを排し、じっくりと歌を聞かせる
アダルト・オリエンテッドなシャバービーに仕上がっています。
かつてのクラウス・オガーマンを思わすストリングス・オーケストレーションにも、
うっとりさせられますよ。
今作のプロデューサーは、
アンガームと結婚したばかりの新しい夫、アフメド・イブラヒム。
アラビア文字だらけのライナーの中で、数少ないアルファベットで
「スペシャル・サンクス」「ミュージック・プロデューサー」
「アフメド・イブラヒム」と大書きされた文字が、ひときわ目立ちます。
以前、結婚した途端に浮気が発覚した2番目の夫とも結局離婚して、
今度が3度目の結婚になったわけですけれど、はや暗雲が立ち込めているようですねえ。
アンガームの新しい夫アフメド・イブラヒムが、
既婚者で子持ちであったことを公表せずに、二人の結婚が発表されたことに、
エジプトのメディアは非難を集中。しかもアフメドの前妻が、
アンガームと親しいシリアのトップ歌手アサラの夫の姪だったことが発覚し、
二人の友情にヒビが入ることも懸念されている模様です。
さらに、アンガームがアーメッドに送った
バースデイ・レターの写真がネットに晒されたりと、
相変わらずスキャンダルに事欠かないアンガームなのでありました。
Angham "HALA KHASA GEDEN" Rotana CDROT2028 (2019)
2019-04-23 00:00
コメント(4)
60年代のトゥンテー・テインタン [東南アジア]
.jpg)
.jpg)
少しずつですけれど、ビルマ大衆歌謡の黄金時代の録音が
CD復刻されるようになってきたようで、積年の渇きがいやされる思いがします。
その皮切りが、一昨年のコー・アンジーの3枚でしたけれど、
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-09-20
今度は90年代まで息長く活躍したヴェテラン歌手トゥンテー・テインタン。
芸名のとおりトゥンテー出身の歌手で、41年生まれ、63年デビュー。
歌手のほか役者としても人気を博し、大衆から愛された歌手です。
今回手に入れたのは、『ベスト集第3集』。
実は、すでに『ベスト集第1集』を持っていたんですが、
冒頭1~4曲目に、シンセサイザーやドラムスも入る、
晩年の90年代とおぼしき録音が収録されていて、
後半5~11曲目が60年代録音という、妙な編集になっていたんですね。
この第3集は、1~8曲目までが60年代録音で、
9~11曲目からシンセ入りの80年代録音。
う~ん、同時期の録音でまとめてくれた方が聴きやすいんですけれどねえ。
未入手の第2集も新旧入り乱れているのかな。
『ベスト集』の表紙は、後年のトゥンテー・テインタンの写真があしらわれていますが、
ビルマ女性の憧れの的だったという、若き日のイケメンなポートレイトをあしらった
CD“TEA YE THEIN TAN ALWAN PYAY” も出ています。
ただし、内容はエレクトリック化した80年代以降の録音なので、ご注意のほど。
なんでこういう紛らわしいことするのかなあ。
さて、その注目の60年代録音ですけれど、
ピアノ(サンダヤー)、ヴァイオリン、トランペット、サックスなどの管楽器に、
ミャンマー伝統の響きを添えるチャルメラ(フネー)、太鼓、シンバル(リン・グイン)が
混然一体となって、ミャンマー独特の旋律を奏でます。
ミュート・トランペットのひなびた音色もまた、味わい深く聞こえます。
この時代のビルマ歌謡ほど、東洋と西洋が濃厚にミクスチャーされた音楽も
なかなかないんじゃないでしょうか。
のちのミャンマータンズィンでは、サイン・ワインも加わり、
西洋スタイルのバンド・スタイルの演奏とスイッチしながら曲が進行する、
摩訶不思議な音楽へと発展していきますが、
この時代はサイン・ワインを使わずとも、
ピアノやヴァイオリンが濃厚なビルマ臭を漂わせる一方で、
サックスとトランペットのソリは西洋のビッグバンド・スタイルのアレンジで、
東洋と西洋がくんずほぐれつしています。
トゥンテー・テインタンの歌もハツラツとしていて、
こぶしを利かせながら、明るい表情でメリハリのある歌い回しを披露しています。
台詞が入る曲もあり、往時の映画挿入歌も収録されているようですよ。
Twante Thein Tan "SHWE GANDAWIN (3)" Man Thiri CDMTR21086
Twante Thein Tan "SHWE GANDAWIN (1)" Man Thiri CDMTR21087
2019-04-21 00:00
コメント(0)
マルチニークの過去と現在が交錯する伝統ポップ デデ・サン=プリ [カリブ海]
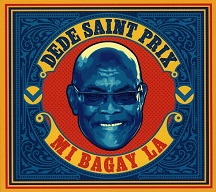
デデ・サン=プリの絶好調がとまらない。
新作はなんと2枚組。今ノリにのっている様子が、うかがえるようじゃないですか。
マルチニークの大衆芸能を受け継いで現代化する音楽家として、
もっとも理想的な仕事をしているのが、この人なんじゃないですかね。
前作も良い出来でしたけれど、ちょっとした不満もあったので、
ミュージック・マガジン誌の17年ラテン部門1位は、少し甘いかなと思いましたが、
今作は掛け値なしの最高傑作。ケチのつけようなど、これっぽっちもありません。
ディスク1の1曲目を、太鼓と笛のシュヴァル・ブワでスタートするように、
デデは自分の立脚点をはっきりと明示しながら、
どの曲においても伝統と現代をしっかりと往来させた音楽を生み出していますよ。
たとえば、麗しい女性コーラスを従えたズーク色の強いトラックでも、
タンブー(太鼓)やシャシャ(シェイカー)のリズムが強烈な自己主張をするし、
デデのエネルギッシュな歌が野趣に富んだ味わいを醸し出し、
洗練されたオシャレなズークとは、ほど遠い仕上がりとなるわけですね。
その一方、打楽器と笛のみで男声の囃子とコール&レスポンスする
アフロ・カリビアンの伝統色濃いトラック‘Racine’ では、
プログラミングを大胆に施すといった具合で、
伝統音楽の民俗性をムキ出しにすることもありません。
オーセンティック一辺倒でもなければ、モダンに偏るでもない、
伝統と現代のはざまで、さまざまなアイディアで料理した全32曲。
マルチニークの多様な伝統リズムにビギンやズーク、
サルサやメレンゲ、ハイチ音楽、アフリカ音楽までも取り入れています。
そこに忍ばされたアイディアを読み解く面白さは、
カリブ海音楽ファンなら、たまらないものですね。
それにしても、各曲それぞれ違った趣向で繰り広げていく構成は、圧巻です。
同じようなサウンドが連続することがないから、
2枚組という長さが苦になるどころか、あっという間に感じますよ。
次々に湧き出すアイディアをもとに、さまざまなセッションを繰り広げていったら、
この曲数になってしまったみたいなイキオイが伝わってきますね。
‘Fraternité’ ではコラとンゴニがフィーチャーされて、
西アフリカ風になるのかと思いきや、ルンバ・コンゴレーズとなって、のけぞり。
しかもリード・ヴォーカルを取るのが、コンゴ共和国出身のヴェテラン歌手、
バルー・カンタなのだから、びっくりです。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-06-23
カメルーン出身の異才ブリック・バッシーを迎えた
‘Nou Sanblé’ の愛らしさも聴きものなら、
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-09-27
グアドループ出身のフランスのラッパー、MCジャニックを迎えた‘LPK Janik’ では、
デデ自身がプログラミングしたダンスホール・トラックに仕上げるという芸当に降参です。
デデの引き出しの多さは、ヴェテランの蓄積の賜物ですね。
デデはトレードマークのバンブー・フルートのほか、
ほら貝(コンケ・ド・ランビ)も吹きますけれど、
今作では特にほら貝を効果的に使った曲が、強く印象に残りました。
フォークロアな‘Kongo’ はもちろんのこと、
‘Kilti’ での、ピアノ、ベース、トランペットがジャズ的なソロを取る脇で、
ほら貝が伝統的な旋律のリフレインを吹くという、
まさしく伝統と現代を拮抗させたアレンジが、すごく面白いんです。
今作に起用されたミュージシャンは、前作にも増して多彩で、実力者揃い。
特にピアニストの充実ぶりがすごくて、マルチニーク・オール・スターズですね。
前作で、キーボードをチープな音色で無神経に鳴らしていた
ロラン・ピエール=シャルルを起用しなかったのは大正解といえます。
主だったところをあげてみると、
アラン・ジャン=マリー、ティエリー・ヴァトン、
グレゴリー・プリヴァ、エルヴェ・セルカル(p)、
ジャン=フィリップ・ファンファン(ds)、ティエリー・ファンファン、
ミシェル・アリボ(b)、ジャン=フィリップ・マテリー(vo)といった面々。
これだけの才能を集めたからこそ、
デデの豊富なアイディアを具現化できたともいえる大傑作です。
Dédé Saint-Prix "MI BAGAY LA" Anbalari Edisyon 16007-2 (2018)
2019-04-19 00:00
コメント(0)
アズマリのメリスマ ギザチュウ・テショム [東アフリカ]

なんて味のあるコブシ回しなんだろうか。
メリスマの利かせ方ばかりでなく、発声の強弱を駆使して
風が舞うような節回しを描く、その技量の高さにタメ息がでます。
ヴァイタルに歌えば野趣な味わいがにじみ出るし、いやあ、いい歌い手ですねえ。
アズマリでなければできない芸当、その鍛え抜かれた芸能の深淵が
まさにそこに表現されている、そんな思いを強くさせる見事な歌唱です。
ギザチュウ・テショム。
経歴などのバイオ情報が見つからなくて、詳細はわかりませんが、
間違いなくアズマリ出身、中堅どころといった歌手でしょうか。
11年にこんなアルバムがカナダで出ていたとは知りませんでした。
これほど素晴らしいシンガーをずっと知らずにいたなんて、などと反省しながら、
データベースに打ちこんでいたら、あれ? この人の旧作を持ってる!
ぜんぜん記憶になくて、棚をごそごそ探して、ジャケットを見て、ようやく思い出しました。

エチオピアで出た08年作(表紙の2001はエチオピア暦)で、
今回手に入れたカナダのサミー・プラス・プロダクションからも出ているようです。
歌はいいんだけど、プロダクションがちょっと難だったような覚えがあったんですが、
聴き返してみたら、やっぱりその通りでした。
主役のせっかく歌の上手さを、シンセやサックスなどバックの音がジャマしたり、
ヴォーカルがサウンドに埋没気味となっているミックスもいただけません。
そんな08年作の欠点をすべて改善してみせた本作は、
ギザチュウのヴォーカルが前面に押し出され、
クラール、マシンコ、ワシントなどの伝統楽器と、
サックスやエレクトリック・ギターとの絡みもこなれています。
反復フレーズでじわじわと熱を帯びていくのは、アズマリのお約束。
ウチコミ使いと思えぬグルーヴィなビート感も申し分ありません。
辛口の女声のお囃子と、パワフルなギザチュウとのかけあいに手に汗握れば、
絶妙なタイミングで炸裂するウルレーションに昇天します。
Gizachew Teshome "DES BELONAL" Samy Plus Production no number (2011)
Gizachew Teshome "YEHUNA" Master Sound no number (2008)
2019-04-17 00:00
コメント(0)
サハラン・ロックの嘆き エムドゥ・モクタール [西アフリカ]

『パープル・レイン』のトゥアレグ・バージョン映画
“AKOUNAK TEDALAT TAHA TAZOUGHA” で主役を演じた
エムドゥ・モクタールの新作がリリースされました。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-12-04
前作は弾き語りのアルバムでしたけれど、
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-10-18
今作は、エムドゥ本領発揮のギター・バンド・スタイルのアルバム。
あ、ちなみに、「ムドゥ」と書いている人がいますけれど、
映画を観ればわかるとおり、現地ではエムドゥと呼ばれています。
Mdou はM.dou を省略したものだからなんですね。
さて、今回は初の本格的なスタジオ録音。
アメリカへ渡り、デトロイトでレコーディングしています。
エムドゥのリード・ギターに、リズム・ギター、ベース、ドラムスの4ピース・バンドで、
ベースはワシントンのアヴァンギャルド・バンド、
レ・リノセロスのベーシスト、マイケル・コルトゥンが務めていて、
マイケルは、レーベル・オーナーのクリストファー・カークリーとともに、
プロデューサーにもその名を連ねています。
レ・リノセロスは、ヘヴィー・メタル、マス・ロック、ノイズ、音響系、
クレズマー、レゲエなどをごたまぜしたバンドで、
ツァッディークからアルバムをリリースしているといえば、おおよその想像はつくかな。
そのレ・リノセロスのリーダーであるマイケルは、カマレ・ンゴニを弾いたり、
‘Takamba’ なんてタイトルの曲も書いていたので、
きっとサハラの音楽にも通じている人なんでしょうね。
冒頭のかすかな音量で分散和音をピッキングするギターに、
歌とコーラスのかけあいが静かに重なり合う幻惑的なオープニングから、
独特の雰囲気に包まれます。
静寂を破るドラムスのフィルに導かれて、
エレクトリック・ギターの金属的な響きを高らかに奏でられる時点で、
はや持っていかれちゃいました。
じわじわと熱を帯びて、曲後半になるほどに激しさは増し、
エムドゥのギターがジミ・ヘンドリックスばりに唸りを上げます。
左右のチャンネルを行き来するギター・ソロには、めまいがしそう。
この痛快なロック・サウンドは、先輩格ボンビーノと共通するセンスで、
エムドゥはボンビーノの強力な対抗馬となりましたね。
二人ともヴォーカルは弱いものの、それを補って余りある
力量のあるギター・ミュージックを聞かせてくれます。
二人の違いと言えば、割り切りの良いドライなボンビーノに比べ、
エムドゥにはアソウフが醸し出すディープな情感が強くあるところでしょうか。
タミクレストの寂寥感を思わす、サハラン・ロックのブルージーな嘆きが、
たまらなく人を惹きつけます。
Mdou Moctar "ILANA:THE CREATOR" Sahel Sounds SS051 (2019)
2019-04-15 00:00
コメント(0)
30年ぶりの再会 ピポ・ジェルトルード [カリブ海]
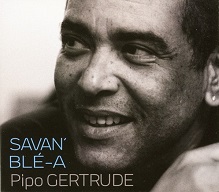
マラヴォワのフロントを務めた名クルーナーのラルフ・タマールが退団し、
後任を務めたシンガーが、ピポ・ジェルトルードでした。
コーラスの一員にトニー・シャスールも加え、マラヴォワは89年に来日しましたが、
正直ラルフ・タマールが抜けた穴は大きすぎて、
ピポの力量では到底埋められないというのが、
後楽園ホールのライヴ後の率直な感想でありました。
あの時のライヴでは、ピポがメインで歌いましたけれど、
数曲歌ったトニーの方が良かったという記憶が残っています。
あれから四半世紀。ミジコペイの活躍によって、
トニー・シャスールが魅力溢れるシンガーに成長したことを、
再認識させられましたけれど、なんとピポの新作も出ていたんですねえ。
ピポのソロ・アルバムというと、ひょっとして93年のアルバム以来でしょうか。
ほかにアルバムが出ていたら、ゴメンナサイですけれど、
ぼくにはすっごく久しぶり感のあるアルバムです。
CD裏には「2017」のクレジットがあるものの、18年2月に出たという本作、
シュヴァル・ブワなどマルチニークの伝統色も生かした、
オーガニック・サウンドのズークを聞かせてくれます。
ヌケのいいサウンドの要となっているのは、ロナルド・チュール。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-02-20
ほとんどの曲のアレンジをロナルドが担っていて、
エレガントなビギン・ジャズのニュアンスを醸し出すピアノ・プレイを堪能できます。
リズム・セクションも強力で、
ジャン=フィリップ・ファンファンが叩くシンバルとハイハットの高音と、
バゴが叩く太鼓の低音の絶妙なコンビネーションが、
リズムをグルーヴさせているところも、アルバムの聴きどころとなっています。
ピポのヴォーカルは、昔と変わらないスウィートかつスマートな歌いぶりで、
ラルフ・タマールと比較するような無茶を言わなければ、
十分魅力のあるヴォーカリストですよね。
ほとんどがピポのオリジナル曲ですが、
ジミー・クリフの‘Many Rivers To Cross’ のカヴァーもなかなかの聴きもの。
ラップも飛び出す‘Je Suis Content’ は、ホーン・セクションとシンセサイザーが
80年頃のマグナム・バンドを思わせるソウル色の濃いコンパなら、
‘An Pèp An Sel Konba’ は、ル・フラール・デジャンふうのコンパで、
ハイチ音楽ファンならカンゲキすることウケアイ。
伝統リズムを強調した民俗色濃い‘Chagrin La Tcho’ もあれば、
アルバム・ラストの‘Bay Lavwa’ はシュヴァル・ブワと、
ジャズ色の濃いミジコペイに対してピポのソロ作は、
マルチニークのフォークロアもたっぷりと詰まった快作になりました。
Pipo Gertrude "SAVAN’ BLÉ-A" Solibo Music SM2017-001 (2017)
2019-04-13 00:00
コメント(0)
クレオール・ビッグ・バンド・ジャズ ミジコペイ [カリブ海]
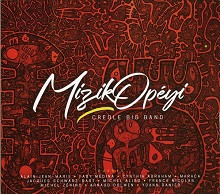
いったいどれくらい、ミジコペイのライヴDVDを観たかなあ。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-03-07
3か月近く毎日観続けたくらいだから、100回はもちろん下らないし、
その後も週末に観返したりしてたから、200回以上は観たかも。
フィナーレの高揚感がたまんないんですよね。
ぼくもここでは立ち上がって、踊りながら画面最後のテロップを追ったものです。
いまでも、トニー・シャスールやバンド・メンバーの所作ひとつひとつが、
脳裏にくっきりと刻み込まれていますよ。
あれほど夢中になったライヴ映像は、シティ・ヌールハリザの
ロイヤル・アルバート・ホールのライヴVCD以来でしたねえ。
で、あの14年のライヴDVD以来となる、ミジコペイの新作であります。
これまでミジコペイのスタジオ作は、
バンドのダイナミズムをうまく封じ込めずにいました。
あれだけ迫力のあるDVDを観てしまった後だけに、不安もあったんですが、
これまでのスタジオ録音のなかでは、一番の出来になったんじゃないでしょうか。
クレオール・ビッグ・バンドの名を冠したタイトル通り、
ビッグ・バンドのジャズ・サウンドを全面に押し出した仕上がりとなっています。
音楽監督のピアニスト、ティエリー・ヴァトンがほとんどの曲をアレンジしていて、
第1トランペットのクリスチャン・マルティネスが2曲でアレンジをしています。
いずれも旧来のビッグ・バンド・スタイルのジャズ・アレンジで、
「スターダスト」なんてレパートリーがどハマリですね。
ここのところ、新世代ジャズのオーケストレーションばかり聴いていたせいか、
昔ながらのビッグ・バンド・アレンジが、かえって新鮮に響きましたよ。
そして今作の目玉は、
これまでオリジナル曲中心だったレパートリーから、がらりと変わった選曲です。
クレオール・ジャズをアイデンティファイするかのように、
カリの大名作‘Racines’ を筆頭に、ユジュヌ・モナの‘Bwa Brilé’、
マリウス・クルティエの‘Laïni’、マリオ・カノンジュの‘Péyi-Mwen Jòdi’ を
取り上げているのが注目されます。
トニー・シャスールが16年に芸歴30周年記念ライヴで披露していた、
アレクサンドル・ステリオの古典ビギン曲‘Gran Tomobil’ は、
初のスタジオ録音となりましたね。
さらにクレオール・ジャズを拡張する視点から、
ハイチのシンガー・ソングライター、ベートーヴァ・オバスの出世作‘Si’ に、
レユニオンのジャズ・ピアニスト、メディ・ジェルヴィルの‘Di Amwin’ という
マルチニーク以外のレパートリーを取り上げた選曲眼には、ウナらされました。
両名ともぼくのごひいきの音楽家ながら、
知名度の低さが悔やまれてならなかっただけに、
ミジコペイが取り上げてくれたのは、嬉しさひとしおです。
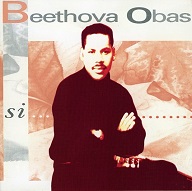
それにしても、ヘイシャン・エレガンスの極致ともいえる‘Si’ が
取り上げられるとは、カンゲキです。
思わずひさしぶりに、棚から取り出して聴き返してみましたけれど、
いやあ、これもハイチ音楽の名盤ですね。
Mizikopéyi "CREOLE BIG BAND" Aztec Musique/3M 3M-CM2581 (2018)
Beethova Obas "SI..." Déclic Communication 001-2 (1993)
2019-04-11 00:00
コメント(2)
60年代シングル時代のアパラ カスム・アディオ [西アフリカ]

おぉ、カスム・アディオのCDが出た!
なんて喜ぶ日本人は、ぼくくらいのものでしょうけれど、
アインラ・オモウラ登場以前、ハルナ・イショラの全盛期だった
60年代末から70年代に人気を集めたアパラのシンガーです。
ハルナ・イショラと同郷のイジェブ=イボ出身で、
19年生まれのハルナ・イショラよりは、だいぶ若い28年の生まれ。
24年生まれのリガリ・ムカイバと競い合いながら、
ハルナ・イショラ独走のアパラ・シーンをにぎわせた歌手の一人です。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07
41年にプロ歌手となり、48年に初録音、
デッカから69年に出したシングル‘ORIKI IBEJI’(WAX135)がヒットし、
このシングルが本CDに収録されています。
LP時代のようなA・B面2トラックではなく、短めの6トラックが収録されているので、
おそらくシングル盤3枚をCD化したものじゃないでしょうか。
CDには‘In the 60's’ の文字も見えますから、
おそらく同時期の60年代末に出たものと思われます。

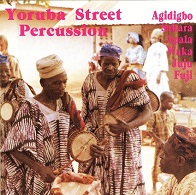
この人のレコードは手に入りにくくて、ぼくも10インチとLP1枚しか持っておらず、
LPの方は手放してしまいました。たしかLPの方は、
演奏が退屈だったような記憶が残っていますけれど、
このCDと一緒に入ってきた『第5集』がやはりLP時代の復刻で、
トーキング・ドラムほかパーカッション・アンサンブルにメリハリがなく、単調でしたね。
60年代のシングル時代の録音の方が良かった人なのかもしれません。
この時期のものとしては、オリジナル・ミュージック盤
“YORUBA STREET PERCUSSION” でカスムの曲を2曲聴くことができます。
重厚で威厳のあるハルナのいぶし銀の声とも、
からっとした枯れた味わいのリカリ・ムカイバの声とも違う、
クールで苦味の少ないカスムのヴォーカルは、クリーンなハリのある声で、
また違った味わいのアパラを聞かせます。
歌と囃子の合間に割って入ってくるトーキング・ドラムや、
各種パーカッションのフィルも絶品です。
アギディボがごんごん、ぐいんぐいんと、
アンサンブルを低音部からグルーヴさせていて、ゾクゾクしますよ。
Kasumu Adio & His Apala Group "VOL.1: ORIKI IBEJI" Afrodisia (Nigeria) WAPS114
[10インチ] Kasumu Adio and His Apala Group "KASUMU ADIO AND HIS APALA GROUP" Decca WAL1062
v.a. "YORUBA STREET PERCUSSION" Original Music OMCD016
2019-04-09 00:00
コメント(0)
クール・ミスB ベティ・ブライアント [北アメリカ]

カンサス・シティ生まれで、ジェイ・マクシャンはお師匠さん、
アール・グラントとはマブダチだったという、
「クール・ミスB」の異名を持つ女性弾き語りピアニスト、ベティ・ブライアント。
御年88歳で、これだけ歌えちゃう!
そもそも老人声でないのが、驚異的じゃないですか。
ピアノも達者で、ブギウギで鍛えた運指は
衰え知らずなのだから、脱帽です。
いやあ、このくらいの齢の女性って、なんでこんなに元気なのかなあ。
実は、うちの母も同い年なんですけれどね。
この人が病気になったことがないという、ちょっと考えられない人でして、ええ。
じっさい寝込んだ姿なんて見たことないし、インフルエンザはおろか、
風邪もひいた記憶がないっていうんだから、ほんとに人間かよ、と。
で、そのベティさんの新作のタイトル「プロジェクト88」は、
88歳の米寿と88鍵のピアノをひっかけて、
テナー・サックスのロバート・カイルを中心に、
大勢の仲間を集めて企画されたもの。
メンバーには、なんとあのジェイムズ・ギャドソンも参加していて、
‘Just You, Just Me’ では歌も披露して、ベティとデュエットしているんです。
たったの2曲というのが、なんとも惜しいというか、全曲叩いて欲しかったなあ。
ギャドソンのドラムスってシンプルなんだけど、グルーヴがふくよかで、
あったかいから、すぐわかる。ぼくの大好きなドラマーです。
‘Oh, Lady Be Good’‘Ain't Nobody's Business’ といった
カンサス・シティ・ジャズ好みの古いナンバーがいいのは当然として、
ベティのオリジナルがまた良いんだなあ。
‘My Beloved’ なんて甘いスローや、
アクースティック・ギターとフルートをフィーチャーした
小粋なサンバの‘Cho Cho’ のセンスの新しさに、ウナらされます。
すごいよね、ミュージシャシップの若さが。
なんでもベティは、代官山のジャズ・クラブ「タブローズ・ラウンジ」に、
13年間も定期的に出演していたんだそう。
なんだあ、それを知っていたら、一度くらい母を誘って観に行ったのに。
Betty Bryant "PROJECT 88" bry-mar music no number (2019)
2019-04-07 00:00
コメント(0)
若手育つボレーロ・シーン レー・クエン [東南アジア]
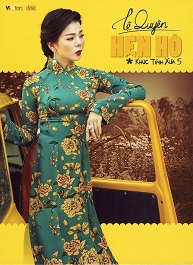
そしてもう1作が、シリーズ化したボレーロ集“KHÚC TÌNH XƯA” の第5弾。
初めてぼくがレー・クエンと出会ったのが、このシリーズの初作でした。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-12-11
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-08-21
本シリーズの前作“KHÚC TÌNH XƯA : LỆ QUYÊN - LAM PHƯƠNG” が、
「ミュージック・マガジン」のベスト・アルバム2017ワールド・ミュージック部門で
2位となったのには、さすがにぼくもビックリしましたよ。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-03-20
レー・クエンを絶賛しているヤツなんて、ぼく一人だけのもので、
長い間ずっと孤軍奮闘だったんですから、えぇ。
日本盤が出るわけでなし、大型輸入CDショップには相手もされず、
日本で在庫しているのは、セレクト・ショップ2店だけというお寒い状況で、
よくぞ2位という破格の評価をしてくれたものです。
世の流行やら業界事情などではなく、真に内容を評価してくれたからこそで、
これは本当に嬉しかったですよ。カンゲキしました。
毎年のように一人絶賛しているのも、アホみたいというか、
どうせ人から呆れられているのだろうと、
個人の年間ベストに入れるのを、初めて遠慮した年のアルバムだっただけに、
カタキをとってくれたみたいな気分で、痛快至極でありました。
さて、その日本を代表する音楽誌で年間2位の評価を得た作品の次作となる本作は、
2部構成という初の企画。
前半の1部はレー一人が歌いますが、後半の2部は、ボレーロ・コンテストで入賞し、
レーが育ててきた若手歌手たちとのデュエットという構成になっています。
レー・クエンが歌い始めたのをきっかけに、
古いヴェトナム歌謡は、ボレーロのジャンル名で親しまれるようになりました。
当時を知るオールド・ファンばかりでなく、若者にも受け入れらて、
コンテストが開催されるほか、レー・クエンのフォロワーが登場するまでの
盛り上がりをみせています。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-04-26
今作でレーとデュエットした7人のうち、ぼくが耳をそばだてられたのは、
9曲目のマイ・フォンという女性歌手。
ザンカー系の素養をうかがわせる、発声とこぶしを駆使する歌手で、
繊細なこぶし使いや、厚みのある中音域の落ち着いたトーンがいいですね。
レーと一緒に歌って、レーの声より前にせり出してくる押しの強さは、傑出しています。
そして、レー・クエン自身も成長しています。
出だしの第一声の、軽やかなハイ・トーンに驚きました。
一瞬、え? これ、レー・クエンか?と戸惑い、
しばらく別人じゃないのかと、首をひねりながら聴き進めていくうちに、
ようやく彼女の声だとわかりました。
シリーズ初作の頃から考えると、レーの発声もずいぶん軽やかになりました。
前作にもその傾向はうかがえましたけれど、今回かなりはっきりしましたね。
低音のアルト・ヴォイスで、ぐぅーっと声を絞り上げる、
レーのトレードマークともいえる歌い回しが、影を潜めるようになったともいえます。
これでレー・クエンが苦手といっていた人も、あらためてファンになる人が出てくるかも。
レーが語るところによると、これまでのレコーディングでは、
歌の世界に没入するあまり、完パケのあとは憔悴しきっていたとのこと。
歌の主人公の悲哀に打ちのめされ、自室にひきこもってしまうほど、
メンタル面で打撃を受けていたんだそうです。
それが結婚や出産を経て、より歌を快適に、自然に歌えるようになったといいます。
こうしたメンタル面での成長が、エモーショナルなアルト・ヴォイスを抑えて、
軽やかさをもたらしたようですね。
このシリーズを始める前、レーがまだカヴァー歌手だった若い頃は、
古い叙情歌謡にトライしてみても、詩の解釈や歌い込みが不足していて、
自分の未熟さを痛感していたといいます。
歌の主人公になりきれるよう、自らを追い込まないと歌えなかったそうで、
そうした激しさが、あの深い情念をもたらしたんですね。
それが人生経験を積むようになって、歌との距離感をコントロールできるようになり、
楽に歌えるようになってきたと、インタヴューで彼女は語っています。
ボレーロ・ブームのさきがけでとして、後進を育てつつも、
みずからも成長を続けるレー・クエン、頼もしい人です。
芸歴20周年を迎える今年、12月には記念コンサートも予定され、
すでに20年記念プロジェクトがスタートしているそうです。
Lệ Quyên "KHÚC TÌNH XƯA 5 : HẸN HÒ" Viettan Studio no number (2019)
2019-04-05 00:00
コメント(2)
悲恋を歌わせたら世界一 レー・クエン [東南アジア]

少しごぶさたになっていたヴェトナムのボレーロ・クイーン、レー・クエン。
2年ぶりに、また彼女の歌に溺れる日々がやってきました(←喜んでる)。
う~ん、心おどりますねえ。
2年ぶりなのは、昨年リリースされた『チン・コン・ソン集』ががっかりだったから。
8年前のヴェトナム旅行でレー・クエンを発見して以来、
新作が出るたび、欠かさずに記事を書いてきましたが、
前作の『チン・コン・ソン集』は、さすがに書く気はおこりませんでした。
次作は『チン・コン・ソン集』という話が漏れ伝わってきた時点で、
イヤな予感はしていたんです。シロウトぽい歌手が、とつとつと歌ってこそ
味の出るチン・コン・ソンの曲をレーが歌うだなんて、
あまりにも歌い手の資質を無視した、無謀な企画。
彼女はどう対峙するつもりだろう、何か妙案でもあるのかしらんと気をもみましたが、
仕上がりは、彼女の持ち味と全くかみ合っておらず、レー初の失敗作。
アルバムが出るたび傑作というレー・クエンも、ついにつまづいちゃいましたね。
というわけで、ひさしぶりになったレー・クエンなんですが、
年初め早々から、いきなり2作同時リリースです。
前にもこういうことがありましたけれど、意欲満々じゃないですか。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-02-18
実は『チン・コン・ソン集』もセールスは芳しくなく、イニシャルが4000枚だけ。
ところが、今回の2作は発売初日でいきなり7000枚がはけたとのこと。
ヴェトナム歌謡界で一番怠惰な歌手と、レー本人も告白するとおり、
これまでミュージック・ヴィデオの制作をしてこなかったものの、
今回は新作から2曲のヴィデオ・クリップを制作して、やる気も十分です。
発売前の1月3日にハノイ・オペラ・ハウスで、
発売当日の1月10日にはホーチミンで、新作お披露目のコンサートが行われたそうです。
ここ最近のレーは、若手作曲家によるポップス・アルバムと、
ヴェトナム戦前の作曲家たちによる抒情歌謡のボレーロ・アルバムを、
それぞれ制作していて、今回の2作もそれに従っています。
今回紹介するのは、第6集と銘されたポップス・アルバムの方。
「6」のカウントの仕方がいまひとつよくわからなくて、
というのも、もっと多くのポップス作を出しているからなんですが、
今回のパッケージ・デザインの美しさには、目を見開かされます。
アート・ディレクションのファッション・センスは、
今のヴェトナムのクオリティの高さを表していますね。
おなじみとなったホルダー・ケ-スには、
歌詞と美麗写真を表裏にしたカード6枚が入っています。
カード枚数からもおわかりのとおり、全6曲。
収録時間30分に満たないミニ・アルバムですが、内容は濃いですよ。
レー・クエンお得意の、情感たっぷりに悲恋を歌ったラヴ・ソング集です。
アクースティック・ギターを効果的に使い、ヌケのあるサウンドを作っていて、
レーの歌いぶりも重々しくならないよう、歌いぶりを変化させているのに気付きます。
軽やかなハイ・トーンを意識的に使い、発声の仕方を変えていますね。
それでも、にじみ出る情念の濃さは、レーならではでしょう。
悲恋を歌わせたら、この人を凌ぐ人は世界にいないのではと思わせるほど、
胸の奥を締め付けられるような深い情感を絞り出す。やっぱりスゴイですよ。
ヴェトナム語をまったく介さない人間が、その歌いぶりとメロディに、
これほど感情を揺さぶられてしまうのだから、
あらためて歌の力のスゴ味を思い知らされます。
Lệ Quyên "TÌNH KHÔN NGUÔI VOL.6" Viettan Studio no number (2019)
2019-04-03 00:00
コメント(0)
無敵の推進力 ファヴィオ・ゴウヴェア [ブラジル]

あれこれサンプルを聴いて、もう1枚拾い上げたのが、
ファヴィオ・ゴウヴェアというギタリストの17年作。
最近好作品を連発している注目のジャズ・レーベル、ブラックストリームのアルバムです。
CDが手元に届き、クレジットを見て、ビックリ。
クインテートのピアノはベト・コレーアで、ドラムスはクレベール・アルメイダ。
なんとまあ、同じようなメンツのアルバムを2枚同時に買っていたんでした。
サンプルを聴いてピンときたのは、
やっぱりクレベールのドラミングに反応したからだったのかな。
ファヴィオ・ゴウヴェアは、サン・パウロ出身のギタリストで、
96年にアンドレ・マルケス、クレベール・アルメイダとともに
トリオ・クルピーラを結成し、いまもなお活動を続けているという人。
トリオ・クルピーラって、重要なグループだったんだなあと、再認識しました。
ファヴィオもまたエルメート・パスコアール一派で、
イチベレ・ズヴァルギのトラとしてベースを弾くこともあるのだそう。
ギター以外にも、フルートも吹くマルチ・プレイヤーで、
本作でもフルートをプレイしています。
で、オープニングの‘Moema Morenou’ から強烈。マラカトゥのリズムが炸裂し、
クレベール・アルメイダのキレ味抜群なドラミングが冴えわたります。
ドー・ジ・カルヴァーリョのサックスが快調にトばして、
うぉーと、前のめりになっていると、ベース・ソロになって一転クールになり、
続いてファヴィオのギター・ソロへと移っていく。カッコよすぎ!
なんとこの曲、パウリーニョ・ダ・ヴィオラと
エルトン・エデイロスの作というのだから、驚きます。
この二人のコンビで、マラカトゥを作っていたなんて、意外ですねえ。
2曲目はもろにエルメートなテクニカルなコンポジション、
3曲目もアブストラクトなテーマを持つものの、
ウタゴコロに富んだメロディが出入りするので、具象性から離れることはなく、
難解な印象をこれっぽちも与えず、めちゃ親しみやすい。
さらに、密度の高いアンサンブル・ワークと、
ぐいぐいと疾走していく推進力のあるグルーヴが、気持ちのいいのなんのって!
無敵だぁ。
ベト・コレーアのデビュー作でも演奏していた7拍子の‘Camisa 10’ を
こちらでもやっていて、終盤にメンバーがコーラスする高揚感は悶絶もの。
こりゃあ、ベト・コレーアのアルバムと抱き合わせで、
2~3か月ヘヴィ・ロテになること疑いなしですね。
Fabio Gouvea Quinteto "MÉTODO DO ACASO" Blaxtream BXT0013 (2017)
2019-04-01 00:00
コメント(2)




