エレクトロニック・ポップの極北 エリカ・ド・カシエール [北ヨーロッパ]

おぉ、もう2年半も経っていたのか。
タイトルどおり、ぼくにとってはセンセーショナルだったエリカ・ド・カシエールの前作。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-09-23
すっかりトロけさせられたあのアルバムから、もう新作?と思ったら、
2年半も経っていたんだね。
この音楽をオルタナR&Bと呼ぶにせよ、アンビエントR&Bと呼ぶにせよ、
そもそもR&Bを名乗らなくたって、いいんじゃないですかね。
そんなことを思わせる、まさしくオルタナティヴ・ポップの極北といえそうなサウンドです。
UKガラージをベースとするのは、Y2Kリヴァイヴァルと並走しているし、
エリカの歌い込まないアトモスフェリックな歌唱だって、
トリップ・ホップを汲むものだしね。
エレクトロニック・ポップの最先端ともいえるそのエリカ・ド・カシエールが、
ニュージーンズに楽曲提供したのには驚いたけど、今作収録の ‘Lucky’ を聴けば、
実験性とポップの共存がとんでもなく高いレヴェルで実現していて、
アンテナの高いニュージーンズのプロデューサーが起用するのもナットクできます。
レゲトンやヒップ・ホップをやってるのに、それらしく聞こえない音作りって非凡だよねえ。
耳元をくすぐるような甘いヴォイス、
デリカシーの塊のような磨き上げられた音色。
アンニュイな歌の表情がエクスタシーへと誘われるのは、前作同様。
今回は生楽器も使われているらしく
( ‘Twice’ のドラムスのブラシはエリカが叩いているとのこと! )、
前作とは作り方が違うといいますが、聴感上はあまり変化を感じず。
それほど音像の完成度が高いということなんでしょう。
こういう最先端の音楽を、オールド・メディアのCDでもちゃんと出してくれるところに、
オールド・エイジのファンとしては感謝の限りなんであります。
Erika De Casier "STILL" 4AD 4AD0639CD (2024)
2024-03-23 00:00
コメント(0)
コンポーズと即興演奏のオーガナイザー コマ・サクソ [北ヨーロッパ]
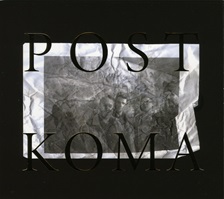
コマ・サクソの新作がスゴイことになってる。
前作のエクレクティックなサウンドに、
未来派ジャズを幻視したような錯覚を覚えたものですが、
今思えば、それは錯覚じゃなかったんですね。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-05-23
ジャズ、クラシック、フォーク、ファンク、ビート・ミュージック、エレクトロニカと、
あらゆる音楽の実験場となっていた前作でしたけれど、
今作はその実験がひとつの完成形を見せていますよ。
どアタマから強靭なゆらぎビートで、クリス・デイヴ以降のジャズと
ビート・ミュージックを咀嚼したグルーヴがたまりません。
今作では、ペッター・エルドがサンプラーをかなり積極的に使用していて、
随所に短いカット・アップを組み込むなど、
サウンド・アーティストぶりを発揮しているんですが、
同時に即興演奏を際立たせるサウンドの構成が巧みで、
楽曲に明確なヴィジョンがあって、それを実現するアイディアも豊富なのね。
全13曲中1曲を除いてたった1日で録音した後に、
エルドが録音を重ねて完成させています。
なにより今作のいいのは、サウンドの風通しが良いこと。
リーダーのペッター・エルドのフレキシブルな音楽姿勢がメンバーに伝わり、
メンバー同士がインスパイアしあって、演奏にサプライズが起こっています。
コンセプト・アルバムの色彩が強かった前作とは、演奏の爆発力が違います。
バップからフリー・ジャズを経由してビート・ミュージックまでシームレスに繋がっていて、
ジャズの歴史を横断しつつ21世紀のジャズを響かせるコンポジションがスゴイ。
コンポーズと即興演奏をオーガナイズするペッター・エルドの力量を示した傑作です。
Koma Saxo "POST KOMA" We Jazz WJCD50 (2023)
2023-12-16 00:00
コメント(0)
ギター・ミュージックの可能性 オリ・ヒルヴォネン [北ヨーロッパ]

ブルックリンを拠点に活動するフィンランド人ギタリスト、オリ・ヒルヴォネンが来日。
最新作 “KIELO” のレコーディング・メンバー、マーティ・ケニー (b) と
ネイサン・エルマン=ベル (ds) とのトリオのライヴを、
9月21日代官山「晴れたら空に豆まいて」で観てきました。
圧巻のギター・ミュージックでしたねえ。
クリーンなギターのトーンは、どんなに激しくカッティングしようが、
きらめくような美しさがあり、北欧の大自然を連想させる
雄大さと深淵さが伝わってきて、圧倒されました。
新作のフィンランドのフォークから着想を得た曲で、それは特に発揮されていましたね。
シングル・トーンからコード・ソロそしてリズム・カッティングへと、
自在にソロ・スタイルを変化させながら弾き倒す、オリのリズム感がスゴかった。
リズムにブレが寸分もなくて、正確無比。トレモロを多用するんだけれど、
音の均整が素晴らしくて、どんだけ練習すればあんなギターを弾けるんでしょうか。
4拍子と6拍子が何度もスイッチしたり、変拍子も多用しながら、
曲中に何度もギアを入れ替えて、瞬時にリズムを変化させるアンサンブルも見事でした。
14年にこのトリオを結成して、すでに10年近い活動歴を持つという、
3人の息の合い方が完璧。ネイサンのしなやかなドラミングが、
曲のスケール感を倍加させるダイナミズムを発揮していましたよ。
シンプルなドラム・セットを使い、ドラミングで歌わせるのが得意なドラマーなんですね。
ユニークだったのが、マーティ・ケニーがベースを弾かずにギターを使っていたこと。
開演前に、ベース・アンプにギターが繋がっていて、???と思っていたんですが、
エレクトリック・ベースの奏法でギターを弾いていて、こういうベースもあるんですねえ。
オリは11年にニュー・ヨークへ渡り、13年にマンハッタン音楽学校で修士号を取得、
16年にモントルー・ギター・コンクールで優勝し、
審査委員長のジョン・マクラフリンに賞賛されたギタリスト。
オリのギター・ミュージックには、コンテンポラリー・ジャズ、フォーク、シューゲイザー、
バロック音楽、ノイズ・ミュージックが養分となっているのが刻印されています。
サインを入れてもらった19年作の “DISPLACE” は、
このトリオにルーク・マランツ(p)が加わったアルバムで、
オリのアルバムでぼくが一番愛聴してきたもの。
すでにこの地点から、オリははるかに前進していましたね。
オリの独創的な音楽世界に、ギター・ミュージックの可能性は
まだまだ尽きないことを教えられた一夜でした。
Olli Hirvonen "DISPLACE" Ropeadope no number (2019)
2023-09-23 00:00
コメント(0)
ポリリズムを深化させたアフロビート・ジャズ サンボーン [北ヨーロッパ]

デンマークのアフロ・ジャズ・バンド、クティマンゴーズが、
サンボーンとバンド名を変えて再出発。改名後第1作が届きました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-10-08
また一歩、音楽性の歩みを進めましたね。
オープニングの ‘Dancing In The Dusk’ から、
オーケストレーションを思わせる
重厚なホーン・アンサンブルのアレンジに引き込まれました。
サックスのひび割れたサウンドや、ブレイクでフルートが立ち上ってくる場面など、
これまでにないスケール感を生み出しているじゃないですか。
アフリカ音楽のポリリズムを取り入れつつ、
ハウス・ビートを生演奏にトレースしたようなドラムスの、
トランシーなグルーヴにもドキドキさせられます。
今回、ドラマーだけが新しいメンバーに交代したんですね。
‘Night Sweats’ で、ホーン・セクションがまるでEDMのシンセ・リフのように
響かせているのも面白いなあ。
デジタル・サウンドを生演奏に置き換える試みですよね。
電子音楽のコンテクストをアクースティックな演奏に転換する試みは、
クラフトワークの ‘Metropolis’ のカヴァーでも見事に発揮されていますよ。
アフロビートのグルーヴを生み出すドラムスとのミックスも鮮やかです。
南ア・ジャズのサウンドスケープをトレースした ‘Under The Same Sky’ もいい。
アフロビートだけじゃなく、こういう曲も書けるところが、このバンドの強みで、
アフリカ音楽を深く探求している証拠だね。
ザップ・ママやプリンスのニュー・パワー・ジェネレーションの一員だったこともある、
デンマーク人女性ベーシストのイダ・ニールセンと、
ニュー・ヨークのジャズ・シーンで活躍する
日本人ピアニスト、ビッグユキがフィーチャーされた ‘Mankind?’ は、
ヘヴィーでワイルドなグルーヴに満ちたトラック。シンセ・ソロのパートを差しはさんで、
サックス・ソリがサウンドを切り裂きながら進行していくアレンジが、壮観です。
ポリリズムを深化させたアフロ・ジャズ、というよりもアフロビート・ジャズでしょうか。
バンド名を改名して、さらに奥行を増したサンボーンです。
Sunbörn "SUNBÖRN" Tramp TRCD9114 (2023)
2023-05-20 00:00
コメント(0)
リェナ・ヴィッレマルクの背中を追って ジュース・オック・リクタ [北ヨーロッパ]

なんてフレッシュなポリフォニー!
一聴して、魅せられちゃいました。
「光とランタン」を名乗る、スウェーデンのフォーク・グループのデビュー作です。
女3男1の4人組で、全員が歌います。
伴奏がギターとフィドルだけという潔さがいいじゃないですか。
ソロのシンギングやポリフォニーのコーラス、リルティングも自由闊達で、
実にのびのびとしていて、キモチいいですねえ。
レパートリーは舞台芸術庁のアーカイヴから見つけてきた
スウェーデンの伝統歌ばかりだそうで、
それを彼ら流にアレンジを練ったものなのでしょう。
伝統に沿いながらも、ポリフォニーには現代性が感じ取られ、
熟達したフィドルのプレイもビートが立っていて、スリリングです。
歌と演奏の双方がそれぞれ引き立つ場面が作られていて、
構成がしっかりしています。
なんでもリード・ヴォーカルのクララ・エックマンは、
リェナ・ヴィッレマルクのコンサートを観たことで、
伝統歌の世界にのめりこむことになったんですって。
それを聞いて、ぼくもリェナの89年のデビュー作を思い出して、嬉しくなっちゃいました。

リェナ・ヴィッレマルクといえば、
ぼくにスウェディッシュ・フォークの素晴らしさを教えてくれた人。
トラッドに立ち位置を置きながら、ロックやジャズなどへと領域を広げ、
さまざまな実験も重ねて、このジャンルの第一人者となりましたが、
ブズーキとフィドルをバックに、ゴリゴリの伝統歌を歌った
リェナの鮮烈なデビュー作が、いまでもぼくには忘れられません。
そんなリェナのデビュー作にもオーヴァーラップする、
若々しさが輝かしい、とびっきりフレッシュなジュース・オック・リクタのデビューです。
Ljus Och Lykta "LJUS OCH LYKTA" Caprice CAP21938 (2022)
Lena Willemark "NÄR SOM GRÄSET DET VAJAR" Amigo Musik AMCD722 (1989)
2023-04-26 00:00
コメント(0)
リリカルにして精悍 エイヨルフ・ダーレ [北ヨーロッパ]

息も凍りそうな冬空の下で、両手を広げ、深呼吸したくなるようなすがすがしさ。
ノルウェイのピアニスト、エイヨルフ・ダーレの新作のオープニングに、破顔一笑。
ハープシコードの親戚みたいな鍵盤楽器ハンマースピネットや、
ベーシストが弾くソーをオーヴァーダブしたサウンドが、
北欧ジャズの特徴が陰影ばかりではない、北国独特の明るさをもたらしています。
エデイションからの5作目となる新作は、
21年に出した前作“BEING” に続くピアノ・トリオでの第2作。
前作から引き続き、ベースのペア・ザヌッシ、
ドラムスのアウドゥン・クライヴェの3人で演奏しています。
ノルウェイのフォーク・ジャズらしい牧歌的なメロディをたたえながらも、
ロマンティシズムに傾きすぎないビターな味わいがあって、いいですね。
豊かな陰影のあるスローな曲で、情感のある抒情をたっぷりと聞かせる一方、
リズム・セクションがアグレッシヴに攻める曲もあって、
シャープでスリリングな展開を楽しめます。
ピアニストだけでなく作編曲者としての魅力が発揮されたアルバムで、
『旅人』というタイトルが示すとおり、旅程でのさまざまな場面を描いた
映像的な着想が、アルバムに起伏を与えているのを感じます。
1曲1曲が簡潔にまとめられているのも、
演奏家であるとともに作編曲家である思慮深さがうかがえますね。
リリカルにして精悍という、
北欧ジャズに期待するすべてが備わっているアルバムです。
Eyolf Dale "THE WAYFARERS" Edition EDN1212 (2023)
2023-03-15 00:00
コメント(0)
スカンジナビアン・フォーク・ジャズ・エレクトロニカ スヴェイヌボルグ・カーディブ [北ヨーロッパ]

スヴェイヌボルグ・カーディブは、デンマーク北部の港町、オールボー出身の二人組。
ジャズの鍵盤奏者ニコライ・スヴェイヌボルグと、
フォーク・ミュージックのドラマー、ヨナス・カーディブという、
異なる音楽性を持つ二人が13年に出会い、19年にデビュー作を出したとのこと。
3作目となる新作が、マンチェスターのインディ・レーベル、ゴンドワナから出て、
初めてこの二人を知りました。
温かみのあるメロウなウーリッツァーと、ひんやりしたシンセのサウンドが、
浮遊感のあるサウンドスケープをかたどり、
さまざまなリズム・アプローチを試みるドラムスとともに、
アンビエントなフォーク・ジャズ・エレクトロニカといった趣の、
いかにも北欧らしい演奏を聞かせてくれます。
どの曲も抒情を強調しすぎず、メロディがひそやかなところが、いいなあ。
まるで旋律が冬の大気に解き放たれて、たゆたうかのような曲が並んでいて、
その繊細なミニマリズムの心地よさに、うっとりしますね。
ドラムスが一定のリズムをキープしながら、
わずかずつ変化を加え、シンバルの連打で山場を作っていくんですね。
小物打楽器を組み合わせたパーカッション・アンサンブルを聞かせる
‘Orbit’ では、アフリカのリズムを参照したかのようで、惹かれました。
一部の曲で、トランペット二人とギターが参加しているんですけれど、
二人のサウンドにすっかり溶け込んでいて、ゲストの存在を意識させません。
ミニマルなグルーヴが心地よいこと、このうえないですね。
北欧のアトモスフィアに満ちたサウンドスケープは、
息も凍える真冬のサウンドトラックにぴったりです。
Svaneborg Kardyb "OVER TAGE" Gondwana GONDCD057 (2022)
2023-02-05 00:00
コメント(0)
ノルウェイの小さな町のシンギング シノヴェ・ブロンボ・プラスン [北ヨーロッパ]

オスロから北へ約300キロの中央部、
ノルウェイ東部の渓谷にある、オステルダレン地方の小さな町フォルダル。
人口1600人ほどという小さな町に生まれ育ったシノヴェ・ブロンボ・プラスンは、
ノルウェイ音楽アカデミー民俗音楽部門の修士課程に在籍する音楽家。
シノヴェはデビュー作の制作にあたって、フォルダルの伝統音楽に狙いを定め、
フィドラーだった曾祖父から幼い時に習った曲や、
古い音楽書、アーカイヴ録音から素材を集めたといいます。
全21曲、無伴奏によるア・カペラという内容なので、
地味なアルバムかと思いきや、リズミカルな曲が多く、
カラフルなメロディに、ノルウェイ民謡独特の味わいがたっぷり練り込まれていて、
すっかり夢中になってしまいました。
シノヴェは歌いながら床を踏み鳴らし、そのリズムが打楽器代わりになって、
ア・カペラに生き生きとしたビートを送り込んでいます。
そして、なにより心地よいのが、シノヴェの芯のあるナチュラルな発声。
上がり下がりの激しいメロディを歌っているんですが、めちゃくちゃ音程がいい。
歌いぶりも力強くて、胸をすきますねえ。
北欧の歌手はぼくの苦手な人が多くて、敬遠していた時期が長くありました。
ノルウェイの有名なシンガー、トーネ・フルベクモもその一人。
ハイ・トーンの芸術的なヴォーカルが、ぼくには受け付けられませんでした。
もっとニュートラルな発声で、土の香りのする歌を聴きたいと思っていたから、
シノヴェ・ブロンボ・プラスンの歌は、ぼくには理想的です。
この伝統的なシンギングは、ダンス音楽がベースとなっていて、
ハーディングフェーレやフィドルで演奏する器楽曲に、
ナンセンスな言葉をつけて声楽にしたものだそうです。
それが副題にある slåttetralling なんですね。
歌詞のある曲もあれば、リルティングのように言葉のない曲もあり、
バラッドや賛美歌とは、まったく性格が異なる音楽ですね。
そういえば、先に挙げたトーネ・フルベクモも、
オステルダレンの伝統的な歌唱をルーツとする人ですけれど、
彼女からこういう歌を聴けたためしはなかったなあ。
シノヴェが歌うア・カペラだって、それは十分に洗練されていて、
じっさいに村人が歌うような野良の歌とは、まるで違うんだろうけれど、
それでも彼女が真摯に伝統音楽を追及した本作は、
ケルト音楽を演出したり、過度に北欧色を強調した<ツクリモノ>とは無縁。
伝統を凝縮した純度の高さに、感じ入ります。
Synnøve Brøndbo Plassen "HJEMVE" Grappa HCD7373 (2021)
2022-12-11 00:00
コメント(0)
作曲と即興のハーモニー ワコ [北ヨーロッパ]

バンドキャンプ・デイリーのジャズ新作の記事を読んでいて、
シェーティル・アンドレ・ミュレリッドというノルウェイのピアニストを知りました。
91年生まれという新世代ながら、ピアノ・ソロやトリオほか、
さまざまなフォーマットのアルバムを出していて、
すでに大きな注目を集める期待の若手のようですね。
北欧ジャズ独特の鋭敏な音楽性を感じさせる人なんですけれど、
片っ端からサンプルを聴いていて、強烈に引き込まれたのが、
シェーティルが参加しているグループ、ワコの20年作。
美しいメロディが引き立つ卓越した作曲能力と、
爆発的なインプロヴィゼーションを繰り広げるフリー・ジャズの演奏力に感じ入って、
こりゃあ、スゴイと、すぐさまオーダーしたんでした。
するとシェーティルご本人からメールがきて、
「申し訳ないけれど、いまツアー中でCDを発送できないんだ。
帰ったらすぐ送るので、しばらく待ってもらえるかな」とのこと。
メールに日本を懐かしむ文面があったので、え?と思ったら、
すでに来日経験があったんですね。
18年にピアノ・トリオで、19年にはこのワコで来日しているじゃないですか。
なんと、ご近所の下北沢でも演奏していたとは。
ワコは、シェーティルが通っていた、
トロンハイムのノルウェー科学技術大学ジャズ科の
学生仲間と結成したグループだったんですね。メンバーは、シェーティルに、
マーティン・ミーレ・オルセン(サックス)、バルー・ライナット・ポウルセン(ベース)、
シーモン・オルダシュクーグ・アルバートシェン(ドラムス)の4人。
作曲と即興の絶妙な調和が、ワコの最大の魅力。
曲はシェーティルとマーティンの二人が書いています。
細分化された現代的なビートで、
推進力のあるグルーヴを生み出すトラックもあれば、
メロディが内包するリズムに対応して複雑なドラミングを聞かせるトラック、
サックスがタンギングをして規則的なリズムをつくるトラックなど、
リズム・アプローチが全曲違うところが、すごくクリエイティヴ。
幾何学的な音列のなかに、美しいメロディの断片が散りばめられていたり、
弦や管が折り重なって、色彩感豊かなハーモニーと立体的なサウンドを構築していて、
そのヒラメキのある楽曲づくりに惹き込まれます。
本作にはゲスト・ミュージシャンが大勢参加していて、
弦楽四重奏、ヴォブラフォン、トランペット、バリトン・サックス、
モジュラー・シンセサイザー、ヴォイスが、それぞれのマテリアルに添って、
絶妙に配置されているところも、聴きどころ。
コンテンポラリーとフリーを横断しながら、
フォー・ビートでオーソドックスなモード・ジャズをやったり、
ストレートなエイト・ビートでジャズ・ロック調に迫るトラックでは、
メンバーがコーラスを聞かせたり、
CDのラスト・トラック(LP未収録)は、なんと!ビバップで、
途中フリーと行き来するなど、その引き出しの豊かさに舌を巻きます。
いやぁ、このバンド・サウンドの豊かさ、スゴイな。
あー、ライヴ観たいなあ。ぜひぜひ再来日してくださーい。
Wako "WAKO" Øra Fonogram OF157 (2020)
2022-07-18 00:00
コメント(0)
未来に開かれたジャズ コマ・サクソ [北ヨーロッパ]
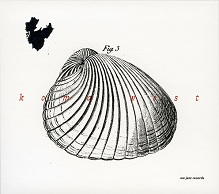
ウィ・ジャズというフィンランドのレーベル、面白いなあ。
年初め、リンダ・フレデリクソンのユニークな作品に感じ入ったんですけれど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-01-23
続き番号でリリースされた、ベルリンで活動するスウェーデン人ベーシスト、
ペッター・エルドのユニットの新作が、これまた輪をかけてユニーク。
このレーベルからは、目が離せなくなりそうですね。
コマ・サクソは、ベース、ドラムスに3管サックスのクインテット。
このメンバーで19年にデビュー作を出しているそうで、そちらは未聴なんですが、
今作はソフィア・イェルンベリのヴォイスを全面的にフィーチャーして、曲により
ピアノ、ヴァイオリンとチェロ、アコーディオン(ペッター・エルドのお母さん!)が
加わった作品となっています。
3分前後の短い14曲が収録されているんですけれど、
ミニマル・アートを思わせるようなアルバムですね。
サックス3管の武骨なリフに、ソフィアのヴォイスが
ソプラノ・サックスのように絡みつくアレンジや、
ギクシャクしたビートとルバートのパートを、巧みに楽曲に構成するなど、
作曲とアレンジに詰め込まれたアイディアが聴きどころ。
曲はどれもしっかりと構成されているんですけれど、演奏には自由度があり、
ビート・ミュージックを展開する曲あり、フリ-・ジャズの展開をみせる曲ありで、
多彩な楽曲に対応する、柔軟な演奏力が発揮されています。
ペッター・エルドはベースだけでなく、
サンプラー、ピアノ、パーカッションも演奏しているんですね。
ヴァイオリンとチェロの二重奏で始まり、ソフィアのヴォイスが絡む
室内楽的な曲など、美しい印象画を観るかのようで、
サウンドトラックにも使えそうな曲が、このほかにもあります。
本作は、ペッター・エルドが育ったスウェーデン西海岸の民謡をモチーフとして
作曲したのだそうで、ミニマルな技法を使った作品でありながら、
どこか牧歌的で親しみやすさをおぼえるのは、伝統的なメロディゆえなのですね。
物語を生み出す楽曲とアレンジ、未来に開かれたアンサンブルが、
新しいジャズの風景を拡げているのを実感させてくれる作品です。
Koma Saxo with Sofia Jernberg "KOMA WEST" We Jazz WJCD41 (2022)
2022-05-23 00:00
コメント(0)
デリカシーに富んだフォーク・ジャズ エリ・ストルベッケン [北ヨーロッパ]

寒い日々が続きますねえ。
「新しい日常」なんぞどこ吹く風で、
あいもかわらぬ、ウォーキング30分+電車50分の通勤生活を送っていますが、
さすがに雪が降ると、早足ウォーキングは足元不安となるので、事故が怖い。
この冬は、東京でもたびたび雪に見舞われているから、なおさらなんですけど、
家で仕事するのはまっぴらなので、「リモート・ワークお断り」を貫いているのです。
今日は家に帰ったら、何を聴こうかなあと考えるのが、
退社間際のルーティンというか、お楽しみですけれど、
寒い毎日にぴったりの、北欧もののいいアルバムと出会えたんですよ。
それがこのノルウェイのフォーク・シンガー、エリ・ストルベッケンの新作。
今回初めて知った人なんですが、ぼくより5つも年上で、
数々の受賞歴を誇るヴェテランなんですね。
父親のエギル・ストルベッケンはノルウェイの著名な音楽家で、
さまざまな民俗楽器を制作・演奏し、作曲活動のほか、
数多くの伝統歌を採集した研究家だったそうです。
親子二代でノルウェイを代表する伝統音楽家となったエリですが、
新作は、デンマークの二人の司祭トーマス・キンゴ(1634-1703)と
ハンス・アドルフ・ブロルソン(1694-1764)が書いた賛美歌を中心に、
古い宗教的な民謡を歌っています。
伴奏を務めるのが、フォーク系のミュージシャンでなく、
ジャズ・ミュージシャンというところが今回の目玉。
ノルウェイはフォークとジャズの相性が良くって、
ジャズのイディオムが素材を壊すことなく、
きちんと引き立てるメソッドをもっているんですね。
以前にも、ここでそんな好作を取り上げたことがあります。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-02-19
ピアノのアンドレアス・ウルヴォを中心に、
ベース、パーカッション、トランペット、フィドルの編成。
アンドレアスがアレンジやプロデュースにも携わり、キー・パーソンのようです。
アンドレアスは、たしか何回か来日してますよね。
エリの凛としたシンギングに、伴奏陣は努めてデリケイトなバックアップに徹しています。
インタールードに移っても、ピアノとトランペットが歌のメロディをなぞったり、
ピアノの分散和音を背景にフィドルがメロディを奏でるなど、
歌のパートと演奏のパートに温度差を作らないようにして、
純度の高いエリの音楽世界に寄り添い続けています。
パーカッションがドラム・キットのシンバル、スネア、タムを使っているようなんですけど、
キックの音が聞こえてこないので、アンサンブルとしてのリズムは作らず、
アクセントを加えることに終始しています。
フィドルは、まるでチェロのような響きを想起させる、悠然としたプレイを聞かせます。
聴いていると、古い賛美歌を題材としているのを忘れるほど現代性に溢れていて、
鳥のさえずりでアルバムを終える聴後感もいいですねえ。
デリカシーに富んだ、ノルウェイのフォーク・ジャズを堪能できるアルバムです。
Eli Storbekken "TIDLØSE TONER" Grappa HCD7378 (2021)
2022-02-16 00:00
コメント(0)
北国のジャズが奏でるパーソナルなサウンドスケープ リンダ・フレデリクソン [北ヨーロッパ]

前回に続いてもうおひとかた、女性バリトン・サックス奏者のアルバムです。
これがソロ・デビュー作という、フィンランドの人なんですが、
すでに数々のバンドでの活躍している人で、
モポやスーパーポジションなど、フィンランドのジャズの新世代グループとして、
10年ほど前から注目を集めていたのだとか。
ぼくは今回初めて知ったのですが、出たばかりのソロ・デビュー作では、
バリトン・サックス、アルト・サックス、バス・クラリネットのほか、
ギターやピアノ、シンセも演奏して、独特の世界を生み出しています。
ジャズというより、シンガー・ソングライター的作風のインスト・アルバムといった趣で、
短編小説を読むような作品の世界に、すっかり取り込まれてしまいました。
リンダのほかは、ローズ、モーグ、プロフェットを弾く鍵盤奏者に、
モジュラー・シンセとモーグを弾く別の鍵盤奏者、ベース、ドラムスの編成。
さまざまなシンセがレイヤーされ、その合間をぬって、
静かに奏でられるピアノの音色は、はかなくも美しく、胸に沁みこみます。
バリトンが咆哮する場面も少しあるものの、
おおむねサックスは、ソフトなトーンで語りかけるように奏でられています。
内省的な楽想に沿って、必要なところで必要な音だけを鳴らしていくサウンドスケープは、
引き算だけで作られているといったアレンジですね。
コンポジションが表現しようとする世界に、
それぞれの演奏者が奉仕するアティチュードが、すみずみまで行き渡っています。
ミュージシャンのエゴをまったく感じさせないところが、
新世代ジャズ・ミュージシャンの作法でしょうか。
音の割れたアクースティック・ギターをぽろんぽろんと弾きながら、
ハミングする曲など、人肌のぬくもりを感じさせるフォーキーな曲では、
北国の家の中でゆらめく、ろうそくの明かりを見る思いがします。
Linda Fredriksson "JUNIPER" We Jazz WJCD40 (2021)
2022-01-23 00:00
コメント(0)
アンビエントR&Bにヒストリーあり エリカ・ド・カシエール [北ヨーロッパ]

うわ~、これは、トロけるなぁ。
去年ココロ射抜かれたジェネイ・アイコやケラーニとおんなじテイストで、
ぼくをトリコにする歌声の持ち主ですね、この人は。
コペンハーゲンから登場した、アンビエントR&Bの新鋭、エリカ・ド・カシエール。
日本のみで出たデビュー作CDは、チェックしそびれていましたが、
4ADに移籍して出した第2作は、冒頭の曲を十数秒聴いて、即買いしましたよ。
90年代のUKガラージを思わせるサウンドにのる、
エリカのコケティッシュなヴォーカルのオープニング、‘Drama’ にヤラれたんですが、
続く‘Polite’ のコンガなんて、ネイキッド・ミュージック・NYCが絶好調だった
00年代のハウスを思い出さずにはおれません。
こちらの好みを見透かされるようなサウンドのリファレンスに、
ちょっとクヤシイ気分にもなるんですけれど、
そこにのるエリカのラップまじりのヴォーカルは、当時はなかったものですよねえ。
そのフロウは、間違いなく現代のアンビエントR&Bの新しさが刻印されています。
アンビエントR&Bは一日にしてならず、ヒストリーありですねえ。
エレクトロニカ、アンビエント、ディープ・ハウス、ジャングルなどを咀嚼したサウンドは、
はかない美しさに富んでいて、クールなサウンドスケープに、
温かな感情が満ち溢れているのが、びんびん伝わってきます。
選び抜かれた音色のデリケイトな質感には、感じ入ってしまいますねえ。
90年代からのさまざまな音楽要素を収斂させてこそ、
この新しいヴォーカル表現が生かされているのを感じます。
ラストの‘Call Me Anytime’ なんて、バックで鳴っているビートは、
まぎれもなくジャングルじゃないですか。
あの凶暴なジャングルが、まさかこんなに静謐なアンビエントと融合するなんて、
あの頃誰が予想しましたかね。
デンマークから出てきた才能というのも、なかなかに新鮮ですけれど、
なんとご両親はベルギーとカーボ・ヴェルデの出身だそうで、
エリカが生まれたのは、ポルトガルなんだそうです。
う~ん、クレオールの香りが漂ってくる話で、ぼくが惹かれるのも当然なのか。
Erika De Casier "SENSATIONAL" 4AD 4AD0354CD (2021)
2021-09-23 00:00
コメント(0)
コペンハーゲンの実験的ジャズ ネゼルホーンズ [北ヨーロッパ]

テナー・サックス奏者のナナ・パイが率いるコペンハーゲンのクインテット、
ネゼルホーンズのセカンド・アルバム。
リーダーのナナ・パイはデンマーク出身ですが、
トロンボーンのペッター・ヘンゼルと
ドラムスのクリストファー・ロステットはスウェーデン出身、
トランペットのエリック・キメスタッドはノルウェー出身、
ベースのヨハネス・ヴァートはエストニア出身と、
北欧各国からコペンハーゲンに集まった才能によるグループです。
グループの核となっているのが、
作曲を担当しているナナ・パイとペッター・ヘンゼルで、
二人とも調性と無調が行き来するコンポジションを書き、
協和と不協和が並列するサウンドスケープを、伝統的なジャズな語法で演奏しています。
即興性は強いけれど、フリー・ジャズとは言い難い構造のあるコンポジションを演奏する、
実験性の高いグループで、このビミョーな案配が、めちゃ好みだなあ。
タイトル曲の冒頭でナナが、テナー・サックスの無伴奏ソロを吹くんですが、
不協和音やノイズを駆使しながら、けっして破調になることなく、
抑制の利いた即興演奏となっているところが聴きものです。
ナナの独特なトーンは、やっぱ強烈な個性があるなあ。
坂田明が18年12月に渡欧ツアーした時、彼女と共演したんですよね。
北欧ジャズらしいダークなトーンのコンポジションは、
余計な抒情を挟み込んでこない、無糖コーヒーの味わいにも似て、
とても魅力的です。
Nezelhorns "SENTIMENT" Barefoot BFREC066CD (2021)
2021-05-24 00:00
コメント(0)
オヤジ殺しの悩殺歌唱 エレン・アンデション [北ヨーロッパ]
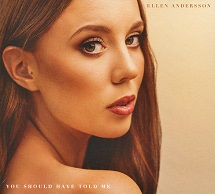
エレン・アンデションは、母国スウェーデンのほか、
デンマークのヴォーカル・グループ、トゥシェのメンバーとしても精力的に活動する
若手ジャズ・ヴォーカリスト。
91年生まれだから、この人もまた新世代ジャズの一員ですね。
レパートリーは新旧スタンダードで、古いところではエリントンの‘Just Squeeze Me’、
ホーギー・カーマイケルの‘I Get Along Without You Very Well’、‘Too Young’。
新しいところではランディ・ニューマンの‘You've Got A Friend In Me’ あたりか。
レノン=マッカートニー作の‘Blackbird’ は、いまさら新しいとはいえないけれど。
こうしたスタンダード中心のジャズ・ヴォーカリストに、
あまり興味のない当方でありますが、
この人の粘っこい歌唱には、耳が反応しました。
みずみずしい若さと妖艶さをあわせ持つ個性は、抗しがたい魅力があります。
オープニングの‘You Should Have Told Me’ での、
奔放に暴れるドラミングやトランペット・ソロは、歌伴にしては遠慮がなくスリリングで、
ぐいぐいと惹きつけられました。
ちょっと掠れ気味のハスキー・ヴォイスで歌い始める、
ルグランの名曲‘Once Upoan A Summertime’ も、洒脱な味を出していて、
エレンの個性がよく発揮されています。
抒情派だけど純情ではなく、ちょっとハスッパな小粋さを持ち合わせているのが、
エレンの持ち味かな。スウィンギーなグルーヴを生み出すリズムのキレもあるし、
アーシーなブルース・フィーリングが、自然とにじみ出てくるところも、いい。
こういう個性って、若い人が出そうとすると作為がつきまとうものなんだけれど、
この人にはそんなケレンがまったくないから素直に聞けて、耳に馴染みます。
スキャットやハミングも器楽的になるのではなく、
そっとつぶやくようなキュートな歌唱の延長線上に出てくるところが、
肩ひじ張らずに聞けるところ。う~ん、オヤジ殺しの悩殺歌唱だな。
弦楽四重奏を加えたバックも好演していて、
‘The Thrill Is Gone’ のインタールードの凝ったアレンジを施したパートなど、
アグレッシヴなピアノ・ソロを含め、手に汗握る場面多し。
日一日と冬に向かう寒さが増す今日この頃、ナイトキャップに絶好の1枚です。
Elle Andersson "YOU SHOULD HAVE TOLD ME" Prophone PCD204 (2020)
2020-11-11 00:00
コメント(0)
モノマネなんかいらない クティマンゴーズ [北ヨーロッパ]
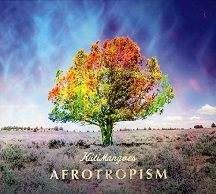
デンマークのアフロ・ジャズ・バンド、クティマンゴーズの3作目となる新作です。
ブルキナ・ファソ人歌手をフロントに立てた過去2作も良かったけれど、
白人メンバー6人のみで、アフリカ音楽のリズム探究を深めた本作、
会心の出来じゃないですか。
ぼくがクティマンゴーズを買っているのは、アフリカ音楽のモノマネに終わっていないから。
逆に、ぼくがあまたあるアフロビートそっくりさんバンドを評価しないのは、
完コピーしただけの音楽なんて、何の価値もないと考えているからです。
ビートルズ・バンドと同じようなもので、アマチュアの愉しみとしてならわかるけど、
それをレコードにして金をとるってのは、プロの音楽家として、どうなのよと。
こういうと、モノマネ芸を否定するのかとか言われるんですけれど、
そもそも「モノマネ芸」になってないじゃないですか。
「芸」になってない、ただのモノマネだから批判してるんです。
それを強く感じたのが、
アンティバラスの“WHO IS THIS AMERICA?” が評判になった時です。
えぇ~、みんなあれを絶賛しちゃうんだと、かなり呆れていたんですけれども、
そんなのはぼくだけなのか、その後もアコヤ・アフロビート・アンサンブルや
マイケル・ヴィール&アクア・イフェなど、
雨後のタケノコが続くのに、ウンザリしてました。
贋作は時に本物を超えるともいいますけれど、だから何?
憧れや影響を血肉化して、自分たちの音楽を作る人にしか、ぼくは興味をもてません。
このクティマンゴーズは、西アフリカ音楽に大きな影響を受け、
アフリカのリズム構造を理解してさまざまな民族のメロディを取り入れる一方、
3管バンドの管楽器の鳴りには、北欧ジャズのハーモニーの特徴が浮き彫りとなっていて、
アフリカとヨーロッパそれぞれの良さが十二分に活かされたバンドなんですね。
彼らがアフリカのクロス・リズムを学んだのは、
バラフォンの左手と右手が生み出すポリリズムからだそうで、
そのアプローチは、スウェーデン人ジャズ・ドラマーのベンクト・バーリエルが
クリエイトしたアフロ・ジャズと共通するものがあります。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-01-14
そんなポリリズムが生かされたオープニングの‘Stretch Towards The Sun’、
グナーワのカルカベのリズムをカクシ味にした‘A Snake is just a String’、
南アのホーン・アンサンブルのソリを思わせる‘Call of the Bulbul Bird’、
ギターがカマレ・ンゴニのようなフレーズを奏で、
ペンタトニックのメロディがまるでバンバラ民謡みたいな‘Thorns to Fruit’ などなど、
アフリカ音楽を研鑽してきた跡が、そこらじゅうに点在しています。
‘Money is the Curse’ でのアフロビート解釈なんて、
モノマネ・バンドの足元にも及ばないサウンド構造の解体と再構築の深さがあります。
そんなアフリカ音楽愛にもとづいた深い知識と、
バリトン・サックスとトロンボーンの厚みのある合奏などにみられる肉感的な演奏が
あいまって作り出されるサウンド、大いに支持したいですね。
KutiMangoes "AFROTROPISM" Tramp TRCD9083 (2019)
2019-10-08 00:00
コメント(2)
ヨイクの伝統の呪縛から放たれて ヴィルダ [北ヨーロッパ]

ヨイクのシンガーとアコーディオンの女性デュオのアルバム。
ヨイクをコンテンポラリーなサウンドで歌うアーティストは、
アリ・ボイネはじめいろいろ聞いてきましたけれど、
どれも<極北のエスニック音楽>といった作り物ぽさが拭えなくて、
二の足を踏んできたのが正直なところ。
でも、この二人はちょっと印象が違いました。
まず、ヨイクのミスティックな面を誇張していないのが、いい。
ヨイクが持つ霊性を過度に演出することなく、
音楽に生命感が宿っているのが自然に感じ取れます。
シャーマニズムといったサーミ人の伝統文化から抜け出た現代から、
ヨイクをリサイクルしているようなニュアンスさえ感じさせるその作法には、
先人たちのワールド・ミュージック的な語法から離れた自由さを感じます。
ヨイクの特殊性を強調したサウンドを組み立てるのではなく、
フィンランドのアコーディオン音楽と融合させながら、
そのなかにヨイクの即興性を浮かび上がらせる二人のやり方は、
伝統の継承とは異なる、現代性に富んだ方法論を獲得したんじゃないでしょうか。
歌とアコーディオンの二人を中心に、手拍子やパーカッション、
ビートボックスなどのゲストを多数迎えているように、
伝統の呪縛から放たれたそのサウンドには解放感があり、
風通しが良く、すがすがしさを覚える新鮮さが得難いですね。
Vildá "VILDALUODDA / WILDPRINT" Bafe’s Factory/Nordic Notes MBA030 (2019)
2019-06-24 00:00
コメント(0)
抑えの美学 エイヨルフ・ダーレ・シーエン・ジャズオーケストラ [北ヨーロッパ]

これまであまり関心を向けてこなかったジャズ・オーケストラの作品が、
がぜん面白く感じられるようになったのは、
ジャズが「アンサンブルの時代」を迎えた象徴でもあるんでしょうね。
マリア・シュナイダー・オーケストラに耳目を集めるようになってだいぶ経ちますけど、
最近では、このノルウェイのジャズ・オーケストラが気に入りました。
エイヨルフ・ダーレというピアニストが率いる、シーエン・ジャズオーケストラ。
シーエンとは、エイヨルフが住むノルウェイ南部の都市で、
ノルウェイ国立音楽大学の准教授でもあるエイヨルフが、
大学のあるオスロまで通勤する退屈な時間を使って作曲したという作品です。
タイトルの『通勤者レポート』とは、そういうわけなんですね。
車窓に広がる冬の空模様が流れ行く様子を、
描写するかのような映像的なオープニングは、
シーエンからオスロへの電車からの眺めでしょうか。
イントロのクラシカルなピアノのタッチから、
北欧ジャズらしいサウンドが横溢しますけれど、
続く2曲目は、オリエンタルな旋律を細かく動かしていくアレンジで、
がらりと雰囲気が変わります。
オリエンタルなメロディばかりでなく、アコーディオンを起用するような音色の選択、
優雅なワルツを取り入れたリズム処理など、
エキゾティックに響く要素をあちこちに散りばめながら、
あくまでもスパイスにとどめた、抑制の利いた作編曲がすばらしいですね。
美しく整ったオーケストレーションで聞かせるクラシカルなトラックもあれば、
幾何学的なラインでアグレッシヴに攻めるトラックもあるという、
バランス感覚のある作曲と、抑えの利いた編曲が豊かな色彩感を生み出し、
音楽に風格をもたらしています。
Scheen Jazzorkester Eyolf Dale "COMMUTER REPORT" Losen LLOS204-2 (2018)
2019-02-24 00:00
コメント(0)
ラトヴィアの古代と未来 ラタ・ドンガ [北ヨーロッパ]

ラトヴィアといえば合唱。
歌の宝庫で知られるお国柄ですけれど、
ラトヴィアの夫婦と娘2人のラタ・ドンガも、
3世代にわたって歌い継いできた民謡をレパートリーにしているといいます。
フィンランドのカンテレによく似たラトヴィアの民俗楽器、
クアクレの清涼な弦の響きを生かしつつ、
ピアノ、ベース、エレクトロほか、さまざまな楽器を多彩に取り入れています。
プロダクションがよく作り込まれているうえに、デリケイトな仕上がりで、
デビュー作にしてこの完成度の高さは、スゴいですね。
クアクレは、お父さんのアンドリス・カプストが弾いていますが、
プログラミングやエレクトロを担当しているマルチ奏者のウギス・ヴィティンシュが、
サウンドづくりのキー・パーソンのよう。
ラトヴィアの古代と現代だけでなく、ラトヴィアと世界をつなごうという音楽性は、
インド南東部のテルグ語とラトガリア語をミックスしたグループ名にも、
はっきりと表れています。
なんでも、「ラタ」は、テルグ語で女性を象徴する植物だそうで、
「ドンガ」はラテン語の砦を意味し、神と霊の家を象徴するラトガリア語とのこと。
古代インド・ヨーロッパ語族バルト語派の広がりをさかのぼる試みは、
インドのサロード、西アジアのダフ(枠太鼓)、
中東のダルブッカをフィーチャーしたサウンドに表明されていて、
アンドリスは、ラトヴィアの伝統音楽に影響を及ぼしてきたスラヴ、インド、
中東の音楽の要素を露わにしようとしています。
こんな学究的なテーマをポップ・ミュージックとして成立させるのは、
容易なことではないんですけれど、これは稀有な成功作ですね。
4人のア・カペラのコーラスは、深みのある荘厳な響きを持ち、
力強いシンギングからは北の生命力が溢れ出ます。
ラトヴィアの古代と未来を鮮やかに示してみせた野心作です。
Lata Donga "VARIĀCIJAS" Lauska CD079 (2018)
2018-11-20 00:00
コメント(0)
アフリカ音楽を体得した初のジャズ・ミュージシャン ベンクト・バーリエル [北ヨーロッパ]

こりゃ、驚き。
ベンクト・バーリエルの87年作“PRAISE DRUMMING” が、
オリジナル原盤所有のスウェーデンのレコード会社から、まさかのCD化。
「ベングト・ベルガー」と書かれることがもっぱらな
ベンクト・バーリエルは、スウェーデン人ジャズ・ドラマー。
二十代の時、インド音楽を学びたくて、65年に北インドをヒッチハイクしてタブラを習い、
68年には南インドへ出かけ、ムリダンガムを修得したという無類の民俗音楽好き。
70年代に入るとアフリカ音楽へ関心を寄せ、75年から77年にかけてガーナに滞在し、
カクラバ・ロビからコギリ(木琴)を学んだという、ユニークな経歴のジャズ・マンです。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-10-01
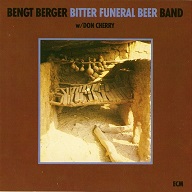
ベンクトがECMから82年に出した“BITTER FUNERAL BEER” は、
カクラバ・ロビ直伝によるロビ人の葬儀音楽をもとにジャズ化するという、
衝撃的なアルバムでした。
それまで、いわゆる「アフロ・ジャズ」と称するジャズ・ミュージシャンによる
アフリカ音楽もどきのでたらめぶりにウンザリしていたので、
非アフリカ人による初の本格的なアフリカン・ジャズ作品となった
本作には目を見開かされ、大カンゲキしたものです。
なんせベンクト・バーリエル登場以前のアフリカン・ジャズは、
「まがいもののアフリカ音楽」だらけでしたからねえ。
ジョン・コルトレーンからシカゴ前衛派に至るまで、
60年代にアフロ回帰の思想で産み落とされた作品は、
すべて観念上の想像の産物にすぎませんでした。
アート・ブレイキー、ランディー・ウェストン、トニー・スコット、渡辺貞夫など、
アフリカ人ミュージシャンと共演した人も一部にはいましたが、
アフリカ音楽の構造やポリリズムを理解し、体得した人は、皆無でした。
それだけに、この“BITTER FUNERAL BEER” は、ほんとに画期的だったんですよ。
“BITTER FUNERAL BEER” の録音にあたって、
ベンクトはメンバーのスウェーデン人ミュージシャンたちに、
ガーナで学んだ伝統音楽のリズムやアフリカ音楽の曲構造を、
徹底的に教え込んだんでしょうね。
そういえば、ベンクトが78年に制作したEPに、
カクラバ・ロビのバラフォンのデモ演奏があり、
異なるリズムによる左右の手の演奏法を理解する、格好の教則レコードとなっていました。
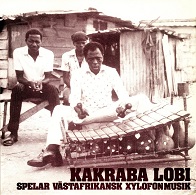
非アフリカ人だけで、
これほど本格的なアフリカン・ジャズを作り上げたことに感服しますけれど、
単に模倣に終わるのではなく、北欧ジャズならではの管楽器による高度な即興演奏もあり、
ワールド・ジャズともいうべきその完成度の高さは、いまなお新鮮です。
『アフロ・ポップ・ディスク・ガイド』に選盤されていたのも、至極当然ではありましたが、
音楽の中身をまったく理解できていないジャズ評論家のテキストにはがっくりでした。
今回30年ぶりとなるCD化で、
ひさしぶりに“PRAISE DRUMMING” を聴き直しましたけれど、
うん、やっぱりこれも傑作ですね。
アフリカ音楽の持つクールネスが、北欧ジャズのクールネスと絶妙に融合していますよ。
“BITTER FUNERAL BEER” をさらに発展させて、
アフリカ音楽ばかりでなく、インドネシアのバリのメロディをモチーフとするなど、
オリエンタルな要素も加えて、さらに魅力が倍化しています。
日本では名前すらまともに書かれないぐらいの人なので、
ご存じない方が多いのかもしれません。ぜひ聴いてみてください。
Bengt Berger & Bitter Funeral Beer Band "PRAISE DRUMMING" Dragon DRCD449 (1987)
Bengt Berger "BITTER FUNERAL BEER" ECM 839308-2 (1982)
[EP] Kakraba Lobi "SPELAR VASTÄFRIKANSK XYLOFONMUSIK" Caprice no number (1978)
2018-01-14 00:00
コメント(0)
エストニアの祝祭感 トラッド。アタック! [北ヨーロッパ]

トラッド方面は、できるだけ歌の素の味を愉しみたいというキモチが強いので、
トラッド・ロックは苦手です。クラブ・マナーなエレクトロ仕立てとか、
プログレ方面にサウンドが向かうのも、御免こうむりたいですね。
ドラムスが入ると、ヤボったくなると思ってるもんで、
よほどセンスのよい使い方をしていない限り、満足できないんですよ。
昔から、フェアポート・コンベンションすらダメという、
狭い器量の持ち主なもんで、すんません。
で、エストニアのこの3人組。
ロック・バンドと変わらないドラム・セット、かき鳴らし系アクースティック・ギター、
残る女性がバグパイプ、口琴、ソプラノ・サックス、ホイッスルを持ち替えて演奏するという
変則トリオで、そっからして、自分向きじゃないなと思ってたんですが、
意外や意外、面白かったです。
エレクトリックな意匠がないところも個人的嗜好に合いましたけど、
半世紀ほど昔のエストニア女性が歌ったアーカイヴ音源をサンプリングして、
曲を組み立てるというアイディアが面白い。
それらの音源は、エストニアの伝統的な歌い手によるもので、
メンバーのギタリストのお婆さんの録音も使われています。
1曲目のお婆さんが唱えるバター作りの呪文が面白くって、
この曲のヴィデオがYoutubeにもあがっていますけど、とってもユニークな仕上がりです。
ほかにも、治癒のための歌など、
メロディのない呪文めいた語りのサンプル音源を練り込んでは、
ユニークなサウンドづくりをしていて、聴きものです。
北欧的なダークさがなく、解放感のあるダンス・ミュージックが中心で、
リズムが多彩なところにも興味をひかれました。
Trad.Attack! "AH!" Nordic Notes NN068 (2015)
2017-07-04 00:00
コメント(0)
ジャズ新時代を先取りしていたエスビョルン・スヴェンソン E.S.T. [北ヨーロッパ]

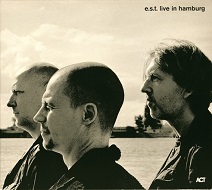
スウェーデンのエスビョルン・スヴェンソン・トリオを継ぐかのような新世代ジャズが、
最近目立つようになってきたと思いませんか。
UKのママル・ハンズとか、日本のフォックス・キャプチャー・プランとか。
エスビョルン・スヴェンソンといえば、
キース・ジャレットの影響下のピアニストという立ち位置から、
一歩も二歩もハミ出たポスト・ロック的なサウンド・メイキングを成し遂げた人として知られ、
大胆なリズム処理とクラシックのハーモニーを融合したジャズとして、
一時期注目を集めましたよね。
ぼくもその割り切りのいい、わかりやすい迫力に興味はおぼえつつ、
いかにも白人的な音楽性というか、北欧ジャズらしいクラシカルな美しさは、
心底から惚れ込めるタイプのジャズではありませんでした。
正直言って、ECM作品にありがちな、アタマで感心はしても、
カラダは悦ばないタイプのジャズの典型というか。
そのため、従来のジャズ観をはみ出す新鮮さを感じつつも、
その後まったく聴かないままとなっていたんですが、
10年ぶりに聴き返してみたら、
あれ? いいじゃん!と、聞こえ方ががらり変わってしまったのに、ビックリ。
ライヴ盤のグルーヴ感たっぷり、ダイナミックな演奏に、カラダの芯を揺さぶられました。
昔聴いた時は、昂揚感あふれる演奏にも、
こういうのが好きな人はタマらないんだろうなという、醒めた感想を抱いていたのに、
どうしたことでしょう。素直に盛り上がれちゃって、ちょっと自分でも不思議な気分。
ママル・ハンズ、ゴーゴー・ペンギン、フォックス・キャプチャー・プランのような、
少女趣味なおセンチ・メロディに馴らされたせいなのかなあ。
どうもブルー・ノート育ち(レーベルにあらず、スケールの方ね)の人間には、
クラシカルなメロディの美しさって、奥行きがないというか、
深みがないように捉えがちなんですけど、
それって、昔ながらの黒人ジャズ好きの思い込みというか、
偏見にすぎませんよね。あらためて反省させられました。
現代のジャズがグローバル・ミュージックとして多角的に拡張している今、
エスビョルン・スヴェンソンを聴き直すことによって、
ジャズの聞こえ方が変わるという、いみじくもフレッシュな体験となりました。
E.S.T. (Esbjörn Svensson Trio) "SEVEN DAYS OF FALLING" ACT Music ACT9012-2 (2003)
E.S.T. (Esbjörn Svensson Trio) "LIVE IN HAMBURG" ACT Music 2CD6002-2 (2007)
2016-08-26 00:00
コメント(0)
故郷カレリアの伝統に立ち返って ヴァルテイナ [北ヨーロッパ]

ずいぶん聴いてなかったなあ、ヴァルテイナ。
ぼくがこのグループを知ったのは、ご多分にもれず、94年の“AITARA”。
言わずと知れたヴァルティナの代表作で、
フィンランドの伝統音楽を大胆にポップ化した、一大名盤でしたよね。
伝統性をしっかりと保持しながら実験性を高めていくという彼女たちの方向性は、
このあとも続いていくわけなんですが、“AITARA” を凌ぐアルバムは現れませんでした。
インダストリアル・ビートを取り入れたりと、野心的な意欲は買いたいんだけれど、
すんません、ぼくにはトゥー・マッチです、みたいなアルバムがずっと続いたもんで。
そんなわけで、最近はすっかり遠ざかっていたヴァルティナなんですが、
故郷カレリアの伝統に立ち返ったという新作、ライスから日本盤も出て評判がいいというので、
試聴してみたら、あら、びっくり。
リフレッシュされたヴァルティナ・サウンドが飛び出てきて、目を見開かされちゃいました。
まず、サウンドが一新。アクースティックなサウンドにがらりと変わりましたね。
カンテラやニッケルハルパといった伝統楽器の響きをメインに打ち立て、
かつてのエレクトロやファンクの要素はぐっと後退しました。
伝統様式の輪唱を聞かせたり、サーミのヨイクもあるなど、
北欧の音楽文化の古層に触れる試みを行う一方で、
ヴァルティナ流のポップなはじけぶりはこれまでどおり健在で、
速射砲コーラス&掛け合いがたっぷりと楽しめます。
なんでも、ロシア領カレリア地方を訪問したことをきっかけに、
自分たちのルーツに立ち返り、この作品を制作したのだそうで、
うん、この方向性、絶対支持だな。
さっそく買ってじっくり聴こうと思ったら、ライス盤はライセンスのドイツ盤。
わ~ん、オリジナルのフィンランド盤じゃないんですかあ。
しかたなくフィンランドから取り寄せ、えらい時間がかかちゃいましたが、ただ今絶賛愛聴中です。
Värttinä "VIENA" KHY Suomen Musiikki Oy KHYCD075 (2015)
2016-02-18 00:00
コメント(0)
フィンランドの昭和歌謡インスト・バンド ダリンデオ [北ヨーロッパ]

こりゃあ、おもしろい。
エキゾティックなメロディに、サスペンス映画のサウンドトラックを思わせるサウンド。
スウィング・ジャズあり、サーフ・ギターあり、ツイストあり、スカあり、クレズマーありの、
モッドなセンスたっぷりの演奏はまがまがしさイッパイで、
なんなんだ、この連中は!とCDに飛びついちゃいました。
ダリンデオはフィンランドのバンドなんですと。へ~え。
シネマティック・ジャズを自称しているそうで、なるほど聴けばナットクですね。
フィンランド映画といえば、アキ・カウリスマキ監督がいますけど、
アキの作風にも通じるところがあるようなないような。
アルバム・タイトルのカッリオは、ヘルシンキ市内にあるブティック、カフェ、レストランが立ち並ぶ
人気の場所だそうです。その街をテーマにした彼らのインストゥルメンタル・ミュージックは、
どこか懐かしい昭和の匂いもする歌謡サウンドをも思わせます。
じっさい彼らは、フィンランドの50~60年代のポピュラー・ミュージックから
インスパイアされているというので、昭和歌謡流れる映画音楽に近いものを感じさせるのも、
あながちハズレではなさそう。
徹底したラウンジー・タッチの演奏はよくアレンジされていて、
これは「ジャズ」ではなく、無国籍インストゥルメンタル・ミュージックでしょうね。
メンバーはいずれもジャズの素養もあるプレイヤーなので腕は確かです。
粋なアイディアに富んだサウンドに、スノビズムを感じさせないマジメな演奏姿勢は好感が持てます。
Dalindèo "KALLIO" KHY Soumen Muiikki KHYCD51/5053105560721 (2013)
2014-04-29 00:00
コメント(2)
北欧のポリフォニー スデン・アイカ [北ヨーロッパ]

真冬にぴったりの北欧のポリフォニー。
結成10周年を迎えるというフィンランド女性4人組のスデン・アイカの新作です。
美しいコーラスばかりでなく、逞しい地声を生かしたワイルドな歌唱を聞かせたり、
パーカッシヴなヴォイス・パフォーマンスを繰り広げたりと、
幅広いヴォーカル・ミュージックの表現を持つグループです。
新作は、コーラス・ワークの生のエネルギーを見事に封じ込めた会心作となりました。
サブ・タイトルにライヴと謳われていますが、観客を入れずに録ったもので、
彼女たちのパフォーマンスの実力の高さが示されています。
最初は美しいコーラスで始まる曲も、途中から地声が混じっていくと、
歌の表情がぐっと肉感的になっていきます。
地声どおしが激しくかけあう曲など、まるで口げんかしているみたいで、ドキドキしてしまいますね。
このなまなましさが彼女たちの魅力でしょうか。
無伴奏曲のほか、カンテレや笛などの伝統楽器を使った曲もあり、
フィンランドらしい極北のサウンドをたっぷりと味わえるところもまた魅力です。
彼女たちが歌うのは、フィンランド人の心のふるさとといわれるカレリアの伝承文化。
歌詞の多くは、カレリア地方に残っていた民話をもとに編まれた叙事詩カレワラから採られています。
スデン・アイカの立ち位置は、ポップに向かいすぎたヴァルティナを
もう一度民俗的な地平に揺り戻したところにあるのかもしれませんね。
フィンランドの古謡を煮詰め、蒸留して純化したエッセンスを、
民俗性と芸術性の両面からバランスよく表現してみせた傑作です。
Suden Aika "LAITURILLA : LIVE AT SISSOLA" Laika 3510298-2 (2013)
2014-01-31 00:00
コメント(0)
シンと冷えた冬の夜に ハイディ・シャルヴァ [北ヨーロッパ]
寒い、寒いと騒いでみたところで、季節は変わっちゃくれないので、
こういう時こそ、北欧の音楽を聴きましょうかね。
しんと静まった深夜に、アツアツの生姜入り紅茶を飲みながら聞いている
ノルウェイの女性シンガー、ハイディ・シャルヴァの新作。
一応ジャズにカテゴライズされているハイディですが、
いわゆるジャズ・ヴォーカル的な唱法はまったくしない人。
ウイウイしい声とストレイトな歌いぶりは、トラッドやフォークを歌うのに向いていて、
伝統歌とオリジナル曲を半々とした今回の新作は彼女にぴったりです。
静謐ながら耽美すぎない曲の良さを引き立てるように、
クリアーなハイディの歌声がリリカルな詩情を紡いだアルバム。
ピアノ、ベース、バリトン・サックスの3人のバックも、
最小限にして効果的な音を残していきます。
バリトン・サックスとユニゾンでリルティングを聞かせる短い曲や、
メンバーの男性たちとリルティングした曲を交えているのが、とてもいい感じ。
ジャズの語法を用いずに伴奏を付けるところが好感を持てます。
ノルウェイにはこういうフォーク・ジャズというか、
トラッド・ジャズみたいなジャンルがあるんでしょうか。
以前、ノルウェイの伝統歌をジャズに料理したダーグ・アーネセン・トリオを
ずいぶん愛聴したものですが、このハイディ・シャルヴァも手放せない一枚となりそうです。
Heidi Skjerve "VEGEN ÅT DEG" Øra Fonogram OF036 (2012)
2013-02-19 00:00
コメント(0)
秋の夜のお供 ヘッレ・ブルンヴォル [北ヨーロッパ]
今年の秋の夜長の愛聴盤は3枚。
麗しい女性の歌もの2枚のうち1枚は、ルーシー・ファベリーの60年頃のシーコ盤。
名手フリオ・グティエーレスの伴奏で歌った極上ボレーロ集を、
エル・スール・レコーズが盤おこしとは思えない音質でCD-R化してくれました。
これがなんとも美味で、う~ん、ジャジー。
ボレーロをジャズぽいフレージングで歌うところは、ルーシーの得がたい個性ですねえ。
ルーシー・ファベリーは、今年になってもう2回も話題に取り上げたのでこのくらいにして、
今回はもう1枚のノルウェイの女性ジャズ・ヴォーカリスト、ヘッレ・ブルンヴォルのお話。
北欧のジャズ・ヴォーカリストというと、カーリン・クロッグやモニカ・セッテルンドを思い出しますけど、
案の定というか、ヘッレもこの二人に影響を受けているそうです。
でもヘッレは大先輩の二人とは持ち味が違って、
もっとインティメイトな雰囲気を感じさせる歌い手さん。
ジャズCDショップのコメントに、「クールで透明感あるヴォーカル」とかありましたけど、
北欧のシンガーという先入観で、ロクに聴きもせずにテキトーに書いたんですかね(怒)。
ふんわりと温かな歌い口がこの人の持ち味で、「クール」とは正反対の個性。
優しく隣に寄り添ってくれるかのような、柔肌のぬくもりが伝わるヴォーカルです。
メロディを素直に歌うところも好ましく、しっとりと歌うスタイルがワタクシ好みであります。
このアルバムはヘッレの2作目で、ギター・トリオをバックに歌ったもの。
全曲オリジナルの英語曲で、ヘッレの書いた1曲以外は、
すべてギタリストのハルヴァート・カウスランドとヘッレの共作。
ギタリストのハルヴァート・カウスランドは、歌伴らしく抑えたプレイでヘッレの歌に寄り添いつつ、
随所できらりと光るコード・ワークやソロを聞かせ、ジャズ・ギター・ファンの耳をそばだてます。
ここひと月くらいこのアルバムを聴きながら、この味わいって誰かに似てるなあと思って、
誰だっけとずっと考えていたんですけど、ようやくナンシー・ハーロウだと気付きました。
そういえばナンシー・ハーロウも、ジャック・ウィルキンスのギター・トリオを
バックに歌ったアルバムがありましたね。えーと、79年のオーディオファイル盤だっけ。
秋の夜のリラックスした時間に、最高のお供となってくれるアルバムです。
Helle Brunvoll "YOUR SONG" Prophone Norwegian Jazz PCD127 (2012)
2012-10-04 00:00
コメント(2)
ノルウェイのア・カペラ エペレモイア・ソングラグ [北ヨーロッパ]
全編ア・カペラのアルバム、なんていうと地味に思われるかもしれませんけど、
曲ごと表情の異なるカラフルな内容に、一気に引き込まれてしまいました。
エペレモイア・ソングラグと読めばいいのでしょうか。
ノルウェイのア・カペラ女声三重唱のデビュー作です。
トラッド・シンガーと二人のジャズ・ヴォーカリストから成るグループで、
2曲を除いて全曲トラディショナルとクレジットされたレパートリーを聞かせてくれます。
伝統歌集といっても、コンテンポラリーな感覚の北欧トラッドといった仕上がりで、
高度なハーモニーと洗練されたアレンジを施したア・カペラ集となっているんですね。
いかにも北欧らしい純度の高い頭声中心の発声で、
妖気を漂わせる4曲目など、マジカルな魅力にゾクリとさせられます。
リード・シンガーの後ろで、喉歌でリズム楽器や伴奏楽器代わりの効果音を務めたりと、
スリリングかつ実験的なインプロヴィゼーションをまじえながらも、
ユーモアのある3人の歌いぶりには温かみがあって、親しみが持てます。
クアルテート・エン・シーの魅力にも相通じるように思いますね。
ストーリーテリングの楽しさもあり、語り物としての興味もそそられるところですけど、
ノルウェイ語では、残念ながら歯が立ちません。
そのかわり音楽的な興味としては、ブルガリアの女声合唱や、
ホーミーが現れてもおかしくないような場面が出てきてハッとさせられたり、
マレウレウのウポポを思わせるようなところもあったりと、
興味のつきないアルバムとなっています。
ノルウェイにはクヴェディングと呼ばれる伝統的なア・カペラのスタイルがありますけれど、
3人のア・カペラは、クヴェディングを現代化させたものといえるのかもしれませんね。
Eplemøya Songlag "EPLEMØYA SONGLAG" Norcd NORCD1091 (2010)
2011-06-10 00:00
コメント(0)
北欧のフォーキー・ロマネスク・ジャズ ダーグ・アーネセン [北ヨーロッパ]
去年の年末から、なんだかんだ言いながらよく聴いている、
ノルウェイの人気ジャズ・ピアニスト、ダーグ・アーネセンのノルウェイ曲集の第3弾。
基本はピアノ・トリオでも、半数の曲でトランペットのパレ・ミッケンボルグが参加しています。
「なんだかんだ言いながら」というのは、はじめ聴いた時、そのメランコリックな牧歌調に、
なんだこのヌルいジャズは? 最近ハヤリの女子ジャズか?と、
ソッコー売却予定の棚に投げ込んでしまったからなんですね。
ところが、仕事のイザコザで心身共にくたびれきって帰ったある夜、ふと思いついて聴いてみたら、
センチメンタル過ぎると感じた旋律が、心にじんわりと染み渡り、
ダーグがゆったりと紡いでいく耽美的なメロディー・ラインに、
すっかり疲れが解きほぐれていったのでした。
「癒し」なんて言葉、好きじゃないのであまり使いたくないんですけど、
疲れきってなーんにも考えたくない時など、このアルバムを鳴らしてぼけーっと聴いていると、
ゆったりと温泉に浸かっているように心が落ち着き、ささくれだった気持ちも回復していきます。
パレの抑えの効いたミュート・トランペットも、ダーグの詩情豊かな世界に陰影を付け、
そのかすれた音色が、コクのある芳醇な味わいを醸し出しています。
バラードばかりでなく、リズムのエッジをたて、ビートボックスをフィーチャーした曲もあったりして、
アルバムがリリカルに流れすぎないよう、適度なアクセントを付けているところもいいですね。
最初は「女子ジャズ」とか悪口言っときながら、
今では「北欧のフォーキー・ロマネスク」なぞと言ってるんだから、イイカゲンなもんです。
仕事で疲れた夜には、いまや手ばなせない一枚となりました。
Dag Arnesen Trio "NORWEGIAN SONG 3" Losen LOS101-2 (2010)
2011-03-08 06:38
コメント(2)




