ブラジルと出会ったドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者 ヘンドリック・モウケンス [西・中央ヨーロッパ]
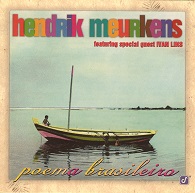

20年ぶり(?)くらいに聴き返したドイツ人ジャズ・ハーモニカ奏者、
ヘンドリック・モウケンスのブラジリアン・ジャズ・アルバム。
ブラジリアン・フュージョンと言ってもいい内容なんだけど、
「フュージョン」というタームを使うと、
どうも外国人がやるパチモンみたいなニュアンスがぬぐえないので、
あえていうならブラジリアン・スムース・ジャズかな。もっとイメージ悪い?
99年にコンコード・ピカンテから出たこのアルバム、
イヴァン・リンスをゲストに迎え、ロメロ・ルバンボ(ギター)、テオ・リマ(ドラムス)、
クラウジオ・ロジチ(フリューゲルホーン)といった名手を揃え、
サンバ、ボサ・ノーヴァ、バイオーン、ショーロのオリジナル曲を中心に聞かせます。
カヴァーはイヴァン・リンスの2曲、ジョビンの3曲にマット・デニスの ‘Angel Eyes’。
キーボードがべたっとコードを鳴らすところは難ありだけど、鋭いハーモニカと、
ふくよかなトロンボーンやフリューゲルホーンの響きが組み合わされて、
豊かなサウンドを生み出しているところが、いいんだな。
ぼくはこのアルバムで初めてヘンドリク・モウケンスを知ったんですけれど、
もとはバークリー音楽院でヴィブラフォンを学んだヴィブラフォン奏者。
このアルバムでも、3曲でヴィブラフォンを演奏しています。
トゥーツ・シールマンスを知って、独学でクロマチック・ハーモニカを修得し、
その後ブラジル音楽に熱を入れ、80年代初めにはリオへ移住して、
ブラジルの多くのジャズ・ミュージシャンとプレイして
人脈を作ったという変わり種なんですね。
ドイツ帰国後はラジオやテレビなどのスタジオ・ミュージシャンとして活動し、
90年代にコンコードと契約して、ニュー・ヨークへ進出します。
ヘンドリック・モウケンスは、トゥーツのような超絶技巧を駆使するタイプじゃないから、
リラックスして聴けるんですよ。
おのずとフュージョン/スムース・ジャズとも相性が良くなるわけなんですが、
イージー・リスニングのように聴いちゃうから、気に入っても棚の肥やしになりがち。
今回思い出したように棚から引っ張り出してきたのは、
実はこのコンコード・ピカンテ盤がきっかけじゃなくて、
マンデル・ロウ・トリオと共演した99年作のほう。
ひさしぶりに聴いて、う~ん、いいなあと感じ入っちゃって、
そういえばもう1枚あったっけと、コンコード・ピカンテ盤も出してきたんでした。
マンデル・ロウは、ぼく好みの職人肌のプレイを聞かせるギタリスト。
派手さはないけれど、音色がエレガントでねえ、いいんですよぉ。
キレのいいコード・ワークといい、じっくり聞かせる技に、
ジャズ・ギター教室に通った学生時代、憧れたもんです。
シブいプレイが持ち味のマンデル・ロウと、
テクニカルすぎないヘンドリックのハーモニカは相性バツグン。
実はこのアクースティック・ミュージックというレーベルには、
前の年の98年にハーブ・エリス・トリオと共演したアルバムも残しています。
こちらはライヴのせいか、ヘンドリックがウケ狙いの大味なプレイをしていて
ヒンシュクもんなんですけど、マンデル・ロウとの共演作の方は抑制が利いています。
すっかりぼくは忘れていたヘンドリック・モウケンスですが、
チェックしてみたら、その後も精力的にアルバムを出していたんですね。
あまり話題にならない人ですけれど、
ジャズ・ハーモニカ・ファンなら知っておいて損はないでしょう。
Hendrik Meurkens "POEMA BRASILEIRO" Concord Picante CCD4728 (1996)
Mundell Lowe & Hendrik Meurkens "WHEN LIGHTS ARE LOWE" Acoustic Music 319.1190.242 (1999)
2023-08-30 00:00
コメント(0)
エアコンがなかった真夏の夕べに ジョン・ヘラルド [北アメリカ]
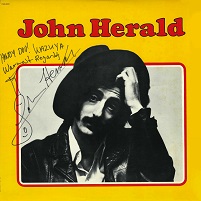
大昔の夏の定番を取り出してきました。
70年代のはじめ、ウッドストック周辺のシンガー・ソングライターを熱心に追いかけてた
高校生時分に大好きだった、ジョン・ヘラルドの73年パラマウント盤。
60年代にグリーンブライア・ボーイズの一員としてグリニッチ・ヴィレッジの
フォーク/ブルーグラス・シーンを賑わしたジョン・ヘラルドが、
ウッドストックに移り住んでウッドストックの仲間たちと録音したアルバムです。
レコーディングはニュー・ヨークなんですけど、
ウッドストック・サウンドの名盤としてファンに愛されたレコードですよね。
かん高いジョン・ヘラルドの愛嬌のある声が、めちゃくちゃ個性的で、
自宅が火事にあった出来事をコミカルな歌にしてしまう1曲目から、
この人の卓抜したユーモア・センスが発揮されていて、惹きつけられます。
フィドルが舞うハッピーなダンス・チューンあり、ほろっとさせるスローあり、
ノベルティ味のある曲と、レパートリーは多彩。
エイモス・ギャレットのギターが活躍していて、コーラスにはマリア・マルダーもいて、
ウッドストック・サウンド・ファンにはたまらないレコードでした。
グリーンブライア・ボーイズ時代の旧友
エリック・ワイズバーグのマンドリンも聴きものです。
ジョン・ヘラルドはブルーグラス出身のミュージシャンながら、ケイジャンを取り入れたり、
このレコードでもジャック・エリオットに捧げた曲で、
マウンテン・ミュージックの影響をうかがわせるように、
ブルーグラスにとどまらない音楽性が魅力でした。
このレコードの最高の山場は、レコード終盤に収録されたライヴ録音。
オールド・タイム・フィドラーが定番とするダンス・チューン
‘Hangman's Reel’ に始まる3曲で、最高潮になります。
夏の夕方、きつい西日が部屋に差し込む頃になると、
きまって聴いていたこのレコード、うちわ片手によく踊ったっけなあ。
当時自分の部屋にエアコンなんてものはなかったから、
汗をだらだら流しながら聴くのに最高なレコードだったんです。
ずいぶん長い間聴かずじまいだったのは、エアコン生活で忘れていたからかな。
このレコードは77年にマッド・エイカーズが来日した時、
ジョンにサインを入れてもらいました。池袋のヤマハで行われたイヴェントでしたね。
03年には韓国のボングラスがCD化して、ジョン・ヘラルドのブルーグラスのギターの腕前を
披露した曲を含む3曲がボーナス・トラックで追加されました。
オリジナルLPはシングル・ジャケットでしたけれど、
ゲートフォールドの紙ジャケット仕様で32ページのブックレットが封入され、
全曲歌詞にディスコグラフィー、ジョン自身の解説が載せられるという、
至れり尽くせりのリイシューでしたね。
[LP] John Herald "JOHN HERALD" Paramount PAS6043 (1973)
2023-08-28 00:00
コメント(0)
これがサンバ・ピアノだ シド・ビアンシ [ブラジル]
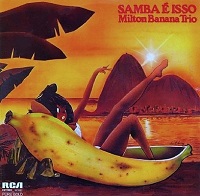
サンバ・ブームに沸いた77年、日本で大ヒットしたインスト・サンバの傑作。
のちにシリーズ化したミルトン・バナナ・トリオの本作は、
本国ブラジルより日本の方が売れたんじゃないかしらん。
『コパカバーナの誘惑』のタイトルで出た日本盤は、
キュートなジャケットも手伝って人気盤となりました。
CD時代になって日本が真っ先にCD化しましたが、
ブラジルではとうとうCDになりませんでしたね。サブスクにもないし。
ミルトン・バナナ・トリオといえば、
初アルバムの65年から続く老舗ジャズ・サンバ・トリオ。
70年代も後半になって出たこのアルバムでは、
女性コーラスをフィーチャーしてジャズ色を薄め、
ぐっとポップに仕上げて、サウンド・イメージをがらりと変えました。
これが功を奏してヒットしたんですが、「通」には受けが悪かったようで、
ジャズ・サンバのレコードを徹底網羅したディスク・ガイド
『ボサノヴァ・レコード事典』(ボンバ・レコード、2001)では、
「コーラスが余りにポップ過ぎる」(板橋純)と選盤されませんでした(苦笑)。
ベッチ・カルヴァーリョ、アルシオーネ、クララ・ヌネスなどの
当時のヒット・サンバをメドレーで演奏した本作、
上質なポップ作品に仕上げたのは、
サン・パウロのピアニストでアレンジャー、ジョゼー・ブリアモンチの手腕でした。
ジョゼー・ブリアモンチは60年代にサンサ・トリオで活躍した後、
テレビ番組の挿入歌を多く手がけてアレンジを磨いたんですね。
マルコス・ヴァーリが歌ったテレビ主題歌 ‘Pigmalião 70’ も、
ブリアモンチが手がけた作品です。
そんなジョゼー・ブリアモンチによるポップなアレンジが、
ヒットを呼んだ大きな要因であることは間違いありませんが、
本作の最大の魅力は、ミルトンのドラミングもさることながら、
ピアノのグルーヴィな魅力です。こんなにタッチが明晰で、
ノリのいいサンバ・ピアノ、めったに聞けるもんじゃありません。

シドという名前以外、このピアニストの経歴がわからなかったんですが、
だいぶ経ってから、伝説的なジャズ・サンバ・トリオ、ジョンゴ・トリオのピアニスト
シド・ビアンシ(本名アパレシード・ビアンシ)だとわかりました。
シドのバツグンの演奏力、とりわけリズムのノリは当時から圧倒的で、
しかも声楽教育を学んでいたことから、シドがコーラス・アレンジを施し、
ジョンゴ・トリオは3人がコーラスで歌うという、
歌謡性のあるポップなジャズ・サンバ・トリオだったのでした。

そのシド・ビアンシと当時共演した日本のジャズ・ミュージシャンが、渡辺貞夫です。
68年7月15日、サン・パウロでブラジリアン・エイトと録音した
『ブラジルの渡辺貞夫』がそれで、中村とうようの解説にあるとおり、
アパレシード・ビアンシがリーダー。
『コパカバーナの誘惑』がヒットしていた当時、渡辺貞夫が
昔ブラジルでこのピアニストと共演したことがあるという発言に、
えっ!と思ったんですが、68年のタクト盤だったんですね。
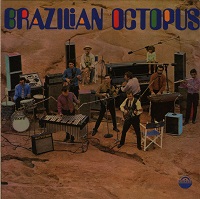
シド・ビアンシのキャリアでユニークなのは、ブラジリアン・オクトパスです。
シドがファッション・ショーで演奏するため68年に結成したグループで、サックスの名手
カゼーことジョゼー・フェレイラ・ゴジーニョ・フィーリョが在籍していました。
このグループが、実は渡辺貞夫と共演したブラジリアン・エイトなのです。
カゼーはレパートリーがあまりにコマーシャルなことに怒ってシドと喧嘩になって脱退し、
代わってエルメート・パスコアールが参加します。
ブラジリアン・オクトパスが残した1枚だけのレコードは、
カゼーが脱退しエルメートが加入した時期のもので、
オリジナル・メンバーによる録音は、『ブラジルの渡辺貞夫』がゆいいつなのでした。
グルーヴィなサンバ・ピアノの傑作 “SAMBA É ISSO”、
歌うジャズ・サンバ・トリオ、ジョンゴ・トリオ、
ラウンジーなポップ・センスを発揮したブラジリアン・オクトパスが、
シド・ビアンシの代表作といえますね。
[LP] Milton Banana Trio "SAMBA É ISSO" RCA 107.0257 (1977)
Jongo Trio "JONGO TRIO" Mix House MH0005 (1965)
渡辺貞夫とブラジリアン・エイト 「ブラジルの渡辺貞夫」 タクト COCB54256 (1968)
Brazilian Octopus "BRAZILIAN OCTOPUS" Som Livre 0223-2 (1969)
2023-08-26 00:00
コメント(0)
革命闘争の夢と幻滅を越えた半世紀 マラン・マネ [西アフリカ]

ギター2台、ベース、ドラムス、パーカッションの5人が奏でるまろやかなグンベーに、
胸アツになりました。かつてのスーパー・ママ・ジョンボのサウンドそのままの
アナログなサウンドの良さに、ああ、人力演奏っていいなあと、しみじみ感じ入ります。
歌う主は、マラン・マネ。
ギネア=ビサウ独立闘争時に結成された伝説のバンド、
スーパー・ママ・ジョンボのフロントを飾った歌手のひとりです。
90年にフランスへ亡命してから30年の間に書き溜めた曲が、
フランスのドキュメンタリー作家によって見いだされ、
リスボンのヴァレンティン・デ・カルヴァーリョ・スタジオでの録音が実現して、
アラン・マネにとって初のソロ・アルバムが完成しました。
リード・ギタリストのアドリアーノ"トゥンドゥ "フォンセカに、
パーカッショニストのアルマンド・ヴァス・ペレイラというスーパー・ママ・ジョンボの
オリジナル・メンバー2名に、セザーリオ"ミゲリーニョ "オフェルの後任となった
2代目リズム・ギタリストのジョアン"サジョ "カサマ、
アルマンド・ヴァス・ペレイラの弟のアントニオ"トニー ペレイラなど、
スーパー・ママ・ジョンボゆかりのメンバーで固めた5人に、
コーラスでママニ・ケイタとジュピテール(再来日中!)が参加しています。
ほっこりとしたグンベーのグルーヴに身を任せながら、
英訳された歌詞カードを読んでみたところ、
独立闘争で培った革命の信念を持ち続け、
解放闘争に身を挺した者の軌跡が刻まれていて、思わず背筋が伸びました。
マランがスター歌手から無名の移民労働者となり、
モントルイユの労働者宿舎で30年間の長き沈黙をしいられた生活にあっても、
革命家アミルカル・カブラル時代の精神に忠実で、失望や挫折の後もなお
不屈のプライドを持ち続けた気概が、その歌詞には溢れていたのでした。
かつてマランは、フランスと戦った英雄サモリ・トゥーレを讃えた
ベンベヤ・ジャズの ‘Regard Sur Le Passé’ からヒントを得て、
‘Sol Maior Para Comandante’ という曲で、
アミルカル・カブラルの生涯をたどった一大叙事詩を歌いました。
本作に、再会したメンバーによる同窓会アルバムにありがちなユルさがなく、
80年に出たスーパー・ママ・ジョンボの第1作と地続きで聞けるのも、
革命の夢と幻滅の半世紀を生き抜いた者の強度ゆえでしょう。
スーパー・ママ・ジョンボは、79年にリスボンの
ヴァレンティン・デ・カルヴァーリョ・スタジオで初レコーディングを行い、
ひと月近くかけて70曲以上を録音しています。
80年に出た第1作の “NA CAMBANÇA” と第2作の “FESTIVAL” が
この時の録音で、残りの多くは未発表になりましたが、長い時を経て
オランダのコビアナとアメリカのニュー・ドーンが、一部の未発表曲を復刻しました。
これら4枚でマランの歌声をきくことができます。
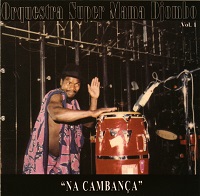



ちなみに、スーパー・ママ・ジョンボは86年に解散し、
のちに93年の映画『青い瞳のヨンタ』のサウンドトラックで再結成しますが、
この時すでにマランはフランスへ亡命していて、録音には参加していません。
最後に、マランが所属していた時代のスーパー・ママ・ジョンボのCDを掲げておきます。
ちなみに “NA CAMBANÇA” と “FESTIVAL” のCDは、
オリジナルLPとジャケットが違っていますが、
数年前にオリジナル・フォーマットのままLPリイシューされました。
Malan "FIDJU DI LION" Archie Ball ARCH2201 (2023)
Orquestra Super Mama Djombo "NA CAMBANÇA" Teca Balafon Productions CDBAL001/99 (1980)
Orquestra Super Mama Djombo "FESTIVAL" Teca Balafon Productions CDBAL002/99 (1980)
Super Mama Djombo "SUPER MAMA DJOMBO" Cobiana COB02
Super Mama Djombo "SUPER MAMA DJOMBO" New Dawn ND001CD
2023-08-24 00:00
コメント(0)
私はキゾンベイラ ヨラ・セメード [南部アフリカ]
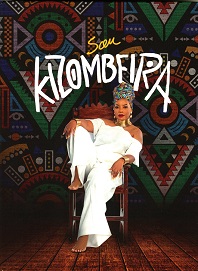
キゾンバの成熟を強烈に印象付けた、ヨラ・セメードの “FILHO MEU”。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-06-09
エディ・トゥッサの新作を押さえて16年のマイ・ベスト・アルバムに選ぶほど、
ぼくはひいきにしましたが、その後このアルバムの良さに気付いたファンが
少しづつ現れてくれて、心強く思いましたよ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-12-30
“FILHO MEU” から4年をかけて出した2枚組 “SEM MEDO” は、
10人のプロデューサーに70人のミュージシャンが参加して制作された大力作でした。
ディスク1ではキゾンバやズークばかりでなく、
センバ、モルナ、コラデイラ、ビギンが混在するクレオール・ミュージックを展開したほか、
ディスク2ではバラード中心に王道のポップ路線でまとめ、
ゴージャスなプロダクションにふさわしいヨラの歌いっぷりに、感じ入りました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-06-30
あれから4年。12月3日にアンゴラでリリースされた新作は、
CDはブック仕様、さらにLPも同時発売されるという異例ぶり。
ヨラが大統領夫人を表敬訪問して、LPとCDを手渡している報道写真を横目に、
日本に届くのをいまかいまかと待ち望んでいたんですが、
なんとアンゴラ現地で完売というニュースに、ええっ!
アンゴラでは、CDはイニシャル・プレスのみで再プレスしないから、
やば!手に入らないかも!とアセったんですが、なんとか無事届きました。
さすがはアンゴラのディーバの名に恥じぬ、貫禄の歌いぶり。
前作 “SEM MEDO” はクレジットがまったく書かれていませんでしたが、
今作は10曲中7曲が、
フェルナンド・ジョアン・サンバ・キジンゴ(プニドール)という人の作です。
81年ルアンダ生まれの作曲家兼プロデューサーで、ルアンダ州ベラス市の
観光文化レジャー青少年スポーツ局長でもあるそう。
パウロ・フローレスの曲も1曲歌っていて( ‘O Povo Isso É Boda’ )、
「キゾンバ、センバ、クドゥロ、人々の輪がエネルギー」というリフレインが耳残りします。
この曲のほか、今回は ‘Pátria’ ‘Vida Alheia’ と3曲もセンバを歌っているのが嬉しい。
「私はキゾンベイラ」と題したように、今回バラードはなく、
キレのあるダンス・トラックで通しています。キゾンバ女王の矜持を示した快作ですね。
Yola Semedo "SOU KIZOMBEIRA" Energia Positiva Music EPCD010 (2022)
2023-08-22 00:00
コメント(0)
グアドループの口太鼓ブーラジェルの新解釈 アラン・ジャン=マリー [カリブ海]

ビギン・ジャズ・ピアノのマエストロ、アラン・ジャン=マリー、
グウォ・カのグループ、カンニダのリーダーのルネ・ジョフロワ、
カメルーン出身、ニュー・ヨークで活動するヴォイス・パフォーマー、
ジノ・シトソンの3人によるコラボレーション。
CDには3人の名前が並列で記されていますが、
サブスクではアラン・ジャン=マリー名義のアルバムとなっています。
アランのピアノに、中低音を受け持つジョフロワのディープなヴォイスと、
高音を受け持つジノの軽やかで千変万化なヴォイスが交錯するという内容。
『追憶』と題しているのは、アランとジョフロワの故郷であるグアドループの伝統音楽、
ブーラジェル(口太鼓)を回想した企画だからなのですね。
ブーラジェルは、かつてグアドループの葬儀の晩に男たちが行うパフォーマンスでした。
ウォン・ア・ヴェイエとして知られる通夜の輪で、
歌い手の号令に従って、手拍子を打つレポンデと、
ノド音の口太鼓でポリリズムを作るブーラリエンがアンサンブルをかたどり、
ノドが生み出す擬音によって、パーカッシヴなパフォーマンスを演じます。
歌い手が即興の歌詞で歌ったり、ちゃちゃをいれたりしながら場を盛り上げ、
故人の家族と参列した者たちの連帯を高める役割を担いました。
太鼓の演奏を禁じられた奴隷たちが生み出したこの口太鼓パフォーマンスは、
80年代には消滅してしまったそうです。ブーラジェルが復活したのは、
グウォ・カが見直されるようになった90年代以降のこと。
幼少期にブーラジェルを体験しているルネ・ジョフロワは、
今回の企画には最適任だったのでしょう。
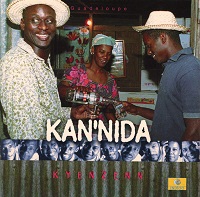

カンニダのアルバムでも、ジョフロワはブーラジェルを披露していましたね。
“KYENZENN” 所収の ‘Evariste Siyèd'lon’、
“NOU KA TRAVAY” 所収の ‘Nou Ka Travay’ ‘Tan Ki Tan’ では、
歌にブーラジェルを取り入れた復興後の新しいスタイルを聴くことができます。
驚異のヴォイス・パフォーマーとして知られるジノ・シトソンは、
グアドループでブーラジェルを観て、そのパフォーマンスに魅了されていたそうです。
ルネ・ジョフロワがジノの19年作 “ECHO CHAMBER” に参加しているので、
その縁が今回の企画につながったのかなと思ったら、
本作は14年2月にパリでレコーディングされているんですね。
リリースまで9年も寝かせた理由は不明ですが、
ブーラジェルをアラン・ジャン=マリーのビギン・ジャズ・ピアノで新解釈した
ユニークな作品、フレンチ・カリブ・ファンなら聴き逃せません。
Alain Jean-Marie, René Geoffroy, Gino Sitson "REMINISCENCE" THYG Production no number (2023)
Kan’nida "KYENZENN" Indigo LBLC2566 (2000)
Kan’nida "NOU KA TRAVAY" Debs Music KANID007/6117.2 (2010)
2023-08-20 00:00
コメント(0)
DJカルチャーが生んだアフロ・フューチャー・ジャズ アフロ=ミスティック [北アメリカ]

ボキャ貧(死語?)ライターのクリシェ・ワード、
「トライバル」をいかにも誘発させそうなグループが、アフロ=ミスティック。
サン・フランシスコのレーベル、オムを主宰するDJ・フルイドこと
クリストファー・スミスが99年に結成したグループです。
女性ヴォーカル、ドラムス、パーカッション2名にDJ・フルイドという陣容で、
DJ・フルイドが生演奏にエレクトロ処理したクラブ・ジャズを聞かせます。
ハウスDJがクリエイトしていたクラブ・ミュージックのクロスオーヴァー・サウンドを、
当時はフューチャー・ジャズなどと呼んだりしていましたが、
最近ではすっかりその名を聞くことはなくなりましたね。
マイルズ・デイヴィスの『ビッチズ・ブルー』のジャケットをモチーフにした
03年作の “MORPHOLOGY” は、多彩な音楽要素をミクスチャーして、
トラックごとに色彩の異なるサウンドを繰り広げていきます。
ラテンとアフリカとそれぞれ得意分野の異なるパーカッショニスト二人が
叩き出すビートをDJ・フルイドが巧みにピック・アップしながら、
エレクトロなブロークン・ビートに接続していのが、このグループの特徴です。
高速バツカーダで異常に早いBPMのアゴゴが飛び出したりして、
生演奏なのかサンプリングなのか判然としないところもまた魅力。
ガラージ色の強い女性ヴォーカルをフィーチャーしたブラジリアン・フュージョンもあれば、
ゲスト・ラッパーをフィーチャーした
フューチャリスティックなアブストラク・ヒップ・ホップもあり、
アップリフティングなムードからアンダーグラウンドなムードまで、
落差のあるトラック・メイキングに聴きごたえがありました。
イントロにピグミーのコーラスやアフリカの笛をサンプリングしたトラックもあって、
アフリカ音楽の研究にも余念がないところをみせていて、
個人的に好感を持っていたところです。
アフロ、ラテン、ブラジルをモチーフに、ハウスやブロークン・ビートを媒介としながら、
洗練されたマジカルなサウンドを提示していたアフロ=ミスティックですけれど、
こうした方法論を生演奏に置き換えているのが、
UKのK.O.Gやヌビアン・ツイストなんじゃないですかね。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-08-17
さらにエズラ・コレクティヴにも通じるものがあるのでは。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-11-19
Afro-Mystik "MORPHOLOGY" OM OM115 (2003)
2023-08-18 00:00
コメント(0)
日本のクラブ・ジャズを回顧して スタジオ・アパートメント、アイ・デップ [日本]


昔のCDをほじくり返してたら、止まらなくなっちゃいました。
フリーテンポよりも、さらにブラジリアンだったスタジオ・アパートメント。
04年の『WORLD LINE』なんて、バツカーダからスタートするんだから本格的です。
ジョージ・デュークあたりが大手を振っていた
80年代のブラジリアン・フュージョン時代から比べると隔世の感というか、
まがいものだらけだったフュージョン/クラブ・ミュージック周辺も、
この頃になるとようやくホンモノのサンバが聞けるようになってきました。
クラブ・ジャズの音楽家が、何々ふうの演奏でゴマカすのをやめて、
ちゃんと勉強するようになったのに比べ、
あいかわらずダメなのは、ライターの勉強不足ぶりかなあ。
ダンス系の文章は、総じて語彙が貧しいんだけれど、
「トライバル」を乱発するテキストを見たら、読む価値なしと思って間違いないです。
サンバ、マルシャ、バイオーン、フレーヴォが聴き分けられないんじゃ、
ブラジル音楽を語る資格がないように、
アフリカ音楽を語るのに、それがマンデなのかヨルバなのかズールーなのかもわからず、
全部「トライバル」で片づけられると、ほんとウンザリします。
「トライバル」の中身を紐解く知識がなくて、全部「トライバル」で済ます雑さというのは、
ロックもジャズもブルースも「ミュージック」と呼ぶのと同然。
もっとも「トライバル」としか言いようのないフェイクものじゃ、しかたないんだけどね。
話が脱線しちゃいましたが、
スタジオ・アパートメントは、ギター、ピアノ、ホーン・セクションなどの生演奏を
たっぷりフィーチャーしていて、ハウスを起点としていながらも、
クラブ・ジャズのニュアンスが強くて、70年代のクロスオーヴァーや
80年代のフュージョンと地続きで聴ける音楽でした。
フュージョンと違うのは、DJが踊らせることを目的に作る音楽だということですね。
スタジオ・アパートメントの『WORLD LINE』と同じ年に出た
アイ・デップも良かったなあ。
アイ・デップはキーボード、サックス、ギター、ベース、ドラムスというバンド編成で、
生バンドで演奏するクラブ・ジャズでした。
エレクトロな要素がフュージョンとは質感の異なるニュアンスがあって、魅力的でしたね。
楽曲がユーモアに富んでいてチャーミングだったのも、アイ・デップの良さだったなあ。
そうそう思い出したけど、娘たちがスタジオ・アパートメントやアイ・デップが大好きで、
新宿のタワーレコードでやったアイ・デップのインストア・ライヴに
娘二人を連れて観に行ったのを覚えています。
Studio Apartment 「WORLD LINE」 New World NWR2007 (2004)
i-dep 「MEETING POINT」 AZtribe/Rainbow Entertainment AZT001 (2004)
2023-08-16 00:00
コメント(0)
クラブ・ミュージックがクロスオーヴァーし始めた頃 アナンダ・プロジェクト/ピーター、フリーテンポ [その他]
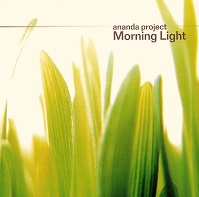

ノヴァ・フロンテイラで火が点いて、またぞろ昔のハウス周辺の
クラブ・ミュージックを棚から取り出す日々が続いています。
90年代末から2000年代にかけて、
クラブ・ミュージックを聴いていた一時期があったことは、
前にもちょっと書いたことがありましたね。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-03-02
クラブ・ミュージックがハウス、テクノ、ヒップ・ホップ、ドラムンベース、
ブロークン・ビート(定着している「ブロークンビーツ」は誤記)と
さまざまにクロスオーヴァーしていたこの時期、
ハウスを基調としたオーガニックなニュアンスのある
エレクトロニック・ミュージックに惹かれていました。
その代表がアナンダ・プロジェクトだったんです。
98年にアトランタで結成されたアナンダ・プロジェクトは、
ワムドゥー・キッズやピーターなどの名義で活動していた
DJ/プロデューサーのクリス・ブランを中心としたグループ。
男女ヴォーカル、キーボード、パーカッションのメンバーを擁し、
フュージョン、ブラジル、ジャズ、アンビエントなど多様な要素を凝縮した
サウンドを繰り広げていました。
03年に出た “MORNING LIGHT” は、エレピやシンセが幾重にもレイヤーされて、
ヌケのいいサウンドスケープを描いた名作でした。
ナイロン弦ギターの甘やかな響きを引き立てて、
ほのかなブラジリアンなテイストを演出していましたね。
そしてブラジルのサウダージとは異なる感触の、
孤独感をしのばせたメロディにも魅力がありました。
同じ年にピーター名義で出した “STARING AT THE SUN” も同趣向の好盤でした。
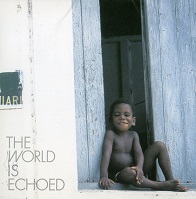
アナンダ・プロジェクトと時同じくして、日本に登場したのがフリーテンポでしたね。
当時渋谷のHMVが強力にプッシュしていて、それでぼくも買った記憶があります。
のちに半沢武志の名で活動するようになるフリーテンポのファースト・アルバムは、
ぼくにはアナンダ・プロジェクトの姉妹盤のように聞こえました。
フリーテンポはアナンダ・プロジェクトよりブラジリアン・フュージョン色が強く、
もろにサンバな曲もいくつかやっています。
ティピカルなパラッパ・スキャットがフィーチャーされるサンバでは、
ラテン・タッチのピアノやティンバレスもフィーチャーするという、
「ブラジル+ラテン」の面白い仕上がりとなっています。
アクースティック・ピアノをバックに男性ヴォーカルをフィーチャーしたトラックの
せつないメロディは、アナンダ・プロジェクトのメロディ・センスと見事に共振します。
渋谷のHMVが推すのもナットクのオシャレなクラブ・ミュージックなんですけど、
フリーテンポは東京に出てくることなく、仙台で音楽制作をしながら、
イタリアのイルマ・レコーズからデビューするという、
地方からダイレクトで海外進出する新しさに、時代の変化を実感したものでした。
Ananda Project "MORNING LIGHT" Nite Grooves/BPM King Stret Sounds KING234 (2003)
P’tahh "STARING AT THE SUN" Ubiquity URCD124 (2003)
FreeTEMPO 「THE WORLD IS ECHOED」 Forestnauts no number (2003)
2023-08-14 00:00
コメント(0)
ディスコ・ハウスの意外な使い道 ノヴァ・フロンテイラ [ブリテン諸島]
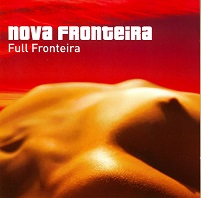
すっかりコロナが明けてしまった後ではあるんですが、
今頃になってリモート・ワークを始めるようになりました。
家で仕事をするのは、あまり気が進まないんですけれども。
これまで自分が担当していた仕事が、リモート不能な業務ばかりだったので、
コロナ蔓延中もずっと通勤していたんですが、システム環境が整い、
業務プロセスも見直されたため、週2日在宅勤務をすることになりました。
ゆいいつ在宅勤務のいいのは、音楽を聴きながら仕事ができることですかね。
こればっかりは、職場じゃできないからねえ。
でも昔にも、音楽を聴きながら仕事をしていたことが、わずかにありました。
20年前、監査の部署にいたときのことです。
各地の事業所を4泊5日で監査して、年100日近く出張する
ドサ回り生活をしてたんですが、なかなか得難い経験でした。
事業所の実査を終えた最終日前日の夜が、いちばんキツかったんですよ。
ビジネス・ホテルの部屋に缶詰めで、
監査調書を徹夜で仕上げなければならなかったんです。
その夜はエナジー・ドリンク代わりに、
アッパーな音楽をイヤホンで流し込みながら、
1万字超の報告書と関係データをグラフ化した参考資料を仕上げるのに、
悪戦苦闘しました。
この部署には都合3年いましたが、
少し慣れた2年目から少し睡眠をとれるようになったものの、
最初の年なんて、ほんとに一睡もできなかったですもん。
朝になってもまだ仕上げられなくて、朝メシ抜きで
カタカタとキーボード叩いてたもんなあ。
調書を書くBGMで最適だったのは、
気分をハイ・テンションに持っていけるイケイケのディスコ・ハウスでした。
耳から爆音を流し込めば、強烈なグルーヴに、
身体の血流も上がって、足や肩が勝手にリズムをとりながら、
指が快調にキーボードを叩いてくれたもんです。
ディスコ帝王ジョーイ・ネグロのサンバースト・バンドとか、
Z・レコーズの諸作は、本当にお世話になりましたねえ。
UKのDJ、ジョーイ・ネグロは、ハウス・ミュージックに
ディスコ・サンプルを組み込んだ最初のアーティストで、
数えきれないアルバムを制作したダンス・ミュージック・シーンの重鎮。
90年代後半から00年代になると、リミキサーとしての活躍もめざましく、
ダイアナ・ロスやペット・ショップ・ボーイズなど名だたる人気アーティストの
リミックスをてがけ、名プロデューサーの地位を確立しましたね。
徹頭徹尾ダンス・フロア向けに作られた、
ジョーイ・ネグロのレーベル、Z・レコーズにこんな使い道があるとは、
ジョーイ・ネグロもまさか思いつくめえ(笑)。
安ビジネス・ホテルのシングルなんて、デスクはちっぽけだし、
照明は暗いし、およそ仕事をするような環境じゃないんだけど、
そこを無理やりアドレナリン放出させて一晩格闘するには、
強烈にブギーなハウスが必需品だったんですよ。
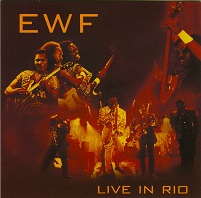
ちょうどこの頃、EW&Fの全盛期といえる
82年未発表ライヴ “LIVE IN RIO” が突然出て、
絶好のBGMになってくれたものですけれど、
ノヴァ・フロンテイラの本作はEW&Fをも凌ぐグルーヴで、
この2枚は監査中のホテルの夜のお供盤として鉄板になりました。
ひさしぶりに聴いたけど、いやぁ、アガる、アガる。
とびっきりディスコなトラックをアレンジしてるのは、
デイヴ・リー(ジョーイ・ネグロ)だしねえ。
ミケーレ・キアッヴァリーニのユニット、ノヴァ・フロンテイラは、
このアルバム以外知りませんが、Z・レコーズの最高傑作でしょう。
ラテン・フュージョンやブラジリアン・フュージョンを練り込んで、
ひたすらアップリフテイングなトラックで攻めまくる70分。
サマー・アンセムとしていまなお通用するディスコ・ハウスの逸品です。
Nova Fronteira "FULL FRONTEIRA" Z ZEDDCD04 (2002)
Earth, Wind & Fire "LIVE IN RIO" Kalimba 9730012 (2002)
2023-08-12 00:00
コメント(0)
草原に抱かれて 扎格達蘇榮 [東アジア]

内モンゴル自治区出身の女性監督の長編デビュー作
『草原に抱かれて』の試写(9月公開予定)を観ました。
主人公は、内モンゴルの都会に暮らすミュージシャンのアルス。
アルスの兄夫婦と暮らしている母親は認知症で、
兄夫婦は介護ノイローゼになっています。
アルスは一大決心をして母を引き取り、草原の故郷へ連れ帰る決心をします。
認知症が進んで徘徊を繰り返す母をアルスは自分の身体と太いロープで括り、
母が求めてやまない思い出の木を探して旅を続けていくという物語です。
内モンゴルの雄大な自然と、生と死が隣り合うテーマを、
都市の現代社会と草原の伝統生活を交錯させながら描く物語が秀逸で、
あたかもへその緒でつながったかのような逆転した母子像は、
死へ向かう人間が自然に融解していくさまを見ているようでした。
この映画を観終えた直後に、
内モンゴルの長調歌のアルバムと出会うとは面白い縁です。
扎格達蘇榮(ザクダスーロン)は、内モンゴル自治区シリンゴル盟出身の
オルティン・ドー(長調歌)の大御所。
広い声域を持ち、ホレボレとするメリスマを披露してくれます。
オルティン・ドーが「長い歌」と称するのはトルコのウズン・ハワとまったく同じで、
中近東から西アジア、中央アジアを経て日本の追分につらなる
こぶしロード(
中村とうようが指摘したこぶしロードは、小泉文夫が唱えた
中央アジアから日本のこぶし文化圏を拡張したものでしたけれど、
小島美子は日本民謡とモンゴル民謡の同源説を、
歴史学の観点から証明できないと否定的でした。
学問的な正しさはさておき、オルティン・ドーを聴けば、追分との類似について
音楽的妄想というか想像力をふくらませずにはおれません。
馬頭琴、三絃、笛、琴などを伴奏に歌われる悠然とした歌いぶりに、
あっという間に雄大な草原へと連れていかれます。
しっかりとアレンジされた演唱は、オーセンティックさより、
芸術的洗練を感じさせるものですけれど、
それでも十二分にフォークロアな味わいを感じ取ることができます。
長調は歌そのものが長く、音階の変化も少なくて、ゆったりと安定していますね。
歌詞が少ないので、メロディの深みとメリスマの美しさにうっとりさせられますよ。
36ページのブックレットが付属されていて、中国語・英語による解説と、
中国語とモンゴル文字で歌詞が載せられています。
解説によると、1曲目の「都仍扎那(ドゥルンザナ)」は、
19世紀にモンゴル相撲の力士として英雄視されたドゥルンドリガルの物語とのこと。
横綱となったドゥルンドリガルは、モンゴル語で「象」を表すザナの名で称賛され、
ドゥルンザナの称号を与えられた伝説の英雄となったそうです。
モンゴル民族の英雄や、モンゴルの美しい草原や自然の賛美、
家族への愛情や友情などを歌った21篇。心が透明になります。
扎格達蘇榮 「蒙古族長調歌王」 中国 CCD2598 (2008)
2023-08-10 00:00
コメント(0)
クラクションをパウ・パウ! ザ・ラ・ドライヴァーズ・ユニオン・パウ・パウ・グループ [西アフリカ]
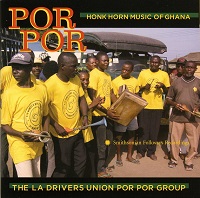
キング・アイソバのアルバム “WICKED LEADRERS” で、
ぶかぶかと鳴らされる珍妙なラッパ音。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-07-12
音程の出ない素朴な楽器を使ったこういう音楽を、
ほかにも聴いた覚えがあるんだけどなあ。
中央アフリカ、チャド、コンゴあたりの古い民俗音楽のフィールド録音とかじゃなくて、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-07-08
もっと最近のやつで聴いた気がするんだけど、なんだったっけ。
そう思いつつ、十年近く思い出せなかったんですけれど、
そうか、パウ・パウだったのか。同じガーナじゃん!
その昔、スミソニアン・フォークウェイズから出た、ガーナの首都アクラに所在する
ラ地区運転手組合のグループを野外録音したクラクション・ミュージック。
乗合バスのトロトロに付けられているクラクション=パウ・パウを使って、
組合員の運転手の葬送で演奏される音楽です。
ニュー・オーリンズのジャズ葬を思い浮かべるところですけれど、
現地アクラでは日常生活のやかましい音風景のひとつであって、
音楽という認識はされていないみたいですね。
かちゃかちゃと金属音を鳴らす廃品タイヤのリムに、
伝統楽器の椅子型打楽器ゴメや、木箱型打楽器タマリンがリズムをかたどり、
男たちがコール・アンド・レスポンスで歌うさなか、
クラクションのパウ・パウがぶかぶかと鳴らされるというパーカッション・ミュージック。
へぇ~、こんな音楽がガーナにあるのかと、当時は物珍しく聴いたものの、
フォークロアな音資料的な内容に、2・3回聴いたくらいで棚の肥やしとなっていました。

それをなぜ思い出しのたかというと、このグループの09年作を見つけたからなんです。
環境音のように録音されていたスミソニアン・フォークウェイズ盤とは段違いの、
ヴォーカルとコーラスを前面に出したミックスで、
グッと音楽的な仕上がりになっているんですね。
どちらも民族音楽学者のスティーヴン・フェルドが録音したものですが、
02年にスティーヴン・フェルドが設立した
ドキュメンタリー・サウンド・アート専門レーベル、
ヴォックスロックスから出たこのアルバムは、
曲がきちんとアレンジされていて、
音楽作品を制作する明確な姿勢が感じ取れます。
10人のメンバーと3人のゲストの名前と担当楽器がきちんとクレジットされており、
それを見ると、廃品タイヤのリムを叩いていたスミソニアン・フォークウェイズ盤の
普段着姿の演奏との違いがわかります。本作で金属音を響かせるのは、
ダブル・ベルのアダブランタで、ガ人の太鼓パンロゴ、
椅子型打楽器ゴメ、ひょうたん製シェイカーのアカシャ、
フィンガー・ベルのアダワヌといった多くの伝統楽器が使われています。
パウ・パウも5人のメンバーに二人のゲストが演奏するほか、
音楽監督を務めるリード・ヴォーカリストが、笛のアテンテベンを吹いています。
単音しか出ないパウ・パウを複数台使ってベースとなるリズムを作り、
そこにパロンゴが即興でクロス・リズムを加えていくところなど、すごくスリリング。
アダブランタが反復リズムを繰り返して、パウ・パウと笛とパロンゴが即興しあったり、
リズムの構成が曲ごとにしっかりと組み立てられていますね。
キャッチーなメロディーの曲が多くて、ハーモニー使いのコーラスも交えて、
けっこうポップなんですよ。いやぁ、これ、めちゃ楽しいじゃないですか。
そんなポップにも聞こえる曲のなかで、
パウ・パウがゆいいつ不協和な音をまき散らす面白さにヤられます。
スミソニアン・フォークウェイズ盤に退屈した人にも、これはオススメ!
最後に、日本語テキストでは
もっぱら「ポル・ポル」と書かれていますが、「パウ・パウ」と発音します。
The La Drivers Union Por Por Group "POR POR: HONK HORN MUSIC OF GHANA" Smithonian Folkways Recordings SFWCD40541 (2007)
The La Drivers Union Por Por Group "KLEBO!" VoxLox 109 (2009)
2023-08-08 00:00
コメント(0)
怒りの時代を伴走してくれた大楽団 渋さ知らズ [日本]






そういや渋さ知らズだって、ちっとも聴いてないなあ。
なんでなんだろう。一時期は毎日浴びるように聴いてたのにねえ。
渋さ知らズは、それまでの日本のアングラ系ジャズにありがちだった
「暗さ」がなくて、そこに惹かれたんですよね。
デビュー作の『渋さ道』(93)だけ、なぜか持ってないんですが、
2作目の『DETTARAMEN』(93)から『渋旗』(02)までは、ずっと聴いていました。
不破大輔が渋さ知らズを始動させる前に、川下直弘(サックス、ヴァイオリン)と
大沼志朗(ドラムス)と活動していたパワー・トリオ、
フェダインにノック・アウトを食らったのも大きかったかな。

フリー・ジャズど真ん中のフェダインとは違って、
渋さ知らズはメンバーが持つ雑多な音楽が紛れ込んでいて、
ロックからチンドンまでなんでもありの自由さに加え、
なんといっても編成がデカいから、音圧勝負では無双でしたよね。
あの当時は、仕事のプレッシャーがハンパなくてねえ。
身の丈に合わない大きな仕事の連続で、
キモチで負けたら先がないといった日々に、自分を奮い立たせるのに必死でした。
30代半ばから40代半ばの10年間を渋さ知らズが伴走してくれて、
そりゃあずいぶん勇気づけられたものです。
ダンドリストとして渋さ知らズを差配する不破大輔は、
駅伝の青山学院大学の原監督や、サッカー日本代表森保監督、
WBC日本代表の栗山監督に匹敵する、
新しいリーダーのロール・モデルを先取りしていたと思うなあ。
04年の「渋星」が、なんだかすっきり整理されてしまったのにガッカリして、
それから熱が冷めていったんですけど、その後メジャーに移籍して
歌謡曲カヴァーしたりして、ますます疎遠になっちゃいました。
あらためて90年代のアルバムを聴き直してみたら、
やっぱりこの時代の渋さのエネルギー量は圧倒的でしたね。
単純なメロディを、これでもかというくらい繰り返すしつこさと
音塊をぶつけ合って音圧を出すことに血道を上げるバカバカしさを、
どこまで本気で面白がれるかに、渋さの生命線がありました。
いつのまにか渋さ知らズを聴かなくなってしまったのは、
仕事のプレッシャーの質が変わって、
単純な熱量だけでは足りなくなったからなのかもしれないな。
それでも30~40代の働き盛りのリーマンには、
渋さは何にも代えがたい存在だったんですよ。
ひさしぶりに手持ちの渋さ全作とフェダインを聴いたら、
あの当時の仕事やらなんやらの思い出が次々蘇ってきました。
あの頃は、年がら年中仕事で怒っていた気がするけれど、
若かったんだろうねえ。なんでもすぐにムキになってたもんなあ。
あの時一生ぶん怒っちゃったからか、いまや怒ることなんてまったくなくなっちゃった。
渋さ知らズは、怒りが必要だった時代のBGMだったのかも。
渋さ知らズ 「DETTARAMEN」 ナツメグ NC2066 (1993)
渋さ知らズ 「SOMETHING DIFFERENCE」 地底 B1F (1994)
渋さ知らズ 「BE COOL」 地底 B3F (1995)
渋さ知らズ 「渋祭」 地底 B9F (1997)
渋さ知らズ 「渋龍」 地底 B14F (1999)
渋さ知らズ 「渋旗」 地底 B21F (2002)
Fedayien 「FEDAYIEN Ⅱ」 ナツメグ NC2052 (1992)
2023-08-06 00:00
コメント(0)
酷暑には熱いファンク・ジャズで ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテット+1 [北アメリカ]

今年の夏も酷暑になっちゃいましたねぇ。
クソ暑い夏をぶっとばそうと、とびっきり熱い1枚を棚から拾い出して、
30年ぶりのヘヴィロテとなっております。
それがジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットの85年ライヴ盤。
夏はこういうわかりやすくって、祝祭感たっぷりでイェ~イとばかりに
盛り上がれるライヴ盤がぴったりなんであります。頭カラッポで阿呆になれるし。
ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットのアルバムは数が多くて、
どれ聴いてもあんまり変わんないんだけど、
これはジョン・スコフィールドという異物(?)が交じったことが功を奏して、
決定的な名作となったんでした。
ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットといえば、
ドラマーはダニー・リッチモンドと、
ベースをのぞく全員がチャーリー・ミンガスの門下生で、
ブラック・ジャズの伝統を継承したともいえるグループ。
そこに当時はまだ変態ギタリストと揶揄されてもいた
白人のジョン・スコフィールドが加わったというのがミソ。
白人が加わったことでブラックネスがより増すという、稀有なアルバムになったんです。
ジョージ・アダムス/ドン・プーレン・カルテットって、
アダムスがサックスをぶりばりと咆哮しまくり、
プーレンが肘打ち、拳ころがしでピアノを痛めつけるパフォーマンスが有名で、
世間的にはアヴァンギャルドとかみなされてたんですけど、実は全然違うんですよ。
プーレンのぶち切れパフォーマンスも聴き慣れてしまえば、
あぁ、またいつものパターンかとわかる安定感ある演奏で、手クセも満載。
つまり前衛なのではなく、鍵盤を使って音の奔流を巻き起こす
黒人芸能的なエンタテインメントなのですね。
しかし、そこにジョン・スコフィールドというまさしく異物が入って、
グループをかく乱したことにより火が点き、
いつものカルテットの安定感をぶち破ったんですね。
ジョン・スコフィールドのオリジナルの1曲目 ‘I.J.’ から、
ディストーションのかかったファンク・ギターが大暴れ。
アダムスとプーレンを食うプレイの連続に、さすがに4人の目の色も変わったんでしょう。
続くアダムスのオリジナルのファンク・ジャズ ‘Flame Games’ は、
このカルテット+1の最高の名演となりました。
ソウル・ゴスペル色強いプーレンのオリジナル2曲はポップといえるほどで、
ミンガス門下生らしいブラック・ジャズの美点を示しています。
いまだったら、渋さ知らズのファンとかが聴いても、気に入るんじゃないかしらん。
George Adams / Don Pullen Quartet "LIVE AT MONTMARTRE" Timeless CDSJP219 (1986)
2023-08-04 00:00
コメント(0)
ロンドンでデビューしたニュー・オーリンズのソウル・シンガー アカンサ・ラング [ブリテン諸島]

もう1枚UKから届いた女性シンガーのデビュー作。
こちらは70年代スタックスのサウンドを思わす
サザン・ソウル・フィールたっぷりのアルバム。
アカンサ・ラングはロンドンを拠点に活動する人ですが、出身はニュー・オーリンズ。
ニュー・ヨークに進出してナイト・クラブ、ザ・ボックスの初代MCの座を勝ち取り、
それが縁でザ・ボックスのロンドンの姉妹店でレジデントを務めることになり、
ロンドンをベースに活動してレコーディングに至ったのだそう。
おだやかな低音の歌い始めから、曲の中盤の盛り上がりに従って、
ハスキーな高音を織り交ぜながら歌う人で、そのハスキーな歌声に
サザン・フィールがしたたり落ちます。う~ん、実にいい味わいじゃないですか。
ホーン・セクションに女性コーラスもフィーチャーしたバックも見事。
マッスル・ショールズのサウンドが再現されていて、
これが全員ロンドンのミュージシャンで、
ロンドンでレコーディングされたものとは、にわかに信じがたいほど。
ジャケットだって、まるで70年代のスタックスみたいじゃないですか。
父親との再会を歌った ‘Come Back Home’ や、
母親にオマージュを捧げた ‘Lois Lang’ など、自叙伝的なアルバムらしく、
歌詞カードにも幼い時のアカンサの写真が載せられています。
そしてこのアルバムのハイライトは、ラスト・トラックの ‘Ride This Train’。
曲の最後にホーン・セクションがセカンド・ラインを奏でて、
アルバムが締めくくられます。
めちゃハッピーな聴後感がサイコーです。
Acantha Lang "BEAUTIFUL DREAMS" Magnolia Blue MBR001CD (2023)
2023-08-02 00:00
コメント(0)




