ダウンテンポのサウンドスケープで 憶蓮(林憶蓮) [東アジア]

林憶蓮(サンディ・ラム)の新作。
うわー、ずいぶんとご無沙汰してました。
ディック・リーとコラボした91年の『夢了、瘋了、倦了』『野花』を最後に、
ぜんぜん聞いていなかったなあ。
ひさしぶりに巡り合ったCDのスリップケースには、
「林」がなく「憶蓮」とだけ書かれていて、改名したのかと思いきや、
歌詞カードのクレジットはすべて林憶蓮とあり、どーなってんの?
そういえば、87年に『憶蓮』というCDを出してたことがあったけど。
そこらへんの事情はわかりませんが、
今回香港から届いたCDは、18年にデジタル・リリースされた作品。
翌19年に台湾のみで限定LPリリースされ、
昨年末になり5周年を記念して香港で限定CD化され、
今年に入って平裝版(通常版)として再リリースされたものとのこと。
平裝版には限定版にないシークレット・トラック ‘Angels’
(3曲目「纖維」の英語ヴァージョン)が最後に収録されています。
個人的には30年以上ぶりに聴くサンディ・ラムですが、
ひそやかな歌い口は変わらず。しゃべるような語り口は、この人の個性ですね。
年月を経て円熟を示すのではなく、昔と変わらぬみずみずしさを表出するのは、
守りでなく攻め続けてきたアーティストの証のように思えますね。
そんなことを思ったのは、アルバムのサウンドが意外にもダウンテンポだったから。
なるほどサンディの静謐で幽玄な音楽世界に、
ダウンテンポのサウンドスケープは、ぴたりハマリますね。
アンビエントやエレクトロのデリケイトな扱いは抑制が利いていて、
声高に主張することはありません。
エレクトロすぎず、ミニマルすぎず、実験的すぎず、
過剰にアーティスティックとならぬよう、ロック調の曲で通俗さを残しつつ、
ドリーミーに表現されるサウンド。
サンディのため息まじりの声とファルセットに恍惚とさせられます。
この歌声が50代半ばって、スゴくないですか。
憶蓮 「0」 Universal 650211-5 (2019)
2024-02-28 00:00
コメント(0)
オールド・タイム・ソウル制作の舞台裏 ダン・ペン/ボビー・ピューリファイ [北アメリカ]

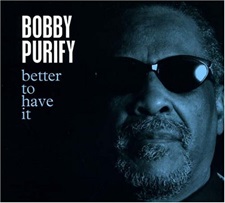
昨年のレコード・ストア・デイで限定発売されていたというレコードがCD化。
レコード・ストア・デイはぼくの関心外なので、
こんなレコードが出ていたとはちっとも知りませんでしたが、
こりゃあ、ダン・ペン・ファンにはたまらない贈り物ですね。
ダン・ペンが曲提供してプロデュースした、
サザン・ソウル・シンガー、ボビー・ピューリファイの05年復帰作
“BETTER TO HAVE IT” のダン・ペンのデモ音源10曲と、
ボビー・ピューリファイによる同じ完パケを並べた企画作。
ダン・ペンのデモ音源の素晴らしさは、
60年代のフェイム・レコーディングですでに証明済みですよね。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-12-09
ダン・ペン名義で出るのもナットクの企画です。
ボビー・ピューリファイの復帰作は、スプーナー・オールダム、カーソン・ウィットセット、
レジー・ヤング、ジミー・ジョンソン、デイヴィッド・フッド、ウェイン・ジャクソンという
そうそうたるメンバーを揃えて、ナッシュヴィルでレコーディングされたものでした。
このアルバムを制作したのは、ダン・ペンがソロモン・バークの02年の復帰作
“DON'T GIVE UP ON ME” のタイトル曲を書いて、
大きな手ごたえを得たのがきっかけとなったそうです。
グラミー賞を獲得する高い評価を得て自信を深めたダンは、
次なるホンモノのソウル・シンガーに自分の作品を歌ってもらいたいと、
曲作りとともに候補のシンガーを探し始めたのだそうです。
そうして巡り合ったのが、60~70年代のサザン・ソウル黄金期に活躍するも、
過小評価に甘んじていたボビー・ピューリファイ(本名ベン・ムーア)だったんですね。
R&B歌手ボビー・ピューリファイとゴスペル歌手ベン・ムーアの双方で活動するも、
緑内障のために94年から視力を失い始め、その4年後には失明して
絶望の淵に立たされ、当時サーキットから離れていたといいます。
その後レイ・チャールズに励まされ、再起を考えたところにダンと巡り合ったのでした。
ボビー・ピューリファイとダンとは、不思議な因縁がありました。
かつてのソウル・デュオ、ジェイムズ&ボビー・ピューリファイの66年のヒット曲
‘I'm Your Puppet’ は、ご存じダン・ペンとスプーナー・オールダムの作。
これを歌った初代ボビー・ピューリファイ(本名ロバート・リー・ディッキー)が
71年に健康上の理由で音楽活動を引退して、後任のボビー・ピューリファイを
ベン・ムーアが引き受け、第二期ジェイムズ&ボビー・ピューリファイで活動したのです。
この新生ジェイムズ&ボビー・ピューリファイでも ‘I'm Your Puppet’ を再録音し、
76年にイギリスで全英12位となるヒットとなったのですね。
ボビー・ピューリファイの慈愛に満ちた温かな歌声に、
サザン・ソウルのスピリットが詰まった名作でしたけれど、
カーソン・ウィットセットとバッキー・リンゼイを伴奏に歌うダンのデモ音源に、
あらためて名作曲家だなあと感じ入ります。
Dan Penn "THE INSIDE TRACK OF BOBBY PURIFY" The Last Music Co. LMCD231
Bobby Purify "BETTER TO HAVE IT" Proper PRPACD001 (2005)
2024-02-26 00:00
コメント(0)
タイムレスなR&B グレン・ジョーンズ [北アメリカ]

ひさしぶりに棚から引っ張り出して、聴き惚れちゃった。
これは、やっぱり傑作だわ。四半世紀経っても変わらぬみずみずしさ。
タイムレスな作品だということの証明ですね。
グレン・ジョーンズ。58年フロリダ生まれ。
4歳から教会で歌うゴスペル育ちで、8歳で初レコーディング。
14歳でゴスペル・グループ、ザ・モジュレーションズを結成して全米ツアーし、
80年になってソウルに転向、83年にソロ・デビューした「歌えるシンガー」です。
奇しくもぼくと同い年で、これはグレンが40歳の時の作品。
RCA~ジャイヴ~アトランティックと渡り歩いた彼のキャリアからすると、
メジャーではなかなか決定打を出せず、
マイナー落ちしてからの作品ということになるんだけど、これが彼の最高傑作。
歌のうまさ、実力は超一流なのに、
メジャー時代のアルバムはいまひとつアピールするところが弱くて、
代表作がなかなか作れない人でした。
80年代当時、こういう「歌えるシンガー」はグレン・ジョーンズばかりでなく、
フレディー・ジャクソンも同じポジションにいた人でしょう。
98年になって、インディからひっそりと出されたこのアルバムは、
気迫のあるジャケットのポーズからして、名作の予感がありました。
しかも、このタイトル。期待にたがわぬ出来で、
ついにグレン・ジョーンズがやった!と嬉しさひとしおでした。
楽曲とプロダクションが見事にかみ合って、
ついにこの人の実力に見合った作品が完成したんですね。
さらにこのアルバムに輝きを増したのが、ボーナス・トラックとして収録された、
ニュー・ヨークKISS-FMのオン・エア・ライブ。
過去のヒット曲5曲を再演しているんですが、これがもう素晴らしい出来。
これ聴いて、もう過去作持ってなくてもいいやと、全部処分しちゃったんだよな。
90年代ならではのアンプラグド・ライヴが、
80年代のオリジナルのプロダクションを完全に凌いでいるんですよ。
楽曲の魅力があらためて引き出されているばかりか、
グレンの歌いっぷりもまっことソウルフルで、感激しました。
バックもすごくいいんだ。ポール・ジャクソン・ジュニアのアクースティック・ギターが、
これぞ歌伴のお手本といった職人芸のプレイで、ウナらされます。
スタジオのDJ二人(なんとアシュフォード&シンプソン!)の感極まったMCや、
リスナーの声もヴィヴィッドで、数多くのボーナス・トラックが蛇足に終わるなか、
こんな贅沢なボーナス・トラックは後にも先にもないですよ。
プロデュースはロス・ヴァネリ。かのジノ・ヴァレリの弟で、
アース・ウィンド&ファイア、デニス・ウィリアムズ、ジェフリー・オズボーンなど、
数多くのアーティストを仕事をしてきた作編曲家兼プロデューサーです。
グレンは4年後にピークへレーベル移籍してアルバムを出しましたが、
プロデューサー陣をがらりと変えた “FEELS GOOD” は、本作の出来に及ばず。
本作の成功は、ロス・ヴァネリの力が大きかったんじゃないかな。
Glenn Jones "IT’S TIME" SAR SAR1001-2 (1998)
2024-02-24 00:00
コメント(0)
アブストラクトにしてエレガント ディヴル [西・中央ヨーロッパ]

衝撃のピアノ・トリオが登場!
1曲目のイントロではや、ぎゅっと耳をつかまれちゃいましたよ。
無機的な音魂を叩くピアノ、いびつにずれたリズムを叩くドラムス、
チェンバロのようなトレモロを響かせる内部奏法。
なに、このカッコよさ!
スイスのトリオのデビュー作で、ぼくが注目するフィンランドのウィ・ジャズからの新作。
このレーベルの作品って、ぼくのツボに見事ハマるなあ。
グループ名はディヴルと読めばいいのかな。
一聴で金縛りにあっちゃって、CDが届くのを首を長くして待っていました。
抽象的なコンポジションを、
フリー/アンビエント/ミニマルな手さばきで演奏するジャズ。
まったくエレクトロを使用しないアクースティックの編成なのに、
電子音楽のようにも聞こえる不思議さ。
モチーフの断片から即興的に発展したような曲が多くて、
ミニマルなフレーズの連なりにいっさい甘さのないところが、いい。
物憂げなコードも抒情を呼びよせないので、音楽がキリッと引き締まります。
ピアノがギザギザとした弧を描いて、エネルギッシュにかけあがっていく
レディオヘッドのカヴァー ‘All I Need’ など、もうドキドキが止まりません。
実験的なアンビエント・ジャズのキーボード奏者ダン・ニコルズが、
ミックスとポスト・プロダクションをしていて、
このポスト・プロダクションがかなり利いていますね。
ピアノをガムランのような音に加工したりしていますよ。
アブストラクトにしてエレガントな仕上がりは鮮やかです。
まもなくウィ・ジャズから届くオーティス・サンショーの新作も、
ダン・ニコルズ、ペッター・エルドとの3人による作品なので、
こりゃあ、めちゃめちゃ楽しみだなあ。
divr "IS THIS WATER" We Jazz WJCD60 (2024)
2024-02-22 00:00
コメント(0)
無頼人生のぶっきらぼー節 ソティリア・ベール [東ヨーロッパ]

世界一ぶっきらぼーな歌を歌う人。
ソティリア・ベールを初めて聴いた時は、
音楽の審美的価値観をひっくり返される思いがしました。
情感もへったくれもないその歌いぶりに、
世の中にはこういう歌の美学もあるのかと、衝撃でしたよ。
ソティリア・ベールは、40年に無一文でアテネに出てきて、
さまざまな仕事をしながら糊口をしのぐ一方、レジスタンス活動にも身を投じ、
44年12月のアテネの戦いに参加して負傷したという烈士。
47年に酒場で歌っているところをヴァシリス・ツィツァーニスに見い出されて、
戦後レンベーティカを代表する歌手となった人です。
生まれはエーゲ海西部、エヴィア島の都市ハルキダですが、
アテネに出てきた理由が凄まじい。
十代で望まぬ結婚を親に強いられ、
夫から頻繁に殴られる日々が続いたというのです。
ある日身を守るために、夫の顔面にワイン瓶を投げつけて逮捕され、
3年の実刑判決を受けて6か月服役したのだそうです。
服役後に実家から縁を切られて故郷を出たというのだから、壮絶です。
レジスタンス活動中にも逮捕され、
悪名高いマーリン通り拘置所に投獄されて拷問を受けたといいます。
こうしたエピソードの数々は、
ソティリア・ベールの強烈な歌いぶりへの納得感を補完するものでしょう。
50年代半ばにレンベーティカがその歴史を終えるのと同時に、
ソティリアも活動を止めてしまうのですが、
60年代に入って活動再開した時に、声がすっかり変わって男のような低い声となり、
ただでさえディープな歌うたいだったのが、さらに凄みを増していました。
そんなソティリアの凄みを実感できるのが、80年の本作。
当時若手気鋭の作曲家イリアス・アンドリオプロスと、
このアルバムで作詞家としてのスタートを切ったミハリス・ブルブリスの
コンビで制作された作品です。
ジャケットの黄昏れた絵がなんとも雰囲気があって、大好きな作品なんですが、
このアルバムがCDブックのデラックス・エディションでリリースされていたことを知り、
買い直したのでした。09年に出た限定版ですけれど、まだ今でも売っていますね。
80年の作品なので、ライカの意匠であるものの、
レンベーテイカのムードを濃厚に残した歌を聞かせる名作です。
美しく清楚な女性コーラスがフィーチャーされる曲では、
ソティリアのヴォーカルとのあまりの落差に、笑っちゃうくらいですよ。
ソティリア・ベールは晩年アル中になったうえ博打に溺れて経済的に困窮し、
97年に亡くなった時に無一文だったのも、博打が原因だったといいます。
ソティリアの人生は、まさしく波乱万丈。
48年には極右の狂信者集団がライヴ会場に乱入して、
ソティリアを共産主義者と罵りながら殴打する事件も起きています。
晩年にレズビアンを公言したのも、当時のギリシャ社会では考えらないことでした。
破天荒な人生を送った人ならではの、ぶっきらぼー節です。
[CD Book] Sotiria Bellou "LAIKA PROASTIA" Lyra 3401176915 (1980)
2024-02-20 00:00
コメント(0)
南イタリア、チレントの丘から イーラム・サルサーノ [南ヨーロッパ]

緑豊かな丘の上で、ダンス・ポーズをキメた女性。
曲の最後なのか、両手を高く上げ、
左手にタンバリン(タンブーリ・ア・コルニーチェ)を掲げています。
後ろのすみっこに小さく写っているのは犬かと思ったら、
歌詞カードを見ると、どうやら羊のよう。
南イタリア、カンパーニャ州チレントから登場したイーラム・サルサーノは、
故郷の山岳地帯に伝わる伝統音楽を今に継承する人。
チレント地方は同じ南イタリアでも、ピッツィカやタランテッラが盛んな
サレント半島とは反対側の南西部にあり、ピッツィカやタランテッラ以外に、
さまざまな土地のリズムがあることを、このデビュー作が教えてくれます。
全曲伝承歌で、イーラム自身がアレンジしているんですけれど、
みずからのヴォイスをループさせてドローンにしたり、
ヴォイスを使ってさまざまなビート・メイキングしているところが聴きどころ。
現代のテクノロジーを駆使して、伝統音楽を現代の音楽として
受け継ごうとする彼女の意志を感じます。
1曲目の ‘Otreviva’ では、口笛による鳥のさえずりに始まり、
イーラムのヴォイスをループさせたドローンのうえでイーラムが歌い、
タンバリンが三連リズムを刻み、アコーディオンがリズム楽器として重奏して、
厚みのあるピッツィカのグルーヴを生み出しています。
演奏はタンバリンを叩くイーラムと、
アコーディオン兼マランツァーノ(口琴)奏者の二人が中心となり、
曲によって、サンポーニャ(バグパイプ)、チャルメラ、キタラ・バッテンテ
(複弦5コースの古楽器)を操る奏者とウード奏者とドラマーが加わります。
2拍3連のダンス曲もあれば、ゆったりとした3拍子あり、
ドラムスが入ってレゲエ的なアクセントを強調する曲もあって、
多彩なリズムが聴き手を飽きさせません。
ハリのあるイーラムの歌いぶりに飾り気がなく、土臭さのあるところが花丸もの。
アイヌのウコウクやリムセを思わせる歌もあり、
口琴まで伴奏に加わると、ますますアイヌ音楽みたいに聞こえて、
とても楽しいです。
Hiram Salsano "BUCOLICA" no label HS001/23 (2023)
2024-02-18 00:00
コメント(0)
ニューカッスルのルオ人ニャティティ奏者 ラパサ・ニャトラパサ・オティエノ [東アフリカ]

ケニヤ西部ヴィクトリア湖畔シアヤ生まれのラパサ・ニャトラパサ・オティエノは、
ルオの伝統楽器ニャティティを弾きながら、ルオの民話をモチーフにした
自作曲を弾き語るシンガー・ソングライター。
現在は北部イングランド、ニューカッスル・アポン・タインを拠点に活動しています。
ラパサの21年の前作 “KWEChE” を聴いた時、
ルオ独特の前のめりに突っ込んでくるビート感がなくて、平坦なリズムに終始しているのに、
昔のアユブ・オガダを思い出し、ガッカリしました。
アフリカの伝統音楽家で、欧米に渡って白人客だけを相手にするようになると、
音楽の姿勢が歪んでくる人がいるので、この人もその部類かなと。
いまではアユブ・オガダを知っている人もほとんどいないでしょうが、
昔リアル・ワールドからCDを出し、来日したこともあるニャティティ奏者。
この人の場合、キャリアの始めから西洋人を意識した音楽をやっていた人だから、
ぼくは、伝統音楽を装ったインチキな音楽家と見なしていました。
オガダを気に入ったピーター・ガブリエルの審美眼って、お粗末だなあと。
話が脱線しちゃいましたが、
そんなわけでラパサの新作もまったく期待していなかったんですけど、
これが存外の出来で、見直しましたよ。
ひとことでいえば、ポップになっているんですよ。
前作ではニャティティの弾き語りをベースに、
曲によってベース、ギターなどがごく控えめにサポートするだけだったのが、
今作は男女コーラスも配して、ウルレーションも炸裂する
華やかなサウンドになっています。
ベンガのビート感はまだ弱いとはいえ、なるほどベンガだと思わせる曲もあって、
サウンドメイクをポップにしながら、
ソングライティングはベンガのルーツを掘り下げたことがうかがわれます。
反復フレーズを強調した曲が増えたこともそのひとつで、
しつこく繰り返す反復フレーズによってダンスを誘い、トランスへと招きます。
なんでも本作の制作にあたってラパサは、
ベンガのパイオニアたちの音楽を研究したそうで、その成果が表れたんでしょう、
クレジットをみると、ルオの一弦フィドルのオルトゥほか、
数多くのパーカッションや笛などのルオの伝統楽器が使われています。
ラパサが8弦楽器オボカノを弾く ‘Adhiambo’ も聴きもの。
オボカノはルオに隣接して暮らすグジイ人の伝統楽器で、
クリーンな音色のニャティティと違って、強烈なバズ音を出します。
ひとことイチャモンをつけたいのは、2曲目の ‘Unite’ だな。
タイトルからもわかるとおりの空疎なメッセージ・ソング。
アフリカのミュージシャンが唱える Unite くらい、現実味のないものはなく、
ぼくはこのワードを発するアフリカ人音楽家の薄っぺらさが、ガマンならんのですよ。
この曲がなかったらよかったのに。
Rapasa Nyatrapasa Otieno "JOPANGO" no label no number (2023)
2024-02-16 00:00
コメント(0)
いまのフジを支えるのは誰 ティリ・アラム・レザー [西アフリカ]

「人を見かけで判断しちゃいけない」の典型だった、
童顔でも歌えるフジ・シンガー、ティリ・アラム・レザーの新作。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-04-19
本名のティリ・アボンラガデ・アラムに沿って、
ステージ・ネームの「レザー」の間にアラムを加えたようです。
表ジャケットにはティリ・アラムとだけしか書かれていませんが、
裏の作編曲クレジットには、ティリ・アラム・レザーとあります。
昨年9月にリリースされた本作には、
短尺の2曲と長尺の2曲が収められ、どの曲もいがらっぽい声に、
ドスの利いたこぶし回しが咆哮する、漆黒の純正フジを聞かせてくれます。
4曲ともリズムもテンポもおんなじで、アレンジになんの工夫がなくても、
飽きさせず一気に聞かせてしまう力量は、主役の歌ぢからでしょう。
アフロビーツ時代となった21世紀、
フジやジュジュといったヨルバ・ミュージックが
すっかり後退してしまった感は拭えませんが、
いまもフジを支えている人たちって、どういった層なんでしょうね。
いつの頃からか、フジの曲名から「アルハジ」を冠した高名そうな人の名が消え、
いわゆる誉め歌のたぐいのレパートリーがなくなっています。
フジの支持層が変わりつつあるんじゃないですかね。
フジに限らずジュジュなどのヨルバ・ミュージックは、
首長、政治家、実業家といったパトロンたちの御前演奏で誉め歌を歌って、
なりわいとしてきた歴史がありますけれど、
そうした側面が薄れてきているんじゃないでしょうか。
Youtube や TikTok にあがっているティリ・アラム・レザーのライヴを観ると、
Tシャツに短パンみたいな普段着姿でライヴをやっている映像が多く、
たまにバンド・メンバーともども伝統衣装を着ているシーンも観れますが、
圧倒的にカジュアルな演奏風景の方が多い印象なんですよね。
観客がダッシュする場面がぜんぜん出てこないのも、変化を感じます。
パフォーマンス会場も、仮説テントの下でやっているようなライヴばかりで、
金持ちたちが集まっているパーティに出向いているような映像は、
ほとんどお目にかかりません。
バリスターやコリントンがぶいぶい言わせてた時代には、
プールのある邸宅やシャンデリアが光る室内などを背景にしたヴィデオが
よく登場しましたけれど、ご本人やファン・クラブのインスタグラムでも、
そういう成金志向はまったく見受けられません。
「アフロビーツなんてシャレのめした音楽は、
オイラたちとはカンケーねえよ」というような貧しい庶民たちが、
いまのフジ・シーンを支えるようになったんでしょうか。
Alhaji Tiri Alamu Leather "VALUABLE" Okiki no number (2023)
2024-02-14 00:00
コメント(0)
ニュー・ボトル・オールド・ワイン ニュー・マサダ・カルテット [北アメリカ]

ジョン・ゾーンくらい、ジャズというジャンルを飛び越えて
多角的な音楽性を発揮する音楽家もいないですよね。
ジョンが日本で活動していた80年代には、ライヴに通ったこともあるんだけど、
CDとなると自分でも意外なほど持っていないんだよなあ。
特にコブラなんて、CDで聴いたって面白くないから、ライヴを観に行ってたんだし。
コブラは聴くものじゃなくて、観るもんだって。もっと言えば、参加するものか。
大友良英がMCを務めるNHK-FMの「ジャズ・トゥナイト」で昨年11月、
ジョン・ゾーン特集をやるというので、
自分の知らないレコードがいっぱい聴けるかと期待したら、
意外にもよく知ってるレコードばかりかかったのでした。
ジョンのレコードは大量で、ごく一部をつまみ食いしてるにすぎないんだけど、
大友と趣味が一致してるのかも。
聞いたことがなかったのは、のっけにかかったニュー・マサダ・カルテット。
これがいきなりカッコイイ!
かつてのマサダから、トランペットをギターに変えて新たに始動した
ニュー・マサダ・カルテットは、第1作を聴いてガッカリしてただけに、
2作目となる新作のカッコよさは意外でした。
ニュー・マサダ・カルテットの第1作にがっくりきたのは、
クレズマーとオーネット・コールマンというコンセプトがすっかり消えていた点。
これじゃマサダじゃないじゃんねえ。
これに落胆して2作目をスルーしちゃったんだけど、マサダという看板を外して聴けば、
ジュリアン・ラージとジョン・ゾーンという組み合わせは刺激的で、スリル満点。
2管だったマサダから1管となり、ジョンと音域の違うギターが参加することで
ハーモニーが豊かとなって、バックの厚みが増しましたね。
それが如実に表れているのが、マサダおなじみのナンバー、
‘Idalah-Abal’ や ‘Abidan’。
‘Idalah-Abal’ は94年のマサダ第1作目 “ALEF”、
‘Abidan’ は95年のマサダ第3作目 “GIMEL” 初出の曲で、
その後に何度も演奏されていますけれど、
ジュリアン・ラージの存在感が大きくて、サウンドに広がりが出ました。
ジョン・ゾーンの雄叫びの鋭さは衰えていなし、瞬発力も切れ味もある。
ソロが短くなったのは、初期のマサダに戻ったかなという印象があって、
全体には落ち着いた印象かな。もちろん暴れてるところは暴れてるんだけど。
ドラマーがジョーイ・バロンからケニー・ウールセンに交代して、
しなやかなノリとなり、疾走一辺倒となる場面はなくなりました。
やはりジュリアン・ラージを起用したジョンの慧眼が、さすがですね。
マサダでヘブライ旋法をハーモロディックにやって、
調性から離れようとしていたのが、ギターが和声へと還元して、
マサダをまた別次元に連れて行こうとしているじゃないですか。
マサダのブランド名を引き継ぐも、中身は別物というチャレンジングな姿勢に、
まだまだ円熟などと言わせない、ジョンの気概を感じます。
最後に蛇足のボヤキ。
ラジオを聴き終えてソッコー注文したものの、郵便事故でアメリカから届かず、
もう一度送り直してもらって、届くまで二か月半もかかってしまいました。
ラジオで盛り上がった気分もすっかり鮮度が落ちてしまって、ガックリでした。
John Zorn "NEW MASADA QUARTET VOL.2" Tzadik TZ8396 (2023)
2024-02-12 00:00
コメント(0)
ライヴはジャズ・ファンク100% マーカス・ミラー [北アメリカ]
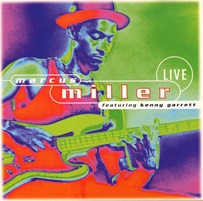

マーカス・ミラーはスタジオ録音よりライヴの方がいい。
それを実感したのが、四半世紀以上前に買ったブートレグでした。
渋谷HMVの試聴機でぶっとんで買ったのをよく覚えています。
当時のマーカス・ミラーの新作 “TALES”(95) が力作なことは
十分理解しつつも、作品としてあまりにもきっちりとプロデュースされすぎていて、
キモチが入り込めなかったんですよね。
ちょうどその直後に出たブートレグ・ライヴに、
そうそう、こういうのが聴きたかったんだよと、快哉を叫んだのでした。
“TALES” は、レスター・ヤング、ビリー・ホリデイ、チャーリー・パーカー、
デューク・エリントン、マイルズ・デイヴィスの生声をサンプリングして、
マーカス・ミラーのブルース/ジャズ観を示してみせた力作。
作品としての完成度の高さは、ルーサー・ヴァンドロスや
デイヴィッド・サンボーンの作品をプロデュースしてきた
マーカスの手腕が十分発揮されたものでした。
思えばマーカスは、再復帰後のマイルズ・デイヴィスにフックアップされただけでなく、
マイルズのアルバムをプロデュースするまでになった人ですからね。
プロデューサーとして磨きがかかった時代でもあったといえますが、
作品主義に傾いたプロデュース・ワークは、スポンティニアスな
ジャズ/フュージョンの魅力を損なっていたことも否めませんでした。
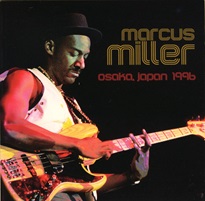
ブートレグ・ライヴは、88年アメリカとだけクレジットされていましたが、
同メンバーによるさらに強力なライヴ盤が出たんですね
(例のいかがわしいキプロス盤レーベルですが)。
“TALES” のリリースに合わせて96年に来日した時のライヴで、
ブルーノート大阪でのステージが丸ごと、2枚のディスクに収められています。
96年の来日ツアーが充実していたことは、
東京・大阪・福岡のブルーノートでのライヴに、
モントルーとカリフォルニアのライブを加えて編集された
“LIVE & MORE” が97年に出されたとおり。
大阪でのライヴは “LIVE & MORE” に3曲収録されましたが、
当夜の全曲を楽しめるこの2枚組はまたとないものです。
メンバーは件のブートレグと同じ、ケニー・ギャレット(as)、マイケル・スチュワート(tp)、
プージー・ベル(ds)、バーナード・ライト(key)に、
モーリス・プレジャー(key)がデイヴ・デローンと交代して
ハイラム・ブロック(g)とレイラ・ハサウェイ(vo)が加わった強力な布陣。
ハイライトはやはり、レイラ・ハサウェイのヴォーカルをフィーチャーした
‘People Make The World Go Round’ ですね。
“LIVE & MORE” では9分に短縮されていましたが、
こちらではノー・カット14分半に及ぶ大熱演を堪能することができます。
ジャム・セッション風なパフォーマンスを冗長に思う人があるかもだけど、
ライヴらしいこういうラフさが、ぼくは好き。
スタイリスティックスが歌ったこの曲、
なぜかジャズ・ミュージシャンがよく取り上げますが、
レゲトンにアレンジしてみせたのは秀逸でした。
そしてケニー・ギャレットがぶち切れた咆哮を繰り返す、
ラストの ‘Come Together’ がスゴイ。
大団円のエンディングのあと、マーカスがバス・クラリネットに持ち替え、
ケニーのアルト・サックスとマイケルのトランペットの3人で
ディキシーランド・ジャズをやらかして、二度目のエンディングへ。
この演出には、会場も大盛り上がり。
いや~、いいライヴだったぁと、上気した顔で会場を出る
観客たちの様子が目に浮かぶアルバムです。
Marcus Miller "LIVE" no label MK42536
Marcus Miller "TALES" PRA 60501-2 (1995)
Marcus Miller "OSAKA, JAPAN 1996" Hi Hat HH2CD3249
2024-02-10 00:00
コメント(0)
たまにはハード・バップも フレディー・ハバード [北アメリカ]

別に昔を懐かしんでいるわけじゃないんだけど、
アート・ファーマー、ヒノテルと続いて、トランペット繋がりで
フレディー・ハバードにまで手を伸ばしたら、これまたハマっちゃいました。
これはめちゃくちゃ久しぶり。いったい何十年ぶりだ?
ハード・バップなんて、まったく聴かなくなっちゃってたからねえ。
フレディ・ハバードの61年録音ブルー・ノート盤。
ハバード23歳の時の録音です。
う~ん、ハバードの若い時って、やっぱ格別だなあ。
ハバードのアルバムでは、このブルー・ノート盤が一番好きかも。
まず曲がいいんだよね。つまんないブルース・ナンバーがないし。
昔のブルー・ノート盤でイヤだったのが、
スタジオでパパッと即興で作ったふうの
やっつけなブルース・ナンバーが入ってたりすること。
なんでもアルフレッド・ライオンが、
1曲はブルースを録音するように指示していたらしんだけど、
ジャズ・ミュージシャンならブルース曲なんてすぐ作れちゃうから、
こんなリクエストしちゃあ、ダメだよなあ。
事前にちゃんと作曲したブルースと、
その場でテキトーに作ったブルースとじゃあ、仕上がりは別物になるよねえ。
「ブルース入れろ」じゃなくて、「ビバップ入れろ」と
ぼくがプロデューサーなら指示するところだけど、
本作にはハバード作曲のゴキゲンなビバップ・ナンバーが入っているんです。
チャーリー・パーカーにオマージュを捧げたと思われる曲名の ‘Birdlike’。
まさしくパーカーのビパップをなぞらえたテーマがカッコいい。
ハバードのスピード感とタイム感の素晴らしさが、いかんなく発揮されています。
フレージングにはアイデイアがほとばしり、
ひらめきのあるプレイにもホレボレするばかりですよ。
一方、バラードの ‘Weaver Of Dreams’ では、
23歳とは思えぬ成熟した貫禄のあるプレイを聞かせていて、
その深みのある美しいトーンにも、ウナらされます。
そういえば 、ラストの ‘Crisis’ を Us3 がサンプリングした
トラックがあったよなあ。 ‘Just Another Brother’ だっけ。
本作は、マッコイ・タイナー、アート・テイラー、エルヴィン・ジョーンズという
当時のマッコイのレギュラー・トリオに、ウェイン・ショーターのテナーと
バーナード・マッキーニーのユーフォニウムとの3管編成。
エルヴィンのどっしりとした安定感たっぷりなバックビートと、
シンバル・レガートで絶妙に表情をつけていくところも、
昔さんざん味わったとはいえ、何十年ぶりに聴いても、やっぱ快感ですね。
Freddie Hubbard "READY FOR FREDDIE" Blue Note CDP7243-8-32094-22 (1962)
2024-02-08 00:00
コメント(0)
日本のクロスオーヴァーの立役者 渡辺貞夫、日野皓正 [日本]


ジャズのヴェテランがクロスオーヴァーを手がけるようになったのは77年と、
前回書きましたけれど、その象徴的なミュージシャンがナベサダ(渡辺貞夫)でした。
76年に、ハンク・ジョーンズ、ロン・カーター、トニー・ウィリアムズと
『アイム・オールド・ファッション』というタイトルどおり、ビバップにまでさかのぼった
伝統回顧作を出して、その翌77年に出したのが、デイヴ・グルーシン、リー・リトナー、
チャック・レイニー、ハーヴィー・メイソンとのクロスオーヴァー作
『マイ・ディア・ライフ』だったんですよ。この振れ幅は大きかったよねえ。
76年といえば、前回も書いたリー・リトナーやアール・クルーのデビュー作や、
クルセイダーズの “THOSE SOUTHERN KNIGHTS” に夢中になっていた年。
あ、ジョージ・ベンソンの “BREEZIN'” も76年だっけか。
そういう下地のあった翌77年に、日本でもクロスオーヴァーが大爆発したわけで、
ナベサダがその旗振り役でした。


それには少し出遅れというか、時差があったのが日野皓正で、
77年にクロスオーヴァーではなく、最高にトガったジャズ作品『メイ・ダンス』を出して、
79年にバリバリのクロスオーヴァー作『シティ・コネクション』を出したんでした。
この二作の振れ幅の大きさは、ナベサダの二作と双璧。
『メイ・ダンス』は、トニー・ウィリアムズとロン・カーターという重鎮に、
新人ギタリストのジョン・スコフィールドを加えたカルテットで、
いまでもぼくはヒノテルの最高作はコレだと思っています。
それに対し、79年に出した『シティ・コネクション』は、
冬のサントリーホワイトCMにタイトル曲が起用されて、大ヒットしたんですよね。
クロスオーヴァーが日本で流行したのは、CMタイアップの影響が大きくて、
同じ年の夏にナベサダの「カリフォルニア・シャワー」が
資生堂ブラバスのCMで大ヒットしたのに味をしめたんでしょう。
いまとなってはナベサダの『カリフォルニア・シャワー』を聴き返すことはないですけど、
ヒノテルの『シティ・コネクション』は、冬の定番といってもいいくらい、
今も聴き続けています。ぜんぜん古くならないんですよね。
本作の魅力はヒノテルのトランペットではなく、アルバムが持つムード、
そのサウンドをクリエイトしたレオン・ペーダーヴィスのアレンジにありました。
オープニングから、流麗なストリングスが誘う
ラグジュアリーな都会の夜を演出するサウンドに酔えるんですよ。
ナナ・ヴァスコンセロスがヴォイスでクイーカの音色を模すパフォーマンスをして、
これがいい効果音となった映像的なサウンドで、サウンドトラックかのような仕上がりです。
レゲエのレの字もないこの曲名が「ヒノズ・レゲエ」なのは、失笑ものなんですが。
またヴォーカル曲をフィーチャーしているのも、このアルバムの良いところ。
ジャズがネオ・ソウルと接近しているいまこそ、再評価できるんじゃないかな。
あとこのアルバムで最高の聴きどころが、アンソニー・ジャクソンのベース。
アンソニーでしかあり得ない、シンコペーション使いや裏拍を使ったリズムのノリ、
経過音やテンション・ノートの独特な使い方がたっぷり聞けて、ゾクゾクします。
タイトル曲「シティ・コネクション」のベース・ワークなんて、
アンソニーの代表的名演だと思うぞ。
中古レコード店の100円コーナーの常連だったシティ・ポップが、
いまや壁に飾られるようになったのと同じく、
見下され続けてきたクロスオーヴァー/フュージョンも、返り咲く日がくるか?
渡辺貞夫 with The Great Jazz Trio 「I’M OLD FASHIONED」 イーストウィンド UCCJ4008 (1976)
渡辺貞夫 「MY DEAR LIFE」 フライング・ディスク VICJ61366 (1977)
日野晧正 「MAY DANCE」 フライング・ディスク VICJ77051 (1977)
日野晧正 「CITY CONNECTION」 フライング・ディスク VDP5010 (1979)
2024-02-06 00:00
コメント(0)
ヴェテランがクロスオーヴァーを始めた77年 アート・ファーマー [北アメリカ]

ふと思い出して聴き返したらハマってしまい、ここ最近ヘヴィロテになってる
アート・ファーマーの77年CTI盤 “CRAWL SPACE”。
アート・ファーマーがフリューゲルホーンに専念して、
バラードのお手本のような優美にして極上なアルバム2作を、
イースト・ウィンドから出した直後だっただけに、
本作のがらりと変わったクロスオーヴァー・サウンドには、驚かされました。

日本が制作したイースト・ウィンドの2作、
特に76年に出た『イエスタデイズ・ソウツ』には、シビれましたねえ。
これぞジャズにおけるバラード表現の最高峰。
トランペットからフリューゲルホーンに持ち替えた時期のアートの作品で、
この楽器の代表作にも数えられると思います。
その続編として翌77年に出た『おもいでの夏』からまもなく
輸入盤店に並んだのが、 “CRAWL SPACE” でした。
あれはたしか大学1年の夏休みだったよなあ。
ぼくのなかで『おもいでの夏』の印象が薄いのは、
直後に聴いた “CRAWL SPACE” の衝撃がデカすぎたからでしょう。
ジャズのヴェテランもクロスオーヴァーを手がけるようになったのが、
ちょうどこの77年が境で、アート・ファーマーはその先駆けでした。
メンバーは、デイヴ・グルーシン(key)、エリック・ゲイル(g)、スティ-ヴ・ガッド(ds)、
ウィル・リー、ジョージ・ムラーツ(b)、ジェレミー・スタイグ(f)という最高のメンバー。
ジョージ・ムラーツは1曲のみの参加で、コントラバスを弾いてます。
クレジットにはありませんが、
このレコーディングの采配をふるったのはデイヴ・グルーシンで間違いないでしょう。
ちょうどこの前年にグルーシンの後押しで、
リー・リトナーやアール・クルーが相次いでデビュー作を出しましたが、
それらの作品とこのアルバムがだいぶ違った趣なのは、レーベルがCTIだからです。
他のCTI作品同様、ニュー・ジャージーのイングルウッド・クリフスにあった
ヴァン・ゲルダー・スタジオでレコーディングされていて、
エンジニアはもちろんルディ・ヴァン・ゲルダー。
グルーシン相棒のエンジニア、
フィル・シェアーやラリー・ローゼンの音作りとはまったく違って、
奥行きのあるレコーディング・ブースの鳴りが、
まさにヴァン・ゲルダー・サウンドになっているんです。
一番それを印象付けられるのが、ウィル・リーのベースで、
これほどファットなベース・サウンドは、当時ウィルが参加していた
ブレッカー・ブラザーズ・バンドでも聞けませんでした。
山下達郎の「Windy Lady」のワイルドなミックスと双璧かな。
ぼくが愛するレコードは、たいてい世間では相手にされていないので、
本作もジャズ名盤ガイドなんかには、決して載らない作品。
CDも日本盤はあるけど、本国アメリカでは出てないし。
ぼくにとってカッコいいアート・ファーマーといったら、ぜったいコレなんだけどね。
[LP] Art Farmer "CRAWL SPACE" CTI CTI7073 (1977)
Art Farmer 「YESTERDAY'S THOUGHTS」 イーストウィンド UCCJ4017 (1976)
2024-02-04 00:00
コメント(0)
リズムの合間を縫う色香漂うこぶし アスマ・レムナワル [中東・マグレブ]


昔のばかりじゃなく、近作のシャバービーも聴きたくなって、
いろいろチェックしてみたら、極上の聴き逃し案件を見つけました。
モロッコのアスマ・レムナワルが17年と19年に出した2作です。
アスマ・レムナワルといえば、10年作のハリージとグナーワのミクスチャーに
仰天させられた人ですけれど、それ以降のアルバムに気付かずじまい。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2012-04-19
う~ん、こんなステキなアルバムを出していたとは。
もうこの時期は、アラブ方面がすでにCD生産を縮小していた頃なので、
メジャーのロターナですら入手困難となっていました。
時機を逸したいまになって入手できたのは、ラッキーだったなあ。
ただアスマもこの19年作を最後に、アルバムを出していませんね。
チュニジアのアマニ同様、シングルは出ているようなんですが。
17年作は楽曲が粒揃いですよ。
ジャラル・エル・ハムダウィやラシッド・ムハンマド・アリがアレンジした曲は、
パーカッシヴなノリを巧みに織り込んでいるところが聴きどころ。
泣きのバラードでもビートが立っていて、
リズムの合間を縫う色香漂うこぶし使いに、ウナらされます。
さすが「ヴォイス・オヴ・グルーヴ」の異名を持つアスマならではですね。
クウェートのマシャリ・アル=ヤティム、スハイブ・アル=アワディが
ルンバ・フラメンカにアレンジした曲も楽しいし、本作にはなんと1曲、
リシャール・ボナがゲスト参加してアスマとデュエットしている曲もあります。
19年作は、ハリージを前面に押し出したアルバム。
サウジ・アラビアやクウェートの作曲家の作品を多く取り上げていて、
アレンジには、新たにバーレーンのヒシャム・アル=サクラン、
エジプトのハイェム・ラーファット、ハレド・エズが参加しています。
ストリングスのアレンジには、エジプトのアレンジャーが多く起用されていますね。
どんがつっか、どんがつっかと、ギクシャクしたハリージのリズムにも、
柔らかなこぶし使いがあでやかに舞って、その歌唱力に感じ入るばかり。
晴れ晴れとした歌いぶりに胸がすきます
歌い口がより柔らかになったようで、ほんと、いいシンガーだよなあ。
スウィンギーなミュージカル調の曲などもあって、粋なムードが楽しめます。
17年作とはまた趣を変えて、2作とも甲乙つけがたい、
秀逸なシャバービー・アルバムに仕上がっています。
Asma Lmnawar "SABIYET" Rotana CDROT1978 (2017)
Asma Lmnawar "AWSAT EL NOUJOUM" Rotana CDROT2027 (2019)
2024-02-02 00:00
コメント(0)




