ミャンマータンズィンの新展開 メーテッタースウェ [東南アジア]

かわいいなぁ、メーテッタースウェ。
まんまるのお月様みたいな笑顔がとっても愛らしく、典型的な福顔ともいえる彼女、
スキー、ジャンプの高梨沙羅選手にも似てる気がしますねえ。
彼女のフェイスブックをフォローしているんですけれど、
ライヴ動画や写真がたくさん載っていて、伝統歌謡歌手としての活躍ばかりでなく、
ミャンマーの中学生の日常が垣間見れて、すごく面白いんです。
学校のテストの点数表を堂々とアップしてたりして、びっくりしちゃうんですが、
きっと成績優秀なんだろうな。すごく利発そうだもんなあ。委員長タイプかしらん。
学校帰りの田舎道みたいなところで友達と一緒にいるところや、おうちで勉強してる様子など、
ほんとにフツーの中学生の女の子という感じで、目を細めてタイムラインを眺めています。
さて、そんな「ガール・ネクスト・ドア」的存在のメーテッタースウェの新作が、
1月10日彼女の誕生日に合わせてリリースされました。
タイトルの『アピョーズィン』は、「処女」という意味だそう(ドギマギ)。
去年の“SANDA KAINAYI NIN DUTIYA SHWE NINSI” のジャケットは、
背伸びしすぎな大人びた化粧が不自然でしたけれど、
今作のジャケットは、そのタイトルゆえか、薄化粧でとってもカワいく写ってます♡
前作は本格的な仏教歌謡集でしたが、
今作は伝統ポップスのミャンマータンズィンですね。
伴奏にバンジョーやマンドリンがフィーチャーされ、世界一のどかなポップスを聞かせます。
時代錯誤とも思える健全歌謡ぶりは、毒のなさが際立っていますけれど、
それが退屈でないのは、ミャンマー独特の不思議メロディゆえ。
うねうねとしたメロディは、インドにもタイにもないミャンマー独自のもので、
本来ミャンマー音楽になかった和声を西洋音楽から取り入れて、
伝統的な旋法とミックスした面白さを楽しむことができます。
今作にはサイン・ワインやサウンといった伝統楽器は登場せず、
伝統音楽の楽器編成と西洋音楽のバンド演奏がスイッチするタイプの
ミャンマータンズィンとはなっていません。
ヴァイオリン、バンジョー、マンドリン、ギター、各種スライド・ギターといった、
弦楽器を効果的にフィーチャーしたバンド演奏となっています。
なかでも耳奪われるのは、「ミャンマー・ギター」とジャケットにクレジットされているギターで、
これはリゾネイター・タイプのスライド・ギターでしょう。
これとはまた他に、スティール・ギターも聞こえてくるし、
伝統歌謡の世界でずっと廃れていたスライド・ギターが、
復興しはじめた兆しを感じさせ、嬉しくなります。
メーテッタースウェのアルバムは、前作の仏教歌謡集でもサイン・ワインを使わず、
サウン中心の弦楽アンサンブルとなっていたし、
ポップスの本作も近年のミャンマータンズィンにはほとんど登場しない
バンジョー、マンドリン、スライド・ギターを積極的に使うなど、
意欲的な取り組みをしていて、サウンドづくりにも注目できます。
十年一日の伴奏スタイルから抜け出し、過去の楽器編成やサウンドも参照しつつ、
新たな歩みをすすめようとするプロダクションは、
天才少女の歌いぶりをさらに輝かせています。
May Thet Htar Swe "APYOZIN" Rai no number (2016)
2016-02-28 00:00
コメント(7)
ダサい10乗ダンドゥットの底力 ラトナ・リスティ [東南アジア]

うわ、ダッせぇ~~~
なんじゃ、このアナクロなアレンジは!
はじめ、口ぽっかーん、やがて、ぎゃははと腹を抱えましたよ。
大げさなブレイクを、これでもかというほどしつこく繰り返す、わざとらしさがたまりません。
あー、悪口に聞こえたら、ごめんなさい。
悪口ではなくて、大衆音楽のあるべき姿といえるアナクロな世界を、
臆面なくも堂々とやってのける腹の座った根性に、魂抜かれてしまったんですよ。
いや~、ダサさもここまで極めれば、すがすがしいってか。
「ダサかっこいい」なんて甘っちょろいもんじゃない。ダサい10乗の突き抜け方ですよ。
東ジャワの西の都市マディウン出身、
90年代からビンタン・ラジオの専属歌手として活躍したラトナ・リスティが歌うダンドゥット。
グマ・ナダ・プルティウィからクロンチョン・アスリのアルバムを出していたのが
記憶に新しいんですけれど、チャンプル・サリもポップもなんでもこいの人だそうで、
まさかダンドゥットまで歌う人とは知りませんでした。
全編通して耳残りするのは、横打ちのクンダンのパーカッシヴな響き。
重低音のビートを轟かせながら、大げさなロック調ギターをぐわんぐわん鳴り響かせるサウンドに、
ぜんぜん負けてないラトナのパワフルなヴォーカルが胸をすきます。
オブリガードをとるスリンに、バックでうっすらとメロディをなぞるシンセと、
90年代のダンドゥット・サウンドをブラッシュ・アップしたサウンドが圧巻です。
Ratna Listy "MANA KEMANA" HP AC386.0215 (2015)
2016-02-26 00:00
コメント(2)
たおやかなヴェトナム情歌 ルー・アイン・ロアン [東南アジア]

ニュ・クインの新作、ちっとも出ませんね。
歌謡ショー「パリ・バイ・ナイト」のステージには立っているようなんだけど、
レコーディングの場からは、ずいぶん長く遠ざかっちゃってます。
ここのところヴェトナムのポップスは、本国のシーンが活発になったせいで、
ニュ・クインなど在外ヴェトナム人の越僑シーンは、すっかり影を潜めた感があります。
そんなことをふと思い出したのは、
ルー・アイン・ロアンなる女性歌手のアメリカ盤CDを入手したから。
ヴェトナム盤ならジャケット裏に政府発行の証紙が必ず貼ってあるので、
証紙がなければアメリカ盤だとわかります。
V Music というレーベルは初耳で、ソフトケースという仕様は海賊盤みたいですけれど、
ちゃんとした正規盤のようです。
ルー・アイン・ロアンという歌手を知らなかったので、調べてみたら、あれ?
この人、越僑歌手ではなく、ホーチミン在住の歌手ですよ。
え? じゃ、なんでアメリカ盤なんだ? う~ん、よくわからん。
VOL 1 と書かれていて、アメリカでリリースされたのが初ってことなのか?
ヴェトナムではかなりの数のアルバムを出していて、中堅どころのようなんですが。
このアメリカ盤、昨年出たばかりのもので、
ニュ・クインとそっくりの歌いぶりに、驚かされました。
デリケイトな節回し、丁寧なヴィブラート、さりげないコブシ使いと、
見事なまでに、ニュ・クインの歌いぶりの良さが共通しています。
ルー・アイン・ロアンは77年生まれ。
ヴェトナム南部キエンザン省キエン・ルオン出身の歌手だそうです。
ダン・バウ、ダン・チャン、ギター・フィムロンなど、
ゆらぐヴェトナムの弦の響きを効果的に配した伴奏で、
民歌調バラードを歌った本作、全曲がスロー、ミディアム・スローで埋め尽くされています。
全16曲78分52秒、いくらなんでも長すぎでしょとは思いますが、
ぼんやり流しながら聴けば、心はヴェトナムの田園に持っていかれます。
Lưu Ánh Loan "NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH" V Music no number (2015)
2016-02-24 00:00
コメント(0)
サンバにアレグリアを取り戻せ アウグスト・マルチンスとクラウジオ・ジョルジ [ブラジル]

そうか、メロディが違うのか。そういうことだったのかぁ。
ここ2か月ほど、ずっともやもやしていたことが、
このアルバムを聴いてようやく解消することができました。あ~、すっきりしたぁ。
そのもやもやとは、ロベルタ・サーの新作に対する違和感。
一度は夢中になった人なのに、こういうことを言うのはツラいんですが、
今のロベルタ・サーにはまったく期待をしていません。
デビュー当初のみずみずしかった歌唱は、もはやどこにも残っていないし、
だからといって、円熟してまた別の味わいを獲得したってわけでもない。
どこにでもいるMPB歌手になっちゃった感が強くて、
なまじ期待がデカかっただけに、がっかり度合も相当なものでしたよ。
で、12年の前作は単なるMPB作品だったので、簡単に無視できたんですが、
新作はまたぐっとサンバ寄りの作品に仕上がっていたので、困っちゃったんです。
バックがとても良くって、楽器の配置も含めアレンジはバツグンだし、
魅力薄になったロベルタの歌いぶりでも、耳をそばだてられること十分なんですが、
それでも強く残る違和感の原因が何なのか、ずっとわからずにいたんですね。
ざっくりいってしまうと、これって、ブラジル音楽なんだろか、という疑問です。
サンバかどうかという以前の問題で、サウンドだけ聴いていると、
カーボ・ヴェルデ音楽の方が近いようにさえ思えるんですよ。
サンバ新世代によるMPBを通過したサンバ・ノーヴォは、
より汎ポルトガル語圏音楽としての色彩を濃くしているように思えます。
それはある意味で、ブラジル成分を薄めてるようにも思えてならないんですよね。
そう感じる理由はどこにあるのか、それがずっとわからずにいたところ、
アウグスト・マルチンスとクラウジオ・ジョルジの共演作を聴いた途端、雲散無霧。
サンバ育ちのMPBシンガー二人が今作で歌っているのは、
エスコーラ・ジ・サンバを最初に作り出したイズマエル・シルヴァのサンバ集なんですが、
冒頭の“O Que Será de Mim” で、うわー、と思わず声を上げてしまいました。
そうそう、こういうメロディなんだよ、サンバってのはさ。これこそサンバだよってね。
こんなこというと、そりゃアンタが古いサンバが好きなだけだろって、若い人に反発されそうで、
はい、それはその通りなんですけど、古いものばっかりが好きなわけじゃないので、
そこは素直に聞いてほしいんですよね。
サンバの原点といってもいい、イズマエル・シルヴァのサンバを聴いた途端、
するっと理解できるのが、メロディの違い。それって、若い人でも、わかるでしょ?
こういうメロディが、21世紀のサンバからまったく聞かれなくなってしまったのは、
まぎれもない事実でしょう。70年代のサンバ・ブームの頃まではあったのにねえ。
サンバの魅力であるサウダージの感覚は、今も昔も変わることはないものの、
イズマエル・シルヴァのサンバにある、溢れんばかりのアレグリアの感覚が、
今のサンバのメロディには失われてしまっているんじゃないでしょうか。
そのせいか、サウダージ感ばかりが強調されるようになってしまったんじゃないのかな。
ロベルタ・サーがハスッパな歌い方になってしまったのに、ぼくがものすごく抵抗を感じたのも、
サンバが持つアレグリアの感覚を、彼女が失ってしまったことに反応したからだったようです。
比べて言うのも悪いですけど、ベッチ・カルヴァーリョがかつての魅力を失ったといっても、
ベッチにはちゃんとアレグリアの感覚があって、ハスッパな歌い方などはしてませんからね。
アウグスト・マルチンスとクラウジオ・ジョルジは、
シコ・ブアルキやパウリーニョ・ダ・ヴィオラの系譜といえるソフトな歌い口のサンバを歌いつつ、
MPBセンスに富んだ曲も分け隔てなく歌ってきた、似た者同士。
イズマエル・シルヴァという古典サンバを、モダンなサウンドに仕上げつつ、
サンバの魅力の本質であるアレグリアの精神を、しっかりと今に継承して歌ってくれています。
Augusto Martins e Cláudio Jorge "ISMAEL SILVA ; UMA ESCOLA DE SAMBA" Mills MIL051 (2015)
2016-02-22 00:00
コメント(0)
ボッサのあるラパ新世代サンビスタ アルフレード・デル=ペーニョ [ブラジル]
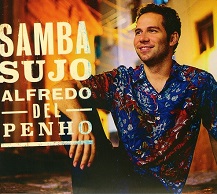
ここんところ、若手のサンバにグッとくることがなかったんだけど、この人はいいねえ。
アルフレード・デル=ペーニョ。
ソフトな歌い口の底に、しっかりとした下町のサンバの味が備わっています。
ちょっとした歌い回しに、サンビスタ独特のニュアンスがにじみ出ていて、
こういう<ボッサ>を持ってる人のサンバを聴くと、頬がゆるみますねえ。
ラパの新世代サンバ・シーンを飾る一人で、クリスチーナ・ブアルキとのサンバ・ジ・ファトほか、
ペドロ・パウロ・マルタとデュオをするなどの活躍をしてきた人だそうで、
今回、インスト作と歌ものの本作2作を同時にリリースしました。
クラウドファンディングで制作したのだそうで、
最大の寄附がシコ・ブアルキだったというのが、なかなか美しい話であります。
フルート、サックス、トランペット、トロンボーンも加わったガフィエイラ・スタイルのサンバで、
コーラスにはマルコス・サクラメント、モイゼス・マルケス、ペドロ・パウロ・マルタといった
同世代のサンビスタが勢揃い。アルフレード自身は7弦ギターや、カヴァキーニョ、バンドリンを弾き、
ショーロの味わいをたっぷり堪能できる伴奏も申し分ありません。
レパートリーも、アルフレード自作の4曲のほか新旧織り交ぜ、
一番古い39年の“Do Outro Lado Do Mundo” から、
シロ・モンテイロが歌ったバーデンとヴィニシウス作の“Garota Porongodons”、
クララ・ヌネスが歌った“Moeda” ほか、ジョアン・ノゲイラ、デルシオ・カルヴァーリョに、
同世代でオルケスタ・インペリアルで活躍するルビーニョ・ジャコビーナの曲まで取り上げています。
そして締めはカルトーラの“A Cor Da Esperança”。うるさがたのファンも降参でしょう。
ここ数年オーソドックスなサンバで、
これといったアルバムに出会えずにいましたけれど、これは大当たりでした。
Alfredo Del-Penho "SAMBA SUJO" no label no number (2015)
2016-02-20 00:00
コメント(0)
故郷カレリアの伝統に立ち返って ヴァルテイナ [北ヨーロッパ]

ずいぶん聴いてなかったなあ、ヴァルテイナ。
ぼくがこのグループを知ったのは、ご多分にもれず、94年の“AITARA”。
言わずと知れたヴァルティナの代表作で、
フィンランドの伝統音楽を大胆にポップ化した、一大名盤でしたよね。
伝統性をしっかりと保持しながら実験性を高めていくという彼女たちの方向性は、
このあとも続いていくわけなんですが、“AITARA” を凌ぐアルバムは現れませんでした。
インダストリアル・ビートを取り入れたりと、野心的な意欲は買いたいんだけれど、
すんません、ぼくにはトゥー・マッチです、みたいなアルバムがずっと続いたもんで。
そんなわけで、最近はすっかり遠ざかっていたヴァルティナなんですが、
故郷カレリアの伝統に立ち返ったという新作、ライスから日本盤も出て評判がいいというので、
試聴してみたら、あら、びっくり。
リフレッシュされたヴァルティナ・サウンドが飛び出てきて、目を見開かされちゃいました。
まず、サウンドが一新。アクースティックなサウンドにがらりと変わりましたね。
カンテラやニッケルハルパといった伝統楽器の響きをメインに打ち立て、
かつてのエレクトロやファンクの要素はぐっと後退しました。
伝統様式の輪唱を聞かせたり、サーミのヨイクもあるなど、
北欧の音楽文化の古層に触れる試みを行う一方で、
ヴァルティナ流のポップなはじけぶりはこれまでどおり健在で、
速射砲コーラス&掛け合いがたっぷりと楽しめます。
なんでも、ロシア領カレリア地方を訪問したことをきっかけに、
自分たちのルーツに立ち返り、この作品を制作したのだそうで、
うん、この方向性、絶対支持だな。
さっそく買ってじっくり聴こうと思ったら、ライス盤はライセンスのドイツ盤。
わ~ん、オリジナルのフィンランド盤じゃないんですかあ。
しかたなくフィンランドから取り寄せ、えらい時間がかかちゃいましたが、ただ今絶賛愛聴中です。
Värttinä "VIENA" KHY Suomen Musiikki Oy KHYCD075 (2015)
2016-02-18 00:00
コメント(0)
円熟したアンニュイ・ヴォーカル ガブリエラ・アンダース [北アメリカ]
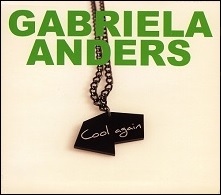
ガブリエラ・アンダースの新作 !?
うわぁ、すんごい、ひさしぶり~。今も歌っていたんだぁ、嬉しいな。
アメリカのボサ・ノーヴァ・ユニット、ベレーザのヴォーカルとして名をあげた彼女ですけど、
ぼくがトリコになったのは、98年のソロ・デビュー作の方。
ボサ・ノーヴァをベースに、ジャズ、ソウル、サルサ、レゲエ、ダブなど、
多様な音楽をブレンドしたサウンドにのせて歌うウィスパリング・ヴォイスに、トキめいたのでした♡
サウンドもとびっきり洗練されていて、スタイリッシュなAORといった趣は、
アメリカより日本で受けるタイプのシンガーのように思えましたね。
あとになって知ったことですけれど、彼女はベレーザ以前に、
セルヒオ・ジョージのプロデュースによる日本向け企画で、
ジリアンとのコンビによるザ・ピーナッツのサルサ・カヴァー集も出していたんですね。
う~ん、日本のプロデューサーもめざといなあ。
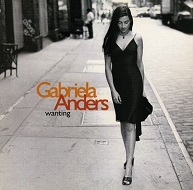

そして、デビュー作の“WANTING” の次に愛聴したのが、4作目の“LAST TANGO IN RIO”。
こちらは、ヒネリの利いたタイトルどおり、バンドネオンをフィーチャーしたのがミソ。
アルゼンチン生まれのガブリエラらしい、ボサ風味のポップスに仕上げていて、
これもいいアルバムだったなあ。
アクースティックなサウンドのテクスチャが、
けだるくアンニュイなガブリエラのヴォーカルとマッチして、爽やかな小粋さを演出していましたね。
あれから十年以上が経ったんですよねえ。
その間には、ガブリエラ・アンダースのそっくりさんがブラジルから登場して、
即ファンになったりもしたんでした。誰のことか、おわかりですか? タミーですよ。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-04-11
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-10-29
昨年出た新作、一目みて、おおっと思ったのは、ジャケットに彼女の写真を使わなかったところ。
メジャー・レーベル時代の、モデルばりの美人を押し出した売れ線ジャケに
彼女自身、ヘキエキとしてたんじゃないのかな。
美人ジャケで内容のないチャラい作品と軽んじられるのを敬遠したのなら、その意気に感ずです。
もともと彼女はカレッジでオーケストレーションを学び、高い作曲能力も持つ、
れっきとした音楽家なんですからね。
タイトルが示すとおり、新作は、クールな彼女の音楽性を前面に押し出した、
シブい作品に仕上がっています。
ご主人のウェイン・クランツのギターに加え、アンソニー・ジャクソンのベース、
オラシオ“エル・ネグロ”エルナンデスのパーカッションといった名手を従えた
7人編成のバンドによる一発録りぽい生演奏で、
よりジャズ・ヴォーカル的な作品に仕上がっています。
オシャレなサウンド・プロダクションから距離を置き、音数を少なめにしたことで、
ガブリエラの音楽性であるクールネスを、よりくっきりとさせた新作。
その円熟した味わいは、オシャレな美人ヴォーカルなんてナメてる人を、驚かせますよ。
Gabriela Anders "COOL AGAIN" East Village Joint no number (2015)
Gabriela Anders "WANTING" Warner Bros. 9-46907-2 (1998)
Gabriela Anders "LAST TANGO IN RIO" Narada 9-46907-2 (2004)
2016-02-16 00:00
コメント(0)
渡辺香津美の80年代最高傑作 [日本]


渡辺香津美がジャズ/フュージョン・ギタリストという枠を超え、
野心溢れる音楽家として才能を溢れさせていた80年代の最高傑作が、
『ガネシア』(82)と『MOBO SPLASH』(85)の2作でした。
当時はLPで聴いていたんですけれど、
85年にCDリリースされた時の音質があまりにショボくて、残念でなりませんでした。
今回、渡辺香津美のデビュー45周年を記念して、ユニバーサルミュージックから
ポリドールdomo時代(1982年~2001年)の19作品がSHM-CD仕様で出るというので、
喜び勇んでこの2作品を買い直しましたよ。
85年に出たCDを今見直したら、なんと3300円もしてたんですねえ。
初期のCDがいかに高かったかがわかろうというものですけれど、
今回は1728円とお値打ち価格でございます。
あらためて今聴き直しても、この当時の香津美は、本当にスゴかった、うん。
1作ごとにどんどんサウンドを進化させていってたもんなあ。
TVCFに起用されて大ヒットとなった『トチカ』(80)は商業的成功を呼びましたけれど、
大きな音楽的な成果を上げたのは、カズミ・バンドの2作目『ガネシア』のほう。
当時もっともプログレッシヴなジャズ・ロックを展開していたプロジェクトのマライアから、
清水靖晃(ts, bcl)、笹路正徳(Key)、山木秀夫(ds)の3人を起用し、
セッション・ベーシストの高水健司を加えたカズミ・バンドは、
軟弱化していくフュージョンに背を向けた、アンチテーゼともいえました。
張りつめた緊迫感あふれる演奏でスタートする「リボージ」から、
極端にハイ・ピッチなチューニングをした山木秀夫のスネア・ドラムが甲高い打音を炸裂させ、
香津美のベスト・パフォーマンスといえる圧倒的なギター・ソロを展開する「ガネシア」、
チンドンをジャズ化したオリエンタル趣味の「カゴのニュアンス」まで、
溢れ出るハイ・テンションなエネルギーは、ただごとじゃありませんね。
これを聴いて、キング・クリムゾンやビル・ブラッフォードを想起する人がいるのも、
むべなるかなです。
カズミ・バンド解消後、香津美はMOBOプロジェクトを始動させますが、
ぼくが評価したいのは、スライ&ロビーを起用して話題をさらった第1弾の『MOBO』(83)ではなく、
MOBOプロジェクトの最終作となった第3弾の『MOBO SPLASH』のほう。
グレッグ・リーのベース(1曲のみ井野信義)に村上ポンタのドラムスのトリオ編成を核に、
鍵盤担当を置かず、香津美がギター・シンセサイザーやサンプラーを駆使して、
先進的なサウンドを作り出しています。実験的ともいえる音づくりをしつつも、
ポップにまとめあげるところは、YMOとの活動を通じて学び取ったセンスなんじゃないのかな。
ゲストにマイケル・ブレッカー、デビッド・サンボーン、梅津和時の3人のサックス奏者を起用し、
それぞれの持ち味にあった曲で、3人の水を得た魚のようなプレイを楽しめるのも、
本作の聴きどころ。「時には文句も」での梅津さんのフリーキーなアルト・ソロも痛快なんですが、
びっくりしたのは「師走はさすがに忙しい」のサンボーンのトリッキーなソロです。
最初は梅津和時がソロを取ってるのとばかり思ってたんだけど、
こんなブチ切れたサンボーンのソロ、ほかじゃ絶対聞けませんよ。
これほどの傑作2枚なんですが、当時も今も、
この2作を香津美の最高傑作と評した記事に、お目にかかったことがありません。
だから、わざわざここで書いているってこともあるんですけれど、
記録的な大ヒットを読んだ『トチカ』(80)や新プロジェクトで話題をさらった『MOBO』(83)ばかりが、
常に香津美の代表作として取り上げられ、名盤ガイドに載ることもなかったのは遺憾千万です。
フュージョンが軽んじられたのも、
セールスや話題を呼んだかどうかという、業界事情に左右されすぎていて、
音楽的な中身できちんと評価する姿勢に欠けていたからなんじゃないですかね。
フュージョンの名盤ガイドを見るたび、毎度違和感を感じるのは、
ライターの確かな耳で選んでおらず、
定評を優先しすぎる編集サイドの問題のように思えてなりません。
 最後に蛇足ながら、
最後に蛇足ながら、今回のSHM-CDリイシュー、
音質もグンとアップしてとても嬉しいんですが、
『MOBO SPLASH』がオリジナル・ジャケット(写真右)でなく、
再発時のジャケットに変更されたのが残念でした。
ホログラム・ペーパーの色合いがキレイで
気に入ってたんですけどねえ。
MOBOの一連の作品は、
アメリカのグラマヴィジョンからもリリースされて、
その際にこの赤いジャケットに変わったんじゃなかったっけ。
デスマスクみたいと敬遠されたのかなあ。
Kazumi Band 「GANESIA」 ユニバーサルミュージック UCCJ4111 (1982)
渡辺香津美 「MOBO SPLASH」 ユニバーサルミュージック UCCJ4116 (1985)
渡辺香津美 「MOBO SPLASH」 ドーモ H33P20050 (1985)
2016-02-14 00:00
コメント(7)
生演奏のフューチャー・ジャズ クリスチャン・スコット [北アメリカ]

真っ赤なバックに、ユニークな形をしたトラッペットを構えるクリスチャン・スコット。
時代の先端を切り拓く気概が表わされているようなデザインがカッコいい。
ここ二十年くらいのジャズの沈滞は、ジャケットに露骨に表われていて、
えらくコンサバになるか、ECMみたいなファイン・アート偏重になるかの両極端が、
時代とシンクロできていない証拠でもありましたよねえ。
どんなジャンルの音楽でも、イキオイがあってシーンが活性化している時って、
名作ジャケットが次から次とたくさん出るもの。
そんなわけで、これは新しいジャズが聞けるのではという予感のジャケ買いであります。
1曲目から、えらくカッコいい音が飛び出してきましたよ。
ドラムンベース調のツイン・ドラムスにのる、クールなメロディ。
ドラムスの音色が面白くって、クレジットをみたら、
一人のドラマーには「パン・アフリカン・ドラムス」と書かれています。
どんなドラムスなんですかね、コレ。見てみたい。
全編通して感心させられたのが、サウンド・テクスチャの良さ。
そして、クリスチャン・スコットの作曲能力ですね。
ポスト・ロックやクラブ・ジャズを通過した世代が、
自分の吸収した音楽を無理なくジャズへフィードバックした感のある、
オルタナ・ジャズ的な音響がすごくいいじゃないですか。
ただ、音楽そのものは、ちっとも新しくはないんですね。
身もふたもなく言うと、クラブ・ジャズ界隈で一時期評判になった、
フューチャー・ジャズを生演奏しただけだもんなあ。
「うわー、こんなジャズ聴いたことない」みたいなオドロキを予感していたので、
その点はやや期待はずれではありました。
とはいえ、しっかりと時代とシンクロした新鮮なサウンドを響かせるジャズであることに、
異論はありません。スケール感もあるしね。
いわば、ヒップ・ホップのマシン・ビートを人力演奏する、
新傾向ジャズと同系統の音楽といえるんでしょうね。
実は、ドラマーがブッチャー・ブラウンのメンバーだというので、ちょっと警戒してたんですよね。
でも、ブッチャー・ブラウンみたいな70年代クロスオーヴァーの焼き直しじゃなくて、ホッとしました。
余計な話ですけど、ブッチャー・ブラウンみたいなバンドをもてはやすのって、
あのくだらないアシッド・ジャズ・ブームを再来させるかのようで、ウンザリします。
あえて注文をつけるなら、もうちょっとソロをなんとかしてくんないかなあ。
トランペットの音色はいいのに、ソロがぜんぜんつまんない。
バリバリでもクールでもどちらでもいいので、
もう少し印象に残る、マシなソロ・ワークをお願いします。
Christian Scott "STRETCH MUSIC" Stretch Music/Ropeadope no number (2015)
2016-02-12 00:00
コメント(0)
タトラ山地の親子トリオ カペラ・マリショフ [西・中央ヨーロッパ]
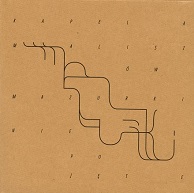
ポーランドの伝統音楽って、あんまりよく知らないんですけれど、
昔聴いた、ポーランド南部タトラ山地に暮らすグラル人の伝統音楽が強烈で、
こりゃ、すごいやとノケぞった記憶が、かろうじてあるくらい。
その頃に買ったCDがわずか3枚あるだけで、中欧の音楽はまったく暗いかぎり。
というわけで、「ミュージック・マガジン」の今月号で松山晋也さんが紹介されていた、
「驚くべき逸材」というポーランドの家族バンドに、がぜんソソられたのでした。
カペラ・マリショフというそのグループ、お父さんと16歳の息子に12歳の娘による3人で、
南部の町メンチナ・マワの出身とのこと。
調べてみたら、なんと、まさしくタトラ山地じゃないですか。
外界との接触の少なかったこの地方には、ポーランド平地部とは異質の音楽が育まれ、
厳しい自然環境に鍛えられた強靭な響きが特徴になっています。
スロヴァキアからルーマニアに連なる、カルパティア山脈一帯の伝統音楽と同系統のもので、
硬く太い音質を好み、鉈を振り下ろすようなビートの激しさと、不均等なリズムは、
ロマ音楽との親和性を強く感じさせますね。
親子3人は、ヴァイオリン、ギター、コントラバス、アコーディオン、ハーディガーディ、
バラバン、フレーム・ドラム、バラバン・ドラムをさまざまに演奏するんですが、
16歳の息子のヴァイオリンがスゴいんです。最初お父さんが弾いてるのかなと思ったんですが、
YouTubeで見て、ノケぞりました。艶やかな音色を聞かせる熟達プレイは、名人級ですよ。
そして、12歳の娘の素朴そのもののブッキラボーな歌が、またいいんです。
タトラ山地の伝統音楽らしい野性味が、たっぷりと表現されています。
タイトルに“mazurek” が付く曲が目につきますが、マズレックとはポーランド語のマズルカのこと。
ご存じのとおり、マズルカはポーランドが生んだダンス・ミュージックなわけですけれど、
この地方流のマズルカは、一般に思い浮かべる優雅なマズルカとは、
まるっきり別物のビートを繰り出します。
この土地に伝わってきた伝統音楽の資質をしっかりと受け継ぎながら、
民俗音楽的な野趣とは一線を画す、現代ならではの洗練を演奏に示すところに、
このグループのインターナショナルな活躍を期待せずにはおれませんね。
Kapela Maliszów "MAZURKI NIEPOJĘTE" Karrot Kommando KK79 (2015)
2016-02-10 00:00
コメント(0)
バルカンからアナトリアへ ソフィア・パパゾグルー [東ヨーロッパ]

ギリシャ歌謡三連チャンの最後は、華ある女性シンガーのアルバム。
ヨルゴス・ダラーラスやグリケリアなどトップ・シンガーたちの眼鏡にかない、
コンサートのコーラス・シンガーとして起用されてきた、ソフィア・パパゾグルー嬢です。
ベルギー、ブリュッセルに生まれ、家族とともにギリシャ、テサロニキへ移住し、
その後6歳の時から歌いはじめたというソフィアは、96年にCDデビューし、
玄人好みのシブい作品を作ってきた人とのこと。
ソロ・アルバムを聴くのは本作が初めてなんですけれど、ライカ新世代というか、
エレフセリア・アルヴァニターキ以降のシンガーという印象を受けました。
ひとことでいえば、かつてのギリシャ歌謡が持っていた飾り気のない無骨さがなくなり、
愛想がよくなったということでしょうか、
歌い口はソフトになり、世界共通言語のポップスが下地になっているのを感じます。
といっても、あくまでもモダン・ライカ路線を貫いているので、
いわゆるグリーク・ポップとは一線を画す、
トラッドなギリシャ歌謡の味わいをちゃんと残しているんですけれどもね。
本作は正調ライカの合間に差し挟まれる、
ラテン調、マヌーシュ・スウィング調、トルコ古典風の曲が聴きものとなっています。
特に、トルコの軽古典~シャルクを思わせる曲にしのばされている、
アラブの香りやバルカンの響きには、ゾクゾクしてしまいますね。
ロック寄りになったり、汎地中海音楽の様相をみせたりと、
練り合わせる要素によって、さまざまな表情をみせるモダン・ライカですけれども、
バルカンからアナトリアに連なるギリシャとトルコの古層に触れたサウンドは、
たまらなく魅惑的です。
Sofia Papazoglou "O HTYPOS TIS KARDIAS MOU" Music Links Knowledge MLK3221 (2015)
2016-02-08 00:00
コメント(0)
ライカのアマチュアリズム マノリス・リダキス [東ヨーロッパ]
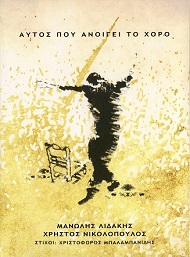

ヨルゴス・ダラーラスの新作同様、去年の暮れに出たマノリス・リダキスの新作も大当たり。
う~ん、ひさしぶりにギリシャ歌謡の波が、来てるかも。
ダラーラスに次いでぼくの好きな男性歌手が、マノリス・リダキスなのです。
マノリスもレンベーティカのルーツを受け継いだライカを歌う人で、
ぼくが最初にこの人にホレ込んだのは、92年作の“KARAVI APOPSE TO FILI”。
「無頼」や「闇」といった部分ばかりでないレンベーティカの甘美な側面を、
ノスタルジックな響きの中に表わした大傑作でした。
男っぽいダラーラスとは違い、草食系優男ふうのマノリスは、
クレタ島出身で、82年にアルバム・デビュー。
ぼくが初めて聴いた92年作当時、すでに中堅どころとなっていて、
色男ふうのモテそうなルックスをしてたんですけれど、
最近の写真を見ると、すっかり中年太りのオヤジ面になってしまいました。
メロウな哀愁味を持ち味としていて、歌唱力より味で聞かせる、
カエターノ・ヴェローゾに似たタイプの歌手といえます。
新作は、ライカの名作曲家フリストス・ニコロポウロスの作品を歌ったアルバム。
ブズーキ、バグラマー、ピアノ、アコーディオンという完全アクースティックの編成で、
余計な装飾など何一つない、生粋のギリシャ歌謡たるライカを聞かせてくれます。
時代の流行に左右されず、ポップスにも色目を使わない、
頑固一徹なまでに真正ライカを貫くマノリスらしく、
今作も朴訥とした変わらない歌い口で、嬉しくなります。
ヴェテランになっても、歌がうまくならないのが、この人のいいところ。
良い意味でアマチュアぽさを残しているところに、
みずみずしさを失わない秘訣があるんじゃないかな。
そんなところも、いつまでたっても歌がへたっぴーなカエターノとそっくりですよね。
Manolis Lidakis "AFTOS POU ANIGI TO HORO" To Rima A003 (2015)
Manolis Lidakis "KARAVI APOPSE TO FILI" Portrait 471638-2 (1992)
2016-02-06 00:00
コメント(0)
レンベーティカ・ミーツ・ラグタイム ヨルゴス・ダラーラス [東ヨーロッパ]
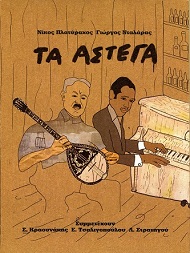
2016年のベスト・アルバム、一番のり~♪
昨年末にギリシャでリリースされた、ヨルゴス・ダラーラスの新作でっす。
老いを隠せないハリス・アレクシウの歌いぶりにショックを受けたせいか、
ギリシャ歌謡からすっかり遠のいた、今日この頃なんでありますが、
やっぱヨルゴス・ダラーラスは、帝王だわ。さすがです。
歌いぶりこそ、ヴェテランの安定感にウナらされますけれど、
さまざまな音楽家とコラボしながら、野心的なアルバムを作り続ける
チャレンジングな姿勢がすごい。攻めてますよねえ。
新作は、映画音楽作曲家のニコス・プラティラコスとの共同制作で、
いつものミノスからではなく、ニコス・プラティラコスが関係する映画配給会社のレコード部門、
フィールグッド・レコーズからのリリースとなっています。
ニコス・プラティラコスは、アテネのミュージック・コンセルヴァトリーでピアノと作曲を学んだ後、
ハノーヴァーとケルンの大学で演劇と舞踏を学んで、ドイツの映画音楽界で成功した人とのこと。
現在もドイツとギリシャを行き来しながら活躍をしているそうですが、
ダラーラスとタッグを組んだ今作は、映画『スティング』を思わすムードの、
安酒場のアップライト・ピアノで弾かれるラグタイムに始まります。
このオープニングのインスト・ナンバーから、いつものダラーラスと違う予感を漂わせますが、
なんと今回の新作、レンベーティカとラグタイムをミックスするというアイディアを実現したもの。
これがなんとも絶妙な組み合わせというか、
こういう音楽が昔から存在したんじゃないのかと思わせるほどの相性の良さをみせます。
鄙びたジューク・ジョイントの雰囲気を横溢するラグタイム・ピアノの響きに、
レンベーティカらしいブズーキやバグラマーの弦の響きが混ぜ合わさり、
そこにディキシーランド・ジャズふうの金管・木管の管楽器が華を添えていくサウンド。
レンベーティカとラグタイムのどちらも、裏町の影をひきずっていて、
この二つの音楽が抱える闇が、妖しく共鳴するのを感じます。
レンベーティカがハッシシを吸わせるアテネの外港ピレウスのテケー(バー)から生まれたように、
ラグタイムが1880年代のセント・ルイスのサロンや売春宿から生まれたのは、
世界の大衆音楽史からみれば、偶然なんかじゃありませんよね。
ダラーラスも、いつもよりざらりとした舌触りを残す苦味の強い歌い口を聞かせていて、
枯れた味わいのなかに、ブルージーなやるせなさを溢れさせています。
裏街道を行く哀愁を濃厚に表わしつつ、
意外にもノスタルジックなムードをまとっていないのは、この音楽が仮想のものだからでしょうか。
ランディー・ニューマンのアイロニーに通じる現代性を感じさせます。
Gergos Dalaras & Nikos Platyrachos "TA ASTEGA" Feelgood 521003300094 (2015)
2016-02-04 00:00
コメント(0)
エチオピアン・ビューティー ハリマ・アブドゥラマン [東アフリカ]


う~ん、典型的なアムハラ美人ですね。
ハリマ・アブドゥラマン、エチオピアの若手女性歌手です。
主役の名前とアルバム・タイトル、曲目だけはアルファベット表記があるものの、
それ以外はびっしりアムハラ文字で埋め尽くされていて、クレジットが読みとれましぇ~ん。
聴いてみれば、アバガス・キブレワーク・シオタのプロダクションとイッパツでわかる、
打ち込みベースのエチオピアン・コンテンポラリー・サウンド。
スタジオの調整卓の前に立つ3人の男性の写真がジャケットに小さく載っていて、
左に立っているのがアバガス・キブレワーク・シオタだとわかります。
髪と髭に白いものが混じっていて、シオタも年を取りましたねえ。
90年代にゼロ年代と、エチオピアン・ポップス一時代のサウンドを築いたシオタのサウンドは、
ホーン・セクションを使えない低予算のハンデの中から生み出されたもの。
打ち込み中心とはいえ、カラフルなアレンジで、数多くの名作を作り出してきました。
今作でも、レトロな感触のあるオルガンの響きを取り入れるなど、
曲ごとに鍵盤の音色を巧みに使い分けた、丁寧なサウンド作りが楽しめます。
主役のハリマはのびのびと若々しい歌声を響かせ、
アムハラ独特のメロディを、巧みなこぶし使いで歌っています。
アディス・アベバ出身だそうで、デビュー作“KALEHBET” を12年にリリース、
本作が2作目なのかもしれません。
伝統色はあまりないんですけれども、クラールをカクシ味に使った“Tizita” では、
曲名のとおりアムハラ叙情に溢れた情歌を聞かせてくれます。、
シオタ・マジックともいえる引き出しの多いプロダクションにのせて、
全15曲計78分マイナス1秒という長さも、飽きずに楽しませてくれますよ。
Halima Abdurahman "SEMAY" ARDI Entertainment no number (2015) [Ethiopia]
Halima Abdurahiman "SEMAY" Nahom no number (2015) [US]
2016-02-02 00:00
コメント(0)




