フォーキー・ソウル・フロム・ロンドン リアン・ラ・ハヴァス [ブリテン諸島]

ジャケ買いです。
縮れ毛で顔は隠れていても、チャーミングな表情に、一目惚れしちゃいました。
ぼくには初めての人で、すでにこれが3作目という、
ロンドンのシンガー・ソングライターとのこと。
お持ち帰りして、ファクトリー・シールをはがすと、見開きジャケットの内側には、
いかにもロンドンらしい風景をバックにした、モノクロームの写真が2枚。
エキゾティックな顔立ちで、めっちゃキュートな女性じゃないですか。
おとうさんはギリシャ人、おかあさんはジャマイカ人だそうで、
リンダ・ルイスみたいなポジショニングのシンガーでしょうか。
物憂げにつぶやくような歌い出しに、ムードのある歌声だなと思わせるんですが、
感情の高まりとともに、声量をたっぷりに、パンチのある声も繰り出せる人です。
振れ幅の大きな表現力を持っているんですけれど、
曲の流れのなかで、それがとても自然に移ろっていくので、
「歌い上げる」といった印象を与えないところが、ミソ。
のびやかで、ドラマのある歌を歌える人ですね。
ジャケットの粗い粒子のモノクロームが、音楽のマチエールをよく表しています。
ギターやベースの手弾き感やシンバルの響きがライヴ感たっぷりで、
ざっくりとした粗い音づくりに、ミックスの手腕を感じます。
ギターはリアン自身が弾いているんですね。
アルペジオやコード・バッキングのギター・ワークを聴いていると、
フィル・アップチャーチとかアーサー・アダムスといった
往年の歌伴の職人芸を思わせ、感心させられました。
ソングライティングも巧みで、5拍子のラスト・トラックなんて、
変拍子好きにはココロくすぐられます。
13年に来日して‘Tokyo’ なんて曲を作っていたり、東京で撮ったMVがあったり、
プリンスとも共演していたなんてエピソードも、いまごろようやく知りました。
17年にも来たそうなので、また観ることもできるかな。
その時を楽しみに待ちましょう。
Lianne La Havas "LIANNE LA HAVAS" Warner 0190295254889 (2020)
2020-08-19 00:00
コメント(2)
UKトリニダーディアン・ポエトリー アンソニー・ジョゼフ [ブリテン諸島]

ブリティッシュ・トリニダーディアンの詩人で小説家のアンソニ・ジョゼフは、
ブリティッシュ・レゲエのダブ・ポエトリーで知られる
リントン・クウェシ・ジョンソンと肩を並べる、カリブを出自とする社会運動家です。
スパズム・バンドを率いた初期のアルバムでは、アヴァンギャルドなアフロ・ジャズをやり、
ミシェル・ンデゲオチェロがプロデュースした14年のソロ作では、
ギル・スコット・ヘロンをホウフツとさせる、
アフロビートからスピリチュアル・ジャズを横断したサウンドを聞かせていました。
これまで気になりつつも、横目に見てるだけの人だったんですが、
18年にこんなスゴイ作品を出していたとは、知りませんでした。
自身のルーツであるトリニダードに軸足を置いたアルバムで、
トリニダード・トバゴの首都ポート・オヴ・スペインで、
現地のミュージシャンたちを多く迎え入れて、レコーディングしています。
リリース当時に聴いていれば、間違いなく年間ベスト・クラスの傑作で、
なぜこれほどの作品が、話題にもならなかったんでしょう?
本作の前に、“CARRIBEAN ROOTS” というアルバムを14年に出していて、
スティールドラムのアンディ・ナレルを招いて、
カリブのルーツに立脚した音楽へ転身していたんですね。
いわば本作はその続編にあたるもので、トリニダードに直接乗り込み、
スティールドラムのカリスマ・プレイヤーで、
スティール・オーケストラのリーダーとしても名高い
レン“ブグジー”シャープをはじめ、ラプソの3・カナルにブラザーズ・レジスタンス、
グレナダ出身のトリニダーディアン・シンガーのエラ・アンダール、
シンガー・ソングライターのジョン・ジョン・フランシスなどが参加しています。
オープニングは、ヨルバ起源の海の女神、イエマンジャに捧げるチャントをする
エラ・アンダールをフィーチャーした‘Milligan’。トーキング・ドラムを絡ませて、
奴隷文化が育んだアフロ・カリブの古層にさかのぼってアルバムをスタートさせると、
続いてブグジーのスティールドラムをフィーチャーしたソカの‘Sans Souci’。
スティールバンドのエンジン・ルームと呼ばれる
パーカッション・アンサンブルのリズムがハジけまくります。
そして、政治意識の高いラプソのアーティストとの共演が続きます。
3・カナルをフィーチャーした‘Bandit School’ はPファンクとソカのミックス、
ブラザー・レジスタンスをフィーチャーした‘Dealings’ は、
アフロビートとソカのミックスでダブ・ポエットしたといった趣。
いずれもアンソニーとの相性は抜群ですね。
それにしても、3・カナルもブラザー・レジスタンスも久しぶりすぎて、ビックリですね。
彼らのCDをよく聴いていたのは、もう20年近くも前のことで、
以来まったく動静が伝わってこなかったけれど、ちゃんと現地では活躍していたんだな。


チャトニー(インディアン・ソカ)ふうの‘Jungle’ は、
トリニダードのインド系住民ばかりでなく、
イギリスのインド系移民も視野に入れたものでしょうか。
ちなみにこの曲は、アンソニーの娘のミーナ・ジョゼフが歌っています。
ホーンやストリングスも加えた贅沢な音作りで、
トリニダードの過去と現代を往来した一大音楽絵巻、聴き応えタップリです。
Anthony Joseph "PEOPLE OF THE SUN" Heavenly Sweetness HS185CD (2018)
3 Canal "HEROES OF WHA?" Rituals CO8106 (2001)
Brother Resistance "WHEN DE RIDDUM EXPLODE" Rituals NTCD116 (2001)
2020-07-24 00:00
コメント(2)
UKブラック・ジャズのレガシー シード・アンサンブル [ブリテン諸島]
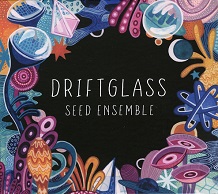
またも南ロンドン発のジャズの好アルバムに遭遇しました。
アルト・サックス奏者で作曲家のキャシー・キノシ率いる
シード・アンサンブルのデビュー作。
1年半も前に出ていたんですね。
アルト・サックス、テナー・サックス、トランペット2、
トロンボーン、チューバの6管を擁し、
ピアノとローズには、レギュラー・メンバーのサラ・タンディと
ゲストのジョー・アーモン=ジョーンズが、曲により弾き分けています。
ジョー・アーモン=ジョーンズが弾く曲では、
ネオ・ソウルのサウンドがぐっと前面に出てくるところが、いかにも彼らしいところ。
そしてチューバには、シャバカ・ハッチングスのサンズ・オブ・ケメットのメンバーとして
注目を浴びるテオン・クロスが起用されていて、ここでも大活躍をしています。
重厚なベース音で始まるオープニングに、60年代ジャズの予感を覚えていると、
ホーン・セクションの分厚いハーモニーが炸裂する大胆なコンポジションとアレンジに、
いきなり金縛りにあってしまいました。テオン・クロスのチューバばかりでなく、
ミゲル・ゴロディのトランペットも、目の覚めるようなソロを聞かせてくれます。
シード・アンサンブルには、60年代から現代のジャズまで
シームレスに繋がるジャズの語法が共有されていますね。
政治・社会問題に強くコミットしたキャシーのシアトリカルなコンポジションを、
ネオ・ソウルやアフロビートのサウンドを加味しながら、
スケールの大きな一大音楽絵巻に仕上げる手さばきは、
黒人解放運動とジャズが連動していた時代から連綿と続く、
ジャズのブラックネスを継承していると言って過言ではないでしょう。
シェリス・アダムス=バーネットのソウルフルなヴォーカルや、
Xana のポエットにMr Ekow のラップが飾る現代ジャズの意匠は、
そのままUKブラック・ジャズのレガシーの証明となっています。
SEED Ensemble "DRIFTGLASS" Jazz Re:freshed no number (2019)
2020-06-24 00:00
コメント(0)
ロンドンの奇才二人が起こすケミストリー トム・ミッシュ&ユセフ・デイズ [ブリテン諸島]
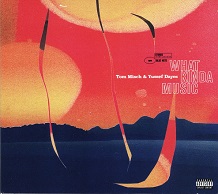
SNS世代を象徴するかのような鮮烈なデビューを果たした、
自分のベッドルームをスタジオにするロンドンの音楽家、トム・ミッシュの新作が面白い。
18年の話題作“GEOGRAPHY” の非凡ぶりには、ぼくも舌を巻きましたけど、
新作はユセフ・デイズとの共演作で、ブルー・ノートから配給されるというニュースに、
どんな作品なのかと、聴く前からワクワクしていました。
ユセフ・デイズは、鍵盤奏者のカマール・ウィリアムスと、
ユセフ・カマールというユニットで活動しているドラマー。
ユセフ・カマールでは、ブロークン・ビートやダブステップ、グライムを、
生演奏に置き換えた音楽をやっていて、ぼくにはUKジャズのドラマーというより、
クラブ・ミュージック通過後のクロスオーヴァー感覚を持ったセッション・ドラマー
というイメージがあります。

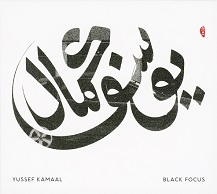
ビートメイカーでもあるトム・ミッシュとのコラボは、
ビート・ミュージックになるのかなと思ったら、
かなり繊細に組み立てられた仕上がりを見せていて、
ビート・ミュージックのセッションといったラフさはどこにもありませんね。
全体にメランコリックなサウンドとなっているのが特徴で、
多幸感に溢れた“GEOGRAPHY” とは対照的な、
グルーミーな世界を生み出しているのが新鮮です。
ユセフ・デイズのアナログ感いっぱいのドラムスは、
音色や音質も、UK独特のセンスを強く感じさせます。
スネアのロールやフラムなんて、トニー・アレンを思わせるところもありますよ。
ベースのロッコ・パラディーノが加わったトラックでは、
レゲエ/ダブのニュアンスがぐっと前に出てきますね。
キックを含む低音域がファットで、スネアのちょっと詰まったような音色が耳残りします。
シンバル系の高音が広がらないようにして、サウンド全体をコンパクトに収めているので、
クラブ・サウンドのトラックメイクに近い感覚で聞けます。
アメリカのヒップ・ホップやR&B流れのグルーヴ感たっぷりなドラミングとは、
まったくタイプが違いますね。
トム・ミッシュならではのドリーミーなサウンドと混じり合って、
この二人ならではのケミストリーが生まれているところが妙味。
トムのメロディアスな才能と、ユセフが持つUKブラックのクラブ・サウンドが、
絶妙なバランスをみせています。
ベッドルームから外の世界に飛び出た若き天才は、ワールド・ツアーも成功させましたが、
新たな変化を求めてチャレンジしたコラボレーションは、トムに自信を与え、
さらなる音楽領域の可能性を広げたのではないでしょうか。
Tom Misch & Yussef Dayes "WHAT KINDA MUSIC" Beyond The Groove/Blue Note 2812124273 (2020)
Tom Misch "GEOGRAPHY" Beyond The Groove BTG020CD (2018)
Yussef Kamaal "BLACK FOCUS" Brownswood Recordings BWOOD0157CD (2016)
2020-05-23 00:00
コメント(0)
アフロフューチャリスティック・エレクトロニカ オニパ [ブリテン諸島]
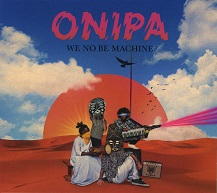
無国籍アフリカ音楽バンドのオニパの新作は、なんとストラットから!
さすがストラットから出すと、ジャケットもがぜんアカ抜けますねえ。
前作のパチもんなジャケットとはえらい違いで、
アフロフューチャーリスティックな意匠となっています。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-02-02
オープニングのタイトル曲が、
そんなアフロフューチャリスティックなエレクトロニカで、
しょっぱなからこのバンドの音楽性を、リスナーに提示してくれます。
ハチロクのアフリカン・リズムを叩く太鼓の生音と、
電子音を共存させたトラックの作り込みが巧みで、
エレクトロニックな均等なビートを、これぞアフリカンといった
ダンス・トラックに変換させてみせる手腕が見事です。
バラフォンの反復フレーズとシンセ・ベースのスペイシーな響きが、
絶妙なコズミック・サウンドを作り出す‘Fire’や、
アフリカン・ヒップ・ホップの‘Free Up’、
ジュピテール&オクウェスのボフェニア・ロックを思わせる、
電化リケンベ(サンプリングか)とドラムスが疾走する‘Nipa Bi’、
ノイジーなフルベの笛(サンプリングか)がフィーチャーされる‘Onipa’ など、
聴きどころ満載。
もろにガーナイアン・ハイライフなメロディで、コーラス・パートがスークース調になる
‘Yenimno’ のようなナンバーがあったり(ちなみにヴォーカルはガーナ人)、
割合まっとーなルンバの‘Makoma’ ‘Kon Kon Sa’ があるところも、
いいチェンジ・オヴ・ペースとなっています。
生音と電子音のいいとこどりをして、アフリカらしい肉体性を存分に発揮させた、
痛快なダンス・ミュージックです。
Onipa "WE NO BE MACHINE" Strut STRUT217CD (2020)
2020-03-30 00:00
コメント(0)
ネオ・ソウル・ジャズの俊英 ジョー・アーモン=ジョーンズ [ブリテン諸島]

モーゼズ・ボイドの新作で、まっさきにクレジットの名前を探したのが、
鍵盤奏者のジョー・アーモン=ジョーンズでした。
‘2 Far Gone’ でのプレイに、おぉ!と引き込まれたからです。
ジョー・アーモン=ジョーンズと知って、なるほどとナットク。
多彩な才能を次々と輩出している南ロンドンのジャズ・シーンで、
アシュリー・ヘンリーやカマール・ウィリアムズなどとともに、
ジョーも注目を集めるピアニストの一人で、
先日エズラ・コレクティヴの一員として、来日したばかりですね。
東京公演がコロナ騒ぎで飛んじゃったみたいですけれど。
そういや、昨年出たセカンドをまだ聴いていなかったなと思い出し、
早速試してみました。18年のデビュー作“STARTING TODAY” や
話題のエズラ・コレクティヴ同様、なぜか手は伸ばさずにいたんですけれど、
今回はなんかヒラメクものがあって、試聴もせずに購入。
カンは当たったというか、まさに出会うべきタイミングだったのか、
すっかりトリコとなっています。
冒頭‘Try Walk With Me’ のゆるやかなダブ的空間に、
たゆたうヴォーカルやトランペットがざまざまな色合いを変化させるサウンドに
グイグイ引き込まれました。バックで叩いているモーゼズ・ボイドも、
グルーヴを保ちながら、さまざまな変化をビートに加えています。
途切れずに2曲目の‘Yelow Dandelion’ へなだれ込んでいくところも、
すごくいい感じ。
グナーワに触発されたらしいタイトルの3曲目は、
グナーワのグの字もなく、グナーワの影はどこにも見当たらず。
ご本人、ホントにグナーワを知ってるのかと疑っちゃいますが、
それとは関係なくネオ・ソウル的なサウンドの質感がめちゃくちゃ気持ちいい。
モーゼズ・ボイドの新作と共通しているのは、
ヒップホップやR&Bの影響より、
クラブ・ミュージック経由したサウンドを特徴としていること。
ジェストのラップがフィーチャーされるトラックを聴いていても、
USとUKの違いを感じますよねえ。特にジョーの作品は、
ネオ・ソウルと現代的なジャズを結び付けたサウンドが魅力的。
ラスト・トラックのふわふわとした軽いタッチのアフロビートなど、
いかにもこの人らしいな。
Joe Armon-Jones "TURN TO CLEAR VIEW" Brownswood Recordings BWOOD0207CD (2019)
2020-03-04 00:00
コメント(0)
クラブ・ミュージックからジャズへ モーゼズ・ボイド [ブリテン諸島]

モーゼズ・ボイドがエクソダス名義で18年に出した“DISPLACED DIASPORA” の記事で
「すでにボイドはここから一歩も二歩も歩みを進めているはず」と書きましたけれど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-12-10
まさにそれを証明する新作が届きました。
重くもたったビートを繰り出す生ドラムスと、打ち込みを並走させた
冒頭のトラック‘Stranger Than Fiction’ から、
ジャズとビート・ミュージックを融合させるボイドのネライが明確に伝わってきます。
ジャズの生演奏をもっとも強く打ち出した‘BTB’ は、
ジャズ寄りのアフロ・ファンクといったアプローチで聞かせるトラック。
分厚いホーン・セクションは、アフロビートを思わせるアレンジを聞かせるものの、
ベースは自在にうねりまくり、ドラムスは一定のビートしつこくを刻み続け、
余計なオカズを加えず変化をつけないところは、
アフロビートのリズム・セクションのフォーマットとは真逆です。
ところが、演奏全体としてはアフロビートを感じさせるのが面白いんだなあ。
アフロビートの新解釈というべき、良きお手本ですね。
後半になると、ポスト・プロダクションの打ち込みと
生演奏を並走させるトラックが多くなり、
モーゼズの生ドラムスが打ち込みのビートに聞こえたりして、
音像が脳内変換するような不思議な感覚に囚われます。
ぼくはこれを聴いていて、20年くらい前によく聴いていた、
ブロークン・ビートやハウスなど、西ロンドン界隈でクロスオーヴァー化していた
クラブ・ミュージックを思い起こしました。




そこで、まっさきにCD棚から引っ張り出した、
IGカルチャーのメイン・ユニット、ニュー・セクター・ムーヴメンツが、どハマリ!
ボイドがポスト・プロダクションで作り込んだドラムのパーツごとの音色の選択なんて、
完全に相通じるじゃないですか。
この当時西ロンドンでアフロ、ソウル、ハウス、テクノと拡張していた
エクレクティックなクラブ・ミュージックのサウンドの質感が、
モーゼズ・ボイドがここで試みているサウンドと地続きなのを感じます。
20年ぶりくらいに聴き返したニュー・セクター・ムーヴメンツが、めっちゃ新鮮で、
さらに棚を掘り起こしてアフロノウトやネイサン・ヘインズなどなど、
当時のクラブ・ミュージック熱を再燃させるきっかけとなった、
モーゼズ・ボイドの新作でした。
Moses Boyd "DARK MATTER" Exodus no number (2020)
New Sector Movements "DOWNLOAD THIS" Virgin 7243-8-49922-2-4 (2001)
Afronaught "SHAPIN’ FLUID" Appollo/R&S 049CD (2001)
Nathan Haines "SOUND TRAVELS" Chilli Funk CFCD005 (2000)
v.a. "CHILLI FUNK RECORDINGS V DUB TRIBE SOUND SYSTEM" Chilli Funk CFCD007-1,2 (2001)
2020-03-02 00:00
コメント(2)
通俗アラブ・ムードを捨てよ ヤズ・アハメド [ブリテン諸島]

ヤズ・アハメドの前作は、何度か聴くうちに、
オリエンタリズムむき出しの楽想がだんだん鼻についてきて、
記事にしたことをちょっと後悔していました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-02-23
出自はアラブでも、西洋文化のもとで育った彼女のような若い音楽家が、
自身のルーツを傾倒したにしては、あまりにインチキなアラブ風メロディを
作曲するのって、いかがなもんですかね。
だいいち彼女のエキゾ・センスって、
「キャラバン」や「ナイト・イン・チュニジア」くらい古臭くない?
ご本人はラビ・アブ=ハリルに影響を受けたと発言しているので、
それなら、もっとちゃんとアラブ古典を勉強すればいいものを。
まあ、そんなわけで、新作1曲目のミスティックなムードを漂わせるイントロで、
あぁ、またか……と思ったんですけれど、
展開していくうちに、どんどんと熱気を帯びていき、
前作とはだいぶ様相の違う展開の演奏となっていきます。
前作がムード・ミュージック臭い短い曲が並んでいたのとは打って変わって、
本作は10分前後の長尺曲ばかり。作編曲の才能を存分に発揮した、
ラージ・アンサンブルの醍醐味を堪能できるジャズ作品となっています。
サウジ・アラビアの映画監督ハイファ・アル=マンスール、
公民権活動家のルビー・ブリッジズにローザ・パークス、
パキスタンの人権活動家マララ・ユスフザイ、女性参政権を主張したサフラジェット、
パーキンソン病と闘いながら演奏活動を続ける
イギリス人サックス奏者バーバラ・トンプソンなど、
女性のロール・モデルとなる活動家たちに捧げられた本作は、
曲のテーマごと、趣向の凝らされた楽曲が並びます。
アラビック・ムードの1曲目から一転、
2曲目はいきなりセカンド・ラインのリズムで始まるという意表を突く展開。
13年にマララ・ユスフザイが国連本部でスピーチした内容を、
ヤズを含む複数の女性演奏家たちによって朗読した‘One Girl Among Many’ は、
スティーヴ・ライヒの‘Different Trains’から着想を得たもののようです。
いずれの曲も、コンポジションと即興のバランスがとてもよく、
練られた編曲に感心しました。
ヤズとともに新世代UKジャズ・シーンを引っ張る女性プレイヤーたち、
サックスのヌバイア・ガルシア、ピアノのサラ・タンディ、ギターのシャーリー・テテー、
トランペットのシーラ・モーリスグレイのプレイもそれぞれの個性を十分発揮しているし、
前作に続いてヴィブラフォンが重要な役割を果たしています
(奏者はルイス・ライトからラルフ・ワイルドに交代)。
前作でもレディオヘットのカヴァーがもっとも秀逸だったように、
オルタナティヴ・ロック、ミニマル・ミュージックなどの要素を、
ジャズのラージ・アンサンブルにまとめ上げるところに、
この人の才能が光ります。
その意味でも、通俗なアラブ・ムードはジャマなだけ。
アラビック・ジャズを標榜するなら、もっと真摯にアラブ音楽を学んでほしいですね。
Yazz Ahmed "POLYHYMNIA" Ropeadope RAD506 (2019)
2019-11-11 00:00
コメント(0)
グライム世代の南ロンドン・ジャズ アシュリー・ヘンリー [ブリテン諸島]

南ロンドン、なんかもうスゴすぎる。
才能ある音楽家が、次から次へとわいてくるかのように登場しますね。
91年生まれというアシュリー・ヘンリー、
すでに先行EPの2枚で話題となっているピアニストですけれど、
最新作のフル・アルバムを聴いて、その才能に脱帽しました。
ジャズをベースとしながら、ヒップ・ホップ、R&B、ブロークン・ビート、
ベース・ミュージックを横断するその自在ぶり。
なんかもう一度「クロスオーヴァー」という語をあてはめたくなるサウンド・デザインで、
あらためて、「フュージョン」(=融合)とは設計思想が違うと強調したくなりますねえ。
60年代にジャズ・ロック、70年代にクロスオーヴァー、80年代にフュージョン、
90年代にスムース・ジャズとラベリングされた音楽は、
すべて地続きのように捉えられ、白眼視され続けてきましたけれど、
再評価ではなく、もう一度評価を仕切り直す必要があると思います。
このアルバムも、切り取りようによっては、ジャズ・アルバムにも、
ヴォーカル・アルバムにも、ビート・アルバムにも聞こえます。
それでいてアルバムの統一感はしっかりとあって、
ヘッドハンターズ以降のハービー・ハンコックの
エレクトリック・ジャズ(クロスオーヴァー)を、
グライム世代の感性で更新したといえるんじゃないですかね。
参加ミュージシャンも、同世代のクリエイターがずらり並んでいて、
南ロンドン仲間のモーゼズ・ボイドの参加は当然として、
アメリカからトランペットのキーヨン・ハロルドと、
ドラムスのマカヤ・マクレイヴンを起用したのは、大正解でしたね。
ロイヤル・アカデミーを卒業し、クラシックの教育を十二分に兼ね備えたスキルも、
リリカルで美しいタッチに、はっきりと表れています。
Ashley Henry "BEAUTIFUL VINYL HUNTER" Sony Music 19075891582 (2019)
2019-09-28 00:00
コメント(0)
70年代クロスオーヴァー+ドラムンベース レベッカ・ナッシュ&アトラス [ブリテン諸島]

レザヴォアを愛聴しているところに、また嬉しいジャズ新作が届きました。
今度は話題の南ロンドンから登場した新グループ。
ブリストル育ちのピアニスト、レベッカ・ナッシュが率いるアトラスのデビュー作です。
きらきらとした鍵盤のネオ・ソウル的な音感で誘いながら、
やがてうねるようなドラミングによって、雄大なサウンドスケープを生み出していく
アンサンブルが聴きもののグループですね。
マット・フィッシャーのしなやかで軽快なスティックさばきと、
前へ前へと推進していくエネルギーのあるドラミングが、がっしりとした骨格のある
バンド・サウンドを組み立てていますよ。
レベッカ・ナッシュはブリストルで育っただけに、
マッシヴ・アタックやドラムン・ベースに影響を受けたというのもうなずけるんですが、
‘Tumbleweed’ の細かくビートを割っていくドラム表現など、
生のドラムンベースとも受け取ることもできそうな気もするなあ。
中盤のサラ・コールマンのヴォーカルがフィーチャーされる曲は、
ジョニ・ミッチェルとイメージがダブったりしますよ。
トランペットのニコラス・マルコムとレベッカのエレクトリック・ピアノの絡みが、
エディ・ヘンダーソンとハービー・ハンコックを思わせるところもあり、
アトラスには、70年代前半のクロスオーヴァー・サウンドに、
ドラムンベースを合体させたような魅力がありますね。
エレクトロニクスも交えたハードなインプロヴィゼーションを展開するラスト・トラックまで、
聴き応え満載の作品です。
Rebecca Nash and Atlas "PEACEFUL KING" Whirlwind Recordings WR4748 -2019-
2019-09-06 00:00
コメント(0)
繊細にして豪胆なギター・トリオ プレストン・グラスゴウ・ロウ [ブリテン諸島]
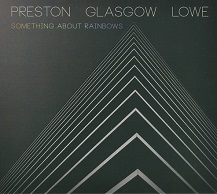
CDショップのジャズ・コーナーであれこれ試聴していたところ、
まるでシュミじゃないサイケなジャケットのCDに、ピンとくるものがありました。
全然知らない人でしたけれど、キレのあるコンテンポラリー・ジャズ・ギターに、
こりゃあいい、と買ってみたところ、家に帰って聞いてみれば、ええぇ~?
まるで違うエレクトロな音楽が飛び出し、ビックリ。
なるほど、これならジャケどおりだわなと、ひとりごち。
どうやら試聴機に間違ったCDが入っていたようで、翌日再訪したところ、
「すみません、これ全然別のCDですね」と店員さん平謝り。
試聴機に入っていたのは、こちらですと差し出されたのは、
UK新世代ジャズのプレストン=グラスゴウ=ロウの新作。
なーるほど、彼らか! それならナットクだわ。
おととしのデビュー作がお気に入りとなっていた、プレストン・グラスゴウ・ロウ。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-05-09
デイヴィッド・プレストンのメカニカルなギターに、ケヴィン・グラスゴウの6弦ベース、
ローリー・ロウのドラムスが緊密に絡み合ってインプロヴァイズする快感は、
2年ぶりの今作も変わりません。
ローリー・ロウのしなやかなドラミングが、
バンド・サウンドにあざやかなコントラストをつけ、
ギターとベースにフリーなスペースを与えることで、
バンドのダイナミズムを拡張しているところが、この3人組のキモ。
パット・メセニー、アラン・ホールズワース、ロバート・フリップに通じる
デイヴィッド・プレストンのギター・テクニックも舌を巻くばかりなんだけれど、
そのギター・サウンドを輝かせているのが、ローリーのドラミングといえます。
多くのトラックをデイヴィッドが作曲していますが、
今作の聴きどころは、ケヴィン・グラスゴウが作曲した2つのトラック。
そのひとつが、アルバム中もっともロックぽいサウンドとなったタイトル・トラック。
オーヴァードライヴしたベースがごつい響きをあげて、
重厚なメタル・ロックを繰り広げます。
一方、ドイツの現代音楽の作曲家ハンス・ヴェルナー・ヘンツェの頭文字を
曲名に取ったラスト・トラックは、十二音技法を取り入れたもので、
このトリオの音楽性をさらに前進させましたね。
繊細にして豪胆な新世代ジャズ・ギター・トリオ、次作は間違えないように買おう。
Preston Glasgow Lowe "SOMETHING ABOUT RAINBOWS" Whirlwind Recordings WR4731 (2018)
2019-07-12 00:00
コメント(0)
あれから22年 イライザ・カーシー [ブリテン諸島]
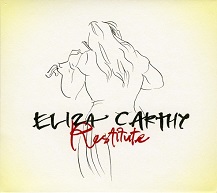
うぉ~、この大物感、ハンパないね。
もはや父マーティン・カーシー、母ノーマ・ウォーターソンの名前を出さずとも、
イングリッシュ・フォークのヴェテランと肩を並べる貫禄が備わった、イライザ・カーシー。
新作は原点回帰ともいうべき、直球勝負の伝統音楽アルバムです。
オープニングの曲で、ハンマー・ダルシマーの響きを鈍くしたような音色に、
何の楽器だろうかと思えば、どうやらヴァイオリンの弦を、箸で叩いているらしい。
う~む、こういうところも、フォーク・シーンのイノヴェイターとして活躍してきた、
型にはまらないイライザの面目躍如だなあ。
パワフルな無伴奏歌ともども、伝統の型をなぞらない逞しさが彼女にはありますね。
ノース・ヨークシャー、ロビン・フッド湾にある、
イライザの自宅の寝室で録音されたという本作、
父マーティン・カーシーのギターに、コンサーティーナやベースなどが数曲で加わるほかは、
イライザが弾くヴァイオリンやヴィオラを多重録音しただけのシンプルな構成だからこそ、
伝統音楽家としてのイライザのスケールの大きな音楽性が、浮き彫りになっています。
イライザを初めて観たのは、両親と3人で来日した97年1月のこと。
ウォーターソン:カーシーの初アルバムでその歌声とフィドル演奏を披露し、
ソロ・デビューを果たしたばかりの、まだ初々しい時代でした。
ジャケットのイライザの美少女ぶりに、サインを入れてもらうのが忍び難く、
バックインレイに3人のサインをもらったんだっけ。


あのライヴも思い出深いなあ。
新年明けて間もない5日の夜、ハコは新宿ロフトでした。
イライザの真っ赤に染めたショートヘアとスニーカーの、
いかにも現代っ子らしい姿が瞼に焼き付いていますよ。
当時まだ19歳だったんだよねえ。
床をがんがん蹴るステップもパワフルなら、ボウイングも思いのほか激しく、
ニコニコしながらヴァイオリンを弾きまくるチャーミングな姿に、
うちのコたちもこんな女のコに育ったらなあ、なんて思いながら観たもんでした。
ライヴが終わり、翌日が年明けの初出勤日だったので、
単身赴任先だった群馬へと向かったんでした。
東京は雨だったんですけど、熊谷を過ぎたあたりから雪になって、
新前橋の駅に降り立つと、そこは一面の銀世界。
幻想的な景色にたじろぎながら、シンと静まり返った雪降る街を一人、
新雪を踏みしめながら、単身寮へと向かったことが忘れられません。
Eliza Carthy "RESTITUTE" Topic TSCD599 (2019)
Waterson:Carthy "WATERSON:CARTHY" Topic TSCD475 (1994)
2019-06-26 00:00
コメント(0)
ハイランドと東欧を繋ぐバグパイプ ブリーチャ・キャンベル [ブリテン諸島]
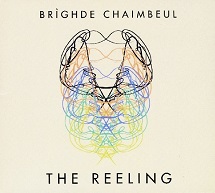
スモールパイプス(小型バグパイプ)の持続するドローンのディープな音色に、
金縛りとなってしまう深淵な音楽。これを演奏しているのが、
まだハタチの女性だというのだから、驚かされます。
ブリーチャ・キャンベルは、スカイ島の音楽一家に育ったパイプ奏者。
16年にBBCラジオ2のヤング・フォーク・アワードを受賞、
翌17年にはスコッツ・トラッド・ミュージック・アワードの新人部門に
ノミネートされたという若き実力者です。
7歳の時、女性バグパイプ奏者ローナ・ライトフットの
演奏を聴いて感銘を受け、パイパーを志したのだそうで、
現在82歳となったそのローナもレコーディングに参加し、
パイプのフレーズを教えるときの口三味線を披露しています。
こういう口三味線って、一般的にはリルティングと呼ぶと思うんですけれど
ライナーのクレジットには、キャントリッチド Canntaireachd と書かれていて、
調べてみたら、スコティッシュ・ガーリックでパイプを模したチャントをそう呼ぶんだそう。
18世紀のハイランドの古謡をはじめとする伝統曲をレパートリーに、
スモールパイプスのソロ演奏を聴かせるんですが、
凄みさえ覚えるリズムの深さには圧倒されるばかりです。
興味深いのは、ブルガリアのバグパイプ音楽もレパートリーとしていることで、
なんでも17年にブルガリアを訪れた時、
ブルガリアのバグパイプ、ガイダを知って惚れこみ、
ガイダの演奏曲を習ってきたんだそうです。
バグパイプ音楽でハイランドと東欧の古層をつなぐ試みは、
今後の彼女の音楽を発展させていく、大きなファクターとなりそうですね。
ブラックアイル半島の由緒ある教会でレコーディングされたという本作、
プロデューサーを務めるイダン・オルークのフィドルや、
コンサーティーナが加わる曲もありますが、
ブリーチャの重量感あるスモールパイプスが、圧倒的な存在感を示した作品です。
【追記】2019.6.22
「ブリッド・チェインビョール」とあやふやなカナ表記を書いていたところ、
山岸伸一さんから「ブリーチャ・キャンベル」と発音することを教えていただきました。
修正させていただきます。山岸さん、ありがとうございました。
Brìghde Chaimbeul "THE REELING" River Lea RLR003CD (2019)
2019-06-22 00:00
コメント(2)
ウェールズの詩情 シァン・ジェイムズ [ブリテン諸島]

胸の奥底に染み入ってくる歌。
世俗にまみれたぼくのような人間の穢れた魂をも、
救済してくれるかのようなその響きに、陶然としてしまいます。
ウェールズを代表する女性歌手、シァン・ジェイムズのアルバムを聴くたび、
他の歌手にはない聖性を帯びたものを感じます。
不信人者にもそんな気持ちを抱かせる、スペシャルな歌い手さんですね。
10作目となる今作でも、ウェールズの伝承曲をもとに自作も交えながら歌う、
これまでと変わらない作品に仕上がっていますが、
特に純度を頂点にまで高めた今作は、ひとつの芸術様式に到達したのをおぼえます。
冒頭の無伴奏歌の清らかな声は、これが59歳の声かと思わずにはおれません。
女性の年齢を言う失礼を許していただきたいんですが、
その美しい声は、「珠玉」としか表現できない深みがあります。
聴き終えた後に残る深い余韻は、アルバムの数を重ねるほどに、
その色を濃くしているようで、今回は訳もなく涙をこぼしてしまいました。
シァン自身が弾くウェルシュ・ハープとピアノに、
シンセサイザーやギターがそっと寄り添うシンプルなサウンド。
たまに、パイプやチェロなどが彩りを添えるほか、余計な音を重ねるものはいません。
そうした伴奏こ支えられるシァンの清らかな歌声は、夢の中へ誘う美しさに満ちたものです。
それは、いわゆるエンヤ以降イメージしやすくなったケルト・ミュージックでもあり、
ともすればヒーリング・ミュージックとも受け止められかねませんが、
良い音楽を聴き分ける耳のある者なら、
そんな卑俗にまみれた音楽とは、次元の違うものであることがわかるはず。
この人を知ったのは、96年の3作目“GWEINI TYMOR” でした。
以来、全作ではありませんけれど、折に触れ聴き続けてきましたが、
ウェールズの詩情をここまで磨き上げた作品は、他にありません。
傑作の誕生です。
Siân James "GOSTEG" Recordiau Bos RBOS030 (2018)
2019-05-01 00:00
コメント(0)
伝承歌の世界観 クレア・ヘイスティングス [ブリテン諸島]

スコットランド、きてるなあ。
ハンナ・ラリティにファラと、注目のアルバムが続出じゃないですか。
去年大注目したアイオナ・ファイフのミニ・アルバムが出るというので、
心待ちにしていたところ、それとはまた別の嬉しいアルバムが届きましたよ。
それが、ウクレレを弾き歌う女性歌手クレア・ヘイスティングスのソロ第2作。
女性4人組のトップ・フロア・テイヴァーズのメンバーとしても活動している人ですね。
今回はウクレレはお休みで、歌に徹し、エレクトリック楽器の使用もなし。
ギター、フィドル、ピアノ、アコーディオンの4人が伴奏を務めています。
今作のテーマは「旅」で、伝承曲を中心に自作の2曲と、
アメリカのルーツ・ロック・バンド、ブラスターズのメンバー、
デイヴ・アルヴィンの‘King Of Callifornia’ を取り上げています。
デビュー作と変わらぬ凛とした粒立ちの良い発声に、ホレボレとしますねえ。
スコットランドの女性歌手って、声の透明感に共通性があって、
イングランドとはまったく異なる土地柄を感じます。
そして、きりりとしたシンギングをもりたてる伴奏がまた見事です。
たった4人の伴奏とはいえ、フィドルを多重録音するなど、
丁寧なアレンジが施されていて、クレジットはありませんが、
通奏低音のように流れるシンセやエフェクトも、ごく控えめながら使われています。
アルバムの最後を締めくくるのは、
18世紀起源とされるイングランドの伝承曲‘Ten Thousand Miles’。
ニック・ジョーンズの名唱でも知られるこの唄は、
アメリカでは‘Fare Thee Well’ のタイトルで知られ、
ボブ・ディランやジョーン・バエズほか、
多くのフォーク・シンガーが取り上げてきた旅の唄ですね。
クレアはこの曲を無伴奏の多重唱で歌っていて、
旅立つ恋人との別れを、映画のワン・シーンのように描写します。
伝承歌の世界では、歌い手が余計な感情を加えず、
詩と旋律が生み出す情感だけで、雄弁な物語となりうることを、
このトラックは証明しています。
Claire Hastings "THOSE WHO ROAM" Luckenbooth LUCKEN002CD (2019)
2019-03-12 00:00
コメント(4)
オルカディアン・フォーク・カルテット ファラ [ブリテン諸島]

ハンナ・ラリティのデビュー作の記事にいただいたコメントで、
山岸伸一さんから教わった、スコットランド、オークニーの女性4人組ファラの新作。
フィドル3人とピアノというユニークな編成のグループで、今作が2作目。
オープニングのポルカ、ジグ、リールの三連メドレーから、もうエキサイティング。
キリリと立ち上る3台のフィドルの響きに、
後ろからピアノがゴンゴンと打楽器の如く押し出していく
若々しいプレイに、ワクワクしちゃいましたよ。
曲はすべて彼女たちのオリジナルですけれど、
どれもオークニーの伝統に沿っていて、知らずに聞けば、伝承曲としか思えませんね。
ソングの可憐なみずみずしさにも、目を見開かされます。
う~ん、若いって、ほんとにいいねえ。
コーラス・ハーモニーも音を重ねて厚みを作るのではなくて、ずらしてレイヤーしたりと、
さりげないんだけど、アレンジに繊細な工夫が施されているのがよくわかります。
ピアノもアクースティックばかりでなく、‘See It All’ ではエレクトリックを使い、
柔らかな音色使いで、心あたたまるサウンドを作り出していますね。
ラスト・トラックは、短編映画を観るかのようなドラマを感じさせるインスト演奏で、
アルバムの聴後感をとても豊かなものにしていて、満足度はもう100%。
作編曲のアイディア、音色の選択、リズム・センスと、
いずれも抜きん出た音楽性を持つこの4人組、すごい才能です。
前作の垢抜けないフォークぽいジャケット・デザインから、
一転ロック・バンドかとみまがうカッコいいジャケットになったのにも、
オルカディアン・フォーク・カルテットとしての気概を感じさせます。
Fara "TIMES FROM TIMES FALL" Fara FARA002 (2018)
2019-02-18 00:00
コメント(2)
アフリカン・クロスオーヴァー・エキゾティカ オニパ [ブリテン諸島]

エスニック雑貨屋なんかでよく売ってる、似非アフリカンな仮面。
アフリカ現地の土産物屋に並んでいるコピー商品なら、まだマシな方で、
インドネシアのバリ島あたりで作っているフェイクものをよく目にします。
アフリカの仮面もオセアニアの仮面も見分けがつかない人なら、
なんとも思わないんでしょうけれど、プリミティヴ・アートを愛する者には、
そのあまりなガラクタぶりに、目をそむけずにはおられません。
インチキな匂いがぷんぷん漂うジャケ画に、そんなことを思いながら、
まったく期待せずに聴いてみたんですが、あらららら。
意外にもオモロイどころか、ゴキゲンじゃないですか。
バッタもんの面白さを超越した、アフリカン・ダンス・ミュージックです。
コノノを思わすアンプリファイド・リケンベをフィーチャーした1曲目、
スークース・ギターが活躍するアフロ・ディスコの2曲目、
ヘヴィーなシンセ・ベースに、
コラやカルカベが絡み合うトラックをバックにラップする3曲目、
シャンガーン・エレクトロをパクった4曲目と、
アフリカのトライバルなダンス・ビートを縦横無尽にクロスオーヴァーするオニパは、
イギリス白人ギタリストとガーナ人シンガーのデュオ。
ギタリストのトム・エクセルは、サウンドウェイやトゥルー・ソーツなどのレーベルで、
プロデューサー兼エンジニアとして活躍してきた人で、
なるほどそういうキャリアの人なら、思いつきそうなアイディアですね。
そして歌っているのが、コンゴ人でもなけりゃ、
シャンガーンやツォンガでもないガーナ人で、
アカン語で歌っているっていうんだから、笑っちゃいます。フェイクやん!
アルバムはさきほどの4曲に、
ハウス、ガラージュ、エレクトロニカのリミックス・ヴァージョン3トラックを加えたもの。
クラブでかけたら大ウケしそうな、理屈抜きに楽しめるダンス・アルバムです。
レス・バクスター、マーティン・デニー、アーサー・ライマンのセンスで、
クラブ・ミュージックを通過させた
アフリカン・クロスオーヴァー・エキゾティカでしょうか。
Onipa "OPEN MY EYES" Wormfood MWF005 (2018)
2019-02-02 00:00
コメント(0)
スウィンギン・アイリッシュ・フィドル ジェリー・オコナー [ブリテン諸島]
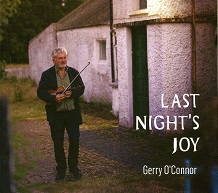
もう一丁、とびっきり清廉な1枚を。
こちらはアイリッシュで、歌ものでなく、インスト演奏。
ラ・ルーやスカイラークの活躍で知られるフィドルの名手、
ジェリー・オコナーのソロ作です。
バンジョー奏者のジェリー・オコナーじゃありませんよ、念のため。
ジェリーほどの名手ながら、これが2作目というのも意外ですけど、
ソロ・アルバムはなんと14年ぶりというんだから、
寡作ぶりにも程があるというもの。
ジェリー・オコーナーは北部ラウス州のダンドーク出身。
母親のローズ・オコナーは、多くの演奏家を育てた
ラウスを代表するフィドル奏者で、ジェリーもローズからフィドルを仕込まれたんでした。
ジェリーの息子のドーナル・オコナーも優れたフィドル奏者で、
ギターも弾くほか、プロデューサーとしても活躍しています。
本作では、フィドル、テナー・ギター、ピアノを演奏していて、
プロデュースとミックスも手がけています。
最初に挙げた同姓同名のバンジョー奏者も参加して、
なんとも軽やかでスウィンギーなフィドルの名人芸を堪能することができます。
伴奏のピアノやギターがリズムを生み出すのではなく、
ジェリーのボウイングがこのスウィング感をもたらしているところが、スゴイですね。
ダンスせずにはおれないグルーヴ感いっぱいのプレイで、身体がむずむずします。
アイリッシュ・ダンスのステップを習いたくなりますねえ。
うきうきするリールやジグに、歌ごころ溢れる美しいエアのほか、
1曲米国産ポルカをやっているのも聴きものです。
ジェリーの軽妙なスタイルとすごくマッチしていますね。
ジャケットの暗い写真があまりに不釣り合いな、
春の光を想わすすがすがしいアルバムです。
Gerry O’Connor "LAST NIGHT’S JOY" Lughnasa Music LUGCD966 (2018)
2019-01-07 00:00
コメント(0)
スコットランドの新星デビュー ハンナ・ラリティ [ブリテン諸島]

またしても清廉な歌声がスコットランドから届きました。
18年のBBCラジオ、スコットランド若手伝統音楽家賞を受賞した、
グラスゴーの若き新進女性歌手のデビュー作。
このクリアーなクリスタル・ヴォイスに、
ココロときめかないトラッド/フォーク・ファンなんて、いないでしょう。
ただきれいに歌うだけじゃありません。
アルバム1曲目を飾るのは、ジーニー・ロバートソンが歌った伝承曲の
‘The Moon Shine On My Bed Last Night’ なんだから、
スコットランド古謡へのまなざしも確かです。
才能豊かな若きハンナを盛り立てるのが、ベーシストでプロデューサーの
イアン・バートン、シボーン・ミラーやキム・カーニーなど、
多くの女性トラッド/フォーク・シンガーのプロデュースを務めるほか、
ジャズ・フィールドでの活躍もめざましいミュージシャンです。
そのせいか、イントロや間奏などなにげないところで、
おやっと思わせるハーモニーやフレージングを聞かせるところは、イアンの仕業でしょうか。
トラッド/フォークの味を損なわないように、目立たないところで、
カクシ味的なアレンジが利いています。
ハンナの歌いぶりで引き込まれたのが、
ディック・ゴーハンが歌った伝承曲の‘Erin Go Bragh’。
ひそやかに歌う曲とは違う力の入った歌いぶりに、
はっちゃけた素の顔が垣間見れて、とても魅力的でした。
フィル・カニンガムのアコーディオンをバックに、
デイヴィ・スティールの曲で静かに締めくくった、アルバム・ラストまで、
コンテンポラリーなフォーク・サウンドも抑制が利いていて、満足感が得られます。
Hannah Rarity "NEATH THE GLOAMING STAR" Hannanh Rarity HR085NEA (2018)
2019-01-05 00:00
コメント(2)
ロンドンのブラック・ディアスポラ モーゼズ・ボイド・エクソダス [ブリテン諸島]

鳴り響くパトカーのサイレンに続いて、ヨルバ語のチャントが吟じられ、
エレクトロ・ファンク・グルーヴがすべり込んでくるオープニングに、
胸をぎゅっとつかまれました。
その昔、ロンドンにひと月ほど滞在した時によく通った、
ブリクストンやトッテナム、セヴン・シスターズといったアフリカ系移民街の街並みが、
まざまざと目の前に蘇ったからです。
UK新世代ジャズで注目を集めるドラマー、
モーゼズ・ボイドが率いるエクソダス名義の初アルバムは、
タイトルが示すとおり、アフリカ/カリブ系移民子孫のまなざしを投影した作品で、
ブラック・ディアスポラ意識の高い音楽家たちが数多く集まっています。
ドミニカ人の父とジャマイカ人の母のもとに生まれたモーゼズ・ボイドは、
南ロンドンのキャットフォード生まれ。
南ロンドンのアフリカ系移民街ペッカムにもなじみがあり、
ペッカムのメイン・ストリート、ライ・レーンをタイトルに掲げた曲も収められています。
このアルバムで大きな存在感を放っているのが、
トリニダッド・トバゴにルーツを持つアルト・サックス奏者、ケヴィン・ヘインズですね。
ケヴィンはアフリカン・ダンス・カンパニーのパーカッショニスト兼ダンサーから、
ジャズ・ミュージシャンへ転身した人で、キューバでサンテリアの音楽を学び、
バタやヨルバ語を習得したというユニークな経歴を持っています。
ケヴィン率いるグルーポ・エレグアが参加した4曲は、
オープニングの‘Rush Hour/Elegua’ ほか、
チューバとギターが冴えたプレイを聞かせる‘Frontline’ に、
ファラオ・サンダースやサン・ラが思い浮かぶ‘Marooned In S.E.6’、
バタとエレクトロが交差する‘Ancestors’ と、
都会に野生を宿らせたナマナマしい演奏ぶりに、ドキドキさせられます。
新世代スピリチャル・ジャズともいうべき、熱のある演奏を聞かせる一方で、
UKジャマイカンのザラ・マクファーレンが歌うジャズ・バラードや、
テリー・ウォーカーをフィーチャーした、
ヒップ・ホップ/ネオ・ソウルのトラックもあるのは、
エレクトロのプロデューサーとしての別の側面を表わしたものなのでしょう。
コンクリートとアスファルトの街に響き渡るバタのリズムと、
アフロフューチャリスティックな響きを獲得したエレクトロニカが、
熱量のあるドラミングによく映えた本作がレコーディングされたのは、15年のこと。
すでにボイドはここから一歩も二歩も歩みを進めているはずで、
多角的な才能を発揮する俊英ドラマーの今後にも、期待が高まります。
Moses Boyd Exodus "DISPLACED DIASPORA" Exodus no number (2018)
2018-12-10 00:00
コメント(0)
40年後のソフト&メロウ ホンネ [ブリテン諸島]

通勤ウォーキングのお供に、
ロンドンのエレクトロ・デュオ、ホンネの新作が加わって、はや2か月。
CRCK/LCKS、キーファー、リジョイサーと連続プレイして違和感がないのは、
ジャジーなアーバン・テイストのサウンドに、
共通するセンスがあるからでしょうね。
ホンネの音楽性はエレクトロ・ポップですけど、
ジャズ新世代がデザインするサウンドと、親和性があるのを感じます。
プロフェットのサウンドとか、ネオ・ソウル的な音色の選択に対するこだわりは、
すごくありそうじゃない?
昼と夜をイメージした楽曲を半々に収めたというものの、
メロウなムードは、昼夜ともに共通していて、
ややファンキーな昼とメランコリックな夜といった程度の違い。
ジャジーなヒップ・ホップ・センスのビートメイクは、テン年代らしいものの、
スムースで聴き心地のよいソングライティングの才は、
「ソフト&メロウ」全盛期を思わせます。
歌詞に「東京」や「渋谷」が出てくるほど、日本大好きデュオだということは、
解説を読んで初めて知りましたけど、デュオ名は日本語の「本音」から取っていて、
彼らのレーベル名が「建前レコーディングス」だというんだから、面白い。
「ソフト&メロウ」を称したクロスオーヴァー・サウンドが日本で流行した40年前には、
将来、東京に憧れるロンドンの若者が「ソフト&メロウ」なサウンドを作るなんて、
想像だにしなかったよなあ。
だって、当時のロンドンといえば、パンク全盛の時代だもんねえ。
40年前を知る者には、時代の移ろいを感じずにはおれません。
ホンネ 「ラヴ・ミー/ラヴ・ミー・ノット」 アトランティック WPCR18074 (2018)
2018-10-17 00:00
コメント(0)
イングランドの香り豊かに レイチェル・マクシェイン [ブリテン諸島]

バンドの名義が添えられているものの、
主役のフィドル以外のメンバーは、メロディオンとギターの3人だけ。
最小人数バンドを率いるレイチェル・マクシェインは、
イングランドのフォーク・ビッグ・バンド、ベロウヘッドで、
フィドルとチェロを担当していた人のこと。
ベロウヘッドといえば、08年のセカンド作“MATACHIN” をよく聴いたけど、
レイチェルの名を意識したのは、今回が初めてです。
ソロ・アルバムとしては、デビュー作から9年ぶりというのだから、
ずいぶんと長いインターヴァルです。
さすがにキャリアを積んだ人なので、演奏にはゆとりがあるし、アイディアも豊富。
イングランドの有名な古謡‘Two Sisters’‘Sheath And Knife’や、
イングランドの古い詩にレイチェルが曲をつけた‘Sylvie’など、
ベロウヘッド時代のワールド・ミュージック的なアプローチとは違って、
真正面から伝統音楽に向き合った作品となっています。
きりっとしたレイチェルのシンギングがいいんです。
粒立ちのよいギターの響きと、豊かなメロディオンの音色によく映えるヴォーカルで、
これぞイングリッシュ・フォークといった味わいを感じます。
レイチェルが弾くヴィオラの深い音色も、演奏に奥行きを与えていて、
たった3人とは思えないサウンドを生み出していますよ。
ゲストには、プロデューサーのイアン・スティーブンソンのウッド・ベースのほか、
マンドリン、エレクトリック・ベース、パーカッションが参加。
メロディオン奏者ジュリアン・サットン作のインスト曲メドレーには、
オーボエが加わり、映像的なサウンドスケープを繰り広げるほか、
アルバム・ラストの‘Green Broom’では、
トランペット、トロンボーン、チューバのブラスを加えて華やかに締めくくり、
気持ちの良い聴後感を残します。
Rachael McShane & The Cartographers "WHEN ALL IS STILL" Topic TSCD596 (2018)
2018-09-29 00:00
コメント(0)
歌の宝庫アバディーンシャーから アイオナ・ファイフ [ブリテン諸島]

声が立っている。
第一声を聴いただけで、才能に恵まれた歌い手だということが、すぐにわかります。
スコットランド北東部のアバディーンシャーから登場した、
アイオナ・ファイフのデビュー作。
まだハタチという若さで、その清廉な発声の粒立ちに、
ジュリー・ファウリスのデビュー時を思い起こしました。
アバディーンシャーといえば、バラッドの宝庫として知られる土地柄。
フランシス・ジェームズ・チャイルドの『英蘇バラッド集』に使われた
一次資料の三分の二が、アバディーン州から集められたことが、その証しです。
アイオナは、地元のリヴァイヴァリストと呼ばれる伝承歌の歌い手たちから、
じかに歌を習い、バラッドを研究してきたという熱心な人だそうです。
歌詞カードに、「誰それのシンギングから学んだ」と書き添えられているように、
かのジーニー・ロバートソンを生んだ、トラヴェラーたちが伝えてきたバラッドの伝統は、
こうした若い世代に着実に受け継がれているんですね。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-03-29
スコットランド文化の豊かさを見る思いがします。
文献や音資料ではなく、その文化の担い手である人間から直接歌を学ぶことは、
単に歌を習うことにとどまらず、
歌の背景である生活や文化をまるごと知る、絶好の機会となります。
バラッドが生まれた時代から、
社会状況も生活習慣も大きく変貌した現代に、その歌を歌うためには、
口伝によって歌の意味を理解することは、なにより貴重なはずです。
“Two Sisters” のスコットランド・ヴァージョンである
“The Swam Swims” でのアイオナの歌唱が、とりわけ心に響きました。
バラッド理解に注いできた若いアイオナの熱意が、見事に結実したデビュー作です。
Iona Fyfe "AWAY FROM MY WINDOW" Cairnie IF18AWAY (2018)
2018-04-20 00:00
コメント(7)
オリエンタリズム紙一重のフェイク・アラビック・ジャズ ヤズ・アハメド [ブリテン諸島]

不思議なムードを持ったアルバムですね。
バーレーン生まれ、イギリスで音楽教育を受けて、
ロンドンで活動中という、女性トランペッターのセカンド作。
アラビックなクォーター・トーンを奏で、妖艶なエキゾティズムをふりまく、
経歴そのまんまのアラビック・ジャズを聞かせます。
バス・クラリネットやヴィブラフォンの起用が効果を上げていますね。
ジャズというには、ときおりムード・ミュージックみたいに聞こえてしまうのは、
アラブを強調した音づくりが、オリエンタリズム臭を漂わせているから。
アラビア語の朗読を交えたり、スピリチュアルなアラブ・ムードを醸し出す演出が、
どうもウサン臭く感じるのは、ぼくだけ?
たとえば、アラブのパーカッション、ダルブッカやレクのプレイにも、
それが表われていますね。ビートが利いてなくて、
効果音的なプレイに終始しているところなんて、
このパーカッショニスト、アラブ人じゃないのは、バレバレ。
アラブ人の出自が自然ににじみ出るとか、
ルーツを掘り下げるとかいった音楽では毛頭なくて、
まるで作り物ぽい、西側リスナーのウケを狙った演出が感じられます。
まあ、こういう
というより、フェイクとは気付かずにカッコいいと思っているんだろうけれど。
その演出がわかる者には抵抗もおぼえる、ビミョーなアルバムであります。
魅力的なんだけれども、ね。
一番の聴きどころは、スピード感のある“Bloom” かな。
このトラックだけ、やたらとカッコよく、抜きんでた仕上がりと思ったら、
なんと、レディオヘッドのカヴァーだそう。
レディオヘッドのオリジナル・ヴァージョンの方にも、ヤズが参加しているのだとか。
アラブ・ムードな曲より、こういうロックの方が、ぼくは好感がもてます。
厚手の紙で作られた見開きのカード・スリーヴ式ジャケットは、
艶消しのコーティングを施した贅沢な作りで、アートワークもステキ。
28ページもあるブックレットといい、フィジカル愛が炸裂しています。
Yazz Ahmed "LA SABOTEUSE" Naim NAIMCD340 (2017)
2018-02-23 00:00
コメント(0)
ゴリゴリのドニゴール伝統派三姉妹 ザ・フリーエル・シスターズ [ブリテン諸島]


厳しい冬の寒さに音をあげ、春の訪れが恋しくなると聴きたくなるアイルランド音楽。
今年は、ドニゴールにルーツを持つ家系に生まれた、
グラスゴー出身の3人姉妹ザ・フリーエル・シスターズの新作が届きました。
アルタンのマレード・ニ・ウィニーが献辞を寄せていた4年前のデビュー作では、
ドニゴール訛りのフィドル・プレイに象徴されるとおり、
ゴリゴリの伝統音楽を聞かせてくれた彼女たちでしたけれど、
2作目もデビュー作同様、伝統に忠実な古風なスタイルを堅持しています。
3人のインタヴューを読むと、母方の祖先に音楽家が大勢いたとのことで、
祖母の兄弟姉妹がフィドル弾きや歌い手だったようです。
さらに叔父さんは、スコットランドのロック・バンド、
シンプル・マインズのメンバーだったとか。
グラスゴーに暮らしているといっても、
これだけゴリゴリのアイリッシュを奏でるのだから、面白いですよねえ。
3人が歌う無伴奏歌も、とても優美なんだけど、
芯にゴツッとしたものがあって、若いのに風格さえ感じさせますよ。
フィドル、イーリアン・パイプス、フルートの3人姉妹をサポートするのは、
ギターとブズーキの二人のみで、デビュー作にいたバウロンは、今回は不在。
ギターの音色がクリアで、タッチも明快ですがすがしく、いいギターだなあ、誰だろうと
クレジットを見たら、なんとHajime Takahasi!
うわお、なんと日本代表の高橋創が起用されています。
高校生デビューして、天才アイリッシュ・ギタリストと騒がれた高橋さん、
とうとう今はアイルランドで活動しているんですね。すごいなあ。
こういう伝統まっしぐらなアルバムで出会えるなんて、すごく嬉しい。
がぜんこのアルバムが、輝いてみえます。
今作では、トゥリーナとマレード姉妹に加え、
トミー・ピープルズまでもが献辞を寄せているんだから、
どれだけ期待が寄せられているかがわかろうというものです。
The Friel Sisters "BEFORE THE SUN" Friel Music FRL002 (2017)
The Friel Sisters "THE FRIEL SISTERS" Friel Music FRL001 (2013)
2018-02-17 00:00
コメント(4)
イングランド南部ウィルトシャーから ロージー・フッド [ブリテン諸島]
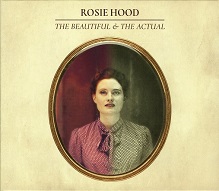
ジャケットには、ずいぶん昔に撮られたご婦人ふうの写真が載っていますけれど、
じっさいのロージー・フッドは、まだ若い英国の女性歌手。
これがデビュー作になります。
イングランド南部ウィルトシャー出身の人で、
地元ウィルトシャーに残された伝承歌を掘り起こし、
自作の曲をつけて歌っている人だそう。
第一次世界大戦前に、ウィルトシャー出身の詩人で
歴史家のアルフレッド・ウィリアムズが、多くの民謡を採集して
それらをまとめた本を23年に出版していて、
その本から多くの曲がレパートリーに選ばれています。
このデビュー作のタイトルも、その本の冒頭の一文から、採られたものなんですね。
きりりとした発声が、いかにもイングランドらしくて、すがすがしいじゃないですか。
その真摯な歌いぶりに、デビュー作らしいほどよい緊張感が溢れていて、
聴いているこちらの背も伸びます。
ロージー自身が弾くテナー・ギターとフィドルのほか、
メロディオンだけを伴奏に歌った曲や、ベースのみで歌った曲など、
曲に合わせて、もっとも効果のある楽器を選び抜いて歌っているところが良く、
これ以上引き算できない、シンプルな伴奏が、歌を鮮やかに引き立てています。
冒頭1曲目の通奏低音のように響くサウンドは、
てっきりシンセが作っているものと思ったら、
ラップ・スティールとベースとフィドルで出していると知り、すっかり感心。
こういうアイディアを目の当たりにすると、安易にシンセを使って、
ケルト・サウンド一丁上がり式なプロダクションが恥ずかしくなりますね。
ほかに、エミリー・ポートマンと2曲デュエットしているのも聴きものなんですが、
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2010-04-12
無伴奏で歌った“The Cruel Mother” での二人のハーモニーは、
アルバムのハイライトとなっています。
Rosie Hood "THE BEAUTIFUL & THE ACTUAL" Rootbeat RBRCD36 (2016)
2017-12-19 00:00
コメント(0)
リルティングの魅力 ジュリー・ファウリス [ブリテン諸島]

3年ぶりに届いたジュリー・ファウリスの新作。
スコットランドの女性ガーリック・シンガーで、ぼくのいっちばん好きな人。
i の母音を発声する時のチャーミングさは、この人を凌ぐ女性歌手はいません。
ジュリーの声を聴いているだけで、幸せになれるんですよ。
ほんとにこればっかりは、相性ですよねえ。
前作“GACH SGEUL - EVERY STORY” が出たさいに、
「大人への階段を上った新作」という記事を書きましたけれど、
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-04-03
あのあと、ジュリーは二人の娘がいるお母さんだということを知りました。
えぇ~、それじゃあ、「大人への階段を上った」もなにもあったもんじゃないなあ。
ジュリーが結婚していたことすら知らなかったので、びっくりだったんですが、
ご主人はアイリッシュの人気バンド、ダヌーのエイモン・ドアリーだそう。
ジュリーのアルバムにいつもブズーキ奏者として参加していた音楽パートナーで、
07年に結婚、10年に長女を、12年に次女を出産していたとのこと。
いやあ、知りませんでした。
デビューまもなくの、十代の歌声としか思えない若々しい印象があまりにも強くって、
いつまでも二十代みたいなイメージが抜けなかったんですけれど、
実は今年ですでに三十代終わりの歳なんですね。
このみずみずしい声を聴いていると、そんな感じがまったくしません。
今作も、ガーリック・シンガーとして着実な歩みを進めたことを実感させる充実作で、
軽やかなダンス・チューンから、メランコリックなラメントや清涼なバラッドまで、
どんなレパートリーでも、それぞれにふさわしい表現と奥行きを持って歌っています。
初めて取り上げた英語曲、アン・ブリッグスとアーチー・フィッシャーの2曲が
話題を呼びそうですけれど、ぼくにとって一番魅力なのは、
愛らしいリルティングを聞かせてくれる“Thèid Mi Do Loch Àlainn”。
リルティングは、ジュリーの生まれ故郷、
北ユーイスト島でも盛んなアウター・ヘブリディーズ特産の毛織物ツイードを、
叩いたりひっぱたりする作業で歌われる労働歌のウォウキング・ソングでよく使われますね。
一種のマウス・ミュージックのようなものですけれど、リルティングが好きなもので、
ウォウキング・ソングも大好物なんであります。
ウォウキング・ソングは、カパーケリーが現代化して再生し、
カパーケリー登場以降、ハイランドの重要なレパートリーとなりました。
音符が弾むジュリーの声で歌われるリルティングは格別。
1音1音エッジが立ったアーティキュレーション、スタッカートの利いた発声は、
ジュリーの真骨頂です。
Julie Fowlis "ALTERUM" Machair MACH008 (2017)
2017-12-17 00:00
コメント(0)
ピアノ・トリオ+ビッグ・バンド フロネシス [ブリテン諸島]
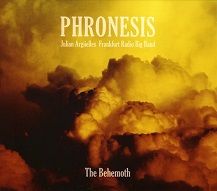
今年のジャズはヴィジェイ・アイヤーでキマリと、勝手に認定してますけど、
それにしても、こんなにジャズが面白くなるなんて、
ちょっと前には想像もつきませんでしたねえ。
ジャズ新作を買わなくなり、専門店からも足が遠のいていた時期が長かっただけに、
ひさしぶりに通い出すようになると、店の品揃えがガラッと変わっていて、
隔世の感というか、なんだかすごく新鮮です。
で、目下のお気に入りが、フロネシスというイギリスのピアノ・トリオ。
ピアノ・トリオといっても、
リーダーはデンマーク出身のベーシスト、イエスパー・ホイビーで、
イギリス人サックス奏者ジュリアン・アーギュロスの指揮・編曲による、
ドイツの名門フランクフルト・ラジオ・ビッグ・バンドとの共演作となっています。
ピアノ・トリオの演奏と、ビッグ・バンドのオーケストレーションを絡ませた編曲が絶妙で、
木管楽器を多用した厚みのある豊かな響きが、楽曲の魅力を引き立てています。
手数の多いアントン・イーガーのドラムスが、複雑なリズムをいとも軽やかに押し出し、
アイヴォ・ニームが紡ぐ込み入ったフレーズと絡み合って緊張感を生み出すところに、
ビッグ・バンドのハーモニーが雄大なサウンドスケープをもたらしていて、
いやあ、ぐっときますねえ。
息つかせぬ展開に汗握る場面など、ドラマティックなアレンジが効果的で、
現代的なビート・センスのピアノ・トリオが、カラフルなビッグ・バンド・サウンドを得て、
スケールの大きなサウンドを生み出しているんですね。
このピアノ・トリオの他のアルバムは聴いたことがないんですが、
ピアノ・トリオだけでは、このスケール感は出ないはずです。
ハード・ドライヴィングなインタープレイのあとに、抑制を利かせたオーケストラの
ハーモニーのパートをバランスよく配する構成には、降参というほかありません。
Phronesis "THE BEHEMOTH" Edition EDN1085 (2017)
2017-10-16 00:00
コメント(0)
インプロ志向のUKジャズ・3ピース・バンド プレストン=グラスゴウ=ロウ [ブリテン諸島]

デヴィッド・ギルモアの新作と交替だな、こりゃ。
ロンドンからすごいジャズ・ギタリストが出てきましたよ。
その名はデヴィッド・プレストン。
ベーシストのケヴィン・グラスゴウ、ドラマーのローリー・ロウによる
3ピース・バンドで、姓名を繋げたシンプルなバンド名を名乗っています。
オープニングから、圧倒的なテクニックでトリッキーなプレイを聞かせて、圧巻。
うっわー、スゲー。
カート・ローゼンウィンケルみたいな高速ピッキングに舌を巻いていたら、
パット・メセナーみたいなメロディ・ノートをくっきりと残すソロを披露したり、
アラン・ホールズワースを思わすオルタネイト・ピッキングのトーンを聞かせたりと、
何通りのギター・スタイルを持っているんだか。
めちゃくちゃテクニカルなプレイの連続に、
いやー、若さっていいよねえ、ギラギラしててと、おじさん、嬉しくなっちゃいました。
サウンド志向の淡泊な表現が主流になりつつある新世代ジャズで、
こういうインプロ志向のバンドって、これからは希少になるのかもしれないけど、
やっぱりジャズの醍醐味は、インプロよ。
ギターのことばっかり書いてしまいましたけれど、
ケヴィン・グラスゴウの6弦ベースもすごい。
デヴィッドのギターに絡んでくるフレージングにひらめきを感じます。トーンもいいね。
ローリー・ロウのドラミングは、柔軟でしなやか。
手数が多いのに、たっぷりとした重量感もあって、
長いソロもよく歌う、いいドラマーです。
3人の緊密なプレイはエネルギッシュそのものなんだけど、
同時にクールな佇まいを感じさせるところが、現代性でしょうか。
サウンドにはポスト・ロック的な快感もあります。
聞くところによると、去年の10月に来日してたそうで、うわー、観たかったなあ。
あいかわらずライヴ情報に疎い自分に嫌気がさすけど、
また来てくれるよね。待ってまーす。
Preston - Glasgow - Lowe "PRESTON - GLASGOW - LOWE" Whirlwind Recordings WR4686 (2016)
2017-05-09 00:00
コメント(2)
真面目なシンギング ロビン・ステイプルトン [ブリテン諸島]
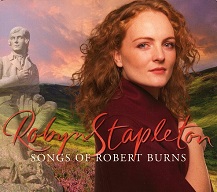
ロバート・バーンズの歌ほど知られている、スコットランドの詩人はいないでしょうね。
たとえその名前を知らなくても、
「蛍の光」や「故郷の空」を聞いたことない人はいないでしょう。
その「故郷の空」“Comin' Through The Rye” で始まり、
「蛍の光」“Auid Lng Syne” で締めくくられるロビン・ステイプルトンの2作目は、
ロバート・バーンズ曲集となっています。
「故郷の空」を聴くと、どうしてもザ・ドリフターズの「誰かさんと誰かさん」を
思い出してしまう世代なんですが、
なかにし礼がコミック・ソングに仕立てたあのHな歌詞は、
じっさいバーンズが書いた元歌に近い雰囲気がありました。
そもそもこの曲を、明治時代に教育的な唱歌にしたのが
間違いというか無理筋だったわけで、
いまでも英語圏では、この曲は春歌として扱われていると聞きます。
その“Comin' Through The Rye” も“Auid Lng Syne” も、
ロビンが歌うと、スコットランドらしい清廉な空気感が溢れ出しますね。
ロビンの節回しには、独特の格調の高さがあります。
持って生まれた気品というべきか、ちょっと人を寄せ付けないところもあって、
親しみのあるタイプとはいえないかもしれません。

いつも真面目で、真摯な態度がカタブツと敬遠されてしまう損な性格。
そんなイメージのある歌手ですけれど、ぼくは好きなんだな、こういうタイプ。
ロック的な感性とは真逆のタイプですね。
前作15年のデビュー作でも、きりっとしたシンギングを聞かせていて、
ピアノのみの伴奏や無伴奏歌など、裸に近い歌いぶりに、
この人の真面目さが美しく昇華しているようで、とても気に入っていたんですが、
2作目でもそんなロビンの伝統歌に対する意識の高さがうかがえる秀作に仕上がっています。
Robyn Stapleton "SONGS OF ROBERT BURNS" Laverock LAVE002CD (2017)
Robyn Stapleton "FICKLE FORTUNE" Laverock LAVE001CD (2015)
2017-04-27 00:00
コメント(0)




