アンゴラのソウルフルなアーバン・ポップ ヨラ・セメード [南部アフリカ]
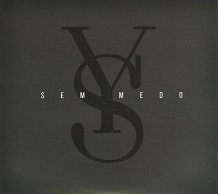
アンゴラのキゾンバ・シンガー、ヨラ・セメードの前作“FILHO MEU” は、
アフロ・ズークの亜流と受け止められがちなキゾンバのイメージを払しょくする、
一大傑作でした。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-06-09
ポルトガル語圏アフリカとフレンチ・カリブの多様な音楽要素をミクスチャーした手腕が、
それまでのキゾンバにない高度な洗練を遂げていて、
ゴージャズなプロダクションともども、魅惑的なクレオール・ポップに仕上がっていました。
2016年のベスト・アルバムで、エディ・トゥッサの新作を押さえて選んだんですけれど、
迷いはありませんでしたよ。
あれから4年、昨年春にリリースされた新作が、1年遅れでようやく手元に届きました。
CD2枚組、全29曲120分超の新作は、ヴォリューム感たっぷり。
前作が弦オケから始まる意表を突くオープニングだったのに比べると、
今作は打ち込み使用のキゾンバでスタートし、
前作の練り上げたクレオール・ミュージックの豪華さに比べると、
ちょっと後退した感のある、平均的な仕上がり。
ディスク1の4曲目まで、打ち込み使いの平凡なキゾンバが続き、
5曲目でようやく生ドラムスにクラリネットをフィーチャーしたモルナとなります。
レゲエのリズムを取り入れたこのトラックがフックとなり、
その後生ドラムスによるトラックがしばらく続き、ビギンとセンバのミックス、
センバとコンパのミックス、コラデイラなど多彩なクレオール・ミュージックを繰り広げ、
終盤には、アコーディオンをフィーチャーしたストレートなセンバも出てきます。
プロダクションのことばかり書いてしまいましたけれど、
伸びのある声でしなやかに歌うヨラのヴォーカルは、
アンゴラのポップ・クイーンといった風格を感じさせます。
まさにヴェテランの味わいというか、いいシンガーですよねえ。
クレオール・ミュージック中心にまとめたディスク1に対して、
ディスク2はバラード中心のポップスで、
ヨラのソウルフルな歌いぶりを堪能できる美メロ曲が並びます。
2曲目のボレーロ‘Athu Mu Njila’ での歌いぶりにはグッときたし、
インドネシアかマレイシアのポップ曲を思わす7曲目の‘Dias Da Semana’ は、
アンゴラでもこんなメロディがあるのかと、とても新鮮でした。
プロダクションもオーケストラを使うなど、バラード編の方が手が込んでいますね。
コンガ、ディカンザ、ギター3台のシンプルな伴奏で歌うセンバを、
ラスト・トラックに持ってきたのは意表を突かれましたけれど、
爽やかな締めくくりになっています。
Yola Semedo "SEM MEDO" Energia Positiva Music EPCD005 (2018)
2019-06-30 00:00
コメント(0)
前半フュージョン/後半キューバン・ジャズ エル・コミテ [カリブ海]

取り上げようか、やめようか、ちょっと迷ってたんですけど、
なんだかんだよく聴いているんだから、やっぱ書いておこうかという気になりました。
キューバ新世代ジャズのグループ、エル・コミテのデビュー作。
ツイン・ピアノに2管の7人編成、全員キューバ人ですが、
リリース元はフランスのレーベル。
「超絶のキューバン・ジャズ」なる触れ込みで買ったものの、
最初聴いた時、「ジャズ」でも「キューバ」でもぜんぜんないじゃん!
オープニングの割り切った8ビートのドラミングからして、
ジャズというよりはフュージョン。
ロドネイ・バレットのドラムスは、手数は多いもののコンパクトに叩くから、
うるさくならないスタイルで、歌伴上手そうと思わせるタイプです。
新世代ジャズのドラマーのリズム・フィールを期待したもんだから、
それとは違うスタジオ出身のフュージョン・ドラマーといった端正なプレイに、
あれれ、と思っちゃったんでした。巧いのはわかるんだけどさ。
新世代ジャズらしいサウンドが聴けるのは、4曲目の‘Transiciones’。
アブストラクトなラインからホーンズを含む合奏になだれ込むと、
複雑なリズム・アレンジとなって、フュージョン臭は解消します。
うん、こういうのを、期待していたんですよね。
そして、メンバー全員キューバ人というのに、ホントか?と思ったのは、
冒頭から中盤4曲目までのリズムに、ぜんぜんクラーベのフィールがないから。
キューバン・ジャズの強いグルーヴがなくて、
なめらかといえば聞こえはいいけど、淡白なフュージョンのリズム感があまりに支配的。
5曲目の‘Carlito's Swing’ でようやくオン・クラーベとなり、
ピアノがトゥンバオを弾き始めるブリッジから、
ようやくラテンらしくなるとはいえ、薄味だなあ。
で、一番キューバらしいサウンドを聞かせるのが‘Son A Emiliano’。
90年代キューバン・ジャズの傑作、
ガブリエル・エルナンデスの“JAZZ A LO CUBANO” 所収のソンゴで、
これなら文句なしのキューバン・ジャズといえます。
そして、続くラスト・トラックのラテン・ジャズ化した、
マイルス・デイヴィスの‘So What’ で締めくくるという、
終盤になってようやくキューバン・ジャズらしくなるアルバム。
これ、曲順を真逆にしたら、印象がガラリと変わったんじゃないかと思わずにはおれない、
前半と後半では別グループの演奏のように思える作品です。
El Comité "Y QUÉ?" Inouïe Ditribution SDRM5072018/1 (2018)
2019-06-28 00:00
コメント(2)
あれから22年 イライザ・カーシー [ブリテン諸島]
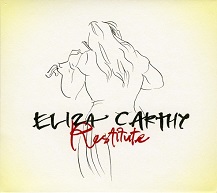
うぉ~、この大物感、ハンパないね。
もはや父マーティン・カーシー、母ノーマ・ウォーターソンの名前を出さずとも、
イングリッシュ・フォークのヴェテランと肩を並べる貫禄が備わった、イライザ・カーシー。
新作は原点回帰ともいうべき、直球勝負の伝統音楽アルバムです。
オープニングの曲で、ハンマー・ダルシマーの響きを鈍くしたような音色に、
何の楽器だろうかと思えば、どうやらヴァイオリンの弦を、箸で叩いているらしい。
う~む、こういうところも、フォーク・シーンのイノヴェイターとして活躍してきた、
型にはまらないイライザの面目躍如だなあ。
パワフルな無伴奏歌ともども、伝統の型をなぞらない逞しさが彼女にはありますね。
ノース・ヨークシャー、ロビン・フッド湾にある、
イライザの自宅の寝室で録音されたという本作、
父マーティン・カーシーのギターに、コンサーティーナやベースなどが数曲で加わるほかは、
イライザが弾くヴァイオリンやヴィオラを多重録音しただけのシンプルな構成だからこそ、
伝統音楽家としてのイライザのスケールの大きな音楽性が、浮き彫りになっています。
イライザを初めて観たのは、両親と3人で来日した97年1月のこと。
ウォーターソン:カーシーの初アルバムでその歌声とフィドル演奏を披露し、
ソロ・デビューを果たしたばかりの、まだ初々しい時代でした。
ジャケットのイライザの美少女ぶりに、サインを入れてもらうのが忍び難く、
バックインレイに3人のサインをもらったんだっけ。


あのライヴも思い出深いなあ。
新年明けて間もない5日の夜、ハコは新宿ロフトでした。
イライザの真っ赤に染めたショートヘアとスニーカーの、
いかにも現代っ子らしい姿が瞼に焼き付いていますよ。
当時まだ19歳だったんだよねえ。
床をがんがん蹴るステップもパワフルなら、ボウイングも思いのほか激しく、
ニコニコしながらヴァイオリンを弾きまくるチャーミングな姿に、
うちのコたちもこんな女のコに育ったらなあ、なんて思いながら観たもんでした。
ライヴが終わり、翌日が年明けの初出勤日だったので、
単身赴任先だった群馬へと向かったんでした。
東京は雨だったんですけど、熊谷を過ぎたあたりから雪になって、
新前橋の駅に降り立つと、そこは一面の銀世界。
幻想的な景色にたじろぎながら、シンと静まり返った雪降る街を一人、
新雪を踏みしめながら、単身寮へと向かったことが忘れられません。
Eliza Carthy "RESTITUTE" Topic TSCD599 (2019)
Waterson:Carthy "WATERSON:CARTHY" Topic TSCD475 (1994)
2019-06-26 00:00
コメント(0)
ヨイクの伝統の呪縛から放たれて ヴィルダ [北ヨーロッパ]

ヨイクのシンガーとアコーディオンの女性デュオのアルバム。
ヨイクをコンテンポラリーなサウンドで歌うアーティストは、
アリ・ボイネはじめいろいろ聞いてきましたけれど、
どれも<極北のエスニック音楽>といった作り物ぽさが拭えなくて、
二の足を踏んできたのが正直なところ。
でも、この二人はちょっと印象が違いました。
まず、ヨイクのミスティックな面を誇張していないのが、いい。
ヨイクが持つ霊性を過度に演出することなく、
音楽に生命感が宿っているのが自然に感じ取れます。
シャーマニズムといったサーミ人の伝統文化から抜け出た現代から、
ヨイクをリサイクルしているようなニュアンスさえ感じさせるその作法には、
先人たちのワールド・ミュージック的な語法から離れた自由さを感じます。
ヨイクの特殊性を強調したサウンドを組み立てるのではなく、
フィンランドのアコーディオン音楽と融合させながら、
そのなかにヨイクの即興性を浮かび上がらせる二人のやり方は、
伝統の継承とは異なる、現代性に富んだ方法論を獲得したんじゃないでしょうか。
歌とアコーディオンの二人を中心に、手拍子やパーカッション、
ビートボックスなどのゲストを多数迎えているように、
伝統の呪縛から放たれたそのサウンドには解放感があり、
風通しが良く、すがすがしさを覚える新鮮さが得難いですね。
Vildá "VILDALUODDA / WILDPRINT" Bafe’s Factory/Nordic Notes MBA030 (2019)
2019-06-24 00:00
コメント(0)
ハイランドと東欧を繋ぐバグパイプ ブリーチャ・キャンベル [ブリテン諸島]
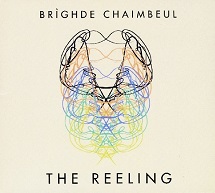
スモールパイプス(小型バグパイプ)の持続するドローンのディープな音色に、
金縛りとなってしまう深淵な音楽。これを演奏しているのが、
まだハタチの女性だというのだから、驚かされます。
ブリーチャ・キャンベルは、スカイ島の音楽一家に育ったパイプ奏者。
16年にBBCラジオ2のヤング・フォーク・アワードを受賞、
翌17年にはスコッツ・トラッド・ミュージック・アワードの新人部門に
ノミネートされたという若き実力者です。
7歳の時、女性バグパイプ奏者ローナ・ライトフットの
演奏を聴いて感銘を受け、パイパーを志したのだそうで、
現在82歳となったそのローナもレコーディングに参加し、
パイプのフレーズを教えるときの口三味線を披露しています。
こういう口三味線って、一般的にはリルティングと呼ぶと思うんですけれど
ライナーのクレジットには、キャントリッチド Canntaireachd と書かれていて、
調べてみたら、スコティッシュ・ガーリックでパイプを模したチャントをそう呼ぶんだそう。
18世紀のハイランドの古謡をはじめとする伝統曲をレパートリーに、
スモールパイプスのソロ演奏を聴かせるんですが、
凄みさえ覚えるリズムの深さには圧倒されるばかりです。
興味深いのは、ブルガリアのバグパイプ音楽もレパートリーとしていることで、
なんでも17年にブルガリアを訪れた時、
ブルガリアのバグパイプ、ガイダを知って惚れこみ、
ガイダの演奏曲を習ってきたんだそうです。
バグパイプ音楽でハイランドと東欧の古層をつなぐ試みは、
今後の彼女の音楽を発展させていく、大きなファクターとなりそうですね。
ブラックアイル半島の由緒ある教会でレコーディングされたという本作、
プロデューサーを務めるイダン・オルークのフィドルや、
コンサーティーナが加わる曲もありますが、
ブリーチャの重量感あるスモールパイプスが、圧倒的な存在感を示した作品です。
【追記】2019.6.22
「ブリッド・チェインビョール」とあやふやなカナ表記を書いていたところ、
山岸伸一さんから「ブリーチャ・キャンベル」と発音することを教えていただきました。
修正させていただきます。山岸さん、ありがとうございました。
Brìghde Chaimbeul "THE REELING" River Lea RLR003CD (2019)
2019-06-22 00:00
コメント(2)
モンペリエから登場したエチオ・バンド エチオダ [西・中央ヨーロッパ]

エチオピアで研究活動をされている映像人類学者の川瀬慈さんから教わった1枚。
エチオダは南フランスのモンペリエのバンドで、エチオピア音楽をベースに、
アフロビート、ファンク、レゲエをミックスした音楽をやっているといいます。
3年前にアルバムを出したようなんですけれど、日本未入荷。
早速オーダーしてみました。
う~ん、さすが川瀬さんが推薦するだけのことはある、本格派のバンドですね。
重心の低いリズム・セクションに、サックス、トロンボーン、トランペットの3管が織り成す
サウンドは、まさしくエチオピア音楽黄金時代の70年代サウンド。
冒頭の‘Ambassel Groove’ からしてエチオ色充満で、
曲名のとおりアンバセルの旋法を使った曲となっています。
2曲目の‘(Satie a dit ça) Beba’ はアンチホイェの旋法でレゲエにアレンジしていて、
大半の曲を作曲している鍵盤奏者のオリジナルは、見事にエチオ・マナー。
アフロビートは‘Respecto’ で1曲やっています。
多重録音したサックスをレイヤーした短いインタールードのような‘Echi’ は、
雄大なエチオピアの平原をたゆたうようなメロディが
映像的なサウンドを生み出していて、心に響きます。
こういうアイディアがフェレンジから出てくるっていうのも、スゴイな。
ギタリストがスペイシーなサウンドを作るタイトル曲も面白く、
後半になるほど、エレクトロなサウンドも加味されて聴き応えが増します。
次作はこうした実験的なサウンドを、もっと反映してみてもいいかも。
フランス発のエチオ・ポップ・バンドとしては、アカレ・フーベに続く注目株ですね。
Ethioda "TEZET RESET" no label no number (2016)
2019-06-20 00:00
コメント(0)
オーガニックなマンデ・ヒップ・ホップ ルカ・プロダクションズ [西アフリカ]

バマコのアンダーグラウンド・シーンで活動する、
ラッパー/トラックメイカーのルカ・ギンドによるプロジェクト、
ルカ・プロダクションズの新作がすごく面白い。
前2作では、バラフォン、コラ、ジェンベなどの演奏を散りばめてはいても、
全体的にはエレクトロニックなサウンドが支配していましたけれど、
今作はンゴニを中心とする伝統楽器による生演奏をメインに全面展開。
いわば生演奏のマンデ・ヒップ・ホップといった仕上がりになっているんです。
なんだかアレステッド・ディヴェロップメントのデビュー作を思い出しますね。
ちなみに、16年のデビュー作“MALI KADY” は配信とカセット、
17年の2作目“FASOKAN” は配信とLPが出ていましたけれど、
今作は配信とLPに加え、CDも出ています。
トラックメイキングはマンデの伝統音楽に沿ったもので、
ンゴニ、バラフォン、ジェンベといった生音の伝統楽器アンサンブルが主体。
ルカが操るシンセサイザーは、サウンドの後景へと退き、
打ち込みのビートも、華やかなジェンベのソロの引き立て役に徹しています。
伝統的なマンデの歌と、ヒップ・ホップ・トラックがごく自然に並んでいるのが、
ヒップ・ホップ世代だなあと実感させられますね。
マンデの伝統音楽とヒップ・ホップに距離感がまったくないのは、
ヒップ・ホップを外から取り入れているのでなく、
すでに内に持っているという世代の強みでしょいう。
グリオ出身の歌手を大勢ゲストに迎えているほか、
今作のキー・パーソンとなっているのは、若きンゴニ演奏者カンジャファの起用です。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-12-12
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-11-01
ンゴニでジプシー・スウィングを演奏するというユニークな音楽性を持つカンジャファは、
ここではンゴニ・プレイヤーとして、ばっちばちに音の立ったプレイを聞かせてくれます。
シタールのサンプル音をフィーチャーしたインド風メロディの‘Indiefoli’
キング・アイソバのようなダミ声ヴォーカリストをフィーチャーした‘Kodouma’ など
ルカ・ギンドのトラックメイクにも豊かなアイディアが詰まっています。
女性グリオの歌とコーラスをフィーチャーし、
ジェンベがグルーヴィなビートを打ち出す‘Badjan’ は伝統的なマンデの歌と演奏で、
続く‘Djessou’ も同じような伝統的な演奏と思いきや、
打ち込みが四つ打ちのビートを刻んでいるし、
ンゴニの反復フレーズをループさせて、生演奏によるンゴニ・ソロをフィーチャーするなど、
サウンドづくりは一筋縄ではありませんね。
オーガニックなマンデ・ヒップ・ホップの名作、誕生です。
Luka Productions "FALAW" Sahel Sounds SS052 (2019)
2019-06-18 00:00
コメント(0)
南スーダンのファニーなポップス パンチョル・デン・アジャン・ラック [東アフリカ]
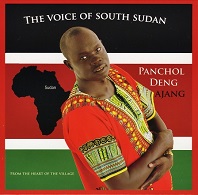
南スーダンのポップス?
あの国にポップスなんて存在するのか?
独立早々の国境紛争から内戦に突入した南スーダンの惨状を思えば、
当然わき上がる疑問です。
南スーダンの国旗の三色を背に、『南スーダンの声』と題した本作の主役、
パンチョル・デン・アジャン・ラックは、内戦を避けて国外に脱出した難民たちにとって、
レジェンド扱いされている歌手だとのこと。
いかにも低予算なチープな打ち込みは、ポンチャックの南スーダン・ヴァージョンの体で、
聴き始めはやれやれという気分にさせられたんですけれど、
聴き進めていくうちに、グングン引きつけられてしまいました。
いかにもスーダンらしいおおらかなメロディと、
2・4拍でハネるリズムがユーモラスというか、ファニーというか、
とにかく楽しいことこのうえないんですよ。
オルガン、シンセサイザー、シンセ・ベースをレイヤーしたスッカスカのサウンド、
キーボードのキュートな音色に、クスクス笑いを誘われます。
アコーディオンやエレクトリック・ギターは手弾きのようで、
シンセ・ベースでなく、手弾きらしきベースが聞こえる曲もあるんですけれど、
見事にチューニングが合っていなくて、アブなく妖しいサウンドを生み出しています。
何が功を奏するか、わからないもんですね。
パンチョル・デン・アジャン・ラックは、現在の南スーダン、デュック・パディエット群で、
69年の生まれ。兄弟の多くを失くし、父親は76年に、母親は90年に他界。
内戦のため通っていた学校も閉鎖され、初等教育も満足に受けられなかったそう。
歌手活動だけでなく、レスリングの選手としても活躍したが、
ディンカ人主体の反政府組織SPLMによる内戦が激しくなった91年には、
ほとんど芸能活動が不可能となり、
現在は難民キャンプを回って避難民を勇気づけているという。
国外へ逃れた難民の支援を受け、13年にカナダ、15年と17年にオーストラリア、
17年にアメリカへ招待されて公演を行っています。
ハイル・メルギアの85年の多重録音盤が好きな人や
アフリカ音楽カセットのマニア、ブライアン・シンコヴィッツさんのレーベル、
オウサム・テープス・フロム・アフリカのファンには、絶好の一枚でしょう。
Panchol Deng Ajang Luk "THE VOICE OF SOUTH SUDAN" JBT no number (2017)
2019-06-16 00:00
コメント(0)
スーダンのブルース・レジェンド アブドゥル・アジーズ・ムハンマド・ダウード [東アフリカ]
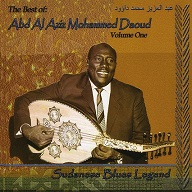
黄金の宝が眠っていることはわかっているのに、
待てど暮らせど、いっこうに発掘されないスーダン大衆歌謡。
オスティナート・レコーズのヴィック・ソーホニーが手がけ始めたので、
その成り行きを見守っていたところ、まったく別のところから、
ヴィンテージものがひょっこりリイシューされました。
それがアリゾナ州トゥーソンを拠点とする
ブルー・ナイル・レコーズというレーベルがリリースした、
アブドゥル・アジーズ・ムハンマド・ダウードのリイシュー作。
アメリカに渡ったスーダン人が主宰しているレーベルのようです。
アブドゥル・アジーズ・ムハンマド・ダウードは、伝統的なハギーバから
スーダン歌謡の現代化が大きく進んだ60年代に活躍した歌手。
北部の町ベルベル出身で、生年はライナーには30年とありますが、
ぼくの手元にある資料では22年説と16年説があり、ちょっと不確かのようですね。
少年時代のクッターブ(コーラン学校)では、コーラン朗唱に優れた生徒だったものの、
歌が好きでよく大声で歌っていたダウードは、
音楽を禁じるイスラームの教えに背いたとして、よく鞭打たれとのこと。
47年にラジオ・スーダン(ウム・ドゥルマン・ラジオ局)で歌い始めたダウードは、
ハギーバなどの大衆歌謡ばかりでなく、スーフィーの古い聖歌や
コーランの一節を吟唱したり、即興のコメディを歌うなど、
さまざまなレパートリーを歌える歌手としてその才能が高く評価され、
スーダンの著名な作曲家や詩人が競うようにダウードのために曲を書いたといいます。
50~60年代に人気を博したダウードのスタイルは、「ブルース」と呼ばれ、
やがて「スーダンのハウリン・ウルフ」の異名をとり
(アメリカのブルース・シンガーとは無関係)、
このCDにも、「スーダニーズ・ブルース・レジェンド」と記されています。
ウム・ドゥルマン・ラジオ局の公式記録では、ダウードは49を超すアルバムを残し、
186曲を録音したとあり、国内ばかりでなくアラブ諸国をツアーし、
74年にはドイツ、アメリカへも渡っています。
本CDは、60年代のオリジナル音源をもとに、
93年に伴奏をオーヴァー・ダブして差し替えられたもの。
ディスク化されたのは、今回が初のようですけれど、
せっかくお化粧直しした音源を、なぜ眠らせておいたんでしょうね。
そこいらの事情はよくわかりませんが、
ヴォーカルと伴奏に不自然さはなく、違和感なく聴くことができます。
オリジナルの録音時期は、けっこう幅がありそうです。
アコーディオン、ウード、エレクトリック・ギター、ボンゴが繰り出す
まろやかなビートがたまりません。ヴァイオリン・セクションが舞う
エレガントなサウンドは、スーダン歌謡の醍醐味といえます。
ダウードの気っ風のいい歌いっぷりやこぶしの利かせ方は、
まさに熟練の味わいで、奥行きのある歌声に懐の深さを感じます。
ブルース・シンガーというより音頭取りと言った方が、日本人にはピタッときますね。
60年代のオリジナル音源も、ぜひ聴いてみたいものです。
Abd Al Aziz Mohammed Daoud "THE BEST OF ABD AL AZIZ MOHAMMED DAOUD VOLUME ONE" Blue Nile BLN1804
2019-06-14 00:00
コメント(0)
21世紀に蘇るレンベーティカ ヴィヴィ・ヴーツェラ [東ヨーロッパ]

マリカ・ニーヌを聴いていて、この春カンゲキしたレンベーティカ新作を
取り上げそこねてたのを思い出しました。
これがデビュー作という、女性歌手ヴィヴィ・ヴーツェラのアルバムです。
デビュー作で、戦前スミルナ派のレンベーティカのレパートリーを歌うというのも
スゴい話なんですけれど、こういうアルバムがぽろっと出るところが、
まさしくギリシャ歌謡の奥深さなんでしょうねえ。
デビュー作といっても、それなりにキャリアを積んでいる人らしく、
レンベーティカの古典曲を集めた企画アルバムなどに録音を残していて、
古いレンベーティカへの並々ならぬ情熱がうかがえます。
あれ? この曲、知ってると、熱心なレンベーティカ・ファンなら、
耳馴染みのある曲も多いはずで、曲目をチェックしてみたところ、
2曲目の‘Marikaki’ と8曲目の‘Spasta Fos Mou’ は、
ローザ・エスケナージのよく知られた代表曲。
6曲目の‘Mesa Sto Pasalimani’ と9曲目の‘Spasta Fos Mou’ は
スミルナ派を代表する女性歌手リタ・アバジの歌で知られ、
3曲目のステラーキス・ペルピニアーディスの‘I Foni Tou Argile’ は、
ダラーラスもカヴァーした曲ですね。
タイトル曲の‘Kardiokleftra’ は、歌手以上にヴァイオリン、サントゥーリ、
ギターの演奏家として名高いヨルゴス・カヴーラスの曲で、
7曲目の‘Nisiotopoula’ もヨルゴス・カヴーラスの曲です。
1曲だけ戦後の曲が取り上げられていて、10曲目の‘Sevilianes’ は、
サロニカ生まれのユダヤ人女性歌手ステラ・ハスキルの曲。
47年の曲ということで、この曲のみ伴奏に弦楽オーケストラを加えて、
ゴージャスなサウンドにしています。
伴奏を取り仕切るのは、ヴァイオリンのキリアコス・グヴェンタス。
ロンドンのロイヤル・アカデミーでも学んだ音楽家で、
ライカからいにしえのレンベーティカまで通じるプロフェッサーと称される人とのこと。
古きレンベーティカの伝統的な編成を基礎としながら、
現代の息吹を感じさせるアンサンブルのアレンジが、
ヌケのいいサウンドを生み出しています。
そんなリフレッシュメントされたサウンドに応えるように、
透明感のあるヴィヴィの節回しが、実にさわやかで、
ディープでブルージーな前世紀のレンベーティカの猥雑さとは、別物ですね。
単なるスミルナ派の再現にとどまらないモダンなセンスが、
レンベーティカ消滅後、半世紀の時を経て、新たに蘇らせたのを実感します。
トルコのシャルクやサナートが再興したのとも、シンクロしているような気も。

ジェネラル・ミュージックというこのレーベル、
12年にもケイティ・ンタリのレンベーティカ集を出していましたけれど、
レンベーティカ・ファンは注目する必要がありそうですね。
Vivi Voutsela "KARDIOKLEFTRA" General Music GM2392 (2019)
Kaiti Ntali "TA REMBETICA" General Music GM5288 (2012)
2019-06-12 00:00
コメント(0)
戦後レンベーティカの恋唄 マリカ・ニーヌ [東ヨーロッパ]

これまた原田さんから、するりと差し出された温故知新盤。
アラブの旧作もそうですけど、ギリシャも古いCDがまだ結構残っているらしく、
CD衰退の現在、CDショップとしては古いカタログに活路を見出すのは、
手堅い選択でありますね。
30年くらい前によく聴いた、レンベーティカの名女性歌手マリカ・ニーヌ。
レンベーティカをギリシャの国民歌謡に引き上げたヴァシリス・ツィツァーニスとのコンビで
有名になった人ですけれど、このCDは見たおぼえがないなあ。
バック・インレイを見るとライヴ録音らしく、ありがたくいただいてまいりましたよ。
55年にアテネの「太っちょジミー」というタヴェルナ(居酒屋)で
アマチュア録音されたものが、77年に発掘されてLP化され、
92年にCDリイシューされたものとのこと。
55年というと、マリカはすでにツィツァーニスとのコンビを解消し、
ソロ歌手として独立していた時期。太っちょジミーは、
ツィツァーニスとのコンビ時代からレギュラー出演していた馴染みのお店です。
ライヴ録音といっても観客の拍手はカットされていて、
録音はあまりよくありませんが、臨場感がすごいんです。
ブズーキ、ヴァイオリンなどの弦楽器に、ピアノ、アコーディオン、
さらに男性コーラスも加わった伴奏のグルーヴィなことといったら。
なまめかしいヴァイオリンや、硬い弦の響きがリズムのエッジを立てるブズーキなど、
戦前とは異なる近代化されたレンベーティカ・サウンドが楽しめます。
そっけなく歌う、マリカの張りのあるヴォーカルも、なまなましいですね。
この2年後には癌がもとで亡くなってしまう、晩年の時期のマリカですけれど、
ここで聞かれる歌声からは、病気の影はまったく感じ取れません。
54年に癌の手術をしていて、その翌年の録音になるわけですけれど、
このギリシャならではの歌声には、35歳の若さで亡くなってしまったのが、
つくづく悔やまれます。レンベーティカからライカ時代に移っても、
存分に活躍できたはずなのに。
レンベーティカというと、ついSP時代のディープなスミルナ派ばかり
聴き返してしまうんですけれど、レンベーティカが消滅する50年代に、
最後の輝きを放ったピレウス派の、
センチメンタルな恋唄の良さが詰まった好盤でした。
Marika Ninou "MIA VRADIA STOU TZIMI TOU XONTROU" D.P.I. Atheneum D.P.I.066
2019-06-10 00:00
コメント(0)
親しみやすさに込められた強靭なメッセージ ジアード・ラハバーニ [中東・マグレブ]

エル・スール・レコーズに行くと、ジアード・ラハバーニの70年代のCDが入荷中。
「あれ、懐かしい」と思わず口にすると、
「いいですよねえ、これ。まだ在庫があったんで、入れてみたんですけど、
インストだから売れないかなあ」とは原田さん。
ところが、その後すぐさま売り切れとなったようで、
さすがはエル・スールのお客さん、いいモノをよくご存じです。
アラブ古典の器楽演奏というと、ちょっと敷居の高いものが多いですけれど、
なかでもこれはもっとも親しみやすい一枚として知られている名作。
フェイルーズの息子で、いまや母のアルバム・プロデュースもするまでになった
ジアードですけれど、まだ当時は20歳そこそこの気鋭の若手音楽家でした。
原田さんがいみじくも「アラブのデスカルガ」と言っていたように、
自由闊達なジャム・セッションを味わえるアルバムなんですね。
ぼくもひさしぶりにCD棚から引っ張り出して聴き直しましたけれど、
うん、やっぱり極上品ですね。
表紙には正装したメンバーが勢揃いしていますが、
ジャケット裏のレコーディング風景を撮ったスナップ・ショットの方が、
演奏の雰囲気をよく表わしていて、スタジオで演奏している
普段着姿のリラックスした様子が、ありありと伝わってきます。
掛け声をかけたり、手拍子も交えたりと、レコーディングの緊張感など、どこへやら。
即興する演奏者をはやしたり、笑い声まで録音されていて、
そのリラックス・ムードがさらに演奏をいきいきとさせています。
フィリップスから77年に出された本作は10曲の組曲で、
ジアード・ラハバーニの自作曲に、近代アラブ音楽の基礎を作った
サイード・ダルウィーシュの曲や、レバノンの作曲家で音楽プロデューサーの
ハリーム・エル・ルーミー(マジダ・エル・ルーミーのお父さん)の曲、
アルメニア民謡がメドレーで演奏されます。
CDには、LPに記載のなかった‘Moukadimat Sahriye’が5曲目にクレジットされています。
ただし、組曲形式だから38分弱のノンストップで、CDも1トラック扱いとなっています。
宗派対立が極限まで達し、ベイルートで内戦がぼっ発した75年、
ジアードはこのビル・アフラー組曲を演奏するため、
クリスチャンとムスリム両方の音楽家を集めて、
ビル・アフラー・アンサンブルを編成しました。
のちにジアードは、「ベイルートのボブ・ディラン」と称されるとおり、
社会批評家として政治的立場を鮮明にしましたけれど、
若干19歳にして、宗派を超えて器楽演奏をすることで、
無言の雄弁なメッセージを放ったのです。
なぜ古典器楽を、かくも楽しげに演奏してみせたのか。
それは、幾千の言葉を重ねたプロテスト・ソングよりも、
強烈なカウンターとなることを、ジアードは理解していたからでしょう。
ビル・アフラー・アンサンブルが、
キリスト教徒もイスラーム教徒も共存できることを証明し、
その親密なセッションが、憎しみあい敵対することの愚かさを照射してみせました。
単に、親しみやすい古典器楽と聴いていた本作に、
そんな深いメッセージが込められているとはツユ知らず、
ずいぶん後になってから知った時は、ぼくもウナってしまいました。
そういえば、4年前ニュー・ヨークで、ビル・アフラー結成40周年を記念した
ビル・アフラー・プロジェクトが結成され、コンサート活動をしています。
トランプ以後の分断されたアメリカだからこそ、こうした活動を応援したくなりますね。
Ziad Rahbani "BIL AFRAH" Voix De L'Orient VDLCD606 (1977)
2019-06-08 00:00
コメント(0)
里帰りしたヴェテラン越僑シンガー タイン・ハー [東南アジア]

うわぁ、まるでエドワード・スタイケンのファッション写真みたいじゃないですか。
マレーネ・ディートリッヒやグレタ・ガルボの名フォトの数々が思い浮かぶ、
ノスタルジックなセピア調のジャケット・デザインに目を奪われました。
ヴェトナムのヴェテラン・ポップス・シンガー、タイン・ハーの新作です。
ドイツ系アメリカ人の父とヴェトナム人の母のもとに生まれたタイン・ハーは、
少女時代から地元ダナンのラジオ局で歌ってきたという人。
高校卒業後に難民申請してフィリピンへ渡り、
難民キャンプの美人コンテストで優勝してから本格的に歌手活動を始めたそうで、
91年にアメリカへ移り、96年にトゥイ・ガからデビュー、
越僑歌手として20年以上のキャリアがあります。
白人の父親の影響でヴェトナム人的な顔立ちでないところが、フィ・ニュンと同じですね。
そんなタイン・ハーが、17年から活動拠点をヴェトナムへ移し、
ヴェトナムの若手作曲家や音楽家たちとプロジェクトを組み、
2年の歳月をかけて作り上げたのが本作です。
若手による作品ながら、ノスタルジックな抒情歌謡路線のアルバムで、
近年のボレーロ・ブームに沿った作品といえます。
実は、タイン・ハーを聴くのはこれが初めてなんですが、
おそらくトゥイ・ガから出していたアルバムとはがらりと違っているんじゃないかな。
語尾のヴィブラート使いのしつこさがやや気になりますけれど、
少しハスキーな声で軽やかに歌いながら、
しっとりとした情感を出すあたりは、さすがですよ。
ドラマティックな曲で歌い上げても、まったくしつこさを感じさせず、
さっぱりしてるところも美点ですね。
ドライな味に魅力のある人です。
Thanh Hà "MỚI MẺ NÀO CŨNG NGỌT NGÀO" Phương Nam Phim no number (2019)
2019-06-06 00:00
コメント(0)
タクシー・ギャングのミリタント・ビート ビティ・マクリーン [カリブ海]
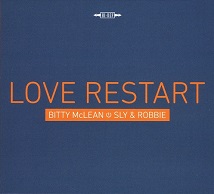
う~ん、このリディムの快楽といったら!
スライ&ロビーが繰り出すビートに、いつまでも身を浸していたくなります。
まさしく満足度100%保証付きのグルーヴであります。
ブラック・ウフルーを支える屋台骨として大活躍していた
80年代を思わすミリタント・ビートが、また聴けるとは思いもよりませんでした。
これもまた、ルーツ・レゲエの回帰現象なんでしょうか。
懐かしいリディム・コンビに乗るのが、甘々のラヴァーズ・ロックで、
しゃがれ声のルーツ・レゲエが好きな当方には、甘味が強すぎますけれど、
とにかくバックのサウンドの魅力には抗しがたく、買ってまいりました。
ビティ・マクリーンというこの人、UKレゲエのヴェテラン・シンガーとのこと。
レゲエ門外漢なもので初耳でしたが、もう何度も来日しているようですね。
もともとはサウンド・エンジニアで、UB40を手がけていたというのだから、
相当なキャリアの持ち主です。
スライ&ロビーのリディム・セクションに、マイキー・チャンのギター、
ロビー・リンのキーボード、スティッキー・トンプソンのパーカッションって、
どんだけ80年代タクシー・ギャングまんまなのって感じ。
あの当時はエッジの利いたサウンドが、どんどん攻撃的になっていって、
ポール・グルーチョ・スマイクルがミックスするようになると、
かなり派手なサウンドになっちゃったんだっけ。
グルーチョがまだ絡む前のタクシー・ギャングのサウンドが好きだったから、
鍵盤類が音を重ねすぎない、このシンプルなプロダクションはすごく好み。
なんたって、スライのドラミングが映えるもんねえ。
はじめは甘すぎると感じたビティのスムースな歌い口も、繰り返し聴くうちに抵抗感も薄れ、
初夏に向かうこの季節にぴったりな、爽やかな風を浴びている気分です。
Bitty McLean・Sly & Robbie "LOVE RESTART" Taxi/Silent River/Tabou 1 SRCD002 (2018)
2019-06-04 00:00
コメント(0)
パウロ・フローレスのルゾフォニア音楽絵巻 [南部アフリカ]
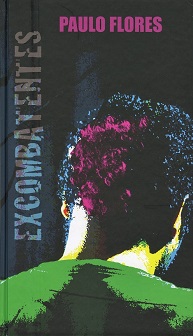

アンゴラのヴェテラン・シンガー・ソングライター、パウロ・フローレスが
09年に出した3枚組の力作“EXCOMBATENTES” がようやく手に入りました。
12年に出た“EXCOMBATENTES REDUX” は、本作の抜粋ヴァージョンで、
あー、全編聴きたいなあと、長年願っていたんですよ。
10年も前の作品で、入手はもう不可能だろうとすっかり諦めていたんですが、
よく残っていたもんです。うれしー♡
3枚のディスクは、それぞれ「旅」「センバ」「島」と題され、
トール・サイズのCDブックに収められています。
パウロ自身が音楽監督を務めるほか、
ブラジルのプロデューサー、シコ・ネヴィスを迎えて制作されました。
シコ・ネヴィスといえば、レニーニの97年ソロ・デビュー作の
プロデュースを手がけたことなどで知られていますね。
レコーディングは、ルアンダ、リオ・デ・ジャネイロ、リスボンと、
アンゴラ、ブラジル、ポルトガル3か国に渡って行われていて、
まさしくルゾフォニア(ポルトガル語圏)・コネクションといえます。
ブラジル録音では、ベースのアルトゥール・マイア、チェロのジャキス・モレレンバウム、
ピアノのダニエル・ジョビン、クラリネットのパウロ・モウラ、ラベッカのシバ、
ピファノとサックスのカルロス・マルタといった名うてのミュージシャンたちが参加。
その名をよく知るブラジル音楽ファンなら、おおっ!と注目せずにはおれないでしょう。
2枚目がセンバと題されているとおり、センバのリズムの曲が多いものの、
3枚ともMPBならぬMPAと呼ぶべきサウンド・プロダクションで、
パウロの詩的な美しさを湛えたコンポーズを引き立てています。
パウロの自作曲以外では、ユリ・ダ・クーニャとデュエットした、
ダヴィッド・ゼーの往年の曲‘Rumba Nza Tukiné’ や、
マイラ・アンドレーデとデュエットしたヴィニシウス・ジ・モライスと
バーデン・パウエルの名曲「プレリュードのサンバ」がハイライトですね。
もちろんこれらは抜粋盤にも収録されていましたけれど、
そこから漏れた曲ではドロドロのブルースの‘Eu Quero É Paz’ や、
アコーディオンとホーン・セクションを配したダンサブルなセンバの‘Contratempo’、
カーボ・ヴェルデのダンス・リズム、フナナーの‘Funana Di Nha Filo’ など、
聴きものが目白押しで、やっぱりこの3枚を聴けばこそ、
パウロのルゾフォニア音楽絵巻を堪能することができます。
Paulo Flores "EXCOMBATENTES" LS Produções no number (2009)
Paulo Flores "EXCOMBATENTES REDUX" Terra Eventos 3700409810480 (2012)
2019-06-02 00:00
コメント(0)




