ムーリッシュ・エレクトロ アフメドゥ・アフメド・ロウラ [西アフリカ]

サヘル・サウンズの新作は、モーリタニアのシンセ奏者のソロ・アルバム。
相変わらずのサヘル・サウンズの悪弊で、CDには曲名しか載っておらず、
解説もクレジットもまったくなし。レーベル・サイトを見てもロクな情報は載っておらず、
かろうじてバンドキャンプの解説に、父親が有名なティディニート奏者である
音楽一家の生まれ、という一文があるので、
イガウィン(ムーア人のグリオ)出身の音楽家だということがわかります。
シンセサイザーとパーカッションによって演奏されるこのインスト音楽は、
バンドキャンプの解説によれば、モーリタニアでWZN(何の略?)と呼ばれていて、
街中、タクシーなどでガンガンかけられている人気のポップ・ミュージックなんだそう。
なかでもアフメドゥ・アフメド・ロウは、このジャンルの大スターで、
ラヌアクショットのパーティーや結婚式で引っ張りだこといいます。
聴き始めは、80年代初めのオラン産ポップ・ライみたいな、
チープなシンセ・サウンドかとも思ったんですが、
聴き進むうちに、しっかりとアレンジされ、練られた構成のサウンドに
すっかり感心してしまいました。いやぁ、音楽性高いぞ、この人。
初期ポップ・ライみたいな手癖のフレーズを垂れ流してたシンセとは大違いです。
アフメドゥ・アフメド・ロウラがシンセで演奏しているのは、
欧米のコピー音楽などではなく、ムーアの伝統音楽そのもの。
「カル」「レブテイト」といった曲名に表わされているとおり、
ムーア音楽の旋法ブハールに沿った演奏をしています。
伝統音楽にはなかった新たなハーモニーを加えて、
歌や合唱のメロディをさまざまな音色でレイヤーさせつつ、
伝統楽器のティディニートをエレクトリック・ギターに置き換えたサウンドも、
シンセで模しています。
ムーア音楽の本質をなんら歪めることなく、
ダイレクトにエレクトロニックなサウンドに変貌させたところがすごく新鮮で、
現地で大受けというのもよくわかります。
なんでもギリシャのシンセ奏者ヤニーの影響を受けたとのことで、
YouTube のライヴ・パフォーマンスなどを観ると、なるほどと思わせます。
Ahmedou Ahmed Lowla "TERROUZI" Sahel Sounds SS054 (2019)
2019-07-30 00:00
コメント(0)
コンゴ独自のルンバ誕生史物語 [中部アフリカ]

『パームワイン・ミュージック・オヴ・ガーナ』から2年。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-08-27
ついに出ました! コンゴ・ポピュラー音楽黎明期のヴィンテージ録音集。
深沢美樹さん所有のSPコレクションから選曲、
健筆もふるった48ページの日本語解説(プラス全文英訳!)付きという、
世界中のアフリカ音楽ファンが瞠目する2枚組ボックスです。
アフリカ全土に影響を及ぼしたコンゴ生まれのルンバがどのように誕生したのか、
それは長い間ベールに包まれたままでした。
コンゴで誕生した独自のルンバが50年代以降発展していく姿は、
ドイツのポピュラー・アフリカン・ミュージックやベルギーのクラムド・ディスクが
優れた編集盤を出していましたけれど、それより以前の40年代録音は
ウェンドの大ヒット曲「マリー=ルイーズ」1曲を除き、
ずっと未復刻のままだったからです。
今回深沢さんは、その知られざる40年代録音から復刻するというので、
大期待していたんですけれど、ディスク1冒頭1曲目でもう、快哉を叫んじゃいました。
コンゴで初めて「ルンバ」と記されたというその音源、
なんとブラス・バンドじゃないですか。
オルケストル・オデオン=キノワ名義のその2曲から、
これぞアフリカ・ポピュラー音楽史の醍醐味と、ウナりましたよ。
「コンゴ・ポピュラー音楽の父」と呼ばれる、
ウェンドのギター弾き語りスタイルに代表されるとおり、
歴史は素朴なギター弾き語りから始まった、な~んて思いがちじゃないですか。
でも、アフリカ大衆音楽の歴史を少しカジっている人なら、
ぜんぜんそうじゃないことは、ご存じですよね。
ゴールド・コースト(現在のガーナ)やナイジェリアしかり、南アしかりです。
はじまりは軍楽隊がもたらしたブラス・バンドであり、ミッション系合唱の賛美歌であり、
アフリカのブラックネスとはほど遠い、<白い>音楽がそのスタートだったのです。
その演奏も<素朴>どころか、模範とする西洋音楽の洗練をしっかりと獲得したもので、
じっさいこの冒頭の1曲目でも、対位法のアレンジを用いた
見事なブラス・アンサンブルを聴くことができます。
その後は、西アフリカのパームワイン音楽に影響されて誕生したという
ギター音楽のじっさいを聴くことができるんですが、
20年代に西アフリカの労働者たちがもたらしたギター・スタイルの痕跡が
くっきりと表れているのには、興奮させられましたねえ。
ゲイリー・スチュアートの著書などで、西アフリカのパームワイン音楽の影響が
コンゴ音楽黎明期にあったとは知っていても、
具体的な音資料で聴くことができないものだから、いまひとつピンとこなかったんですよ。
だって50年代以降の録音を聴くと、
ルンバの独自のギター・スタイルがもう出来上がっていて、
そこにはパームワインの影響など、微塵も感じられなかったからです。
ウェンドの48年録音だって、そのギターにパームワインの影は感じられませんでした。
しかし、ここに収録されたデ・サイオの46年録音や
コジア・アレクサンドルの46-47年録音、レオン・ブサカの48-49年録音、
オリヴェイラの50年録音などを聴くと、いずれも20年代のパームワイン音楽の
ギター・サウンドと共通している点が聴き取れます。
それは、クワメ・アサレのような前のめりにつんのめるビート感を持つ、
デルタ・ブルース的なサウンドとはまた違ったギター・スタイルです。
特に、低音弦がステデイなベース音を鳴らし、せわしないアルペジオを奏でるところは、
20年代のジョージ・ウィリアムス・アインゴなど、
ファンティ人やガ人のパームワイン・ギタリストたちと共通するフィンガリングで、
同時代アメリカのイースト・コーストの
ラグタイム系ブルース・ギタリストさえ想起させます。
これには思わず、なるほどぉ、とウナらずにはおれませんでした。
ようやく積年の謎が解けた思いですよ。
これがやがて、ディスク1のラストを飾るジミーの51年録音では、
アニマシオンまで聞ける、後年のコンゴ独自のルンバ完成型を聴くことができます。
ちなみにこの曲、フランス、ブダが先日出した編集盤
“NOSTALGIQUE KONGO: RUMBAS LINGALA, SWAHILI, KIKONGO & DOUALA
1950-1960” に収録され、タッチの差で世界初CD化の栄誉を譲りましたけれど、
本盤の方がヴォーカル、ギターともに輪郭がくっきりとしたガッツのある音質で、
マスタリングでは勝ちましたね。
ディスク1のことばかり書いちゃいましたけれど、
ディスク2に移ると、コンゴ独自のルンバがもう全面展開。
ゴツゴツとしたベースに、粘るオルガンもヘヴィーな黒光りするサウンドの、
55年の6・7曲目のアフリカン・ジャズなど、もう失禁ものでしょう。
コンゴ独自のルンバ誕生の歴史物語を鮮やかに描いてみせた作品、マスターピースです。
v.a. 「EARLY CONGO MUSIC 1946-1962: FIRST RUMBA, TO THE REAL RUMBA」 El Sur 009
2019-07-28 00:00
コメント(2)
クロンチョンの生まれ故郷で クロンチョン・トゥグー [東南アジア]

クロンチョン・トゥグー? そんなクロンチョン楽団があるの?
クロンチョン発祥の地トゥグーのクロンチョン楽団といえば、
由緒あるオルケス・クロンチョン・カフリーニョ・トゥグーが有名ですけれど、
クロンチョン・トゥグーという楽団名は、初耳です。
調べてみると、オルケス・クロンチョン・カフリーニョ・トゥグーの
チェロ奏者だったアレンド・J・ミッシェルが、88年に結成した楽団とのこと。
アレンド・J・ミッシェルは、かつての解放奴隷(トゥグー集落の住民)の末裔たちの
絆を深めるため、76年にコミュニティ組織を設立し、
さらに若い世代へ伝統音楽を継承するために、クロンチョン・トゥグーを結成したとのこと。
93年にアレンドが死去した後は、息子のアンドレが楽団リーダーを継いだそうです。
トゥグーのクロンチョン楽団は、70年代になると、
オルケス・クロンチョン・カフリーニョ・トゥグー
ただひとつになるまで衰退してしまいますが、
アレンドたちの努力によって、若手音楽家の育成が図られ、
現在オルケス・クロンチョン・カフリーニョ・トゥグー、クロンチョン・トゥグー、
クロンチョン・ムダ=ムディ・コルネリスの3つのグループが活動しているそうです。
で、このクロンチョン・トゥグー、いいじゃないですか。
真面目な伝統保存一辺倒なのかと思いきや、
風通しのいい演奏ぶりで、とても自由なんですよ。
伝統保存に足を縛られることもなければ、型を守るあまり窮屈となることもなく、
伸び伸びと演奏しているのが伝わってきて、嬉しくなります。
もちろん、クロンチョンの伝統形式に沿った演奏ではあるものの、
洒落たブリッジを挟み込んだり、
ヴァイオリンを多重録音して柔らかなハーモニーを作ったり、
ギターのちょっとしたトリッキーなプレイでユーモラスな場面を付け加えたりと、
自然なヘッド・アレンジで生まれたアイディアが、ふんだんに盛り込まれています。
優雅なワルツの‘Oud Batavia’ や、
若い女性歌手が歌う‘Mardijkers’ のしっとりした味も格別。
全体にアマチュアぽさが貫かれているところもこの楽団の良さで、
ローカルな味わいに溢れています。
クロンチョンの生まれた原点が、そのまま息づく姿をパッケージした得難い作品です。
Krontjong Toegoe "DE MARDIJKERS" Gema Nada Pertiwi CMNP438 (2018)
2019-07-26 00:00
コメント(4)
トゥアレグのゴッドマザー バディ・ララ [中東・マグレブ]

ティナリウェンの”LIVE IN PARIS” にフィーチャーされた、
伝説のトゥアレグ人女性歌手バディ・ララ。
80歳にしてリリースされた初アルバムです。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-01-09
アルジェリア南部、ニジェール国境に近い町
イン・ゲザムで37年に生まれたバディ・ララは、
10歳の時から母親とともに、ティンデが催される祝祭の場で歌ってきた大ヴェテランで、
60年代にトゥアレグのミューズとして人気を博した人です。
70~80年代には、テイナリウェン同様、
トゥアレグの民族意識を高める文化的アイコンとなって、
トゥアレグのゴッドマザー的な役割を果たします。
アルジェリアやマリの若いトゥアレグ人ミュージシャンたちと積極的に共演し、
90年に15人の男女からなるグループを率いてヨーロッパをツアーするなど、
海外でも知られる存在となりました。
そんな伝説的存在のバディ・ララの初アルバムでは、
太鼓(ティンデ)と手拍子とお囃子のみで歌われる伝統的なティンデと、
ギター・バンドを加えた、いわゆる「ギター・ティンデ」と呼ばれるスタイルを織り交ぜて
歌っていて、ギター・ティンデの伴奏は、イムザードが務めています。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-08-30
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-07-28
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-02-24
ティナリウェンのライヴでも披露された、
チャントを唱えるドローンのようなお囃子をバックに、
バディ・ララが詩を吟じるのですけれど、
単調な反復だけでできている曲が退屈しないのは、
歌と手拍子とバンドのリズム・セクションが生み出す、
ポリリズムの豊かなニュアンスゆえですね。
微妙にズレる手拍子や、お囃子の男女の異なる声がレイヤーされるところに、
ティンデの味わいがあるといっても、過言じゃありません。
ゆるい独特のグルーヴは、催眠的なトランスを招き寄せる魅力があり、
アルバム中盤で3曲続けて歌われる伝統的なティンデに、
それはひときわ強く表われています。
トゥアレグ女性の歌のレパートリーには、昼間の祝祭で歌われるティンデともうひとつ、
夜に若い女性が将来の伴侶を見つけるために歌う、イスワットというものがあるそうです。
トゥアレグ版歌垣みたいなものなのでしょうかね。
イスワットは、男性が低音でずっと唸るように歌う
イシガダレンと呼ばれる合唱をバックに、女性が詩を吟じるもので、
ティナリウェンのライヴの曲がまさにそれに近いものでしたね。
曲名は‘Tinde’ となっていましたけれど、
ティンデとイスワットって、どういうふうに聴き分けるんだろう?
Badi Lalla "IDI YANI DOUHNA" Padidou CD783 (2017)
2019-07-24 00:00
コメント(0)
『バイーアのサンバ』と『サンバのバイーア』 ギガ・ジ・オグン、ヴァルミール・リマ、セウ・レジ・ジ・イタプアーン [ブラジル]


バイーアの3人のヴェテラン・サンビスタが集まり、
各自4曲ずつ持ち寄って歌ったサンバ・アルバム。
この企画の下敷きとなったのが、73年にフォンタナから出た
バイーアの重鎮サンビスタ3人、リアショーン、バタチーニャ、パネーラによる
“SAMBA DA BAHIA” だというのだから、嬉しいじゃないですか。
“SAMBA DA BAHIA” は、ぼくもさんざん愛聴したバイーアのアフロ・サンバの名盤。
リアショーンの野性味たっぷりなマランドロ気質をうかがわせる歌いっぷりと、
対照的にバタチーニャの哀愁味のある繊細な味わいなど、
リオとは違うバイーアの闊達なサンバをとことん味わえるアルバムです。
リアショーンもバタチーニャも本作が初アルバムで、
パネーラにいたっては、このアルバム以外の録音を聞いたことがないという
極端に録音が少ない人たち。
いまだ未CD化というのも、この名盤が忘れられている証拠と思っていましたが、
こんな企画が立てられて新たなサンバ・アルバムが制作されるとは、
神様はちゃんといるんだななんて、不信人者のぼくでも思っちゃいますね。
ギガ・ジ・オグン、セウ・レジ・ジ・イタプアーンという人は初めて知りましたが、
ヴァルミール・リマは、リアショーンやバタチーニャたちとも一緒に歌ったサンビスタで、
その作品はベッチ・カルヴァーリョやフンド・ジ・キンタルなどもよく取り上げていました。
ヴァルミールのコクのあるノドは、さすがヴェテランの味わいといえます。
ギガ・ジ・オグンのあけっぴろげな歌いっぷりは、庶民的な雰囲気いっぱいだし、
低音のセウ・レジ・ジ・イタプアーンの歌声も温かみがあって、
ときどき音程が怪しくなるあたりも微笑ましくて、憎めません。
‘SAMBA’ と ‘BAHIA’ をひっくり返したタイトルも、
かつてのバイーア・サンバ名盤へのリスペクトに溢れた
サンバ・ファン必聴の名作誕生です。
Guiga De Ogum, Walmir Lima & Seu Regi De Itapuã "BAHIA DÁ SAMBA" Kyrios KYRIOS3426-18 (2018)
[LP] Riachão, Batatinha e Panela "SAMBA DA BAHIA" Fontana 6470.506 (1973)
2019-07-22 00:00
コメント(0)
バイーアの新人サンフォネイロ ジュニオール・フェレイラ [ブラジル]

バイーアらしいアフロ・リズムにのせて、
ヴォイス・パーカッションの多重録音で始まる冒頭からぐぐっと引き込まれる、
バイーア出身の新人サンフォネイロ(アコーディオン奏者)のデビュー作。
続いて、バイオーンのリズムにのせてアコーディオンがすべり込んでくるところで、
もうツカミはオッケーというか、前のめりになるしかありません。
途中、ギターがジャジーな速弾きを繰り出すところで、降参です。
アコーディオンの腕前は確かで、随所で聞ける軽やかな運指やリズム感に、
技量の高さがはっきりとわかります。
自作曲のショーロ‘O Pó da Rabióla’ や、
ガロートの名ショーロ‘Jorge do Fusa’ での歌ゴコロいっぱいのプレイにも、
それはよく表れていますね。
本人が歌うシロウトぽい素朴な歌い口も、味わいがありますよ。
ナザレー出身のサンビスタ、ロッキ・フェレイラ作の‘Dona Fia’ で聞かせる
温かなヴォーカルは、ロッキ・フェレイラのオリジナルを凌ぐ仕上がりじゃないですか。
MPBのセンスを十分に発揮したサウンド・プロダクションにも、
音楽性の高さが発揮されています。
ラストのフレーヴォ‘Dona Fia’ まで、北東部の多彩なリズムを活かしながら、
確かなテクニックで聞かせたサンフォーナの快作。
ドミンギーニョスに師事して、ジルベルト・ジルやイヴェッチ・サンガロなどに
引っ張りだことなっている新進アコーディオニスト、
メストリーニョの良きライヴァルとなる、頼もしい新人の登場です。
Junior Ferreira "CASA DE FERREIRA" Aruwá Produções 2018781165 (2018)
2019-07-20 00:00
コメント(2)
タラフ・ドゥ・ハイドゥークスの先達 タラフル・ディン・クレジャニ [東ヨーロッパ]

写真家の石田昌隆さんが、00年12月にルーマニアのクレジャニ村を訪れ、
タラフ・ドゥ・ハイドゥークスの写真を撮った時のことを書かれた
フェイスブックの記事を読んでいて、気になる記述を見つけました。
ベルギーの作曲家ステファーヌ・カロがタラフ・ドゥ・ハイドゥークスを発見したのは、
88年のオコラ盤『クレジャニ村の楽師たち』がきっかけでしたけれど、
それよりもずっと昔に、ルーマニアの国営レコード会社のエレクトレコードが、
クレジャニ村の楽師たちの音楽を録音していたと、石田さんが書かれていたんですね。
その録音は49年と52年に行われたもので、07年になってその音源が
ルーマニアの民族音楽学者マリアン・ルパシュクによって編集され
CDリイシューされたとあり、そのCDタイトルも書かれていました。
こんな記事を読んだら、手に入れるっきゃないじゃないですか。
さっそくルーマニアから取り寄せましたよ。
届いたのは、簡素なペーパー・スリーヴのCD。
音楽学者がコンパイルして国営レーベルから出したものだというから、
てっきり充実した解説付きのCDが届くとばかり想像していたので、これにはがっかり。
というわけで、文字情報は得られませんでしたが、
ハイドゥークスの先人たちの音楽を聴くことができました。
タラフ・ドゥ・ハイドゥークスとまったくかわらない、
祝祭感いっぱいの奔放な演奏ぶりが圧巻です。
生命力あふれる歌いぶりに、なるほどハイドゥークスは
この村の伝統を忠実に継承してきたんだなということが、よくわかります。
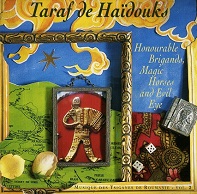
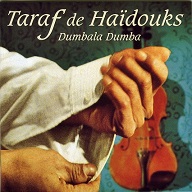
じっさい、このCDに収録された歌曲の‘Săbărelu’ は、ハイドゥークスの94年作
“HONOURABLE BRIGANDS, MAGIC HORSES AND EVIL EYE” で聞けるほか、
高速ダンス・チューンの‘Brâu’ も98年作“DUMBALA DUMBA” で聞け、
編成の違いがあるとはいえ、その演奏ぶりに半世紀近い開きを感じさせないのだから、
スゴイです。強烈なスピード感は、昔からずっとそうだったんですねえ。
音質がめちゃくちゃ良いせいで、なおさら古さを感じさせません。
91年のデビュー作でタラフ・ドゥ・ハイドゥークスに圧倒されたぼくには、
その後世界各国で引っ張りだこになるにつれ、
超絶技巧を売り物するケレン味が強くなっていくのに、食傷気味となりました。
いまでもタラフ・ドゥ・ハイドゥークスの90年代のアルバムに一番愛着があるせいか、
このタラフル・ディン・クレジャニの演奏は、ぼくにはとても美味であります。
Taraful Din Clejani "CLEJANI DE ALTĂDATĂ 1949-1952" Intercont Music no number
Taraf De Haïdouks "HONOURABLE BRIGANDS, MAGIC HORSES AND EVIL EYE" CramWorld CRAW13 (1994)
Taraf De Haïdouks "DUMBALA DUMBA" CramWorld CRAW21 (1998)
2019-07-18 00:00
コメント(0)
季節はずれのクリスマス・アルバム ジュリア・ブトロス、マジダ・エル・ルーミー [中東・マグレブ]


ジュリア・ブトロスのクリスマス・アルバムが12年に出ていたんですね。
アラブのポップスのサイトを眺めてたら、偶然に見つけちゃって、大あわて。
いやぁ、これまでぜんぜん気付かなかったなあ。
あれ、13年にはマジダ・エル・ルーミーまで、
クリスマス・アルバムを出してるじゃないですか。
こりゃなんたることかと、レバノンのお店に早速オーダー。
昨年ヒバ・タワジのクリスマス・アルバムを、
1年遅れでようやく聴いたところでしたけれど、それより5年も前に出ていた、
ぼくのごひいきの二人のクリスマス・アルバムを知らずにいたとは、不覚も不覚でした。
それにしても、レバノンくらいクリスマス・アルバムを出す国は、
アラブ世界にありませんね。
国民の4割がキリスト教徒ですもんねえ。
フェイルーズのクリスマス・アルバムも有名ですね。
ジュリア・ブトロスのクリスマス・アルバムは、
兄のジアド・ブトロスの作曲、伴奏はプラハ市交響楽団で、
ジャズ・ピアニストのミシェル・ファデルによるアレンジという、
12年1月にリリースされた“YAWMAN MA” とまったく同じ布陣で制作されたものです。
これ以上何を求めようかというくらい、完璧なプロダクションにのせて歌う
ジュリアの慈愛に満ちた艶っぽい歌いぶりに、もうメロメロです。
児童合唱団の子供たちと歌うユーモラスな曲など、
今回はさすがにクリスマス・アルバムということもあり、
愛国心やアラブの団結を訴えかける曲はないようですね。
4曲目の、ハーモニカをフィーチャーしてラテン・ボレーロにアレンジした
トロけるような曲など、そっと語りかけるようなジュリアの歌い口に、
ああ、いい歌手だなあと、しみじみ思います。
マジダ・エル・ルーミーのクリスマス・アルバムはミニ・ブック仕様で、
内容は歌詞付きの写真集となっています。
こちらはベルリン交響楽団が伴奏を務めていて、ジュリアのアルバム同様ゴージャス。
ジュリア・ブトロスのクリスマス・アルバムとの違いは、
ミュージカル/オペラ調のプロダクションが目立つことでしょうか。
マジダらしい温かみのある声が発揮されたキャロルはステキだけれど、
オペラ調の強く声を張って歌う曲や男性コーラスが入る曲などは、
ちょっとぼくの好みとは違うかなあ。
特にラストがオペラチックな曲で終わるのは、ちょっと後味悪し。
というわけで、ジュリア・ブトロスのクリスマス・アルバムの方が
断然お気に入りですけれど、どちらもレバノンを代表する歌手にふさわしい
力のこもった制作ぶりが光る、クリスマス・アルバムです。
Julia Boutros "MILADAK" Longwing no number (2012)
Magida El Roumi "NOUR MEN NOUR" V. Production no number (2013)
2019-07-16 00:00
コメント(3)
梅雨寒にジャジー・ヒップ・ホップ ザ・デリ [北アメリカ]
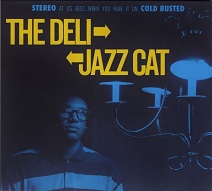
ぜんぜんお日様が顔を見せませんねえ。
7月に入ったら、夏どころか季節が逆戻りしたような梅雨寒になってしまって、
職場で半袖シャツを着てるのがぼくだけで、一人クールビズかよという、
恥ずかしいことになっています。
まあ、通勤でウォーキングするぶんには、ぜんぜん寒くないし、
本人的にはノー・プロブレムなのではありますが。
6月までせっかく夏気分の音楽でウォ-キングしてたんですけれど、
すっかり音楽も梅雨対応に替えている今日この頃。
そんな梅雨寒の時期には、これまたぴったりというアルバムに出会いました。
オースティンのビートメイカー、ザ・デルズのジャズ・サンプリング・ビーツ作品。
50年代のジャズ・レーベル、
ベツレヘムあたりのジャケット・デザインを思わせるムードが、
この音楽の内容を、的確に表現しています。
ラッパー不在のインストのビート・アルバムで、いわゆるジャジー・ヒップ・ホップ、
ヒップ・ホップ感覚のラウンジ・ミュージックですね。
傘をさしていても、腰下をびっしょりと濡らしてしまう、
しとしと雨の中をウォーキングするBGMには、ぴったりです。
ローズやシンセの鍵盤がたゆたうサウンド、温かみのある箱物ギターの響き、
フックの利いたビートの刻みや、地の底を這う重いベース・ライン、
そして全編にかぶさるレコードのチリ音、そのすべてが美しく、耳に心地良いんです。
ジャジー・ヒップ・ホップって、梅雨時に合うよねえ。
サウンド・プロヴァイダーズもこの季節の定番。
そういえば、また最近再プレスしたらしく、CDショップに並んでいました。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-11-14
ところで、収録トラックには、
‘2:11AM Ikebukuro’ ‘Rainy Day In Japan’ なんてタイトルもあって、
この人、日本に住んでいたことがあるんでしょうか?
The Deli "JAZZ CAT" Cold Busted BUSTED163CD (2018)
2019-07-14 00:00
コメント(0)
繊細にして豪胆なギター・トリオ プレストン・グラスゴウ・ロウ [ブリテン諸島]
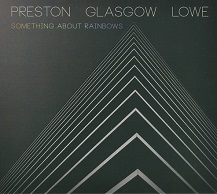
CDショップのジャズ・コーナーであれこれ試聴していたところ、
まるでシュミじゃないサイケなジャケットのCDに、ピンとくるものがありました。
全然知らない人でしたけれど、キレのあるコンテンポラリー・ジャズ・ギターに、
こりゃあいい、と買ってみたところ、家に帰って聞いてみれば、ええぇ~?
まるで違うエレクトロな音楽が飛び出し、ビックリ。
なるほど、これならジャケどおりだわなと、ひとりごち。
どうやら試聴機に間違ったCDが入っていたようで、翌日再訪したところ、
「すみません、これ全然別のCDですね」と店員さん平謝り。
試聴機に入っていたのは、こちらですと差し出されたのは、
UK新世代ジャズのプレストン=グラスゴウ=ロウの新作。
なーるほど、彼らか! それならナットクだわ。
おととしのデビュー作がお気に入りとなっていた、プレストン・グラスゴウ・ロウ。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-05-09
デイヴィッド・プレストンのメカニカルなギターに、ケヴィン・グラスゴウの6弦ベース、
ローリー・ロウのドラムスが緊密に絡み合ってインプロヴァイズする快感は、
2年ぶりの今作も変わりません。
ローリー・ロウのしなやかなドラミングが、
バンド・サウンドにあざやかなコントラストをつけ、
ギターとベースにフリーなスペースを与えることで、
バンドのダイナミズムを拡張しているところが、この3人組のキモ。
パット・メセニー、アラン・ホールズワース、ロバート・フリップに通じる
デイヴィッド・プレストンのギター・テクニックも舌を巻くばかりなんだけれど、
そのギター・サウンドを輝かせているのが、ローリーのドラミングといえます。
多くのトラックをデイヴィッドが作曲していますが、
今作の聴きどころは、ケヴィン・グラスゴウが作曲した2つのトラック。
そのひとつが、アルバム中もっともロックぽいサウンドとなったタイトル・トラック。
オーヴァードライヴしたベースがごつい響きをあげて、
重厚なメタル・ロックを繰り広げます。
一方、ドイツの現代音楽の作曲家ハンス・ヴェルナー・ヘンツェの頭文字を
曲名に取ったラスト・トラックは、十二音技法を取り入れたもので、
このトリオの音楽性をさらに前進させましたね。
繊細にして豪胆な新世代ジャズ・ギター・トリオ、次作は間違えないように買おう。
Preston Glasgow Lowe "SOMETHING ABOUT RAINBOWS" Whirlwind Recordings WR4731 (2018)
2019-07-12 00:00
コメント(0)
ナイジェリアとUKが共振するバンクー・ミュージック ミスター・イージー [西アフリカ]
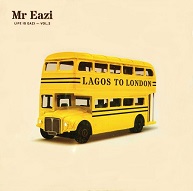
アフロビーツの新人、ミスター・イージーの新作は、
ミックステープ“LIFE IS EAZI” の続編。
前作の「アクラからレゴス」から今作は「レゴスからロンドン」と、
いまも旅の途中にあるようです。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-06-12
冒頭の短いイントロが、クラシックな香りのハイライフで、
思わず頬をユルませていると、続くトラックで登場するゲストは、シミ。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-02-07
そのチャーミングな歌声を聞けば、すぐシミとわかります。
アデクンレ・ゴールドのヨメさんになっちゃったけど、プリティぶりがたまりませぬ♡
前半にフィーチャーされるのは、ナイジェリアのアーティストが中心で、
後半はUKベースのアーティストが中心で、おそらくロンドン録音なのでしょう。
EDM最強のプロデューサー、ディプロの参加には驚かされましたけれど、
ディプロとコラボした‘Open & Close’ がめちゃくちゃカッコよくて、
アルバム最大のフックとなっていますよ。
このほか、ルーツ・レゲエ・リヴァイヴァルを牽引する若手のクロニクスや、
バーミンガムのラップ・デュオのロト・ボーイズに、
ブリクストンのラッパーのスニークボ、ペクナムのラッパーのギグスも登場します。
ミスター・イージーがバンクー・ミュージックと標榜する、
アフロ・フュージョンの中身が前作ではよく見えなかったんですけれど、
今作ではその多様な音楽性が、はっきりと見てとれるようになりましたね。
ハイライフ、ダンスホール、グライム、EDM、ニュー・エイジR&Bがミクスチャーされ、
そのうえに、ナイジェリアのピジン、ケニヤのシェン、ジャマイカのパトワ、
ロンドンのストリート・トークと、さまざまな言語が織り重なって、
UKとナイジェリアのヴァイブを共振させたアフロビーツの魅力を輝かせています。
Mr Eazi "LIFE IS EAZI, VOL.2 - LAGOS TO LONDON" Banku Music no number (2018)
2019-07-10 00:00
コメント(0)
ナイジェリアのヘップ・キャットが残したトランペット・ハイライフの傑作 ジール・オニイア [西アフリカ]

ジール・オニイアのリーダー作なんて、あったんですか!
うわあ、まったく知りませんでした。これは驚きのリイシューです。
ジール・オニイアは、ナイジェリアン・ハイライフの巨匠
ボビー・ベンソンのジャム・セッション・オーケストラでキャリアをスタートした、
ナイジェリアの名トランペッターの一人。
ボビー・ベンソンのもとから巣立ったトランペッターに、
ヴィクター・オライヤ、エディ・オコンタ、ロイ・シカゴがいますけれど、
ジール・オニイアもその一人だったんですね。
ボビー・ベンソンの代表曲であり、ナイジェリアン・ハイライフ最重要曲の
「タクシー・ドライヴァー」でトランペット・ソロを取った
ビル・フライデーの控えとして、49年にリクルートされた時のジールは、
まだオニッチャの中等学校に通う15歳の少年でした。
51年に撮られたジャム・セッション・オーケストラの有名な写真には、
テナー・サックスを構えてひざまずくボビー・ベンソンの後方で、
譜面台を前にした11人のメンバーの中に、
トランペットを持ったジールが写っているそうで、
一番左に座っているのがジールなのかもしれません。

ジールは54年にボビー・ベンソン楽団を退団すると、
ガーナのアクラへ向かい、E・T・メンサーのテンポスの一員に加わり、
その後リズム・エイシズ、メロディ・エイシズという
ガーナのハイライフ・バンドを渡り歩き、
翌55年にダンス音楽を学ぶため、ロンドンへ留学します。
ロンドンで勉学に励むかたわら、
夜はジャズ・ミュージシャンたちとジャム・セッションを重ね、
アンブローズ・キャンベルのウェスト・アフリカン・リズム・ブラザーズと
ハイライフやカリプソなどを演奏する2年間を過ごし、57年にナイジェリアへ帰国します。
帰国後は、自身の楽団で活動するほか、イボ・ハイライフのシンガーの伴奏を務め、
デビューまもないステファン・オシタ・オサデベに、
トランペットや音楽理論にアレンジを教え、一躍人気歌手へと押し上げました。
60年にはナイジェリア音楽家組合NUMの副会長
(会長はヴィクター・オライヤ)に就任する一方、
アフロ・ジャズを志向して、62年にコリコ・クラン・ジャズ・グループを結成、
64年にはピアニストのアート・アラデ率いるジャズ・プリーチャーズに、
サックス奏者のクリス・アジロとともに加わりジャズを演奏しますが、
いずれも活動は短命に終わったようです。
そして66年に内戦(ビアフラ戦争)がぼっ発すると、
東部出身のハイライフ・ミュージシャンたちが続々とレゴスを離れて帰郷しはじめ、
レゴスのナイトクラブの火は一気に消えてしまいます。
仕事がなくなってしまったジールは、
同じく活動の場を失っていたフェラ・クティを誘ってガーナへ行き、
クラブでの演奏の仕事にありつくなど、67年は苦難の年だったようです。
そんな頃、ナイジェリアにやってきた
ドイツの室内管弦楽団に招かれるというチャンスが、ジールにめぐってきます。
ジールはこれは好機と、クラシック音楽を勉強するためドイツへと渡ったのでした。
ドイツでの10年に及ぶ長期滞在を経て帰国すると、
ナイジェリア放送協会のプロデューサーに迎えられ、
84年に引退するまで、ラジオ・ナイジェリアで演奏活動をしました。
そんなジールの音楽人生の最後に残されたゆいいつのリーダー作が本作です。
オリジナルLPのレーベルをスキャンしたディスク面に1975年のクレジットがありますが、
ハイライフ研究家ジョン・コリンズの著書“HIGHLIFE GIANTS” によれば、
81年作とあり、ドイツからの帰国後の録音ということを考えると、
こちらの方が信ぴょう性は高そうです。
伴奏を務めるのは、レコード会社のハウス・バンドである
タバンシ・スタジオ・バンドとクレジットされていますが、
当時としてはオールド・スタイルの、50~60年代のダンス・バンド・ハイライフの
サウンドを見事に再現していて、ちょっと驚かされました。
メンバーは不明ですが、録音当時流行のファンキー・ハイライフとはまったく毛色が違い、
50~60年代当時のミュージシャンを起用しているとしか思えないサウンドです。
冒頭の‘Zeal Anata’ では、イボの伝統音楽になくてはならない双頭ベルのオゲネが
♪コンコンコンコン♪と打ち鳴らされ、ジールのルーツがさりげなく表されます。
続く優雅なワルツの‘Nnata Na Ano Uso’ もイボ・ハイライフらしいメロディですけれど、
‘Zealonjo Nnoa’ では、曲のメロディといい、ホーン・セクションのハーモニーといい、
完全にガーナイアン・ハイライフ・マナーですね。
ハイ・トーンのGを5分以上吹ける技量の持ち主という評判どおり、
リップ・トリルやフラッター、グロウルなどのテクニックも随所で聴くことができますよ。
ナイジェリアにやってきたルイ・アームストロングに、
「ナイジェリアのヘップキャット」といわしめた、ジール・オニイアの傑作ハイライフです。
Zeal Onyia "TRUMPET KING ZEAL ONYIA RETURNS" Tabansi/ BBE497ACD
2019-07-08 00:00
コメント(5)
初期フジに接近したスピード感あるサカラ オライウォレ・イショラ [西アフリカ]
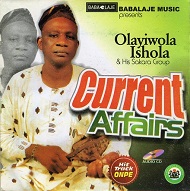
ジュジュ化していくフジにいまさら変革を求めるより、
いっそのことサカラの新人に期待を寄せた方が、実りは大きいのかも。
そんなことを思わせる作品に出くわしました。
サカラなんてすたれた音楽に、
いまさら新人が登場することななんてないと思っていたら、
いやあ、出てくるんですねえ。まだまだサカラ、生き延びています。
講談の神田松之丞みたいなものかしらん。
オライウォレ・イショラという名前は聞いたことがなく、ジャケット写真も新しいので、
もしかしたら新人?と思いながら買ってきたんですが、ホントに新人のようですよ。
インターネットで検索しても、まったく情報が出てきません。
アマゾンでダウンロード販売をしていて、本作と“FAAJI EKO” という
2タイトルのアルバムが、17年3月に販売されてます。
新人といえど、長く歌ってきた人なんでしょうね。
見事に練れたこぶし使いで、土臭い節回しにたまらない味のある歌い手です。
録音が新しいだけあって、サカラのヘヴィーなビートも迫力満点。
ゆったりとした昔ながらのサカラのサウンドなのですけれど、スピード感があって、
かつてのような優雅にスウィングするようなリズム感とは、
センスの異なるモダンさがあります。
また、70年代の初期のフジでよく歌われたメロディがあちこちで出てきて、
ゴジェを弾いていなければ、これ、フジと聴き分けられないだろうなあ。
歌だけ聴いていると、まるっきりフジに聞こえますよ。
シキル・アインデ・バリスターが生み出したフジは、
もともとイスラームの目覚まし音楽ウェレから派生したもので、
サカラ色の強いものだったから、フジと似るのも道理なんですね。
オライウォレがここでやっているサカラは、フジとしては古い初期のスタイルで、
これまでのサカラになかったモダンなスピード感を組み合わせたところが
とても新しく、ユニークなものとなっています。
面白いのは、オライウォレが弾いているゴジェで、
歌のバックでずーっと1音(モノ・トーン)で弾いている場面が多く、
まるでドローンのように鳴らしているんですね。
オライウォレが歌うメロディには起伏がかなりあり、
サカラとしてはかなりメロディアスだけに、
そのバックでドローンのように鳴り続けるゴジェは、強烈に耳残りします。
Olayiwole Ishola and His Sakara Group "CURRENT AFFAIRS" Babalaje Music no number
2019-07-06 00:00
コメント(2)
モダン・フジの課題 スレイモン・アラオ・アデクンレ・マライカ [西アフリカ]

ナイジェリアから誕生したアフロビーツは、
目まぐるしくシーンが動く、今もっとも生きのいいジャンルへと発展し、
他のアフリカ諸国や欧米にまで、グローバルな支持を広げています。
それに比べたら、ここ十年来音楽性が停滞したままのフジなど、
もう完全に無視して構わないっていう気分になろうというもの。
評判の良かったスレイマン・アラオ・アデクンレ・マライカの新作を、
試聴する気すらなれずスルーしてたのも、そんなせいなのでした。
深沢美樹さんがミュージック・マガジンに紹介されていたのを見て、
さすがに試聴くらいはしておくべきだったかと思いつつ、
その後再入荷もなく、記憶の彼方になっておりました。
で、ようやく1年遅れで聴いてみましたよ。
なるほど確かにこれは、ジュジュのサウンドを取り入れたモダン・フジとしては、
傑作のひとつといえます。
ふにゃふにゃと軟弱な音を鳴らすソプラノ・サックス、ちゃらいシンセ、
アルペジオをテキトーに垂れ流すギターがモダン・フジの三大汚点ですけれど、
ここではパーカッション・アンサンブルのみのパートと、
サックスやスティール・ギターなど、
西洋楽器と合奏するパートのバランスもよく、
ジュジュのリフを取り入れたアレンジもこなれています。
なによりパーカッション・アンサンブルの充実ぶりが、聴き応え十分です。
トーキング・ドラムのサカラが、重低音の強烈なアクセントを打ち込み、
畳みかけるように疾走するパーカッション陣と、
トラップ・ドラムの派手なフィル・インが、すさまじいグルーヴを生みだしています。
野性味あるスレイモンのスモーキー・ヴォイスも、
激しくシャウトもすれば、一転じっくりコブシを利かせるなど、硬軟使い分けも鮮やか。
フジもせめてこのレヴェルの作品が当たり前くらいになってくれないと、
昔のように熱心に追っかける気には、もうなれないなあ。
音楽的にも、ジュジュのモノマネからいい加減脱却して、
ヒップ・ホップやビート・ミュージックへ接近して、
もっと大胆に変革してくれたらと願っているんですが。
その課題をクリアするうえでキーとなるのは、
フジが当初持っていたストリート感を、いかに取り戻すかなんじゃないのかなあ。
フジのミュージシャンも、いまやお金持ちのパーティを中心に稼ぐようになり、
支持層がジュジュのそれと変わらなくなっているじゃないですか。
かつての不良が、いつのまにか金持ちのおべっか使いになったのが、
フジ堕落の一因と考えるのは、当たらずといえども遠からじのはず。
貧しい若者たちのストリートのコンペティションから誕生した原点に、
もう1度フジが立ち返ることができれば、
この停滞を打破できるきっかけが生まれるように思うんですけれども。
そんなのは、ロックに不良性を求めるのと同じアナクロニズムなんですかねえ。
Sulaimon Alao Adekunle Malaika "GOLDEN JUBILEE" Golden Point Music no number (2018)
2019-07-04 00:00
コメント(2)
プータイのラム モンルディー・プロムチャック [東南アジア]




10年以上前、たった1枚見つけたCDで、
トリコとなったモンルディー・プロムチャック。
モーラムの伝統的な歌唱法をしっかりと備えた人で、
太く芯のあるコブシ回しの絶妙さに、いっぺんでマイってしまいました。
当時どういう人なのか調べるも、手がかりがなく、
前川健一さんの『まとわりつくタイの音楽』に書かれた、
わずか6行の短い紹介が、ゆいいつの日本語情報でした。
そこで前川さんも「安テープの山から見つけた宝物のひとつ」と語られているとおり、
伝統モーラム・ファンを夢中にさせる力量は、折紙付きといえます。
その後、Soi48 の『旅するタイ・イサーン音楽ディスク・ガイド』で
モンルディー本人へのインタヴューを含む8ページの記事が載り、
ようやくこの人のバイオグラフィを知ることができました。
その記事のおかげで、以前ぼくが手に入れたクルーン・タイ盤CDは、
82年頃に録音されたアルバムをCD化したものだということもわかりました。
しかしモンルディーのCDはこれ1枚しか見つからず、
ほかにないのかなあと、長年思っていたんですよね。
『旅するタイ・イサーン音楽ディスク・ガイド』には、
もう1枚別のCDの写真も載っていたので、
きっと現地に行けばもっと出ているんだろうとは思っていたんですが。
ところがつい最近、現地でモンルディーのLP・CD・カセットを
ごっそり買い付けてきた人がいて、さきほどの
『旅するタイ・イサーン音楽ディスク・ガイド』に載っていたCDもあり、
喜び勇んで3タイトルいただいてきました。
いずれも『ラム・プータイ集』と名付けられたアルバムです。
モンルディーはイサーン出身のラーオ人ですけれど、
ラオスへ行ってモーラム修行したという人だということは、
件のインタヴューで語られていたとおりです。
ラオスで流行していたラム・タンワーイとラム・プータイをとても気に入り、
猛練習して自分のものにし、タイに持ち帰ってヒットをあげたそうで、
今回の3枚は、そのラム・プータイを集めたCDのようです。
プータイというのは、中国雲南省や杭省周辺からヴェトナム、ラオスの北部を抜け、
タイ東北部イサーン地方に移り住んだ少数民族ですね。
独自の言語を持ち、プータイ固有の文化と音楽を受け継いできた人々で、
ラム・プータイはプータイ語で歌われるモーラムなのでしょう。
ゆったりとした自由リズムで、歌う、というか、吟じる、といった表現の方が
ぴったりくるモンルディーのおおらかにうねる節回しは、
クルーン・タイ盤ですでに承知とはいえ、耳を惹きつけられぱなしになります。
ケーン、ピン、ソーなどの伝統楽器に、
オルガンやシンセを加えたシンプルな伴奏も、必要最小限で申し分ありません。
全曲同じような曲調にテンポでも、まったく聴き飽きることがないのは、
デビュー前に名人チャウィーワン・ダムヌーンとも一緒に活動していたほどの、
本格ラム使いであるモンルディーの至芸ゆえでしょう。
Monruedi Phromchak "SAO NAK RIAN TAM TO" Krung Thai KTD008
Monruedi Phromchak "LAM PHUNTHAI VOL.1" V. Musicsound SCD9
Monruedi Phromchak "LAM PHUNTHAI VOL.3" V. Musicsound SCD11
Monruedi Phromchak "LAM PHUNTHAI VOL.4" V. Musicsound SCD12
2019-07-02 00:00
コメント(0)




