ハイライフ+タウンシップ・ジャイヴ ダイトマイト・スターライト・バンド [西アフリカ]
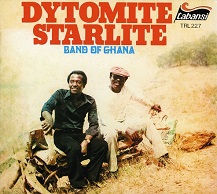
ジール・オニイアのアルバムがタバンシから出ていたなんて、意外も意外。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2019-07-08
というのは、タバンシといえば、凡庸なアフロ・ポップやディスコものの
レーベルというイメージが、あまりにも強かったから。
80年代半ばのサニー・アデ・ブームで、日本にナイジェリア盤が大量に入ってきた折に、
タバンシのカタログもずいぶん聞きましたけれど、
どれもこれもB・C級のポップ作ばかりで、幻滅したものです。
当時買ったレコードは全部売っぱらちゃって、手元には1枚も残ってないもんねえ。
70年代初めにイボ人レーベル・オーナーの
チーフ・タバンシが設立したタバンシ・レコーズは、
ぼくが知るようになった80年代半ばには、
ポップスやディスコものがカタログの中心でした。
70年代にハイライフのアルバムを多数出していたことは、
ずいぶんあとになって知りました。
このガーナのハイライフ・バンド、ダイトマイト・スターライト・バンドもそんな1枚。
レコード番号から類推すると、70年代ではなく、83年頃のアルバムと思われます。
当時はガーナが深刻な経済不況に陥っていた時期で、
ナイジェリアのレコード会社に録音したのも道理です。
当時ガーナ国内ではレコーディングが行なわれることはなくなり、
ハンブルグ、ロンドン、アビジャン、トロントなど、
海外でハイライフのレコードが制作されていました。
ダイトマイト・スターライト・バンドというバンドは、
今回のリイシューで初めて知ったんですけれど、
聴いてみると、これがなかなかユニーク。
1曲目のイントロのホーン・セクションが入ってくるところで、
ええぇ~、これ、タウンシップ・ジャイヴじゃないの!とびっくり。
でも、リズムは確かにハイライフだし、歌が始まればそのメロディは、
まぎれもなくガーナ産ハイライフなんですけれども。
狐につままれたような気分でいたら、2曲目もホーン・セクションのリフが、
南アそのもので、ノケぞってしまいました。ガーナのハイライフと
南アのジャイヴがこんなふうにミックスされた音楽は、初めて聴きますね。
もっとも南ア色が濃いのは冒頭の2曲だけで、
ほかの曲はすべてガーナらしいダンス・バンド・ハイライフ。
ギターが「エル・マニセーロ」のリフを弾く曲や、
キーボードがユニークなサウンドを作っているところも、耳をひかれます。
いったいどういう経歴を持つバンドなのか、興味がわくところなんですけれども、
このダイトマイト・スターライト・バンドに関する資料は皆無のようで、
リイシューに携わったジョン・アームストロングも、ライナー・ノーツで困惑を隠しません。
バンドを名乗るも、メンバーの名前はおろか、人数すら不明で、
ジャケットに写る二人が、歌手なのかプレイヤーなのかもわかりません。
ガーナのハイライフが停滞した80年代に、
謎のバンドが残した知られざるハイライフ名作です。
Dytomite Starlite Band of Ghana "DYTOMITE STARLITE BAND OF GHANA" Tabansi/BBE BBE547ACD
2019-08-31 00:00
コメント(0)
マルチニークの新人コンテンポラリー・ジャズ・ピアニスト マエ・ボーロワ [カリブ海]

マルチニーク出身の若手ジャズ・ピアニストの実質デビュー作
(12年にデジタル・リリースのみのEPあり)です。
「カリビアン・ジャズの新星」とか謳われていますけれど、
そのテの宣伝文句は、疑ってかからないとねえ。
カリブ出身者だからといって、必ずしもルーツ・コンシャスな人とは限りません。
近年のマルチニーク出身のジャズ・ピアニストでは、
エルヴェ・セルカルとグレゴリー・プリヴァの二人が、そのいい例。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-12-16
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2018-01-22
クレオール性を視座に置いたジャズを演奏するエルヴェと、
マルチニークの伝統音楽とは別の、アカデミックな教育を受けて
新世代ジャズを演奏するグレゴリーとでは、まるで音楽性が違います。
カリブ出身というだけで、「カリビアン・ジャズ」や「クレオール・ジャズ」と
喧伝するのは、本人の音楽性を歪めて伝えることに繋がるだけ。
ジャズ界隈はこういう安易なラベリングが横行するので、注意が必要です。
で、マエ・ボーロワくんは、どちら派なのかといえば、後者の新世代ジャズですね。
クレオールやアフロ・アンティーユのリズムもメロディも、まったく参照されていません。
経歴を聞けばバークリー出身ということで、そうだろうなあとナットク。
編成はピアノ・トリオにヴィブラフォンとヴァイオリンが加わったクインテット。
1曲のみパーカッションがゲストに加わっていますが、
名前から察するにスペイン系で、マルチニーク出身者ではなさそう。
他のメンバーも、ヴィブラフォンの出身だけ不明ですが、
オーストラリア人女性ベーシストにスイス人ドラマー、
フランス人ヴァイオリニストと、多国籍な顔ぶれです。
ヴァイオリンがかなり個性的なプレイをしていて、要注目ですよ。
インタヴューを読むと、マリオ・カノンジュを尊敬しているというコメントがあったので、
もう少しクレオールな音楽性を聞かせるかとも思ったんですが、違っちゃいましたねえ。
でもそんななかにも、マエがヴォーカルを取った‘La Sirène’ で、
ラルフ・タマールばりの色気たっぷりな歌声を聞かせているのには驚かされました。

ラルフ・タマールのソロ・デビューEP“EXIL” 中の1曲‘Ba Mwin’ が
マエのお気に入り曲ということで、ロマンティックな甘いヴォイスは、
ラルフ・タマールからの影響かもしれません。
そのラルフ・タマールとも、マエは16年にライヴで共演しています。
歌モノにマルチニークをわずかに感じさせるとはいえ、
本作最大の魅力は、コンテンポラリー・ジャズ・マナーの、
マエのコンポジションの良さにありますね。
ヴァイオリンの起用が成功したのも、コンポジションにぴたりハマったからで、
コンテンポラリー・ジャズのニュー・スターの誕生に喝采を送りましょう。
Maher Beauroy "WASHA!" Aztec Musique/Déclic Jazz CM2612 (2019)
Ralph Thamar "EXIL" GD Productions GCD45004 (1987)
2019-08-29 00:00
コメント(0)
サイケデリック・エレクトロニック・マロヤの大傑作 チ・フォック [インド洋]

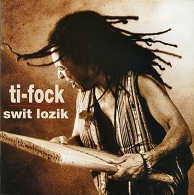
エレクトロニック・マロヤのコンピレで
ひさしぶりにチ・フォックと再会したんですけれど、
そういえばチ・フォックって、どうしてるんだろう。近況がぜんぜん伝わってきませんね。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2019-08-01
チ・フォックはジスカカンと並ぶ、現代マロヤの重要アーティスト。
マロヤをフューチャリスティックに変貌したサウンドで、
伝統マロヤを革新したイノヴェイターです。
なかでも、ジャズの語法も借りながら、大胆にマロヤのサウンドをリクリエイトした
94年の“SWIT LOZIK” は、レユニオン音楽史に残る一大傑作でした。
安直なエレクトリック化やフュージョン化がはびこっていた90年代当時のレユニオンで、
アクースティックでプログレッシヴなサウンドを生みだした才能は突出していました。
でも、あれ以降、チ・フォックの活動が聞こえなくなってしまって、
あらためて調べてみると、11年にアルバムを出していたことが判明。
早速オーダーしてみたら、これはスゴイ!
なんともチ・フォックらしい才気あふれる力作じゃないですか。
11年といえばマロヤ再評価で盛り上がっていた時期だというのに、
なんでこのアルバムは輸入されなかったんだろう。
全編で繰り広げられるサイケデリックなサウンド・プロダクションは、
チ・フォックの面目躍如。歌詞カードには、全曲「シャンソン・ワールド・ミュージック」と
クレジットされていて、マロヤといっさい名乗らないところが面白いなあ。
しかし、聴いてみれば、どの曲も横揺れのビートをベースとした、マロヤであることは歴然。
カヤンブが入っていない曲でも、しゃかしゃかと鳴るカヤンブのリズムが聞こえてくるのは、
打ち込みやエレクトロのビートが、マロヤのリズムを下敷きとしているからですね。
エレクトロを大胆に取り入れ、トランス・ミュージックばりのダンス・ビートを放つ一方で、
サウンドの要所にルーレやカヤンブなどの打楽器、アコーディオンやギター、
女声のウルレーションなどの生音をガチンコでぶつけたプロダクションがスゴイ。
ヘヴィーなエレクトロなサウンドと打楽器の生音が互いにゆずらず、
肉感的な生々しさをグイグイと打ち出してくるんですよ。
いわゆるアンビエント・テクノといった方向には寄らず、
レユニオン伝統音楽の太い幹を感じさせるところが、頼もしいじゃないですか。
さりげなくアフロビートの要素も絡ませた2曲目も白眉。
クセのある声でねちっこく歌う、チ・フォックのロック的なヴォーカルも痛快です。
例のエレクトロニック・マロヤのコンピレには、初期の曲のリミックスなんかじゃなくて、
このアルバムから選曲したら良かったのになあ。
誰からも気付かれずにいたサイケデリック・エレクトロニック・マロヤ。
今からでも遅くないというか、今こそ聴くべき大傑作、
バイヤーさん、ぜひ日本に輸入してください。
Ti Fock "GAYAR NATIR" Sedm/Oasis CD44915 (2011)
Ti-Fock "SWIT LOZIK" Sedm/Oasis 66956-2 (1994)
2019-08-27 00:00
コメント(0)
アフロ・グルーヴ・クイーン マヌ・ガロ [西アフリカ]

うぇ~い! カッコえぇ~!!
元ザップ・ママのベーシスト、マヌ・ガロが昨年出していた4作目、サイコーっすね!
1年以上も前に出てたのかぁ。気付いている人、誰かいた?
『アフロ・グルーヴ・クイーン』ってドンピシャなタイトルに、このジャケ!
いや、もう、なにをかいわんやでしょう。
ブーツィー・コリンズとチャックDをゲストに呼んだアフリカのアーティストって、
彼女が初じゃないの?
ぼくがマヌ・ガロに注目したのは、ジンバブウェのモコンバのデビュー作がきっかけ。
あのアルバムをプロデュースしたのが、マヌ・ガロだったんですけれど、
その抜きんでたポップ・センスには目を見張りました。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-12-29
パン・アフリカンなコンテンポラリー・ポップスを作り出す
アフリカ人プロデューサーといえば、
かつてはカメルーン出身のマヌ・ディバンゴがいましたけれど、
マヌ・ガロはそのマヌ・ディバンゴと同じ系譜に連なる人ですね。
マヌ・ガロはコート・ジヴォワール出身ですけれど、
コート・ジヴォワールやカメルーンには、
パン・アフリカンな視点に立ったクリエイターを輩出する土壌が昔からあって、
マヌ・ガロもまさにそんな一人といえます。
そのマヌ・ディバンゴも1曲ゲストで参加した本作、
痛快なアフロ・ファンクが全編で炸裂しまくります。
呼び物は、ブーツィー・コリンズがゲストに加わった4曲で、
なかでもチャックDを交えたトラックがクールですねえ。
ほかにも、マリー・ドルヌやサビーヌ・カボンゴなどザッパ・ママのメンバーたちに、
ビート・ボックスも加わったア・カペラ・コーラスも聴きものです。
でも、ぼくが一番興味をひかれたのが、
故国コート・ジヴォワールのエルネスト・ジェジェに捧げたインストのトラック。
ジェジェは70年代にベテ人の伝統ダンス音楽ジグリビテイを、
モダン化したクリエイターでした。83年にジェジェが亡くなったあと
ジグリビテイを継ぐ者は現れませんでしたが、
80年代末にコート・ジヴォワールで大流行したズグルー誕生の
呼び水となったことは間違いありません。
ズグルーはのちにクーペ・デカレへと発展しますが、
コート・ジヴォワールのダンス・ポップの一大潮流となったルーツにジグリビティがあり、
こうしたアフロ・ファンク色濃いグルーヴがベースにあったことを再認識させられます。
パン・アフリカンなサウンドながら、そこにはコート・ジヴォワールの伝統リズムが
しっかりと生かされているんですね。
Manou Gallo "AFRO GROOVE QUEEN" Contre-Jour CJ033 (2018)
2019-08-25 00:00
コメント(0)
クールなヒップ・ホップ世代のコロゴ スティヴォー・アタンビレ [西アフリカ]
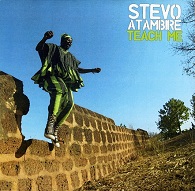
脚光を浴びるガーナ北部フラフラ人の音楽コロゴから、ニュー・フェイスの登場です。
届いたのはガーナ盤CDで、これは珍しいですね。
メイド・イン・ガーナのコロゴCDを手にするのは、ボラ・ナフォ以来じゃないかな。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-07-05
早速聴いてみると、多彩な語り口を持つ実力派で、
雄弁な歌いっぷりが説得力十分の、いいシンガーですねえ。
コロゴは反復フレーズをひたすら繰り返すシンプルな曲が特徴ですけれど、
全19曲というアルバムを、単調になることもなければ、ワン・パターンにも陥らず、
さまざまなアイディアで飽きさせないプロデュースが光ります。
プロデュースは、先日来日したルーマニア生まれのガーナ人という、
マルチ・カルチュラルなルーツを持つワンラヴ・ザ・クボロー。
レコーディングやミキシングも担当していて、
アルバム制作では、モーリシャスのレーベルとコラボして資金を集めるところも、
ワールドワイドな活動をするワンラヴの手腕のようです。
ブダペスト出身の鍵盤奏者率いるアフロ・グルーヴ・バンド、アバセに、
スティヴォーがゲスト参加していたのも、ワンラヴの仕掛けなのかも。
さまざまなゲストの起用も、ワンラヴの人脈をフル活用したようで、
一番の聴きものは、ハイライフの大ヴェテラン、
ジェドゥ・ブレイ・アンボリーをゲストに迎えた‘Minus Me’。
ホーン・セクションをフィーチャーして、
ファンク・ベースも交えた、ユニークなコロゴ・ファンクをやっています。
ワンラヴ自身も参加してラップ(語り?)を2曲で披露しているほか、
ガーナのヒップ・ホップ・ミュージシャン、メディカルをフィーチャーして、
ヒップ・ホップ・コロゴをやってみたりと、多彩なゲストの個性とのぶつかり合いが
いい化学反応を起こして、スティヴォー自身の才能を拡張させています。
コロゴ一本の弾き語りもあれば、
ベースが低音をブーストしたダンス・トラックでは、
鮮やかなグルーヴを披露してくれます。
ビートの組み立てがよく工夫されていて、
トーキング・ドラムなどの生のパーカッションに、
エレクトロのビートを控えめに絡ませたりして、
サウンドの意匠は、アクースティックな伝統的なスタイルを保ちながら、
リズムやビート感覚は現代的なセンスに富んでいるところが、とてもフレッシュです。
少し調べてみたら、スティヴォーはこのソロ・デビュー作以前、
ブルキナ・ファソ気鋭のラッパー、アート・メロディと組んだマビーシというユニットで、
1枚アルバムをデジタル・リリースしているんですね。
アート・メロディと組んでいたとは、ヒップ・ホップのセンスも十分なわけです。
スティヴォーの天然・野生児なヴォーカルが、めちゃくちゃクールに響くのも、
そんなヒップ・ホップのセンスを兼ね備えたうえで、
巧みなサウンド・プロダクションが貢献したからといえそうです。
Stevo Atambire "TEACH ME" Koool Kreol no number (2017)
2019-08-23 00:00
コメント(2)
ジャイヴ・ヴォーカル名盤 スキャットマン・クローザーズ [北アメリカ]
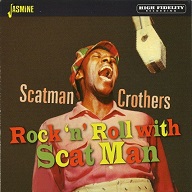
祝♡ 祝♡ 祝♡
マイ・フェヴァリット・ジャイヴ・アルバム、
スキャットマン・クローザーズの56年トップス盤が、
ようやーっと、まともなフォーマットでCD化されました!
ジョー・キャロルのチャーリー・パーカー盤にエピック盤とともに聴き倒した、
生涯の愛聴盤であります。
「まともなフォーマットで」と書いたのは、
98年に“OH YEAH!” というタイトルで一度CD化されたことがあったんですけれど、
曲順バラバラ、タイトルもジャケットもオリジナル盤無視で、
LPで愛聴していた者には耐えがたいものだったんですよ。
その後、06年にハイドラからシングル曲を集大成した編集盤が出たんですけれど、
トップス盤の曲は一部のみの収録だったんですよねえ。
初めて聴くシングル曲は、すごく嬉しかったんですけども。
というわけで、今回のジャスミン盤は、トップス盤の全12曲を収録したあとに、
48年から56年までの17曲を、ボーナス・トラックとしてクロノロジカルに並べるという
願ってもない編集で、あぁ、待った甲斐がありましたねえ。
ハイドラ盤に未収録の曲が多数収録されたのも、めちゃ嬉しい。
リー・ドーシーの“YES WE CAN” 完全CD化実現の時を思い起こしますねえ。
あの時と同じ感激ですよ。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-09-01
スキャットマン・クローザーズのあけっぴろげな歌いっぷりは、
植木等の「ぶあーっと行こうぜ、ぶあーっと!」に通じる爽快感で、もうたまりません。
しゃがれ声の味わいといったら、これぞ黒人芸能の粋そのもので、
全編スウィンギーな演奏にのせて、熟練の歌いぶりと豪快なスキャットを堪能できます。
なんといっても、ジャンプ・ブルースのノリがサイコー。
急速調の ‘I Got Rhythm’ のカッコよさなんて、
半世紀以上経ってもなお新鮮で、シビれますねえ。
タイトルのロックンロールは、当時の流行にあやかった名ばかりのもので、
中身はジャイヴ/ブルース/ジャズのてんこ盛り。
なんせスキャットマン・クローザーズは、46年にスリム・ゲイラード・トリオに
レオ・ワトソンの後釜ドラマーとして加入した経歴の持ち主ですからね。
30年代半ば、まだ中西部のサーキットを流していた時代には、
同い年のTボーン・ウォーカーとも共演したそうで、
その後一旗揚げようとハリウッドに進出して、最初に組んだトリオには、
なんと18歳のスタン・ゲッツが在籍していたんでありました。
ボーナス・トラックでは、プレスリーの ‘Hound Dog’ を聴くこともできますけれど、
やっぱり本領発揮は ‘Transfusion’ のように、小粋なギターと
スネア・ドラムのブラシで歌ったジャイヴィーな曲の方ですね。
スキャットマンは30~50年代は歌手として活動しましたが、
50年代以降は映画俳優として活躍し、広くは俳優として知られるようになります。
主な出演作に、『ジョニイ・ダーク』(54)、『ならず者部隊』(56)、『ボクサー 』(70)、
『ビリー・ホリディ物語/奇妙な果実』(72)、『カッコーの巣の上で』(75)などがあり、
晩年は『シャイニング』(80)での名脇役としても有名になりました。
テレビ・ドラマの『ルーツ 』や『スタスキー&ハッチ』にも出演していたそうで、
ぼくもそうとは知らずに、スキャットマンを観ていたんだろうなあ。
そうそう、ランディ・ニューマンが映画音楽を手がけた『ラグタイム』(81)でも、
オープニング曲をスキャットマン・クローザーズが歌う予定だったのが、
結局キャンセルになった、なんて話も残っていますね。
ジャイヴ・シンガーとしてのスキャトマン・クローザーズの魅力を
あますことなく詰め込んだ名編集盤、お聴き逃しなく。
Scatman Crothers "ROCK ’N ROLL WITH SCAT MAN" Jasmine JASCD1010
2019-08-21 00:00
コメント(2)
フェラ・クティのエネルギーを借りて ファルズ [西アフリカ]

いきなりフェラ・クティの‘JJD’ が飛び出し、ノケぞり。
のっけからアッパー・カットを食らって、身体は硬直、ボーゼンとしてるところに、
続いて‘Zombie’ が畳みかけてくるんだから、
うおーーーーーーー、こいつぁ、ハンパない。
さらに‘Coffin For Head Of State’ をサンプリングしたトラックまであるじゃないですか!
ナイジャ・ヒップ・ホップのラッパー、ファルズの新作は、
フェラ・クティの遺産を大々的に引用するという、
そんじょそこらの覚悟じゃできないことをやらかした衝撃作。
ジャケットのアートワークも、フェラ・クティの数多くのジャケットを描いた名デザイナー、
ガリオクウ・レミが手がけています。
胸の昂ぶりを抑えるのも大変なアルバムなんですが、
ナイジェリア社会の不正義に、真正面から本気で怒りまくったラッパーは、
イードゥリス・アブドゥルカリームの“JAGA JAGA” 以来なんじゃないでしょうか。
「ナイジェリアは何もかもメチャクチャ」とラップした、
イードゥリスの04年作“JAGA JAGA” のジャケット・カヴァーも、
そういえばガリオクウが描いてましたね。

冒頭の‘JJD’をサンプリングした‘Johnny’ は、
18年7月に、アブジャでNYSC(国家青年奉仕団)の女性メンバーが
警官に撃たれて死亡した事件に触発されたトラックです。
この事件は、NYSCのミッションをあと数日で終えようとしていた女性メンバーと、
彼女の友人たちが乗っていたオープン・カーが、検問を停止せずに通過したとして、
警官が車に向けて発砲したことで起きたものです。
撃たれた女性は病院に運び込まれたものの、
病院は治療の承認が警察から得られないと治療を拒絶し、
女性は大量出血で死亡、わずか23歳の若さでした。
軍政時代から依然として変わらない、社会の不公正、警察による残虐行為、
政治システムの腐敗、宗教問題の二重基準、富の集中と貧困。
ファルズはこうした社会問題に向き合うために、フェラ・クティの力を借りたのですね。
ナイジャ・ヒップ・ホップがビッグ・ビジネス化したことで、
ソーシャル・メディアからの圧力も高まり、
社会問題や政治的なコメントを避けるラッパーが増えたとも聞きます。
そんななかで、社会問題に舌鋒鋭く対峙するファルズは、
フェラ・クティをサンプルする有資格者といえるでしょう。
フェラの音源を引用したラッパーは、ファルズが初めてではありません。
カーリ・アブドゥのミックステープ“MINISTRY OF CORRUPTION” がありました。
しかし、フェラのスピリットにまで迫って、そのエネルギーを引き出すことができたのは、
ファルズが初めてでしょう。それが出来たのは、
ファルズのエネルギーがそれだけ凝縮され、スパークした証左です。
‘E No Finish’ でのピジン・イングリッシュの滑舌なんて、
フェラの歌いっぷりをホーフツとさせるじゃないですか。
ピジン・イングリッシュ独特のがくがくとしたフロウからは、
なめらかにラップしたんじゃ、若者の胸にメッセージが突き刺さらないという、
ファルズの心意気が聞こえてくるようです。
Falz "MORAL INSTRUCTION" Bahd Guys no number (2019)
Eedris Abdulkareem "JAGA JAGA" Kennis Music KMCD040 (2004)
2019-08-19 00:00
コメント(0)
オールド・タイム・バンジョー ケリー・ハント [北アメリカ]

ゴミやキズがたくさん付いたネガ・プリント。
まるで災害現場に落ちていたかのような、古く退色した写真を演出したジャケットは、
メンフィス生まれ、今はカンザス・シティに暮らすという、
女性シンガー・ソングライターのデビュー作です。
テナー・バンジョーの弾き語りという、シブいアメリカン・フォークのスタイルは、
近年のアメリカーナとはちょっと趣が違っていて、
よりオーセンティックなルーツ志向を感じさせます。
ケリー・ハントの機知に富む歌い口には、ガッツを感じさせるだけでなく、
スウィートさもあって、ボニー・レイットのデビュー当時を思い起こしてしまいました。
これって、新人だけが持つイキの良さじゃないですかね。
ほとんどの曲が、彼女の弾くテナー・バンジョーに、
フィドルやベースが控えめにバックアップするだけというシンプルなつくりで、
太鼓だけをバックに歌う‘Delta Blues’ など、彼女のピュアな歌声が胸に響きます。
ケリーは十代の頃からピアノで曲づくりをする一方、演劇を習い、
大学でフランス語とヴィジュアル・アートを学んでいる時、
100年前に使われていた古いテナー・バンジョーを手に入れ、
独学で弾くようになったのだといいます。
ブルーグラスのような派手な弾き方をしないので、
かつてジョン・ハートフォードが弾いた、オールド・タイム・バンジョーのような
味わいを感じさせます。
モノトーンなサウンドの曲が続くなか、ラスト・トラックの‘Gloryland’ のみ、
オルガンやコーラスも加わったカラフルなサウンドとなっているところが、
アルバムを締めくくるうえで、とてもいい演出になっていますね。
古いゴスペルの味わいにスワンプの香りが漂う、
とても印象的なトラックに仕上がっています。
Kelly Hunt "EVEN THE SPARROW" Rare Bird RBR01 (2019)
2019-08-17 00:00
コメント(0)
ギュイヤンヌのクレオール・リズム ヴァレリー・ジョアンヴィユ [南アメリカ]
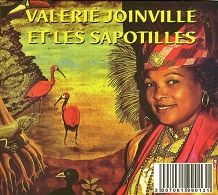
フランス領ギアナのCDをあれこれ買ったのは、
ヴァレリー・ジョアンヴィユの80年作がCD化されたのを知ったからでした。
せっかくだから、ほかにも何かないかなと探して、網に引っ掛かったのが、
スフランとフェルミエやヴィクトール・クレだったんですね。
で、そのお目当てのヴァレリー・ジョアンヴィユの80年作、
フランス領ギアナの伝統音楽に関心がある人なら、見逃せない名作なんですよ。
太鼓と歌というシンプルなフォーマットの、
コーラスとのコール・アンド・レスポンスの音楽ですけれど、
トトー・ラ・モンポシーナが好きな人だったら、ゼッタイ気に入りますよ。
フランス領ギアナに伝わるクレオール・リズムには、
カセーコ、グラジェ、レロール、カムゲ、デボ、ベリア、グラジェヴァル、
ジャンベル、ムララ、カラジャ、ジュバなど、数多くのリズムがあります。
このうちヴァレリーは、最初に挙げた6つの代表的なリズムを取り上げた曲を
メドレー形式で歌っていて、各リズムの特徴をはっきり聴き取ることができます。
カムゲとベリアは奴隷時代に遡るワーク・ソングを起源とするリズムで、
ベリアはフルベ(プール)人が伝えたリズムだとのこと。
グラジェとレロールはアフリカとフランスが混淆したリズムで、
グラジェはワルツ、レロールはカドリーユを、
アフリカのテイストでミックスしたリズムです。
グラジェはフレーム・ドラムで演奏され、このリズムで踊られるサロンは、
人々をダンスに招き入れるイントロダクションの役割を果たし、
このアルバムでも1曲目で演奏されています。
デボはセント・ルシア島から伝わったムララが起源のリズムで、
基本パターンはカセーコと変わりありませんが、
歌やソロの場面では違いが出るといいます。
そして、フランス領ギアナを代表する
アフロ=ガイヤネーズ文化が生み出しリズムがカセーコですね。
西隣のスリナムでブラス・バンドと結びつき、
ポピュラー化したジャンル名として有名になりましたけれど、
もとはギュイヤンヌ発祥のクレオール・リズムなのです。
ヴァレリーはギュイヤンヌの伝統音楽を継承するため、
75年にレ・サポティーユを結成し、国内ばかりでなく海外にも招聘されて演奏し、
フランス、イゼール県のモンセーヴルーで開催された
国際フォーク・フェスティヴァルに出演した時に、本ライヴ録音が残されたのでした。
野性味溢れる太鼓のサウンドを生々しく捉えた録音もバツグンなら、
当時44歳のヴィヴィアンの歌声にも華があり、ギュイヤンヌ音楽の名盤となりました。

82歳となった今もヴァレリーは現役で歌い続けていて、
今年リリースされたギュイヤンヌの伝統音楽集でも、
ヴァレリーの歌が2曲収録されていました。
ちなみにこのギュイヤンヌの伝統音楽集では、全16曲中13曲がカセーコ、
ベリアが1曲、カラジャが1曲、デボが1曲と、カセーコがほとんどを占め、
ギターやベースが伴奏に付く曲が多くなっています。
カラフルなギュイヤンヌのクレオール・リズムと、
オーセンティックなパーカッション・ミュージックの良さを双方味わえる
ヴァレリーの80年作は、またとないアルバムです。
Valérie Joinville Et Les Sapotilles "VALÉRIE JOINVILLE ET LES SAPOTILLES" Sun Studio SUN199013 (1980)
v.a. "GUYANE HERITAGE 1ER DEGRÉ" Patawa KK11 (2019)
2019-08-15 00:00
コメント(0)
ギュイヤンヌのおちんちん ヴィクトール・クレ&ブルー・スターズ [南アメリカ]
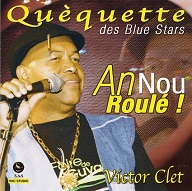
ギュイヤンヌのカーニヴァルの季節になると、
仮面をつけ着飾ったダンス・パーティーが、
首都カイエンヌのあちこちのダンスホールで行われるんだそうです。
カイエンヌでもっとも有名なダンスホール、ル・ソレイユ・レヴァン=シェ・ナナを所有する
ヴィクトール・クレは、彼のバンド、ブルー・スターズとともに、
カーニヴァル・シーズンを盛り上げるのに、なくてはならない人気歌手。
ブルー・スターズは、今年でバンド創立50周年を迎えたヴェテラン・バンドで、
今年のカーニヴァルは、さぞ盛り上がったんでしょうねえ。
近作がすべて売り切れだったのは、売れっ子の証拠なのかな。
ゆいいつ10年作の在庫があったので、
スフランとフェルミエの兄ちゃんコンビと一緒に買ってみました。
コンパから始まるこのアルバム、レパートリーはマズルカが多く、
ビギンももちろんやっていて、クレオール・ポップ満開のアルバムです。
フランス領ギアナのポップスらしい。
打ち込み不使用・生演奏保証の総天然色サウンドで、
サックスの鳴りも痛快なら、バンジョーらしき音もカクシ味で利いています。
ヴィクトール・クレも、エンタテイナーらしい吹っ切れた歌いぶりを聞かせてくれますよ。
ところで、ジャケットにも大きく掲げられているヴィクトールのニックネーム、
Quéquette とは、なんと、おちんちん(!)。
地元民から愛情込めてそう呼ばれているそうですけれど、
名付ける方も、それを受け止める方も、スゴいなギュイヤンヌ人。
Victor “Quéquette” Clet des Blue Stars "AN NOU ROULÉ!" Vhc Studio OBFS24 (2010)
2019-08-13 00:00
コメント(0)
ギュイヤンヌのカーニバル スフラン・ケ・フェルミエ [南アメリカ]
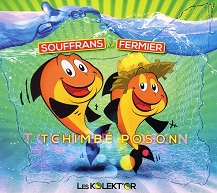
フランス領ギアナの音楽というと、
マルチニークの音楽をイナタくしたという印象が強いんですけれど、
スフランとフェルミエというコンビの新作なんて、まさにそのもの。
ギターのカッティングや、ぴちぴちと弾けるリズム・セクションを聴いていると、
ラ・ペルフェクタとかパカタクといったあたりの
80年代マルチニークの伝統ポップ・サウンドが思い浮かんで、
なんだか懐かしくなりますねえ。
ちょっと古い感じのシンセの音色にも、和んでしまいますよ。
サックスとトロンボーンの2管が舞う生音サウンドも、嬉しいじゃないですか。
主役の二人を囃すコーラスがまた、サウンドを一層楽しくしています。
どこまでもハッピーで、哀愁だとか、憂いなんて、みじんもない音楽ですね。
お子様向けなジャケット・デザインは、
どうやらタイトル曲「魚を捕まえろ」をヴィジュアル化したもののよう。
そのタイトル曲のYouTubeを観ると、
二人が川や海で漁をしたり、市場でさばいた魚を売ったりという、
日常生活感たっぷりのヴィデオで、近所の兄ちゃん的な雰囲気そのものですね。
いずれもカーニヴァル向けのアッパーな曲ばかりで、
カラオケ用のインスト・ヴァージョン2トラックを含む全7曲を収録。
カラフルな仮装衣装で飾られたギュイヤンヌのカーニヴァルのスペクタクルが、
目の前を通り過ぎていくのを目撃するかのようで、
あっという間に終わってしまう短さに、
どこか夢うつつの幻を見たかのような思いを覚えます。
Souffrans Ké Fermier "TCHIMBÉ POSON" Patawa KK12 (2019)
2019-08-11 00:00
コメント(0)
芳醇なオールディーズ・ルンバ ウタ・マイ [中部アフリカ]

な~んて芳醇なルンバ・コンゴレーズなんでしょうか!
グッド・オールド・デイズなサウンドに、身も心もトロけます。
コンゴ音楽史上最高の名門楽団TPOKジャズに74年に入団し、
フロント歌手の一人として活躍したヴェテラン歌手、ウタ・マイの新作です。
前回のランバート・カバコの遺作にも、ウタ・マイはコーラスに加わっていましたけれど、
ソロ・アルバムはいつ以来ですかね。ウン十年ぶりなんじゃないのかしらん。
TPOKジャズ以降のウタ・マイのキャリアを振り返ると、
コート・ジヴォワールのプロデューサーによって編成された
レ・カトル・エトワールで、82年から96年まで活動していましたね。
レ・カトル・エトワールは、美声歌手として名をはせたニボマに、
ギタリストのシラン・ムベンザ、ベーシストのボポール・マンシャミナに
ウタ・マイの4人でしたけれど、このうちボポールを除く3人が、
00年にイブラヒム・シラが仕掛けた
コンゴ音楽リヴァイヴァル・プロジェクトのケケレへと合流します。
こうして考えると、ウタ・マイやニボマは、ルンバ・ロック以降のトレンドにのることなく、
古き良きルンバ・コンゴレーズの味を保った音楽をやり続けてきたんですね。
それがけっしてマンネリにならなかったのは、昔のスタイルをただなぞるのではなく、
サウンドにさまざまな工夫を凝らした、プロデューサーの力が大きかったように思います。
特にケケレの場合は、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブのブームに押されて、
ヴェテランたちの音楽に目を向けられたことが追い風となりました。
ウタ・マイの本作も、まさにそんなレ・カトル・エトワールからケケレの活動で
得たナレッジが、サウンド・プロダクションに生かされているのを感じます。
まず、耳をそばだてられるのが、アコーディオンの起用。
60年代のカミーユ・フェルジを思い起こされずにはおれないわけで、
優雅なルンバにアコーディオンの響きは、もう絶妙というほかありません。
せっかくヴェテランが昔懐かしいルンバを歌っても、
バックのシンセサイザーが興ざめになることもしばしばなので、
このアコーディオン起用は大正解ですね。
ニボマを筆頭とするコーラス隊の美しいハモリにも、うっとりさせられます。
そして、サックスとトランペットのルーズなサウンドにも頬が緩みます。
ぴたっとは合わない、ばらけたホーン・セクションが、
60~70年代コンゴ音楽のテイストを伝えるかのようで、嬉しくなります。
そんな大らかなサックスと甘いエレクトリック・ギターが活躍する‘Trop C’est Trop’ は、
3-2のクラーベがなんともスウィンギー。
アクースティック・ギターとフルートを効果的に使った、
アンプラグドなルンバの‘L’union Forcée’ なんて、
ケケレの経験を生かした好トラックでしょう。
70近い年齢を感じさせないウタ・マイのなめらかなヴォーカルは、まさに円熟の極み。
ヴェテランでしか成しえない素晴らしいアルバムです。
Wuta Mayi "LA FACE CACHÉE" Debs Music no number (2019)
2019-08-09 00:00
コメント(2)
ルンバ人生を総括して ランバート・カバコ [中部アフリカ]
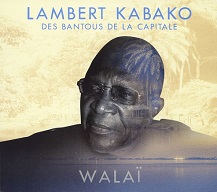
ランバート・カバコは、コンゴ共和国の名門楽団レ・バントゥー・ド・ラ・カピタールで、
45年以上フロントを務めたシンガー。
そのランバートの初ソロ作にして、遺作となったアルバムが届きました。
ランバート・カバコは、48年ブラザヴィルの生まれ。
59年に結成されたコンゴ共和国を代表する名門楽団、
レ・バントゥー・ド・ラ・カピタールに72年に入団し、
‘Osala Ngai Nini’‘Lokumu Na PCT’ などのヒットで看板歌手となりました。
昨年、レ・バントゥー・ド・ラ・カピタール結成60周年に向け、
記念コンサートの計画が動き出した矢先の6月23日、突然ランバートが急死し、
バントゥーの関係者ばかりでなく、大勢のファンに衝撃が走りました。
本作は、ランバートが亡くなるわずかひと月前にリリースされたもの。
ここ数年書きためていたという、全曲未発表の自作曲を歌った意欲作で、
その歌声も老いを微塵も感じさせない、たいへんな力作です。
ゆったりとしたルンバで聞かせる甘い歌い口などは、
ラヴ・ソングの巧者と呼びたくなるほどですよ。
ヴェテランらしい余裕を醸し出す歌いぶりで、ダンス・パートのセベンでは一転、
力のある歌いぶりを聞かせて、その振り幅の大きなヴォーカル表現にウナらされました。
こんなに元気に歌っていたランバートが、
70歳で急逝してしまったなんて、信じがたいですね。
トランペットとトロンボーンのホーン・セクションに、
ドラムスとベースの人力リズム・セクションのコンビネーション、
そこにギターとシンセが加わったアンサンブルが優雅にスウィングして、
黄金時代のルンバ・コンゴレーズを蘇らせます。
これを極上と言わず、なんと言いましょうか。
タイトル曲のサルサも、すごくいい仕上がり。
カチャカチャと金属的な響きを鳴らしている打楽器は、ナイフでしょうか。
耳新しい響きが、とても新鮮なサウンドを生み出しています。
歌手人生を見事に総括してみせた素晴らしい力作、
ランバートが最期に遺した傑作です。
Lambert Kabako "WALAÏ" Cyriaque Bassoka Productions no number (2018)
2019-08-07 00:00
コメント(2)
シカゴのニュー・ジェネレーション・ジャズ・グルーヴ レザヴォア [北アメリカ]

カーテンを開けて、ぱあっと朝の光が差し込むすがすがしさ。
小鳥のさえずりが聞こえてくるなか、
女性のハミングにストリングスが織り成す、柔らかなサウンド・テクスチャー。
ムーンチャイルドを思わせるオープニングのイントロに、心をつかまれました。
シカゴの新世代ジャズ・レーベル、インターナショナル・アンセムから登場した
6人組バンド、レザヴォアのデビュー作です。
思わずムーンチャイルドを連想したように、
サンプリングやループと生演奏とのブレンド具合が絶妙で、
キャッチーなメロディで惹きつけて、アブストラクトなラインを動かしながら、
さまざまな楽器がレイヤーしてサウンドを作っていく、
楽曲構成とアレンジの上手さにヤられちゃいました。
スムースな音の流れのなかで、サックスがおおらかにブロウし、
やがて管楽器が入り乱れて即興を繰り広げたあと、
ギターとウーリッツァーが新たな表情をサウンドに付け加える‘Resavoir’。
ゆったりとうねる波間を行く船のようなグルーヴが、なんという心地よさでしょうか。
‘Plantasy’ は、ストリングス・オーケストレーション(ポスト・プロダクション?)と、
ホーン・セクションのパートを組み入れた壮大なサウンドトラック。
ハンドクラッピングの印象的なビートで始まる‘Clouds’ は、
じっさいこんなに速い3連のクラップはできっこないから、
サンプリングなんでしょうけど、
そのリズムの上にホーンやギターが折り重なるという、
サウンド・スケッチの鮮やかさに舌を巻きます。
わずか30分に満たないアルバムながら、
これほど緻密に設計されたサウンド・デザインは、
昨今のラージ・アンサンブルに通じるものを感じます。
リーダーのトランペッター、ウィル・ミラーの
作曲・アレンジ・プロデュース能力に要注目ですね。
Resavoir "RESAVOIR" International Anthem Recording Co. 0026 (2019)
2019-08-05 00:00
コメント(0)
フレッシュなモーダル・ジャズ アレックス・シピアジン [北アメリカ]
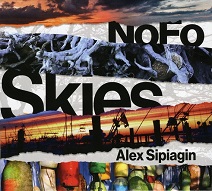
こういうシリアスなモーダル・ジャズを聴くのは、ひさしぶりかも。
クリス・クロスでずっとリーダー作を出していた
トランペッターのアレックス・シピアジンが、
新たにブルー・ルーム・ミュージックから出した新作です。
クリス・クロスじゃありえない、現代的なセンスのあるジャケットがいいですねえ。
「ジャズ保守」を絵に描いたクリス・クロスのジャケット・デザインが
どうにも好きになれないので、新作ジャケットはめちゃくちゃ好感持てます。
メンバーは、クリス・ポッター(ts)、ウィル・ヴィンソン(as)、
ジョン・エスクリート(p, key)、マット・ブリュワー(b)、
エリック・ハーランド(ds)という、クリス・クロス時代からのおなじみのメンバー。
60年代の新主流派よろしく、菅の合奏テーマで始まり、メンバーのソロ回しの後、
テーマに戻るといったオーセンティックなコンポジションに、
すごくひさしぶりといった感触があったんですけれど、
けっして60年代回帰ではなく、現代のジャズとしてフレッシュな響きを持っています。
アレックスのリーダー作ながら、メンバーにソロのスペースを均等に配分していて、
メンバーの技量をたっぷりと堪能できる作品となっているんですね。
アレックスの完成度の高いコンポジションともども、聴き応え十分であります。
アレックスの超絶テクも、アグレッシヴに迫るばかりではなく、
スローでのフリューゲルホーンのストイックな演奏ぶりなど、
キャリアを重ねた余裕を感じさせるプレイにウナらされます。
長年共演しているクリス・ポッターとのあうんの呼吸も、完璧ですね。
エレクトロニック・ミュージックからフリーまで、
振り幅の広いプレイをするジョン・エスクリートとの相性も良く、
ハービー・ハンコックを思わすアクースティック・ピアノや、
アヴァンギャルドに迫るキーボード・プレイなど、
コンテンポラリーなサウンドに貢献しています。
アルバムのフックとなっている女性ヴォーカリストを起用したトラックでは、
メカニカルな複雑なラインをヴォーカリーズしているんですけれど、
ヴォーカリスト自作の曲では、ネオ・ソウルな表情を見せているところがイマっぽいですね。
エリック・ハーランドの細かくビートを割ったドラミングも現代的といえ、
インタールードの短いトラックで叩く、
アフリカン・リズムを参照したパーカッション・プレイも、
モーダル・ジャズ旧世代にはなかったリズム・アプローチです。
新世代のジャズのイキオイも借りて、モーダル・ジャズも元気になったというか、
めちゃくちゃ刺激的でフレッシュな1枚で、絶賛愛聴中であります。
Alex Sipiagin "NOFO SKIES" Blue Room Music no number (2019)
2019-08-03 00:00
コメント(0)
トラディショナルでフューチャリスティックなエレクトロニック・マロヤ [インド洋]
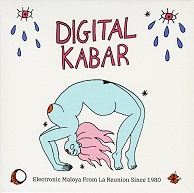
レユニオンのエレクトロニック・マロヤについては、
以前ラベルのデビュー作を取り上げたことがあります。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-03-07
ラベルは「マロヤ・エレクトロニクス」を標榜していましたけれど、
マロヤだけでなく、もっと幅広いクロス・カルチュアルな音楽性を持っていて、
そこに注目したんですけれど、このアルバムは、マロヤど真ん中といった
「エレクトロニック・マロヤ」の名にふさわしいトラックがコンパイルされています。
エレクトロニック・マロヤのDJジャコ・マロンがリミックスした
パトリック・マナンのオープニング曲は、前半エレクトロ、後半生音という仕掛け。
後半の打楽器とコーラスのコール・アンド・レスポンスになっても、
エレクトロがいつ消えたのかわからないくらい、
シームレスに繋がっているところがミソ。
インド洋音楽のエレクトロニック・ミュージックの新進レーベル、
ババニ所属のブーグズブラウンのトラックは、
モザンビークの木琴ティンビラのダンス・リズムとかけ声に、
生のパーカッションとエレクトロニック・ビートを幾層にもレイヤーして、
アフロ色をぐっと濃くしているところがスゴイ。
エレクトロが伝統要素を倍化させて、漆黒のグルーヴを生み出しています。
パリのアフロ・エレクトニック・レーベル、マウィンビ所属の
ロヤことセバシチャン・ルジュンヌの‘Malbar Dance’ は、
マロヤに溶け込んでいるタミール音楽の成分をぐっと表に出しています。
マロヤのトランシーなビートに、タミール人男性歌手の浮遊するヴォーカルを絡ませ、
親指ピアノをカクシ味に使っているところも聞き逃せませんね。
パーカッションの生音と打ち込みが交錯するビートが、
ニュアンス豊かなグルーヴを生み出しているところがいいんです。
オール・エレクトロなトラックもなかにはあるんですけど、
ビートが幾重にも交差する複雑なリズムを作っているところは、
さすがレユニオン人!といった感じ。
あ、でも、アルバム最後に置かれた単調な四つ打ちハウスのJ=ゼウスのトラックと、
クワルドの純然たるエレクトロは、マロヤ要素皆無で蛇足感は拭えず。
ジスカカンと並びマロヤをモダン化した立役者のひとり、
チ・フォックの初期85年作の曲や、
サルム・トラディシオンの05年作の曲をリミックスしたトラックもあり。
サルム・トラディシオンは、フランスのコバルトから世界デビューする以前、
レユニオン地元のレーベルに制作したデビュー作で、
ディレイ・マシンを効果的に使っていたのが印象的でした。
エレクトロニック・ミュージックに接近するかと少し期待していたんですけれど、
コバルトではそういう試みをせず、残念でした。
タイトルの「カバール」とは、マロヤを演奏し、人々がダンスすることで、
レユニオン文化が共有される「場」のことだそうです。
現代のダンスフロアで共有されるのが、デジタル・カバールというわけですね。
Patrick Manent, Boogzbrown, Loya, Jako Maron, Ti Fock, Agnesca, Zong, Labelle, Salem Tradition and others
"DIGITAL KABAR: ELECTRONIC MALOYA FROM LA REUNION SINCE 1980" InFíne IF1052
2019-08-01 00:00
コメント(0)




