浪曲河内音頭の至芸 日乃出家小源丸 [日本]

日乃出家小源丸といえば、
河内音頭界のレジェンドと呼ぶにふさわしい、現役最高峰の音頭取り。
その日乃出家小源丸が生誕80周年を記念して、
浅草木馬亭で記念公演を開くというので、妻を誘い行ってきました。
河内音頭は、基本ダンス・ミュージックなんだから、櫓のまわりで踊ってなんぼ。
♪イヤコラセ~ ドッコイセ♪とばかり、踊りに夢中になってしまうと、
音頭取りの歌の文句など、ぜんぜん耳に入らなくなってしまうこともありますよね。
踊って楽しけりゃ、それはそれで十分なんだけど、
河内音頭のレパートリーは、一大ドラマの演目でもあるので、
そこで語られる物語を楽しまない手はありません。
そのためには、櫓じゃなくって、小屋の方がじっくりと楽しめるというもの。
浅草の木馬亭で、日乃出家小源丸の河内音頭を聴けるというのだから、
こんな贅沢を見逃す手はありません。
その記念公演で小源丸師匠が選んだ演目は、「竹の水仙」。
な~るほど、浪曲の定席、木馬亭という小屋にあわせて、浪曲河内音頭としたわけですね。
竹の水仙は、名工・左甚五郎のもっとも有名な伝承話。
浪曲では京山幸枝若が得意とするネタで、落語でもよく取り上げられていますよね。
小源丸師匠は、円熟を極め尽くした味のある語りで、
左甚五郎のひょうひょうとした人物像を演じていました。
いやぁ、やっぱりこれは踊っていたら、なかなか味わえるもんじゃありません。
その軽妙な語り口にぐいぐい引き込まれてしまって、夢中にさせられました。
ほんと、素晴らしかったです。



師匠の語り口とともに感激したのが、日乃出家源司の太鼓。
抑えに抑えたバチさばきに、ゾクゾクしました。
シンコペーションを利かせたリズムで胴を軽やかに叩き、
皮の打面を打つのは必要最小限だけという、簡潔なスタイル。
胴を叩くリズムのニュアンスが実に豊かで、
ひょいと裏拍のリズムに転じてみせる技巧に、ウナりました。
最初に出演した日乃出家富士春のバックで叩いていた時から、
その<打たない太鼓>ぶりに感じ入って、上手いなぁ~と聴き入っちゃいましたよ。
抑制が利いているからこそ、緩急のダイナミクスがスゴくて、一打一打に無駄がない。
河内音頭のグルーヴ・マスターですね。
終演後、出来上がったばかりという、
小源丸師匠の90年代から00年代初頭の私家録音を編集した4枚組CDをいただいてきました。
ブックレットの印刷が間に合わず、印刷所から木馬亭に直に届けられたのを、
公演中にスタッフが総出で封入し、終演後の販売になんとかこぎつけたんだそう。
タイトルに「十三夜」とあるとおり、
これほど広範なレパートリーを演じ分けられる音頭取りは、
小源丸師匠を置いて他にはいないでしょう。
70年を越す音頭歴を刻んできた小源丸師匠の名調子を、
これでいつでも、じっくりと楽しめます。
日乃出家小源丸 「河内音頭奔流 日乃出家小源丸十三夜」 ミソラ MRON3005
2019-09-30 00:00
コメント(0)
グライム世代の南ロンドン・ジャズ アシュリー・ヘンリー [ブリテン諸島]

南ロンドン、なんかもうスゴすぎる。
才能ある音楽家が、次から次へとわいてくるかのように登場しますね。
91年生まれというアシュリー・ヘンリー、
すでに先行EPの2枚で話題となっているピアニストですけれど、
最新作のフル・アルバムを聴いて、その才能に脱帽しました。
ジャズをベースとしながら、ヒップ・ホップ、R&B、ブロークン・ビート、
ベース・ミュージックを横断するその自在ぶり。
なんかもう一度「クロスオーヴァー」という語をあてはめたくなるサウンド・デザインで、
あらためて、「フュージョン」(=融合)とは設計思想が違うと強調したくなりますねえ。
60年代にジャズ・ロック、70年代にクロスオーヴァー、80年代にフュージョン、
90年代にスムース・ジャズとラベリングされた音楽は、
すべて地続きのように捉えられ、白眼視され続けてきましたけれど、
再評価ではなく、もう一度評価を仕切り直す必要があると思います。
このアルバムも、切り取りようによっては、ジャズ・アルバムにも、
ヴォーカル・アルバムにも、ビート・アルバムにも聞こえます。
それでいてアルバムの統一感はしっかりとあって、
ヘッドハンターズ以降のハービー・ハンコックの
エレクトリック・ジャズ(クロスオーヴァー)を、
グライム世代の感性で更新したといえるんじゃないですかね。
参加ミュージシャンも、同世代のクリエイターがずらり並んでいて、
南ロンドン仲間のモーゼズ・ボイドの参加は当然として、
アメリカからトランペットのキーヨン・ハロルドと、
ドラムスのマカヤ・マクレイヴンを起用したのは、大正解でしたね。
ロイヤル・アカデミーを卒業し、クラシックの教育を十二分に兼ね備えたスキルも、
リリカルで美しいタッチに、はっきりと表れています。
Ashley Henry "BEAUTIFUL VINYL HUNTER" Sony Music 19075891582 (2019)
2019-09-28 00:00
コメント(0)
チルでスウィートなシャングリ=ラ ムーンチャイルド [北アメリカ]

オープニング早々から、アンバー・ナヴランのタメ息ヴォーカルに導かれて、
一気にムーンチャイルド・ワールドへいざなわれるこの快楽。
前作“VOYAGER” でトリコとなり、ライヴも観て、すっかり彼らの大ファンとなりました。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2017-06-22
4作目を数えるムーンチャイルドの新作は、
鍵盤の織り成すレイヤーが、ホログラフィックな映像を見るかのような
美しさだった“VOYAGER” のサウンドとうって変わって、レイヤーをほとんど使わず、
音数をぎりぎりに絞ったシンプルなサウンドへ様変わりしました。
さらに、今回はウクレレやギターといった弦楽器を使って、
新たな響きの実験も試みていますよ。
これだけ、前作の“VOYAGER” とはサウンドを変えてきているのに、
ムーンチャイルドというグループの音楽性に揺るぎがないのは、
3人が生み出すサウンドのグランド・デザインがしっかりとしているからでしょうね。
あと、ゆっくりと雲が流れていく空模様を映すようなコンポジションも、
ムーンチャイルドの世界観を決定づける大事なファクター。
起承転結をつけないミニマムなソングライティングが、
ムーンチャイルド独特の空気感と浮遊感のあるサウンドのベースとなっています。
今作のように、サウンドを削ぎ落としていくと、
音の組み立てをわずかに変えただけで、サウンドの表情ががらりと変わりますけれど、
ムーンチャイルドのサウンドスケープをキープするために、
前作以上に緻密なサウンドづくりをしていることがよくわかります。
アンバーのヴォーカルのリード・ラインにささやき声を加えて、ソフトさに厚みを加えたり、
曲と曲の合間に、ビートの変化をつなぐための音を足して、
アルバム全体の流れをスムーズにしたりと、そのデリケイトな音づくりに感じ入ります。
チルでスウィートなシャングリ=ラを創り出す、LAの若き3人の才能に脱帽です。
Moonchild "LITTLE GHOST" Tru Thoughts TRUCD383 (2019)
2019-09-26 00:00
コメント(0)
原石の輝き ナハワ・ドゥンビア [西アフリカ]

おぉー、ナハワ・ドゥンビアのデビュー作がCD化された!
オウサム・テープス・フロム・アフリカを主宰するブライアン・シンコヴィッツが
レーベル第1弾に選んだのも、ナハワ・ドゥンビアでしたよね。
あの時復刻したのは、82年の3作目の方。
なんでデビュー作じゃなくて3作目なんだよと、当時そのセレクトに不満ぷんぷんでした。
マリ、ワスル出身の女性歌手、ナハワ・ドゥンビアがアルバム・デビューしたのは、
ラジオ・フランスが主宰する新人コンテストで81年に優勝したのがきっかけ。
この年、コート・ジヴォワールのASレコーズからデビュー作を出したんですが、
ギター1本をバックに歌ったそのアルバムは、
粗削りな20歳のパワーを炸裂させた、痛快な仕上がりだったんです。
それはまさに、原石の輝きというべき貴重作でした。
それに比べて、翌82年に出した『第3集』は、
カマレ・ンゴニ、ギター、ベース、キーボード、
パーカッションというアンサンブルにのせて、
ワスル地方に伝わるバンバラ人のダンス音楽ディダディを披露した作品で、
のちの名作“DIDADI” や“MANGONI” のプロトタイプといえるものだったんですね。
世界デビュー後の名作を知る者からは、
コート・ジヴォワール産のチープなプロダクションはあまりにお粗末で、
あらためて復刻する意義は感じられませんでした。
なので、「なんでデビュー作じゃなくて3作目なんだよ」だったわけなんですが、
遅まきながらとはいえ、よくぞデビュー作をCD化してくれました。
ナハワはグリオ出身の歌手ではありませんが、このデビュー作を聴いて、
グリオばりの強力な歌声に圧倒されない人はいないでしょう。
カマレ・ンゴニをギターに置き換えたスタイルで弾く
ング・バガヨコのアクースティック・ギターにのせて、
ナハワは鋼のような強靭な歌声を聞かせます。
Nâ Hawa Doumbia "LA GRANDE CANTATRICE MALIENNE VOL.1" Awesome Tapes From Africa ATFA035 (1981)
2019-09-24 00:00
コメント(0)
アルジェリアのうた フリア・アイシ [中東・マグレブ]

フリア・アイシは、アルジェリアのベルベル系先住民シャウイの音楽を教えてくれた恩人。
アルジェリア北東部オーレス山地に暮らすシャウイ人の伝統音楽を現代化した
08年の“CAVALIERS DE L'AURÈS” には、夢中にさせられました。
モダン化したサウンドよりも、フリアの凛とした歌声に胸を打たれ、
シャウイの伝承歌が持つ、雄大なサウンドスケープに魅せられたんですね。
フリア・アイシは、オーレス地方の中心地バトナに生まれた生粋のシャウイ人で、
幼い頃からさまざまな集まりを通して、シャウイの歌を習い覚えてきたそうです。
そんなシャウイ文化にどっぷり浸かったルーツを持つ一方で、
経済的に恵まれた家庭に育ち、学業も優秀だったフリアは、
都会のコンスタンティーヌへ出て中学に通い、
さらにパリへ渡って大学で心理学を学び、大学院で社会学の学位を取りました。
広い世界へ出て高い教養を身に付け、国際的な視野も養ったフリアが、
あらためてルーツを振り返り、シャウイの歌を再構築したのが、
あの名盤“CAVALIERS DE L'AURÈS” だったわけですね。
そして、フリアはシャウイの文化にとどまらず、さらに視野を広げて、
今作ではアルジェリアのさまざまな伝承歌を取り上げています。
今回も、フリア自身が叩く平面太鼓のベンディールを軸に、
アルジェリア独自の弦楽器マンドール、ゲンブリ、ウードに、
笛のガスパ、ネイなど伝統的な楽器のみの伴奏で、
ベンディールだけで歌う独唱も多くあります。
このシンプルなサウンドとフリアのこぶしが、
歌に備わるエネルギーを最大限に引き出しているんですね。
さまざまな儀式で歌われる宗教歌にスーフィーの歌、さらにカビール民謡まで、
アルジェリアの伝承歌の世界を、フォークロアから昇華した地平から歌えるのが、
フリアの稀有な才能。それゆえ、アルジェリア人でない外国人リスナーの耳に届くのです。
Houria Aïchi "CHANTS MYSTIQUES D’ALGÉRIE" Accords Croisés AC175 (2017)
2019-09-22 00:00
コメント(0)
アンゴラから登場したジャズ新世代シンガー・ソングライター アナベラ・アヤ [南部アフリカ]

アンゴラの新人女性シンガー・ソングライターのデビュー作。
アンゴラとはいえ、センバやキゾンバではなく、
アフロ・ジャズのシンガーというところが、新味の人であります。
アナベラ・アヤは83年ルアンダの生まれ。
5歳の時から教会で歌い始め、将来歌手になることを夢見ていたそうですけれど、
俳優としての才能を見出されて劇団に加入し、
舞台女優として15年のキャリアを積んだという人。
劇団に所属する間、本格的な歌唱レッスンを受け、
この時期にジャズを学んだようです。
演劇の世界から音楽の世界に移り、ジャズのシンガー・ソングライターを志向した
アナベラの音楽性はレコード会社に理解されず、
17年にルアンダの歌謡祭で受賞するも、レコード会社からの引きはありませんでした。
30も半ばになり、3人の子を持つ母親となっていたアナベラは、
歌手デビューする最後のチャンスと、アルバムを自主制作する決心をし、
バー・シンガーとして働きながら資金を作り、昨年デビュー作を完成させたのでした。
そんな遅咲きの人ですけれど、アルバムを出すや否や評判を呼び、
さまざまな賞にノミネート、そして受賞もし、
カーボ・ヴェルデで開かれたジャズ・フェスティヴァルに出演するなど、
アナベラの評価は一気に高まりました。
ウンブンドゥ語で「前進」を意味するデビュー作のタイトル Kuameleli は、
時流に乗らず、自分の音楽を大事に育んできたアナベラの気概が表れています。
芯のあるしっかりとした歌声で、ざっくばらんとした歌いぶりから、柔らかな歌い口、
さらに粘っこい節回しを使ってみたりと、さまざまに表情を変えて歌う技巧派です。
自作の曲のほか、フィリープ・ムケンガ、アルトゥール・ヌネスなどの
曲も歌っていて、アコーディオンやアクースティック・ギターの響きを生かした
オーガニック・テイストのみずみずしいサウンドが胸をすきます。
レベッカ・マーティンやベッカ・スティーヴンスといった、
新世代ジャズのシンガー・ソングライターと共振する同時代性を感じさせる人で、
カミラ・メサやアンナ・セットンあたりが好きな人なら、どストライクでしょう。
昨年12月15日に急死したブラジルの名ベーシスト、
アルトゥール・マイアのベース1本をバックに歌った‘Tic Tac’ などは、
リシャール・ボナのファンにもアピールしそうですね。
ウンブンドゥ語で歌うタイトル曲のほか、クワニャマ語で歌う‘Nangobe’、
ピジンで歌う‘I Love You Bue’、キンブンドゥ語で歌う‘Tia’、
リンガラ語で歌う‘Kaumba’など、多言語使いがアンゴラ人らしい、
新感覚のシンガー・ソングライターです。
Anabela Aya "KUAMELELI" Anabela Aya no number (2018)
2019-09-20 00:00
コメント(2)
泣きのエチオピア歌謡アルバム アスター・アウェケ [東アフリカ]


エチオピア歌謡のヴェテラン女性歌手、アスター・アウェケの新作です。
前作から6年ぶりと、ずいぶん長いインターヴァルになりましたが、
今作はポップな前作“EWEDIHALEHU” とはガラリ変わって、
じっくりと歌ったシブいアルバムになりましたよ。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-11-30
オープニングからスローのエチオ情歌(ティジータ)で迫り、
ハイ・トーンを揺らしながら回すこぶし使いに、胸をキュッとつかまれます。
これぞアウェケ節といえる、若い頃から特徴的だった節回しなんですが、
若い頃は声が細くてキンキンと聞きづらかったものの、
円熟してすっかり角も取れ、まろやかになりましたねえ。いやあ、絶妙です。
前作のようなポップ作では、高音域を揺らすアウェケ節は影を潜めがちでしたけれど、
今作のようなスローやミディアム・スロー中心のレパートリーでは、
緩急自在に炸裂させていて、あらためて上手い歌手だなあと感じ入ります。
また、プロダクションががらっと変わったなと思ったら、
なんと長年の相棒アバガス・キブレワーク・シオタの名がありません。
アウェケ自身がプロデュースを務めていて、
今回はアレンジャーに、4人の名前が並んでいます。
そのアレンジャーも、前作とは総入れ替えになっていて、
1曲のみ担当のアビー・アルカだけが、前作に続いて起用されています。
アクースティック・ギターやホーンズの生音を効果的に使いながら、
ヌケのいいサウンドでじっくりと歌ったティジータ中心のアルバム。
ブルージーな‘Yewedede’ もグッときますねえ。
ディアスポラのエチオピア人を泣かせることウケアイの、
エチオピア歌謡アルバムです。
Aster Aweke "CHEWA" Kabu no number (2019)
左:エチオピア盤 右:アメリカ盤
2019-09-18 00:00
コメント(0)
4声が生み出すモアレ マレウレウ [日本]

マレウレウの新作がいい!
12年の前作『もっといて、ひっそりね。』は、ちょっとがっかりだったんですよね。
マレウレウのメンバー4人による無伴奏歌では、
マジカルなポリフォニーを堪能できるのに、
バンド・アンサンブルが付いたとたん、4人の声が<きれいに>整理されてしまって、
ポリフォニックなマジックが消えちゃうんですよ。
う~ん、なんで、こんなふうにしちゃうのかなあ。
4人の声が織り上げるニュアンス豊かなヴォイス表現を、
バンド・アンサンブルが雲散霧消させるようじゃ、意味ないじゃないの。
マレウレウの一番の魅力である、
ウポポやウコゥクに宿る複雑な声のモアレが生かされず、
単なる女性コーラスにしてしまっていることに、不満ぷんぷんだったのです。
プロデューサーのオキが、そんな点を意識していたのかどうかは知りませんが、
今作は原点回帰で、バンドはおろかリズム・セクションが付く曲もなく、
オキのトンコリが伴奏を付けた1曲あるのみという、シンプルさに徹しています。
たぶんオキも、前作のプロダクションはうまくいかなかったと思ってたんじゃないかな。
マレウレウの一番の良さって、遊び唄を楽しく歌うところだと思うんです。
みんながマレウレウに親しみを持つのは、そこなんじゃないのかなあ。
昔ばなしを聴くのを楽しみに待つ、こどものような心持ちにさせられるのは、
子守唄や遊び唄が持つ豊かな音楽世界を、マレウレウが運んできてくれるからですね。
そのために、アイヌの伝統音楽であるウポポやウコゥクを借りてきた、
そんなふうにもぼくには思えるんです。アイヌの伝統が先にありきだったのではなく、
歌の楽しさをアイヌの歌に発見したような。違うかな。
個性に富んだ4人の声のレイヤーを生かした今作は、
マレウレウの魅力が十二分に発揮されましたね。
4人の声が溶け合うのではなく、異なる声色が重なったり離れたりしながら、
さまざまな色合いの変化をつけていくところがなんとも味わい深く、引き込まれます。
思えばマレウレウにノック・アウトされたのは、
ア・カペラのみで歌ったミニ・アルバムのデビュー作でした。
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-11-23
そのミニ・アルバムのレパートリーをもう一度歌い直した16年の「CIKAPUNI」では、
4人の声の重心が深くなり、ゆったりと大きくうねるようになったグルーヴに、
グループの深化を感じました。
今作は、「CIKAPUNI」の成果をさらに前に進めた作品といえると思います。
Marewrew 「MIKEMIKE NOCIW」チカル・スタジオ/タフ・ビーツ UBCA1065 (2019)
2019-09-16 00:00
コメント(0)
自由な流歌〜沖縄俗謡 嘉手苅林昌 [日本]

本土復帰前にあたる60年代の嘉手苅林昌は、やっぱり格別ですねえ。
アカバナーから出たマルテル音源の編集盤を聴いて、
何十年ぶりで嘉手苅熱が再燃しちゃいました。
マルテルに残されたシングル録音は、
これまでにもいくつかのコンピレでCD化されてきたとはいえ、
18曲もまとめて復刻されたのは、これが初。
カデカル節とじっくりと向き合うには、格好のアルバムといえます。
もうのっけから、嘉手苅林昌の世界に、ぐぃぐぃ引きずり込まれてしまいましたよ。
1曲目から、のちのち林昌を代表するレパートリーとなる「下千鳥」ですからねえ。
ファンにはおなじみの、別れの悲しみを歌ったバラードですね。
林昌は世の無常をも超越したかのように淡々と歌っていて、
その昇華した深い情念に、胸を打たれます。この境地こそが林昌ならではといえます。
後年の枯淡の歌いぶりで聞かせる「下千鳥」も美しいんですけれど、
こんなに丁寧に、言葉を慈しみながら歌っているのは、この時代だからこそでしょう。
マルテルに録音したのは66・67年頃。
林昌が40半ばの頃で、いわば脂ののった男盛りともいえる時期です。
マルテルに吹き込む直前には、65年にマルフクからデビューLPを出していて、
そのレコードを血眼になって探し回った話は、以前ここで書きましたけれど、
https://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-08-31
マルフク盤LPを知るきっかけとなった
平岡正明の『クロスオーバー音楽塾』(講談社、1978)には、
マルテルのシングル盤「国頭大福/サラウテ口説」についても、大いに語られていました。

本盤にはもちろんこの2曲も収録されていて、
ぼくはこのシングル盤をマルフク盤を手に入れた翌年に、
那覇のレコード店で直接手に入れました。
マルフク盤の良さがわかるようになるまでには、少し時間がかかりましたけれど、
「国頭大福」のスウィング感には、一聴でシビれましたね。
古典音楽や民謡の型からひょうひょうとはみ出し、
変幻自在な即興で自由な琉歌の境地を切り開いた、林昌の至芸の数々。
かつてマルテルのシングル盤には、「沖縄俗謡」と書かれていたように、
民謡=民俗音楽ではなく、俗謡=大衆音楽であることが、
くっきりと刻印された名編集盤です。
嘉手苅林昌 「島唄黄金時代の嘉手苅林昌」 アカバナー TR002
[EP] 嘉手苅林昌 「国頭大福/サラウテ口説」 マルテル MT1009
2019-09-14 00:00
コメント(0)
不変のレディ・ソウル アンジー・ストーン [北アメリカ]

そう、この声、ですよ。
アンジー・ストーンの魅力といえば、やっぱり苦みのあるこの声。
いい声ですよねえ、安心して身を委ねられます。
そして、たぐいまれなる才能を感じさせるのが、ディクションの良さ。
言葉を自在にリズムへ乗せていくスキルは、
デビュー当初から変わらぬ、アンジー独特のセンスを感じさせます。
そのマナーは、ブラック・ミュージックとしてのソウルを
体現したオーセンティックなもので、
もちろんゴスペルを土台としてるのは言うまでもありません。
アンジー・ストーンといえば、ディアンジェロ絡みを抜きにしても、
常にネオ・ソウルの括りで語られてきましたけれど、
ぼくは、クラシック・ソウルの伝統を継いだ人と受け止めていて、
そこにずっと惹かれ続けてきました。
もちろん、そのうえでヒップ・ホップR&Bにも柔軟に応えられるところが、
彼女の強みでもあるわけなんですけれどね。
ネオ・ソウル登場時、そのシーンに乗れなかったぼくが、
アンジーには強く反応できたのも、そんな彼女の資質ゆえです
時代に左右されずに、トレンドを追うこともなく、マイ・ペースで歌いながら、
しっかりと時代と共振することのできる才能、その腰の据わった姿勢が、
新作でも貫かれていますよ。
タイムレスな魅力を放ってきたレディ・ソウル、今作も会心の出来です。
Angie Stone "FULL CIRCLE" Conjunction Entertainment/Cleopatra CLO1326 (2019)
2019-09-12 00:00
コメント(0)
グラミー受賞後の自負作 ボビー・ラッシュ [北アメリカ]
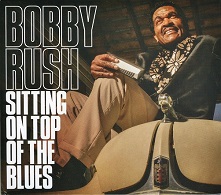
ボビー・ラッシュがまさかグラミーを獲るとは、思いもよらなかったなあ。
前作“PORCUPINE MEAT” が、
16年の最優秀トラディショナル・ブルース・アルバムに輝いたのには、びっくり仰天。
芸能ニュースにさしたる関心のない当方とはいえ、
半世紀近くチタリン・サーキットのショウ・ビジネスで渡り歩いてきた、
ラッシュのような苦労人に光を当てるとは、グラミーもまんざらじゃないですね。
そのグラミー受賞作はラウンダーからのリリースでしたけれど、
新作はいつものラッシュの自己レーベル、ディープ・ラッシュから。
いやあ、ジャケットがこれまでになくカッコいいじゃないですか。
これまでのディープ・ラッシュのアルバムはアカ抜けないものが多かっただけに、
う~ん、グラミー獲ると、違ってくるもんですねえ。
なんたって、タイトルが“SITTING ON TOP OF THE BLUES” ですよ。
ミシシッピ・デルタの人気グループ、
ミシシッピ・シークスが1930年に当てた大ヒット曲で、
のちにハウリン・ウルフなどのブルースマンばかりでなく、
グレイトフル・デッドやボブ・ディランなど多くの歌手が取り上げてきた有名曲ですが、
アルバム中にこの曲はなく、タイトルだけ借りてきたのは、グラミー受賞への自負でしょう。
オープニングの‘Hey Hey Bobby Rush’ からして、
あらためて「オレはブルースマン」と自叙伝的に歌い、
ラッシュはみずからの立ち位置を、しっかりと見つめ直しています。
プロデュースは前作に引き続きスコット・ビリントンが担当した曲のほか、
マルチ・プレイヤーのヴァスタイ・ジャクソンとオルガン奏者のパトリック・ヘイズが、
それぞれラッシュと共に制作しています。
ホーン・セクションを従えたソウル・ブルースあり、
アクースティック・ギターによるカントリー・ブルースあり、スワンプ・ロックありと、
多彩なサウンドを貫くダウンホームな味わいが、ラッシュの真骨頂ですね。
シャッフルもブギウギもファンクも、すべてがラッシュ流に料理され、
粘っこく泥臭いタフなヴォーカルは快調そのものです。
ハープを吹く曲では、ハープを持った両手を高く掲げて静止し、
次の瞬間思い切りよく口元に両腕を振り下ろす、ライヴでのアクションが思い浮かびました。
グラミー受賞後の自負作、殿堂入りといえるんじゃないですか。サイコーっす!
Bobby Rush "SITTING ON TOP OF THE BLUES" Deep Rush 10215CD (2019)
2019-09-10 00:00
コメント(0)
西洋人を前にした初ライヴ・パフォーマンス ヌスラット・ファテ・アリー・ハーン [南アジア]

ヌスラット・ファテ・アリー・ハーンを知ったのは、
82年の2枚組LP“MUSIC AND RHYTHM” に収録された1曲がきっかけでした。
このレコードは、ブルンディ・ドラムに始まり、
ホルガー・シューカイの‘Persian Love’ で締めくくられる、
伝統音楽から最新のポップ音楽まで21組のアーティストを収録したコンピレーション。
ワールド・ミュージック(当時まだその言葉はなかったけれど)の祭典
ウォーマッドがここからスタートした、記念碑ともいうべきアルバムでしたね。
で、このレコードでぶったまげたのが、ヌスラットだったのです。
カッワーリーそのものも初体験なら、
これが宗教音楽だというのだから、ビックリさせられました。
ヌスラットとコーラスが丁々発止の即興で掛け合うインプロヴィゼーションは、
ジャズのスリリングなインタープレイと全く変わることのない興奮を巻き起こします。
手拍子とコーラスとともに高揚していく、そのテンションの高さに圧倒され、
この1曲でヌスラットの名前は、ぼくの脳裏にしっかと刻み込まれました。
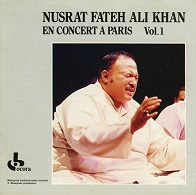
それからだいぶ間が空き、87年の春になって、
ようやく待望のヌスラットのアルバムが出たんですね。
フランスのオコラから出たパリのライヴ盤は、期待にたがわぬ素晴らしい内容で、
連日のヘヴィ・ロテ盤となりました。そんなさなかの9月、
ついにヌスラット一行が初来日してくれたのです。
「アジアの神・舞・歌」と題する国際交流基金が招聘したコンサートで、
会場は国立劇場でしたね。ヌスラットの単独公演ではなく、
トルコのメヴレヴィー教団の旋回舞踏や雲南省の歌舞、アイヌ古式舞踏との
抱き合わせ企画だったんですが、ヌスラットのパフォーマンスは飛び抜けていました。
84年、キング・サニー・アデのライヴ以来の衝撃でしたよ。
ヌスラットのソロからコーラスに移って、ぐんぐんと盛り上がっていく場面や、
歌がすっと消え、場面を暗転させるように、タブラと手拍子のリズムだけになる
瞬間のスリリングさ。はたまた、ヌスラットがコーラスに割り込んで即興する
手に汗握る場面など、絨毯の上に座した男たちが、両手を広げたり、手のひらを
さまざまに動かしながら歌う、初めて見るカッワッリーのパフォーマンスに
目を見張りましたよ。
ダンス・ミュージックではないから、シートで大人しく座っていたわけですけれど、
観ているだけでも血沸き肉躍ってしまって、
身体が熱く火照って、どうしようもありませんでしたね。
その後、ヌスラットたちは何度も来日して、
五反田のゆうぽうとや横浜のウォーマッド(ヌスラットが立ち上がって歌い、
サンディーがひれ伏したあのライヴです)でも観ましたけれど、
やはり87年の国立劇場での衝撃がなんといっても一番です。
さて、今回34年ぶりに陽の目を見た、
85年の第1回ウォーマッドでのライヴ・パフォーマンスは、
ヌスラット一行が初めて西洋の観客の前でやったもの。
オコラ盤のパリ・ライヴの4か月前となる、7月20日深夜にレコーディングされました。
言葉の通じない、ましてや宗教も異なる西洋人を前でも、ヌスラットにアウェイ感などなく、
ダイナミックな即興のパフォーマンスと変幻自在なリズム使いで、観客を圧倒します。
のちにヌスラットが、西洋人の前では、
リズムを強調して歌うとインタヴューで答えていたように、
聴衆の反応を見ながら、当意即妙に場を作り上げていくパフォーマーとしての才能は、
パキスタンの霊廟で歌うカッワールにはない、類まれなる資質を示すものでした。
Nusrat Fateh Ali Khan & Party "LIVE AT WOMAD 1985" Real World CDRW225
Nusrat Fateh Ali Khan "EN CONCERT A PARIS VOL.1" Ocora C.558658 (1987)
2019-09-08 00:00
コメント(2)
70年代クロスオーヴァー+ドラムンベース レベッカ・ナッシュ&アトラス [ブリテン諸島]

レザヴォアを愛聴しているところに、また嬉しいジャズ新作が届きました。
今度は話題の南ロンドンから登場した新グループ。
ブリストル育ちのピアニスト、レベッカ・ナッシュが率いるアトラスのデビュー作です。
きらきらとした鍵盤のネオ・ソウル的な音感で誘いながら、
やがてうねるようなドラミングによって、雄大なサウンドスケープを生み出していく
アンサンブルが聴きもののグループですね。
マット・フィッシャーのしなやかで軽快なスティックさばきと、
前へ前へと推進していくエネルギーのあるドラミングが、がっしりとした骨格のある
バンド・サウンドを組み立てていますよ。
レベッカ・ナッシュはブリストルで育っただけに、
マッシヴ・アタックやドラムン・ベースに影響を受けたというのもうなずけるんですが、
‘Tumbleweed’ の細かくビートを割っていくドラム表現など、
生のドラムンベースとも受け取ることもできそうな気もするなあ。
中盤のサラ・コールマンのヴォーカルがフィーチャーされる曲は、
ジョニ・ミッチェルとイメージがダブったりしますよ。
トランペットのニコラス・マルコムとレベッカのエレクトリック・ピアノの絡みが、
エディ・ヘンダーソンとハービー・ハンコックを思わせるところもあり、
アトラスには、70年代前半のクロスオーヴァー・サウンドに、
ドラムンベースを合体させたような魅力がありますね。
エレクトロニクスも交えたハードなインプロヴィゼーションを展開するラスト・トラックまで、
聴き応え満載の作品です。
Rebecca Nash and Atlas "PEACEFUL KING" Whirlwind Recordings WR4748 -2019-
2019-09-06 00:00
コメント(0)
ヒップ・ホップに娘を思う 泉まくら [日本]

この人に興味を持ったのは、15年の『愛ならば知っている』のジャケットがきっかけ。
大島智子のアートワークが、下の娘とオーヴァーラップして、妙に心にひっかかりました。
どんな人なのかとチェックしてみると、
「普通の女の子が半径数メートルで起こったことを
リリックにしたゆるふわラップ」とのこと。
聴いてみると、時にメロディを歌うパートもあるものの、
ポエトリー・リーディングのようなラップは、淡い語りのよう。
「ゆるふわラップ」というのも言い得て妙だなと思いましたけれど、
つぶやくようなフロウには、しっかりとしたビート感が宿っていて、とても自然に聞けます。
この「自然に聞ける」というところがキモで、語りを音楽的に聞かせるには、
相当な技量が必要だということを、再認識させられます。
歌謡曲の朗読とか、フォークの語りには、さんざん赤面させられてきましたからねえ。
語りを自然に聞かせるには、かつては節回しやこぶし使いというスキルを必要とされたのが、
ヒップ・ホップの時代では、新たにビートに言葉をのせる
リズムの咀嚼力が求められるようになり、それを若い世代が獲得してきたんですね。
ヒップ・ホップというビートの利いた音楽でありながら、
昔のフォークみたいなリズム感のなさを露呈するラッパーがたまにいるのは、
リズムの咀嚼力が足りないからでしょう。
そう考えてみると、泉まくらのラップを「ゆるふわ」と表現するのは、
いささか彼女のスキルを軽んじているようにも思え、
若い日本人ミュージシャンが持つ高度なリズム咀嚼力を、
彼女もまた備えていることがわかります。
トラックメイクも、泉まくらの音楽世界を過不足なく、簡潔に表現しています。
cero に通じるネオ・ソウル~ヒップ・ホップを横断したサウンドで、
どこか都市の郊外感をイメージさせるところも、cero と同じ匂いがしますね。
昨年、下の娘が家を出て一人暮らしを始めてから、
「どうしてるかなぁ~」とふと思い起こすことが増えました。
泉まくらを聴いていると、ますますそんな思いが募ります。
泉まくら 「as usual」 術ノ穴 XQND1012 (2019)
2019-09-04 00:00
コメント(0)
フレッシュなサンバ クラウジオ・ジョルジ [ブラジル]
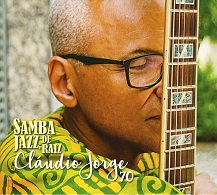
うわー、実にクラウジオ・ジョルジらしいというか、
クラウジオ・ジョルジにしか作れないサンバ・アルバムですね。
80年にオデオンからデビューした時は、
メロウなMPB系サンバで登場したクラウジオ・ジョルジでしたけれど、
ソロ・デビュー前は、ネイ・ロペスやルイス・カルロス・ダ・ヴィラなど
伝統系サンビスタのプロデュースを手掛けていただけに、意外に思ったものでした。
クラウジオは、若い頃にカルトーラやイズマエル・シルヴァなど、
マンゲイラのサンビスタと交流し、カルトーラとの共作も残しているほどで、
伝統サンバを音楽性の芯に持っている人です。
その後、ヴィラ・イザベルのサンバ作家として長く裏方で活躍し、
パゴージ・ブームの時代になって、ようやくソロ・デビューしましたけれど、
クラウジオのサンバはパゴージではなく、伝統サンバなのにポップという、
いそうでいない稀有な才能の持ち主でした。

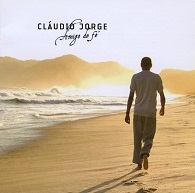
ソロ・アーティストとしては寡作の人ですけれど、01年の“COISA DE CHEFE”、
07年の“AMIGO DE FÉ” ともに、伝統サンバと洗練されたMPBのサウンド・センスを
あわせ持ったクラウジオの個性を存分に発揮した傑作で、ずいぶんと愛聴したものです。
そんなクラウジオが70歳を迎えるにあたって制作した新作は、
サンバ・ジャズを謳ったアルバム。
どんな趣向なのかと思えば、バックがスルドやパンデイロなどのパーカッション隊ではなく、
ドラムスとベースのリズム・セクションを中心に、ギターやサックスなどが、
ジャズぽいソロをとるというプロダクションなのですね。
といっても、取り立ててジャズ色が強い印象はなく、
楽曲は伝統サンバそのものだったり、爽やかなMPBだったりで、
いつものクラウジオらしい作風を湛えた仕上がりとなっています。
アタバーキ1台をバックに歌い、途中ギターやフルートなどが絡むという、
バイーアふうサンバもありますよ。
ドラムスに、長年の盟友である名ドラマー、
ウィルソン・ダス・ネヴィスも参加しているほか、
モナルコの息子マウロ・ジニースがゲストで1曲、クラウジオと一緒に歌っています。
からっと明るいクラウジオのヴォーカルも、とびっきりの爽やかさで、
いくつになってもフレッシュさを失わないクラウジオらしいサンバを堪能できます。
Cláudio Jorge "SAMBA JAZZ, DE RAIZ" Mills MIL063 (2019)
Cláudio Jorge "COISA DE CHEFE" Carioca 270.012 (2001)
Cláudio Jorge "AMIGO DE FÉ" Carioca/Zambo CD0008 (2007)
2019-09-02 00:00
コメント(2)




