ペルナンブーコのヴァイオリン弾き父子 マシエル・サルー、メストリ・サルスチアーノ [ブラジル]

裸電球が照らす、ペンキのはげ落ちた壁。
バイリ(ダンス・パーティ)がはねたあとなのか、
誰もいなくなり、虫の音しか聞こえない夜更けに、
ラベッカを弾く男がひとりと、外で踊る女がひとり。
たまんないなぁ、この写真。
場所はペルナンブーコの田舎町の集会場でしょうか。
屋根の瓦の下に、どでかいスピーカーが付いていて、
この前に大勢の人々が集まって、踊っていたんでしょうねえ。
ノルデスチのヴァイオリン、ラベッカ奏者マシエル・サルーの新作です。
6年前の前作は、ホーン・セクションや女性コーラスまでフィーチャーして、
華やかにしすぎたサウンドに、ちょっと違和感を感じて手放しちゃいました。
ロック・ファンには、ラベッカがぎこぎこ鳴って、
太鼓がどんどん叩かれるノルデスチの伝統色濃いダンス・サウンドより、
「いなたいマンギ・ビート」ぐらいのサウンドの方が、ウケがいいんだろうけど。
で、今作はどんなものかと心配したんですが、
ジャケットどおり、シブい伝統回帰のアルバムとなりました。
ノルデスチ音楽好きには、こういう土埃舞うサウンドの方が、断然いいですよね。
朴訥としたマシエル・サルーの歌い口もちょっと渋くて、いい感じ。


デビュー作や2作目で聞かれた、
マラカトゥやコーコをベースとしたノルデスチのフォークロアを、
ロックを通過した世代のセンスでやるサウンドには、
マシエルの父親であるメストリ・サルスチアーノ世代の
オーセンティックな伝統サウンドとは明らかに違うグルーヴ感がありました。

楽器編成の面でも、せいぜいエレクトリック・ギターやベースを数曲使う程度。
ほぼ伝統的なサウンドなのに、メストリ・サルスチアーノのアルバムと
聴き比べてみると、その感覚の差は歴然です。
世代が変わり、伝統が時代とともに移ろっていく姿が聴き取れますよね。
古い世代には重厚さが、新しい世代には軽妙な身のこなしがあって、
新旧世代それぞれの味わいが味わえます。
Maciel Salú "BAILE DE RABECA" Maciel Salú MS0004 (2016)
Maciel Salú e O Terno Do Terreiro "A PISADA É ASSIM" Marca Registrada MR0983 (2004)
Maciel Salú e O Terno Do Terreiro "NA LUZ DO CARBURETO" Chesf no number (2006)
Mestre Salustiano "SONHO DA RABECA" Cristiano Lins Produções TOP015 (1998)
2017-05-31 00:00
コメント(0)
アフリカン・スタイリッシュなクールネス ジェドゥ=ブレイ・アンボリー [西アフリカ]
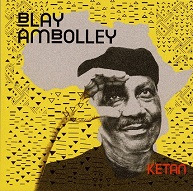
ファンキー・ハイライフのヴェテラン、ジェドゥ=ブレイ・アンボリーの新作。
12年の“SEKUNDE” 以来、5年ぶりのアルバムですね。
前作が出たのと時同じくして、ジェドゥのデビュー作で、
ファンキー・ハイライフの代表的な名盤“SIMIGWA” もCD化されたんだけど、
覚えてる人、どれくらいいるかなあ。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2013-04-18
あの時、ジェドゥ再評価のまたとないチャンスだと思って、
“SEKUNDE” のレヴューをミュージック・マガジンに書いたんですけど、
まったく話題にもならず、CDもほとんど日本に入らなかったしねえ。
もちろん日本盤なんて、出ずじまい(しおしお)。
というわけで、今回の新作は日本盤が出ると聞いて、嬉しかったですよ。
エボ・テイラーやパット・トーマスの活躍によって、
やっとジェドゥにも注目されるようになったんですね。
ストラットによって再評価されたエボやパットと違い、
西洋人が制作に関わっていないジェドゥのアルバムは、
前作同様、ガーナ録音、ジェドゥ自身による作編曲・プロデュースです。
前作はオランダのレーベルでしたけれど、今回はドイツのレーベルからのリリース。
ミックスに、前作オランダのレーベルのスタジオを使っているので、
両レーベルは関係があるのかも。
西洋人絡みの制作でないゆえ、インターナショナル向けの余計な装飾がなくて、
好感持てますよ。クレジットを見ると、ミュージシャンは全員ガーナ人のようですけど、
演奏力は高く、これなら西洋人の手を借りる必要なんて、まったくないですね。
たまたま一緒に聴いていたウム・サンガレの新作が、
西洋人向けのアンビエントな音響を装飾しまくっていて、まあジャマくさいというか。
余計な音響を、脳内リミックスで引き算しながら聴いてたんですけど、
ジェドゥの本作を聴いたら、そんなメンドくさいことしなきゃならないアルバムなんか、
わざわざ聴く必要ないじゃんという気分になっちゃいました。
で、このジェドゥの新作。
ファンキー・ハイライフの人なんですが、前作同様、アフロビート色が強いです。
オープニングの“Afrika Yie”、8曲目の“I Don't Know Why”、
ラストの“I Get Myself To Blame” なんて、まんまアフロビート。
ほかのアフロ・ファンクなトラックでも、アフロビートなニュアンスを強く感じさせます。
それはバンドが弾き出すサウンドばかりでなく、
フェラ・クティの歌い口を強く思わすジェドゥの歌いっぷりのせいでもありますね。
いやあ、かっこいいですよ、ジェドゥの歌いぶり、クールです。
アフリカン・スタイリッシュと言いたくなりますね。
そして、“Teacher” という曲の作詞は、なんとフェラ・クティとクレジットされています。
曲のタイトルから、“Teacher Don't Teach Me Nonsense” かと思ったら違う曲で、
作曲はジェドゥによるもの。ジェドゥはフェラとも親交があったんですね。
ジャジーなアフロ・ファンクでジャムバンドふうの演奏があったり、
スティールドラムのサンプルを使ったポップなライト・ファンク調ありと、
聴きどころも多彩で、タイトル曲はラテン・タッチのイントロで始まるアフロ・ラテン調。
といっても、そのリズムは、クラーベというよりベル・パターンぽく、
ほかでもベル・パターンのリズムがはっきり聴き取れるところが、ガーナらしいですね。
むしろ印象的なのは、典型的なハイライフのメロディがまったく出てこないことで、
その意味では、ハイライフ色のないアフロ・ファンク・アルバムとなった新作なのでした。
Gyedu Blay Ambolley "KETAN" Agogo AR087CD (2017)
2017-05-29 00:00
コメント(2)
43年の眠りを解かれたアフリカン・ポップスの至宝 ザイール74 [中部アフリカ]

世紀のタッグ・マッチの前夜祭として開かれた、音楽祭「ザイール74」の録音。
アリが勝利したタッグ・マッチは、
「キンシャサの奇跡」として伝説となりましたけれど、
音楽祭の方は、「ブラック・ウッドストック」の呼び名がついたものの、
映画化もレコード化もされず、人々の記憶から消え去ってしまいました。
それが再び注目を浴びるようになったのは、
30年以上もの間未発表となっていた125時間にも及ぶフィルムを、
新たに編集して制作された映画『ソウル・パワー』の公開がきっかけ。
主役級のジェイムズ・ブラウンに劣らぬ
タブー・レイやフランコのカッコよさに、ノケぞりましたよね。
「ザイール74」は、キンシャサの5月20日スタジアムで、
74年9月22日から24日までの3日間行われた巨大イヴェント。
アメリカからは、ジェイムズ・ブラウン、スピナーズ、B・B・キング、
ビル・ウィザーズ、クルセイダーズ、シスター・スレッジ、
セリア・クルース、ファニア・オール・スターズほかが出演しました。
対するアフリカ勢はというと、当時ギネアにいたミリアム・マケーバに、
地元ザイールの大スターが勢ぞろい。
今回CD2枚組に復刻されたのはそのアフリカ勢で、
タブー・レイ・ロシュロー&アフリザ・アンテルナシオナル、アベティ、
フランコ&TPOKジャズ、ミリアム・マケーバ、オルケストル・ストゥーカス、
ペンベ・ダンス・トゥループのパフォーマンスが詰まっています。
「74年」という、ルンバ・コンゴレーズ黄金期ど真ん中の年に、
タブー・レイやフランコに、ストゥーカスまでもが出演した
フェスティヴァルがあった事実だけでも、奇跡みたいですが、
加えて、当時最新鋭の16トラックのマルチ・トラック・レコーダーに記録されたのだから、
これはもうまさに、超絶・画期的な出来事だったわけです。
74年当時のザイールでは、テレビ映像などのライヴ録音がDVD化されているものの、
音質なんて推して知るべしのシロモノ。
いちおう「動く○○○○」が観られる、というレヴェルにすぎません。
レコードにいたっては、観客の拍手をオーヴァーダブした疑似ライヴしかなく、
ホンモノのライヴ録音なんて、まだありませんでした。
ゆいいつ、70年にパリのオランピアで録られたロシュローのライヴ盤があるとはいえ、
あの時代に、16トラックのマルチなんてものは存在しません。
というわけで、この2枚組聴いたら、
そのハイ・クオリティな音質にドギモ抜かれますよ。
2017年最高の話題作となること必至のこのアルバム、
日本盤解説を書きました。明日28日発売です。
V.A. 「ザイール74~ジ・アフリカン・アーティスツ」 ライス WRR-3226
2017-05-27 00:00
コメント(2)
正調アラブ歌謡の神星 ヒバ・タワジ [中東・マグレブ]

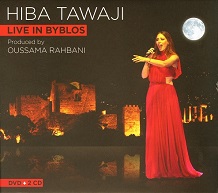
ジュリア・ブトロスと一緒に、ヒバ・タワジの新作も入ってきましたよ。
ひとつ前の旧作で、DVD付の2枚組ライヴ盤も同時入荷という、
これまたジュリア・ブトロスとまったく同じなんだから、奇遇じゃありませんか。
いやあ、それにしても、ヒバ・タワジの前作“YA HABIBI” は評判になりましたねえ。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-11-29
「ミュージック・マガジン」誌で、2015年ワールド・ミュージック部門の
ベスト・アルバム7位に選ばれたし、
ぼくの記事から1年半もかかったとはいえ、
『ヤ・ハビビ~ベイルートの若き宝石』のタイトルで、日本盤も出ましたからね。
ぼくがこれは素晴らしい作品だと思って、ここでいくら力説したとて、輸入もされず、
ましてや日本盤などリリースされることなどないアルバムがほとんどなので、
ヒバ・タワジが評価されたのは、本当に嬉しかったですよ。
さて、そのレバノン期待の若手女性シンガー、ヒバ・タワジの新作であります。
タイトルは、30歳を迎えたことを記念したもので、あわせて、
2枚のディスクに計30曲を収録したことも、ひっかけているんですね。
ジュリアの伴奏がプラハ市交響楽団ならば、
ヒバの方は、前作同様、ウクライナ国立管弦楽団とレバノン管弦楽団という布陣。
プロデュースも、これまた前作同様ウサマ・ラハバーニなのだから、
聴く前から保証付き!てなものですが、期待にたがわず、大力作に仕上がっています。
ウサマ・ラハバーニが作曲したミュージカルの歌曲を中心に歌っていますが、
前作のようなオペレッタ風の作品ではなく、
ディズニーの曲や、R&Bやフラメンコなどのテイストを加えた現代性も加味する一方、
サイード・ダルウィッシュの曲を取り上げるなど、アラブ古典にも目配りしています。
プロダクションは絶品というほかない、言葉を失う素晴らしさです。
現在のアラブ世界で、これ以上ない絢爛豪華な伴奏にのせて、
ヒバも見事な歌唱力で、それに応えています。
前作のイキオイ先行な熱唱ぶりも、だいぶ抑えられるようになりましたね。
ディスク2の4曲目“Bkhatrak” では、たおやかな歌いぶりを聞かせるなど、
前作にはなかった軽みもみせてくれていますよ。
ライヴ盤では、ロック・スターばりのカッコつけまくった登場で、
前に観たばかりの、微動だに歌うジュリア・ブトロスとは大違い。
ダンサーも従えて、ポップ・スターらしく振舞っています。
衣装替えのあとは、前作のレパートリーを中心に、
正調アラブ歌謡ど真ん中といったドラマティックなバラードを歌います。
ムハンマド・アブドゥル・ワハーブの曲では、
ウム・クルスームが歌う古いフィルムを投影するという演出をみせるかと思えば、
一転、ビヨンセの“Crazy In Love” もカヴァーしたりして。
アンコールでは、強力な歌唱力をどうだ!といわんばかりの歌いぶりで、
ああ、まだ若いんだなあと感じますけど、若くて実力のあるシンガーは、
こういう過剰なところを一度経ないと、円熟できないんだろうなあ。
ホイットニー・ヒューストンやマライア・キャリーが出てきたころを思わせる
ヒバ・タワジは、アラブ世界だけでなく、西洋のリスナーにもアピールする大器です。
今後さらにスケールの大きな歌手となっていく予感がありますよ。
Hiba Tawaji "30" Oussama Rahbani Productions no number (2017)
[CD+DVD] Hiba Tawaji "LIVE IN BYBLOS" Oussama Rahbani Productions no number (2015)
2017-05-25 00:00
コメント(4)
大歌手然としていない大歌手 ジュリア・ブトロス [中東・マグレブ]


やっぱり、レバノンのジュリア・ブトロス、素晴らしいです。
最初は新作を聴いて、今回は記事を書くのをやめようと思っていたんです。
なんだか、だんだんご立派になっていく感じの歌いぶりに、
共感しづらくなってきたんですね。
今回もプラハ市交響楽団を伴奏に、プロダクションは完璧。
昔からのジュリアの魅力である、エレガントな曲もあるものの、
一方で、いかにも大歌手然とした、威圧的に歌う曲もあって、
おそらくレバノンへの祖国愛を歌ったものなんだろうなあと想像はしても、
その事情を理解していない異邦人には、
感情移入がしにくいものであることは、素直に認めざるを得ません。
反イスラエルを鮮明に打ち出していたジュリアの政治的姿勢が、
彼女の歌いぶりに与える懸念について、
以前「あでやかさを損なう政治的な正しさ」という記事に書きましたけれど、
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-04-07
いまだその懸念は拭えないままとなっています。
前作“HKAYET WATAN” の前にリリースされていた13年のライヴ盤を聴いても、
すっかり大歌手になったなあと思うと同時に、
力をこめて歌わなければならないような楽曲が増えたことに、
自分との距離が遠くなったのを覚えました。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-01-26
ところが、このライヴのCDを聴いたあと、DVDを観たら、がらっと印象が変わりました。
まず、ジュリア・ブトロスが、ちっとも大歌手ぽくないんですよ。
オーラがない、といっては失礼にあたるかもしれませんが、
近所のお姉さんが歌っているふうの風情は、正直、意外でした。
ジュリアは、コンサートの最初から最後まで、
中央のメイン・マイクの前に立って、ただ歌うだけ。
身体を揺することすらなく、にこにこと笑みを浮かべながら歌い続けます。
その笑顔は実にチャーミングで、とても親しみを感じさせるもの。
フェイルーズのような人を寄せ付けない高貴さとは真逆の、
ほんとにどこにでもいそうな、「隣のおねえさん」です。
オーケストラピットには、バンド・メンバーにプラハ交響楽団の面々、
20人近いバック・コーラスが勢揃いしています。
あまりにフツーの、フツーすぎるジュリアの雰囲気に引きこまれ、
声を張って強く歌う威勢のいい曲も、威圧感がないことに気づきました。
ジュリアの06年傑作“TA’AWADNA ALEIK… HABIBI” に収録されていた
代表曲“Habibi” を歌い終えたあと、感情の高ぶりを抑えられず、
わずかにこぼれた涙を、すっと拭うジュリアの所作に、グッときましたねえ。
そのあとに続いた“Atfal(蛍の光)” も、CDで聴いてたぶんには、
それほどピンとこなかったんですけど、とても感動的なものでした。
フィナーレにちょっとした愛国的な演出があるものの、
歌を聞かせることだけに徹し、演出を排したプログラムで、
終盤に観客が総立ちとなるのも、政治集会のような熱狂とは違う、
ジュリアの歌に共鳴するごく自然なものと受け止められ、
とてもすがすがしく感じられました。
レバノンの人々から愛されるそのライヴの様子を見てから、
あらためて新作を聴き直すと、聞こえ方がぜんぜん違ってくるから不思議です。
で、冒頭の、やっぱり……に続くわけなんですね。
最後に、上に挙げたライヴ盤ジャケットの写真は、スリップケース内の本体のものです。
スリップケースは銀色の光沢紙のため、スキャンすると真っ黒にツブれてしまうので、
本体のジャケット写真を載せました。念のため。
Julia Boutros "ANA MEEN" Longwing no number (2016)
[CD+DVD] Julia Boutros "LIVE AT PLATEA" Longwing no number (2013)
2017-05-23 00:00
コメント(0)
南部ヴェトナムのほのかな郷愁 ハー・ヴァン [東南アジア]

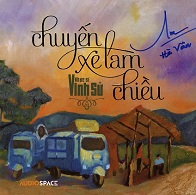
ノスタルジックな南ヴェトナム懐メロ集でデビューしたハー・ヴァン。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2015-12-14
83年生まれの33歳という若さながら、
ヴェトナムのアダルト向けポップスのトレンドとなった、
ボレーロ(ヴェトナム戦争前の抒情歌謡)を歌う歌手です。
レー・クエンのようなドラマティックな濃い口の歌手ではなく、
中庸の極みといってもいい、クセのない歌唱は、
リスナーを選ばず、万人に愛される人じゃないでしょうか。
ひらひらと軽やかに舞うコブシは、コブシを回していることすら意識させないほど自然で、
技巧を感じさせないそのさりげなさが、この人の持ち味といえます。
たおやかなバラード表現は、ハ・ヴィにも並ぶ実力を感じさせ、
ヴェトナム南部の情歌を歌うのに、これほどふさわしい人もいないんじゃないかな。
そのハー・ヴァンの新作が、昨年秋に2作同時でリリースされました。
“XIN TRẢ TÔI VỀ” と“CHUYẾN XE LAM CHIỀU” で、
後者は、ヴィン・スという44年サイゴン(現ホーチミン)生まれの作曲家の曲集です。
ヴィン・スは現在、癌の闘病中で、車椅子の生活を送り、相当弱っているものの、
自分のソングブックが制作されると聞き奮起し、
本作のミュージック・ヴィデオにも出演したのだそうです。
どちらも、デビュー作ほど懐古調を強調しておらず、
ヴェトナムの伝統的な弦や笛の響きも織り込んで、
民歌調でもなければ、懐古調でもない、中庸なサウンドに仕上げています。
こうしたいっさいの演出を排したハー・ヴァンの歌とサウンドの世界を、
「アジアの “歌謡曲” の一つの理想の境地」と評した原田尊志さんに、
ぼくも全面賛成です。
ハー・ヴァンのアルバムは、フィジカルではこの3作しか出ていませんが、
配信のみのデジタル・アルバムを5作
(うち1作はヴー・コック・ヴェトとのデュオ作)出していて、
昨年記事にしたアメリカ盤は、この配信曲から編集したものということが判明しました。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-11-28
デジタル・アルバムもとてもいい内容なので、フィジカル化してほしいなあ。
Hà Vân "XIN TRẢ TÔI VỀ" Audio Space no number (2016)
Hà Vân "CHUYẾN XE LAM CHIỀU : NHẠC SĨ VINH SỬ" Audio Space no number (2016)
2017-05-21 00:00
コメント(0)
ジャーネットのトゥアレグ ナビル・バリ・オスマニ [中東・マグレブ]
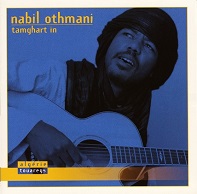
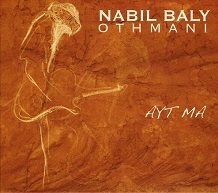
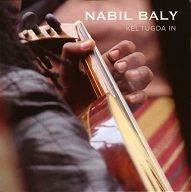

ナビル・バリは85年、アルジェリア南東部のオアシスの町
ジャーネットのトゥアレグの音楽一家に生まれたシンガー。
父親のバリ・オスマニ(1953-2005)はウードの名手で、
詩人としても名高い歌手でした。
13歳でギターを弾き始めたナビルは、
父のバンドでダルブッカを叩いて修行を積んだようです。
ナビルの10年デビュー作“TAMGHART IN” では、
父の曲や父と共作した曲も多く取り上げていましたね。
そして祖母のハジャ・オスマニは、
女性が歌う祝祭歌ティンデの歌い手として尊敬されており、
先のデビュー作では、ハジャの曲も1曲取り上げていました。
その曲“La Helle” では、ハジャをフィーチャーし、
タマシェク語でタルリリットと呼ばれる、
トゥアレグ女性が鳴らす激烈なウルレーションを披露していました。
ナビルはエレクトリックとアクースティック両刀使いのギターに、
ウードやベースもこなしながら、トゥアレグの伝統音楽からデザート・ブルース、
シャアビやレゲエなども取り入れています。
伝統音楽からポップまで、無理なく消化した柔軟な音楽性は、
デビュー作当時から際立っていました。
デザート・ブルース一辺倒ではない才能に、注目してきましたが、
新作の“AMGHAR IN” にも、そんなナビルらしい音楽性が発揮されています。
フランス語で歌ったレゲエも抵抗感なく聞けるし、
むしろナビルの柔軟な音楽性が発揮されて、いい仕上がりです。
ラストの“Eduna Tigla” のポップなセンスにも、ウナらされました。
転調する曲づくりなど、
これまでのトゥアレグ人ミュージシャンになかった個性を感じさせます。
一方、前作のライヴ盤“KEL TUGDA IN” では、ナビルが弾くウードに、
太鼓と女性コーラスたちの手拍子のみというシンプルな編成で歌っていて、
伝統的なトゥアレグのメロディがシャアビ化した味わいを醸し出しています。
オーセンティックとモダンのどちらも行ける、奥行きのある才能の持ち主です。
Nabil Othmani "TAMGHART IN" Reaktion RE16 (2010)
Nabil Baly Othmani "AYT MA" Nabil Baly Othmani no number (2012)
Nabil Baly "KEL TUGDA IN" Nabil Baly Othmani no number (2015)
Nabil Baly "AMGHAR IN" Ezlan/Reaktion EZ001/1 (2016)
2017-05-19 00:00
コメント(0)
若者の元に帰ってきたジャズ ジェフ・パーカー [北アメリカ]

トータスのギタリスト、ジェフ・パーカーが来日中。
5月中にトータスとスコット・アメンドラ・バンドのステージ含む
14公演が予定されているようなんですが、
残念ながら、自身のグループでの公演はないもよう。
ジェフ・パーカーを、ポスト・ロックのギタリストではなく、
シカゴAACMのジャズ・ギタリストとして認識してきた自分にとっては、
ちょっと残念なんですけど、渋谷のタワーレコードでミニ・ライヴをやるというので、
喜び勇んで観に行きました。
なんせ昨年出たジェフ・パーカーのソロ・アルバムは、
シカゴ音響派の面目躍如たる、痛快な仕上がりとなっていましたからねえ。
浮遊感のあるギターとサックスが、フリーキーにプレイすると
緩くひしゃげたサウンドスケープが、オーガニックな清涼感を醸し出し、
ネオ・ソウルにも通じるレイドバックなムードを溢れ出すところは、なんとも魅力的でした。
J・ディラの影響あらたかな、ヨレたビートを打ち出す
ジャマイア・ウィリアムスのドラミングは、新時代のジャズを映しているし、
同時にゆるいファンク風味やネオ・ソウルな趣味も感じさせ、
白昼夢を見るかのような、ラウンジーなオルガンの響きや、
ヒップ・ホップを経由したロウなビート・ミュージックの質感をあわせ持っていたりと、
多様な音楽が複雑に交差する妖しさと心地よさが、ないまぜとなっていました。
ミニ・ライヴ前の公開インタヴューで、
ジャズ評論家の柳樂光隆さんから「影響を受けたミュージシャンは」と訊ねられると、
レニー・トリスターノ、ジョー・パス、グラント・グリーン、デレク・ベイリー、
高柳昌行なんて名前が出てきて、それぞれになるほどと、うなずくものがありました。
ノイズ・ミュージックをやっていたソロ・アルバムもあったもんなあ。
でも、今作はまったく趣向が違っていて、
J・ディラやQ=ティップなどのヒップ・ホップからの影響を表出した、
テン年代らしいジャズとなったわけですね。
ジェフのようなマイナーなアーティストのソロ作が日本盤で出るのも驚きですけど、
それが話題となって、インストア・ライヴに若者が長蛇の列をなすんだから、
時代は変わったよねえ。
ほんとに今、ジャズが来てるんだなあという実感を強くしました。
ワールド系のライヴだと、ぼくと同年代の中高年ばっかで、若人の影が薄いんですが、
音楽を真剣に求める若者の熱気に、なんか感無量になっちゃいましたよ。
若者が夢中になってこそ、ポピュラー音楽。
中高年マニアの愛玩物だけになるようじゃ、ダメだよね。
Jeff Parker "THE NEW BREED" Inernational Anthem Recording Co. IARC0009 (2016)
2017-05-17 00:00
コメント(0)
クレズマー・ミーツ・ジンタ フランク・ロンドン [北アメリカ]
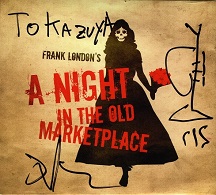

クレズマー・リヴァイヴァルの立役者フランク・ロンドンが来日し、
日本のちんどん・クレズマー楽団、ジンタらムータと共演するという絶好の企画。
ゲストには、ベツニ・ナンモ・クレズマーの時代から、現在のこまっちゃクレズマまで、
日本のクレズマー草分けとして音楽活動をしてきた
梅津和時と巻上公一の二人が顔を揃えるほか、チューバの関島岳郎、
トロンボーンの中尾勘二も参加するという最強の布陣で、役者、揃いすぎ。
これは見逃すわけにはいかないでしょう。
週末金曜日の5月12日、ちゃっちゃと仕事を片づけ、
会社を定時に出て、行ってきましたよ、秋葉原CLUB GOODMAN。
フランク・ロンドンといえば、忘れられないのがクレズマティックスのデビュー作。
あれは、衝撃的でした。
まだクレズマーを聴き始めて間もなく、ヴィンテージ録音を勉強中だったところに、
いきなり飛び出したクレズマティックスのラディカルなサウンドは、
単なるリヴァイヴァルを超えた強度がありました。
クレズマティックスでの活動ばかりでなく、さまざまなユニットやプロジェクトでの
旺盛な演奏活動によるジャンル横断と越境の旅こそが、
クレズマーの復興にどとまらない、フランク・ロンドンの活動の真骨頂でした。
今回の<クレズマー・ミーツ・ジンタ>も、そのひとつに数えられますね。
いやー、痛快な2時間半でした。
1部こそ、伝統的なクレズマー曲を中心に、
オーソドックスなクレズマーを演奏していましたけれど、
2部にゲストを迎えてからが、ハジけたねえ。
クレズマーばかりでなく、スウィング・ジャズあり、エチオピアあり、美空ひばりあり。
「悲しき口笛」「お祭りマンボ」までは、そんなに意外でもなかったけど、
フランクが発見した日本のクレズマー曲という前振りに始まった「魔法使いサリー」は、
新発見でありました。なるほど、確かにコーラスのところなんて、ユダヤ民謡ぽいかも。

レパートリーも楽しかったけれど、
そこで繰り広げられる一人ひとりのパフォーマンスが、スゴかったですよ。
フランクのトランペットの出音の大きさといったら。
梅津さんのアルトの音といい勝負で、やっぱ一流のプレイヤーは、みんな出音がデカイ。
フランクはメンバーにどんどん指示を出してソロを回したり、
一方、メンバーはソロで自由に遊んでみせていました。
リードだけで吹いてみたり、おもちゃの楽器を鳴らしたり、
ヴォイス・パフォーマンスをしたりと、役者揃いのメンバーが引き出しを、
まあ、開けること、開けること。
最後は大団円で、感無量といった大熊ワタルのMCが、その夜を象徴していました。
Frank London "A NIGHT IN THE OLD MARKETPLACE" Soundbrush SR1010 (2007)
Frank London's Klezmer Brass Allstars "DI SHIKERE KAPELYE" Piranha CDPIR1467 (2000)
2017-05-15 00:00
コメント(0)
超絶ストレンジなシャーデー・カヴァー・アルバム ザ・レヴェリーズ [北アメリカ]
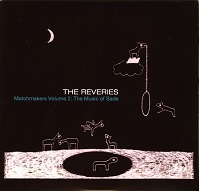
3年前に偶然知った、カナダのライアン・ドライヴァー。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-08-13
そのユニークな音楽性に惹きつけられていたものの、
どういう人なのかよくわからないままでいたところ、
トロントのインディ・シーンを取り上げた「ミュージック・マガジン」の4月号の特集で、
ライアン・ドライヴァーとその周辺について、ようやく知識を得ることができました。
特集記事の推薦CD19枚の中には、
件のライアン・ドライヴァー・クインテットの
“PLAYS THE STEPHEN PARKINSON SONGBOOK” も選盤されています。
ほかにはどんなアルバムがあるのかなと、いろいろチェックしてみたところ、
引っかかったのが、ライアン・ドライヴァーがメンバーとなっているユニット、
ザ・レヴェリーズの本作。
ザ・レヴェリーズは、カヴァー・プロジェクトを目的とするユニットで、
メンバーはライアン・ドライヴァーに、
シンガー・ソングライターでギタリストのエリック・シュノー、
前衛ジャズのマルチ・プレイヤー、ダグ・ティエリ、ドラマーのジーン・マーティンの4人。
07年にウィリー・ネルソンをカヴァーした1作目を出し、
続いて出した2作目が、12年リリースのシャーデー・カヴァー集なんですが……。
とんでもないね、このカヴァー・アルバム。
ベロベロに酔っ払ったおっさんが、シャーデーの曲を鼻歌で歌ってるみたいな素っ頓狂さ。
聴いてると、ニヤニヤ笑いが止まらず、思わず吹き出したりの連続。
CD聴きながら、こんなに笑ったのって、後にも先にもこれが初めてじゃないかな。
ぶつぶつとつぶやくように歌うさまは、泥酔状態を通り越して、
昏睡一歩手前のアブナさも、ぷんぷんと匂ってくるようじゃないですか。
オープニングの“No Ordinary Love” からラストの“Kiss Of Life” まで、
そんな調子でタガが緩みまくった、うわごとのような歌が続き、
バックでは、エフェクトがノイズをまき散らしたり、
マウス・スピーカーで奇声を出したりと、
いやあ、こんなストレンジな音楽聴いたことない!
前衛音楽というと、難解なもの、怖いもの、意味不明なもの、自意識過剰なもの
というイメージがつきまといますけど、そのいずれからも遠いことに、心底感心しました。
無意識過剰とも思える、よじれまくった歌いぶりや、
スカスカのアンサンブルの脱力ぶりは、
アウトサイダー・アートをホウフツさせるじゃないですか。
気取りがなく、ほのぼのとしていて、気安い親しみに溢れながら、
どこか不穏なほの暗さが、通奏低音のように流れるアヴァンなフォーク・ジャズ。
「ヤバい」というボキャブラリーが、これほど似合うアルバムもありません。
“LOVE DELUXE” を生涯の愛聴盤とするシャーデー・ファンのぼくも、
脱帽もののカヴァー・アルバムです。
The Reveries "MATCHMAKERS VOLUME 2 : THE MUSIC OF SADE" Barnyard BR0327 (2012)
2017-05-13 00:00
コメント(0)
ライヴ・エレクトロニクスのジャズ マーク・ド・クライヴ=ロウ [北アメリカ]
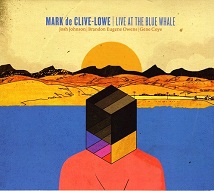

クラブ・ジャズのセンスを、ジャズの即興演奏の中に生かせる才人。
前作“CHURCH” を聴いて、マーク・ド・クライヴ=ロウをそう認識したのは、
間違いじゃなかったですね。
インプロヴァイザーであり、プロデューサーであるという資質を
鮮やかに示して見せたのが前作とすれば、
新作ライヴは、ジャズ・プロパーであることを明らかにして、
インプロヴァイザーの才能を発揮した快作となりました。
マーク・ド・クライヴ=ロウは、
ウエスト・ロンドンのブロークン・ビーツのパイオニアという触れ込みだったので、
前作で初めてこの人を聞いた時は、ちょっとびっくりしたんですよ。
豊富な音楽のボキャブラリーは、クラブ・ジャズで鍛えられたからでしょうけれど、
単なるビートメイカーとして機能させた音楽ではなく、生演奏の比重が高いというより、
全編、生演奏そのもの。エレクトロだって即興してるんだから、
これをジャズと呼ばずに何といおうって感じ。
これまでにも、ジャジー・ヒップ・ホップ界隈で、
打ち込みの上物として生演奏をするなんてのはよくありましたけれど、
あれって、やっぱり発想はフュージョン的というか、
ジャズの即興とは別種のサウンド・クリエイティヴィティですよね。
だからクラブ・ジャズって、ジャズとは名ばかりの本質はフュージョンで、
イージー・リスニングとも親和性のあるダンス・ミュージックだと思ってます。
ところが、“CHURCH” でマークが示したのは、
そんな上モノと打ち込みの関係ではなく、
その場でサンプリングやループをして、演奏者とともに即興するという、
まさしく新世代のジャズとなっていたのでした。
そして、新作は管一人のカルテット編成で、マークはピアノ、キーボード、
ライヴ・エレクトロニクスとクレジットされています。
なんとサン・ラとアーマッド・ジャマルのカヴァーもやっていて、
これがまた聴きものなんですが、
惜しむらくは収録時間わずか28分弱と、やたら短いこと。EPか。
特にラストのアーマッド・ジャマルの“Swahililand” は、
演奏がグルーヴし始める3分すぎで、あえなくフェイド・アウト。
えぇ~! なんでここで終わるの!!
信じらんない、すっごくいい感じで始まったばかりなのに!!!
完奏を収録しないとは、許せん。来日してこの続きを聞かせてください~。
Mark De Clive-Lowe "LIVE AT THE BLUE WHALE" Mashibeats/Ropeadope MB004 (2017)
Mark De Clive-Lowe "CHURCH" Mashibeats/Ropeadope MB001 (2014)
2017-05-11 00:00
コメント(0)
インプロ志向のUKジャズ・3ピース・バンド プレストン=グラスゴウ=ロウ [ブリテン諸島]

デヴィッド・ギルモアの新作と交替だな、こりゃ。
ロンドンからすごいジャズ・ギタリストが出てきましたよ。
その名はデヴィッド・プレストン。
ベーシストのケヴィン・グラスゴウ、ドラマーのローリー・ロウによる
3ピース・バンドで、姓名を繋げたシンプルなバンド名を名乗っています。
オープニングから、圧倒的なテクニックでトリッキーなプレイを聞かせて、圧巻。
うっわー、スゲー。
カート・ローゼンウィンケルみたいな高速ピッキングに舌を巻いていたら、
パット・メセナーみたいなメロディ・ノートをくっきりと残すソロを披露したり、
アラン・ホールズワースを思わすオルタネイト・ピッキングのトーンを聞かせたりと、
何通りのギター・スタイルを持っているんだか。
めちゃくちゃテクニカルなプレイの連続に、
いやー、若さっていいよねえ、ギラギラしててと、おじさん、嬉しくなっちゃいました。
サウンド志向の淡泊な表現が主流になりつつある新世代ジャズで、
こういうインプロ志向のバンドって、これからは希少になるのかもしれないけど、
やっぱりジャズの醍醐味は、インプロよ。
ギターのことばっかり書いてしまいましたけれど、
ケヴィン・グラスゴウの6弦ベースもすごい。
デヴィッドのギターに絡んでくるフレージングにひらめきを感じます。トーンもいいね。
ローリー・ロウのドラミングは、柔軟でしなやか。
手数が多いのに、たっぷりとした重量感もあって、
長いソロもよく歌う、いいドラマーです。
3人の緊密なプレイはエネルギッシュそのものなんだけど、
同時にクールな佇まいを感じさせるところが、現代性でしょうか。
サウンドにはポスト・ロック的な快感もあります。
聞くところによると、去年の10月に来日してたそうで、うわー、観たかったなあ。
あいかわらずライヴ情報に疎い自分に嫌気がさすけど、
また来てくれるよね。待ってまーす。
Preston - Glasgow - Lowe "PRESTON - GLASGOW - LOWE" Whirlwind Recordings WR4686 (2016)
2017-05-09 00:00
コメント(2)
フェイルーズの伝記映画 [中東・マグレブ]

え? フェイルーズの伝記映画? そんなものがあるの?
98年にフランスで公開された映画だそうで、ぜんぜん知りませんでしたねえ。
監督はフレデリック・ミッテラン。
ミッテラン元大統領の甥で、現在は自身も政治家になった人ですね。
05年にフランスでDVD化されていたことが、あとになって調べてわかりました。
今回ぼくが入手したのは、07年にEMIミュージック・アラビアが出したUAE盤DVD。
フランス盤DVDはPALなので、日本の通常のプレイヤーでは観れませんが、
UAE盤はNTSCのオール・リージョンなので、オッケーです。
それにしても、フェイルーズの伝記物語だなんて、
評判になったってよさそうなものだけど、
そんな映画があったなんて、話題にのぼったこともなかったですよねえ。
フェイルーズにちなんだ映画といえば、
『愛しきベイルート アラブの歌姫』が日本でも公開されましたけど、
あの映画は、フェイルーズを愛したベイルートの人々の物語で、
フェイルーズ本人はぜんぜん登場せず、あてが外れてしまって、
すごくがっかりしたのを覚えています。
確か、最後に、コンサート・シーンがちょっと出てくるだけだったよねえ。
フェイルーズ・ファンとしては、大いに不満が残るものだったので、
このDVDをカタログで見つけた時も、あの映画かと思ったんですけれど、
あちらは03年のオランダ映画なので、別物とわかってオーダーしたんでした。
いやあ、びっくりしました。
のっけからフェイルーズ本人が登場して、インタヴューに答えながら、
人生を振り返るというドキュメンタリーもの。
フェイルーズが出演した映画、テレビ番組、コンサートから、
フェイルーズの歌うシーンが次から次へと登場するので、
もう画面にくぎ付けになりっぱなし。
20~30代の頃の貴重なフィルムが、ふんだんに盛り込まれているんですけれど、
若いフェイルーズの美しいことといったら。
小学校の教室で子供たちと歌を歌う教師に扮したり、
結婚式でお祝いの歌を歌うなど、初めて観るものばかりで、
カラー映像の美しさにも、もうクラクラ。
若いフェイルーズは、ういういしさというより、
気品のある立ち振る舞いに、圧倒されます。
たたずまいが高貴で、もう存在感からして違いますね。本物の<お姫さま>です。
歌もクリスタル・グラスの如く繊細で、
完成されたコブシ回しの技量に、惹き込まれます。
あらためて、若い頃から歌声がちっとも変化していないのが、よくわかりました。
意外だったのは、インタヴューに答える地声がすごく低いこと。
歌と全然違うのに、驚かされました。
全編122分。英・仏語字幕。本編だけでも貴重な映像の連続ですけれど、
ボーナス・トラックとして、ヴィデオ・クリップが5曲付いています。
映画本編では、抜粋の歌のシーンを、完奏ヴァージョンで観れるので、
フェイルーズ・ファン必見のDVDといっていいでしょう。
[DVD] Dir: Frédéric Mitterrand "FAIROUZ"
Arte Video/EMI Muisc Arabia 0946 394610 97 (1998)
2017-05-07 00:00
コメント(2)
13年ぶりの大人のゆりかご シーラ・マジッド [東南アジア]

うわぁ、やっと新作を出してくれましたね、シーラ・マジッド。
ハリラヤ・アルバムがあったとはいえ、ポップ・アルバムのスタジオ新作としては、
04年の“CINTA KITA” 以来なんだから、本当にずいぶん待たされたものです。
「マレイシアのポップ・クイーン、シーラ・マジッドの完全復活」と書いてから6年。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2011-10-20
その記事を「再始動」と題したものの、
そこからまたしても、シーラの姿は視界から消えてしまったんですよね。
シーラのオフィシャル・サイトもまったく更新されず、
どーしちゃったんだよー、と嘆き節の日々で、
マレイシアの若手フォロワー、アティリア嬢に、
シーラの影を追ったりしていたものでした。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2014-01-23
ファンが長年待ち焦がれたこの新作、
プロデューサーには、インドネシアのトーパティが起用されています。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2016-06-07
前作のハリラヤ・アルバムでは、アチスのプロデュースに不満を感じていたので、
思い切って国外の才能に目を向けたのは、大賛成。
かつてシーラを輝かせた、ロズラン・アジズのプロデュースの手腕を知る者には、
クリシェやクリスダヤンティらを手がけた敏腕プロデューサー、
トーパティなら申し分ない人選といえます。
ラストの英語曲のバラードのみ、シーラの古くからのパートナー、
ジェニー・チンがプロデュースしていて、友情出演的な起用もファンには嬉しいところ。
さて、その新作、たおやかで柔らかなシーラの歌い口は、昔のままです。
もちろん20代、30代の時のような、キラキラッとした輝きはなくても、
大人のポップスを楽しませてくれる落ち着いた歌いぶりに、
長年の喉の渇きを癒されます。
ユーモラスな愛らしいメロディの1曲目から、楽曲も粒揃い。
力の抜けたゆるさが心地よい、大人のゆりかごのようなポップス・アルバムです。
Sheila Majid "BONEKA" Magada Entertainment/Universal 5756021 (2017)
2017-05-05 00:00
コメント(0)
サルサの若大将 エドウィン・ペレス [カリブ海]
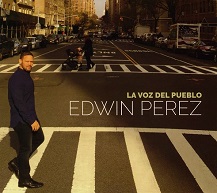
すっかり興味を失っていたサルサ新作ですけれど、
去年あたりから、本格的に復調した兆しを感じるようになりました。
ちょうど一年前あたりにも、サルサ新作の記事を連投したおぼえがありますけど、
今年もきてますねえ、熱いやつが。
それが、この若手のエドウィン・ペレスのソロ・デビュー作。
若手と呼ぶものの、キャリアは十分。すでに中堅どころといってもよい人で、
ラ・エクセレンシアで10年のキャリアを積んでいるんだから、
満を持してのソロ・デビューなわけですね。
全10曲、オリジナル。キャッチーなメロディを書ける人ですよ。
エドウィンのヴォーカルとコロのコール・アンド・レスポンスも狂おしく、
切れ味バツグンのホーン・セクションとパーカッションが繰り出すグルーヴに、
シビれまくり。このティンバレスを叩いてるの誰?と思ったら、
ルイジート・キンテーロだって。うわ、そりゃ、スゴイわけだわ。
サルサはやっぱりこのグルーヴがなきゃ、ダメだよねえ。
スムースになっても、ポップになってもいいけど、
このキレとダイナミズムを失っちゃいけません。
サルサになくてはならない<熱>が、ここにはあります。
いいサルサを聴いていると、身体が黙っていない。
自然に足がステップを踏んで、腰が動いてしまう、バイラブレなサウンド。
エドウィン・ペレスのヴォーカルも、若い時のイスマエル・ミランダのような
「青春の光と影」の味わいがあって、もうたまりまへん。
Edwin Perez "LA VOZ DEL PUEBLO" Edwin Perez no number (2016)
2017-05-03 00:00
コメント(4)
パナマ音楽をやらないパナマ元観光大臣 ルベーン・ブラデス [中央アメリカ]

ルベーン・ブラデスの新作であります。
2年も前にリリースされていたのに、なんでまたラテン専門店のバイヤーさんは、
ずっと見逃してたんでしょう?という感じですが、これが日本初入荷。
ルベーンは、何年か前にタンゴ・アルバムを出したりしてた記憶がありますけど、
ぼくがルベーンを聴くのは、チェオ・フェリシアーノとの共演作以来だから、5年ぶり。
http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2012-06-14
それでも、そんなひさしぶりという感じがしないのは、
5年前なんて、ついこの前に思える老人に、自分がなったせい?
いやいや、そうじゃなくって、
それ以前のルベーン・ブラデスとの疎遠にしてた期間が、
ずっと長かったからなんですね。
なんせ、82年にウィリー・コローンとコンビを解消して、
シンセとドラムスを取り入れた自己のバンド、セイス・デル・ソラールを率いてからは、
ルベーンはぼくの視界から完全に消えていたもんで。
ぼくは、セイス・デル・ソラールのサウンドを受け入れられなかったんです。
というわけで、チェオの共演作まで、30年以上のブランクがあったので、
5年ぶりなんて、ぜんぜんひさしぶりじゃないわけなんですが、
15年新作の伴奏も、セイス・デル・ソラールではなく、
サルサのオルケスタなので、ぼくにとっては安心して聴けるというか、大歓迎。
今回共演しているのは、パナマのロベルト・デルガード率いるオルケスタ。
トロンボーン×3、トランペット×2、バリトン・サックスの6管編成による
厚みのあるサウンドで、にっこり。サルサはこうでなくっちゃねえ。
オープニングの曲を、ラストでゲスト歌手に歌わせているんですが、
これがサボール溢れる歌声で、シビれましたね。このメドロ・マデラって誰?
聴く前は、『パナマの音』というタイトルと、
パナマの国旗がずらっとはためくジャケットに、
おお、ルベーンも、ついにパナマの伝統音楽に挑戦かと色めき立ったんですが、
そうではなく、パナマのオルケスタを起用して、
パナマで録音したということなんですね。
なんだぁ。タンボリートやタンボレーラ、メホラーナでもやってるのかと思ったのに。
せめて、パナマの作曲家のレパートリーぐらい、取り上げればいいのにねえ。
カルロス・エレータ・アルマランの「ある恋の物語」とか、
リカルド・ファブレガの「パナマ・ビエホ」とか、
パナマにはいくらでも名曲があるんだからさ。
ルベーンはパナマの観光大臣をやったくせに、
いっこうに自分の音楽には、地元の音楽を反映させようとしませんね。
そういえばずいぶん昔の話ですけど、
晩年のミゲリート・バルデスがパナマ歌謡を歌った名作を引き合いにして、
中村とうようさんがパナマ音楽を手がけないルベーンを、
ディスってたことがあったっけなあ。
とうようさん、ちょっと天国から、ルベーンの尻にケリを入れてくれません?
Rubén Blades "SON DE PANAMÁ" Subdesarrollo no number (2015)
2017-05-01 00:00
コメント(0)




