儚げなインドの唄 ミーナ・クマリ [南アジア]
エル・スールの原田さんに教えてもらった一枚。
ミーナ・クマリという名前をぜんぜん知らず、どういう人?と訊いたら、
独立前のインドで天才子役として人気を博し、
50~60年代に悲劇のヒロインを演じた女優兼歌手で詩人でもあった人とのこと。
役どころと同じ不幸な実生活を送り、39歳の若さでアルコール依存症で早世した、
インド映画界の伝説的な悲劇の女王だそうです。
ミーナにはプレイバック・シンガーのような完璧な歌唱力はなく、
その歌いぶりは不安定ともいえるんですけど、
その不安定さが歌い手のぬくもりとして伝わってきて、う~ん、これがいいんですよ。
歌の導入部で語りが入るパートなんか、幸薄そうな声でせつせつと語っていて、
男としては黙っていられなくなりますね。
インドというとすぐ連想してしまうキンキン声とは無縁の、落ち着いた柔らかな声も魅力的。
歌われている曲は、白黒トーキー時代のヒンディー映画音楽らしく、
ウルドゥー語によるしとやかなガザル集で、そのたおやかな歌声に聴き惚れてしまいます。
このアルバムは、ミーナが書いたウルドゥー語の詩に、
大御所の映画音楽の作曲家ハイヤームが曲を付けたものだそう。
ミーナの歌声に寄り添うサントゥールやサーランギなどの控えめな伴奏が、
薄幸な人生を歩んだ悲劇のヒロインを彩り、
その実人生とも写し絵のようになった、儚げな美しさに溢れています。
中高年男性が枕を濡らす、秋の夜長盤がまた1枚増えました。
Meena Kumari "I WRITE I RECITE" Universal CDNF480
2010-10-31 07:33
コメント(0)
サンバ・パウリスタの大物新人 マルキーニョス・ジャカ [ブラジル]

これがデビュー作とは頼もしいですねえ。
サンパウロのアフロ・ルーツ系サンビスタ、マルキーニョス・ジャカのソロ・アルバム。
写真から察するに、30代前半といったところでしょうか。
声は若々しく、歌い回しに生硬さはあるものの、
おどけた感じのある歌いぶりなど、なかなか軽妙です。
ゲストのサンビスタたちやコーラスとかけあいでパルチード・アルトを披露するところは、
前回話題にした即興の妙味とは異なり、きちんと構成されたものとはいえ、
パルチデイロの名にふさわしい、鍛えられたノドを聞かせてくれます。
伴奏は標準的なサンバの編成にコーラス隊という、きわめてオーソドックスな陣容で、
なんら奇をてらったところのない、ナチュラルなもの。
どっしりとしたリズムが醸し出すふくよかさが、サンバ好きの頬をゆるませます。
コミュニティのなかで育まれてきたサンバの、もっとも純度の高い姿がここにありますね。
パルチード・アルトのほかジョンゴなども歌っていて、
サンバのルーツに深く根ざした内容は、80年代のウィルソン・モレイラを思い起こさせます。
最近のリオでは、こういったルーツ系サンバのアルバムがほとんど制作されなくなっているので、
サンパウロにすっかりお株を取られている感じがしますね。
そのサンバ・パウリスタの良心とも呼べる立役者が、
このCDを制作しているコロンボロ・ジア・ピラチニンガ。
サンパウロのサンバを保存・普及に努める非営利団体で、
サンビスタが多く暮らすヴィラ・マダレーナ地区に拠点を置いて活動しています。
コロンボロに注目が集まったのは、なんといっても昨年の『サンパウロのサンバの記憶』シリーズ。
そういえば、あのシリーズはまだ残り8タイトルがあって、
今年の上下期に4タイトルずつリリース予定だったはず。
コロンボロが制作したサンバ・パウリスタの大型新人
マルキーニョス・ジャカのデビュー作の仕上がりの素晴らしさに、
シリーズ残りのリリースがますます待ち遠しくなります。
Marquinhos Jaca "NÚMERO UM DO BRASIL" Tratore 20.1975.001 (2010)
2010-10-29 06:37
コメント(0)
パルチード・アルトのスリル [ブラジル]

こりゃ、ゴキゲン!
4人の無名サンビスタによる生のサンバ・セッションを収めたライヴで、
ほんもののパルチード・アルトのスリルが味わえます。
「パルチード・アルト」を銘打ったアルバムは数あれど、
じっさいはほとんど即興なんかじゃありませんね。
事前にばっちり歌詞を作ってレコーディングしたものがほとんどで、
即興のスリルを感じられるものは、ほんのわずかしかありません。
まあ、もちろん商品としてレコードを作るわけですから、
純然とした即興のパルチード・アルトをやるわけにはいかないにせよ、
あまりにも打ち合わせバッチリ、お互いの手の内知り尽くした録音ではシラけます。
もちろんぼくも、レコードを聴くだけで即興かそうじゃないかを、
正確に聴き分ける自信があるわけじゃないですど、
何人ものサンビスタが、あまりにもなめらかに歌い継いでいけば、
こりゃ、リハーサルを積んでるなってことくらい、いくらなんでもわかりますよ。
その場で初めて即興で作った歌なら、かけあいのスリルや緊張感が自然と溢れ出るもの。
このアルバムには、そんな即興のスリルがそこかしこから感じ取ることができます。
歌詞に反応するコーラスのメンバーの笑い声や嬌声などからも、
当意即妙なパルチード・アルトの楽しさがいっぱい。
メロディーに歌詞が乗り切らず、字余りふうになってしまうところなんて、
まさに即興ならではのスリルです。
Marquinhos China, Renatinho Partideiro, Serginho Procópio, Taigo Mocotó
"RODA DE SAMBA DE PARTIDO ALTO" Cedro Rosa CR032010 (2010)
2010-10-27 06:40
コメント(0)
アフロペルアーナのコク デ・ロンペ・イ・ロハ [南アメリカ]

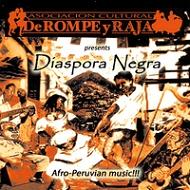
なんだかここのところ、ペルーがきてますねえ。
サヤリー・プロダクションによるクリオージョ音楽の珠玉のようなアルバムが続いたと思ったら、
今度はアフロペルー音楽の逸品を見つけました。
95年、アフロペルー音楽の普及を目的に北カリフォルニア在住のペルー人によって
結成されたグループ、デ・ロンペ・イ・ロハのアルバムで、
北カリフォルニアの彼らの自主レーベルから2タイトル、リリースされています。
01年に出たデビュー作“EL RETORNO” は、フェステーホ、ランドー、サマクエーカ、アバネーラを、
ギター、カホン、キハーダほか打楽器の伝統的な編成で歌ったオーセンティックな内容。
混声コーラスが実に味わい深く、これぞアフロペルー音楽の神髄といった仕上がりとなっています。
そして、このデビュー作の翌年から彼らは新たなプロジェクトに取りかかり、
昨年ついに2枚組の大作“DIASPORA NEGRA” を完成させました。
8年をかけただけのことはある、たいへんな力作です。
89年に渡米したリマ生まれの女性ダンサーで芸術監督のガブリエラ・シオーマと、
打楽器奏者で音楽監督のペドロ・ロサーレスがプロデュースしたこのアルバム、
デビュー作同様フェステーホ、ランドー、サマクエーカなどのレパートリーを繰り広げているんですが、
デビュー作のオーセンティックな路線を維持しつつ、現代的な感覚のサウンド・アイディアを施し、
デビュー作をはるかに凌ぐ充実した内容に仕上げています。
たとえば、トロンボーンを加えたディスク1の4曲目のサウンドは、
どこかウィリー・コローンを思わせますし、
ディスク1の6曲目でマリンバの音色を模したキーボードをフィーチャーしたのも、
なかなか洒落たアイディアです。
カホンほか打楽器のみの伴奏をバックに、男気たっぷりのヴォーカルが交叉する
ディスク1の7曲目のフェステーホに次いで、8曲目のランドーでは一転、
泣きのヴァイオリンをフィーチャーした泣き節となるところなど、なかなかニクイ演出となっています。
さらにディスク2の2曲目では、ジャズ・ギターとエレキ・ベースを加えて印象的なリフを作るなど、
さらりとコンテンポラリーなアレンジで聞かせるセンスもいいですね。
こうした多彩なアイディアが、
アフロペルー音楽の輪郭をくっきりと強調するのに成功しているわけです。
レコーディングは1曲を除いてカリフォルニアで行われていますが、
ミックス、マスタリングはペルーで行われています。
ペルー本国でも、これほど意欲的なアフロペルー音楽のアルバムはめったにお目にかかれず、
デ・ロンペ・イ・ロハの活動が貴重なばかりでなく、その成果は功労賞ものです。
こういう本格的なのを聴くと、味気ないスサーナ・バカなんか、とても聴けなくなりますよ。
アルバムを通じて痛感するのは、
アフロペルー音楽の<黒っぽさ>にもいろいろあるなあっていうこと。
リズムはアフロ系でも、歌はムラート感覚が強いものがあったりと、
その<黒っぽさ>には、さまざまなグラデーションがあることに気付きます。
一方、混淆音楽であるクリオージョ音楽でも、
黒人歌手が歌うヴァルスなどには、もろアフロ系といった強烈な黒っぽさを感じさせるものもあり、
こうした混淆の複雑さこそに、ペルー音楽独特の深いコクの秘密がありますね。
De Rompe Y Raja "EL RETORNO" no label no number (2001)
De Rompe Y Raja "DIASPORA NEGRA Ⅰ&Ⅱ" no label no number (2009)
2010-10-25 06:42
コメント(0)
剛毅なフジを求めて アバス・アカンデ・オベセレ [西アフリカ]

ナイジェリアのフジが90年代以降、魅力を失った原因のひとつは、
パーカッション・ミュージックのサウンド・アイデンティティをかなぐり捨てたことでした。
シキル・アインデ・バリスターがパーカッションのみの演奏だったフジに、
西洋楽器を導入し始めたのが82年あたり。
はじめはアルバムのごく一部で、トランペット(軍隊ラッパ)やハーモニカなどを
ほんのアクセント程度、実験的に使うだけだったのが、
次第にスティール・ギターやシンセサイザーなどを派手に使い始め、
91年にインターナショナル・デビューしたイギリス・グローブスタイル盤では、
ジュジュを意識したハッタリ十分なスティール・ギターの大活躍ぶりに、鼻白んだものでした。
グローブスタイル盤でフジを初めて知った多くの人にとっては、
ぼくとはぜんぜん違う感想をお持ちだと思いますけども、
あの当時ぼくはすでにシキルを見限っていて、西洋楽器の導入を頑なに拒んでいた
ワシウ・アインデ・バリスター(当時)の方を、断固支持していました。
なので、シキルのグローブスタイル盤でフジが世界に紹介されたのは、
片腹痛い思いがしたものです。
しかし、ワシウも世の流行には逆らえず、
その後まもなく西洋楽器を取り入れるようになってしまいます。
70年代のフジは、どす黒いパーカッション・アンサンブルが地を這うヘヴィーなサウンドだったのが、
やがてスティール・ギターやシンセのちゃらい音が支配する軽いサウンドへとシフトし、
猛烈に疾走する早いリズムへと変わっていったのが、80年代から90年代にかけての変化でした。
そして世紀を越えたあたりからは、ついに女性コーラスまで加わるようになり、
硬派のマッチョな音楽だったフジは、ここに来て完全にナンパな音楽へと成り下がります。
エディ・サンティアゴだのウィリー・ゴンザレスだのが、
男前だったサルサをサルサ・エロチカへと堕落させたように、
フジを大甘にした立役者のひとりが
アバス・アカンデ・オベセレでした。
オベセレはセックスを歌ったエロ路線で人気沸騰となり、
ストリッパーが登場する成人指定VCDまで乱発。
ぼくはその下卑たエロ路線まっしぐらのオベセレの諸作に、
ヘキエキとしてました。
(参考までにいっちばん下品なVCDがこれ。中身はほとんどノリウッド・ポルノです。
裏ジャケはさらに過激でお見せできません。サイテーです)
オベセレの歌唱力はいわば関脇クラスで、シキルやワシウに比べればかなり小粒。
演奏はといえば、サックスや鍵盤楽器がチープな音をまき散らし、
疾走するパーカッション・アンサンブルも一本調子で、ガサツさが否めず、
かつてのフジのパーカッション・アンサンブルのリッチで緻密な構成を知る者には、
とても満足できるものではありませんでした。
とはいえ、なかには息もつかせぬ強烈な疾走感で圧倒する良作も残していて、
04年の“OLD SKOOL LAPEL” は、オベセレの代表作の名にふさわしいものでした。
それでも個人的には、女性コーラスがジャマでしょうがなかったですけどね。
オベセレに限らず、アデワレ・アユバ、ワシウ・アラビ・パスマ、サヒード・オスパ、レミ・アルコなど、
近年のフジ・アーティストはやたらとアルバムを乱発するんですけど、
いくら追っかけても石ばっか、という感じで、玉に当たるのは10にひとつあるかないかといった程度。
女性コーラスがおジャマ虫なもの、ヤスッぽいシンセがショボいもの、リズムが一本調子なものと、
1枚の良作見つけるまでに10枚以上の駄盤が積み上がるという、
ボリウッド・サントラ並の低率ぶり。
これが今のフジ・シーンの実態で、
昔惚れ込んだ弱みがなけりゃ、とっくに見限っているジャンルなんですが、
ハズレを引いてる数が多いだけ、当たりにうまいこと出くわすとゾクゾクしちゃいますね。
そして、その数少ない当たりと自信を持って紹介できるのが、
オベセレの30作目を数える08年作の“OLOGBOJO” で、
拙著『ポップ・アフリカ700』にも載せてあります。
オベセレのアルバムでいつも耳障りだった女性コーラスがやっといなくなり、お囃しは男声のみ。
サックスや鍵盤楽器も、イントロや曲のつなぎなど、場面展開のみの控えめな使用となっていて、
力まかせにツッ走るだけではない抑えの利いたアンサンブルや、
コーラスとのかけあいも、これまでにないゆとりを感じさせます。
名義に新しくPK1st とあるとおり、「パラマウント・キング」の称号をいただき、
オベセレもようやくセックス路線からの転換を図っているのかもしれません。
エル・スールに最近また入ってきているようなので、この機会にぜひどうぞ。
Abass Akande Obesere "OLOGBOJO" Zee Entertainment ZEE002 (2008)
[VCD] Abass Akande Obesere "GOGO IN LONDON" Afeezco Films International no number
2010-10-23 00:18
コメント(0)
デレ・アビオドゥンのオルモ録音 [西アフリカ]
ナイジェリアでジュジュが黄金時代を迎えた70年代から80年代、
デレ・アビオドゥンは、エベネザー・オベイ、サニー・アデと肩を並べる三羽烏の一人でした。
当時のオベイやアデの録音は、ナイジェリアでもかなりCD化されましたが
(編集はでたらめなものが多いですけどね)、デレはまったくCD化されずじまい。
最近はデレの活動ぶりも伝わらなくなり、すっかり忘れられた存在になっていたんですが、
デレが70年代にオルモ・レーベルへ残した13タイトルが、このたび一挙にCD化されました。
妙な編集はしておらず、オリジナル・アルバムをそのままCD化しているので、
歓迎すべきストレート・リイシューといえます。
ただ、ジャケット・デザインやタイトルがオリジナル盤をまったく踏襲していなくって、
どのアルバムをCD化したものか判別つきにくいのが、困りものなんですよね。
CD番号がLP番号と同じなので、オリジナル盤を確認するには番号が頼りです。
どうもナイジェリア盤CDというのは、満足いくリイシュー仕事をしてくれませんね。
入手できた12タイトル中、ぼくが聴いたことのあるのは5タイトルのみで、
ほとんどが初めて聴くものなかり。
あらためて、デレのキャリアをデビュー当初からじっくり聴くことができたわけですが、
デレのアルバムは出来不出来の差が大きく、
やはり名作といえるのは、ぼくが手元に残した3タイトルだけといえそうです。
その3タイトルとは、代表作の117番に106番と79番。
“G'ESIN NI KESE” がオリジナル・タイトルの117番は、84年にPヴァインから
『アダワ・スーパー・キング登場!』のタイトルで日本盤がも出たこともある、デレの最高傑作。
クラヴィネットを全面的に導入し、
キャッチーなリフやブレイクを多用したファンキーなジュジュが痛快です。
スティール・ギターの使い方もオベイやアデよりずっと派手で、
ギター・リフやブレイクなど、ロック世代に受け入れやすい割り切りの良さに
デレの個性が表われています。
オリジナルLPと同一タイトルの106番は、クラヴィネットをはじめて導入した作品で、
いわば117番のプロトタイプ的な内容。
クラヴィネットは117番ほど活躍していませんが、
ロック/ソウル色を強く打ち出した骨太な感覚が、痛快なポップなセンスにつながっています。
オリジナル・ジャケットは、教会の前の新郎新婦を漫画にしたデザインでした。
79番は、メリハリのある構成で聞かせる快作。印象的なギター・リフはアデのパクリとはいえ、
力技で押し倒すようなパワフルな感覚は、アデにはないデレの個性でした。
オリジナル盤は、赤い地に室内のデレのスナップ・ショットを飾ったジャケットでした。
今回初めて聴いたアルバムのなかでは、
もっとも初期のアルバム“ABANIJE” が、完全にアデ・フォロワーで面白かったですね。
精緻なギター・アンサンブルや空間をいかしたクールなサウンドなんて、アデのジュジュそのもの。
デレの歌い口も明らかにアデを真似ていて、後年のロックぽい感覚は見る影もありません。
デレのキャリアのスタートは、アデのコピーから始まったことがよくわかりました。
残るデレのレコードでCD化を期待したいのは、
オルモを離れ、自己のレーベル、アダワ・スーパーから最初に出した、
81年の“THE BEGINNING OF THE NEW ERA” ですね。
ぼくにとっては“G'ESIN NI KESE” 以上に聴きまくった最愛聴盤です。
Admiral Dele Abiodun and His Top Hitters Band
"ABANIJE" Olumo ORLPCD023 (1975)
"ODALE A JIYA" Olumo ORLPCD028 (1975)
"ESHIN O WE WU" Olumo ORLPCD038 (1976)
"ASIKO LOTO" Olumo ORLPCD056 (1976)
"ILE OLA MI" Olumo ORLPCD060 (1977)
"HALLELUYAH MODUPE" Olumo ORLPCD065 (1977)
"AGBA WA BURA" Olumo ORLPCD066 (1977)
"GBANJO KOBOKO" Olumo ORPLPCD079 (1978)
"ELEMU NGET ON" Olumo ORLPCD083 (1978)
"ABERE A LO" Olumo ORLPCD089 (1979)
"FOR BETTER FOR WORSE" Olumo ORPCDS106 (1980)
"LAI SE LAI RO" Olumo ORPCD117 (1980)
2010-10-21 06:33
コメント(4)
54年前のアメリカの歌 バーバラ・リー [北アメリカ]

秋の夜長、女性ヴォーカルを愉しむのにいい季節になってきました。
ぼくが三十年来ごひいきにしてるご婦人方に、
リー・ワイリー、バーバラ・リー、メレディス・ダンブロッシオがいます。
今夜はバーバラ・リーのプレスティッジ盤に手が伸びました。
バーバラ・リーを知ったのは、とあるジャズ廃盤専門店主の親父さんのおかげ。
18・19の頃、リー・ワイリーの“NIGHT IN MANHATTAN” にゾッコンだったぼくに、
「それじゃあ、バーバラ・リーは知ってる?」と親父さんが棚から手に取ったレコードが、
このプレスティッジ盤でした。
ヴォーカル・マイクの前で歌う気品のある顔立ちの女性のモノクロ写真に、
ピンクの太文字でBarbara Lea と書いた、いかにも50年代らしいデザイン。
いいジャケットだなあとしげしげ眺めつつギョッとしたのが、ゼロが4つもついたお値段。
目を白黒させて、こんな高いレコード買えるわけないじゃないと、あわてて返したら、
親父さんは後になってダビングしたテープをプレゼントしてくれたのです。
テープから流れてきたバーバラの歌声に、ぼくは一瞬にしてトリコとなりました。
なんてあたたかな歌声。そして慈しむようにメロディーを歌う歌唱は、
明らかにリー・ワイリーの流れを汲むものです。
“I'm Coming Virginia” “Gee Baby, Ain't I Good to You” “Baltimore Oriole” など、
ぼく好みの曲も満載で、すっかりこのアルバムのトリコになりました。
以来、91年にOJCがCD化するまで、このテープがぼくの宝物になったことは言うまでもありません。
じっくりと聴けば、リーのぞくぞくするような妖しいまでの色気はバーバラにはなく、
もっとくだけた庶民的な親しみやすさが、バーバラの持ち味であることがわかります。
それでもそのあたたかな歌の表情は、リーを想わせるのに十分でした。
そんなことをずっと思いながら二十年以上が過ぎ、
2002年にNHKで放映された
「世界・わが心の旅 アメリカ 私のリー・ワイリー」を観たときはびっくりしました。
女優の宮本信子がニューヨークへバーバラ・リーを訪ね、
リー・ワイリーの思い出話を聞かせてもらうというドキュメンタリー番組だったのです。
リーとバーバラとは深い親交があり、姉妹関係のような付き合いをしていたというのですから、
ぼくが二人を似ていると思っていたのも、まさにしかりだったわけです。
ひさしぶりにCDを聴きながら、ぼんやりとクレジットを眺めていたら、
1956年10月18日・19日のレコーディングということに気付きました。
え? それって、ちょうど54年前の今日じゃない!
録音日に手が伸びるなんて、なんという偶然でしょう。
なにかに呼ばれたんでしょうか。なんとも不思議な感じです。
Barbara Lea "BARBARA LEA" Prestige/OJC OJCCD1713-2
2010-10-19 06:31
コメント(0)
カルトーラのデビュー録音 [ブラジル]

ジャズ評論家の後藤雅洋さんにお招きいただいて、
後藤さんのお店、いーぐるでレコード・コンサートをするのも今度が4回目。
今月30日土曜日のテーマは、「カルトーラとノエール・ローザを偲んで」です。
(ぼくは勝手にレココンとか言ってますけど、お店では「連続講演」と呼んでいます)
今年はカルトーラ没後30年、そしてノエール・ローザ生誕100年にあたるため、
それにちなんだ企画でもあるんですけど、実はこのテーマ、ぼくが考えたのではなく、
4月にショーロの歴史を辿るレココンを行った際、お客さまからいただいたリクエストなんです。
レココン終了後、建部さんとおっしゃる方がいーぐるの掲示板に、
「ショ―ロの会凄く良かった。今度はカルトーラとノエール・ローザをやってもらえば有難いのだが。
是非お願いします」と書き込まれたんですね。
しかもそのお名前のあとに「89歳」と書き込まれていて、驚愕!
レココンの時、すごくお年を召した方がいらしてるなあとは気付いていましたが、
まさかこんなリクエストをいただけるなんて!
89歳の方がネットの掲示板でリクエストされたのもびっくりでしたけど、
おととし亡くなった父と同い年であることに、ジンときました。
なんせ父はぼくを無類の音楽好きにした張本人。
天国の父からリクエストをもらったみたいで、感無量でした。
そんなこともあって今回は力が入り、何度も選曲を練り直して、ばっちり流れを作りましたよ。
カルトーラがハタチそこそこで作曲したサンバから、最晩年の曲までをお聴きいただきます。
なかでも楽しみにしていただきたいのが、カルトーラのデビュー録音。
これを聴いたことのある方って、あんまりいないんじゃないかと思います。
そのデビュー録音が行われたのは、1940年。
なんとブラジルのレコード会社による録音ではなくて、
アメリカのコロンビア・レコードが録音したものです。
なんでまたアメリカ・コロンビアがと思われるでしょうが、
ブラジルを訪れていたクラシック音楽家レオポルド・ストコフスキーが、
アメリカ・コロンビアの依頼でブラジル音楽の録音をすることになったのが事の始まり。
レオポルドは録音にあたり、ブラジルの友人だったエイトール・ヴィラ=ロボスへ相談し、
ヴィラ=ロボスはレオポルドにピシンギーニャを紹介したのです。
その結果、レコーディングはピシンギーニャが仕切り、カルトーラにも声がかかったのでした。
当時カルトーラは、マンゲイラの外にも広い交友関係を持っていて、
作曲者仲間のノエール・ローザほか、ピシンギーニャやヴィラ=ロボスとも付き合っていました。
そんな交流があったからこそ、レコーディングも実現したわけで、
カルトーラはブラジルよりも早く、インターナショナル・デビューしてしまったというわけです。
このレコーディング・プロジェクトは、"NATIVE BRAZILIAN MUSIC"と題した
SP4枚組のアルバム2巻にまとめられ、アメリカで発売されました。
カルトーラが歌った“Quem Me Vê Sorrir” は、第2巻の方に収録されています。
ぼくはこの録音を、87年にブラジルで復刻されたLP(MINC/FNPM MVL033)で初めて耳にし、
その後だいぶ経ってから、オリジナルのアメリカ・コロンビアのSPアルバムを入手しました。
レココンではこのデビュー録音ほか、カルメン・ミランダが歌った曲や、
マンゲイラの最大のライヴァル、ポルテーラの作曲家パウロ・ダ・ポルテーラと共作した曲など、
若き日のカルトーラが残した仕事も、たっぷりとお聴きいただこうと思っています。
建部さん、その後お元気でいらっしゃいますか。
リクエストをいただき、張り切って選曲をしました。ぜひいらしてくださいね。
東京近郊の皆様も、どうぞお越しください。お待ち申し上げております。
[SPアルバム] "NATIVE BRAZILIAN MUSIC VOLUME 2" Columbia C84
2010-10-17 00:14
コメント(0)
ヴァージニアのフィンガー・ピッカー ウィリアム・ムーア [北アメリカ]

荻哲さんのブログに、戦前ブルースのラグ系ギタリスト、
ウィリアム・ムーアなんて懐かしい名前が出てきたものだから、耳がぴくんと立っちゃいました。
ブラインド・ブレイクやブラインド・ウィリー・マクテルあたりは有名でも、
ウィリアム・ムーアとなると、よほど戦前ブルースを聞き込んでる人じゃないと、知らないはず。
思わず嬉しくなってシッポ振り振り、高校の頃の思い出をコメントしたら、
「高校生で、こんな音楽のコピーをしていたんですか?」なんて呆れられちゃいました。
ぼくが高校生になって戦前ブルースを聴くようになったのは、
フィンガー・ピッキング・スタイルのギターのコピーに夢中になっていたからです。
ライ・クーダーやステファン・グロスマンのコピーでは飽き足らず、
戦前ブルースのオリジナル演奏にものめり込んで、
ブラインド・ブレイクやブラインド・ボーイ・フラーなど、
イースト・コーストのラグ系ギターを夢中でコピーしたもんです。
でもねー、むずかしいんですよー。
ライ・クーダーが“PARADISE AND LUNCH” でカヴァーした
ブラインド・ブレイクの“Diddie Wa Diddie” なんかも、
一応それらしく弾けるようにはなったんですけど、
ブラインド・ブレイクのような独特のリズム感はとても出せません。
ウィリアム・ムーアの“Old Country Rock” も、事も無げにギターを弾いてるように聞こえますけど、
いざコピーしてみると難易度Sランクもので、とってもじゃないけど歯が立ちませんでした。
そんな思い出もあるもんだから、「ウィリアム・ムーアの“Old Country Rock”」と聞いただけで、
「はいっ! オリジン・ジャズ・ライブラリーの“REALLY! THE COUNTRY BLUES 1927-1933” の
A面2曲目、レコード番号はOJLの2番ですっ!」などといまだにするすると出てきます。
こんな役にも立たない記憶が、いつまでもぼくの脳ミソの記憶容量を塞いでるもんだから、
近頃物覚えは悪いわ、忘れっぽいわのメモリー不足を起こしてて、まー、困ったもんですね。
LP時代はあちこちのレコードに録音がばらばらに収録されていたウィリアム・ムーアですが、
CD時代になってからは、ドキュメントがムーアの録音を8曲まとめてCD化しました。
荻哲さんのブログでも話題に上っていた
“Ragtime Millionaire” “Midnight Blues” も入っています。
ギターのコピーに挫折してからの方が、ますます戦前ブルースにのめりこんだぼくですが、
ムーアの“Old Country Rock” を聴くと、
コピーに悪戦苦闘したあの頃を思い出さずにはおれません。
William (Bill) Moore, Tarter and Gay, Chicken Wilson and Skeeter Hinton, Bayless Rose, Willie Walker and Blind Blake "RAGTIME BLUES GUITAR (1927-1930)" Document DOCD5062
2010-10-15 06:39
コメント(2)
ソプラノ・ヴォイスの民謡唄い ジーン・リッチー [北アメリカ]
うわぁ、ついにジーン・リッチーのデビュー10インチがCD化されましたねー。
思わず手にとって、しげしげと眺めてしまいました。
もう二十年以上も前になりますけど、某レコード店でこの10インチを見つけて、
ずいぶん迷ったあげく結局買わず、あとあとまでずうっと後悔が残ってたんですよ。
ジャケットがいいんですよねえ。
絶妙なレタリングと、ジーンの頭とダルシマーだけをコラージュしたデザインがバツグンで、
う~ん、ほしいなあ、どうしようかなあと迷ったんです。
迷ったのは、ジーン・リッチーがあまり好きじゃなかったからで、
ジャケ目当てに買うのも、なんだかなあみたいに思ったからなんですね。
ずいぶん昔、ジーン・リッチーのレコードを2枚買ったことがあるんですけど、
どちらも好きになれず、手放してしまったのでなおさらでした。
その後だいぶ経って、あの10インチがジーンのデビュー作で、
フォーク・リヴァイバルの重要作とのレコード評を読み、
うわあ、やっぱり買っとくべきだったなあと大後悔。
今回ようやく、CDで四半世紀ぶりの再会となったわけです。
民謡唄いというと、ぼくはスコットランドのジーニー・ロバートソンのような、
低めの力強い声で歌う人が好きなので、
ジーンのようなか細いソプラノ・ヴォイスは苦手。
このアルバムでもその苦手意識は変わりませんでしたが、
昔聴いたレコードより、ガラス細工のような繊細さが印象的で、
その無垢な味わいに、ちょっと感じ入ってしまいました。
ギターとマウンテン・ダルシマーの素朴な伴奏で歌うジーンの歌声は、
陽を浴びてきらきらと輝くせせらぎや小鳥のさえずりを思わせます。
昔はその<こぎれいな>民謡のたたずまいに抵抗を覚えたのですが、
ゴツゴツとした力強さばかりが民謡の良さじゃないことを、
このデビュー作から教わったような気がします。
Jean Ritchie "SINGING THE TRADITIONAL SONGS OF HER KENTUCKY MOUNTAIN FAMILY" Elektra/Tartare T8014 (1952)
2010-10-13 06:43
コメント(0)
天性の声 アルトゥーロ・サンボ・カベーロ [南アメリカ]

あぁ、もう1年が経ってしまったんですね。
去年10月9日に68歳でこの世を去ったアルトゥーロ・サンボ・カベーロ。
昨年CD化された78年作がいわば追悼作ともなってしまったわけですが、
アルバムを聴きながら、あらためて涙を誘われました。
アルトゥーロ・サンボ・カベーロのアルバムに駄作はないといっても過言ではありませんが、
さすがに髪が真っ白になってしまった晩年の録音は、やや声に衰えも感じられました。
しかし78年というこの頃の録音は、まさに脂ののったすばらしいノドを聞かせてくれます。
胸の奥からこんこんと溢れ出る太く逞しい、豊かな発声。
どんなに張り上げて歌おうとも、その声はオペラ歌手のように十分にコントロールされていて、
コクと艶のある響きはビクとも変わることがありません。
その天性ともいえる声の才能が十二分に発揮された、珠玉のようなアルバムです。
タイトルにもなっているオープニング曲の“Contigo Peru” は、
クリオージョ音楽の名作曲家アウグスト・ポロ・カンポスの名曲。
サンボの良き相棒であったギタリスト、オスカル・アビーレスの歯切れよいギターとともに、
クリオージョ音楽最高の演奏を聞かせてくれ、泣かされます。
サンボの歌はしょっぱい涙の味がするというか、
やるせない泣きの感情がこもっていて、聴くたびに胸に熱いものがこみあげてきます。
オスカル・アビーレスのほか、リンデール・ゴンゴーラやペペ・トーレスが伴奏を務めた曲もあり、
サンボに絡む合いの手のコーラスも含めて、その演奏ぶりにスキはありません。
セピア色のジャケットに写るサンボの表情も若々しい、
代表作に数えるべきCDがまた1枚増えました。
Zambo Cavero "CONTIGO PERU" Iempsa IEM668 (1978)
2010-10-11 00:09
コメント(0)
ベスト・パートナーズ ジャスティン・アダムズ&ジュルデー・カマラ [西アフリカ]


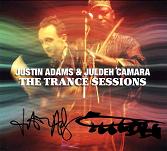
ティナリウェンを世界に知らしめた
ワールド・ミュージックのプロデューサーでギタリストのジャスティン・アダムズと、
ガンビアのフラニ人で1弦フィドルのリティを流麗に弾きまくる
ジュルデー・カマラのコンビが日本にやってくる!
そのニュースを聴いた時は、思わずガッツ・ポーズしちゃいましたね。
この二人は“SOUL SCIENCE” “TELL NO LIES” と2作連続で大力作を出した名コンビ。
ティナリウェン以降のアフリカン・ポップスで、ぼくがもっとも期待している二人なので、
そりゃあもう、ライヴの日を心待ちにしておりました。
そして迎えた10月7日の渋谷クラブクアトロ。
期待どおりのアフリカン・グルーヴを堪能しまくって、もう大満足。
ジャスティンとジュルデーにドラムス兼パーカッションがサポートするという、
バンドとしては最少人数ながら、その3人が叩き出すグルーヴのぶっといことといったら!
ジャスティンのギターを持った立ち姿は、
若いロッカーみたいにばっちり決まった痩身なんですけど、
ストロークの一振り一振りが確信に満ちていて、
筋肉隆々の逞しさを思わせる太いビートをはじき出すのです。
そこにジュルデーのリティが抜群のスウィング感で自在に絡みつき、
両者互いに前に回ったり後ろに回ったり、並んだりしながら、
縦横無尽なインプロヴィゼーションを繰り広げます。
ジュルデーがリティを弾きながらユニゾンで歌うヴォーカルも、力強かったですねえ。
そのゆるぎない堂々とした歌いっぷりは圧巻でした。
CDだとロック色を強く感じた曲も、ライヴのノリは完全にアフリカン・グルーヴそのもの。
ジャスティンって本当にイギリス白人なのか、アフリカ人なんじゃないの?と言いたくなるほど、
彼のビート感はアフリカン・マナーなセンスに貫かれていましたね。
ジャスティンの縦ノリのビート感とジュルデーの横揺れのスウィング感が絶妙にミックスされ、
まさに二人のコンビならではのグルーヴが快感でした。
ジャスティンがンゴニに持ち替えたり、
ジュルデーが2弦バンジョーのコロゴに持ち替えて演奏する曲や、
ジャスティンがベンディール、ジュルデーがトーキング・ドラムを叩きあう曲もありましたが、
二人の息のあったインプロヴィゼーションはまさに「対話」と呼ぶにふさわしく、
アフリカン・ポップス最高の演奏をこれでもかっ!てくらい全身に浴びまくった感じです。
“TELL NO LIES” ではマディ・ウォーターズをパクるような遊び感覚も富んでいたので、
ライヴではもっとギミックぽくなるのかなと思ったら、ぜんぜんそんなことはありませんでしたね。
マディのフレーズに、ボ・ディドリー・ビートを絡ませたりして、
本気でブルースとのミクスチャーを狙ってるふうでしたけど、
それがぜんぜん実験的なものとならず、さらりと自然に聴かせてしまうところなど、
ジャスティンのミュージカル・センスは完全にライ・クーダーを凌いでます。
二人のバツグンのコンビネーションを目の当たりにしながら強く印象に残ったのは、
ジャスティンにとっても、ジュルデーにとっても、
それぞれ互いがベスト・パートナーなんだなあということでした。
ジャスティンがMCでジュルデーを紹介するその言葉に、
ジュルデーをリスペクトしている気持ちがとてもよく込められていましたし、
終演後ジャスティンと少し話をした時にも、
「どうだい、ジュルデーって、すごいプレイヤーだろう」と褒めちぎっていて、
こういうプロデューサー気質というか、相手を立てるジャスティンの人柄が、
ティナリウェンのメンバーにも信頼されたんだろうなと感じました。
Justin Adams & Juldeh Camara "SOUL SCIENCE" Wayward 704 (2007)
Justin Adams & Juldeh Camara "TELL NO LIES" Real World CDRW170 (2009)
Justin Adams & Juldeh Camara "THE TRANCE SESSIONS" Real World RWEP17 (2010)
2010-10-09 00:17
コメント(2)
「アトラスのライオン」復活 ナジャ・アータブー [中東・マグレブ]
姐さん、お帰りなさいましっ!
モロッコ歌謡界最強の女性歌手ナジャ・アータブーの新作に、往年の輝きが戻りました。
ここ4~5年パワー不足のアルバムが続き、
ナジャもなんだか元気がなくなっちゃたなあと思ってましたが、
さすがは「アトラスのライオン」の異名を取るナジャ、ゴッド姐さんぶりはどっこい健在でした。
この新作では、滑舌よく母音を叩きつける激しい歌いっぷりが蘇り、
ひっくり返る裏声使いや、フレーズのお尻をくいっとヒネって歌うナジャ節が炸裂しまくってます。
二十年前はじめてナジャを聴いた時は、ぶったまげたもんです。
モロッコ人の気性の荒さは有名ですけど、そのイメージをさらに倍加させるような
激烈な歌いぶりに圧倒され、いっぺんでファンになりました。
ナジャが歌うアトラス地方のリズムを取り入れた都市歌謡シェイハートは、
アルト・ヴァイオリンのカマンジャ、ウード、ベンディールに、
シンセサイザーや打ち込みを加えたのが標準的な編成。
プロダクションのお粗末さは、ローカルなライやレッガーダと変わらず、歌手の力量が命。
歌さえ良けりゃあ、バックがどんなにチープだってオッケーってことです。
ライは世界市場に通用するプロダクションの作品もリリースされるようになりましたが、
ナジャはいまだローカル仕様のプロダクションに止まっているのが残念ですね。
リミッティの“N’TA GOUDAMI” に匹敵するようなアルバム、誰か作ってくれないもんかなあ。
ケミカル・ブラザーズがサンプルしたヤスっぽいテクノ・トラック、
“Galavanize” ぐらいでしか欧米のリスナーには知られてないナジャですが、
彼女の本当の底力を、広く世界にも知らしめてほしいものです。
Najat Atabou "KANEBKI ÂLA ZHAR LI MAÂNDICH" Fassiphone CDFES579 (2010)
2010-10-07 06:57
コメント(0)
神様のおくりもの セプテート・ナシォナール [カリブ海]

セプテート・ナシォナールの新作、もう聴かれましたか?
ライスからも『ルンバがなければソンはない!』のタイトルでリリースされましたが、
キューバ音楽ファンにとってはたまらない、それはそれは胸をすく快作です。
今年は春先にセプテート・アバネーロの結成90年作がリリースされ、
これでソンの二大名門楽団の新作が出揃ったというわけですね。
アバネーロがかつての泥臭さを懐古するかのような仕上がりだったのに対し、
ナシォナールはかなり現代的なソンの感覚が強く、
熱唱型のエウヘニオ・ロドリゲス “ラスパ” がバンド全体をぐいぐいと引っ張り、
スピーディーでキレのよいサウンドは、アダルベルト・アルバーレスに近いといえます。
いずれにせよ、イグナシオ・ピニェイロや
カルロス・エンバーレがいた時代のナシォナールとは、
まったく感覚の異なるサウンドとなっているわけです。
そこで、思わずかつての大傑作“SONES CUBANOS” にも手が伸び、
久しぶりに聴き返してしまったら、またまた目頭が熱くなってしまいました。
いやー、やっぱりこのアルバムの黒光りしたエレガントさは、唯一無二ですね。
だからこそ、ソンの最高傑作として名高いアルバムなわけですけど、
何度聴いても、はじめて聴いた時と変わらない感動が鮮やかに蘇ります。
カルロス・エンバーレのノドを締めた発声と、
そのエンバーレにコントラカントで絡んでくる
セカンド・ヴォーカルとの絶妙なコンビネーション。
トレスがどっしりと重厚なリズムを打ち出し、
濃厚なサボールがこんこんと泉のように湧き出る、
これほどキューバ音楽の深いコクを味わえるアルバムは、他にありません。
多くのキューバ音楽ファンがシーコ盤で愛聴してきたこのアルバムに、
オリジナル盤の存在があることを知った時は、それはビックリしたものです。
エル・スール・レコーズの原田さんが8年前にキューバへレコード買い付けした時に、
オリジナル盤を発見され、ファン騒然の大事件となったのでした。
しかもそのオリジナル盤であるシエラ・マエストラ盤の解説に62年9月の記載があったおかげで、
長年録音年不詳だったこのアルバムが、かつてインタビューでエンバーレが発言したとおり、
62年だったことも判明したのです。
原田さんにオリジナル盤を見せてもらった時は、
シーコ盤の安易なイラスト・ジャケとは大違いの、
風格あるジャケットのたたずまいにウナったものです。
その時は高価な貴重盤をお目にかかれただけで十分満足したのですが、
なんとその6年後に、某オークションであっけなく手に入ってしまったのには、
嬉しさを通り越して、ちょっとボーゼンとしちゃいましたね。
原田さんがシエラ・マエストラ盤を発見して以来、
古いキューバ盤を買い付けるバイヤーたちが、こぞって現地でこのアルバムを掘り出し始め、
ジャケぼろぼろの状態の悪い盤まで、その後ずいぶんとオークションに出るようになりました。
そんなこともあって、当初ぼくが手に入れられるはずもないと思ってた値段も、
あっという間に値崩れをおこし、次第にオークションでの過熱ぶりも冷めていったのでした。
そしてオークションへの出品も珍しくなくなっていた頃のこと、
めちゃくちゃコンディションの良い盤がひょっこりと出たのに誰もビットせず、
野口英世2枚より安い最低価格で、落札できてしまったというわけです。
あまりに拍子抜けというか、「嬉しさを通り越してボーゼン」だったわけですが、
キューバ音楽を長年愛し続けたご褒美に、神様が微笑んでくれたものと、勝手に思っています。
Septeto Nacional. Ignacio Piñeiro "¡SIN RUMBA NO-HAY SON!" World Village 468105 (2010)
[LP] Septeto Nacional De Ignacio Piñeiro "SONES CUBANOS" Sierra Maestra SMLD-P1 (1962)
2010-10-05 06:38
コメント(4)
ブラジリアン×イタリアン=コスモポリタン リカ・セカート [ブラジル]


リカ・セカート? なんか聞き覚えのある名前。えーと、坊主刈りの人じゃなかったっけ!?
でも、このCDにはロール・ヘアの金髪女性が写っているので、
ぼくの記憶違いかと思ったら、なんとおんなじ人。
髪を極端に短くしてたのは、“PELE”(99)、“CONSTELARIO”(01)の頃だけだったみたいですね。
リカはサンパウロ生まれのイタリア人。なので、本当はセカートじゃなく、チェカートと読むはず。
リカ・セカートと書かれているのは、ブラジル語の読みなんでしょう。
78年にイタリアでデビューした後、アメリカ、オーストラリア、ドイツと世界を又に駆けて活動していて、
94年のデビュー作はイタリア、2作目はドイツ、3作目はブラジルでリリースしています。
ぼくは3作目の“CONSTELARIO” でリカを知りましたが、
ジャズの素養をはっきりとうかがわせる安定感ある歌いっぷりに、
MPB歌手とは毛色の違う、個性的なシンガーという印象が強く残りました。
のちに、リカがバークリー音楽院に入学し、
「サラ・ヴォーン・ミュージック・アワード」を受賞したと聞き、
なーるほどねとナットクしたことをよく覚えています。
ロメロ・ルバンボやアルトゥール・マイアなど
錚々たるメンバーを従えたインディ盤“CONSTELARIO” は、
のちにメジャー・レーベルから再リリースされたと記憶しているので、
ブラジルでの評価も高かったはず。
リカはパリ、ケルン、リオに住まいがあり、この3都市を拠点に、
世界各国で活動するコスモポリタンな才女ですが、
海外のマーケットを意識している様子がなく、
持ち前のブラジリアン・センスをいかした音楽を、自然体でやっているところがいいですね。
先日来日したジアナ・ヴィスカルジ以上のマルチリンガルの人で、
6ヶ国語が堪能、しかも日本語まで読み書き自在というのだから、びっくりです。
新作は2曲を除き全曲自作という、シンガー・ソングライターとしての面を押し出した作品。
ボサ・ノーヴァの香り高いアクースティックかつジャジーなアルバムに仕上がっています。
バックをかためたメンバーがまた豪華で、ジャズ・ギタリストの重鎮エリオ・デルミーロに、
ロメロ・ルバンボやアルマンド・マルサルなどブラジルの実力者のほか、
ジョン・パティトゥッチ、リシャール・ボナ、ヴァーノン・リード、ロドニー・ホームズといった面々を揃え、
キレと深みのある歌いぶりで楽しませてくれます。
リカは04年、06年、07年、08年とたびたび来日していますが、
ぼくは毎度事後に知るというマヌケぶりで、いまだ観るチャンスに恵まれず(泣)。
近いうちにまた来日してくれることを願っています。
Lica Cecato "COPACABANA" Art Music LICA003 (2010)
Lica Cecato "CONSTELARIO" Mix House/Ouver 1004407-2 (2001)
2010-10-03 00:14
コメント(0)
ソダーデにこんがらがって ルーラ [西アフリカ]

カーボ・ヴェルデの女性シンガー、ルーラが去年出したアルバム、いいですね。
いままで以上に、カーボ・ヴェルデの伝統寄りのアルバムとなっています。
最初聴いたときは、ずいぶん地味な作品だなと思いましたが、
繰り返し聴くうちに、その地味なところが好ましく思えるようになりました。
ルーラを知ったのは、04年の3作目“DI KORPU KU ALMA”が最初。
モルナやフナナーなど島のリズムを取り入れた曲と、
R&B、MPB、アフロ・ズークの影響を受けたクレオール・ポップが無理なく同居していて、
ハツラツとしたのびやかさと、哀感のあるソダーデ感覚を併せ持ったポップ・センスが、
それまでのカーボ・ヴェルデのシンガーにない個性を感じさせました。
このアルバムはかなりヒットしたらしく、翌05年には2曲削って新たに3曲を追加したCDと、
ライヴ8曲にヴィデオ・クリップ2曲、インタヴューを収録したDVDとをカップリングした
新装版がリリースされました。
前作“M'BEM DI FORA”(06)は聴かないままとなってしまいましたが、
カーボ・ヴェルデ音楽の偉人B・レザの曲をタイトルにした5作目の本作は、
たおやかなアクースティック・サウンドに、
メランコリックなソダーデ感あふれるメロディーをのせた、
渋い味わいのアルバムに仕上がっています。
ポップさを抑えたことで、きりっとしたルーラのヴォーカルが、かえって輝いて聞こえます。
ルーラは、カーボ・ヴェルデが独立した75年に、
サンティアゴ島出身の父とサント・アンタン島出身の母のもと、リスボンで生まれました。
幼い頃からカーボ・ヴェルデ音楽になじみ、
カーボ・ヴェルデ人のアイデンティティを強く意識して育ったそうです。
17歳の時、サントメ・プリンシペのズーク・シンガー、
ジュカのアルバムにデュオ・ヴォーカルで起用され、
96年に自作曲で固めたデビュー・アルバムをリリースし、
その内容はアフロ・ズークとR&Bが半々といったものだったそうです。
カーボ・ヴェルデの伝統と今を繋いだルーラは、ディアスポラの立ち位置から離れ、
カーボ・ヴェルデ人としての足固めを確かなものとしたのではないでしょうか。
そんな実感がシンとした空気となって伝わってくるこのアルバム、
涼しくなってきた秋口によく似合います。
Lura "ECLIPSE" Lusafrica 562222 (2009)
2010-10-01 12:00
コメント(4)




