ポッピン・ジャズ・ヴォーカル エミリー=クレア・バーロウ [北アメリカ]
エミリー=クレア・バーロウ? 誰?と思ったら、カナダのジャズ・シンガーだそう。
はじめて聴く人でしたけど、1曲目のバカラックの「雨にぬれても」で即気に入りました。
これが8作目という新作は、60年代のヒット・ソングを取り上げたアルバム。
ジャズ・ヴォーカルというより、ポップ・センスに富んだヴォーカル・アルバムに仕上がっています。
なじみ深いヒット曲を小粋に料理していて、そのアレンジ・センスにウナったのですが、
なんとアレンジはご本人がしているというのだから、なかなかの才能です。
タイトル曲の“The Beat Goes On” に
“Soul Bossa Nova” をヌケヌケと差し挟んだアレンジなんて、
最初聴いた時は、思わず噴き出しちゃいました。ウイットのセンスも、なかなかですねえ。
ほかにも、ディランの「くよくよするなよ」をボサ・アレンジに仕立てのにもびっくり。
こんなキテレツなアイディアも、ぜんぜん違和感なく聞かせるんだから、恐れ入ります。
そのうえこの曲では、キュートなスキャットを披露してるんですけど、
そのなめらかなスキャットに、しっかりとした実力が表れています。
歌い口には、はっきりと現代っ子のニュアンスを感じる人ですけど、
温かみのある落ち着いた声質が耳に甘く響き、すっかり気に入ってしまいました。
昨年知ったソフィー・ミルマンといい、カナダっていいジャズ・シンガーがずいぶんいるんですね。
90年代以降のジャズ・ヴォーカルものって、偶然耳にしたのを聴いてる程度なので、
実はいまだにダイアナ・クラールすら、未体験。
そういえばダイアナ・クラールも、カナダのジャズ・シンガーでしたっけ。
ま、縁があれば、ダイアナもそのうち聴くチャンスがあるでしょう。
Emilie-Claire Barlow "THE BEAT GOES ON" Empress Music Group EMG445 (2010)
2010-11-30 06:39
コメント(0)
古風なサンバ ペリ [ブラジル]

前回パウラ・モレレンバウムのつつましさにホレたという話をしましたけど、
反対にぼくが苦手なのは、自意識が前に出るインテレクチュアルなタイプのアーティスト。
ブラジルだと、マリーザ・モンチやアドリアーナ・カルカニョット、
ギリシャならエレフセリア・アルヴァニタキといったあたりでしょうかね。
はっきりキライってほどじゃないんだけど、体質が合わないというか、ぼくはカンベンというか×です。
それぞれのファンの方には、すみません、という話なんですけども。
インテレクチュアルな自己主張より、持ち味で存在感を示せるアーティストの方がやっぱりいいなあ。
アーティストの「器の大きさ」というか、「格」のようなものとでもいえばいいでしょうか。
そういうものがあれば、余計な自意識を振り回さなくたって、メッセージは伝わってきます。
すでに過去の音楽であるボサ・ノーヴァを、いまどきやること自体がインテレクチュアルなので、
イヤミなくボサ・ノーヴァを歌えるアーティストを見つけるのは、案外難しいものです。
だからこそ、パウラ・モレレンバウムのつつましさは貴重なわけで、
男性シンガーはと見渡してみると、
ペリことペリアンド・コルデイロ・ノゲイラがいることに気付きました。
ペリはボサ・ノーヴァのシンガーではなく、サンパウロのシンガー・ソングライターですが、
ウィルソン・バチスタに捧げた曲や、
ネルソン・ゴンサルヴィスが取り上げたショコラーチのサンバを歌うなど、
古いサンバに親和性を持つ、ジョアン・ジルベルトの忠実な継承者ともいえる人です。
特に、ギターの弾き語りで通したペリの4作目“SAMBA PASSARINHO” は、
サンバのバチーダをギターに置き換えたジョアンのギター・サウンドを再現していて、
ボサ・ノーヴァの男性シンガーと見なしても、まんざらハズレでもありませんね。
このアルバムを聴いた時は、ちょっとびっくりしました。
ギター1本でサンバ・カンソーンからボサ・ノーヴァまでさらりと歌ってのける才能は、
デビュー時のカエターノをほうふつとさせ、甘酸っぱくやわらかな歌い口にもトロけました。
また、CDパッケージも秀逸で、音楽ソフトがネット配信に移行しつつある時代に、
CDを作ることにこだわったデザイナーの良心ともいうべき作品に仕上がっています。
扉の開いた鳥かごが描かれたブルーの塩ビ・ケースから、
中に入った二つ折りの紙ケースを引き出すと、
かごから飛び立つ小鳥が出てくるというシンプルな線画が描かれています。
さらに紙ケースを開くと、青空に浮かぶ白い雲の鮮やかな写真が現れます。
青と白を基調とした塩ビ・ケースと紙ケースのすみずみまで神経を配ったデザインは、
もの作りにこだわるデザイナーの職人気質を感じさせる仕上がりで、
アートの街サンパウロならではの作品といえます。
シンプルなデザインながらその高いクオリティは、中身の音楽とも見事にシンクロしたものでした。
このアルバムのゆいいつ残念な点は、ラストのクラブ・ミックスが蛇足なこと。
ギター1本で、サンバの落とし子たる音楽をここまで聴かせる才能の持ち主が、
クラブ・ミックスなんて通俗的な流行に色目を使ったのは、ちょっとがっかりです。
それだったら、ノスタルジックなマルシャにアレンジするような気概をみせてほしかったなあ。
このラスト・トラックをオミットすれば、パーフェクトです。
そして“SAMBA PASSARINHO” の次作、“SEGUNDO TEMPO” もまた秀作でした。
今度はヴィオローンからエレキ・ギターに持ち替え、スモール・コンボをバックに歌うという趣向。
ジャズ・ギターのトーンで弾くバチーダとブラシが刻むドラムスがジャジーで、なんともクールです。
スティックでエイト・ビートを叩くドラムスとバチーダを絡ませた曲なんてのもあり、
ふつうサンバでこんなドラムスの使い方をしたら最悪になりそうなところ、
見事なリズム処理を聞かせてくれるんだから、そのセンスには舌を巻きます。
う~ん、才人ですねえ。
こういうさりげない振る舞いで懐の深さをみせるアーティストが、ぼくは好きです。
Péri "SAMBA PASSARINHO" Baticum no number (2005)
Péri "SEGUNDO TEMPO" Baticum no number (2008)
2010-11-28 00:22
コメント(0)
つつましいボサ・ノーヴァ歌い パウラ・モレレンバウム [ブラジル]

パウラ・モレレンバウムはかつてのボサ・ノーヴァの味わいを体現できる数少ないシンガーです。
パウラの歌声に魅せられたのは、パウラのご主人でチェロ奏者兼アレンジャーの
ジャキス・モレレンバウムと坂本龍一がコラボした“CASA” がきっかけでした。
その後リリースした“A DAY IN NEW YORK” でも、
パウラは素晴らしい歌声を聞かせていましたね。
ところが、その後のソロ・アルバム“BERIMBAUM” では、
ボサクカノヴァやセルソ・フォンセカによるクラブ仕様のプロダクションが
パウラの歌声を殺していて、大幻滅。
イマドキのこじゃれたプロダクションでは、古風な佇まいを持つパウラの個性は損なわれるだけです。
今度の新作は、ジョアン・ドナートとの共同名義によるドナート作品集となりましたが、
麗しいパウラの歌声が蘇り、“BERIMBAUM” の雪辱を果たす快作となりました。
ドナートが昨年リリースしたジャズ・サンバ作品“SAMBOLERO” も
現役復帰後の最高作でしたけど、中音域を豊かに鳴らすドナートの穏やかなピアノ・タッチや、
フェンダー・ローズを想わせる懐かしいエレピ・サウンドは、今作でも快調ですね。
パウラの歌声とも相性バツグンで、しなやかなサウンドが極上のボサ・ノーヴァを紡いでいます。
パウラの声質ってクリアなんだけど、適度な湿り気を帯びていて、
それが落ち着きのある表情につながっているんですね。
主張しない声と、余計な自意識を感じさせない歌いぶり、そのつつましさにホレてしまいます。
本作にはアップ・トゥ・デートなプロダクションも施されているとはいえ、
クラブ・サウンドのような派手なものではなく、あくまでも控えめなので、
落ち着きのあるドナートのピアノ・サウンドにもよく馴染んでいます。
歌の途中で唐突に日本語が登場する“A Paz” のしなやかな美しさは、この二人ならではですね。
Paula Morelenbaum & João Donato "AGUA" Biscoito Fino BF992 (2010)
2010-11-26 07:11
コメント(4)
晩秋の薫り イヴァン・リンス [ブラジル]
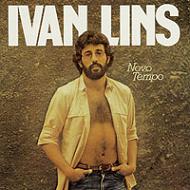
銀杏の落ち葉で街路が黄色い絨毯となる季節。
落ち葉を踏みしめる「さく、さく」という音が、晩秋から初冬へと向かう序奏を導きます。
そんな季節になると必ず手が伸びるのが、イヴァン・リンスの“NOVO TEMPO”。
このアルバムに出会ったのが大学4年の秋なら、
人生の折々の季節で、このアルバムにさまざまな思い出が加わったのも、いつも秋でした。
初めてこのアルバムを聴いた時は、これがブラジルの音楽なのかと驚いたものです。
まるでフランス映画を観ているみたい、そんな言葉が思わず口に出るほど、
イヴァンが紡ぐヨーロッパ的なメロディーと、
ジルソン・ペランゼッタが施す映像的なサウンドに魅了されました。
ブラジル音楽を聴いて「フランス映画みたいな」と思ったのは、このアルバムが初めてではなく、
アントニオ・カルロス&ジョカフィの73年作“ANTONIO CARLOS E JOCAFI” (乞CD化)の
B面5曲目“Um Abraço No Lucien Extensivo Ao Edu” が最初でした。
その洗練されたメロディーや曲想は、過去聴いたどんなブラジル音楽にもなかったもので、
そのヨーロッパ的なセンスがどこから来ているのか、不思議でなりませんでした。
アントニオ・カルロス&ジョカフィ以来ともいえる、
イヴァン・リンスのメロディー・センスが発揮された本作では、
4曲目の“Barco Fantasma” が白眉。
せつなさ、哀しみ、愛おしさといった感情がないまぜとなったメランコリックなメロディーは、
まさしくイヴァン・リンスの真骨頂でしょう。
イントロがまた鮮烈で、バンドリンがどこか異国風のエキゾティックなメロディーを奏でるんですね。
バンドリンといえばショーロといった常識を覆すバンドリンの使い方に驚くとともに、
従来のブラジルのメロディーにはないフレージングにも魅了されたのでした。
そして5曲目の“Setembro - Caminho De Ituverava” では、
幾重にも重ねられた甘美なコーラスと、ソプラノ・サックスが奏でるメロディーが実に映像的で、
秋の陽の光が紅葉の間から射し込み、赤や黄や橙がプリズムのように乱反射するさまや、
まぶしく見上げた青空にうろこ雲が高く広がる風景が、ぼくの瞼には写るのです。
このアルバムでイヴァンは、けっこう社会派な内容を歌っているんですけど、
センチメンタルなメロディーがまぶされた曲の数々に、
せつない恋の記憶をだぶらせたとて、誰が責められましょう。
ぼくにとって本作がイヴァン・リンスのベストであることは揺るぎなく、
次いで74年の“MODO LIVRE”、そして87年の“MÁOS” が個人的ベスト3です。
え? 世間ではイヴァンの最高作といわれる
77年の“SOMOS TODOS IGUAIS NESTA NOITE” が入ってないって?
個人的にそれはベスト4ですね。ついでにベスト5が81年の“DAQUILO QUE EU SEI” です。




Ivan Lins "NOVO TEMPO" EMI 857900-2 (1980)
Ivan Lins "MODO LIVRE" RCA 74321864142 (1974)
Ivan Lins "MÁOS" Philips 832262-2 (1987)
Ivan Lins "SOMOS TODOS IGUAIS NESTA NOITE" EMI 857898-2 (1977)
Ivan Lins "DAQUILO QUE EU SEI" Philips 04400164212 (1981)
2010-11-24 06:43
コメント(0)
円熟したアラベスクの女王 キバリエ [西アジア]

トルコ歌謡アラベスクの女王さま、キバリエの最新作がリリースされました。
04年の“BEN AYAKTA AĞLARIM” 以来で、しばらくぶりーと思ったら、
06年と08年にもアルバムは出ていたらしく、ぼくが気付いていなかっただけみたいです。
かつてのキバリエは、いかにもジプシー出身らしいハスキー・ヴォイスを駆使して、
コブシをぐりんぐりんに回してたものでしたが、
この新作では一歩後ろに引いた奥行きのある歌唱を聞かせ、
キバリエも円熟したなあと感じ入りました。
ごりごりの歌唱から力が抜けたことによって、さらに存在感を増したキバリエは、
アラベスクの帝王イブラヒム・タトルセスの円熟ぶりと、足並みを揃えているようにも思えます。
トルコ歌謡アラベスク界はこの二人がいる限り、安泰ですね。
のっけがタルカンの曲で、コーラスにタルカンもゲストとして加わっているんですけど、
やけに存在が薄くって、クレジットがなければ気付かないほどです。
アラベスクらしい豪華なストリングス・アンサンブルと、
ベリーダンス風のリズム・セクションをベースとしながら、
ピアノ伴奏でじっくりと聴かせる曲あり、ジタン風のギターをフィーチャーしたルンバ調の曲あり、
バグラマーが泣きのフレーズをたっぷりと奏でる曲ありと、手を変え品を変え、楽しませてくれます。
ラストのジプシー・サウンドをダンサブルに仕上げた9拍子曲も、聴きごたえがありますね。
女タトルセスと呼ぶにふさわしい安定感と重量感を示した、ヴェテランらしい作品です。
Kibariye "4 MEVSİM" Avrupa Müzik no number (2010)
2010-11-22 06:40
コメント(0)
世界へ拡散するエチオ・ジャズ ウォイマ・コレクティヴ [西・中央ヨーロッパ]

「ティジータ」というタイトルに、むむっと手が伸びました。
ティジータとは、エチオピアのいわば、ブルース。
日本のヨナ抜き音階にも似たエチオピアの旋法が、独特の情感を醸し出す泣き節ですね。
<エチオピア人の心のふるさと>とも形容される、せつせつと歌われるエチオピアの情歌です。
そんなタイトルを付けたドイツのファンク・バンドのアルバムって何?と思って聴いてみたら、
本格的なエチオ・ジャズのインスト演奏が飛び出してきたので、ブッたまげてしまいました。
全トラックとも見事にエチオピアン・マナーな、オリエンタルかつエキゾティックなメロディー揃いで、
ドイツ人がよくまあこんなメロディーを書けるもんだと感心しきり。
なんでもこのグループは、ドイツのディープ・ファンク・バンド、
ポエッツ・オヴ・リズムのサックス奏者ヨハネス・シュライエマハーが
新たに始動させたユニットだそうで、全曲ヨハネスが作曲した本作がデビュー作とのこと。
ヨハネスはムラトゥ・アスタトゥケに教えを乞うてエチオ・ジャズを習得したというのですから、
本格的なのも道理で、ソングライティングもムラトゥ直伝ってわけですね。
ヨハネスはエチオ・ジャズのほかにモロッコの音楽にも強く影響を受けたとのことで、
6曲目のイントロでちらりと表れるグナーワを思わせるカルカベのリズムに、
その片鱗が表れています。
本作のクレジットで、おやと目を引いたのは、ゲストで1曲参加しているガーナのエボ・テイラー。
前回取り上げたエボ・テイラー復帰作のバックを務めたアフロビート・アカデミーが、
ポエッツ・オヴ・リズム人脈のグループなので、その縁で友情出演したのでしょう。
かつて、はじめてアンティバラスの“WHO IS THIS AMERICA?”(04)を聴いた時、
「白人でもこんな本格的なアフロビートを演奏できるのか!」と衝撃を受けましたけど、
このウォイマ・コレクティヴから受けたショックも、アンティバラスの時と同種のものでした。
もちろん非エチオピア人によるエチオ・ジャズという分野では、
ボストンのイーザー/オーケストラという先達もいますけど、
非アフリカ人によるアフリカ音楽のトレンドが、
アフロビートからエチオ・ジャズへと移りそうな予感のするアルバムです。
次作は、ぜひエチオピアのシンガーをフィーチャリングしたアルバムを期待したいですね。
Woima Collective "TEZETA" Kindred Spirits KS032CD (2010)
2010-11-20 00:17
コメント(2)
アフリカのヴェテラン復活続く エボ・テイラー [西アフリカ]

アフリカ大陸で多くの新興国が独立を果たした「アフリカの年」から半世紀を迎えた今年、
ありし日のアフリカ音楽を蘇らせるかのようなアルバム・リリースが続いたのは、偶然でしょうか。
これまであまり注目されることのなかった、地味なヴェテラン・ミュージシャンたちが
魅力的なアルバムを出しているのは、注目に値します。
今月号の『ミュージック・マガジン』で紹介したコンゴのブンバ・マッサや、
ナイジェリアのジュジュのオールド・タイマー、
オラセニ・テジュオソのソロ作のようなレトロ・サウンドにもトロけましたけど、
ちょっとびっくりしたのが、ガーナのハイライフの大ヴェテラン、エボ・テイラーの新作。
ここ最近聞いたアフロビートでは出色の演奏内容で、思わず引き込まれてしまいました。
これが74歳になるエボ・テイラーの新作というのだから、驚かされます。
バックを務めるのは、ベルリンをベースに活動しているアフロビート・アカデミー。
ドイツ人、アメリカ人、カナダ人、ガーナ人からなる多国籍ユニットです。
ざらっとした音色のオルガンや、ホーンズの鳴り、ポリリズミカルなドラミングなど、
往年のアフリカ70を思わせるサウンドを繰り広げていて、いやー、燃えますねえ。
いまやアフロビートが完全にユニヴァーサルな音楽となったことを実感します。
エボ・テイラーは21歳でハイライフの名門バンド、スターゲイザーズに参加したギタリストで、
62~65年のロンドン留学時代には、フェラ・クティと同じ音楽学校に通った友人同士。
70年代以降はプロデューサー兼音楽監督として、
C・K・マン、パット・トーマス、ジュウェル・アッカーなど多くの後進たちを育て、
エボ自身も数多くのソロ・プロジェクトを手がけました。
当時の録音は、サウンドウェイやアナログ・アフリカでも復刻されていますね。
20年ぶりのレコーディングという本作では、アフロビートを核としながらも、
ハイライフやアフロ・ソウルもしっかりと取り上げていて、
アフロビート一辺倒にしていないところが好感を持てます。
特に3・5・8曲目のハイライフなど、いかにもガーナらしいメロディが飛び出し、思わずニンマリ。
ドラムスとパーカッションがガーナ人なので、ハイライフの演奏も本格的です。
キャッチーなアフロビートばかりでなく、
こういうハイライフにも注目が集まってほしいなと思います。
Ebo Taylor "LOVE AND DEATH" Strut STRUT073CD (2010)
2010-11-18 06:41
コメント(0)
人生は楽し パパ・ウェンバ [中部アフリカ]

パパ・ウェンバが主演した映画“LA VIE EST BELLE”(87)がDVD化されました。
日本では一般公開されず、「アフリカ映画祭'89」で3回上映されただけなので、
観た方は少ないかもしれませんが、なかなか面白い映画なんですよ。
芸術祭向けのマジメなテーマが多かった「アフリカ映画祭'89」の参加作のなかでも、
出色の娯楽作品だったことをよく覚えています。
プロ・ミュージシャンを目指して首都キンシャサに上京した田舎出の青年が、
靴磨きやナイトクラブを経営するパトロンのハウス・ボーイをしながら成功を夢見る、
といったあらすじのコメディーです。
音楽と恋愛というエンタメ二大要素を中心に据えながらも、
アフリカの矛盾に満ちた都市生活を見事にあぶり出しているところが秀逸なんですね。
労働者と富裕層の厳然たる貧富の差や、一夫多妻の問題、
近代的な生活をしながら呪術師に頼る日常生活など、近代と伝統の拮抗といったテーマを
実にうまく活写していて、キンシャサの現実を見せてくれました。
田舎出の青年クル演じるウェンバほか、恋人役のカビビ、歌手として登場するペペ・カレなど、
俳優は素人ばかりなのに、皆演技が巧いのには感心させられましたね。
この作品はコンゴとベルギーの共同制作ですが、
監督は50年ブカブに生まれた生粋のコンゴ人、ムエゼ・ンガングラが務めました。
ンガングラ監督初の長編映画であるとともに、
コンゴの一般の映画館で上映された、初の長編映画でもあったそうです。
それまでのコンゴには国産の映画がなかっただけに、大ヒットとなったわけですね。
主役にキンシャサの庶民が憧れるパパ・ウェンバが演じたのだから、なおさらです。
当時サウンドトラック盤もリリースされ、日本にも入ってきたので、映画を観たことはなくても、
ウェンバの歌う“La Vie Est Belle”(人生は楽し)を聴いたことのある人は、
結構いるんじゃないんでしょうか。
DVDには字幕が付いてないので、フランス語がわからない人にはちょっとキビしいかもしれません。
ぼくもフランス語はまったくダメなので、昔観た字幕付映画の記憶でなんとか理解できましたけど、
はじめて観る方は、その点だけご注意ください。
[DVD] Ngangura Mweze "LA VIE EST BELLE" Rue Stendhal 0070-2 (1987)
2010-11-16 06:40
コメント(2)
芸歴40周年 エバ・アイジョン [南アメリカ]
ペルーのエバ・アイジョンが、今年で芸歴40周年を迎えました。
まだぼくは聴いてないんですが、ペルーでは記念アルバムもリリースされたようです。
昨年のアルバム“QUIMBA, FÁ, MALAMBO, ÑEQUE” でも
堂々たる歌いっぷりを披露してくれていたので、
どんな仕上がりになっているのか、楽しみです。
セリア・クルース亡き後のラテン世界で、
エバ・アイジョンが最高の女性歌手とぼくは信じていますが、
十年くらい前に比べれば、声に潤いがなくなって粗さが感じられるようになったのと、
一部の曲で不自然な力みが感じられたりと、
多少大味な面もみられるようになったのは少し気がかりです。
ヴェテランらしい円熟が臭みとならないよう、
年齢との折り合いを上手くつけていってもらいたいですね。
そういう意味でいうと、エバが最高の絶頂期にあった
15年前にライヴ体験できたのは、本当にラッキーでした。
1995年8月15日、川崎・幸文化センターで観たエバのステージは、
ぼくが生涯観たライヴのなかでも五本指に入る、忘れられないものです。
そのコンサートは在日ペルー人が招聘したもので、
工場などで働くペルー人たちの盆休みをあてこみ、
8月13日群馬県大泉町、15日川崎市幸区、17日静岡市の日程で行われたもの。
なんせ日本人なんか相手にしていないコンサートだから、
お客さんはペルー人のみ。日本人なんてぼく以外に10人いたかどうかでしたね。
会場には看板や垂れ幕はおろか、ポスターひとつ貼ってなかったので、
ペルー人が大挙して集まっているのに、近所の住民が不審な目を向けてましたっけ。
幸文化センターは当時ぼくが住んでいた鶴見から車で10分くらいのところで、
ぼくはエバに贈る花束を用意して開演5時間前に行き、スタッフたちとおしゃべりをしてたんですが、
開演を迎えるまでちょっとしたひと悶着がありました。
なんでも前々日の群馬でのコンサート終了後、ギャラの件でモメたとかで、
メンバーたちは会場入りしたものの、エバは今日は歌わないとおかんむり。
開演前のサウンド・チェックにも現れないばかりか、
開演30分前のブザーが鳴っても現れなかったのです。
スタッフはまっつぁおで右往左往、ホテルでエバを必死に説得し続け、
「中止」の文字もちらつき始めた開演予定時刻を1時間すぎたところで、
エバがようやくタクシーで到着。
楽屋入りしてあっという間に着替えたかと思ったら、到着して3分とたたずに舞台に立ち、
歌い出した早業に、ぼくは舞台袖からただ呆然、口アングリでした。
散々待たされたペルー人のお客さんたちは、
のっけから興奮のるつぼ。
ぼくもあわてて楽屋裏から会場へ向かうと、
自分の席がない!
チケットには「お列31番」とあるのに、
座席番号は25番までって、おい、おい。
まー、ラティーノらしいお仕事ですこと。
席はけっこう空いてたので、
問題はぜんぜんありませんでしたが。
そうして始まったコンサートは、
そんなトラブルをおくびにも出さない、
それは見事なものでした。
メンバーとのかけ合いで盛り上げる
ステージングの旨さ、観客のあしらい方は、
まさに女王様でした。
ステージ終了後、無事エバに花束を渡すこともでき、
ツーショットで撮った写真も宝物となりました。
そんなエバの15年前のステージを思い出させてくれるのが、
06年8月2日でのハリウッド・ライヴを収めたこのDVDです。
オープニングが94年の“PARA TENERTE”収録の“Andar Andar” で、
ひときわ大きな歓声を受ける“Regresa” は“GRACIAS A LA VIDA”収録曲と、
やっぱりあの当時がエバの黄金期だったことを象徴しているかのようです。


しかしこのDVDは、日本で観たステージよりショーアップされていて、
フェステーホではぴちぴちの肢体がまぶしい若い女性ダンサー4人が舞い、
パーカッショニストの二人が見事なタップを披露する場面や、
アレックス・アクーニャも加わり、カホンを4人で競演するなど、見せ場がたっぷりです。
レパートリーも“Toro Mata” “Fina Estampa” の名曲から、
オドロキのEW&Fの“Fantasy” まで、114分たっぷりと楽しめます。
エバ・アイジョン 1995年日本公演 チラシ
[DVD] Eva Ayllón "EN VIVO : LIVE FROM HOLLYWOOD" Nemo Presents no number (2006)
Eva Ayllon "GRACIAS A LA VIDA" Discos Independientes CD9013 (1993)
Eva Ayllon "PARA TENERTE" Discos Independientes CD9036 (1994)
2010-11-14 00:10
コメント(2)
シカゴ・ブルースの若頭 ジュニア・ウェルズ [北アメリカ]

うぉっ、66年のジュニア・ウェルズのライヴ音源! こんなのがまだ出てくるんだぁ。
しかも共演はジ・エイシズですよ。う~ん、シビれますねえ。
66年といえば、かの名盤“HOODOO MAN BLUES”をリリースした翌年、
まさにジュニアが一本立ちして、伸び盛りの時期のライヴじゃないですか。
音質はけっして良好とはいえませんが、そんな音質をものともしない内容の充実ぶり。
1曲目から若さほとばしるジュニアの男っぷりに、圧倒されます。
ジュニアの艶っぽいヴォーカルに瞬発力のあるハーモニカ・プレイ、
MCもナマナマしく臨場感たっぷりで、ジュニアってほんとに色気あるなあ。
シカゴ・ブルースの定番ナンバーを揃えたレパートリーも、
当時のジュニアの充実度を見事に伝えていますね。
そしてバックを支えるフレッド・ビロウのしなやかなドラミングにも、背筋がぞくぞくします。
シャッフルでのビロウのドラミングの気持ちよさといったら、もー、最高。
バンド全体を包み込む大きなウネリを作り出しているのは、ビロウのプレイならではでしょう。
ジュニアとジ・エイシズは50年代初め、フォー・エイシズとして活動してたので、
これは再会セッションともいえるわけですけど、日本人にとってはこの共演って、
第1回と第2回のブルース・フェスティバルのタッグ・マッチみたいなもの。
知ってますか? ブルース・フェスティバル。
第1回は1974年、ぼくは高校1年生でしたけど、
ロバート・ジュニア・ロックウッドとジ・エイシズをナマで観れたなんて、
今思えば、すごい体験ができたもんです。
そして翌年の第2回では、ジュニア・ウェルズとバディ・ガイがやってきたんでした。
この時は、酔っ払いのブルース・ファンがジュニアに心ないヤジをとばし、
最悪の雰囲気になったんです。あの不快な記憶と後味の悪さは忘れられません。
あの当時のブルース・ファンって、ガラは悪いし、小汚い連中が多くて、
あんな大学生にはなりたくないねーって、ひそかに思ってたことを覚えてます。
ジュニアはソウルふうのファッションをバチッとキメて、カッコよかったんですけどね。
ビンボくさい格好してブルース・ファンを気取るような頭でっかちには、
ジュニアのヒップなカッコよさがわかんなかったんでしょう。
Junior Wells & The Aces "LIVE IN BOSTON 1966" Delmark DE809
2010-11-12 06:55
コメント(2)
とどめなき涙 エルザ・ソアレス [ブラジル]

ベッチ・カルヴァーリョのボックスに続いて、エルザ・ソアレスのリイシューCDが届きました。
楽しみにしていたのは、74~76年のタペカール盤3タイトル。
すでにブラジルEMIがボックス・セットでCD化してますけど、
あの時は2イン1でしかもCCCDでしたからねえ。
今回は初のオリジナル・フォーマットによるCD化のうえに、
それぞれボーナス・トラック入りとあって、嬉しい限りです。
3作ともよく聴いたアルバムですけど、
やっぱり一番思い入れ深いのは、74年の“ELZA SOARES” でしょうか。
A面がレジォナール編成、B面がオーケストラ編成のバックとなっていて、
エルザの強烈なハスキー・ヴォイスをいかした、
ヴァイタリティあふれるサンバがぎっしりと詰まっています。
いやー、ほんとによく聴いたよなあ。
2イン1でCD化された時にも聴いたので、あまりひさしぶりって感じはしませんでしたけど、
三十年前にはじめて聴いた時ノックアウトされた、エルザのパンチの効いた歌いぶりは、
まったく古びることがありません。
このアルバムの最大の聴きどころは、2曲目の“Pranto Livre”(「とどめなき涙」)。
エルザ一世一代の絶唱といえるサンバで、その歌唱はソウルフルと呼ぶにふさわしいもの。
まぎれもなく70年代サンバの名唱で、サンバ・ファンには忘れることのできない1曲です。
はじめてフランス・ソノ・ディスク盤で聴いたこの1曲で、魂抜かれたんでした。
そうそう、その後どうしてもオリジナルのタペカール盤が欲しくなって、
知人のつてを頼って、ブラジルに駐在されている方にお願いして、
レコードを買って送ってもらったんだっけ。その節はお世話になりました。
どーしても欲しいレコードがあると、あのてこのてで探し回り、
なんとしてでも手に入れる執念深さは、われながら業が深いと認めざるをえませんね。
Elza Soares "ELZA SOARES" Tapecar/Discobertas DB051 (1974)
2010-11-10 06:47
コメント(0)
雑食性豊かなジュジュの楽しさ ファタイ・ローリング・ダラー [西アフリカ]

ジュジュの歴史をひととおりおさらいした後に、
ファタイ・ローリング・ダラーを知ったのはラッキーでした。
トゥンデ・ナイチンゲール、I・K・ダイロ、
エベネザー・オベイ、サニー・アデといった、
ジュジュの正史を飾るミュージシャンたちに夢中だった頃に聴いたら、
ジュジュの本流とは少し違ったポジションにいたファタイの面白さが、
わからなかったからもしれないからです。
ファタイはジュジュではなく、
アギディボからキャリアをスタートさせたミュージシャンです。
アギディボというのは、キューバのマリンブラやジャマイカのルンバ・ボックスに良く似た
大型の親指ピアノで、4つから6つくらいの弁が付いた低音用のリズム楽器の名前ですけど、
40年代にレゴスで流行したダンス・ミュージックの名前でもあるんですね。
アギディボは貧しい庶民の間で演奏されていたアシコやコンコーマから発展した音楽で、
雑食性の強い性格を持っていましたが、やがてジュジュと合流して、
ヨルバの伝統を色濃くした音楽へと性格を変えていきます。
ファタイと同い年で、ジュジュ色の強いハイライフのミュージシャン、
アデオル・アキンサニャも、もとはアギディボのミュージシャンでした。
50~60年代に活躍したファタイ・ローリング・ダラーは、アギディボやパームワイン、
そしてジュジュ・ハイライフなど、ジュジュ周縁の音楽も盛んに演奏していました。
ファタイは当時のギタリストのなかでもトップ・クラスの腕前を誇り、
往年の録音はトゥンデ・ナイチンゲールとのカップリングCDで聴くことができます。
CDで聴けるファタイのゆいいつの録音ですね。
カムバック後にも再演された“Sisi Jaiye Jiaye” “Won Kere Si Number Wa”
“She Go Run Away” のオリジナル録音もこのCDに収録されています。
エベネザー・オベイがファタイのバンドでキャリアをスタートさせたのも有名な話で、
オベイはアデオル・アキンサニャに憧れて音楽を志し、
ファタイのバンドで修行を積んだのだから、面白い縁ですね。


ファタイは68年に音楽ビジネスから離れ、隠居生活を送っていましたが、
03年に四半世紀ぶりの現役復帰を果たし、
ジャズホールから2枚のアルバムをリリースしました。
オベイやアデが競い合ったジュジュの黄金時代もとうに過ぎ去り、
ノスタルジックな響きのファタイのジュジュが新鮮に響く、
いい時代にカムバックしたといえます。
“WON KERE SI NUMBER” のVCDもあてぶりとはいえ、楽しめます。
そして07年には、50~60年代録音と新録を織り交ぜた
“PAPA RISE AGAIN” をリリースしました。
ざっくりとした手触りのアクースティック・サウンドに
ファタイのサビの効いたヴォーカルが映える、
ヨルバ・ポピュラー音楽史の生き証人らしいレパートリーの豊かさが、
極上のアルバムとなっています。
ぼくはカンゲキして『ミュージック・マガジン』にも紹介したんですけど、
イギリス・エコスター盤は流通事情が悪くて日本に入ってこず、
その代わりにナイジェリア盤が入ってきました。
このアルバムの素晴らしいところは、ファタイの幅広い音楽性を回顧した点にあります。
パームワインやアギディボといった古いスタイルの音楽から、
ミュート・トランペットの響きものどかな
ジュジュ・ハイライフやアフロビートまでやっています。
ファタイはフェラとも親交があり、引退直前にはアフロビートまで演奏し、
引退後にはフェラのカラクタ共和国の隣近所で暮らしていたんだそうですね。
このアルバムには当時録音したアフロビートと、
新録のアフロビートが収録されています。
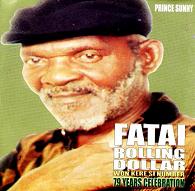

ファタイはカムバック後も精力的に活動を続けていて、
06年にはヨーロッパ・ツアーもしており、
ドキュメントDVDや伝記本の出版なども予定されていましたが、これはまだのようですね。
79歳や82歳の誕生パーティ(タイトルの「83歳」はおそらく間違いでしょう)の
VCDでもかくしゃくとしていて、ギターをがんがん弾いていました。

ジャズホールからアルバムがリリースされたので、すわ新作かと色めきたったのですが、
残念ながら03年の“RETURNS” から2曲“Omolere Aiye (Dance Mix)”
“Easy Motion Tourist (Jazzy Mix)” を削り、04年の“WON KERE SI NUMBER” の2曲
“Eko Akete” “I'm Not A Banker” に、未発表曲の“Omo Oloye”を加えたもの。
そろそろ新作も期待したいところです。
Tunde Nightingale, Fatayi Rolling Dollar "TUNDE & FATAYI" Jofabro/Thomas Organization FMTOPCD012
Fatai Rolling Dollar "RETURNS" Jazzhole JAH006D (2003)
Fatai Rolling Dollar "WON KERE SI NUMBER" Jazzhole JAH009D (2004)
[VCD] Fatai Rolling Dollar "WON KERE SI NUMBER" High Kay Dancent Limited no number
Fatai Rolling Dollar "PAPA RISE AGAIN" Ekostar EKOCD010 (2007)
Fatai Rolling Dollar "PAPA RISE AGAIN" High Kay Dancent Limited no number (2007)
[VCD] Fatai Rolling Dollar "79 YEARS CELEBRATION" Prince Sunny no number (2007)
[VCD] Fatai Rolling Dollar "ROLLING DOLLAR @83" Albasit Music no number (2010)
Fatai Rolling Dollar "RETURNS" Jazzhole JAH012CD (2010)
2010-11-08 00:15
コメント(0)
コロンビアのお祭り音楽 ペドロ・ラサ [南アメリカ]

ペニャランダと一緒に見つけたのが、ペドロ・ラサのアルバム。
ヴィンテージ時代のコロンビア音楽が見直されるきっかけとなった、
イギリス・サウンドウェイ盤“COLOMBIA!: THE GOLDEN YEARS OF DISCOS FUENTES”の
ジャケットを飾った人といえば、若い人にもわかってもらえるはず。
ペドロ・ラサとペラジェーロスのアルバムはLP時代にもたくさんありましたけど、
ぼくはペドロ・ラサとバンダ名義の本作がお気に入りでした。
いかにもラテンな雰囲気の美人ジャケも、なかなかいいでしょ?
まさかこのアルバムがストレートCD化するとは思いもしなかっただけに、大カンゲキ。
クレジットによると09年にCD化されたようですが、
編集盤中心のフエンテス盤CDで、ストレート・リイシューされたのって珍しいんでは。
60年代頃のペドロ・ラサとバンダの編集CDを聴くと、
オーケストラによるきちっとアレンジされた端正なダンス・サウンドで、
いかにもフエンテスのハウス・バンドらしいプロっぽい演奏を繰り広げていますが、
本作のなまなましさは、それとは対極のもの。
太鼓、シンバル、カウベルが生み出す強烈なリズムに加え、
ブラスがぶんちゃか、ぶんちゃかと派手なグルーヴを巻き起こします。
ブラスはユニゾンやハーモニーをつけたリフを吹くばかりでなく、
思い思いのラインを鳴らしながら絡み合う、集団即興的な部分もあってスリリング。
ブラスの鳴りもなまなましく、威勢のいいかけ声もお祭りムードを高め、
聴いているだけでドキドキしてきます。
特に7分に及ぶメドレーなど、コロンビアーナ・ジャム・セッションといった趣で、
スネア・ドラムが高らかに乱打されるインタープレイが大迫力。
その一方、LPの両面ラストのヴァルスでは、ぶんちゃっちゃっ、ぶんちゃっちゃっと、
ヨーロッパ的なワルツそのものの演奏で、アフロ成分ゼロなところが面白いですね。
収録時間は31分足らずという短さですが、
ハジけるようなコロンビアのお祭り音楽を堪能できる一枚です
Pedro Laza Y Su Banda "PEDRO LAZA Y SU BANDA" Fuentes no number (1979)
2010-11-06 00:17
コメント(0)
オールド・コロンビアの味 ペニャランダ [南アメリカ]

クラブ方面のクンビア・ブームのおかげで、
古いクンビアものが紛れて入ってくるなんてこともあるんですね。
会社帰りに寄った下北沢のクラブ・ミュージック系のショップで、
コロンビア・フエンテス盤の古いクンビアCDを見つけ、狂喜乱舞してしまいました。
クラブ系のセレクト・ショップなんて、めったに足を踏み入れないんですけど、
たまにはメンドくさがらずにチェックしてみるもんですねえ。
こんなお宝が見つかるとは、期待もしてなかっただけに、どひゃーてなもんです。
若者が集うお店に背広姿のオヤジが立ち寄ったのは、
かなり場違いぽかったですけど、んなこたぁかまっちゃらんない。
「それにしても、よく入ってきたなあ、お前。」
思わずCDにつぶやいちゃいましたよ。
コロンビアのフエンテス盤なんて、ここ十年くらいぜんぜんお目にかかりませんでしたからね。
ペドロ・ラサやコラレーロス・デ・マハグァールの新しい編集盤CDが出てたこともツユ知らず、
収穫たんまりでホックホク。なにより嬉しかったのが、ペニャランダのCDを発見できたことでした。
二十年前くらいでしたっけ、フエンテス盤のオールド・コロンビアもののCD化が始まった時、
なぜかペニャランダだけはCD化されずに、がっかりしてたんでした。
1907年バランキージャ生まれのホセー・マリア・ペニャランダは、
SP時代から活躍する歌手兼アコーディオン奏者。
かつては数多くのLPを出していたのに、
フエンテス設立50周年記念の8枚組アルバムにも1曲も選曲されないなど、
完全に忘れられた存在となっていました。

ペニャランダはフエンテス初のLPアーティストでもあり、
記念すべきレコード番号の1番を飾ったそのレコードは、
お色気たっぷりのジャケも嬉しい、ぼくの長年の愛顧盤でした。
そのペニャランダがまったく忘れ去られているのは、残念でならなかったのです。
そんな思いをしてただけに、95年にこんなベスト盤CDが出ていたとは嬉しい限り。
しかも件のレコード番号1番のLP12曲中10曲を収録した選曲で、
ペニャランダの軽快なアコーディオン演奏による、
パセーオ、メレンゲ、パランダがたっぷり詰まっていて大満足。
あっけらかんとした歌いっぷりには庶民的な味わいが溢れ、
スクレイパーをせかせかと細かく刻むハチロクのビートも心地いいったらありません。
時代が下った録音では、ベースが加わってツー・ビートを強調して、
バジェナートのルーツをうかがわせるところもあって、なかなかに興味深いのです。
ところで、このお店に通うような若い人で、ペニャランダを買う人っているんでしょうか。
ペニャランダを知る若者なんているわけがないから、
ヴィンテージものを聴いてみようという人がいるかどうかってことですけど、
それがちょっと気になりますね。
Peñaranda Y Su Conjunto "SUS GRANDES EXITOS - VOL.1" Fuentes D10200
[LP] Peñaranda Y Su Conjunto "PEÑARANDA" Fuentes FLP001
2010-11-04 06:38
コメント(0)
タペカール時代のベッチ・カルヴァーリョ [ブラジル]
ベッチ・カルヴァーリョ……。
なつかしい名前ですねえ。
ベッチと出会ったのは76年の“MUNDO MELHOR” が最初。
サンバ・ブームだった当時、『すばらしき世界』のタイトルで日本盤も出た傑作です。
ぼくがサンバに夢中になった70年代後半、まさに上り調子だったサンバ歌手で、
自分がサンバ・ファンとして成長するのに、リアルタイムで伴走してくれた歌手でもあります。
でもその伴走をしてくれたのも、83年の“SUOR NO ROSTO” まで。
“SUOR NO ROSTO” に、それまでのベッチにはなかった手練をかすかに感じ取ったぼくは、
その後ぷっつりとベッチを追うのはやめてしまいました。
それからだいぶたった90年代の半ばに、ベッチの新作を聴くチャンスがあり、
そこには手練以上の驕りのニュアンスを感じて、幻滅したもんです。
でも、いいんです。ベッチは70年代にかけがえのない名作を数多く残してくれたのだから。
76~82年までのRCA時代の7作は、サンバ・ファンにとってマスターピースですよ。
そしてRCA移籍前の73~75年、タペカール・レーベルに在籍していた時代は、
サンバ歌手として大成するいわば助走期間で、貴重な記録といえます。
今回、そのタペカール時代のアルバムのストレート・リイシュー3タイトルに、
EP収録曲やフェスティバルの企画作への参加音源などをレーベルの枠を超えて編集した、
レア・トラック集(60年代編と70年代編)2枚を収めた5枚組ボックスがリリースされました。
タペカール盤の3枚は一度CD化されていますけど、
73年の“CANTO POR UM NOVO DIA” の見開きジャケの内側の写真はモノクロだったし、
75年の“PANDEIRO E VIOLA” のジャケットは、
タイトルとアーティスト名のロゴが変わってたので、
今回が初の完全オリジナル仕様のリイシューといえます。
レーベルもオリジナル盤のタペカールのデザインを使っているところが嬉しいですね。
特に、RCA時代のアルバムと遜色ないタペカール時代最高の名作、
“PANDEIRO E VIOLA” にボーナス・トラックが2曲追加されたのは、
ファンにとって最高のプレゼントですね。
編集盤の方はベッチが歌謡歌手だった時代の音源が中心で、ソフト・ロックふうの曲など、
コンジュント3D時代のアルバムやオデオンのデビュー作に興味がある人には聴きものでしょう。
ぼくが興味あるのは、サンバ歌手のベッチなので、
70年代編の後半、タペカール時代のEP収録曲のサンバがごちそうです。
70年代当時、ブラジル・タペカール盤は日本国内に輸入するルートがなく入手不可能で、
ぼくも長らくフランスのソノ・ディスクからリリースされていたLPで聴いていました。
そうそう、エルザ・ソアレスのタペカール盤もソノ・ディスク盤で聴いてたんだっけ。
そのエルザ・ソアレスのタペカール盤も近くCD化されるそうです。
以前ボックスの2イン1でCD化されたことはありますが、
オリジナル・タイトルどおりのストレート・リイシューは今回初。こちらもリリースが待ち遠しいです。
Beth Carvalho "PRIMEIRAS ANDANÇAS - OS 10 PRIMEIROS ANOS" Discobertas DBOX-01
2010-11-02 07:00
コメント(0)




