キューバ伝説の姉妹の復活劇 ラス・エルマナス・マルケス [カリブ海]

デッド・ストック放出品から見つけた1枚。
キューバの女性コーラス・グループらしいんだけど、ぜんぜん知らない名前。
04年にスペインのレーベルから出たCDで、
「パキート・デリベラ・プレゼンツ」とあるのが気になって、拾ってみました。
手に入れてみると、48ページに及ぶブックレットが入っていて、
グループの歴史の略歴に、往年の写真がたくさん載っています。
歴史的な名グループだったんですねえ。
ラス・エルマナス・マルケスは、
キューバの音楽一家のもとに生まれた3姉妹のコーラス・トリオ。
3姉妹が暮らすプエルト・パードレで31年から活動を始め、
33年にはサンティアゴ・デ・クーバに呼ばれてラジオ出演し、
37年にはハバナへ進出してさまざまなラジオ局へ出演するほか、
劇場でリサイタルを行い、絶大な人気を誇ったといいます。
41年にはRCAビクターへ初録音。
女性トリオがレコーディングしたのは、ラテン・アメリカで初だったとのこと。
第二次世界大戦中から戦後にかけ、キューバ国内ばかりでなく
カリブ海諸国、ベネズエラ、メキシコをツアーしてさらに名声を高め、
51年にニュー・ヨークで1か月公演を行い、
その後そのままアメリカに移住したそうです。
60年代まで東海岸を中心に演奏活動を続けていましたが、
両親の介護のために芸能活動を中止し、長い沈黙によって伝説となり、
忘れられた存在になってしまったんですね。
両親が亡くなり、90年からトリサとネルサの二人で活動を再開したことで、
パキート・デリベラが彼女たちを説得し、このレコーディングが実現したそうです。
ギター、ベース、パーカッションというシンプルな伴奏で歌うマルケス姉妹は、
キレのある歌いぶりを聞かせてくれます。息の合ったハーモニーや掛け合いは、
長年一緒に歌ってきたコンビの賜物ですね。
お二人ともかなりの高齢とは思いますけれど、
軽やかに歌うグァラーチャのノリなんて、バツグンじゃないですか。
曲によって加わるパキート・デリベラのサックス、クラリネットも好演。
エルネスト・レクオーナの名曲 ‘La Comparsa’ のクラリネットには
泣けました。この曲のみインスト演奏なんですよ。胸に沁みますねえ。
ダニエル・サントスが41年に残した ‘Yo No Se Nada’ を歌っているのも嬉しい。
ラテン・ファンには、ボレーロの歴史的名唱 ‘Olga’ と
同日録音の曲としても知られていますね。
ラストにシークレット・トラックでライヴ録音が1曲入っていて、
ユーモラスな歌唱で客を沸かせます。心がほっこりする、
とっても愛らしいステキなアルバムです。
Las Hermanas Márquez "PAQUITO D'RIVERA PRESENTS LAS HERMANAS MÁRQUEZ" Pimienta 8 245 360 599-2 5 (2004)
2023-05-30 00:00
コメント(0)
トリニダーディアン・ディアスポラがつなぐ過去と現代 コボ・タウン [カリブ海]
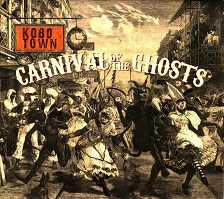
コボ・タウンは、トリニダード島生まれカナダ育ちのドリュー・ゴンサルヴェスのグループ。
4作目となる新作には、熱心なカリプソ・ファンにはおなじみの絵が飾られています。
その絵は、ビクトリア朝時代のロンドンで活躍した
新聞画家で戦争通信員のメルトン・プライア(1845-1910)が描いた、
1888年のポート・オヴ・スペイン、フレデリック・ストリートのカーニヴァル。
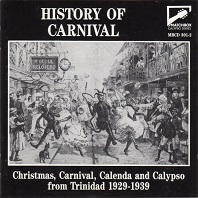
イギリスのコレクター・レーベル、マッチボックスから93年に出た
“HISTORY OF CARNIVAL”のジャケットに飾られていた絵ですね。
そのマッチボックス盤は、カリプソのルーツであるスティック・ファイティングの伴奏音楽
カリンダにスポットをあてて、トリニダードのカーニヴァルの歴史をたどった編集盤でした。
コボ・タウンも、まさにカイソやカリンダといったトリニダード音楽の古層に目を向けて、
ディアスポラの立ち位置で伝統の再構築を試みているグループなので、
このジャケットにはピンときましたよ。
カリプソがダンス音楽ではなく、歌詞を聞かせる音楽であったことは、
現在のトリニダーディアンはすっかり忘れてしまっているかのようにみえます。
ドリュー・ゴンサルヴェスは、ユーモラスな物語の中に風刺の利いたメッセージを
埋め込むという、かつてのカリプソニアンたちと同じ批評精神で作曲したオリジナル曲で、
トリニダード大衆文化が持っていた逞しさをよみがえらせています。
それはどこか、V・S・ナイポールの傑作短編集
『ミゲル・ストリート』と共振するものを感じさせます。
トリニダード島で13歳まで暮らしたドリューは、両親の離婚後、
母親の故国カナダへ引っ越して、ディアスポラとなったわけですが、
トリニダード時代は近所にキチナーが住んでいたり、
カリプソはごく身近な存在だったといいます。
しかし、カリプソは少年の興味をそそる音楽ではなく、
当時はアイアン・メイデンなどのヘヴィ・メタルに夢中だったそうで(笑)、
ドリューがカリプソを再発見するのは、
カナダに移ってトリニダード島を懐かしむようになってからのこと。
カリプソを再発見して、カイソやカリンダの時代までさかのぼることによって、
内なるトリニダード文化を自覚するようになったドリューはルーツを学び直して、
コボ・タウンで実験を繰り返してきたのですね。
今作では、従来作以上にふんだんなアイディアが盛り込まれていて、
より充実した音楽性を聞かせています。
以前はレゲエをやっていましたけれど、今作はレゲエをやめて、スカを取り入れています。
レゲエよりもスカの方が、カリプソと並走するカリブ海音楽としての性格を
はっきりと打ち出せるし、オールド・カリプソとの親和性も高いですね。
さらに、ドリューの歌い口がグンとよくなりました。
ウイットに富んで、古いカリプソニンをホウフツさせていますよ。
ギターやクアトロに加えて、バンジョリンを弾いているのも絶妙。
そうした過去への回帰という要素と、ラガマフィンやエフェクトの多用や
生演奏とサンプリングを組み合わせることで、過去と現代をつないでいます。
間違いなくこれまでのコボ・タウンのアルバムでは最高作。
この力作が日本盤として配給されないとは、もったいないなあ。
Kobo Town "CARNIVAL OF THE GHOSTS" Stonetree ST104 (2022)
v.a. "HISTORY OF CARNIVAL: CHRISTMAS, CARNIVAL, CALENDA AND CALYPSO 1929-1939" Matchbox MBCD301-2
2023-05-28 00:00
コメント(0)
アフロ・グルーヴを勝ち取ったフランス白人二人組 イレケ [西・中央ヨーロッパ]

アンダードッグ・レコーズの新作は、
アルト・サックス他のマルチ奏者兼ビートメイカーのジュリアン・ジェルヴェと、
ギター他のマルチ奏者兼ビートメイカーのダミアン・テッソンの二人組、
イレケのデビュー作。二人ともフランス白人で、
イレケ(サトウキビ)というヨルバ語のユニット名に、志向する音楽性が示されています。
アフロビートばかりではなく、
さまざまなアフロ系リズムをしっかりと血肉化しているのには、感心しました。
ヨーロッパ白人によるポリリズムの咀嚼も、こういうレヴェルにまで達したのかと、
思わず感慨にふけっちゃいますねぇ。
聴く前は、「トロピカデリック」なんて尻軽なタイトルなので、
もっと安直なトロピカル・ダンスものを想像してたんですが、とんでもなかったなあ。
数々のバンドやセッションで腕を磨いてきたようですよ。
なんでも、ジュリアン・ジェルヴェはコンゴ人ギタリスト、
キアラ・ンザヴォトゥンガのバンドで鍛えられたんですね。
キアラは、ネグロ・シュクセから
グラン・カレのアフリカン・ジャズと名門楽団を渡り歩き、ナイジェリアへ渡って、
フェラ・クテイのエジプト80の一員になったヴェテラン・ギタリスト。
ルンバ・コンゴレーズとアフロビート双方のマスターであるキアラから、
しっかりとアフリカン・リズムの真髄を学び取ったのでしょう。
一方、ダミアンは、ダブ・マスターとしてのトレーニングを受け、
国際的に活躍するダブ・アーティストたちとともに活動して、
レゲエとジャズ・ファンクのシーンを横断しながら、演奏活動をしてきたといいます。
フェラ・クティやキング・タビーをヒーローとする二人が、
パット・トーマス(ガーナ)、T・P・オルケストル・ポリ=リトゥモ(ベニン)、
エルネスト・ジェジェ(コート・ジヴォワール)、
レ・ヴィキング(グアドループ)を参照しながら、
アフリカ~カリブのさまざまなリズムを研究してきたんだそう。
本作では二人が作曲したマテリアルに声を与えるため、
二人の活動拠点のヴァンデやナントのシンガーのほか、
二人がよく知るカメルーン、ブルキナ・ファソ、ラオス(!)のシンガーに
歌詞を依頼して、歌ってもらっています。
有名ゲストとかじゃなくて、こういう自分たちの活動範囲の仲間たちを集めて
フィーチャリングするところも、好感が持てますね。
生のパーカッションとプログラミングのビートが絡んで、
シンセ・ベースと手弾きのギターがグルーヴをかたどっていく
オープニングから、ゴッキゲン。
アルトとゲストのバリトンのサックス2管が、サウンドに厚みを加えていきます。
どの曲もビートメイキングがしっかり作られているから、キモチよく聞ける。
ポップなセンスとダンス・オリエンテッドなサウンド・プロデュースが
見事にドッキングした、爽やかなアフロ・グルーヴ・アルバムです。
Ireke "TROPIKADELIC" Underdog UR840872 (2023)
2023-05-26 00:00
コメント(0)
移民文化しか生み出せないポップス コリンガ [西・中央ヨーロッパ]

フランスのアンダードッグというレーベル、面白いですね。
誕生からすでに15年も経っているレーベルだそうですけれど、
ぼくは去年、リヨンの4人組ドウデリンのアルバムで知りました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-11-07
フランス移民社会の現実を投影したアーティストたちが
多数所属していて、関心を持ったんです。
アーティストたちの複雑な出自を武器に、ハイブリッドなポップを創作していて、
同化政策のおためごかしや、多文化共生のキレイゴトからは生まれない
強靭さを感じさせるところが、好感をもてます。
ノー・フォーマットとは明らかにレーベルの性格が違いますね。
そんな思いを強くしたのが、コリンガというグループの2作目。
コリンガは、ヴォーカル/ソングライティングのレベッカ・ムブングと
ギターのアルノー・エストールを中心とする6人グループ。
レベッカ・ムブングは、コンゴ・ブラザヴィル出身の歌手の父親と、
コンゴの国立バレエ団に入団した初のフランス白人女性の母親のもとに生まれ、
南フランスで育ったという人。
シングル・マザーとなった母への愛と、
父からは教わることのなかったコンゴの言語や文化を独力で学んでてきたことが、
『遺産』とタイトルの付けられた本作のテーマとなっているようです。
がらっと場面展開する曲が多く、フォーキー、ファンク、R&B、ヒップ・ホップ、ジャズ、
コンゴリーズ・ルンバ、マロヤが、1曲の中でパッチワークになっています。
楽曲が持つ訴求力がすごくて、歌われている内容はわからずとも、
レベッカの自叙伝的な物語がそこに込められているのだろうと想像つきます。


意外なカヴァー曲が1曲あって、
サンバ・マパンガラの ‘Malako Disco’ を ‘Mateya Disco’ と改題して歌っています。
この曲は、サンバの母が幼い弟たちの面倒を見るようにと自分に託して死んだことを
歌にしたもので、両親を失ったサンバが学校にも行けず、食っていくことに必死だった
生活を歌った歌詞が、なにかレベッカに刺さるものだったのでしょう。
ナイロビ時代のサンバ・マパンガラがソロ・シンガーとして独立して出した
82年作に収録されていた曲で、90年にイギリス、アースワークスがCD化したので、
原曲を聴くのも容易かと思います。
アルバムのなかで、この1曲だけは
ストレートなコンゴリーズ・ルンバで演奏されていますが、
ほかの曲はかなりヒネリのあるアレンジが施されていて、
ドラムス、鍵盤、ギター、パーカッションのマルチ奏者
ジェローム・マルティノー=リコッティのアレンジがサウンドの要となっています。
Kolinga "LEGACY" Underdog UR838042 (2021)
[LP] Samba Mapangala & Orchestre Virunga "IT'S DISCO TIME" ASL ASLP927 (1982)
Samba Mapangala & Orchestre Virunga "VIRUNGA VOLCANO" Earthworks CDEWV16
2023-05-24 00:00
コメント(0)
パリのメトロでバスキングしていたライ歌手 ムハンマド・ラムーリ [中東・マグレブ]


おぉ、2作目が出たよ。
19年のデビュー作 “UNDERGROUND RAÏ LOVE” の生演奏ライに
快哉を叫んだものの、あまりの時代錯誤な仕上がりに、
こりゃ一発屋だなとタカをくくっていたので、まさか2作目が出るとは思いませんでした。
たいへん失礼をしました。
アルジェリア、トレムセン出身というムハンマド・ラムーリ。
03年に21歳でフランスへ不法移民として渡り、
パリの地下鉄メトロ2号線の車内やベルヴィル駅で、
シンセ片手にバスキングしていた経歴の持ち主。
強烈なダミ声で歌うセンチメンタルなライ・ラヴで
(時にイーグルスやマイケル・ジャクソンも交えて)、
通勤客を楽しませていたそうです。
ダミ声が利いた苦みたっぷりのライには、
視覚障碍者で不法移民という苦労人らしい暗さがたっぷり宿っていて、
ポップになったライ・ラヴを、もう一度ライの原点である
アンダーグラウンドな世界に引き戻す訴求力があります。
新作でも、見事にたそがれたライを聞かせていて、グッときますねえ。
生のドラムスでオートチューンもウチコミも使わない、
80年代ライそのままのサウンドを聞かせるバンドのグループ・モスラも
前作と変わらずです。
レパートリーは前作でも歌っていたハスニの曲をカヴァーしていて、
今回はハスニの代表曲である ‘Omri Omri’ ‘Tal Ghyabek’ を取り上げています。
おっ!と思ったのは、ダフマーン・エル・ハラシの ‘Ya Rayah’ を歌っているんですね。
ひょっとして、ラシッド・タハのヴァージョンで知ったのかな。
ラムーリの歌声にぴたりとハマった見事なカヴァーです。
Mohamed Lamouri "MÉHARI" Almost Musique ALMST20CD (2023)
Mohamed Lamouri & Groupe Mostla "UNDERGROUND RAÏ LOVE" Almost Musique ALMST16CD (2019)
2023-05-22 00:00
コメント(0)
ポリリズムを深化させたアフロビート・ジャズ サンボーン [北ヨーロッパ]

デンマークのアフロ・ジャズ・バンド、クティマンゴーズが、
サンボーンとバンド名を変えて再出発。改名後第1作が届きました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-10-08
また一歩、音楽性の歩みを進めましたね。
オープニングの ‘Dancing In The Dusk’ から、
オーケストレーションを思わせる
重厚なホーン・アンサンブルのアレンジに引き込まれました。
サックスのひび割れたサウンドや、ブレイクでフルートが立ち上ってくる場面など、
これまでにないスケール感を生み出しているじゃないですか。
アフリカ音楽のポリリズムを取り入れつつ、
ハウス・ビートを生演奏にトレースしたようなドラムスの、
トランシーなグルーヴにもドキドキさせられます。
今回、ドラマーだけが新しいメンバーに交代したんですね。
‘Night Sweats’ で、ホーン・セクションがまるでEDMのシンセ・リフのように
響かせているのも面白いなあ。
デジタル・サウンドを生演奏に置き換える試みですよね。
電子音楽のコンテクストをアクースティックな演奏に転換する試みは、
クラフトワークの ‘Metropolis’ のカヴァーでも見事に発揮されていますよ。
アフロビートのグルーヴを生み出すドラムスとのミックスも鮮やかです。
南ア・ジャズのサウンドスケープをトレースした ‘Under The Same Sky’ もいい。
アフロビートだけじゃなく、こういう曲も書けるところが、このバンドの強みで、
アフリカ音楽を深く探求している証拠だね。
ザップ・ママやプリンスのニュー・パワー・ジェネレーションの一員だったこともある、
デンマーク人女性ベーシストのイダ・ニールセンと、
ニュー・ヨークのジャズ・シーンで活躍する
日本人ピアニスト、ビッグユキがフィーチャーされた ‘Mankind?’ は、
ヘヴィーでワイルドなグルーヴに満ちたトラック。シンセ・ソロのパートを差しはさんで、
サックス・ソリがサウンドを切り裂きながら進行していくアレンジが、壮観です。
ポリリズムを深化させたアフロ・ジャズ、というよりもアフロビート・ジャズでしょうか。
バンド名を改名して、さらに奥行を増したサンボーンです。
Sunbörn "SUNBÖRN" Tramp TRCD9114 (2023)
2023-05-20 00:00
コメント(0)
フューチャー・ソウル+アフリカン・ヒップ・ホップ サンパ・ザ・グレイト [太平洋・オセアニア]

ザンビア生まれ、ボツワナ育ち、現在はメルボルンを拠点に活動する
ラッパー/シンガー、サンパ・ザ・グレイトの新作。
最近ではエズラ・コレクティヴの新作にもフィーチャーされていましたね。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-11-19
ヒップ・ホップ、ネオ・ソウル、ジャズを横断したプロダクションは、
US産ともUK産とも異なり、ハイエイタス・カイヨーテに代表される
フューチャー・ソウルのフィールに富んだもの。
サン・フランシスコのアカデミー・オヴ・アート大学に学び、
シドニーへ移住したというキャリアがよく反映されています。
パンデミックでザンビアに一時帰国していたサンパは、
故国から受けた影響を反映させた作品を作ろうとしたとのこと。
ザンビアのソングライター/プロデューサーのティオ・ネイソン、
ラッパーのシェフ187、そしてサンパの妹ムワンジェをフィーチャーした
‘Never Forget’ では、ザンビアのヒップ・ホップ・プロデューサー、
マグ44が808で作ったドラム・マシーンのサウンドをベースに、
ザンビアのユース・カルチュラル・パフォーマンス・グループ、
ノマカンジャニのンゴマ(太鼓)奏者2名によるンゴマの生音を絡ませています。
驚いたのは ‘Can I Live?’。
なんとザンビアのサイケ・ロック・バンド、ウィッチとの共演ですよ。
ウィッチが今でも存在していたとはビックリですが、40年ぶりに復活したんだそう。
ウィッチは、70年代にザンビアで流行したザンロックのバンド。
ドラッギーでサイケなサウンドが、2010年代にアメリカのガレージ/サイケ・ロック
周辺で再評価されるようになったんでしたね。
『ポップ・アフリカ800』では、ンゴジ・ファミリーとリッキ・イリロンガの2作に
ザンロックを代表してもらいましたが、ロック・ファンにはウィッチの人気が絶大でしたね。
ちなみに、日本語版ウィキペディアをはじめ、
「ザムロック」とカナ表記しているのは、理解に苦しみます。
「ザンビア」を「ザムビア」とは書かないだろうに。
こうしたザンビアのアーティストたちとのコラボによって制作された新作ですけれど、
そのサウンドは贅沢なもの。オーストラリア産らしいフューチャー・ソウル色濃い、
アフリカン・ヒップ・ホップです。
Sampa The Great "AS ABOVE SO BELOW" Loma Vista LVR02896 (2022)
2023-05-18 00:00
コメント(0)
不滅のメンフィス・ソウル・ジェントルマン ウィリアム・ベル [北アメリカ]
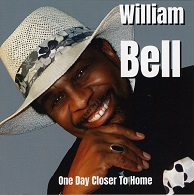
ヴェテラン・ソウル・シンガー、ウィリアム・ベルの新作は、
ホームグラウンドである自身のレーベル、ウィルビーから。
16年にスタックスから出た前作は、その年のマイ・ベスト・アルバムにも選びました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-09-19
あれから7年。
この豊かなヴォイスが、80歳代半ばを迎えようというシンガーのものとは、
信じがたいですね。芳醇と呼ぶ以外どんな言葉も思いつかない、
その年輪だからこそ生み出される味わいだけがそこにあって、
老いは微塵もない情感溢れる歌いぶりに、圧倒されるほかありません。
90年代からベルと一緒に活動している鍵盤奏者レジナルド・ウィザード・ジョーンズとの
共同プロデュースで、バックはすべて人力の生演奏。
ホーンズやストリングスも使って、打ち込みをいっさい使わないレコーディングは、
もはや21世紀とは思えないほど。
それがレトロ・ソウルだとかの思惑やネライなどではなく、
この人はずっとこうやって録音してきたのだという、
ヴェテランの自然体の強さに圧倒されます。
時代も流行もすべてを超越した歌が、ここにはあります。
胸に染み入るメンフィス・ソウル・ジェントルマンの歌い口に、
ただただ酔いしれるばかりの珠玉のアルバムです。
William Bell "ONE DAY CLOSER TO HOME" Wilbe WIL2023-2 (2023)
2023-05-16 00:00
コメント(0)
パンデミックが進化させたエレクトロ・ジャズ・ヴォーカル エリザベス・シェパード [北アメリカ]

会社のお昼休みに “MONTRÉAL” を激愛聴中。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-04-12
ああ、これを5年前に聴いていたらなあ。
間違いなく2018年のマイ・ベスト・アルバムに選んだのに。
そんな前作をヘヴィロテしてるところに、最新作が届きました。
パンデミック下の制約を受けてレコーディングされたこの最新作、
これまでの地平と違う新たな表現を切り開いた力作じゃないですか。
攻めてるなあ、エリザベス。
これまで以上にエレクトロニカの要素を強めて、
なんの音だかよくわからない音響が行き交う、
クリエイティヴなサウンドを生み出しています。
外出禁止によってミュージシャン同士が集まれない状況下、
エリザベスは、身の回りの音からインスピレーションを受けるようになったといいます。
タイプライター、ゴミ箱、レコードの音飛び、鳥の泣き声などをコラージュして
(かなり加工処理しているようで、どれがそれなのか不明ですが)、
サックスやコントラバスと交信しながら、有機的な音と電子音が絡み合って、
ミステリアスな音空間を生み出しています。
エリザベスのソングライティングの特徴であるクールなコード進行や、
独特なコード感が絶妙なスパイスとなって、斬新な表現を獲得しているじゃないですか。
ギタリストがバンジョーを弾いた曲や、ウクレレやカリンバの使用など、
これまでにない楽器の採用や、さまざまな音のレイヤーによって、
知覚の扉を次々と開けていくような、冒険的な試みに、ドキドキさせられますよ。
オーガニックとデジタル、具象と抽象、メロディアスと無調などなど、
アンビヴァレントな要素が共存しながら一体化していく音作りが鮮やかです。
パンデミックの災いを転じて、レコーディングの制作過程に新たな可能性を開いた
アーティストはさまざまいますけれど、エリザベスも音楽性に大きな飛躍を遂げましたね。
エリザベスの才気のほとばしりを感じずにはおれない、たいへんな意欲作です。
Elizabeth Shepherd "THREE THINGS" no label PM106CD (2023)
2023-05-14 00:00
コメント(0)
アコーディオンをキーボードに代えて レ・ピトン・ド・ラ・フルネーズ [西・中央ヨーロッパ]

昨年夢中になり、ベスト・アルバムにも選んだレ・ピトン・ド・ラ・フルネーズ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-18
去年書いた記事は、彼らのフェイスブックにもリンクされましたけれど、
早くも新作EPが届きました。
60~70年代のエレクトリック・セガをレパートリーに、
ノスタルジックなクレオール・ダンス歌謡をリヴァイヴァルする
グループ・コンセプトは今回も変わらず。
前作、前々作と違うのは、アコーディオンがキーボードに置き換わり、
エレクトリック・ギターが前面に出て、エレクトリックに寄せたウンドとなっています。
ヴィンテージ感たっぷりなエレクトリック・サウンドは、もろに60~70年代ですね。
キーボードの音色やギターのエフェクトがユーモラスで、
ファニーなリックを弾くあたりが、セガというダンス歌謡の性格をよく表しています。
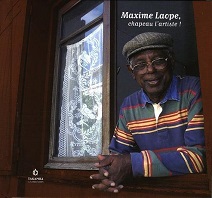

サックス、フルート、キーボードの長いソロを交えてセガ・ジャムを繰り広げる
‘Sous Pieds d'Camélia’ は、 マキシム・ラオープの曲。
クロード・ヴィン・サン楽団をバックに歌ったオリジナルは、タカンバ盤で聴くことができ、
94年の “HOMMAGES” でもメドレーの1曲で歌っていました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-02-15
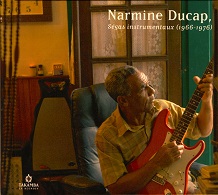
1曲やっているインスト・ナンバーが、ゆいいつメンバーのオリジナル。
これがレユニオンの名ギタリスト、
ナルミン・デュカップのセガ・インストルメントそのもの。
この曲が本作のサウンドを一番シンボリックに表している気がしますね。
ナルミン・デュカップの往年の録音を編集したタカンバ盤でチェックしてみましたが、
やっぱり今回のレ・ピトン・ド・ラ・フルネーズの方向性と、ドンピシャだな。
最後に、バンドキャンプで販売されているLP/デジタルは5曲のみなので、
ライヴ・ヴァージョンの2曲が収録されている限定リリースのCDをオススメします。
Les Pythons De La Fournaise "TOUT Z'ÉTOIL" Catapulte CATACD042 (2023)
Maxime Laope "CHAPEAU L’ARTIST!" Takamba TAKA1218
Maxime Laope "HOMMAGES" Piros CDP5209 (1994)
Narmine Ducap "SÉGAS INSTRUMENTAUX (1966-1976)" Takamba TAKA0813
2023-05-12 00:00
コメント(0)
パフォーマンスよりも音楽性 バルバトゥーキス [ブラジル]

ショランド・アス・ピタンガスの新作で、思いがけずバルバトゥーキスの名を聞いて、
懐かしくなって彼らの15年作を引っ張り出してきました。
175ミリ角のフォトブック仕様という特殊仕様のCD。
彼らの代表作で、ぼくのお気に入りの一枚だったのに、
これまで記事にしていなかったので、取り上げておきますね。
バルバトゥーキスは、95年にサン・パウロで結成された
ボディ・パーカッション・グループ。
顔からつま先に至るまで、全身のありとあらゆる場所を叩きに叩きまくって
ビートを作っていくという、驚異的なパフォーマンスを繰り広げます。
いわばビート・ボックスの発展形ともいえるグループですね。
こういうグループの特徴として、視覚的要素の方が圧倒的に強力で、
CDなどの音源だけで聴くと、魅力半減になりがちなんですが、
このグループに限っては、そうじゃないんです。
本作でもわかるように、途方もないアイディアが随所に詰め込まれていて、
実験性に富んだ音作りもふんだんに取り入れていながら、
それを鮮やかにポップな音楽性に仕上げるスキルが、彼らにはあるんですよ。
それをはっきり認識できるのが、
ぼくの天敵(笑)エルメート・パスコアールをゲストに迎えた曲。
エルメートはあいかわらずのエキセントリックなヴォイス・パフォーマンスを
繰り広げているんですけれど、バルバトゥーキスの見事なパフォーマンスが
エルメートの毒々しさを中和して、ポップな音楽性に昇華させています。
エルメート自身がやると、
悪しきフリー・ジャズみたいになるプリテンシャスなパフォーマンスを、
ちゃんと豊かな音楽に変換できる知力が、バルバトゥーキスにはあるんです。
本作でも、スカとフラメンコを融合したり、ケチャからアイディアを借りてきたり、
マシーシというブラジル音楽の古層にアプローチして
ピシンギーニャにオマージュを捧げるなど、
きわめてインテレクチュアルな試みをしながら、
肉体感溢れる音楽を生み出しているところが、このグループの偉さでしょう。
本作は16年にUKのミスター・ボンゴからも発売され、
世界各地の音楽祭に招かれて活躍しています。
日本にも来てくれないかな。ぜひ生を観てみたいですね。
[CD Book] Barbatuques "AYÚ" MCD MCD468 (2015)
2023-05-10 00:00
コメント(0)
風薫るハーモニカ・ショーロ ショランド・アス・ピタンガス [ブラジル]

さわやかなハーモニカ・ショーロに目の覚める思いがする、ヴィトール・ロペスの3作目。
今作はヴィトールの名が消え、
ショランド・アス・ピタンガスのグループ名義となっています。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-12-22
前2作との違いは、レパートリーからショーロ古典がなくなり、
すべてメンバーによるオリジナル曲になったこと。それでグループ名義になったのかな。
ショランド・アス・ピタンガスは、ハーモニカのヴィトール・ロペスに、
7弦ギターのジアン・コレア、バンドリンのミルトン・モリ、
カヴァキーニョのイルド・シルヴァ、パンデイロのロベルタ・ヴァレンテの5人編成。
今回はゲストに、ギターのシコ・ ピニェイロ、ヴァイオリンのリカルド・ヘルス、
ボディ・パーカッション・グループのバルバトゥーキスが参加して、
彩をぐんと豊かにしています。
特に、現在ニュー・ヨークで活躍するジャズ・ギタリスト、シコ・ピニェイロの参加は、
おっ!と色めき立つ人もいるんじゃないかな。
前半は、ショーロから逸脱しないよう主旋律を生かしたプレイをしつつも、
後半のソロでは冴えたロング・プレイを聞かせるところがキモ。さすがですねえ。

ヴァイオリンのリカルド・ヘルスは、バークリー音楽院で学び、
アントニオ・ロウレイロと共演作を出したりしている人。
知的すぎる音楽性は、ぼくが敬遠するタイプではあるんですが、
クラシックとジャズの素養をベースとして、ノルデスチから南部までさまざまな地方音楽に
チャマメまで研究して、肉体感のあるサウンドを生み出している姿勢は立派。
彼の研究成果を発揮した12年作は、見事な出来でした。
超ユニークなパフォーマンス集団、
ボディ・パーカッション・グループのバルバトゥーキスの起用も、大正解ですね。
ちなみにタイトルの「3回目接種」とは、
コロナ・ワクチンの接種回数と3作目のダブル・ミーニングとのこと。
カンケーないですが、ワクチン接種は3回でやめました、ワタシ。
Chorando As Pitangas "TERCEIRA DOSE" no label no number (2022)
Ricardo Herz Trio "AQUI É O MEU LÁ" Scubidu Music SDU014 (2012)
2023-05-08 00:00
コメント(0)
アシッド・ジャズ・マナーのアフロ・ジャズ・ファンク デレ・ソシミ [西アフリカ]

15年の前作では、正統派アフロビートを聞かせていたデレ・ソシミでしたけれど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-06-11
メンバーを一新した8年ぶりの新作は、だいぶ方向性が変わりましたね。
アフロビートに軸足を置きつつも、
ぐっとジャズ・ファンクへ寄せたサウンドになっています。
エスチュアリー21という2管入りの7人編成のグループは、
エセックスのインディ・ロック・シーンで活躍する、
サム・ダックワースを中心に集められたとのこと。
「ゲット・ケイプ。ウェア・ケイプ。フライ」という長ったらしいステージ・ネームが
クレジットされていますが、それがサム・ダックワースのことで、ギターとシンセを担当。
デレとサムは2012年のフェラブレーションで出会い、
それ以来コラボレーションを続けてきた仲だそうです。
全6曲中4曲はヨルバ語で歌われていて、2曲が英語曲。
英語曲は、モータウンの70年代ソウルを思わせる都会的なアレンジが施されていて、
スノウボーイが1曲でフィーチャーされています。
それでな~るほどと思いましたけれど、
本作の生演奏のヴァイブスって、初期のアシッド・ジャズだね。
ヨルバ語で歌われる4曲は、アフロビートとヨルバ・ファンクの折衷。
リジー・ドスンムという女性歌手が、いい味を出しています。
名前からしてナイジェリア系のようですね。
収録時間わずか21分弱のミニ・アルバムで、
各曲とも3分前後の短尺で仕上げられていますが、
ライヴで長尺ヴァージョンを体験してみたいものです。
Dele Sosimi and The Estuary 21 "THE CONFLUENCE" Wah Wah 45s WAHCD041 (2023)
2023-05-06 00:00
コメント(0)
ブラス・アンサンブルで再解釈したモロッカン・シャアビ シェイクス・シカッツ&ビーネット・シャアビ [西・中央ヨーロッパ]
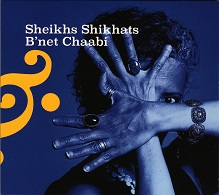
モロッコ系ベルギー人女性歌手ライラ・アメジアンが率いる
シェイクス・シカッツ&ビーネット・シャアビのデビュー作。
総勢18人のアンサンブルのうち、
歌手やパーカッションを担うメンバーがすべて女性なのは、
19世紀のモロッコで表現の自由のために戦ったシカッツやガナヤットと呼ばれる
女性歌手にオマージュを捧げようという意図が込められているそう。
そして本作は、国際女性デーに合わせてリリースされたんですね。
シカッツやガナヤットという存在を知らなかったので、興味を覚えて調べてみたんですが、
アルファベットで調べてもネットにはまったくないですね。
アラビア語で調べないとダメみたい。
アラビア語で「長」を表すシェイフ Sheikh の語尾に s が付く
シェイクス Sheikhs というグループ名もよくわからず、
ここではオランダ語の発音に従って、シェイクスと書いておきますが、真偽は不明です。
ベルギー人ジャズ・トランペッターのローラン・ブロンディアウを音楽監督に据えて、
サックス2,トランペット2、トロンボーン2、チューバという7管に、
ドラムス、パーカッションというブラス・アンサンブルとなっています。
伝統的なシャアビを題材に作曲したマテリアルを、
ジャズやファンクの手法を取り入れたアレンジによって、
祝祭感に富んだ大衆歌謡のグルーヴを表現しています。
モロッコ現地の砂埃舞う野性味は求められないとはいえ、
ほどよい洗練によって再解釈されたシャアビには、得難い味がありますよ。
なにより女性歌手たちのコーラスが醸し出す華やいだ雰囲気がいいですね。
ぱかんぱかんと叩かれる手拍子が、モロッカン・シャアビらしい祝祭感を表出しています。
Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi "SHEIKHS SHIKHATS & B’NET CHAABI" Zephyrus ZEP061 (2023)
2023-05-04 00:00
コメント(0)
バリトン・サックスでジャンプ レオ・パーカー [北アメリカ]
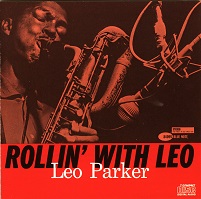
ひさしぶりにソウル・ジャズのCDをいろいろ引っ張り出して聴く機会があって、
最近のオルガン・ジャズが薄味すぎて、てんで物足りないと感じるのは、
ジャック・マクダフやジミー・マグリフみたいなコテコテ・オルガン(
さんざん聴いちゃったせいなんだろうなあと、思い至りました。
そんなことを考えながら、レオ・パーカーのブルー・ノート盤を聴いてみたら、どハマリ。
こちらはコテコテじゃなくて、ブリブリ・サックスか。
ブルー・ノートのソウル・ジャズといえば、グラント・グリーン、ジョン・パットンあたりが
まっさきに上がるところでしょうけど、個人的に愛着のある盤というと、これ。
バリトン・サックス奏者レオ・パーカーの61年のお蔵入り作。
ブルー・ノート・ファンにはイケてないジャケットでおなじみの、
79年にスタートした未発表音源発掘のLTシリーズで80年に出た1枚です。
その後86年にめちゃイケてるカヴァーに変えて再発売され(笑)、
88年にCD化されました。
ブルー・ノートのソウル・ジャズ盤というと、この1曲!というアルバムは山ほどあるのに、
アルバム通して聴くと退屈、というのが多いですよね(個人の感想です)。
でも、レオ・パーカーの本作は、アルバム全編ゴキゲンな一枚。
なんで、これお蔵入りしちゃったの?というアルバムです。
なんといっても嬉しいのが、いろんなタイプの曲をやっているところ。
スウィング・ジャズあり、スロー・ブルースあり、ジャンプ・ブルースあり、
ジャイヴ・ナンバーありで、まったく飽きさせることがありません。
ぼくがソウル・ジャズに関心を持つようになったのは、ジャズからではなくて、
ジャイヴやジャンプ・ブルース経由だったので、
なおさらこのジャンプ寄りのレパートリーが嬉しいんです。
これぞジャンプ・ブルースといったイリノイ・ジャケーの ‘Music Hall Beat’ では、
ロッキン・リズムにのって、バリトンの音圧を生かしたブリブリのブロウが痛快至極。
コールマン・ホーキンスの ‘Stuffy’ を取り上げているのも嬉しい。
ルイ・ジョーダン調のジャイヴ・ナンバーで、
45年のオリジナル曲のテンポを少し落として、
小粋なジャイヴ感覚を強調しているところが、いいんだなあ。
ふと思えば、ジャズ・ファンにはよく知られたレオ・パーカーですけれど、
ジャンプ・ブルース・ファンは、レオ・パーカーを知らない人が多いんでは。
ブルース・ファンは、ブルー・ノートなんてチェックしないもんなあ。
レオ・パーカーの本作は、「ブルー・ノートでジャンプ」の名作ですよ。
Leo Parker "ROLLIN’ WITH LEO" Blue Note CDP784095-2
2023-05-02 00:00
コメント(6)




