ドロドロの愛憎劇を抜けて サマー・ウォーカー [北アメリカ]

サマー・ウォーカーの “STILL OVER IT” が全米1位を獲得したのには、驚いたなあ。
全米1位とかグラミーとかの賞を獲るようなアルバムと、
無縁な音楽生活を送っている当方としては、これはレアな出来事であります。
ア・カペラのボーナス・トラックが入ったターゲット盤で聴いていたんですけれど、
痛みの強い歌に気圧されて、繰り返し聴くのはちょっとツラかったかなあ。
じっさいこのアルバムは、別れをテーマにした私小説アルバムらしく、
男女のイザコザを描いた、かなりドロドロした詞を歌っているとのこと。
ソング・リストの各曲に日付が書かれてあって、
2019年8月から2021年9月の日記になっているみたいです。
歌詞なんてぜんぜん聴き取れないけれど、波乱万丈が綴られているのでしょう。
サウンドの方はアトランタ・ベースあり、トラップ・ソウルあり、
ジャジーなスロウ・ジャムあり、90年代から脈々と続くR&B史をなぞっていて、
プロダクションは王道感があります。

新作は、感情の泥沼のようだった“STILL OVER IT” とまるで趣が異なります。
新作といっても既発のEP2作を合体した変則アルバムで、
生演奏を含むプロダクションにのせて、柔らかな表情の穏やかな歌を聞かせます。
ウォーカーは、闘争やストレスから解放され、セルフ・ケアに重きを置いたのだとか。
まさにそうしたネライどおりの作品に仕上がっていますね。
ゆったりとしたグルーヴは、シルクの柔らかさに身を包む心地良さ。
ジャジーなネオ・ソウル・サウンドは極上です。
繊細な歌いぶりや息遣いのヒリヒリしたニュアンスから、
胸の鼓動が伝わってくるかのようで、ドキドキしてきます。
スポークン・ワードでのインティメイトな語りなど、
すぐ隣にウォーカーがいて、おしゃべりしているかのよう。う~ん、身悶えるなあ。
お休み前の一枚として重宝しそうな予感。
Summer Walker "STILL OVER IT" Target Exclusive version LVRN/Interscope B0034704-02 (2021)
Summer Walker "CLEAR: THE SERIES" LVRN/Interscope B0037928-02 (2023)
2023-07-13 00:00
コメント(0)
アダルトR&Bシンガーの歌ぢから レヴェル [北アメリカ]

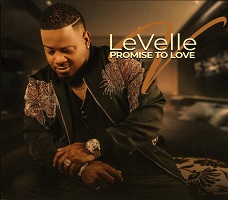
う~ん、やっぱ、歌ぢからが違うなぁ。
レヴェルは、昨年デビュー作を出したカンザス・シティ出身のアダルトR&Bシンガー。
いまどき貴重ともいえる、オーソドックスなタイプの実力派です。
美メロ揃いのデビュー作をヘヴィロテしたんだけど、はや2作目が出ましたよ。
これがまたデビュー作を上回る仕上がりで、すっかり破顔しちゃいました。
こりゃあ、書いておかなきゃねえ。
暑苦しいくらい、ねっとりと甘いラヴ・ソングを歌う人なんですけれど、
このねちっこい歌いぶりから、熱いソウルが滴るようじゃないですか。
やるせない感情を振り絞るように歌って、胸をぎゅっとつかまれます。
王道ソウルそのものの歌手なんだけど、派手さのないところが、またぼく好みの人。
デビュー作ではアンソニー・ハミルトンをゲストに迎えていましたけれど、
2作目ではアンソニー・ハミルトンに加え、ラヒーム・デヴォーン、アフター7、
ザカルディ・コルテスとさらに豪華なメンツが参加しています。
関心してしまうのが、こういう個性豊かなゲストの力を利用して、
みずからの魅力を巧みにアピールしているところ。
ゲスト・シンガーの個性にぜんぜん負けない、キャラの立ったレヴェルの歌声は、
ゲストとくっきりと対比させることに成功しています。
プロデューサーがレヴェルの魅力をよくわかっているんだね。
デビュー作・セカンド作とも、クロード・ヴィラニという人のプロデュースで、
調べてみたら、ソノ・レコーディング・グループというレーベルを設立した人なのね。
ソノ・レコーディング・グループから出たアフター7の21年作でも、
3人のプロデューサーの一人に名を連ねていました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-10-11
そういえばメン・アット・ラージもこのレーベルの作品だったんだな。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-10-26
どうやらぼく好みのレーベルのようなので、今後チェックしなくちゃ。
LeVelle "MY JOURNEY CONTINUES" SoNo Recording Group no number (2022)
LeVelle "PROMISE TO LOVE" SoNo Recording Group no number (2023)
2023-07-11 00:00
コメント(0)
エクスペリメンタルR&Bの逸材 リヴ [北アメリカ]
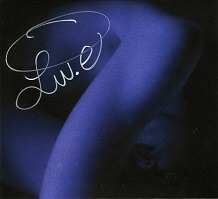
過激なエレクトロで彩られた1・2分台の曲が次から次へと飛び出し、
頭クラクラ、混沌としたサウンドに翻弄されていると、
あっという間にラスト・トラックへと行きつき、トートツに終わってしまい、ボーゼン。
「なんじゃこりゃあ!」と、松田優作みたく思わず叫んじゃいましたよ。
すぐさまアタマからリピートしてしまい、
すっかりこのアルバムの中毒性にヤラれてしまいました。
ダラス出身、ロス・アンジェルスを拠点に活動する、
R&B系新進シンガー・ソングライターの初フル・アルバム。
ドラムンベース? アンビエント・テクノ? アブストラクトR&B?
ヴェイパーウェイヴ? なんと表現すればいいのかわからないトラックが並びます。
プロダクションはえらくエクスペリメンタルなんだけど、
強烈に惹き付けられたのは、甘美な音色とメロディの美麗さゆえ。
最近のR&Bって、めちゃくちゃ音色の選択が良くなったと思うんだけど、
特にこのアルバムなんて、デリカシーの塊みたいな音響。
音の輪郭がくっきりとしていて、不快な響きがいっさい出てこない。
最近、電子音楽やアンビエントにも抵抗なく楽しめる作品が多くなったのって、
間違いなく音選びのチョイスとセンスの向上のせいだな。
リヴが絶叫する場面ですら、ぜんぜん耳に痛くならないのは、
声が浮遊するサウンドスケープに織り交ざって、
ナマナマしい感情表現がメロウなサウンドにくるまれているから。
こんな激情の伝えかたもあるんだねえ。斬新だなあ。
音楽一家に生まれ、エリカ・バドゥやロイ・ハーグローヴらが通った
ブッカーT・ワシントン高校からシカゴ美術館附属美術大学に進んで
アート、音楽を学んだという人だから、その才覚は確かですよ。
すっかりこのアルバムにマイっていたら、
なんとタイミングよく来日するというので、楽しみにしていましたよお。
ビルボードライブ東京、6月18日セカンド・ステージ。
開演前のステージに、どーんとドラムスが鎮座していたのは、意外や意外。
そういやリヴの実兄は、スナーキー・パピーやRC&ザ・グリッツで叩いていた
タロン・ロケット。なので、お兄さんを連れてきたのかと思ったら、違いました。
リヴをサポートするのは、白人男性のドラマーと、
シンセ・ベースを操る黒人男性の二人。リヴもサンプラーをかなり操作します。
いやぁ、強力なステージでした。
リヴのヴォーカルがとにかくストロング。シアトリカルな表現力がダイナミックで、
エリカ・バドゥを苦手とするぼくも、ねじ伏せられちゃいました。
エリカより断然いいじゃん、まじで。
ドラマーがサンプリング・パッドをスティックで叩いてプリセットのビートを鳴らし、
ドラムスの生演奏は、フィル・インを入れたり、ソロで大暴れするというスタイル。
螺旋状のエフェクト・シンバルもセッティングしてありましたよ。
リヴもサンプラーを使ってヴォーカルを加工したり、
モニターにマイクを向けてハウリングさせたりしながら、
アルバムでは1・2分の曲を、ぐんと引き延ばして聞かせます。
サンプリング・ループと生演奏がバトルになる場面では、
トランシーな磁場を生み出すほどでしたよ。
最後に余談ですが、
リヴにサインを入れてもらったCD、日本では手に入りません。
アマゾンにも流通していないので、ぼくはバンドキャンプから購入しました。
さすがにライヴ会場には持ち込んで販売するだろうと思いきや、それもなし。
もうアメリカでは、フィジカルで商売する気がまったくないんだね。
Liv.e "GIRL IN THE HALF PEARL" In Real Life Music inreallife066CD (2023)
2023-06-21 00:00
コメント(0)
アロマテラピーのヴォイス ジャネット・エヴラ [北アメリカ]

ふんわりとした声質にトリコとなったジャズ・ヴォーカリスト、ジャネット・エヴラ。
18年のデビュー作はいまでもよく聴き返していますけれど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-11-23
一年前に新作が出ていたのを、ずっと気付かないままでいました。
21年にはピアニストとの共同名義でスタンダード集も出ていたようなんですけれど
(これまた未聴)、3作目の本作はジャネットのオリジナル曲が中心。
今回も自主制作なんですね。
う~ん、ぼくが夢中になる人って、どうして売れないんだろうなあ。
インディに甘んじるかのようなタイトルを見て、思わず考えこんじゃいましたよ。
でもまあインディだからこそ、のびのびと自分がやりたい音楽ができるわけで、
デビュー作のジャケットにも、そんな飾らない気さくさが表れていましたよね。
ジャネット写真のジャネットの腕に、虫に刺された紅い跡がくっきりとあって、
これ、メジャー・レーベルだったら、ぜったいレタッチして消すよなあと、思ったもんね。
そんなことはさておき、本作はデビュー作と同じメンバーに、
ヴィブラフォンが加わっただけなんですが、
エレクトリック・ギターやローズを効果的に配置するなどの
アレンジが功を奏していて、少しサウンドが華やかとなりましたね。
でも、心を落ち着かせるアロマのようなジャネットの声は、
デビュー作とまったく変わっていません。
ボサ・テイストのオリジナル曲を、フローラルな香りで包み込むような
やわらかなヴォイスで歌いつづっていきます。
その声を聴いているだけで、心がおだやかに身体もリラックスして、
まさにアロマテラピーのような音楽といったら、これ以上のものはありません。
Janet Evra "HELLO INDIE BOSSA" Janet Evra no number (2022)
2023-06-05 00:00
コメント(0)
不滅のメンフィス・ソウル・ジェントルマン ウィリアム・ベル [北アメリカ]
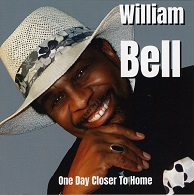
ヴェテラン・ソウル・シンガー、ウィリアム・ベルの新作は、
ホームグラウンドである自身のレーベル、ウィルビーから。
16年にスタックスから出た前作は、その年のマイ・ベスト・アルバムにも選びました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2016-09-19
あれから7年。
この豊かなヴォイスが、80歳代半ばを迎えようというシンガーのものとは、
信じがたいですね。芳醇と呼ぶ以外どんな言葉も思いつかない、
その年輪だからこそ生み出される味わいだけがそこにあって、
老いは微塵もない情感溢れる歌いぶりに、圧倒されるほかありません。
90年代からベルと一緒に活動している鍵盤奏者レジナルド・ウィザード・ジョーンズとの
共同プロデュースで、バックはすべて人力の生演奏。
ホーンズやストリングスも使って、打ち込みをいっさい使わないレコーディングは、
もはや21世紀とは思えないほど。
それがレトロ・ソウルだとかの思惑やネライなどではなく、
この人はずっとこうやって録音してきたのだという、
ヴェテランの自然体の強さに圧倒されます。
時代も流行もすべてを超越した歌が、ここにはあります。
胸に染み入るメンフィス・ソウル・ジェントルマンの歌い口に、
ただただ酔いしれるばかりの珠玉のアルバムです。
William Bell "ONE DAY CLOSER TO HOME" Wilbe WIL2023-2 (2023)
2023-05-16 00:00
コメント(0)
パンデミックが進化させたエレクトロ・ジャズ・ヴォーカル エリザベス・シェパード [北アメリカ]

会社のお昼休みに “MONTRÉAL” を激愛聴中。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2023-04-12
ああ、これを5年前に聴いていたらなあ。
間違いなく2018年のマイ・ベスト・アルバムに選んだのに。
そんな前作をヘヴィロテしてるところに、最新作が届きました。
パンデミック下の制約を受けてレコーディングされたこの最新作、
これまでの地平と違う新たな表現を切り開いた力作じゃないですか。
攻めてるなあ、エリザベス。
これまで以上にエレクトロニカの要素を強めて、
なんの音だかよくわからない音響が行き交う、
クリエイティヴなサウンドを生み出しています。
外出禁止によってミュージシャン同士が集まれない状況下、
エリザベスは、身の回りの音からインスピレーションを受けるようになったといいます。
タイプライター、ゴミ箱、レコードの音飛び、鳥の泣き声などをコラージュして
(かなり加工処理しているようで、どれがそれなのか不明ですが)、
サックスやコントラバスと交信しながら、有機的な音と電子音が絡み合って、
ミステリアスな音空間を生み出しています。
エリザベスのソングライティングの特徴であるクールなコード進行や、
独特なコード感が絶妙なスパイスとなって、斬新な表現を獲得しているじゃないですか。
ギタリストがバンジョーを弾いた曲や、ウクレレやカリンバの使用など、
これまでにない楽器の採用や、さまざまな音のレイヤーによって、
知覚の扉を次々と開けていくような、冒険的な試みに、ドキドキさせられますよ。
オーガニックとデジタル、具象と抽象、メロディアスと無調などなど、
アンビヴァレントな要素が共存しながら一体化していく音作りが鮮やかです。
パンデミックの災いを転じて、レコーディングの制作過程に新たな可能性を開いた
アーティストはさまざまいますけれど、エリザベスも音楽性に大きな飛躍を遂げましたね。
エリザベスの才気のほとばしりを感じずにはおれない、たいへんな意欲作です。
Elizabeth Shepherd "THREE THINGS" no label PM106CD (2023)
2023-05-14 00:00
コメント(0)
バリトン・サックスでジャンプ レオ・パーカー [北アメリカ]
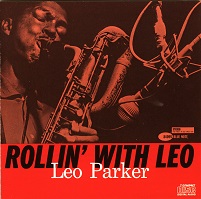
ひさしぶりにソウル・ジャズのCDをいろいろ引っ張り出して聴く機会があって、
最近のオルガン・ジャズが薄味すぎて、てんで物足りないと感じるのは、
ジャック・マクダフやジミー・マグリフみたいなコテコテ・オルガン(
さんざん聴いちゃったせいなんだろうなあと、思い至りました。
そんなことを考えながら、レオ・パーカーのブルー・ノート盤を聴いてみたら、どハマリ。
こちらはコテコテじゃなくて、ブリブリ・サックスか。
ブルー・ノートのソウル・ジャズといえば、グラント・グリーン、ジョン・パットンあたりが
まっさきに上がるところでしょうけど、個人的に愛着のある盤というと、これ。
バリトン・サックス奏者レオ・パーカーの61年のお蔵入り作。
ブルー・ノート・ファンにはイケてないジャケットでおなじみの、
79年にスタートした未発表音源発掘のLTシリーズで80年に出た1枚です。
その後86年にめちゃイケてるカヴァーに変えて再発売され(笑)、
88年にCD化されました。
ブルー・ノートのソウル・ジャズ盤というと、この1曲!というアルバムは山ほどあるのに、
アルバム通して聴くと退屈、というのが多いですよね(個人の感想です)。
でも、レオ・パーカーの本作は、アルバム全編ゴキゲンな一枚。
なんで、これお蔵入りしちゃったの?というアルバムです。
なんといっても嬉しいのが、いろんなタイプの曲をやっているところ。
スウィング・ジャズあり、スロー・ブルースあり、ジャンプ・ブルースあり、
ジャイヴ・ナンバーありで、まったく飽きさせることがありません。
ぼくがソウル・ジャズに関心を持つようになったのは、ジャズからではなくて、
ジャイヴやジャンプ・ブルース経由だったので、
なおさらこのジャンプ寄りのレパートリーが嬉しいんです。
これぞジャンプ・ブルースといったイリノイ・ジャケーの ‘Music Hall Beat’ では、
ロッキン・リズムにのって、バリトンの音圧を生かしたブリブリのブロウが痛快至極。
コールマン・ホーキンスの ‘Stuffy’ を取り上げているのも嬉しい。
ルイ・ジョーダン調のジャイヴ・ナンバーで、
45年のオリジナル曲のテンポを少し落として、
小粋なジャイヴ感覚を強調しているところが、いいんだなあ。
ふと思えば、ジャズ・ファンにはよく知られたレオ・パーカーですけれど、
ジャンプ・ブルース・ファンは、レオ・パーカーを知らない人が多いんでは。
ブルース・ファンは、ブルー・ノートなんてチェックしないもんなあ。
レオ・パーカーの本作は、「ブルー・ノートでジャンプ」の名作ですよ。
Leo Parker "ROLLIN’ WITH LEO" Blue Note CDP784095-2
2023-05-02 00:00
コメント(6)
ケイジャン・ダンスホール エヴァンジェリン・プレイボーイズ [北アメリカ]

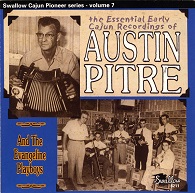
ルイジアナ生まれのアコーディオン奏者オースティン・ピートルは、
ケイジャン音楽にドラムスを取り入れ、モダン化を果たしたパイオニア。
ピートルは81年に亡くなりましたが、
ピートルのバンド、エヴァンジェリン・プレイボーイズの
元メンバーたちが集まって行われた、ハウス・ジャムのライヴ・ドキュメントが出ました。
これは、99年にフィドルのアレン・アルドワンの野外キッチンで行なわれたライヴ録音で、
かつてドラムスを叩いていたマイク・テイトが、
ピートルの代わりにアコーディオンを弾いています。
新しく参加したヴォーカルとギターのボビー・ミショーが、記念にと考えたのか、
ワン・マイクでカセット録音しておいたという音源が、このたびディスク化されました。
最初にハウス・ジャムといったのは、観客のいるライヴではなく、
演奏者の親族縁者が楽しむためのジャム・セッションだからです。
ホストは食材を用意し、鍋をかき混ぜ、時間のかかる料理をしながら、
食事の準備が整うまで、何時間も演奏を続けるというパーティー・ミュージックなのですね。
もともとケイジャンの伝統音楽は、フェ・ドドー Fais do-do と呼ばれる
伝統的な屋内パーティから発展を遂げてきたダンス音楽なので、
こうしたパーティー文化が基礎にあるのでしょう。
音質はワン・マイク録音なので、推して知るべしなんですが、
気の置けない仲間内のパーティらしい、リラックスした雰囲気が最高です。
『オースティン・ピートルに捧ぐ』のタイトルどおり、往年のピートルの曲が歌われていて、
代表曲 ‘Les Flammes D'Enfer’ をはじめ、 ‘Opelousas Waltz’ ‘Rene's Special’
‘Lakeview Special’ ‘China Ball Blues’ などの再演を聴くことができます
(オリジナル録音はスワロウ盤に収録)。
ピートルのノドを詰めたヴォーカルと、ミショーの声を張り上げて、
ポルタメントを利かせるヴォーカルというスタイルの違いはあれど、
とちらにも歌に泣きが滲むところが、ケイジャン・ミュージックの味わい。
メロディは陽気でも、ヴォーカルが泣き節という対比が、
ぼくにとってはとても魅力なのです。
Evangeline Playboys "A TRIBUTE TO AUSTIN PITRE" Nouveau Electric NER1022
Austin Pitre "THE ESSENTIAL EARLY CAJUN RECORDINGS OF AUSTIN PITRE & THE EVANGELINE PLAYBOYS" Swallow SW6211
2023-04-30 00:00
コメント(0)
バグパイプでフリー・ジャズ マット・ムンツ [北アメリカ]

オドロキのバグパイプ・ジャズ。
これが、とてつもなく面白い。
バグパイプでジャズといえば、昔ルーファス・ハーリーなんて人がいましたけれど、
バグパイプという楽器の特性を生かしきれなくて、
ただ変わった楽器でジャズをやるだけの域を超えられていませんでした。
ところが、初めて知るクロアチアのバグパイプという、
プリモルスキー・メーを演奏する、このマット・ムンツのアルバムは違います。
テナー・サックス、オーボエ、クラリネットを加えた4管編成で、
バグパイプの微分音に、チューニングの狂った(もしくは微分音チューニング?)
ギターを絡ませて複雑な色合いを生み出し、
野性味たっぷりの集団即興を繰り広げています。
フリー・ジャズにバグパイプの微分音を落とし込んだアプローチがとても斬新で、
不安定で奇妙な音列を、歪んだ響きがエネルギッシュに演奏するさまに、
ドキドキが止まりません。
ゆったりとしたテンポで、幽玄なメロディを奏でる曲では、
バグパイプのドローンとドラムスのロールが不穏なムードをまき散らし、
魔界に引き込まれていくような怖さを感じさせます。
オーボエとクラリネットが上昇音をひたすら繰り返して、
ドローンのような効果をもたらしたり、
精緻に構成されたホーン・アンサンブルと、
ダイナミックなインプロヴィゼーションの共存が魅力ですね。
バグパイパーでベーシストのマット・ムンツは、
スコットランドのハイランド・バグパイプ、韓国のピリやテピョンソ、
ケルトのカルニクスの音楽家たちと組んだザ・ヴェックス・コレクションという、
異文化ダブル・リード楽器ユニットともいえるグループでも活動していて、
こちらでは、かなり実験色の強い演奏を繰り広げています。
アルバムの最後は、バグパイプとドラムスが丁々発止を繰り広げる
奄美の古謡「おぼくり」。朝崎郁恵が歌って、広まった曲ですね。
この曲を取り上げたのは、クラリネットの上坂悠馬のアイディアかな。
91年ロンドンに生まれ、父親の仕事の関係で
デトロイトで育った上坂のクラリネットも、大活躍していますよ。
Mat Muntz "PHANTOM ISLANDS" Orenda 0102 (2023)
2023-04-28 00:00
コメント(0)
私のモントリオール エリザベス・シェパード [北アメリカ]

10年前、ジャズ・ヴォーカル新時代の到来を感じたのが、グレッチェン・パーラトなら、
その予感を確かなものと実感したのが、エリザベス・シェパード。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2014-12-27
エレクトロなサウンドを大胆に取り入れた14年作の “THE SIGNAL” が衝撃的で、
ずいぶん聴いたんだけれど、その後のアルバムを聴き逃していたとは、ウカツでしたねえ。
新作リリースのニュースを読んでいて、5年も前にアルバムを出ていたことを知り、えぇっ!
あわてふためいてオーダーしましたよ。
Pヴァインから日本盤も出ていたんですね。なんで、気付かなかったのかなあ。
というわけで、新作ではなく18年作の、遅きに失したご紹介。
“THE SIGNAL” の方向性をさらに推し進めた作品で、
独特のコード展開やハーモニー・センスを持つ
エリザベスのクールなソング・ライティングが秀逸。
そのコンポジションを引き立てるエリザベス自身のエレピも聴きもので、
ビートの利いたドラミングとの絡みが、前作以上にグルーヴィで、気分がアガります。
自身のヴォーカルを重ねたコーラス・ワークのポップなセンスも、この人の魅力ですね。
ミュージシャンは “THE SIGNAL” と全員入れ替わっていて、
モントリオールのミュージシャンが中心となっているようです。
にもかかわらず、“THE SIGNAL” の特徴的だったドラムスのサウンドが共通しているのは、
エリザベスがバンド・アンサンブルやサウンド・メイキングに、
しっかりと関わっていることの証左で、アレンジ・プロデュースの才は確かですね。
今作は、フランス語が公用語であるモントリオールをタイトルとしているとおり、
11曲中7曲がフランス語、4曲が英語というバイリンガルなアルバム。
エリザベスは、12年にトロントからモントリオールへと移住したのだそうです。
モントリオールで大勢の人々に取材して、モントリオールの歴史や社会の理解を深め、
モントリオールをテーマにしたアルバムの構想を練っていったとのこと。
オープニングの ‘Tio'Tia:Ke’ 「ティオターケ」とは、カナダの先住民族モホークの言葉で
モントリオールを指す言葉。モントリオールという土地が、誰のものだったのかを
認識するために書いた曲だといいます。
ほかにも、‘Good Lord's Work’ は、
リトル・ブルゴーニュ地区の黒人コミュニティを取材して
生まれた曲だそうで、モントリオールは北のハーレムも呼ばれ、
30~40年代に活発な音楽シーンが存在していたとのこと。
けだるいムードで歌う、古いシャンソンのような
‘Jedlika’ のオールド・タイミーな演出にも、ウナりました。
各曲とも時間をかけた取材によって生み出されたことが、よく伝わってきます。
“THE SIGNAL” を上回る傑作ですね。
Elizabeth Shepherd "MONTRÉAL" no label PM104 (2018)
2023-04-12 00:00
コメント(0)
エレクトリック・ギター史の重要ギタリスト フロイド・スミス [北アメリカ]
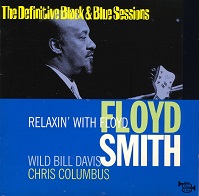
ジャンプ・ブルースのギタリスト、フロイド・スミスがどういう人なのか知らないまま、
これまで72年録音のブラック&ブルー盤を聴いていました。
そのフロイド・スミスを、ワダマコトさんが『ブルース&ソウル・レコーズ』170号の特集
「ブルースこの人この一曲」で、「諸説あるものの、‘Floyd's Guitar Blues’ は、
ジャズ史上最初にエレクトリック・ギターが大フィーチャーされた楽曲
として記録されている」と書かれているのを読んで、ビックリ。
なんでも39年3月16日、
アンディ・カーク&ヒズ・12クラウズ・オヴ・ジョイ名義で録音した
‘Floyd's Guitar Blues’ で、電化ラップ・スティール・ギターを弾いていたんですと。
39年って相当に早い話です。いち早く33年に電化ラップ・スティールを導入していた
ハワイアンから、アイディアを頂戴したらしい。
さっそくYouTubeで検索して聴いてみましたが(便利な時代だ)、
ギュイーンとしつこくスライドさせながら、特徴的なブルースのリックを炸裂させています。
これは確かに、エレクトリック・ギターの歴史に残る名録音といえそうだなあ。
ソロ録音が少なく、ほとんど知られていない人だけに、こんな重要人物だったとは驚きです。
そもそもフロイドが、
アンディ・カークという名門楽団の出身だということも初めて知りました。
ぼくがフロイドを知ったのは、ワイルド・ビル・ディヴィスのギタリストとしてです。
ルイ・ジョーダンのティンパニー・ファイヴのピアニストだった
ワイルド・ビル・デイヴィスは、40年代末にオルガンに転向し、
51年にギターとドラムスによるオルガン・トリオを結成して、
のちのジャズにおけるオルガン・トリオのひな型を作ったことは、よく知られた話。
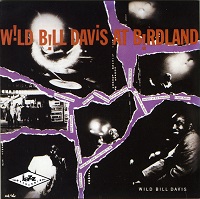
史上初のジャズ・オルガン・トリオのアルバムと目されている、
55年のバードランドでのライヴ録音は、ジャンプ・ブルースの名盤でもあります。
そこでギターを弾いていたのが、フロイド・スミスでした。
ややギターがオフ気味の録音ですけれど、ラップ・スティールではなく、
エレクトリック・ギターによる ‘Floyd's Guitar Blues’ を聴くことができます。

そしてこのライヴ盤の3人が、のちの72年にブラック&ブルーでセッションを行い、
フロイド・スミスとワイルド・ビル・デイヴィスそれぞれの名義で、
2枚のレコードを出したんですよね。
ワイルド・ビル・デイヴィスの方は87年にCD化されましたが、
フロイド・スミスの方は遅れて、96年になってCD化されました。
ブラック&ブルー盤では、ジャンプ・ブルースにビバップを織り交ぜたギターに、
新たにウェス・モンゴメリーの影響を受けたオクターヴ奏法も聞かせていて、
進取の気性に富んだフロイドらしさが発揮されています。
Floyd Smith "RELAXIN’ WITH FLOYD" Black & Blue BB875.2ND219
Wild Bill Davis "AT BIRDLAND" Columbia COL471427-2 (1955)
Wild Bill Davis Trio "IMPULSIONS" Blak & Blue 233037
2023-04-06 00:00
コメント(0)
サザン・ソウル冬の時代に出会ったレコード チャールズ・ブリマー [北アメリカ]
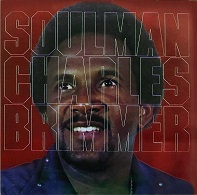
スタン・モズリーと同梱で2か月の遅配の憂き目にあった、もう一枚のCD(船便か!)。
ニュー・オーリンズ出身のソウル・シンガー、
チャールズ・ブリマーの2作目となる76年作。
サザン・ソウル聴き始めのころに、新作としてリアルタイムで聴いたレコードだけに、
個人的に思い出深いアルバムで、これは嬉しいCD化です。
当時はオーティス・レディングに始まり、ジョニー・テイラー、ウィルソン・ピケット、
O・V・ライトと、サザン・ソウル全盛期の過去の名作ばかり熱心に聴いていて、
往時のサザン・ソウルに匹敵する新作など出るような時代ではなかっただけに、
チャールズ・ブリマーのアルバムは貴重だったんです。
といっても、黄金時代の名シンガーたちに比べれば、小粒なシンガーではありました。
それでも、こんなサザン・ソウル・スタイルで聴けるレコードじたい貴重だった時期なので、
すごく嬉しかったんですよ。サザン・ソウル冬の時代から聴き始めた者にとってはね。
だって、スティーヴィー・ワンダーの “SONGS IN THE KEY OF LIFE” と
同じ年のレコードですよ。そういえば、想像つくでしょ?
直球のタイトルがいいよなあ。心意気を感じるじゃないですか。
そしてそれにふさわしいジャケットのアートワークも、風格がありますよね。
同梱のスタン・モズリーの方がはるかにディープで、歌手としての力量も数倍上で、
続けて聴いたら、さすがにカワイソーな感想がよぎったけど、
やはりディープ・ソウル聴き始めのころに出会ったリアルタイム盤だけに、
感慨深いものがあります。
Charles Brimmer "SOULMAN" Good Time GTRCD1212 (1976)
2023-04-04 00:00
コメント(0)
リアル・ブルース、アゲイン スタン・モズリー [北アメリカ]
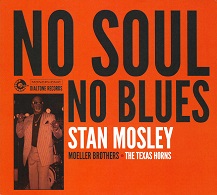
リアル・ブルースを求めるファン大絶賛のスタン・モズリー、
ようやく聴くことができました。
日本で先行発売されていたんですが、アメリカ盤が出るのを待っていたのでね。
1月リリースを機に即オーダーしたんですが、なんと到着まで2か月を超す遅配。
コロナ禍が収まっても、国際郵便はトラブルが続くなあ。
日暮泰文・高地明コンビの企画によるアルバム制作なんだから、
今回もシャーウッド・フレミングの時同様、内容保証付き。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2015-05-28
ジャケットのアートワークも、シャーウッド・フレミングのアルバム同様、
フル・カラーのゴージャスな日本盤より、2色刷りのアメリカ盤の方が、
ブルース・アルバムのフィール濃厚。
このデザイン、オルガニスト、フレディ・ローチのブルー・ノート盤
“DOWN TO EARTH” からの借用だよね。
それにしても、こんな力のあるブルース・シンガーがいて、
ライヴ感たっぷりのバンド演奏をバックにレコーディングをする環境さえ整えば、
21世紀のいまでも、こんなすばらしいブルーズン・ソウルが聴けるのかと、
感じ入らざるを得ませんね。
いくらブルースの新作が活発にリリースされているとはいえ、
こんなレコードがめったに生み出されることのないことを知っているファンなら、
いっそうそうした感を強くするはずです。
8年前書いたシャーウッドの記事は、このアルバムにもそのままあてはまっちゃいます。
というのも、シャーウッド・フレミングのアルバム同様、
エディ・スタウトのプロデュースで、バックの面々も同じ顔触れの、
テキサス・ブルースの現在を支える実力者がずらりと揃っています。
日暮&高地による選曲は、アルバム冒頭からビル・コディの73年名曲
‘I'm Back To Collect’ をカヴァーするという、あまりにディープなセレクト。
あのビル・コディのむせ返るような熱唱を知る者には、無謀な選曲と思いきや、
あの名唱をしのぐ歌いっぷりを聞かせるんだから、この1曲で、傑作と確信しましたね。
しゃがれ声でシャウトしまくるタフなソウル・シンガー、一級品じゃないですか。
スタン・モズリーのほとばしる熱いブルース・フィーリングに、
圧倒されない人はいないでしょう。
O・V・ライト、タイロン・デイヴィス、リトル・ミルトンの影が見え隠れする、
メンフィス・ソウルの味わいがもうたまりません。
‘Undisputed Love’ なんて、ジョニー・テイラーが憑依したかのようですよ。
リアル・ブルースしか聴きたくない、ぼくのようなワガママなファンには、
これ以上ないプレゼントです。
Stan Mosley "NO SOUL, NO BLUES" Dialtone DT0032 (2022)
2023-04-02 00:00
コメント(0)
エリカ・バドゥの影に埋もれた才能 ンダンビ [北アメリカ]
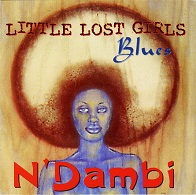
前回に引き続き、『ミュージック・マガジン』3月号
ネオ・ソウルのディスク・ガイドにまつわるお話を。
セレクトで一番驚かされたのが、このアルバム。
まさか、ンダンビの自主制作のデビュー作が選ばれるなんて。
ンダンビは、エリカ・バドゥと同郷のダラス出身のシンガーで、エリカとは親友という間柄。
先にデビューして成功したエリカのバック・ヴォーカリストとなり、
エリカの大ヒット作 “BADUIZM” の翌年に、ひっそりとこのデビュー作を自主制作するも、
話題を呼ぶこともなく、消えていった人です。
と思っていたんですけど、今回の長谷川町蔵さんの記事で、
スタックスに移籍してアルバムを出していたことを知りました。
でもまあ、成功しなかったシンガーではありますよね。
このデビュー作を聞けば、エリカより歌唱力が数段上なのは、歴然なのに。
ぼくはエリカのスカした演劇臭い歌い口が大の苦手で、
だからなおさらンダンビを支持していたんですけれど、
無名に甘んじていたのが、残念でなりませんでした。
ネオ・ソウルのディスク選に登場することなんて、これまで皆無だったはず。
というより、この自主制作盤を知ってる人じたい、どれくらいいるのやら。
それだけに今回のセレクトは快挙で、快哉を叫びましたよ。
本作はタイトルにブルースを謳っているとおり、ブルージーな歌いぶりを聞かせていて、
アーシーなシンガーという一面をみせているところが、
他のネオ・ソウルのシンガーにはない魅力なんです。
R&Bとジャズが混濁したような曲では、達者なスキャットも披露するし、
ユニークなジャズ表現を聞かせていて、可能性をすごく感じていたんだけどなあ。
これまた四半世紀ぶりくらいに聴き直しましたけど、めちゃめちゃ新鮮。
知らない人に聞かせたら、誰も新作だと思っちゃうんじゃない?
N’Dambi "LITTLE LOST GIRLS BLUES" Cheeky-i Productions CPI0827-1 (1998)
2023-03-23 00:00
コメント(0)
J・ディラ以降のネオ・ソウル名作 ドゥウェレ [北アメリカ]

『ミュージック・マガジン』3月号のネオ・ソウルのディスク・ガイドに、
ぼくの愛聴盤がけっこうセレクトされていたのは、意外でした。
ネオ・ソウル華やかりしころの話題作に反応できず、
当時は評判にならないアルバムばかり聴いていた記憶があるんですけれど、
時代を経て、評価軸が変わってきたんですかね。
デトロイトのシンガー、ドゥウェレの03年の “SUBJECT” もそんな一枚。
すっごくいいアルバムだったんだけど、当時ほとんど話題にならなかったよね。
ひさしぶりに聴いたけど、ぜんぜん古くなってない。
つーか、いまの気分にピッタリじゃないの。
仄暗い闇に沈み込んでいくような濃厚なグルーヴが、デトロイトらしいよなあ。
乾いた響きの硬質なビートが甘さを抑え、苦みのある淀みを感じさせるところがいい。
ブラシが刻むリズムとエレピがたゆたう
‘Kick Out Of You’ のジャジーな味わいといったら。
マーヴィン・ゲイばりの色気を醸し出すシンガーとしての魅力ばかりでなく、
ソングライター、プロデューサーとしての才能をJ・ディラに認められたのも、
このアルバムを聴けば理解できますよね。
いま再評価されるようになったのは、
J・ディラ以降のネオ・ソウルという文脈からなのかもしれないな。
J・ディラ自身は関わっていないけれど、
スラム・ヴィレッジがフィーチャリングされたトラックは、やっぱりハイライトかな。
20年ぶりにヘヴィロテ再燃です。
Dwele "SUBJECT" Virgin 72435-80919-2-2 (2003)
2023-03-21 00:00
コメント(0)
テイルズ・フロム・マイ・ホームタウン・ニュー・オーリンズ アンブレ [北アメリカ]

いいジャケットですねえ。
アンブレの故郷であるニュー・オーリンズと、
みずからの属するコミュニティへの愛が、こちらにしっかりと伝わってきますよ。
H.E.R.やケラーニなどにヒット曲を提供してきた
シンガー・ソングライター、アンブレの2作目となるEP。
ロス・アンジェルスを拠点に活動をして、
R&Bシーンで頭角を現してきたアンブレですけれど、
ニュー・オーリンズ出身のルーツを大切にしながら、
パーソナルなソングライティングに反映させてきたといいます。
その言葉どおり、ニュー・オーリンズのジャズ・クラブの
アトモスフィアに富んだオープニングのイントロから、引き込まれました。
マセーゴのサックスをフィーチャーしたサウンドは、クワイエット・ストームのよう。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-05-05
う~ん、トロけるなあ。
傷つきやすそうな繊細さもあれば、自立した女性の逞しさも感じさせるソフトな歌い口。
そのソングライティングは、ドラマティックとは対照的な抑制の利いたもので、
情景に託して感情の機微を伝えることが巧みな人のようです。
なるほど H.E.R. の ‘U’ ‘Changes’ を書いた人だと、独り言ちしました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-03-06
フックの利いたメロディに、熟達したソングライティングの才を感じながら、
スロウ・ジャムでのムーディな歌声に酔いしれます。
全8曲18分40秒という短さにもかかわらず、充足した聴後感を得られるアルバムですね。
Ambré "3000°" Roc Nation ROC00565-02 (2022)
2023-03-05 00:00
コメント(0)
オルタナティヴR&Bの洗練 レイヴン・レネー [北アメリカ]

そして、こちらも配信を聴いて、気に入っていた一枚。
CDを出してくれるのは嬉しいんだけど、なんとまあCD-Rですよ。
名門アトランティックの名が泣く、この所業。
3年前のケラーニの悪夢、再びであります。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-11-01
ケラーニのCDよりヒドいのは、インナーがペラ紙一枚で、
裏にQRコードが付いてるだけというアイソのなさ。
QRコードを読み込めば、歌詞やクレジットが出てくるのかと思いきや、
あるのは曲目のみ。曲目ならバックインレイに載ってるんだから、
このQRコード、意味ないじゃん。
ティンクの新作で、羽根を忍ばせるような洒落た演出を体験した後だけに、ガックリ。
イマドキのデジタル・ネイティヴのアメリカ人らしい仕事ぶりだよな。
で、主役のレイヴン・レネーですけれど、オルタナティヴR&Bのニュー・スター、
これが初フル・アルバムであります。
満を持したという感じで、プロダクションのクオリティは群を抜いてますね。
アルバム冒頭、重厚なシンセ・ベース音に始まるエレクトロ強めなトラックに載せ、
レイヴンがささやく甘いウィスパリング・ヴォイスに、持っていかれます。
ヘヴィーなサウンドと、ライトなヴォイスという取り合わせが絶妙で、
『ピロー・トーク』というアルバム・タイトルは、
ティンクよりこちらの方がお似合いではと、思っちゃいましたよ。
そのティンクと同じシカゴ出身という、レイヴン・レネー。
ティンクのバックグラウンドがヒップ・ホップなら、
レイヴンのバックグラウンドはシカゴ・ハウスですね。
エレクトロ/ハウスのプロデューサー、ケイトラナダの参加は、どハマリといえます。
そういえば、ケイトラナダって、生まれはハイチのポルトープランスなんだよね。
リズミカルな発声のキレも抜群のティンクに対し、
ファルセットを織り交ぜ、美しいレガートでささやくレイヴンの歌唱スタイルは、
まさに好対照で、二人の個性がくっきりと浮き立ちます。
冒頭2曲のような、エレクトロ・ファンクもあれば、
ギターをぽろんと鳴らしながら、ストリングスをフィーチャーした
麗しいアクースティックなトラックもあり、起伏に富んだアルバム構成が巧み。
まんまアフロビーツの ‘M.I.A.’ もあれば、
ムーンチャイルドを思わすドリーミーな ‘Higher’、
ソウルフルなハウス・トラックの ‘Xtasy’もあります。
オルタナティヴR&Bの尖った実験性がそぎ落とされ、
歌ものとして洗練されているところに、このジャンルの進化を感じさせます。
Ravyn Lenae "HYPNOS" Atlantic 075678633256 (2022)
2023-02-01 00:00
コメント(0)
2020年代R&Bの官能 ティンク [北アメリカ]

配信のみといわれてたのが、いつのまにかCDが出てる、なんてことがありますね。
R&B方面に多くて、フィジカル大好き人間には、歓迎すべきことなんだけど、
だからって、そのためにリストを作って、チェックするような熱はとてもなく。
なので、きっと見逃し案件もあるんだろうなあ。
R&Bばかりでなく、ジャズや日本の音楽も、
たまたま知ったのを聴く程度のファンにすぎないから、
まあ、そんな出会いだけで十分と、割り切っております。
ティンクの新作CDも、そんな出会い。去年の9月に出ていたみたい。
ティンバランドにフックアップされたティンク、ラッパーでもあるところに、
彼女のシンガーとしての魅力があると、思っているんですよね。
骨太なラップを叩き込む滑舌の良さとリズム感が、
キレのいい歌のディクションにも連動していて、
ラッパーでもあり、シンガーでもあるという、相乗効果をもたらしているからです。
新作は、全編スロー・ジャム。90年代R&Bテイストの強いサウンドで、
タイトルが「ピロー・トーク」とくるんだから、濃密なセクシーさに溢れるのも当然。
ブルージーなムードを漂わせるなど、ティンクもすっかり
アダルト・オリエンテッドな歌を聞かせるようになったんですねえ。
デスティニーズ・チャイルドをサンプリングした‘Cater’ や、
マニー・ロングをフィーチャーした‘Mine’ でも、貫禄あるおネエさんぶり。
わずか3作目にして、はや中堅の風格を漂わせていますね。
16曲も入っているものの、収録時間は50分に満たず、
長いという印象を与えないのは、1曲が2・3分台の短い曲ばかりだから。
飛びぬけてキャッチーな曲はないけれど、落ち着いたムードで統一されていて、
ラグジュアリーな麗しさに酔えます。
クラシックなR&Bの話法を使いながら、2020年代らしさを味わえる得難いアルバム。
CDのトレイを開けると、白い羽根が一枚、ふわりと飛び出してきて、
ライナー写真の羽毛布団を連想させる、シャレた演出も嬉しいですね。
Tink "PILLOW TALK" Winter’s Diary/WD/Empire ERE851 (2022)
2023-01-30 00:00
コメント(0)
アルメニア系アメリカ人演奏家の道のり スーレン・バロニアン [北アメリカ]

サックス/クラリネット奏者のスーレン・バロニアンは、
ニュー・ヨーク育ちのアルメニア移民二世。
スーレンが70年に立ち上げたという、カルリー・レコーズから出たリーダー作3作を、
まるごと2枚のディスクに収めたリイシューCDが出て、初めてこの人を知りました。
エキゾ趣味なジャケット・デザインに、安直なベリー・ダンスものかと思ったら、大間違い。
抒情性溢れるアルメニアの伝統メロディを生かしたサウンドがたっぷりと味わえ、
すっかり気に入ってしまいました。
CDにはスーレン・バロニアンの来歴が詳細に紹介されていて、
アルメニア移民二世の音楽家が歩んできた道のりをたどることができます。
30年2月25日、ニュー・ヨークに暮らす
アルメニア移民の両親のもとに生まれたスーレンは、
アルメニア移民が集うグリーク・タウンで、
アルメニア、ギリシャ、トルコ、アラブ出身の音楽家たちに刺激され、
16歳でサックスとクラリネットを習い始めました。
同時に、いとこに連れられ、52番街のジャズ・クラブへこっそり入っては、
レスター・ヤングやチャーリー・パーカーを聴き、
ジャズに情熱を燃やす少年時代を送ります。
戦後まもないグリーク・タウンには、わずか2ブロックに
ベリー・ダンサーのいるクラブが8つも9つもあり、活況を極めていたようです。
なかには違法な性的サービスをする店もあり、
スーレン曰く「ファンキーな場所だった」この街で、
アルメニアやトルコ、アラブの音楽を学んだのですね。
18歳の時、同じアルメニア系のウード奏者チャールズ・チック・ガニミアンに誘われ、
スーレンのクラリネットとパーカッションの3人でザ・ノー・アイクスを結成し、
アルメニア移民のダンス・パーティや結婚式、ピクニックで演奏しました。
アメリカ初のアルメニア人バンドだったというザ・ノー・アイクスは、
50年に2曲をレコーディングし、グリーク・タウンのアルメニア人・ギリシャ人・
トルコ人の店で彼らのSPが売られたそうです。
スーレンはザ・ノー・アイクスのほかに、ジャズ・ミュージシャンを集めて
ジャズ・クラブでも活動し、51年に朝鮮戦争で徴兵されると、
軍で一緒になったナット・アダレイとキャノンボール・アダレイとも演奏したそうです。
除隊後アメリカへ帰国してからは、本格的な音楽活動を再開するために、
レニー・トリスターノとウォーン・マーシュに師事してジャズを、
トルコ古典音楽の名クラリネット奏者サフェット・ギュンデールに師事して、
トルコ音楽を学びました。
59年にアトコから、中東音楽とジャズのミクスチャー企画を持ちかけられ、
ガニミアン&ヒズ・オリエンタル・ミュージック名義で
“COME WITH ME TO THE CASBAH” を出し、
シングル・カットされた ‘Daddy Lolo’ がラジオで人気を呼び、ポップ・ヒットとなります。
ガニミアン&ヒズ・オリエンタル・ミュージックのアルバムはこの1作で終わりますが、
その後スーレンは、ベリー・ダンスのレコードや、オリエンタル・ムードを加味した
ジャズ・アルバムの企画(フィル・ウッズの67年作 “GREEK COOKING” や
トニー・スコットの68年ヴァーヴ盤 “TONY SCOTT”)など、
多方面からお呼びがかかり、数多くの録音に名前を残します。
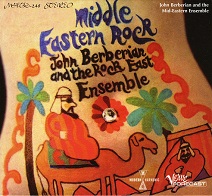
なかでも話題を呼んだのが、中東音楽とクールなサイケデリック・ジャズをミックスした
“MIDDLE EASTERN ROCK”(69)でした。
ジョー・ベックのギターをフィーチャーし、ファズ・アウトしたサイケなサウンドは、
当時のジャズ・ロックの流行に乗じて企画されたもののようです。
しかし、スーレンはこのサイケ・サウンドが気にくわなかったようで、
それがのちに自身のレーベルを立ち上げて、
より伝統的なサウンドを追及することに繋がったんですね。
“MIDDLE EASTERN ROCK” もCD化されたばかりなので、買ってみたところ、
なるほどスーレンが納得できなかったのも、わかるような気がしました。
ジャズを演奏するつもりだったのが、中東風のサイケ・ロックを演じさせられて、
怒り心頭になったのでしょう。リズム・センスが完全にロック・ビートで、
ロック的な熱狂を演じるジョン・ベルベリアンのウードのプレイも、伝統を逸脱していて、
ロックへすり寄る姿勢が、スーレンはイヤだったんじゃないかな。
本作は、サイケ好きのロック・ファンから、カルト的人気を呼ぶアルバムだそうですが、
ロックが未成熟だった時代ならではの、
異文化を取り込むときの傲慢さが見え隠れする作品ですね。
中東文化になんの興味もないロック・ファン相手には、どんな名手の演奏も、
エキゾ趣味をくすぐるスパイスにしかならなかったのは、当時の宿命のようなもの。
半世紀を経て、平均的なアメリカ人でさえ異文化理解が進んだ今となっては、
隔世の感を感じ取れる作品といえるかもしれません。
21世紀の今、半世紀を経て再評価するのはけっこうだけど、
過去の作品に新たな文脈を見つけるのなら、
異文化に接する態度に、見直しが求められていることへの自覚が必要でしょうね。
この作品への反発から、スーレンはジョン・バーベリアンと別れ、
より伝統的なサウンドをめざして、相棒の歌手ボブ・タシュジャンとともに、
カルリー・レコーズを設立。スーレンの息子のカールと
ボブ・タシュジャンの息子リーの名前をくっつけて、レーベル名にしました。
カルリー・レコーズのもとで、“MIDDLE EASTERN SOUL”
“THE EXCITING MUSIC OF THE NOR-iKES”
“HYE INSPIRATIN” の3作を制作、
それが今回コンプリートで復刻されました。
3作とも、レパートリーの多くはアルメニア由来の曲で、
エキゾ趣味を排した抒情性豊かな演唱に、
スーレンのアルメニア人音楽家の志が映されています。
特に印象に残るのが、“MIDDLE EASTERN SOUL” のオープニング曲
‘Siro Yerk’ にフィーチャーされた女性歌手。
偶然リハーサルに来ていた16歳の少女で、
スーレンは彼女の歌声に魅了されてすぐさま起用したそうで、
みずみずしい情感を聞かせています。
Souren Baronian "THE MIDDLE EASTERN SOUL OF CARLEE RECORDS" Modern Harmonic MHCD253
John Berberian & The Middle Eastern Ensemble "MIDDLE EASTERN ROCK" Verve Forecast/Modern Harmonic
MHCD248 (1969)
2023-01-14 00:00
コメント(0)
サウンドの領域を広げた新作 サムスクリュー [北アメリカ]
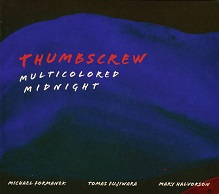
メアリー・ハルヴァーソンのノンサッチ2作品は、ぼくには不満が多く、
ちまたの絶賛ぶりに、首をかしげております。
メジャーのノンサッチから出たから、ホメてるだけなんでは?
ま、それは邪推だろうけど、あいかわらず世間とソリが合わないよな。毎度のことだけど。
そんなこんなで、待ち望んでいたのは、サムスクリューの新作の方。
ハルヴァーソンとベーシストのマイケル・フォーマネック、ドラマーのトマス・フジワラが
12年に結成したサムスクリューは、もう活動歴10年。本作で7作目を数えます。
活動歴の長さがもたらす相互信頼が、奔放な即興を生み出した、聴き応え十分のアルバム。
う~ん、こういうのが聴きたかった。
メンバーそれぞれが書いた緻密な構成を持つコンポジションを、
緊張と弛緩を繰り返しながらプレイする、集中力の高さがスゴイ。
ハルヴァーソンが、常に予想の斜め上を行く即興を繰り出し、
DL4使いのピッチ・モジュレーション・エフェクトが、難解なメロディに並走して、
雄弁なラインを奏でてます。もう、ヴォキャブラリーの豊富さに圧倒されますよ。
今回の新機軸は、フォーマネックが操るエレクトロニクス。
フォーマネックは、コントラバスに接続したエフェクトでトリッキーなサウンドを生み出し、
ハルヴァーソンのピッチ・モジュレーションと相乗効果をもたらしています。
また、フジワラがヴィブラフォンが演奏しているのも、聴きどころ。
以前、アンソニー・ブラクストン・プロジェクトでも、
フジワラはヴィブラフォンを演奏していましたけれど、
サウンドに新たな色彩を加えていて、トリオの音楽性を拡張しています。
10年の活動を経て、サウンドの可能性を模索し続けている、
三人の新たなチャレンジが聴き取れる快作です。
Thumbscrew "MULTICOLORED MIDNIGHT" Cuneiform RUNE485 (2022)
2023-01-12 00:00
コメント(0)
ソウル&ブルースの帝王 ウィリー・クレイトン [北アメリカ]
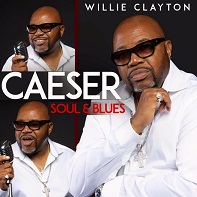
はぁ、今作もサイコー。
やっぱウィリー・クレイトンは、現行サザン・ソウルの最高峰。
去年のアルバム・タイトル『ソウルの帝王』を上回る、
『ソウル&ブルースの帝王』というタイトルに、なんの異存がありましょうか。
御年67歳。ヴェテランならではの歌い口を、これでもかというほど堪能させてくれます。
今日びソウルらしいソウルを歌えるシンガーは、ほんとに少なくなりましたけれど、
この人くらいオールド・スクールなソウルの味わいを、
リアルに感じさせてくれる人はいません。
なんだか最近、レトロねらいのR&Bシンガーがやたらと出てくるけど、
ロードに出もしないで、黒人クラブの現場感なんてまるでないシンガーに、
肩入れはできないよなあ。チタリン・サーキットで鍛えられたシンガーとは、
歌いぶりがまるで違うもん。語りかける力、とでもいうのかなあ。
ステージから観客の女性を見つめて口説いちゃうような、<歌ぢから>がなきゃねえ。
ずいぶん昔にも、この人のアルバムにホレこんで記事を書きましたけれど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2009-11-05
その後コンスタントに出すアルバムも、常に水準以上なのがスゴイ。
20年作の “BORN TO SING” も良かったけれど、
ドラム・マシンがなぁ、などと正直思ったりもしてたんですよね。
でも、今回は違います。
生演奏をふんだんに取り入れたプロダクションで、がぜん聴き応えが5割増し。
ホーンは伝説のマラコ・スタジオで、
ストリングスはラス・ヴェガスで録音したっていうんだから、
ゴージャスじゃないですか。ミックスも良くなったんじゃない?
スムースな ‘On What A Night’ でスタートし、
サザン・ソウル定番の不倫ソング(間男ソング?)とおぼしき ‘Part Time Lover’ の
ステッパー2連チャンで、はやこのアルバムのトリコになりました。
ウィリーの狂おしいヴォーカルが、生演奏に映えることといったら、もう悶絶。
ロック・ギターをフィーチャーしたファンキーな ‘How You Do That’、
ブルージーなブルーズン・ソウルの ‘Get Next To You’、
ヴォコーダーも織り交ぜた ‘Love Machine’、
スロー・バラードの ‘Don't Make Me Beg’ 、
カラーの異なる1曲1曲を丁寧に練り上げていて、
過去作にまして聴き応えのあるアルバムとなっています。
楽曲も半数がウィリーのオリジナルで、
残り半数もウィリーとクリストファー・フォレストとの共作なんだから、
ソングライターとしての充実ぶりも光り輝く傑作です。
Willie Clayton "CAESER SOUL & BLUES" Endzone no number (2022)
2022-12-07 00:00
コメント(0)
ミシシッピ、ジャクソンのメロウネス J=ウォン [北アメリカ]
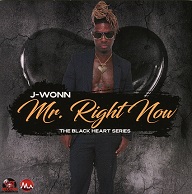
冬はR&B。
今年もコンテンポラリー・サザン・ソウルであったまろうと、
いろいろ試聴してみたら、J=ウォンの新作がいいじゃないの。
3年前にこの人の “MY TURN” を聴いて、才能を感じてたんですけど、
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2019-12-13
ワタクシの目に狂いはありませんでした。いいシンガーに成長しましたよ。
今作は、昨年デジタル・リリースされた5曲入りEPと、
今年デジタル・リリースされた6曲入りのEPをカップリングCD化したものとのこと。
ちゃんとフィジカルで出してくれるのは、嬉しい限りですね。
J=ウォンの魅力は、第一に、少年ぽい色気が充満の声質。
ナイーヴなティーンエイジの恋愛観を歌うのには、ピッタリな気がしますね。
ご本人はもう30超えだけども。
じっさいどういう歌詞を歌っているのかは知らないけれど、
アダルト・オリエンテッドな世界ではないでしょう。
前回はメロウな歌い口に魅力を感じていたんですけど、
今回はキレのある歌いぶりに感心しました。う~ん、イキオイあるなあ。
インディという枠を越えて、メジャーでも十分活躍できるシンガーなんじゃないの。
90年代R&Bへと回帰する美メロ路線が、
この人の持ち味とバツグンの相性を示していて、
ミシシッピ、ジャクソン出身とは思えぬ、
サザン・ソウルのイメージ皆無の、スウィートなR&Bを楽しめます。
J-Wonn "MR. RIGHT NOW" Music Access no number (2022)
2022-12-05 00:00
コメント(0)
R&Bソングライターのメロウ・グルーヴ傑作 マニー・ロング [北アメリカ]

涙腺崩壊。
この温かな声。柔らかく耳に絡みついてくる、人なつっこい節回し。
フックの利きまくった楽曲に、90年代R&Bフィール濃厚なサウンド。
ライミングを効果的に使った歌詞が生み出すグルーヴ。
フェイクから溢れ出す狂おしさに、これが泣かずにいられよかというアルバムです。
プリシラ・レネイの本名で、リアーナ、メアリー・J. ブライジ、マライア・キャリー、
アリアナ・グランデなど、R&Bとポップスの双方で、
数々のヒット曲を手がけるソングライターとして活躍するも、
ソロ・アーティストとしてはなかなか成功できずにいたという彼女。
マニー・ロングと改名し、昨年デフ・ジャムと契約して再出発。
プリシラ・レネイ時代から通算19曲目となる ‘Hrs and Hrs’ がついにバズって、
ようやく表舞台へとジャンプした、80年代生まれの苦労人なのですね。
ぼくも昨年 ‘Hrs and Hrs’ が収録されたEPを聴いて、
CD欲しい!と身をよじってたクチだったんですが(フィジカルはLPのみ)、
続編EPと抱き合わせで、さらに新曲を追加した初アルバムがCDリリース!
で、冒頭の涙腺崩壊となったわけなんですが、
ほんとパーフェクトじゃん、このアルバム。
18曲も詰め込んでるのに、飽きがこないのは、1曲1曲のカラーが違うから。
派手にキャッチーなメロディで、曲の一部を浮き立たせる作風ではなく、
曲の流れでじっくり聞かせる力があって、丁寧に情感を伝える楽曲が揃っています。
さすが長年裏方で、ヒット・メイカーのキャリアを積んできた実力者だけあります。
スウィーティーとコラボした ‘Baby Boo’ だけが、ほかと毛色が違っていて、
ベース・ミュージック仕立ての、サマー・アンセムぽい曲。
これをラストに置いたのは、大正解でした。
全編、90年代R&Bのメロウなテイストが覆っていて、
懐かしさいでいっぱいになるんですけれど、それはオッサンの感想。
懐古ネライのアルバムでは、けっしてありません。
ロマンティックなR&B好きにはたまらない、メロウ・グルーヴの大傑作です。
Muni Long "PUBLIC DISPLAYS OF AFFECTION: THE ALBUM" Supergiant B0035943-02 (2022)
2022-11-09 00:00
コメント(0)
Kawaii エレクトロニカ・ジャズ/フュージョン ドミ&JD・ベック [北アメリカ]

世界中大絶賛のドミ&JD・ベック。
8月13日放送のNHKの音楽番組「おげんさんのサブスク堂」で、
松重豊がいまイチオシと、鼻息荒く紹介したんだけど、
星野源にアメリカでライヴを観たとあっさりいなされて、
唖然とする松重がちょっとカワイソーだったけど、面白かった。
ワタクシも一聴して、こりゃ買いだと走ったんですが、CDショップにあるのはEU盤ばかり。
EU盤を回避して、オリジナルのUS盤を購入するいつもの手段で、
アメリカの Amazon にオーダーしてみたら、なんとEU盤が送られてきた(呆)。
えぇ~? なんだよー、こんなの初めてだぞ。いったいどうすりゃ、いいねん!
どうでもいい話はこれくらいにして、もうご存知ですよね。
03年生まれの超絶技巧のドラマーと、00年生まれ、パリ国立高等音楽院ピアノ科卒、
バークリー音楽院を大統領奨学金全額支給で入学した鍵盤奏者のデュオ。
19歳と22歳にして、ハービー・ハンコック、フライング・ロータス、ルイス・コール、
ザ・ルーツ、サンダーキャット、アンダーソン・パークなどと共演経験を持つこの二人。
名だたるアーティストがラヴ・コールを送るのも、このデビュー作を聴けばナットクです。
高速ドラムンベースを涼しい顔で人力演奏するJD・ベックのドラミングには、
マッドリブ育ちのヒップ・ホップ・ビートが身体に染みついてますね。
8歳からドラムスを、12歳でプロデュースを始め、
多くのアーティストの楽曲制作に関わってきたというんだから、底知れぬ才能だよなあ。
オープニングで、ストリングスをフィーチャーしたゴージャスなプロダクションだったのは、
意外な演出でしたけれど、そこからも汲み取れる複雑なハーモニーに、
二人の音楽性の深さがわかります。
高音をカットした、くぐもったドラムスの音質で、エッジの立たない音像の作り方が、
キーファーやブル・ラブ・ビーツあたりのセンスに通じますね。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2018-08-28
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2022-03-30
甘美な鍵盤とともに中低音が豊かで、ポップでキャッチーな楽曲を、
鮮やかなエレクトロニカ・ジャズ/フュージョンに昇華しています。
主役の二人が、余裕すら感じる演奏と歌声を聞かせるのに、
錚々たるゲストたちの方が緊張みなぎっているところが、面白い。
サンダーキャットが硬質なベース音で存在感を際立たせる‘Bowling’、
ハービー・ハンコックが“SUNLIGHT” 時代を思わすヴォコーダーを駆使した‘Moon’、
カート・ローゼンウィンケルがリキの入ったギター・ソロを弾きまくった‘Whoa’ などなど、
トンデモな若い才能を前に、大のオトナがマジで必死になってる様子が伝わってきます。
DOMi & JD BECK "NOT TiGHT" Apeshit/Blue Note 00602445908363 (2022)
2022-10-28 00:00
コメント(0)
R&Bの秋 メン・アット・ラージ [北アメリカ]

ジェラルド・リヴァートに発掘された巨漢デュオ、メン・アット・ラージの新作。
92年のデビュー曲‘Use Me’ を1曲目で再演しているので、へぇと思ったら、
これ、あの‘Use Me’? ぜんぜん別の曲に聞こえるんだけど。
ニュー・ジャック・スウィングに特に愛着はありませんが、
独特のハネのある16分三連を聴くと、やっぱ懐かしい気分になりますね。
その同じ曲とは思えない‘Use Me’以降は、ミッド/スローが並んだアルバム。
キャッチーなメロディで惹きつける派手さはないものの、
落ち着いたムードで聞ける佳曲が多くて、リラックスできますねえ。
二人のまろやかなハーモニーも健在で、‘Real Close’ なんてトロけます。
92年のデビュー作以降、メン・アット・ラージを聴いていませんでしたが、
3作目からジェイソン・チャンピオンが抜け、メンバーを替えて活動していたんですね。
オリジナル・メンバーの、デイヴ・トリヴァーとジェイソン・チャンピオンのコンビ復活は、
なんと26年ぶりなんだそうです。
二人のヴォーカル・スタイルは、競い合うタイプじゃないので、マイルドなんですよね。
ラップふうのヴォーカルでトラップ・ビートにのる曲もあるけれど、
自分たちのスタイルに引き寄せているから、
トレンドに色目を使ったニュアンスにならず、めちゃ好感持てます。
秋の気配を感じられるようになると、R&Bが恋しくなるんですよ。
去年のアフター7を、また聴き返し始めたところに、嬉しい1枚が増えました。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2021-10-11
Men At Large "LOVE BENEFITS" SoNo Recording Group no number (2022)
2022-10-26 00:00
コメント(0)
イノヴェイティヴなフィンガースタイル・ギター ヤスミン・ウィリアムズ [北アメリカ]
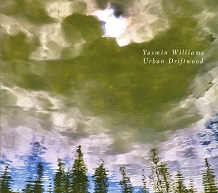
ひさしぶりにスラック・キー・ギターのアルバムを
いろいろ聴いていたのが呼び水になったのか、
ステキなアクースティック・ギターのアルバムと出会えました。
サリー・アン・モーガンのインタヴュー記事で、
最近聴いているアルバムとして挙げられていた、
アクースティック・ギタリスト、ヤスミン・ウィリアムズの20年作です。
18年にデビューした新進のフィンガースタイル・ギタリストで、これが2作目。
サリーがジャケットのレイアウトとデザインをしていて、親交があるようですね。
カントリー・ブルースをベースにゴシックな表現をするジョン・フェイヒーや、
ジャズやクラシックを越境するラルフ・タウナーといったタイプではなく、
マイケル・ヘッジスのようなニュー・エイジ系ギタリストといっていいのかな。
ブルース、フォーク、ジャズ、いかなる伝統にも縛られない音楽ですね。
このタイプのアクースティック・ギタリストで、アルバム一枚聴き通せる作品に、
あまり出会えた試しがないんですけれど、これは満足しました。
スラック・キー・ギター・ファンにもオススメできますよ。
こういうギター音楽って、どうしても超絶技巧だとか、独創的な奏法が売りになって、
ギターのための音楽になってしまうところが、手段の目的化そのもの。
ギターは音楽の道具であって、その逆じゃないですからねえ。
ヤスミンは、膝の上にギターを置いてタップして弾くのと、
アップライトに持ち替えて通常のフォームで弾くのをシームレスに切り替え、
曲のパートによって奏法を使い分けています。
さらに、ギターのボディにカリンバを貼り付け、
右手でカリンバ、左手で指盤をタップしながら演奏もしているんですね。
YouTube で観ると、どうしてもその演奏法ばかりに目が釘付けになり、
肝心の音楽が右から左へ抜けていってしまいます。
曲弾きのように思われるのは、ヤスミンにとっても本意ではないはずなので、
ライヴを観るより、音だけを楽しむ方が正解でしょうね。
じっさい、ぼくが本作に惹かれたのも、
この音楽が作曲優先で制作されているのが、きちんと伝わってくるからです。
ギターの奏法優先で作られた曲とは、アンビエンスがぜんぜん違いますもん。
歌を感じさせるメロディが落とし込まれたコンポジションを、
イマジネイティヴなパフォーマンスによって、幽玄なサウンドをクリエイトしたり、
優美で繊細な表情を見せたり、パーカッシヴな生々しいエネルギーを噴出したりと、
さまざまなテクスチャで表現しています。
チェロとジェンベがゲストで参加する2曲を聴くと、
このイマジネイティヴな才能は、ソロ演奏にとどまらず、
さらにアンサンブルで豊かな才能を開花させていきそうで、これからも期待できますね。
Yasmin Williams "URBAN DRIFTWOOD" Spinster SIS0006 (2020)
2022-08-09 00:00
コメント(0)
フュージョン・ヴァイオリンの名作 ミハウ・ウルバニャク [北アメリカ]
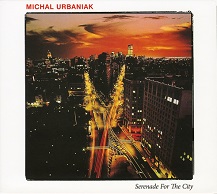
「マイケル・ウルバニアク」と書かれることがもっぱらの、
ポーランド出身のジャズ・ヴァイオリニスト。
「ミハウ・ウルバニャク」と書いた方がいいんじゃないかと思うんですが、
この人のフュージョン作で、80年にモータウンから出たアルバムを、
その昔愛聴していました。
ベースにマーカス・ミラー、ドラムスにバディ・ウィリアムズ、ヨギ・ホートンという、
当時のニュー・ヨークでファースト・コールのミュージシャンが参集。
このアルバムが出た同じ80年に、
マーカス・ミラーは渡辺香津美の『TO CHI KA』で、
バディ・ウィリアムズは川崎燎の『LIVE』で共演し、日本でも大人気でした。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2011-05-29
そして、ピアノにはケニー・カークランド、ギターはドック・パウエルが
参加しているんだから、このメンバーを見ただけで、買いでしたね。
ウルバニャクはクセのある音楽をやる人で、女房のウルシュラ・ドゥジャクの
エキセントリックなヴォーカルが興ざめなこともあり、長く敬遠してましたけれど、
本作は珍しく(?)ジャケットの趣味も良く、飛びついたんだっけ。
モータウンから出たフュージョン作という珍しさが災いしたか、
長らくCD化が実現しませんでしたけれど、
ウルバニャクの自主レーベルUBXから、CD化されました。
聴いてみると、知らない曲がいきなり飛び出して、びっくり。
なんと冒頭1曲目とラスト2曲に、LP未収録曲が追加されているんですね。
ソング・リストにもクレジットにも、追加に関してなんの説明もなくて、
この3曲、未発表曲だったってことなの?
最初聴いた時は、驚きはしたものの、
3曲それぞれが座りのいい曲順に配置されていて、
オリジナルLPを知らなければ、違和感なく聞けるんじゃないですかね。
キャッチーなコーラスが加わるポップな‘Bad Times’ を
アタマに置いたのなんて、大正解じゃないですか。
もともとこういう曲順で出す予定が、なんらかの事情でカットしたのかなあ。
というわけで、オリジナルより内容が良くなった本作、
40年ぶりに聞いても、まったく古さを感じさせません。
ウルバニャクのオリジナルに、マーカス・ミラーが作曲した曲や、
『ネフェルティティ』でよく知られるウェイン・ショーター作の‘Fall’ もやってます。
フュージョン・ヴァイオリンでは、ノエル・ポインターのデビュー作
“PHANTAZIA” とともに、忘れられない名作です。
ところで、追加された‘Bad Times’ ‘North One’ ‘French Kiss’ 3曲について
調べてみたところ、ストリーミングに上がっている“SOMETHING SPECIAL” という
タイトルのアルバムに収録されていることが判明しました。
81年リリースという表示があるものの、ミハウ・ウルバニャクの公式サイトにも、
ウィキペディアほかのディスコグラフィにも、このアルバムの記載がなぜかありません。
フィジカルの存在を調べてみると、“MICHAL URBANIAK” のタイトルで、
ヘッドファーストというMCA系列のレーベルから出ていたことがわかりました。
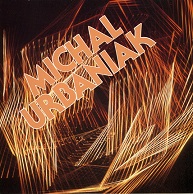
ジャケットはストリーミングのものと違っていて、なんだか手抜きぽいデザイン。
なんとかCDを入手してみたんですが、“SERENADE FOR THE CITY” と
レコーディング・スタジオ、エンジニアも同じなら、
参加ミュージシャンの顔ぶれもほぼ同様です。
ところが、録音年月日の記載がないので、同時期の録音なのかどうかわかりません。
アルバムもう1枚分を録音していたのを、翌年にリリースしたものなのかなあ。
もうひとつ引っかかるのが、81年ならば、CDのみリリースというのは
考えにくいんですけれど、LPの存在が確認できないのも不可解です。
MCA系列のレーベルから出ているので、非公式な盤であるわけないでしょうが、
公式サイトも無視するこのCD、どうにもナゾですね。
Michal Urbaniak "SERENADE FOR THE CITY" UBX UBX10280 (1980)
Michal Urbaniak "MICHAL URBANIAK" Headfirst A635-2 (1981)
2022-08-03 00:00
コメント(0)
オフィシャル・リリースされた名ブートレグ リトル・フィート [北アメリカ]

リトル・フィート・ファンにはおなじみのブートレグが、ライノからオフィシャルCD化!
なんと、去年11月のレコード・ストア・デイの限定商品で、リリースされていたんですと。
レコード・ストア・デイとは縁がないもので、ぜんぜん知りませんでした。
即完売となったものの、数量限定で再流通したらしく、
ロック方面にウトい自分も、ようやくそれで気付くことができました。
音源は、74年9月19日、FMラジオWLIRの放送のために
ニュー・ヨークのレコーディング・スタジオで行われたスタジオ・ライヴ。
ブートレグ未収録の曲もたっぷり入った全11トラック、収録時間73分48秒。
実はこのブートレグ、高校生の時、持っていたんですよ。
その後、シンガー・ソングライター系のロックのレコードを大量処分したのに合わせて、
このブートレグも手放してしまったんですけれどね。
ブートレグのジャケットに貼られていたイラストと同じトナカイが、
ライノ盤でもデザインされていますね。
40年ぶりくらいの再会になるのかなあ。
もう記憶はあいまいですけれど、こんなにいい音じゃありませんでしたよ。
オフィシャル・リリースで、ミックスをやり直したんでしょう。
スタジオ録音にヒケをとらないクオリティに、びっくりしました。
特に嬉しいのが、リッチー・ヘイワードのヘヴィーなドラムス・サウンドが
ちゃんと再現されていること。
リトル・フィートというと、ローウェル・ジョージのスライド・ギターばかりに
スポットが当たるけれど、ぼくはリッチーが叩き出すスネアの、
どすっ!という重たいシンコペーションが大好物なんですよ。
リトル・フィートのバンド・サウンドの要は、リッチーのドラムスだって。
FMラジオWCBN放送の75年ライヴでも、
ここまでファットなサウンドが再現されなかったから、
やっぱ、ちゃんとミックスし直すと、こんなに良くなるんですねえ。
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2013-09-19
ブートレグLPには収録されていなかった
‘Sailin' Shoes’ や ‘Dixie Chicken’ も聴けて、大満足。
やっぱこの頃のローウェル・ジョージのヴォーカルは、最高ですよねえ。
77年のツアーを収録した“WAITING FOR COLUMBUS” では、
ローウェルからこういう輝きが失われていました。
ちまたで評判の8枚組のスーパー・デラックス・エディションは、ぼくには不要。
この74年ライヴだけで十分です。
Little Feat "ELECTRIF LYCANTHROPE: LIVE AT ULTRA-SONIC STUDIOS, 1974" Rhino R2 556518/081227943752
2022-08-01 00:00
コメント(0)
アメリカン・フォークの実験場 サリー・アン・モーガン [北アメリカ]

アパラチアの伝統音楽を拡張するマルチ奏者、サリー・アン・モーガンの第2作。
昨年11月にデジタル・リリースされて、遅れること7か月、
ようやくCDがリリースされ、手元に届きました。
プリ・オーダーしていたのも、すっかり忘れてたんですが、
なんとデジタル版より2曲多く収録されていて、わーい(*´▽`*)
https://bunboni58.blog.ss-blog.jp/2020-11-23
サリーのデビュー作で披露された、伝統音楽の枠をはみ出る実験的な音楽性に、
どういうバックグランドの人なんだろうと思っていたんですが、
サリーのインタヴューを読んでびっくりしました。
初めて買ったレコードが、ボブ・マーリーの『エクソダス』なのには、
微笑ましく思いましたけれど、
絶対に手放せない10枚のレコードとして挙げたアーティストに、
アリス・コルトレーン、ドン・チェリー、アーサー・ラッセル、ジョン・コルトレーン、
ローリー・シュピーゲルの名があるのには、ノケぞりましたね。
真っ先に、ディラード・チャンドラーとクライド・ダヴェンポートという
アパラチア伝統音楽の2枚がリスト・アップされていたとはいえ、
残りの8枚がジャズに現代音楽、電子音楽というセレクトは、意外すぎました。
な~るほどねえ、こういう音楽遍歴の人だと知れば、
今作のインスト集も、素直に受け止めることができます。
全曲サリーが自作したインスト曲なんですけれど
(CDのみ追加の2曲のうち1曲は伝承曲)、
伝統音楽のメロディやリズムの断片をパッチワークしたような曲で、
即興の占めるパートが大きいんですね。
即興といっても、伝統音楽の演奏家による即興演奏とは本質的に異なり、
ミニマルなアプローチや、ヴァースとコーラスといった構成からの逸脱など、
随所に現代音楽や電子音楽から吸収してきたアプローチをしています。
サリーはギター、バンジョー、ダルシマー、フィドル、グロッケンシュピール、
木琴、小物打楽器など、さまざまな楽器を多重録音して、
自由で発想力豊かなサウンドスケープを生み出しています。
フォークトロニカや音響派をホウフツさせる、
まったく新しいアプローチのアメリカン・フォーク、ユニークですねえ。

* Thrill Jockey のツイートより無断転載 (あまりにいい写真なもんで)
Sally Anne Morgan "CUPS" Thrill Jockey THRILL562 (2021)
2022-07-24 00:00
コメント(0)
ヒューストン・ブルーズン・ソウル・レディ ダイユーナ・グリーンリーフ [北アメリカ]

ひさしぶりに、グッとくるブルース・シンガーに出会いました。
ダイユーナ・グリーンリーフ。57年ヒューストン生まれという、
ぼくの一つ年上のブルース・レディであります。
ソウル、ゴスペル色の強いブルーズン・ソウルを歌っているんですけれど、
力のあるヴォーカルには円熟味があって、感じ入っちゃいましたよ。
シャウトをしても無理がなく、内から湧きあがるソウルフルな衝動が
素直に伝わってきて、胸をすきます。
西海岸ブルース・シーンの立役者キッド・アンダーセンのプロデュースで、
もちろんギタリストとしても演奏に参加しています。バックが豪華で、
ジェリー・ジェモットがベースを弾いているのには、涙目になっちゃいました。
最初そうとは知らずに聴いていて、スゲエなこのグイノリ・ベース、誰?と
クレジットをチェックして、目が点になりましたよ。
いまも現役バリバリなんですね、ジェリー・ジェモットって。
ドライヴ感がハンパなくって、衰えを知らないベース・プレイにシビれました。
ほかにも、サックス・ゴードンのホンク・テナーが吠えまくり、
70年代を思わすホーン・セクションもばっちりキマっています。
ダイユーナは両親がゴスペル歌手で、幼い頃から歌ってはいたものの、
プロのシンガーとなったのは40過ぎというのだから、遅咲きの人ですね。
レコーディング・アーティストになるつもりはなかったらしく、
04年になってようやくアルバム・デビュー。
11年ぶりとなる本作は、5作目になります。
オープニングは、ココ・テイラーの‘Never Trust A Man’ のカヴァー。
グっとソウル寄りのサウンドで、ファンキー味たっぷりに仕上げています。
マイナー・ブルースの‘If It Wasn't For The Blues’ は、
アルバート・キングの‘I’ll Play The Blues for You’ を思わす曲で、
こういう曲には、グルーヴ感たっぷりのジェリー・ジェモットのベースがどハマリ。
キッド・アンダーセンも、切れ味鋭いギター・ソロを聞かせています。
ニーナ・シモンの有名曲‘I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free’ の
カヴァーも鮮やかなら、スウィング感たっぷりの自作曲ブルース、
カントリー・バラードの‘When I Call Your Name’、
クラシック・ゴスペルの‘I Know I've Been Changed’ など、
多彩なレパートリーを表情豊かに歌いこなしています。
正直なところ、女性ブルース・シンガーは歌い口が苦手な人も多いんだけれど、
ダイユーナは抵抗をおぼえるところが皆無。
つーか、こんなクリーンな歌い口の女性ブルース・シンガーも珍しい。
ぼくには最高の女性ブルース・シンガーです。
Diunna Greenleaf "I AIN’T PLAYIN’" Little Village LVF1045 (2022)
2022-07-22 00:00
コメント(2)




